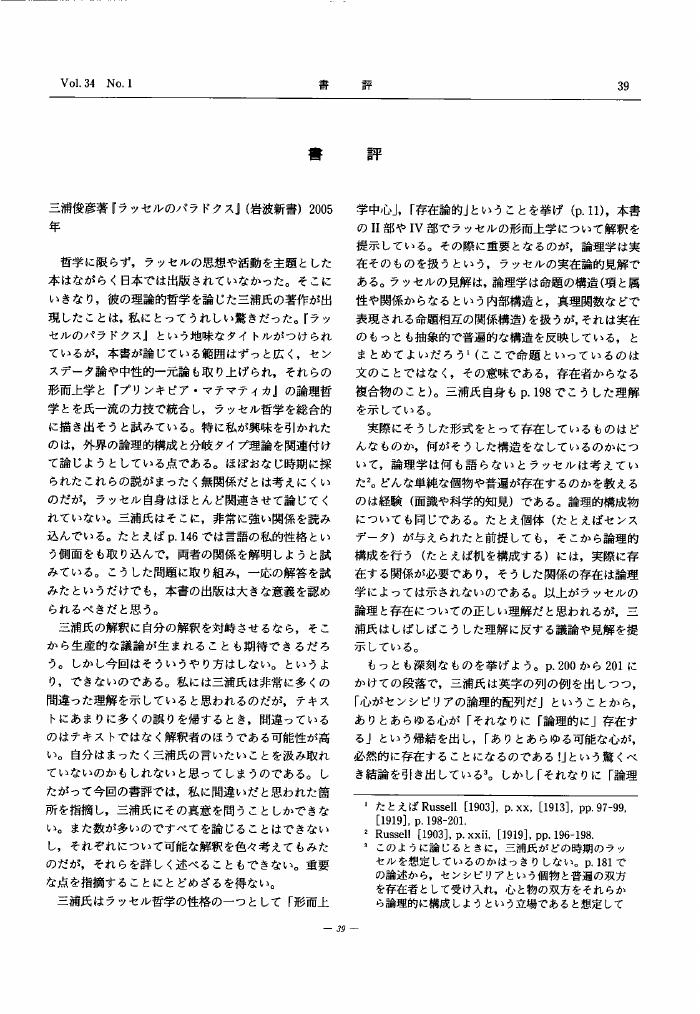4 0 0 0 OA 「さきがけ」, 「すいせい」のシステム設計とミッション運用
- 著者
- 上杉 邦憲 平尾 邦雄 林 友直 原 宏徳 山本 東光 升本 喜就 折井 武 上村 正幸 UESUGI Kuninori HIRAO Kunio HAYASHI Tomonao HARA Hironori YAMAMOTO Harumitsu MASUMOTO Yoshinari ORII Takeshi KAMIMURA Masayuki
- 出版者
- 宇宙科学研究所
- 雑誌
- 宇宙科学研究所報告. 特集: ハレー彗星探査計画報告 (ISSN:02859920)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, pp.17-31, 1987-03
「さきがけ」, 「すいせい」両探査機に対する科学観測ミッションからの要求, 重量, 電力, 通信, 熱設計等工学上の諸要求と制限を考慮したシステム設計及び打上げ後の運用結果によるその評価について述べる。
4 0 0 0 OA Wound bed preparationとしてのハチミツの位置づけ
- 著者
- 権東 容秀 松村 一 今井 龍太郎 小宮 貴子 小野 紗耶香 渡辺 克益
- 出版者
- 一般社団法人 日本創傷外科学会
- 雑誌
- 創傷 (ISSN:1884880X)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.4, pp.154-159, 2011 (Released:2011-10-01)
- 参考文献数
- 17
ハチミツは日本では食用品以外でのイメージは乏しいのが現状であるが,ヨーロッパやニュージーランドなどで古くから熱傷や創傷に使用され,近年さまざまな創傷被覆剤として開発も進んでいる。今回われわれはこのハチミツを通常の軟膏治療や物理的治療に抵抗した症例に使用し,wound bed preparationに有効か検討した。術後感染創で難治性となった5名と顔面新鮮熱傷の1名に対してハチミツを使用した。すべての症例でハチミツ使用後に滲出の量が減少し,不良肉芽であった創は良好な肉芽となり,細菌量が減少した。ハチミツは (1) 高浸透圧,(2) hydroxy peroxide を含む,(3) 酸性である,(4) 適度な湿潤環境を作る,等の作用により創治癒に有効であるといわれている。今回の経験でも不良肉芽を良性肉芽にかえ,滲出液をコントロールでき,細菌量も減少した。ハチミツはwound bed preparationに有効であると考える。
4 0 0 0 OA インフルエンザ流行期における糖尿病の超過死亡
- 著者
- 富永 真琴 山谷 恵一 原 正雄 佐々木 英夫 大島 健次郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本糖尿病学会
- 雑誌
- 糖尿病 (ISSN:0021437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.2, pp.174-179, 1977-03-31 (Released:2011-08-10)
- 参考文献数
- 12
糖尿病と感染症の関係を知るために, インフルエンザ流行期に糖尿病死亡が増加するかどうかを人口動態統計の資料を用いて検討した. 近年, インフルエンザ流行の時期と規模の客観的指標として, また, その慢性疾患への影響の指標として, 超過死亡という概念が欧米諸国, WHOで慣行化されており, 今回この方法を用い, インフル満ンザ流行期を推定し, その流行期における糖尿病の超過死亡について検討した. 超過死亡は実際の死亡と非流行期の死亡から予測される期待死亡との差で求められる. 月別期待死亡率は月別死亡率 (観察値) を人口動態統計より得て, Serflingの方法に準じ, y=a+bt+csin (πt/6-θ) の予測式の係数を最小二乗法で求めることにより得られる. 超過死亡率の有意さの程度は比較強度 (超過死亡率/標準偏差) で検討した. インフルエンザ流行期の推定には呼吸器感染症の超過死亡で検討し, 1961年~1974年の14年間に7回の流行を把握した. この流行期に糖尿病の超過死亡は3回に有意, 1回にほぼ有意であることを認めた. 一方, 臨床的には1975年~1976年冬のインフルエンザ流行期に感冒様症状を呈した糖尿病外来患者の約70%に空腹時血糖値の上昇を認めた. したがってインフルエンザに対し糖尿病患者はhigh riskgroup (高危険群) であり, インフルエンザへの対策は糖尿病の管理上重要であると考えられる
4 0 0 0 OA 地目・等級からみた開墾会社永沢社の入植地整備の特質
- 著者
- 廣橋 碧 三島 伸雄
- 出版者
- 公益社団法人 日本都市計画学会
- 雑誌
- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.1, pp.1-9, 2017-04-25 (Released:2017-04-25)
- 参考文献数
- 24
本研究の目的は、千葉県印旛郡に位置し明治8年から昭和15年の間に開墾会社永沢社によって開発された八街開墾地の特質を地目と等級の観点から明らかにすることである。永沢社は、佐賀藩士によって明治維新後に武士の地位を失った人々に対する窮民授産のために設立された。本研究では、近年発見されたために今日まで学術的研究に用いられたことのない『明治三十二年 土地?帳 印旛郡八街村八街』(土地台帳)を資料として用いる。土地台帳より、当時の各敷地の状況を復元させた地図を作成し、明治政府によって定められた地目と等級と比較した。結果として、街道筋宿駅の短冊状の伝統的地割りを踏襲して開発されたこと、明治半ばの鉄道開発が土地の等級付けにも影響したと考えられることなどが明らかになった。
4 0 0 0 IR 「実践を書く」ということ
- 著者
- 塩村 公子
- 出版者
- 東北福祉大学
- 雑誌
- 東北福祉大学研究紀要 = Bulletin of Tohoku Fukushi University (ISSN:13405012)
- 巻号頁・発行日
- no.45, pp.51-68, 2021-03-18
ソーシャルワーカーがその「実践を書く」ことの意味・必要性について,ソーシャルワークやその近接領域の文献から整理した。具体的には,Ⅰ. 業務として「書く」ことについて整理し,次に,Ⅱ. 業務以外に「実践を書く」ことについて,1「書く」場面,2「書く」行為,3「書く」意味に分けて論じた。「書く」ことは,業務上必要であるという以上に,専門家としての省察が深まる;専門家としての実践知が伝達される;利用者サービス・利用者との関係性を変える;専門家コミュニティや教育を変えていくなど,重層的で複雑な影響をソーシャルワークにもたらすものであることが理解された。また,それらが,ポストモダンの価値観をベースにした,科学やソーシャルワークの実践モデルとも密接に関係している事を見出した。
4 0 0 0 OA 嗅覚と化学:匂いという感性
- 著者
- 平澤 佑啓 東原 和成
- 出版者
- 公益社団法人 日本化学会
- 雑誌
- 化学と教育 (ISSN:03862151)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.10, pp.524-525, 2017-10-20 (Released:2018-04-01)
- 参考文献数
- 3
匂いの感覚は,鼻腔内の嗅覚受容体を匂い物質が刺激することにより生じる。ヒトは約400種類の嗅覚受容体を持ち,それらを無数に存在する匂い物質が様々なパターンで活性化させるので,我々は膨大な種類の匂いを区別して感じることができる。また,嗅覚受容体には遺伝子のタイプが多数存在し,その差異が匂いの感受性の個人差を生み出していると近年明らかにされた。
- 著者
- 空閑 浩人
- 出版者
- 同志社大学社会学会
- 雑誌
- 評論・社会科学 = Social science review (ISSN:02862840)
- 巻号頁・発行日
- no.108, pp.69-88, 2014-03
論文(Article)本稿は,日本人の文化を「場の文化」であるとし,それに根ざしたソーシャルワークのあり方としての「生活場モデル(Life Field Model)」の構想を試みたものである。それは,日本人の生活と文化へのまなざしと,日本人が行動主体や生活主体として成立する「場」への視点とアプローチを重視するものであり,日本人の生活を支える「生活場(Life Field)」の維持や構築,またその豊かさを目指す,言わば「日本流」のソーシャルワークのあり方である。その意味で,この「生活場モデル」研究は,確かに日本の「国籍」をもつソーシャルワーク研究である。しかし,それはいたずらに日本のソーシャルワークの独自性のみを強調し,そこに固執するものでは決してなく,日本の中だけに止まらない国際的な可能性をも持つものである。The purpose of this paper is to examine an idea of "Life Field Model" in social work theory and practice, while considering that Japanese culture is "the culture of field." This model thinks as important the look to Japanese life and culture, and the viewpoint and the approach to the "field" where Japanese people can be as the subject of one's action and life. Furthermore, so to speak, this model is "a Japanese style" of social work, which aims at maintenance, construction, and affluence of the "Life Field" supporting a life of Japanese people. In that sense, this study of "Life Field Model" is that of social work which surely has "nationality" of Japan. However, it never emphasizes and persists in only the originality of social work in Japan. This social work model may be effective as an international model of social work theory and practice.
4 0 0 0 OA 妊娠中および帝王切開術後に発生した癒着性イレウスに対して,大建中湯が奏功した一例
- 著者
- 中山 毅 田中 一範
- 出版者
- 一般社団法人 日本東洋医学会
- 雑誌
- 日本東洋医学雑誌 (ISSN:02874857)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.6, pp.647-651, 2009 (Released:2010-03-03)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 1 1
妊娠中および帝王切開術直後に発生した癒着性イレウスに対して,大建中湯エキスを服用することにより,保存的に加療できた症例を経験した。症例は29歳女性。15歳の時に小腸軸捻転にて開腹歴あり。妊娠11週に癒着性イレウスを発症したため,大建中湯を投与したところ,大量の下痢便を認め症状は軽快。その後,胎児ジストレスにて36週に緊急帝王切開を施行。腹壁前面に小腸の強固な癒着を認めた。術後4日目に術後癒着性イレウスの診断にて,大建中湯を経口投与した。6日目に,軟状便および排ガスを認め,9日目には経口摂取を開始。その後は異常なく25日目に退院した。妊婦の高齢化に伴い,イレウス合併妊娠の報告が数多く認められる。妊娠中は母子ともに,重篤化しやすく外科的処置が必要となることが多いが,妊娠中や出産時に発生した癒着性イレウスに対して,大建中湯を用いることにより,保存的に改善する症例もあると考えられる。
4 0 0 0 女性の政治参画の障壁:国会議員・県連への郵送・ヒアリング調査
- 著者
- 三浦 まり 申 キヨン Noble Gregory スティール 若希 MCELWAIN KENNETH 大山 礼子
- 出版者
- 上智大学
- 雑誌
- 基盤研究(B)
- 巻号頁・発行日
- 2018-04-01
- 著者
- 佐々木 紀葉 佐竹 將宏 伊東 知晃 木元 祐介 岩澤 里美 照井 佳乃 上村 佐知子
- 出版者
- 日本義肢装具学会
- 雑誌
- 日本義肢装具学会誌 (ISSN:09104720)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.3, pp.219-224, 2019-07-01 (Released:2020-07-15)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 1
本研究の目的は,脳卒中片麻痺者の短下肢装具(AFO)の装着方法を調査し,AFOの種類,身体機能およびバランス能力との関係を明らかにすることであった.対象は,AFOの着脱が自立している脳卒中片麻痺者26名(男性18名,女性8名)で,平均年齢は59.3±12.0歳であった.AFOの装着動作を分析した結果,装具を床に立てて装着する方法(立型)と足を組んで装着する方法(組型),その他に分類することができた.立型と組型では装具の種類に有意な違いがみられ,立型は組型よりも感覚と体幹屈曲機能が有意に高く,組型は立型よりも膝伸展筋力と座位バランスが有意に高い値を示した.脳卒中片麻痺者のAFOの装着方法には,装具の種類と身体機能およびバランス能力の違いが影響することが示唆された.
- 著者
- 河野 由美
- 出版者
- 一般社団法人 日本周産期・新生児医学会
- 雑誌
- 日本周産期・新生児医学会雑誌 (ISSN:1348964X)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.2, pp.203-212, 2020 (Released:2020-09-10)
- 参考文献数
- 45
- 被引用文献数
- 1
NRNJデータベースに登録された2003〜2015年出生の極低出生体重児55,444名の予後を総括した.3歳までの死亡は全体で8.1%(NICU死亡7.5%,退院後死亡0.6%),超低出生体重児は13.9%(13.2%,0.7%)であった.3歳時評価例中,脳性麻痺6.8%,両側/片側失明2.1%,補聴器使用1.0%,新版K式発達検査DQ < 70または主治医判定の発達遅滞を16.9%に認め,いずれかを合併する神経学的障害(NDI)を19.3%に認めた.超低出生体重児のみでは,脳性麻痺9.2%,失明3.6%,補聴器使用1.6%,発達遅滞24.4%,NDI 27.8%であった.全対象における死亡またはNDIの割合は16.1%,超低出生体重児では25.6%であった.在胎22〜24週の2008〜2012年出生児を2003〜2007年出生児と比較すると,死亡,死亡または脳性麻痺,死亡または視覚障害,死亡または聴覚障害はすべての週数で減少した.死亡または発達遅滞は23週では減少したが22,24週は有意な変化を認めなかった.児の長期予後の改善は周産期医療の指標となり,産科と新生児科・小児科が連携した調査研究の継続が重要である.
4 0 0 0 OA 書評
4 0 0 0 OA 栃尾鉄道案内
- 著者
- 栃尾鉄道株式会社 編
- 出版者
- 栃尾鉄道
- 巻号頁・発行日
- 1915
4 0 0 0 OA 栄養不良の世界共通言語 新しい低栄養の診断基準―GLIM基準の概要
- 著者
- 福島 亮治
- 出版者
- 日本外科代謝栄養学会
- 雑誌
- 外科と代謝・栄養 (ISSN:03895564)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.4, pp.107-112, 2022-08-15 (Released:2022-09-15)
- 参考文献数
- 15
4 0 0 0 OA 台湾蒋政権における言語に関する政策について : 政府公報を通じて
- 著者
- 徐 秀瑩
- 出版者
- 金沢大学大学院人間社会環境研究(23号)編集委員会
- 雑誌
- 人間社会環境研究 = Human and socio-environmental studies (ISSN:18815545)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, pp.109-118, 2012-03-30
4 0 0 0 IR [研究報告] 男性間性交渉者のHIV抗体検査の受検行動に影響する要因と関連性
- 著者
- 鈴木 美子 Yoshiko SUZUKI
- 出版者
- 日本赤十字秋田看護大学・日本赤十字秋田短期大学教育研究開発委員会
- 雑誌
- 日本赤十字秋田看護大学・日本赤十字秋田短期大学紀要 = Journal of Japanese Red Cross Akita College of Nursing and Japanese Red Cross Junior College of Akita (ISSN:24360384)
- 巻号頁・発行日
- no.25, pp.1-11, 2021-03-31
要旨目的:男性間性交渉者(以下MSM)のHIV抗体検査の受検行動に影響する要因と関連性を明らかにする。方法:多様なセクシャリティのスタッフが営むスナックと性と人権に関するNPO法人へ20歳以上のMSMの紹介を依頼した。5名にHIV感染症/エイズのとらえ方、HIV抗体検査を受ける動機と受けなかった理由について半構造化面接を実施し、質的記述的に分析した。結果:対象者の平均年齢は33.8歳で3名はHIV陽性であった。「HIV感染症/エイズに対する認識」では【感染の恐怖を凌ぐ性欲】【生涯逃れたいHIV感染症/エイズ】【感染する覚悟があるHIV感染症/エイズ】が抽出された。「受検行動に影響する促進要因」では【感染に対する危機意識】【HIV陰性証明の獲得】【ゲイ仲間からの勧奨】、一方「受検行動に影響する阻害要因」では【感染しないという謎の安心感】【HIV陽性判明への恐怖心】【HIV陽性判明による自由にSEXができない不利益】【早期のHIV陽性判明による経済的不利益】【治らないものはあえて受けない】【HIV抗体検査への無関心】【ゲイ告知の困難さ】【検査時のプライバシーへの無配慮】が抽出された。カテゴリの関連性から「リスク自覚時受検行動」「受検離脱行動」「受検回避行動」「受検拒否行動」の4つの受検行動が導き出された。考察:MSMにとってHIV陽性判明は自由な性交渉権利を失う【HIV陽性判明による自由にSEXができない不利益】、身体障害者非該当となった早期HIV陽性者は高額な治療費を強いられてまでは治療を望まない【早期HIV陽性判明は経済的不利益】ととらえていた。Objective: The study was conducted to reveal the factors and related matters affecting the behavior of men who have sex with men (MSM) for HIV antibody tests.Methods: Five people over 20 years of age were introduced by LGBT staff workers of a local bar and a person in charge of an NPO related to sex and human rights. Semi-structured interviews were conducted with those five subjects in regard to their understanding about HIV infection/AIDS, their motivation for taking the HIV antibody test, and/or their reasons for not taking the tests. Then the results were qualitatively and descriptively analyzed.Results: The average age of the subjects was 33.8 years old and three of them were HIV positive. In terms of "awareness of HIV infection/AIDS," the categories of "Libido that surpasses the fear of infection," "desire to avoid HIV infection/AIDS for life time," and "readiness for HIV infection/AIDS" were extracted. Regarding "the facilitating factors affecting their behavior for the tests," the categories of "awareness that may become infected," "hope HIV results are negative," and "recommendation by gay friends" were extracted. When it comes to "the inhibiting factors for the tests," the categories of "false belief that I don't get infected," "fear of HIV results being positive," "disadvantages of being unable to have sex freely if test positive for HIV," "economic disadvantage in early stages of HIV positive diagnosis," "negative feeling towards the tests for an uncurable disease," "indifference for HIV testing." "difficulties in coming out as gay," "lack of considerations for privacy during test" were extracted. In addition, the following four related matters in behaviors toward the test were derived: "the behavior with self-awareness for the risk of in taking test," "withdrawal behavior after taking the test," "avoiding the test," and "rejecting the test."Discussion: The results shows that MSM are aware that their right to have sexual intercourse freely is lost after receiving an HIV positive result as shown by the category of "disadvantages of being unable to have sex freely if test positive for HIV." Also, MSM reluctant to receive medical treatment for HIV infection if fees for required treatment are expensive as shown by the category of "economic disadvantage in early stages of HIV positive diagnosis."
- 著者
- 平井 秀幸
- 出版者
- 四天王寺大学
- 雑誌
- 四天王寺大学紀要 (ISSN:13490850)
- 巻号頁・発行日
- no.58, pp.441-468, 2014
- 著者
- 近藤 英司 陣内 自治 大西 皓貴 川田 育二 武田 憲昭
- 出版者
- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会
- 雑誌
- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)
- 巻号頁・発行日
- vol.118, no.11, pp.1319-1326, 2015-11-20 (Released:2015-12-11)
- 参考文献数
- 30
- 被引用文献数
- 4
ACE (angiotensin converting enzyme) 阻害薬は, 副作用である咳反射の亢進により誤嚥を防止して嚥下性肺炎の罹患率を減少させ, 嚥下障害患者の嚥下機能を改善させる. 一方, 外耳道の刺激は迷走神経反射を介して咳を誘発する. また, カプサイシンは TRPV1 (transient receptor potential vanilloid 1) を活性化して知覚神経を刺激する. われわれは以前の研究で, 嚥下障害患者の外耳道へのカプサイシン軟膏刺激が, 嚥下内視鏡検査のスコア評価法により評価した嚥下機能を改善させることを報告した. 本研究では, 以前の研究の嚥下内視鏡検査ビデオ動画を, 患者情報およびスコア評価法の結果を知らない耳鼻咽喉科専門医が独立して SMRC スケールにより評価した. SMRC スケールは嚥下内視鏡検査の評価法であり, 嚥下の4つの機能である咽頭知覚 (Sensory), 嚥下運動 (Motion), 声門閉鎖反射・咳反射 (Reflex), 咽頭クリアランス (Clearance) を別々に評価する. その結果, 外耳道への0.025%カプサイシン軟膏塗布により, 26名の嚥下障害患者の嚥下機能のうち声門閉鎖反射・咳反射が有意に改善し, この効果は塗布後60分後まで持続した. 嚥下機能がより低下している患者の声門閉鎖反射・咳反射は, 外耳道へのカプサイシン軟膏の単回塗布では変化しなかったが, 1週間連日塗布により有意に改善した. この結果から, カプサイシン軟膏による外耳道刺激は, 新しい嚥下障害の治療法として用いられる可能性があり, ACE 阻害薬のように嚥下性肺炎を予防できる可能性も考えられた.
4 0 0 0 OA アナログゲーム設計を通した心理学教育の可能性
- 著者
- 荒川 歩
- 出版者
- NPO法人 日本シミュレーション&ゲーミング学会
- 雑誌
- シミュレーション&ゲーミング (ISSN:13451499)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.2, pp.84-94, 2020-12-25 (Released:2021-01-05)
- 参考文献数
- 67
現在,ゲームを利用した教育についての研究は多数報告されている.一方,日本においては,現象の分析をもとに独自に立ち上げたゲームの制作そのものを教育の文脈で扱った研究は,デジタルゲームを除いてはほとんど報告されていない.しかし,現実社会の現象を,よく観察・分析し単純化してゲームとして再現(そして修正)する過程を体験することは,心理や行動の力動を理解することに大きく貢献すると考えられる.そこで,本研究では,どのようにすれば,大学生にゲーム設計を通して対象を理解させる教育が可能であり,実際にどのようなゲームが作成されるのかについて著者の試みを詳しく紹介する.この授業は,美術大学の教養科目として開講されており,2018年度は,受講生80人から44個のゲームが提出された.これらは,一部にまだ不備があるものもあるが,実施可能な形で現実の現象をゲームとして理解して表現したものであり,大学の半期の授業でも,このような課題が実行可能であることを示している.