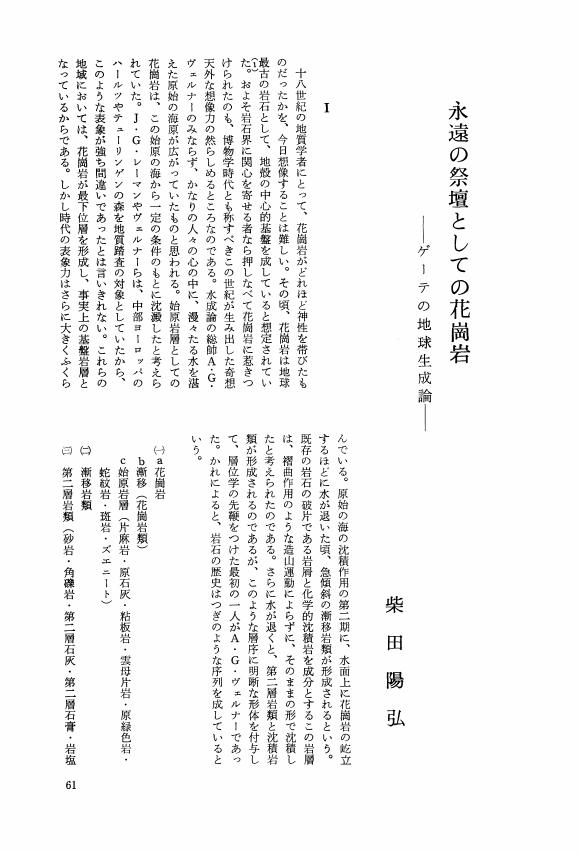4 0 0 0 IR 『諏方大明神画詞』の「唐子」をめぐる試論
- 著者
- 中村 和之
- 出版者
- 法政大学国際日本学研究所
- 雑誌
- 国際日本学 : 文部科学省21世紀COEプログラム採択日本発信の国際日本学の構築研究成果報告集 = International Japan studies : annual report (ISSN:18838596)
- 巻号頁・発行日
- no.18, pp.186-168, 2021-02
Completed in 1356, the "Suwa Daimyōjin Ekotoba" is an important historical source of the medieval history of the Ainu. In this book, the Ainu were referred to by the word ʻEzoʼ. There were three groups in ʻEzoʼ : Hinomoto, Karako, and Wataritō. Among them, the ʻKarakoʼ people have been regarded as a group that lived on the west coast of northern Hokkaido. In the 13th and 14th centuries, the Mongol Empire and the Yuan Dynasty invaded Sakhalin Island. In medieval Japanese, the group name ʻKarakoʼ can be translated as ʻthe children in Chinese attire and hairstyleʼ. The meaning can be explained by the relationship between northern Hokkaido and China.According to the records of Jesuit missionaries in the early 17th century, the place called Teshio on the west coast of northern Hokkaido was a trading hub with Sakhalin Island. And one example of Okhotsk type pottery made in the southern part of Sakhalin Island was found in ruins, dated to be after the 10th century, in Nayoro city in the inland area of northern Hokkaido. It is estimated that this Okhotsk type pottery was carried to Nayoro city via the Teshio River. At the mouth of the Teshio River, there is a large archaeological site of Satsumon culture. Thus, the mouth of the Teshio River was likely a hub for trade with Sakhalin Island from the 11th to the 17th centuries. The newly found evidence indicates the name ʻKarakoʼ originated from the close relationship between Teshio and Sakhalin Island.
4 0 0 0 OA 離婚法理の拡張による同族会社における少数派株主の保護
- 著者
- 岩城 円花
- 出版者
- 東北大学法学会
- 雑誌
- 法学 = HŌGAKU (THE JOURNAL OF LAW AND POLITICAL SCIENCE) (ISSN:03855082)
- 巻号頁・発行日
- vol.86, no.1,2, pp.111-162, 2022-09-30
4 0 0 0 OA ケイパビリティ・アプローチ再考
- 著者
- 杉原 弘恭 田口 玄一郎
- 出版者
- 学校法人 自由学園最高学部
- 雑誌
- 生活大学研究 (ISSN:21896933)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.1, pp.42-68, 2018 (Released:2019-04-05)
- 参考文献数
- 63
フレキシブルで多目的なフレームワークとしてのケイパビリティ・アプローチの汎用性を拡張するために,ケイパビリティの概念整理を行った.その際に,ルーツとしてのネガティブ・ケイパビリティを探るとともに,センの提唱したケイパビリティの定義式を基本とし,ヌスバウムとの比較を通じ,これまでケイパビリティを論ずる際に出されたいくつかのキーとなる概念を,(1) Positive-Negative, (2) Active-Passive, (3) Explicit-Implicit (Potential) の3軸として抽出し,その組み合わせによる静学的な8象限のケイパビリティ・キューブを提示した.さらに,システム論による定義式の解釈を行って,動学的能力と構造変化能力を兼ね備えていることを示した.続いて視座としてのケイパビリティに影響を及ぼすネガティブ・ケイパビリティ,ケア(caring)を概観し,加えて教育的なつながりを確認するために,リベラル・アーツとの関係,さらにはその延長線上に位置するマネジメントとのつながりについて述べた.
4 0 0 0 OA 谷崎潤一郎「青塚氏の話」における映画の位相 : 映画製作/受容をめぐる欲望のありか
- 著者
- 佐藤 未央子
- 出版者
- 日本近代文学会
- 雑誌
- 日本近代文学 (ISSN:05493749)
- 巻号頁・発行日
- vol.91, pp.49-62, 2014-11-15
映画界の隆盛を背景に、「青塚氏の話」は映画製作と受容をめぐる人々の欲望をアクチュアルに批評した。本作において映画は、監督の中田、観客の男を繋ぐ媒介となりながら、女優由良子の<性>を前景化し、視覚的快楽を提供するメディアとして描かれた。一九二〇年代半ばから内面性の表現が重視され始めていた映画は、原初的な記録媒体あるいは<見世物>に押し戻されているのである。男が一人快楽を貪るさまは、受容者による製作者からの所有権奪取を示唆していた。本作では映画の流通過程における主体性が問われ、谷崎が映画に見出した「民衆芸術」性が仮託されていたと考えられる。谷崎の<映画小説>群に通底する批評意識を、「青塚氏の話」からも看取できた。
4 0 0 0 OA 視覚障害と基礎数学教育
- 著者
- 橘 貞雄 武笠 敏夫
- 出版者
- 一般社団法人 数学教育学会
- 雑誌
- 数学教育学会誌 (ISSN:13497332)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.3-4, pp.85-92, 2006 (Released:2020-06-13)
4 0 0 0 場面緘黙の専門資源へのアクセスが難しい地域における遠隔支援の検討
4 0 0 0 IR 「〈民話〉のふるさと」の構造
- 著者
- 小池 淳一
- 出版者
- 国立歴史民俗博物館
- 雑誌
- 国立歴史民俗博物館研究報告 = Bulletin of the National Museum of Japanese History (ISSN:02867400)
- 巻号頁・発行日
- vol.193, pp.293-303, 2015-02
地域の開発に際して文化をどのように位置づけ、利用するか、という問題は実は言語戦略の問題でもある。本稿はそうした地域開発のキャッチフレーズとも標語ともとれる術語についての予備的考察である。ここでとりあげる術語とは〈民話〉である。〈民話〉はしばしば、民俗学の領域に属する語のように思われるが実はそうではない。〈民話〉は民俗研究のなかでは常に一定の留保とともに用いられる術語であり、またそれゆえに広がりを持つ言葉であった。一九五〇年代の日本民俗学において〈民話〉は学術用語としては忌避されていた。それは戦後歴史学のなかで、民話が検討対象となり、民衆の闘いや創造性を示す語として扱われていたことと関連し、民俗学の独立の機運とは裏腹のものであった。そうした留保によって〈民話〉はかえって多くの含意が可能になり、地域社会とも結びつく可能性が残されていった。特に「民話のふるさと」岩手県遠野市では口承文芸というジャンル成立以前の『遠野物語』と重ね合わされることによって〈民話〉が機能した。その結果として、遠野は「〈民話〉のふるさと」となったのである。How to evaluate and utilize culture in community development is also considered as a matter of linguistic strategies. This article provides a preliminary consideration of the terminology used as a catchphrase or slogan for community development. More specifically, this study focuses on folktales. The word "folktale (Minwa)" is often mistaken as a technical term of folklore studies. In reality, folklorists always use the term in a reserved way, which gives it a wide range of meanings. In the 1950s, Japanese folklorists rarely used "folktale" as an academic term. This was partially because after World War II, historians studied folktales using the term to represent creativity or a struggle of people, which was contrary to the trend of independence of folklore studies. Due to the reserved attitude of folklorists, however, the term could have many connotations, leaving the possibility to be linked with local communities. In particular, in Tōno, Iwate Prefecture, a city also known as the Home of Folktales, folktales played a role in relation to "the Legends of Tōno (Tōno Monogatari)" years before the establishment of oral literature as a genre. This is the very reason why the city has become the Home of Folktales.
4 0 0 0 OA 技術の社会的構成とは何か
- 著者
- 綾部 広則
- 出版者
- 特定非営利活動法人 グローバルビジネスリサーチセンター
- 雑誌
- 赤門マネジメント・レビュー (ISSN:13485504)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.1, pp.1-18, 2006-01-25 (Released:2018-03-11)
- 参考文献数
- 30
- 被引用文献数
- 2
技術の社会的構成は、ともすれば技術決定論を否定し、社会決定論的な観点を強調するものとして捉えられがちである。確かにそうした立場を鮮明に打ち出す理論もある一方で、むしろ技術決定論と社会決定論のいわば中間に位置し、二つの対立を無化しようとする理論も存在する。このように技術の社会的構成は決して一枚岩ではなく、むしろそれ故に弛みない論争が続いている。
4 0 0 0 OA 出産後の女性のキャリア継続の諸要因 : 女性の就労環境,「保活」,夫の家事育児に注目して
- 著者
- 前田 正子 中里 英樹 Masako MAEDA Hideki NAKAZATO
- 出版者
- 甲南大学人間科学研究所
- 雑誌
- 心の危機と臨床の知
- 巻号頁・発行日
- vol.23, pp.23-46, 2022-03-20
4 0 0 0 IR エビデンスとナラティヴの関係 : 認知症高齢者と介護者の社会的認知に着目した検討
- 著者
- 村山 明彦 ムラヤマ アキヒコ Akihiko MURAYAMA
- 雑誌
- 最新社会福祉学研究 = Progress in social welfare research
- 巻号頁・発行日
- no.12, pp.25-32, 2017-03-31
DSM−5では,認知機能をこれまでの5領域から6領域とし,新たに社会的認知が加わった.また,認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)の策定に伴い,これまで以上に社会的認知が注目されるようになった.このような背景から,認知症高齢者の社会的認知を,科学的に検討する研究が増加しつつある.一方,高齢者ケア専門職の社会的認知を検討した研究は少ない.本研究では.認知症高齢者と高齢者ケア専門職,双方の社会的認知に着目し,認知症ケアの方法論として有益な知見を提示することを目的とした.本研究の目的を遂行するために,文献研究の手法を用いて,先行研究を踏まえ,本研究における社会的認知を定義するための理路を提示した・認知症ケアの方法論の現状と課題についても言及し,エビデンスとナラティヴに関する先行研究からの知見を援用した.以上の結果を統合し,実践への提言として,社会的認知をSOAP形式にて,評価・記録することの可能性をまとめた.The previous edition which included five domains of cognitive function has been updated to the newly revised edition of the Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) which defines six domains of cognitive function including social cognition. Along with formulation of the Comprehensive Strategy to Accelerate Dementia Measures by the Japanese government (also called "New Orange Plan"), social cognition has drawn more attention. Based on such background, an increasing number of studies on social cognition in elderly people with dementia have been conducted, but only a few studies on social cognition in elderly care professionals have been performed. The present study, based on a literature review, focuses on social cognition in both the elderly with dementia and elderly care professionals, and is aimed at offering findings that are useful for providing dementia care. In order to achieve the objective of this study, a discussion is presented in the following order: a method of defining social cognition based on previous studies is shown; evidence and narrative are cited from previous studies; and recommendations for dementia care practice are provided from these integrated results.
4 0 0 0 OA 東錦絵 : 雪・月・花
- 著者
- 松原 優
- 出版者
- 日本消費者行動研究学会
- 雑誌
- 消費者行動研究 (ISSN:13469851)
- 巻号頁・発行日
- pp.202310.002, (Released:2022-12-15)
- 参考文献数
- 82
本研究は、人が持つ所属欲求と社会的アイデンティティ理論のフレームワークに、ブランド・コミュニティにおける社会的なつながりの質に対する評価であるソーシャルネットワーク・クオリティを加えたモデルを開発することにより、ブランド・コミュニティが、消費やブランドに限定されない消費者の人生全般に関するウェルビーイングに及ぼす影響を明らかにすることを目的とする。その結果、(1)ソーシャルネットワーク・クオリティがブランド・コミュニティ・アイデンティフィケーションの先行要因となること、(2)ブランド・コミュニティ・アイデンティフィケーションが消費やブランドに限定されない消費者の人生全般に関するウェルビーイングの先行要因となることが明らかとなった。さらに、ブートストラップ法を用いた媒介分析の結果、ソーシャルネットワーク・クオリティによる消費やブランドに限定されない消費者の人生全般に関するウェルビーイングへの影響は、ブランド・コミュニティ・アイデンティフィケーションによって媒介されることが明らかとなった。
4 0 0 0 OA 表情認知の心理・神経メカニズム
- 著者
- 佐藤 弥
- 出版者
- 一般社団法人 日本高次脳機能障害学会
- 雑誌
- 高次脳機能研究 (旧 失語症研究) (ISSN:13484818)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.3, pp.332-340, 2019-09-30 (Released:2020-10-01)
- 参考文献数
- 30
表情は感情コミュニケーションの主要メディアである。しかし, 表情処理がどのような心理・神経メカニズムにより実現されるかは明らかではない。本稿では, この問題を調べた我々の一連の心理学・神経科学研究の知見を紹介する。心理学および神経科学研究から, 以下のような知見が示された。 (1) 表情の感情情報は無意識の段階で処理されており, こうした表情への感情処理に関係して扁桃体が約 100 ミリ秒の段階で活動する, (2) 感情表情は中性表情よりも素早く検出されており, その検出パフォーマンスに視覚野における約 200 ミリ秒からの強い活動が関係している, (3) 表情に対しては自動的な表情模倣が喚起され, これにはミラーニューロン領域を構成するとされる下前頭回の約 300 ミリ秒の段階の活動が関係する。こうした知見から, 表情に対して, 感じる・見る・まねるという一連の心理的情報処理が, 扁桃体・視覚野・下前頭回から構成される神経ネットワークにより数百ミリ秒のうちに実現されることが示唆される。
- 著者
- Mai INOUE Nigel C. L. KWAN Katsuaki SUGIURA
- 出版者
- JAPANESE SOCIETY OF VETERINARY SCIENCE
- 雑誌
- Journal of Veterinary Medical Science (ISSN:09167250)
- 巻号頁・発行日
- pp.17-0384, (Released:2018-05-24)
- 被引用文献数
- 31
The life expectancy provides valuable information about population health. The life expectancies were evaluated in 12,039 dogs which were buried or cremated during January 2012 to March 2015. The data of dogs were collected at the eight animal cemeteries in Tokyo. The overall life expectancy of dogs was 13.7 (95% confidence interval (CI): 13.7–13.8) years. The probability of death was high in the first year of life, lowest in the fourth year, and increased exponentially after four years of age like Gompertz curve in semilog graph. The life expectancy of companion dogs in Tokyo has increased 1.67fold from 8.6 years to 13.7 years over the past three decades. Canine crossbreed life expectancy (15.1 years, 95% CI 14.9–15.3) was significantly greater than pure breed life expectancy (13.6 years, 95% CI 13.5–13.7, P<0.001). The life expectancy for male and for female dogs were 13.6 (95% CI: 13.5–13.7) and 13.5 (95% CI: 13.4–13.6) years, respectively, with no significant difference (P=0.099). In terms of the median age of death and life expectancy for major breeds, Shiba had the highest median age of death (15.8 years), life expectancy (15.5 years) and French Bulldog had the lowest median age of death (10.2 years), life expectancy (10.2 years). When considering life expectancy alone, these results suggest that the health of companion dogs in Japan has significantly improved over the past 30 years.
- 著者
- 小川 壮寛 松下 明 中島 利裕 守安 洋子 島田 憲一 江川 孝 五味田 裕 髙橋 正志 髙見 陽一郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本プライマリ・ケア連合学会
- 雑誌
- 日本プライマリ・ケア連合学会誌 (ISSN:21852928)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.4, pp.302-307, 2013 (Released:2014-01-10)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 1 1
目的 : 共同薬物治療管理 (CDTM) を地域医療に導入するための方略の一つとして, 事前に処方医と事後報告を行うポジティブリストを作成し, 疑義照会を事後報告へ切り替えることによる効果を検証した.方法 : 事後報告に替えることのできる疑義照会をリソルブ疑義と定義した上で, ポジティブリストに基づく事後報告への切り替えを行い, その効果をリソルブ疑義の件数, 保険点数およびジェネリック医薬品使用率の変化を調査することにより評価した.結果 : 医師の治療計画を変更することなく, ポジティブリストにより178件 (疑義照会全体の22.7%) の疑義照会を事後報告に替えることができ, 疑義照会にかかる時間を大幅に短縮することができた. これにより保険点数は17,455点削減でき, ジェネリック医薬品使用率は46.6%まで上昇した.結論 : ポジティブリストに基づく薬剤師自身の判断で疑義照会を事後報告に切り替えることにより, 疑義照会実施件数および医療費削減とジェネリック医薬品使用率上昇を可能とした.
4 0 0 0 OA 近世武芸と天道思想―啓蒙書と武芸書との比較を通して―
- 著者
- 笠井 哲
- 出版者
- 日本武道学会
- 雑誌
- 武道学研究 (ISSN:02879700)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.1, pp.1-11, 1989-07-31 (Released:2012-11-27)
- 参考文献数
- 52
The purpose of this article is to elucidate the significance of the concept of “The Way of Heaven”(Tendo). First, the concept of “The Way of Heaven” in some enlightenment books, such as Shingakugorinsho, etc., is examined. Next, the meaning of “The Way of Heaven” in the secret books of martial arts, such as Heihokadensho, etc., is defined. Through a comparison of these two concepts of “The Way of Heaven” follows, the similarities between the two schools of thoughts in discussed.The results of this article are summarized as follows:1) Originally “The Way of Heaven” includes not only the rules of nature but also the rules of morals or “The Way of Man” (Jindo). “The Way of Heaven” as found in the enlightenment books, such as Shingakugorinsho, etc., supports the ideology of the Tokugawa Bakufu, and is based on the unification of the three schools of thoughts, Shinto, Confucianism, and Buddhism.2) “The Way of Heaven” in the secret books of martial arts, such as Heihokadensho, is derived from San-Rue, and permits the unavoidable fight in the cause of justice. This idea was considered suitable for the policy of the Tokugawa Bakufu. According to the written prayer (Kishoumon), “The Way of Heaven” was considered to be a god or buddha. In other words, “The Way of Heaven” in Martial Arts was also considered to have a commonality with both Shintoism and Buddhism.3) As has been examined in this paper, the idea of “The Way of Heaven” in the enlightenment writings and the martial arts writings of the Edo Period contained various and complex meanings, borrowing from the different philosophical and cultural traditions of the Period. In short, “The Way of Heaven”is a “master key”, which elucidates the commonality of Shinto, Confucian, and Buddhist thoughts, as well as martial arts. Therefore, the philosophical thought of martial arts compares favorably with the three schools of thoughts (Shinto, Confucianism, and Buddhism) through the foundation of “The Way of Heaven”.
4 0 0 0 IR アディクションとソーシャルワーク -わが国における理論研究の概観-
- 著者
- 田中 和彦
- 出版者
- 日本福祉大学社会福祉学部
- 雑誌
- 日本福祉大学社会福祉論集 = Journal social Welfare, Nihon Fukushi University (ISSN:1345174X)
- 巻号頁・発行日
- no.143, pp.99-109, 2021-03-31
本研究の目的は,依存・嗜癖といわれる「アディクション」分野におけるソーシャルワーク実践の礎となる理論について,先行研究のレビューから概観を明らかにすることである.アディクションをもつ人たちへのかかわりは難しいとされ,アディクションを専門で取り組んでいる人や機関に支援をゆだねる傾向が強い.そこでアディクションに特化したソーシャルワーク理論が存在しているのか,そもそもその理論の必要性があるのかについて,先行研究のレビューを行い考察した.その結果,アディクションにおけるソーシャルワークの理論ではエンパワーメントアプローチをベースにしており,そこにナラティヴアプローチ,リカバリー概念など親和性が高い理論が影響し合っている.また,当事者の主体性の尊重といったポストモダンの思想潮流と親和性が高いということが考えられた.さらに社会への働きかけの重要性を指摘しているが,一方でマクロレベルのソーシャルワークにおいての理論化と実践がまだなされていないことが課題としてあげられた.上記はアディクションに限らず他の精神保健分野の課題でも同様であると考えられ,アディクションに特化したソーシャルワーク理論があるということではなく,アディクションに対する忌避感情が支援の困難さを生み出しているのではないかという仮説を得ることができた.
4 0 0 0 OA 永遠の祭壇としての花崗岩 ―ゲーテの地球生成論―
- 著者
- 柴田 陽弘
- 出版者
- ゲーテ自然科学の集い
- 雑誌
- モルフォロギア: ゲーテと自然科学 (ISSN:0286133X)
- 巻号頁・発行日
- vol.1986, no.8, pp.61-82, 1986-11-01 (Released:2010-02-26)
- 参考文献数
- 30
4 0 0 0 OA 小札考 : ユーラシアからみた小札鎧の系譜
- 著者
- 梶原 洋
- 出版者
- 東北福祉大学
- 雑誌
- 東北福祉大学芹沢銈介美術工芸館年報 = Tohoku Fukushi University Serizawa Keisuke Art and Craft Museum annual report (ISSN:21862699)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.57-80, 2010-06-23
小札は、アッシリアに始まり、内陸アジアを通して東西に広がった。本論では、ユーラシアに分布する小札について、アルファベットや記号、数字を用いて簡単に小札の縅孔、綴孔などの配置を表現し、それに基づいてA-Hの形式分類と細分を行った。小札鎧は、ユーラシア全体の分布をみると、内陸アジアを中心に西はヨーロッパから東は日本まで分布している(表1)。編年的には、5-6世紀を中心に古くは紀元前から新しくは19世紀まで用いられたことが分かる。(表2)。日本列島における小札鎧もユーラシアに広範に分布する小札鎧文化伝統の最東端に位置するものである。鎧文化における大陸との関係は、古代ばかりでなく中世もしくは近代にまで続き、大鎧の成立や北海道、樺太のアイヌ民族の鎧の存在にも大きな影響を与えたことが考えられる。 Lamellar armor, constructed of hundreds of small rectangular lamellae of wood, hide, bone, antler, bronze, or iron, has been widely used across Eurasia, from Europe to Japan. Rectangular lamellae with holes for lacing one to another with straps or cordsf irst appeared in Assyria in the eighth or seventh century B.C., then spread through central Asia to Siberia, Mongolia, China,Korea and finally Japan in the fifth century A.D.
4 0 0 0 OA 落語「饅頭こわい」の原話
- 著者
- 岡田 充博
- 出版者
- 横浜国立大学国語・日本語教育学会
- 雑誌
- 横浜国大国語研究 (ISSN:02881489)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, pp.1-12, 2011-03-20