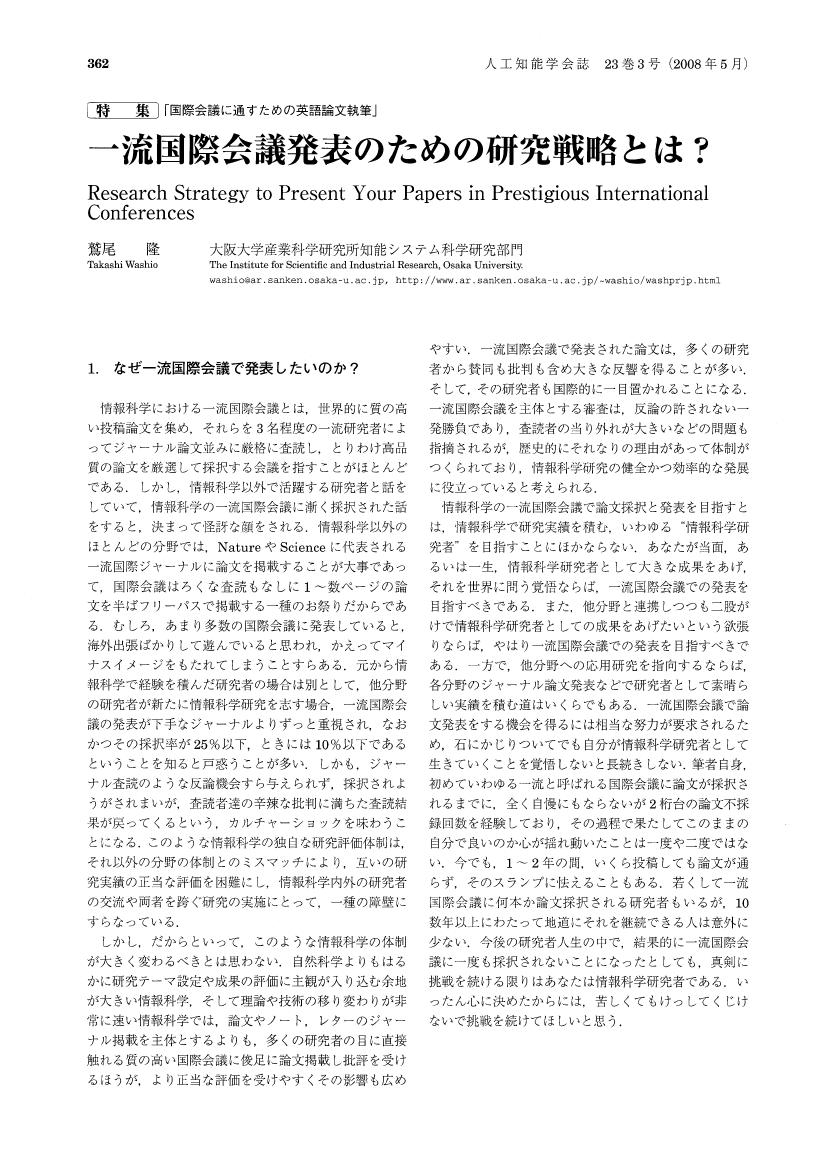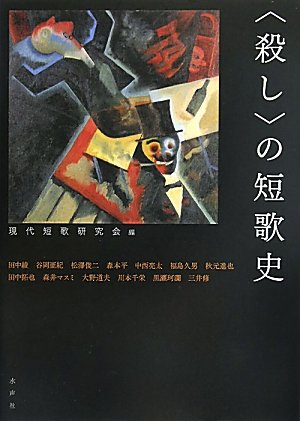4 0 0 0 OA ハワード・ベッカー「アンダードッグの社会学」再考
- 著者
- 秋本 光陽
- 出版者
- 関東社会学会
- 雑誌
- 年報社会学論集 (ISSN:09194363)
- 巻号頁・発行日
- vol.2018, no.31, pp.84-95, 2018-08-25 (Released:2019-08-29)
- 参考文献数
- 25
This article reconsiders the sociological significance of sociologist Howard S. Becker’s liberalist stance. In 1966, Becker presented a lecture entitled “Whose side are we on?” in which he discussed his support for liberalism. However, his stance has been strongly criticized and called “underdog sociology” by Alvin Gouldner and others. Although, these criticisms have insisted that sociologists should be either neutral or a reflection of ourselves, Becker paid attention to the construction of the self as a sociologist within a social organization. Interpreting his ideas in this way provides a perspective from which we can empirically analyze political debates.
- 著者
- 孫 大輔
- 出版者
- 日本医学教育学会
- 雑誌
- 医学教育 (ISSN:03869644)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.1, pp.89-94, 2022-02-25 (Released:2022-06-19)
- 参考文献数
- 8
映画とは, 文学や音楽, 絵画, 演劇と並ぶ芸術的営為の一つである. 映画を芸術の一つとして捉えるならば, 映画は社会の新しい見方を提示するだけでなく, 共通の経験の感覚を新しく創造し直す手段として捉えることができる. 映画を医学教育に活かす手法であるシネメデュケーション (cinemeducation) は, 人間形成機能, すなわち批判的思考や主体性形成を促す作用を持つと同時に, プロフェッショナリズムの涵養にも役立つ. 例えば, 利他主義, エンパシー (共感), 倫理的推論能力などの教育である. シネメデュケーションの具体的方法として, 映画全体または映画のクリップを使用して, 小グループの議論を促進する. 教育目標に合わせた「問い」を学習者に投げかける. また, ロールプレイやレクチャー, 診療・治療計画について考えさせるといった内容を組み合わせる. シネメデュケーションの課題として, どのような映画を選ぶか, 映画全体を見せるか一部を見せるか, どの部分を選ぶかといった教材選択の問題とともに, 学習者のレディネスや学習進度に合わせた授業内容を設計できるかという授業デザインの問題がある.
4 0 0 0 IR コミック読書経験の基底にある性格特性
- 著者
- 諸井 克英 板垣 美穂 MOROI Katsuhide ITAGAKI Miho
- 出版者
- 京都
- 雑誌
- 同志社女子大学生活科学 = DWCLA human life and science (ISSN:13451391)
- 巻号頁・発行日
- no.52, pp.12-20, 2019-02-20
The present study explored the relationship between reading comic books and basic personality traits(Big Five ; Wada, 1996)in female undergraduates. The Experiences of Reading Comic Books Scale(developed by authors)and the Short Version for Big Five Scale(revised by authors)were administered to female undergraduates(N=331). According to the cluster analyses and the principal component analyses, three clusters were extracted as follows : fusion of underworld and actual world, love stories for girls and adult women, and detective and adventure stories. The correlation analyses indicated that conscientiousness inhibited reading comic books which depicted fusion of underworld and actual world. The psychological effects of reading comic books were discussed.原著論文
4 0 0 0 OA 性向と文脈の社会学理論
- 著者
- 磯 直樹
- 出版者
- 日本社会学理論学会
- 雑誌
- 現代社会学理論研究 (ISSN:18817467)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, pp.138-143, 2017 (Released:2020-03-09)
- 著者
- 鈴木 隆哉
- 出版者
- 東北大学
- 雑誌
- 国際共同研究加速基金(国際共同研究強化(B))
- 巻号頁・発行日
- 2022-10-07
4 0 0 0 OA 大型船用水潤滑式船尾管シール
- 著者
- 佐田 裕之 斎藤 健一
- 出版者
- 公益社団法人 日本マリンエンジニアリング学会
- 雑誌
- マリンエンジニアリング (ISSN:13461427)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.1, pp.48-51, 2011 (Released:2013-10-23)
- 参考文献数
- 1
Oil-lubricated sterntube system is generally used for merchant ships while water-lubricated sterntube system is generally used for passenger ships. Recently, the water-lubricated sterntube system is attracting keen interest from the viewpoint of oil-pollution prevention. Conventional seal used in water-lubricated sterntube system has a drawback in that the sealing ring cannot be easily replaced with a spare. This is a problem in large ships for which on-schedule voyage is strongly required. This paper introduces a new water-lubricated sterntube seal in which the sealing ring can be switched to a spare ring with just a simple valve operation.
4 0 0 0 IR 生活保護政策の実施過程 : 政策変容のメカニズムと自律的な官僚制
4 0 0 0 OA 一流国際会議発表のための研究戦略とは?(<特集>国際会議に通すための英語論文執筆)
- 著者
- 鷲尾 隆
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能 (ISSN:21882266)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.3, pp.362-366, 2008-05-01 (Released:2020-09-29)
4 0 0 0 OA 日本のビジュアルメディア領域のための知識グラフ提供へ
- 著者
- ロート マーティン プフェファー マグヌス
- 出版者
- デジタルアーカイブ学会
- 雑誌
- デジタルアーカイブ学会誌 (ISSN:24329762)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.1, pp.31-34, 2022-02-01 (Released:2022-03-22)
- 参考文献数
- 12
日本のビジュアルメディアに関する研究データが不足している中、Japanese Visual Media Graphプロジェクトは、ファンのコミュニティーがオンラインで集めキュレートする膨大な量のデータに注目し、それらの多様なデータを接続し、統合されたRDFベースのオントロジーを有する中心となる知識グラフを作成することを目的とする。本論文はそのデータへの取り組みと今後の展開を紹介する。
4 0 0 0 OA 公理的測定論の歴史と展望
- 著者
- 吉野 諒三
- 出版者
- 心理学評論刊行会
- 雑誌
- 心理学評論 (ISSN:03861058)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.2, pp.119-135, 1989 (Released:2019-07-24)
- 被引用文献数
- 2
4 0 0 0 OA PICUへの早期リハビリテーション導入による効果と課題
- 著者
- 森 貴子 問田 千晶 六車 崇 齋藤 千恵子 横尾 由希子 金子 節志 稲元 未来 橋本 圭司
- 出版者
- 一般社団法人 日本集中治療医学会
- 雑誌
- 日本集中治療医学会雑誌 (ISSN:13407988)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.2, pp.107-114, 2017-03-01 (Released:2017-03-16)
- 参考文献数
- 10
当施設PICUでは,2013年より重篤小児に対する早期リハビリテーション充実へ向けた取り組みを開始した。取り組み導入による効果を検証し,課題を呈示する。【対象と方法】PICUに3日以上滞在した16歳未満の小児に対する早期リハビリテーションの効果,施行率,PICU医師と看護師に対する意識調査を行った。【結果】重篤小児に対する早期リハビリテーションによる効果は実証できなかった。効果を認めなかった要因としては,リハビリテーション施行率の低さ,リハビリテーションに関する知識不足,理学療法士との協力体制の不備,効果の判定方法の問題が示唆された。【考察】今後は,小児の年齢や発達に応じた評価指標に基づき,リハビリテーションの効果を客観的に評価するとともに,年齢,疾患および重症度ごとに検証する必要がある。
4 0 0 0 IR タゴールにとっての「異界」
- 著者
- 丹羽 京子 ニワ キョウコ NIWA Kyoko
- 出版者
- 東京外国語大学総合文化研究所
- 雑誌
- 総合文化研究 (Trans-Cultural Studies)
- 巻号頁・発行日
- no.24, pp.35-49, 2021-02-16
4 0 0 0 OA 予見ファジー制御方式による自動列車運転装置の実現
- 著者
- 大島 弘安 関野 真一 安信 誠二
- 出版者
- The Institute of Electrical Engineers of Japan
- 雑誌
- 電気学会論文誌C(電子・情報・システム部門誌) (ISSN:03854221)
- 巻号頁・発行日
- vol.109, no.5, pp.337-344, 1989-05-20 (Released:2008-12-19)
- 参考文献数
- 13
4 0 0 0 OA 音楽の脳内処理
- 著者
- 佐藤 正之
- 出版者
- 一般社団法人 日本高次脳機能障害学会
- 雑誌
- 高次脳機能研究 (旧 失語症研究) (ISSN:13484818)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.2, pp.139-144, 2005 (Released:2006-07-14)
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 1 7
音楽の脳内処理過程について, 扁桃体の機能を中心に述べた。失音楽症例の過去の報告から, 音楽の知覚能力と情動反応とは二重解離を呈しており, 両者が独立した脳内過程を有していることが示唆された。しかし扁桃体病変についての記載はなく, 音楽的情動への同部位の関与は明らかでなかった。Positron emission tomography (PET) による音楽的情動に関する脳賦活化実験では, 不快感を惹起すると想定された不協和音の聴取時に, 予想された扁桃体の活性化はみられなかった。著者は音色の認知についてのPETによる脳賦活化実験を行った。同じ旋律に対し, 音色に注目して聴いた時とリズムに注目して聴いた時とで脳血流の変化を調べた。その結果, 前者では後者に比し, 扁桃体, 海馬傍回, 帯状回, 側頭葉前部などに両側性に有意な活性化がみられた。扁桃体の活性化の機能的意義として, 進化論的側面と情動的評価から考察した。音楽を刺激に用いることにより, 情動の脳内過程に新たな知見が得られるものと期待される。
4 0 0 0 OA 青年期における対人恐怖的心性と対人不安の差異──罪悪感による両概念の弁別──
- 著者
- 大西 将史
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 心理学研究 (ISSN:00215236)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, no.4, pp.351-358, 2008 (Released:2011-08-26)
- 参考文献数
- 44
- 被引用文献数
- 7 3
This study examined the role of trait guilt in discriminating between anthropophobic tendency and social anxiety. 212 University and technical college students (103 males and 109 females) were administered a questionnaire with a trait guilt scale, an anthropophobic tendency scale, and a social anxiety scale. Trait guilt showed a positive correlation with anthropophobic tendency when the influence of social anxiety was controlled. When the influence of Anthoropophobic tendency was controlled, trait guilt did not correlate as highly with social anxiety. These results were discussed related to cultural views of the self. Japanese culture is a “shame culture” because interdependent view of the self (seeing themselves as essentially connected with others) is dominant. People worry about appearances and how others see them, and are ashamed of their own deficiency or negative side, which leads to a sense of betrayal of others and thus guilt becomes a prominent trait.
- 著者
- 栗林 克匡
- 雑誌
- 北星学園大学社会福祉学部北星論集 = Hokusei Review, the School of Social Welfare (ISSN:13426958)
- 巻号頁・発行日
- no.58, pp.19-26, 2021-03-15
4 0 0 0 OA 東北方言の物理音聲學的研究 [第二報] 秋田及び福島方言並に東北子音の性質
- 著者
- 小幡 重一 雨宮 綾夫
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会、一般社団法人 日本数学会
- 雑誌
- 日本数学物理学会誌 (ISSN:21852715)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.3, pp.181-192, 1937 (Released:2010-03-16)
- 参考文献数
- 4
4 0 0 0 OA 児童のストレス反応に及ぼす社会的問題解決訓練の効果 : 長期的維持効果の検討
- 著者
- 田中 利枝 高橋 高人 佐藤 正二
- 出版者
- 一般社団法人 日本認知・行動療法学会
- 雑誌
- 行動療法研究 (ISSN:09106529)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.1, pp.85-97, 2016-01-31 (Released:2019-04-27)
本研究は、小学6年生に対して社会的問題解決訓練を実施し、訓練効果・維持効果、および、ストレス反応に及ぼす影響について検討した。児童175名は、それぞれ訓練群84名と統制群91名に割り付けられ、訓練群の児童は、担任教師によって4セッション(各45分)からなる介入を受けた。その結果、訓練を受けた児童は、友人とのトラブル場面においてポジティブに問題を捉える問題志向を向上させ、解決の目標としての認知的解決スタイルを習得し、それらは訓練終了3カ月後も維持されていることが明らかとなった。解決策の案出数は、訓練終了11カ月後も訓練効果が維持されていた。また、訓練群の児童では、訓練直後においてストレス反応のうち不機嫌・怒りに低減効果が示された。中学校進学後の11カ月後フォローアップ測定において、解決策の案出数以外に介入の維持効果はみられなかった。中学校入学後の維持促進の操作の必要性が示唆された。
4 0 0 0 OA 健康経営における「職場における健康文化」に関する評価指標の検討
- 著者
- 高橋 由香 津野 陽子 大森 純子
- 出版者
- 公益社団法人 日本産業衛生学会
- 雑誌
- 産業衛生学雑誌 (ISSN:13410725)
- 巻号頁・発行日
- pp.2021-029-B, (Released:2021-12-05)
- 被引用文献数
- 1
目的:健康リスクを改善し生産性維持・向上に寄与することを促進するのは,単に介入プログラムの内容によるのではなく,「職場における健康文化(Workplace culture of health)」の醸成が重要であるというエビデンスが蓄積され始めている.先行研究において,従業員の主観的評価による組織の健康へのサポートに関する認識が高いほど,健康リスクやプレゼンティーイズム損失が小さいといったエビデンスが蓄積され始めており,健康経営においても従業員視点による評価が重要と考えられる.本研究では,従業員視点による職場における健康文化の指標を作成し,健康経営における従業員による主観的評価指標としての有用性を検討することを目的とした.方法:従業員の健康や生産性に関する職場における健康文化の文献レビューにより作成した指標20項目を用いてアンケート調査を実施した.対象はA県内の健康経営優良法人2019に認定された50組織の従業員を対象とした.協力の得られた25組織の従業員886名に調査票を配布し,分析対象者は435名となった.結果:大規模法人部門(ホワイト500)の43件,中小規模法人部門の263件,自社の認定部門が分からない群の123件の3群で分析を行った.大規模法人部門と中小規模法人部門の2群比較では,「健康保持・増進に関する全社方針の内容」,「健康問題が起きた時の対処手順」,「復職に向けた制度や支援」,「心をサポートする体制や支援」,「安全と健康に関する協議の場」は大規模法人部門で有意に良い結果であり,「上司による体調に関する声がけ」,「健康づくりに役立つ情報の提供」は中小規模法人部門で有意に良い結果であり,組織規模による特徴がみられた.一方,自社の健康経営優良法人の認定部門が分かる群と分からない群との比較では,全ての項目で認定部門が分からない群が有意に悪い結果であった.また,本指標は20項目全てで,職場における健康文化が良い結果である者の方が健康リスク数やプレゼンティーイズム損失が小さいことが確認された.考察と結論:従業員視点による職場における健康文化の程度を捉えられること,職場における健康文化は従業員の健康リスクや生産性に関連することが検証され,健康経営における従業員視点での評価指標として有用であることが示唆された.