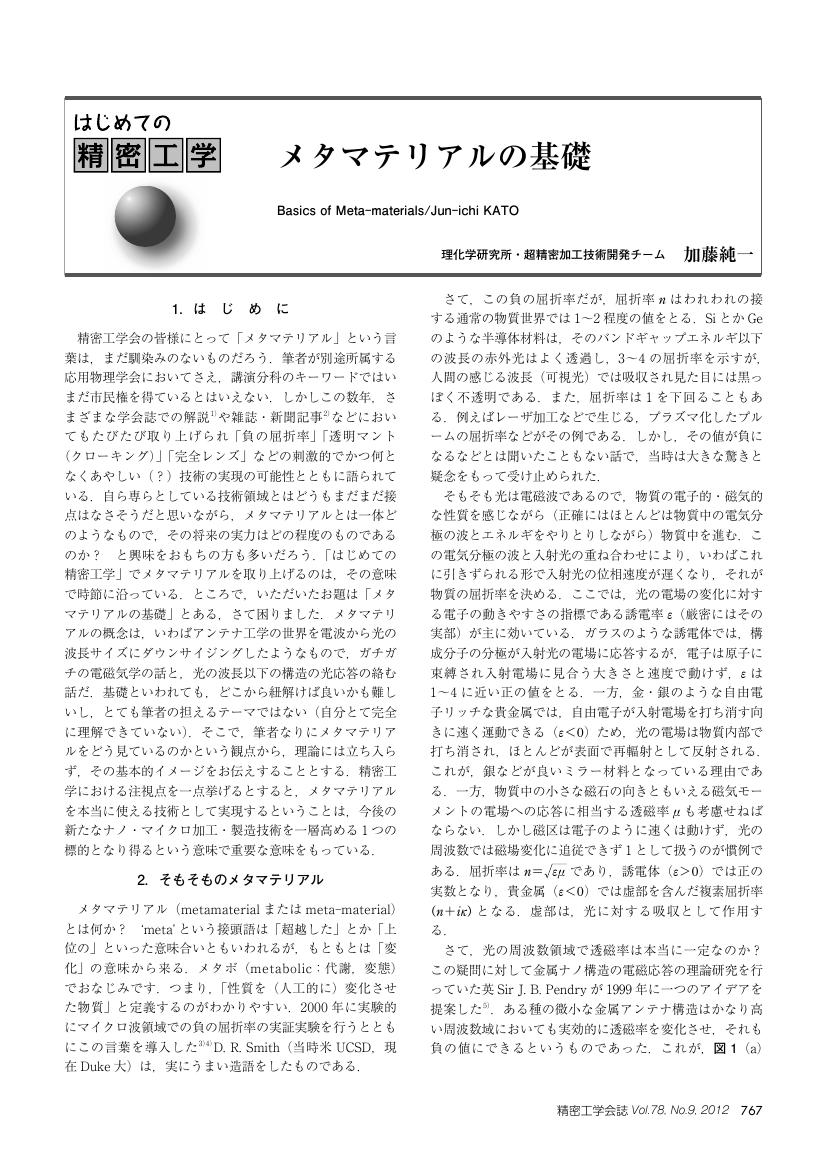4 0 0 0 OA レミニセンスと学習効果 : 小学生用英語学習プログラムの結果からの考察
- 著者
- 安藤 則夫 長谷川 修治
- 出版者
- 学校法人 植草学園大学
- 雑誌
- 植草学園大学研究紀要 (ISSN:18835988)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.25-35, 2015 (Released:2018-04-13)
4 0 0 0 OA うつ・不安にかかわる脳内神経活動と運動による抗うつ・抗不安効果
- 著者
- 北 一郎 大塚 友実 西島 壮
- 出版者
- Japanese Society of Sport Psychology
- 雑誌
- スポーツ心理学研究 (ISSN:03887014)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.2, pp.133-140, 2010 (Released:2010-10-08)
- 参考文献数
- 47
- 被引用文献数
- 4 2
It has been suggested that regular physical exercise is beneficial to not only physiological adaptation, but also psychological health through stress reduction, antidepressant / anxiolytic properties and improvement in mood. However, since exercise regimens have varied widely across experiments, the optimal form, intensity and duration of exertion for producing the maximal benefits of exercise have yet to be established. Recent neuroscience studies have shown that physical exercise could have a positive impact on the brain, raising the hypothesis that the beneficial effects of physical exercise on psychological health are due to morphological and functional adaptation in the brain, rather than physiological adaptation to physical exercise. For example, it has been shown that physical exercise results in increased neurogenesis or expression of brain-derived neurotrophic factor as well as improved cognitive abilities or reduced stress-induced depressive behavior. Although evidence of the neural and behavioral benefits of physical exercise is accumulating, the influences of different regimens of physical exercise on the brain and behavior remain unclear. This issue aims to outline the effects of physical exercise on pathological conditions with a focus on mood disorders, including depression and anxiety, and consider the neural mechanisms of the antidepressant / anxiolytic effects of physical exercise.
4 0 0 0 OA APD/LiD の診断と支援
- 著者
- 片岡 祐子
- 出版者
- 一般社団法人 日本聴覚医学会
- 雑誌
- AUDIOLOGY JAPAN (ISSN:03038106)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.5, pp.314-315, 2022-09-05 (Released:2022-12-16)
- 被引用文献数
- 1
4 0 0 0 ジョヴアンネルラ・モルゲンの「十九世紀初葉のローマの市民生活」
- 著者
- 田村 泉
- 出版者
- イタリア学会
- 雑誌
- イタリア学会誌 (ISSN:03872947)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.83-88, 1953
4 0 0 0 OA 満州国時期の関東軍の新聞関与と中国語新聞
- 著者
- 華 京碩
- 出版者
- 日中社会学会
- 雑誌
- 21世紀東アジア社会学 (ISSN:18830862)
- 巻号頁・発行日
- vol.2016, no.8, pp.124-137, 2016-06-30 (Released:2017-05-22)
- 参考文献数
- 30
满洲国时期的关东军对东三省新闻业的控制和摧残是近代东北报业发展史上一个值得关注的问题。由于关东军在战败时烧毁了大量资料,造成了现代中国的满洲国时期报纸研究的碎片化、往往局限在纯以报纸内容分析为主,而无法完整的解析在幕后控制报纸的关东军的意图及满洲国主要的日系中文报纸的具体经营情况。事实上,在日本的外务省外交史料馆、防卫省防卫研究所战史资料室及国会图书馆的宪政资料室里仍然保存了大量满洲国时期的关东军提交给政府的文书和当事者的记录。但是由于中日两国学者在这方面交流的不足,目前这些资料还未被系统的整理和使用。本稿的目的就是利用日本国内的关东军新闻干预的相关资料,以及中国国内的一部分口述史料、地方志研究的成果,来具体解析三个问题:满洲国时期关东军干预报业发展采取的形式;日系中文报纸最后的消亡;日本报人的最后结局。从而对军事组织关东军的新闻干预,满洲国时期的日系新闻和日本报人的研究进行一点尝试。
4 0 0 0 OA 「文明社会の野蛮人」仮説の検証 : 科学技術と文化・社会の相関をめぐって
- 著者
- 小林 信一
- 出版者
- 研究・イノベーション学会
- 雑誌
- 研究 技術 計画 (ISSN:09147020)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.4, pp.247-260, 1992-10-15 (Released:2017-12-29)
- 被引用文献数
- 6
本論文は、若者の科学技術離れの問題の文化的、社会的背景を明らかにしようとするものである。オルテガは「科学技術文明が高度に発達すると、かえって科学技術を志向する若者が減る事態が発生する」と議論した。これが今日の我が国でも成立するか、成立するとすればそれはどのようなメカニズムによるのかを実証的に検討することが本論文の目的である。このために、まずオルテガの議論を、科学技術と文化・社会の連関モデルとして実証可能な形に定式化した。これを実証するために、世論調査や高校生を対象とする意識調査のデータをログリニア・モデルなどの統計的な連関分析手法で注意深く分析した。その結果、オルテガの仮説は今日の我が国でも概ね成立することが明らかになった。また、短期的な実証分析の結果を外挿的なシュミレーションによって超長期に展開する工夫を施し、その結果がオルテガの文明論的な議論と整合的であることを確認した。分析結果は、オルテガの指摘した逆説的事態は必然的に発生するものであることを示している。
4 0 0 0 OA Development of a novel positive pressure protective suit for Biosafety Level 4 laboratory in Japan
- 著者
- Shintaro Shichinohe Yasuteru Sakurai Daisuke Hayasaka Eri Yamada Katsuaki Shinohara Yohei Kurosaki Kensuke Nakajima
- 出版者
- National Institute of Infectious Diseases
- 雑誌
- Japanese Journal of Infectious Diseases (ISSN:13446304)
- 巻号頁・発行日
- pp.JJID.2022.475, (Released:2022-12-28)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 1
Biosafety Level 4 (BSL-4) laboratories are necessary to study microorganisms that are highly pathogenic to humans and have no prevention or therapeutic measures. Currently, most BSL-4 facilities have suit-type laboratories to conduct experiments on highly pathogenic microorganisms. In 2021, the first Japanese suit-type BSL-4 laboratory was constructed at Nagasaki University. Positive pressure protection suit (PPPS) is a primary barrier that protect and isolate laboratory workers from pathogens and the laboratory environment. Here, we developed a novel PPPS originally designed to be used in the Nagasaki BSL-4 laboratory. We modified several parts of the domestic chemical protective suit, including its front face shield, cuff, and air supply hose, for safe handling of microbiological agents. The improved suit, PS-790BSL4-AL, showed resistance to several chemicals, including quaternary ammonium disinfectant, and did not show any permeation against blood and phages. To validate the suit’s integrity, we also established an airtight test that enabled the elimination of individual differences for quantitative testing. Thus, our developed suit is sufficient as a primary barrier and allows for the safe handling of pathogens in our new BSL-4 laboratory.
4 0 0 0 OA マクシミリアン・フォーテ、山田文訳『リビア戦争―カダフィ殺害誌』(感覚社、2021)
- 著者
- 木戸 衛一
- 出版者
- 明治学院大学国際平和研究所
- 雑誌
- 【書評/Book Reviews】 (ISSN:13404245)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, pp.163-167, 2022-03-31
4 0 0 0 IR 日本における精神病床入院の研究 : 3類型の制度形成と財政的変遷
4 0 0 0 OA メタマテリアルの基礎
- 著者
- 加藤 純一
- 出版者
- 公益社団法人 精密工学会
- 雑誌
- 精密工学会誌 (ISSN:09120289)
- 巻号頁・発行日
- vol.78, no.9, pp.767-772, 2012-09-05 (Released:2013-03-05)
- 参考文献数
- 24
- 被引用文献数
- 3
- 著者
- 義江 明子
- 出版者
- 国立歴史民俗博物館
- 雑誌
- 国立歴史民俗博物館研究報告 = Bulletin of the National Museum of Japanese History (ISSN:02867400)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, pp.35-65, 1992-03-31
日本の伝統的「家」は、一筋の継承ラインにそう永続性を第一義とし、血縁のつながりを必ずしも重視しない。また、非血縁の従属者も「家の子」として包摂される。こうした「家」の非血縁原理は、古代の氏、及び氏形成の基盤となった共同体の構成原理にまでその淵源をたどることができる。古代には「祖の子」(OyanoKo)という非血縁の「オヤ―コ」(Oya-Ko)観念が広く存在し、血縁の親子関係はそれと区別して敢えて「生の子」(UminoKo)といわれた。七世紀末までは、両者はそれぞれ異なる類型の系譜に表されている。氏は、本来、「祖の子」の観念を骨格とする非出自集団である。「祖の子」の「祖」(Oya)は集団の統合の象徴である英雄的首長(始祖)、「子」(Ko)は成員(氏人)を意味し、代々の首長(氏上)は血縁関係と関わりなく前首長の「子」とみなされ、儀礼を通じて霊力(集団を統合する力)を始祖と一体化した前首長から更新=継承した。一方の「生の子」は、親子関係の連鎖による双方的親族関係を表すだけで、集団の構成原理とはなっていない。八~九世紀以降、氏の出自集団化に伴って、二つの類型の系譜は次第に一つに重ね合わされ父系の出自系譜が成立していく。しかし、集団の構成員全体が統率者(Oya)のもとに「子」(Ko)として包摂されるというあり方は、氏の中から形成された「家」の構成原理の中にも受け継がれていった。「家の御先祖様」は、生物的血縁関係ではなく家筋観念にそって、「家」を起こした初代のみ、あるいは代々の当主夫妻が集合的に祀られ、田の神=山の神とも融合する。その底流には、出自原理以前の、地域(共同体)に根ざした融合的祖霊観が一貫して生き続けていたのである。現在、家筋観念の急速な消滅によって、旧来の祖先祭祀は大きく揺らぎはじめている。基層に存在した血縁観念の希薄さにもう一度目を据え、血縁を超える共同性として再生することによって、「家」の枠組みにとらわれない新たな祖先祭祀のあり方もみえてくるのではないだろうか。
4 0 0 0 OA アメリカ連邦議会上院の権限および議事運営・立法補佐機構
- 著者
- 松橋和夫
- 出版者
- 国立国会図書館
- 雑誌
- レファレンス (ISSN:1349208X)
- 巻号頁・発行日
- no.627, 2003-04
4 0 0 0 帝国日本の林学者と植民地林業の研究
本研究は、明治後期から昭和戦前期にかけての、帝国日本のフォレスター(林学者や林政官僚、林業技術者、林業家)が、本国と植民地(ないし勢力圏)において、どのようにして人材と学知のネットワークを築き、植民地化された人々と接しながら、「帝国林業」を展開したのかを問うものである。さらに、帝国日本が展開した「科学的林業」によって確立した森林保全的な思想が、旧植民地にもたらしたポストコロニアルな影響を検討する。その際、近代科学の発展を帝国主義の空間的な展開のなかで捉えるとともに、イギリス帝国との比較を通じて日本の「帝国林業」の特色を捉える。
4 0 0 0 OA リニア中央新幹線全線開通が三重県における観光行動に及ぼす影響の把握
- 著者
- 伊藤 聖樹 松本 幸正
- 出版者
- 公益社団法人 日本都市計画学会
- 雑誌
- 日本都市計画学会中部支部研究発表会論文集 (ISSN:24357316)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, pp.25-28, 2021 (Released:2021-10-05)
- 参考文献数
- 3
リニア中央新幹線は最短で2037年に東京-大阪間の全線が開通予定となっており,三重県へも駅の設置が予定されている.目的地までの移動時間短縮は時間的余裕を生み,観光においても訪問箇所数の増加や範囲の広域化が期待される.そこで本研究では,リニアの全線開通が三重県での観光行動にどう影響するかを把握するため,まず,現在の三重県の人気エリアをSNS投稿データから抽出した.次に,WEBアンケートの結果に基づき,リニア全線開通後の観光地間の関連の強さを算出し,想定される周遊ルートを明らかにした.その結果,リニア全線開通後の三重県内の周遊ルートとしては,伊勢,鳥羽,志摩の組み合わせが最も選ばれることになった.また,広域周遊する場合,大阪や奈良,京都も訪問先として選ばれる可能性があることもわかった.他にも,東京在住者は熊野への周遊が増加する可能性が,大阪在住者は名古屋まで観光範囲が広がる可能性も示唆された.
4 0 0 0 IR 特別養護老人ホームにおける介護過程の展開プロセスに関する研究 : 個別ケアの支援を中心に
- 出版者
- 国際医療福祉大学
- 巻号頁・発行日
- 2015
元資料の権利情報 : CC BY-NC-ND
- 著者
- Hiroshi Takasaki Takahiro Ueno
- 出版者
- The Society of Physical Therapy Science
- 雑誌
- Journal of Physical Therapy Science (ISSN:09155287)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.1, pp.31-39, 2023 (Released:2023-01-01)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 1
[Purpose] We aimed to identify possible solutions to enhance evidence-based practice (EBP) in rehabilitation professionals in Japan. [Participants and Methods] A three-round Delphi method was undertaken among a cohort of clinical therapists (328 physical therapists, 55 occupational therapists, and 6 speech therapists). In the first round, the participants listed possible solutions for promoting EBP, other than 12 solutions presented in a previous study; subsequently, a new list was created. In the second round, a newly-created list of solutions was presented, and the participants responded on a 5-point Likert scale on how much they agreed with the solutions promoting EBP in Japanese rehabilitation professionals. In the third round, the distribution of responses obtained in the second round was presented, and participant’s agreement was again assessed on a 5-point Likert scale. [Results] Across the three rounds, data were collected from 33.7% to 47.0% of all eligible participants. After the first round, 17 possible solutions were developed, and a list of 29 solutions was used in the second round. After the third round, 10 solutions reached the predetermined criteria for consensus. [Conclusion] In this study, ten possible solutions to promote EBP were proposed by the Japanese rehabilitation professionals.
4 0 0 0 OA ウメ加工品の加工方法と品質
4 0 0 0 OA 高齢者 Lutembacher 症候群の1手術治験例
- 著者
- 榎本 直史 川野 博 米須 功 丸山 寛 林田 信彦 田山 栄基 有永 康一 押領司 篤茂 川良 武美 青柳 成明
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本心臓血管外科学会
- 雑誌
- 日本心臓血管外科学会雑誌 (ISSN:02851474)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.5, pp.343-346, 1999-09-15 (Released:2009-04-28)
- 参考文献数
- 6
高齢者の Lutembacher 症候群の1例に対して外科治療を行い, 良好な結果を得たので報告する. 症例は71歳, 女性. 高度心不全を呈し, Qp/Qs=3.08の心房中隔欠損症に僧帽弁狭窄症, 三尖弁閉鎖不全症, 心房細動および肺高血圧症を合併していた. 手術は僧帽弁置換術, 心房中隔欠損パッチ閉鎖術, 三尖弁輪縫縮術を施行した. 術後一時的に呼吸不全に陥ったが, 厳重な術後管理により軽快し退院した. 高齢者の Lutembacher 症候群の手術報告例はきわめてまれであり, 本症例は, 本邦における手術報告例では最高齢と思われた. 本症候群に対しては, 高齢者においても術後臨床症状の著明な改善が得られるため, 十分な手術適応の検討のもと外科治療を行うことが望ましいと考えられた.