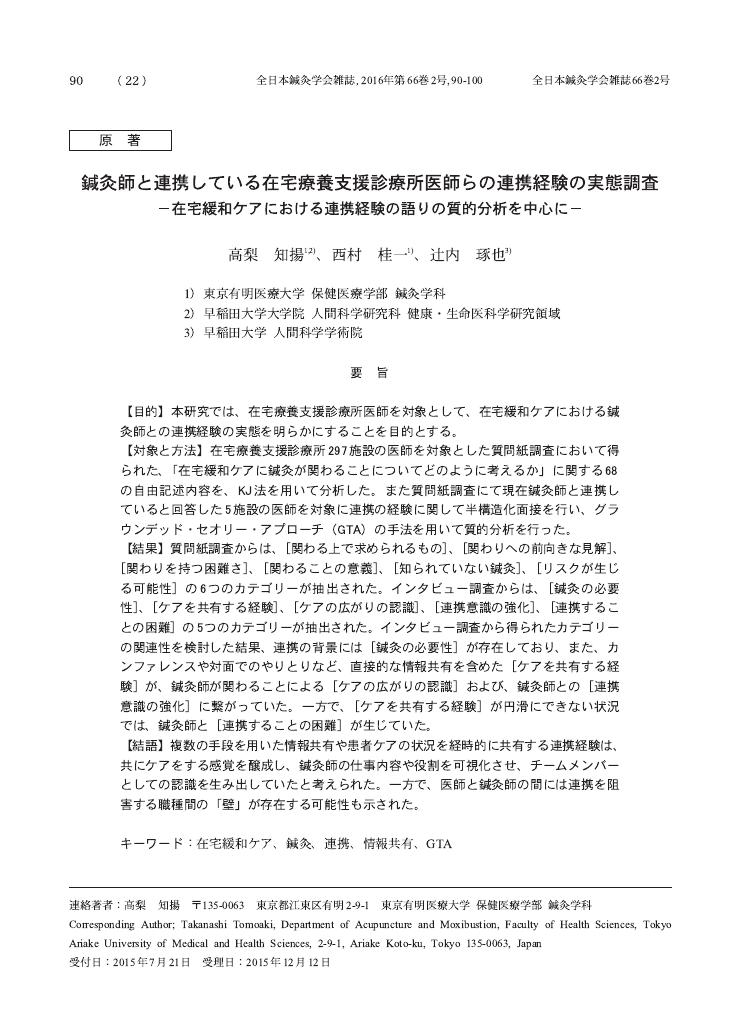- 著者
- Kumiko Hayashi Shinsuke Niwa
- 出版者
- The Biophysical Society of Japan
- 雑誌
- Biophysics and Physicobiology (ISSN:21894779)
- 巻号頁・発行日
- pp.bppb-v18.026, (Released:2021-10-06)
- 被引用文献数
- 2
4 0 0 0 人びとの人生を記述する:「相互行為としてのインタビュー」について
- 著者
- 鶴田 幸恵 小宮 友根
- 出版者
- 社会学研究会
- 雑誌
- ソシオロジ (ISSN:05841380)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.1, pp.21-36,159, 2007
Recently, it has become a new methodological agenda to discuss the methodologies of interviews which could be collected under the rubric of "interview as interaction." But it seems that such discussions do not make clearer the sociological status of the description which is produced by that method.The task of this paper is to point out some confusion in such discussions, and make the viewpoint of "interview as interaction" into a methodological discussion which can thoroughly describe "people's lives."<br> Methodologies that emphasize the view of "interview as interaction" often differentiate themselves from the standpoint which emphasizes "the facticity of data" or "the pattern of narrative." But apart from facticity or pattern, it is unclear what becomes the value of the data.There are two confusions concerning the view of "interaction."<br> First concerns the usage of the two terms, "construction" and "interpretation." By virtue of the confused usage of these terms in such methodology, our understanding of other's conduct is reduced to the activity of "interpretation." The second confusion concerns the claim that they describe not "fact" or "pattern of narrative" but "the mode (or form) of narrative." But in such a claim, "the mode (or form) of narrative" becomes a "model" prepared on the researcher's side.Both miss the difference of the various actions and activities in actual interaction and do not make clear the implication of the term "interaction" within the methodology of interviews.<br> But, for the interviewee, the interview is one scene of his/her life in a literal sense.If this is so, the behavior and the activity which appear there must be the part of his/her life and describing them must be directly describing his/her life.Here, using particular data, we present that proposition and argue the importance of the viewpoint of "interview as interaction."
4 0 0 0 OA 環境および植物ホルモンによるC_<3>,C_<4>光合成の発現制御
- 著者
- 上野 修
- 出版者
- 一般社団法人 植物化学調節学会
- 雑誌
- 植物の化学調節 (ISSN:03889130)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.2, pp.160-168, 1998-12-25 (Released:2018-03-15)
- 参考文献数
- 40
- 被引用文献数
- 1
4 0 0 0 OA Role of Ocean in Global Warming
- 著者
- Syukuro MANABE Ronald J. STOUFFER
- 出版者
- Meteorological Society of Japan
- 雑誌
- 気象集誌. 第2輯 (ISSN:00261165)
- 巻号頁・発行日
- vol.85B, pp.385-403, 2007 (Released:2007-10-26)
- 参考文献数
- 54
- 被引用文献数
- 12 16
Based upon the results obtained from coupled ocean-atmosphere models of various complexities, this review explores the role of ocean in global warming. It shows that ocean can play a major role in delaying global warming and shaping its geographical distribution. It is very encouraging that many features of simulated change of the climate system have begun to agree with observation. However, it has been difficult to confirm the apparent agreement because the density and frequency of the observation are insufficient in many oceanic region of the world, in particular, in the Circumpolar Ocean of the Southern Hemisphere. It is therefore essential to intensify our effort to monitor not only at the surface but also in the subsurface layers of oceans.
4 0 0 0 OA マットゥール村訪問記 : 現代サンスクリット事情の一端
- 著者
- 沼田 一郎 ヌマタ イチロウ Ichiro NUMATA
- 出版者
- 東洋大学文学部
- 雑誌
- 東洋学論叢 = Bulletin of Orientology (ISSN:03859487)
- 巻号頁・発行日
- no.35, pp.147-137, 2010-03
- 著者
- 西尾 佳朋 伊藤 邦弘 加藤 三香子 瀧川 友佳子 篠邉 龍二郎 古橋 明文
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本睡眠歯科学会
- 雑誌
- 睡眠口腔医学 (ISSN:21886695)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.1, pp.15-20, 2022 (Released:2021-10-01)
- 参考文献数
- 27
Objective: We present a case of narcolepsy in a patient with obstructive sleep apnea (OSA) who complained of residual sleepiness without improvement in Epworth sleepiness scale (ESS) after oral appliance (OA) therapy, and who underwent the Multiple Sleep Latency Test (MSLT).Method: The patient was a 48-year-old male who had no significant past medical history and family history, and had been experiencing excessive daytime sleepiness. The initial interview at the Department of Sleep Medicine did not reveal any cataplexy, sleep paralysis, and hypnagogic hallucinations. He was diagnosed with mild OSA (apnea hypopnea index: AHI 10.5/h) based on polysomnography (PSG), and was referred to our department for OA therapy. Excessive daytime sleepiness did not improve after the initiation of OA therapy. Thereafter, follow-up sleep study with PSG and the MSLT were performed.Results: The PSG with OA showed an improvement of OSA in AHI from 10.5 to 3.6/h, and sleep-onset REM sleep period (SOREMP) was not observed. MSLT showed that the mean sleep latency was 4min 6s/five naps, and number of SOREMP was two times; therefore, the patient was diagnosed with narcolepsy type 2. Use of Modafinil 100 mg/day decreased the ESS score from 15 to 4 and improved daytime sleepiness.Conclusion: In patients with OSA and narcolepsy, it is not possible to improve excessive daytime sleepiness by providing treatment for OSA only. Patients who complain of residual sleepiness even after OA treatment should be assessed further for other sleep disorders including hypersomnia.
4 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1932年05月04日, 1932-05-04
4 0 0 0 OA 台湾企業の対中投資の推移と特徴
- 著者
- 廖 婉婷
- 出版者
- 愛知淑徳大学大学院現代社会研究科
- 雑誌
- 現代社会研究科研究報告 (ISSN:18810373)
- 巻号頁・発行日
- no.6, pp.113-126, 2011-03-04
論文
4 0 0 0 OA 中小企業におけるメンタルヘルス対策と従業者のストレス変化
- 著者
- 足立 泰美 木下 祐輔 Yoshimi ADACHI Yusuke KINOSHITA
- 出版者
- 国立社会保障・人口問題研究所
- 雑誌
- 社会保障研究 = Journal of Social Security Research (ISSN:03873064)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.2, pp.182-198, 2021-09
投稿論文
- 著者
- 高梨 知揚 西村 桂一 辻内 琢也
- 出版者
- 公益社団法人 全日本鍼灸学会
- 雑誌
- 全日本鍼灸学会雑誌 (ISSN:02859955)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.2, pp.90-100, 2016 (Released:2017-01-19)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 1
- 著者
- 川口 茂雄 Shigeo KAWAGUCHI
- 出版者
- 甲南大学人間科学研究所
- 雑誌
- 心の危機と臨床の知
- 巻号頁・発行日
- vol.22, pp.二三-二五, 2021-03-20
4 0 0 0 東北大学における研究倫理教育の取り組みについて
- 著者
- 佐々木 孝彦
- 出版者
- 公益社団法人 日本工学教育協会
- 雑誌
- 工学教育 (ISSN:13412167)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.5, pp.5_113-5_118, 2021 (Released:2021-10-02)
- 参考文献数
- 5
In this report for Case Study, we introduce the educational activities for research ethics conducted as part of the promotion of responsible conduct of research at Tohoku University. In particular, we describe in detail the Career Stage-Based Learning Reference Standards and the Research Integrity Advisor System as distinctive systems and initiatives.
4 0 0 0 聖書とオリエント世界
- 著者
- 船越 進太郎
- 出版者
- THE LEPIDOPTEROLOGICAL SOCIETY OF JAPAN
- 雑誌
- 蝶と蛾 (ISSN:00240974)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.3, pp.157-162, 2001-06-30 (Released:2017-08-10)
- 参考文献数
- 11
1995年から1999年にかけて岐阜県谷汲村の神社拝殿で夏眠をするAmphipyra属6種,カラスヨトウA.livida corvina,ツマジロカラスヨトウA.schrenckii,オオウスヅマカラスヨトウA.erebina,シロスジカラスヨトウA.tripartita,オオシマカラスヨトウA.monolitha surniaとナンカイカラスヨトウA.horieiの個体数の変動を調べた.夏眠個体のカウントにおいてオオシマカラスヨトウとナンカイカラスヨトウの種同定は不可能であり,これらは同一種として数えた.この調査地点ではカラスヨトウが常に優占し,50m^2余りの小さな神社拝殿軒下に静止する個体数は多い時で248個体を数えた.その他の種はいずれも個体数が少なく,特にツマジロカラスヨトウは5年の調査期間に5個体しか出現しなかった.夏眠個体数は年によって,また季節によって大きく変動したが,最大個体数を示す年は,種ごとに異なっていた.東海地方におけるそれぞれの種の夏眠期間は,これまで調べられたようにほぼ決まっていた.また,岐阜市周辺の夏眠場所で1987年および1995年から1998年にかけてカラスヨトウを採集し,性を記録すると共に体重を測定した.カラスヨトウ雄成虫は,この属の他種には見られない触角のわずかな鋸歯構造で雌から区別できるが,夏眠後半の個体ではこの特徴が消失する(おそらくすり減るものと思われる).そのため全ての個体を二酸化炭素で短時間の麻酔にかけ,双眼実体顕微鏡により後翅の翅棘で性を確認した.体重は電子自動上皿天秤であらかじめ重量を計ったプラスチック容器に調査個体を移動して測定した.その結果,6月中旬から10月上旬まで,夏眠個体の雄と雌の比は,ほぼ1:1であったが,10月中旬より雄の個体数は減少し,雌の占める割合が増加した.また,体重は9月下旬までは多少雌の方が上回ったがほとんど差はなく,10月上旬になって明らかな差が現われた.その後,体重差は益々広がった.これらの現象は夏眠覚醒の季節とほぼ同時に始まっており,カラスヨトウ成虫に生理的な変化が起こっていることが明らかになった.カラスヨトウは夏眠期間中は,ほとんど光源や糖蜜に誘引されず,交尾行動も見られないことがこれまでの調査で確かめられている.覚醒の後,雄個体は交尾相手を求めて夏眠場所を離れ,活発に活動するためエネルギーを消費し,体重が激減するものと思われる.一方,雌は雄から精包を受け取り,卵が発育するために体重が増加するものと考えられる.しかしながら,夏眠期間中の体重維持や少し早めの体重増加などから,カラスヨトウ類は夏眠期間中も餌をとっていると推定された.
4 0 0 0 OA ナウマンの火山および火山岩研究:ナウマンの日本地質への貢献1
- 著者
- 山下 昇
- 出版者
- 一般社団法人 日本地質学会
- 雑誌
- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)
- 巻号頁・発行日
- vol.96, no.6, pp.479-491, 1990-06-15 (Released:2008-04-11)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 1 1
4 0 0 0 OA メタゲノムデータ解析から見る環境微生物像
- 著者
- 奥田 修二郎
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本バイオインフォマティクス学会
- 雑誌
- JSBi Bioinformatics Review (ISSN:24357022)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.1, pp.1-6, 2021 (Released:2021-10-05)
- 参考文献数
- 34
長年の間、環境微生物の研究は培養できた微生物について実験を実施することで知見を積み上げてきた。しかし、次世代DNAシーケンサーの登場でその解析の方法論が大きく変化した。環境中のすべての微生物のDNAを網羅的に解析することができるメタゲノム解析に加えて、16S rRNA遺伝子のみを対象としたメタ16S解析も次世代DNAシーケンサーで実施することでその解析の深度が増している。このような環境微生物の研究に大規模なDNA配列のシーケンス技術が応用されてからすでに10年以上が経過している。現在では、あらゆる環境においてメタゲノム・メタ16S解析が実施され、環境中の微生物の系統に加えて、遺伝子配列そのものやその機能に至るまで詳細に解析されるようになってきた。本稿ではこれらの環境微生物解析におけるバイオインフォマティクスの役割について述べたい。
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経ビジネスassocie (ISSN:13472844)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.17, pp.40-50, 2010-10-19
満員電車で女性に腕をつかまれて、駅のホームに引きずり降ろされる──。突然、痴漢の疑いをかけられた時、あなたは自分を守れるだろうか。刑事事件の加害者の弁護を手がける弁護士、岡野武志さんに、正しい対処法を聞いた。 大前提として、「自分はやっていない」と毅然とした態度で主張する必要がある。そのうえで迅速に済ませたいのが、家族への電話連絡だ。
4 0 0 0 OA 平成30年度論文賞 学会誌最優秀論文賞・国際誌最優秀論文賞受賞に寄せて
- 著者
- 二宮 晴夫 吉村 芳弘
- 出版者
- 公益社団法人 日本リハビリテーション医学会
- 雑誌
- The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine (ISSN:18813526)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.10, pp.823, 2019-10-18 (Released:2019-12-02)
- 著者
- 吉井 隼 野地 剛史 勝野 渉 田村 茉央 長谷川 美帆 遠藤 匠 森末 明子 青木 敏行 横内 到 杉 薫 渡邉 紳一 西村 宗修
- 出版者
- 一般社団法人 日本透析医学会
- 雑誌
- 日本透析医学会雑誌 (ISSN:13403451)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.9, pp.449-455, 2021 (Released:2021-09-28)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 1
維持血液透析(HD)患者における足趾上腕血圧比(TBI)の予後予測因子としての有用性は不明である.本研究では足関節上腕血圧比(ABI),TBI,皮膚灌流圧(SPP)を検査した157名のHD患者の5年後の生存の有無と因子を用いて予後因子解析を行った.Cox proportional hazards modelを用いた検定の結果,TBIは独立予後因子であった(p<0.001).また死亡予測のROC曲線では,TBIのcut off値が0.56,曲線下面積はTBI 0.91で予測能が最も高かった.算出されたTBIのcut off値を用いてTBI≧0.7群,0.7>TBI≧0.56群,TBI<0.56群およびZero TBI sign群に分類した結果,0.7>TBI≧0.56群の生命曲線はTBI≧0.7群と差がなかった.また,TBI<0.56群が0.7>TBI≧0.56群よりも有意に低く(p<0.001),Zero TBI sign群はTBI<0.56群よりも有意に低かった(p=0.020).TBI≧0.56群の死因には心血管疾患を認めなかったが,TBI<0.56群,Zero TBI sign群でその死因が4割を占めていた.HD患者においてTBIはABIおよびSPPより予後予測因子として有用であった.