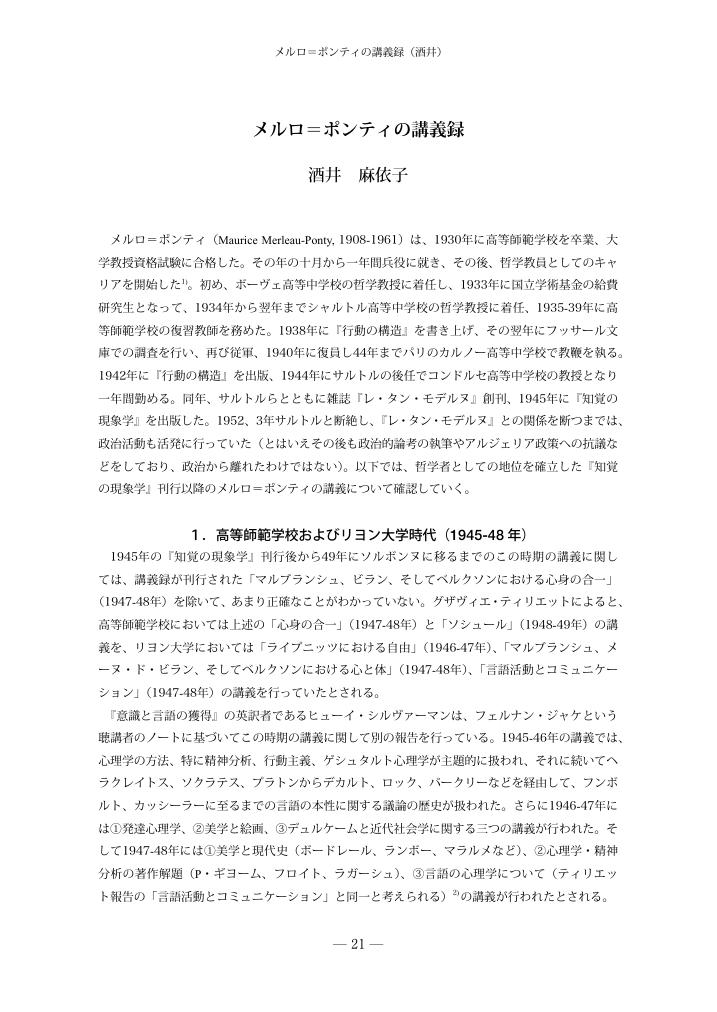3 0 0 0 OA 電気化学インピーダンススペクトロスコピー (EIS) の理論と解析の基礎
- 著者
- 杉本 克久
- 出版者
- Japan Society of Corrosion Engineering
- 雑誌
- Zairyo-to-Kankyo (ISSN:09170480)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.11, pp.673-680, 1999-11-15 (Released:2009-11-25)
- 参考文献数
- 30
- 被引用文献数
- 8 9
Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) has been known as a powerful tool for analyzing electrode reaction mechanism. In this review the history of EIS, the definition of electrochemical impedance, the general concept of transfer function, and the measurement method of electrochemical impedance using a transfer function analyzer are first introduced. Then, analytical methods of impedance spectra using electrical equivalent circuits and the kinetic theory of electrochemical reactions are stated. Finally, the future scope of EIS is briefly given.
3 0 0 0 OA <全文>失われた20年と日本研究のこれから・失われた20年と日本社会の変容
- 出版者
- 国際日本文化研究センター
- 巻号頁・発行日
- 2017-03-31
- 著者
- 佐藤 秀樹 前田 正治 小林 智之 竹林 唯
- 出版者
- 一般社団法人 日本健康心理学会
- 雑誌
- Journal of Health Psychology Research (ISSN:21898790)
- 巻号頁・発行日
- pp.211104167, (Released:2022-08-30)
- 参考文献数
- 29
This study used text mining and examined workers’ psychosocial burdens caused by the COVID-19 pandemic. Employees in the Fukushima Branch of the Japanese Trade Union Confederation (RENGO Fukushima) and related workplaces responded to a web-based questionnaire survey. The survey inquired about psychosocial burdens caused by COVID-19, and the participants responded using a free-text format. We analyzed the responses of 215 respondents. Logistic regression analysis indicated a stronger association between female workers and severe psychological distress than male workers. In addition, correspondence analysis showed that workers with severe psychological distress used more words related to “income” and more first-personal pronouns such as “I” or “we.” In contrast, women with college-age children used more words related to “online college courses,” “burdens,” and “anxiety.” These results suggest that female workers with children experience significant stresses associated with their children, and workers with severe psychological distress experience psychosocial burdens related to their income.
- 著者
- 佐竹 靖 加々見 良 河本 大地 吉田 寛
- 出版者
- 奈良教育大学ESD・SDGsセンター
- 雑誌
- ESD・SDGsセンター研究紀要 = Bulletin of Center for ESD and SDGs (ISSN:27585948)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.41-50, 2023-03-31
本研究は、奈良教育大学附属中学校における「1・2年合同奈良めぐり」において、菩提川(率川)流域から学ぶ ESD 実践を構想し、実践の結果生じた生徒の変容からその効果を明らかにすることを目的としている。また、ESD で重視されるシステム思考を、中学校の実践に落とし込み、そのあり方や有効性についても考察する。本実践のねらいは、多様な視点から川の役割や人との関わりについて読み解き、持続可能な川のあり方や関わりについて自分事に引き 寄せて考えることで、流域の社会変容にせまる自己変容を促すことにある。実践の結果、生徒の流域に対する価値観の変容が引き起こされ、流域の持つ地域課題について自分事に引き寄せて思考することができた。
- 著者
- 清水 研
- 出版者
- 一般社団法人 日本心身医学会
- 雑誌
- 心身医学 (ISSN:03850307)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.5, pp.399-404, 2015-05-01 (Released:2017-08-01)
- 被引用文献数
- 1
本稿においては,心身医学講習会で取り上げた内容の中で,「心的外傷後成長」に焦点を当てて解説を行う.がん罹患に伴う精神的苦痛は大きく,うつ病などの病的な状況に陥る患者も少なくない.一方で,がん体験は必ずしも心理的に負の影響をもたらすだけではなく,精神的な成長を実感するなど,肯定的な変化をもたらすことも少なくない.このような外傷的な体験の後の肯定的な変化について,心理学的な手法を用いてまとめられた概念が「心的外傷後成長」である.心的外傷後成長モデルは人が危機的な状況に陥った後の心像の変遷について,わかりやすく示している.心的外傷を負った人のケアを担う医療者は,必然的に無力感に直面することになるわけであるが,心的外傷後成長モデルを知ることはその無力感をもちこたえ,治療者としてあり続けるためのヒントを与えてくれると筆者は感じている.
3 0 0 0 OA 讃岐平野の農業基盤としての条里遺構
- 著者
- 長町 博 小出 進 山路 永司
- 出版者
- 社団法人 農業農村工学会
- 雑誌
- 農業土木学会誌 (ISSN:03695123)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.12, pp.1371-1376,a1, 1991-12-01 (Released:2011-08-11)
- 参考文献数
- 4
讃岐平野は大和・近江平野と並んで条里遺構が顕著に遺されていることで知られている。この条里遺構は土地基盤整備と密接な関係にある。本研究ではこの条里遺構を, 生産を規定する農業基盤の視点から捉えることとした。そこで讃岐平野における条里遺構分布を地理的に把握・計量し, その歴史的背景を古代条里制開拓として究明する一方, その地割がかなり乱れていて, 不整形地割になっていることの原因の解明を行った。また条里遺構地域では地割が不整形であるうえに, 圃場整備が実施困難で整備が遅れているために, 農業の生産性が停滞していることを指摘した。
3 0 0 0 OA テキストマイニングによる最近10年間の殺人事件における殺害動機の類型化
- 著者
- 財津 亘
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 日本心理学会大会発表論文集 日本心理学会第79回大会 (ISSN:24337609)
- 巻号頁・発行日
- pp.1AM-053, 2015-09-22 (Released:2020-03-27)
- 著者
- 堀場 幸子 Sachiko Horiba
- 出版者
- フェリス女学院大学大学院国際交流研究科
- 雑誌
- グローカル
- 巻号頁・発行日
- vol.03, pp.91-99, 2003-12
3 0 0 0 OA 服装を手掛りとした性格の想定
- 著者
- 土井 千鶴子 土田 正子 倉橋 久子
- 出版者
- The Textile Machinery Society of Japan
- 雑誌
- 繊維機械学会誌 (ISSN:03710580)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.11, pp.T240-T245, 1991-11-25 (Released:2009-10-27)
- 参考文献数
- 8
目的 服装から想定される性格を明らかにするため, 刺激としての服装をスライド写真によって調査対象者に提示し, 推測される性格が服装言語による提示の場合と, どのように異なるかを検討した.成果 対をなす11の服装の11性格尺度上での評定平均値の差は, 服装と性格の組み合わせ121セルのうち, 88%に有意差が認められた.性格が想定されやすかった服装は, シンプル/装飾的, ブランド志向の強い/ブランドにこだわらない, 明るい色/暗い色大胆/平凡地味/派手であった.服装を言語によって提示した場合と比較すると, 大柄/小柄な模様原色/中間色の服装を除く9対の服装については類似した結果が得られた.
3 0 0 0 OA 無知に基づく侮辱的行為はいかにして責任を問われるか
- 著者
- 中村 信隆
- 出版者
- 日本倫理学会
- 雑誌
- 倫理学年報 (ISSN:24344699)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, pp.173, 2017 (Released:2019-04-16)
The purpose of this paper is to consider the moral responsibility for actions from ignorance. For example, a man may behave violently toward women because he mistakenly believes that men are morally superior to women and are, therefore, permitted to treat women as instruments of man’s will. If we assume that such a man acts from a kind of ignorance, how can we hold him responsible for his action? To consider this problem, I look at the Strawsonian theory of moral responsibility and the concept of insult as an object of resentment. According to Peter Frederick Strawson’s famous lecture “Freedom and Resentment,” responsibility can be understood in the context of “reactive attitudes,” such as resentment. Focusing on insult as an object of resentment, Jeffrie Murphy and Jean Hampton argue that we resent injuries done to us because such injuries involve insulting messages about our dignity or moral status. The wrongdoer is saying, “I can use you for my purposes and you are not worth better treatment”; in these circumstances, resentment is the defensive reactive emotion against an action involving such an insult. Based on these ideas, we propose the following hypothesis: a person, who injures someone but mistakenly believes that his action is permitted and acts from ignorance, can be held responsible for his action if the victim appropriately feels resentment toward his action, as it involved an insulting message about the victim’s moral status. To validate this hypothesis, I will begin by critically reviewing previous studies on the moral responsibility for actions from ignorance. Following this discussion, I will explain the distinctive character of the insulting action from ignorance about someone’s moral status. Finally, I will demonstrate that an insulting action from ignorance about the victim’s moral status inevitably causes resentment by attacking the victim’s self-respect, and that ignorance never excuses the wrongdoer from their responsibility.
3 0 0 0 OA メルロ=ポンティの講義録
- 著者
- 酒井 麻依子
- 出版者
- 日仏哲学会
- 雑誌
- フランス哲学・思想研究 (ISSN:13431773)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, pp.21-32, 2022-09-01 (Released:2022-10-01)
3 0 0 0 OA Magnetic Resonance Imaging of Cancer-Associated Deep Vein Thrombus in a Patient With Gastric Cancer
- 著者
- Toshihiro Gi Yasuyoshi Kuroiwa Yasushi Kihara Sae Miyaushiro Atsushi Yamashita
- 出版者
- The Japanese Circulation Society
- 雑誌
- Circulation Reports (ISSN:24340790)
- 巻号頁・発行日
- pp.CR-23-0028, (Released:2023-04-14)
- 参考文献数
- 1
3 0 0 0 OA 日本におけるエホバの証人の展開過程 終戦から一九七〇年代半ばまで
- 著者
- 山口 瑞穂
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.91, no.3, pp.49-71, 2017-12-30 (Released:2018-03-30)
本稿は、日本におけるエホバの証人が、その特異な教説と実践をほとんど希釈することなく二十一万人を超える現在の教勢を築いてきた背景を、日本支部設立の過程における世界本部の布教戦略に着目して検討するものである。資料としては教団発行の刊行物を参照した。検討の結果、エホバの証人において重要な位置を占めているのは「神権組織」と称される組織原則であり、この原則における世界本部への忠節さは神への忠節さを意味するため、日本人信者にとっては社会への適応・浸透以上に世界本部への忠節さが課題となっていたことが明らかとなった。遅くとも一九七〇年代半ばには「神権組織」に忠節な日本支部が確立され、数多くの日本人信者たちが本部の方針に従い「開拓」と称される布教活動に参加した。特徴的な教義でもある予言の切迫感が布教意欲を高めたこともあり、布教の成功率が低い社会状況にありながら膨大な時間が宣教に費やされたことが、その後の教勢拡大を促した。
3 0 0 0 OA 宇宙輸送機用エアブリージングエンジンの開発研究
- 著者
- 佐藤 哲也 田口 秀之 小林 弘明 SATO Tetsuya TAGUCHI Hideyuki KOBAYASHI Hiroaki
- 出版者
- 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS)
- 雑誌
- 令和二年度宇宙輸送シンポジウム: 講演集録 = Proceedings of Space Transportation Symposium FY2020
- 巻号頁・発行日
- 2021-01
令和二年度宇宙輸送シンポジウム(2021年1月14日-15日. オンライン開催)
3 0 0 0 OA 平安朝の五節舞姫 : 舞う女たち
- 著者
- 服藤 早苗 Sanae FUKUTO
- 出版者
- 埼玉学園大学
- 雑誌
- 埼玉学園大学紀要. 人間学部篇 = Bulletin of Saitama Gakuen University. Faculty of Humanities (ISSN:13470515)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, pp.342(27)-327(42), 2011-12-01
十世紀から十二世紀にかけて、新嘗祭・大嘗祭に舞った五節舞姫で名前や出自がわかる44人を検討した。十世紀初期は公卿層でも実子を舞姫に献上していたこと、十世紀から十一世紀中頃にかけて現存の受領層女が公卿層の舞姫になっていたこと、殿上五節舞姫は十世紀後半以降も実女の可能性が高い事、十一世紀中期以降は、大嘗祭献上舞姫叙爵が実際に行われた事、十二世紀には公卿献上者の高位の親族や近臣女性が舞姫になっていたこと、等を指摘した。
3 0 0 0 OA エアウェイスコープ®
- 著者
- 鈴木 昭広 寺尾 基
- 出版者
- 日本臨床麻酔学会
- 雑誌
- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.2, pp.151-158, 2007 (Released:2007-03-30)
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 6 5
エアウェイスコープ® (AWS) はCCDカメラとLCDモニターを内蔵するビデオ硬性喉頭鏡で, 付属のディスポーザブルブレードとともに用いる新しい気管挿管器具である. 舌などの軟部組織に対して最小の外力で声門にアプローチでき, モニター画像で声門を詳細に観察できる. マッキントッシュ型とは異なるアプローチ方法のため, AWSを用いた際の喉頭所見はすべてCormack分類でgrade I 相当となる. さらに, ブレードには気管チューブガイド用の溝があり, チューブは気管軸に対して平行に進む. その際, モニター上にはガイド溝を経由したチューブの予想進行方向を示すターゲットマークが表示されるため, 施行者は声門をマークに合わせるように操作すれば容易に気管挿管を行うことができる. 初心者の気管挿管から熟達者の挿管困難症例への使用まで応用範囲は幅広く, 気管挿管の新しい時代を開くだけの潜在能力をもつと期待される. われわれは2006年7月の発売開始後より毎月50例程度, 4ヵ月でのべ200例の挿管症例を重ねたので, これまでに得られた知見をもとに, 本稿でその使用の実際について紹介する.
3 0 0 0 OA 曲直瀬道三の察証弁治 ―泌尿器疾患を中心に
- 著者
- 熊野 弘子
- 出版者
- 関西大学東西学術研究所
- 雑誌
- 関西大学東西学術研究所紀要 (ISSN:02878151)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, pp.495-513, 2016-04-01
This paper takes a concrete look at Manase Dosan’s Satsusho Benchi, a Japanese edition of the difficult original Chinese Bianzheng Lunzhi. In order to investigate specific individual examples of his diagnostic and clinical approach to diseases, the paper focuses on the treatment of urological disorders, particularly enuresis and incontinence, in medical texts of Dosan’s school. The results may be summarized as follows. Dosan based his writings on direct transmission from his teacher, supplemented by paraphrases and quotations from a wide range of Chinese medical texts. Such Chinese texts were sometimes quite verbose and overly detailed, but Dosan managed to provide a clear and economical explication of the main points of Bianzheng Lunzhi; based on the basic eight-principle pattern identification, which includes diagnoses of vacuity/repletion, cold/heat, and exterior/interior conditions, he gave an orderly presentation of these diagnoses with relevant symptoms and treatments. Such is the content of Satsusho Benchi, a work which may succeed in shedding light on an important aspect of the reception of Chinese medicine in Japan.
3 0 0 0 OA 考古学からみた古代王権の伊勢神宮奉祭試論
- 著者
- 山中 章 YAMANAKA Akira
- 出版者
- 三重大学人文学部 考古学・日本史学・東洋史学研究室
- 雑誌
- 三重大史学 (ISSN:13467204)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.1-18, 2010-03-31
3 0 0 0 OA <論文>渤海国の武器について
- 著者
- 方 学鳳 呉 満
- 出版者
- 大阪経済法科大学アジア研究所
- 雑誌
- 東アジア研究 = East Asian Studies (ISSN:13404717)
- 巻号頁・発行日
- no.25, pp.33-59, 1999-08-01