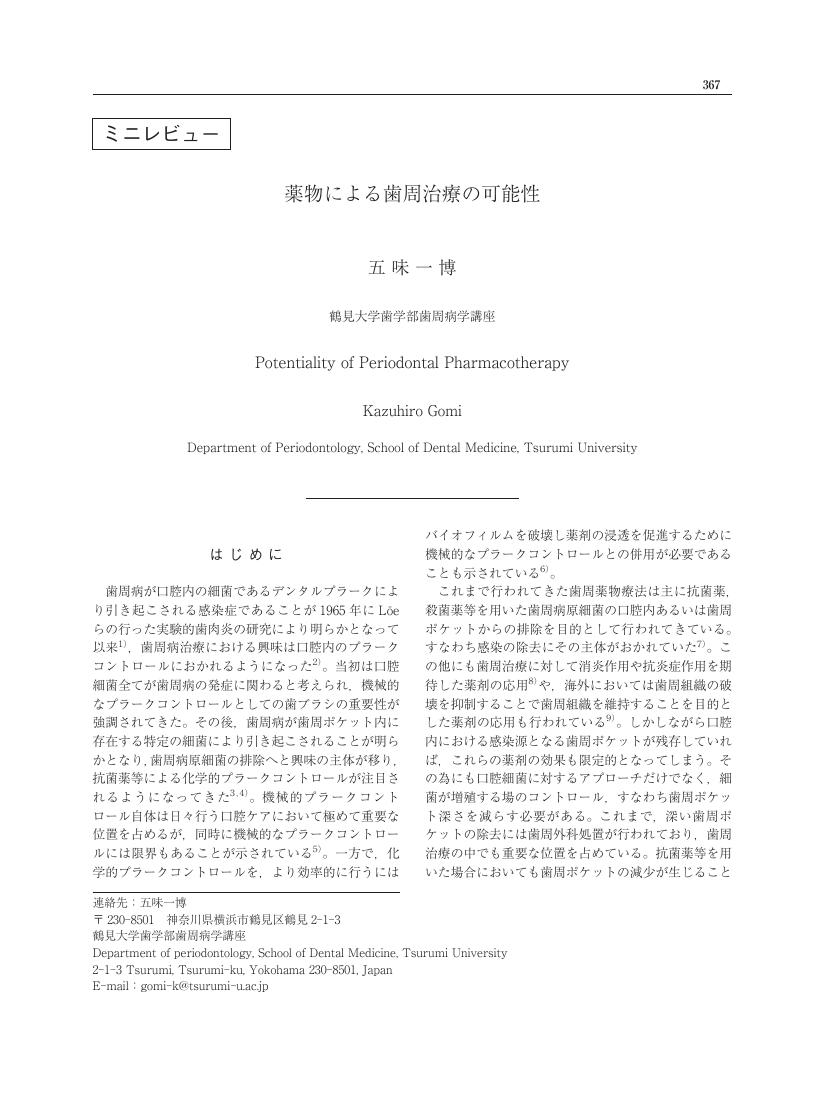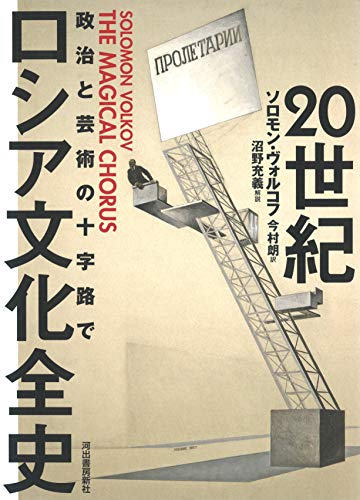3 0 0 0 OA 古代歌謡と和歌に見える漢文の影響
- 著者
- トリーニ アルド
- 出版者
- JSL漢字学習研究会
- 雑誌
- JSL漢字学習研究会誌 (ISSN:18837964)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.66-76, 2015 (Released:2017-05-29)
- 参考文献数
- 12
この論文は,奈良時代から平安初期まで,漢文が日本の和歌に与えた影響を分析することを目標としている。このテーマは色々な観点からアプローチができるが,私の観点は,日本語の表記または表現に漢文がどのような影響を与えたかに焦点を絞ることにする。具体的に,どのようなプロセスを通じて平安初期に,905年に編纂された「古今和歌集」に和歌が仮名表記で書かれ始めて,それから,その形に固まって,和歌の発展に大きく促進をもたらし,今日まで変わらないままで続いたかはこの論文の試みである。
3 0 0 0 OA 脳動脈解離による虚血性脳卒中への内科治療
- 著者
- 星野 晴彦
- 出版者
- 一般社団法人 日本脳卒中学会
- 雑誌
- 脳卒中 (ISSN:09120726)
- 巻号頁・発行日
- pp.10602, (Released:2018-02-27)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 1
動脈解離は我が国の脳卒中の0.7%を占め,その71.9%は虚血性発症であり,特に若年性脳 卒中の原因として重要な疾患である.我が国の動脈解離は後方循環,しかも頭蓋内椎骨動脈が多 く,破裂によるくも膜下出血の危険性を伴うことから,内科的治療選択が難しい問題がある.経静 脈血栓溶解療法については,動脈解離でも問題がなかったという報告が多いが,ほとんどは頭蓋外 動脈解離であり,頭蓋内動脈解離については慎重に症例を選択する必要がある.頭蓋外動脈解離を 対象とした無作為比較試験であるCervical Artery Dissection in Stroke Study(CADISS)では抗血小板療法 と抗凝固療法では転帰に差が認められなかったが,イベント数が少なく,動脈解離における抗血栓 療法についての臨床試験の難しさが明らかとなった.わが国で多い頭蓋内動脈解離については,出 血のリスクを考慮して,繰り返す画像診断で瘤形成がないことを確認しながら抗血栓療法の適応の 有無を慎重に検討する必要がある.
3 0 0 0 OA 薬物による歯周治療の可能性
- 著者
- 五味 一博
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本歯周病学会
- 雑誌
- 日本歯周病学会会誌 (ISSN:03850110)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.4, pp.367-374, 2015-01-30 (Released:2015-02-18)
- 参考文献数
- 60
- 被引用文献数
- 2
3 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1918年11月19日, 1918-11-19
3 0 0 0 OA 都市ごみ焼却飛灰からの重金属の溶出量に及ぼす溶出操作条件の影響
- 著者
- 金子 栄廣 山口 稔
- 出版者
- 一般社団法人 廃棄物資源循環学会
- 雑誌
- 廃棄物学会論文誌 (ISSN:18831648)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.2, pp.45-53, 1994-04-30 (Released:2010-05-31)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 3 3
溶出試験は廃棄物の有害性評価の一指標として広く用いられている。しかし, その方法が多様であるため, 結果の科学的な解釈が難しい, 異なる方法による結果の比較ができないなどの問題を抱えている。これを解決する手段として最大溶出可能量を測定することを目的とした溶出試験が注目されている。本研究では, 都市ごみ焼却飛灰中に含まれる重金属を対象として攪拌強度, 固液比, 接触時間, pHの溶出操作条件をパラメータとした溶出実験を行い, それぞれの条件下で溶出する金属量を調べることによって最大溶出可能量を調べるための溶出操作条件について検討した。その結果, カドミウム, 銅, 亜鉛およびマンガンについては最大溶出可能量を把握する溶出条件を設定できた。しかし, この条件では鉄の溶出量は接触時間の影響を, 鉛の溶出量は固液比および酸の種類による影響を受けることが明らかとなった。このように成分によって溶出の制限となる操作因子が異なるため, 最大溶出可能量を把握するための溶出試験方法を決めるには, 対象成分に応じて適当な溶出操作条件を検討する必要があることが示された。
3 0 0 0 OA 電子レンジ加熱による陶器製食器からの鉛の溶出
- 著者
- 中山 伸 藤井 修平 山本 良一
- 出版者
- The Japan Society of Home Economics
- 雑誌
- 日本家政学会誌 (ISSN:09135227)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.11, pp.951-956, 2003-11-15 (Released:2010-03-10)
- 参考文献数
- 17
Lead (Pb), a metal harmful to health, was found to be leached from ceramic kitchenware into a 5% acetic acid solution when the solution was held in the kitchenware for 90 min. This leaching of Pb was higher from dark-colored ceramic kitchenware such as green and brown than from light-colored ware. Pb was also observed to be leached when the ware containing vinegar samples or organic acids was heated for 1 min in a microwave oven. Acetic acid and oxalic acid, among the organic acids tested, were the most prominent for leaching out of Pb. Contamination of foods by Pb might therefore occur when acidic foods in ceramic kitchenware are heated in a microwave oven.
3 0 0 0 イオン液体を利用した革新的腸管吸収デリバリー技術の開発
3 0 0 0 OA フーリエ結像論とその応用
- 著者
- 村田 和美
- 出版者
- 公益社団法人 計測自動制御学会
- 雑誌
- 計測と制御 (ISSN:04534662)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.3, pp.262-271, 1974-03-10 (Released:2009-11-26)
- 参考文献数
- 37
3 0 0 0 OA 1.脳動脈解離
- 著者
- 後藤 淳
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.98, no.6, pp.1311-1318, 2009 (Released:2012-08-02)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 1
脳動脈解離は,脳梗塞や解離性動脈瘤破綻によるくも膜下出血など,虚血性・出血性脳卒中のいずれの原因にもなる注意すべき脳血管障害である.画像診断の進歩や認識の高まりから診断される機会が増えている.近年,本邦では複数の多施設共同研究で,頭蓋内椎骨動脈解離が多い実態が明らかにされつつある.頭痛や頸部痛を伴う虚血性脳卒中では必ず本疾患を疑い,慎重な問診,診察とともに血管壁を経時的に評価する画像検査が重要である.
3 0 0 0 OA 公立小学校における暖冷房・換気設備の地域別整備状況および使用実態
- 著者
- 吉野 博 飯野 由香利 瀧澤 のりえ 岩下 剛 熊谷 一清 倉渕 隆 長澤 悟 永田 明寛 長谷川 麻子 村松 學
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会環境系論文集 (ISSN:13480685)
- 巻号頁・発行日
- vol.74, no.639, pp.643-650, 2009-05-30 (Released:2009-11-30)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 6 5
This study aims to clarify the actual installing conditions of heating, ventilating, and air-conditioning (HVAC) systems and their operations in public elementary schools based on 568 school data obtained from a nation wide investigation. Some results are shown as follows: 1) Insufficient thermal insulation and air tightness were provided in many school buildings in warm climate areas, 2) Heating systems were provided in almost all rooms but their installing conditions varied with respective areas, 3) Air-conditioning systems for cooling are on the increase in many areas, especially urban areas, and 4) Ventilating systems are not operated under optimum conditions because of inadequate management. We suggest that the building envelope systems should be improved and it is necessary to make guidelines and inform teachers of the essentials of maintenance for HVAC systems for efficient operation.
3 0 0 0 20世紀ロシア文化全史 : 政治と芸術の十字路で
- 著者
- ソロモン・ヴォルコフ著 今村朗訳
- 出版者
- 河出書房新社
- 巻号頁・発行日
- 2019
- 著者
- Ioan ROXIN
- 出版者
- Graduate School of Humanities and Social Sciences, University of Tsukuba
- 雑誌
- Inter Faculty (ISSN:18848575)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.235-249, 2020-12
Suddenly, with the radical lockdown of half the planet, our accelerated, interconnected and hypermobile society found itself at a standstill, forced into immobility. This stillness has revealed to us the limits of consumerism, the flaws of a globalization centered on money and power, the blindness of our habits of thought and of the ideologies of progress. We can also see this lockdown as a philosophical experience that encourages us to reflect on the meaning of our lives. The time has come to learn to live in resonance with our world, to rethink, with more lucidity and finesse, our vision of the ‘good life’.
3 0 0 0 OA 東京電力福島第一原発事故による14C放出の可能性
- 著者
- 中村 俊夫 緒方 良至 箕輪 はるか 佐藤 志彦 渡邊 隆広
- 出版者
- 一般社団法人日本地球化学会
- 雑誌
- 日本地球化学会年会要旨集 2014年度日本地球化学会第61回年会講演要旨集
- 巻号頁・発行日
- pp.218, 2014 (Released:2014-09-12)
2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う東京電力福島第一原発事故により大量の放射性物質が環境中に放出された.大気粉塵,土壌,植物などの放射能分析から大気中に放出された核種とおおよその量が見積もられている.一方,地質学・考古学試料について約5万年までの高精度年代測定に利用されている放射性炭素(14C;半減期:5730年)の放出に関しては,その放出の形態や数量はきちんと確認されてはいない. 事故のあった福島第一原発付近への立入は制限されており,採取できる試料には限りがあるが,2012年に,福島第一原発から南に20~30km離れた広野町の海岸付近で海産物などを採取した.また,2011年秋には,福島第一原発から北西に約60km離れた福島大学金谷川キャンパスにおいて植物を採取し,それらの14C濃度を測定した.測定結果からは福島第一原発事故の影響は検出されなかった.
3 0 0 0 IR マイケェル・オークショット著「政治における合理主義,その他論集」1962
- 著者
- 奈良 和重
- 出版者
- 慶應義塾大学法学研究会
- 雑誌
- 法学研究 (ISSN:03890538)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.3, pp.118-121, 1965-03
紹介と批評
- 著者
- 劉 羽虹
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)
- 巻号頁・発行日
- vol.84, no.765, pp.2407-2415, 2019
- 被引用文献数
- 1
<p> In ancient China, although the changing dynasties frequently, the architecture of "Den" has hardly changed. It is limited to the Emperor's residences. On the other hand, Japan's "Den" is regarding as originated from China, but the meaning of "Den" has changed greatly. Initially, the last word "Den" was limited to the residences of the Emperor's family, which resembles China, but it used in the residences of nobleman as the age declines. The Commons and differences are existing in the way of using "Den" between Japan and China. I would like to clarify the transition process of "Den" in Japan while considering the reason for those differences.</p><p> In this paper, I mainly use historical records and nobility diary 4 books, Nihonkiryaku, Hyakurensyo, Hontyoseiki, Shoyuki. I am conducting surveys by reading whole passages, as it has seen that the last word of the residence changed from "Tei" to "Den", "Den" to "Tei", or mixed use of "Den" and "Tei". So as to clarify the transition process of "Den", I gathered all the descriptions used in "Den" and "Tei" of the residences from historical materials, clarified the actual situation. Following information was revealed about the</p><p> ① The mixed use of "Den" and "Tei" starts in the Emperor ichijyo. Biwatei is the first example. Which is the Michinaga Fujiwara's residence, and serve as the Imperial Palace of Emperor itijou. There is an existence of Michinaga Fujiwara in the mixed background.</p><p> ② Since then, along with the Satoteirika, cases of mixed use of "Den" and "Tei" are increased. Such as Nijou, Kyogoku and Takakura. It is possible that the back of Satoteiri influenced the transformation of "Den".</p><p> ③ The increase in the number of "Den" and "Tei" mixed use is remarkable during the inseiki period. Despite being nyoin and Emperor's father, it uses "Tei" instead of "Den".</p><p> ④ On the other hand, in nobleman's residences and villas outside Heiankyo, "Den" used in place of "Tei". The location may be related to the deviation of the principle.</p><p> ⑤ The percentage of cases where the part that should be marked as "Tei" is larger than the case where the term "Tei" is marked as "Den". Den's transformation is "Den" closed to the "Tei", but we cannot treat them as the same, it will hinge on the content of the articles. This is a big difference from the last word of "Den" in China.</p><p> ⑥ Sanesuke Fujiwara was highly conscious of using "Den" and "Tei". However, did not thoroughly use it. The usage of "Den" runs in a groove.</p><p> The mixed use of "Den" and "Tei" was hit in the Heian period while Emperor itijou, Michinaga's period. The time when Japan's unique culture had developed against the cultures of the Nara period when China's influence was strong. During the period of the inseiki, the increase in mixed use of "Den" "Tei" also estimated as a reflection of urbanization of Heiankyo.</p>
- 著者
- 奥村 賢
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, pp.114-121, 1988-05-20 (Released:2017-07-31)
- 参考文献数
- 8
3 0 0 0 OA 60年代ポップ革命 ~ビートルズとイギリス社会のヘゲモニックな関係~
- 著者
- 渡辺 愛子
- 出版者
- 早稲田大学多元文化学会
- 雑誌
- 多元文化 (ISSN:21867674)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.一四一-一二二, 2013-03-10
3 0 0 0 OA 運動年鑑
- 著者
- 朝日新聞社運動部 編
- 出版者
- 朝日新聞社
- 巻号頁・発行日
- vol.昭和15年度, 1940