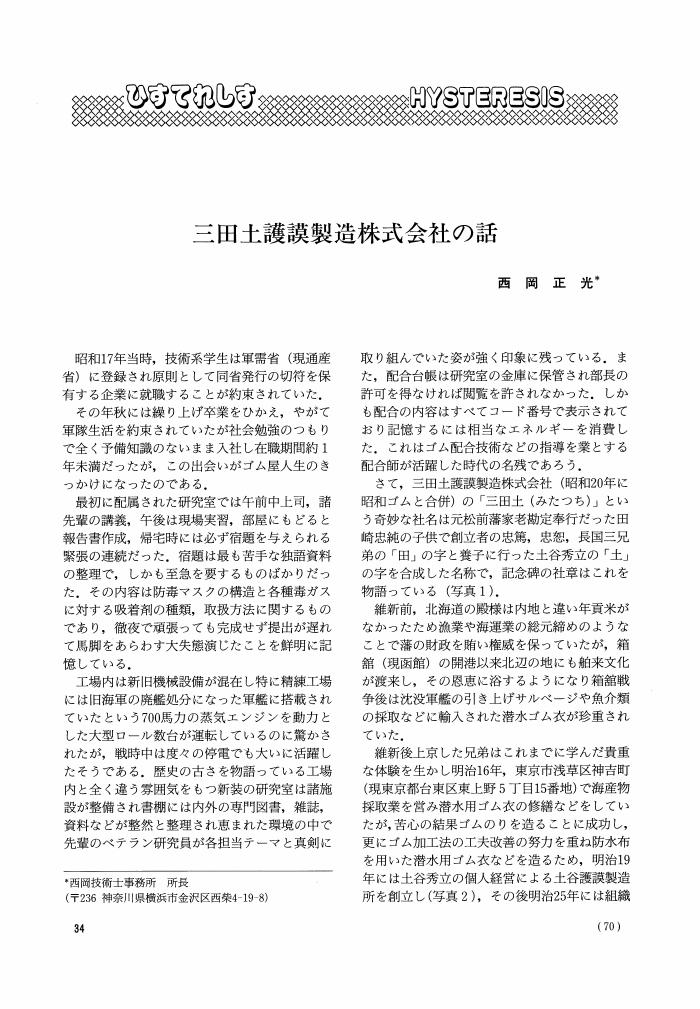3 0 0 0 OA 天皇制の批判 : 打倒?支持? 憲法改正(私案)
- 著者
- 川澄 未来子 藤原 孝幸 輿水 大和
- 出版者
- 日本感性工学会
- 雑誌
- 日本感性工学会論文誌 (ISSN:18845258)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.3, pp.627-634, 2009-02-28 (Released:2016-01-25)
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 1
This paper proposes a new approach for the analysis of a customer's initial impressions of an automobile front view. It is important for manufactures to analyze the differences in the expression that a studied automobile provokes in the viewer. We have tried to estimate quantitatively both the “facial expression” and the “perceived age” using modals that are already in common usage, for fifty automobile front views. Two visual stimuli were used in our experiments: the drawings and the caricatures generated by an automotive caricaturing system coche-PICASSO. The results show that this approach is effective in analyzing motor vehicle viewer perception.
3 0 0 0 OA アラカワ+ ギンズ:有機体 - 人間 - 環境プロセス. ユージン・ジェンドリン[原著]
- 著者
- 岡村 心平
- 出版者
- 関西大学東西学術研究所
- 雑誌
- 関西大学東西学術研究所紀要 (ISSN:02878151)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, pp.381-393, 2017-04-01
This paper is a Japanese translation of "Arakawa and Gins: The Organism-Person-Environment Process" (Genedlin, 2013). The purpose of this paper is a comparative discussion about the project of Arakawa and Gins, and of Genedlin's philosophy. First, the author pointed that Arakawa and Gins used the word "persons" as a verb, and he introduce a new concept "inging" to emphasis that function of personing. Secondly, the inging process is compared with Arakawa and Gins's concept of "landing sites," and they are discussed from the perspectives of the implicit intricacy that characterizes his philosophy and practice. Thirdly, it is shown that there is a physical and direct means of accessing the implicit intricacy that is called a "felt sense." Finally, the author introduces TAE (Thinking at the Edge), which is a practice using felt sense to facilitate creative thinking and theorizing, and is shown in these examples.
- 著者
- 川島 大輔 小山 達也 川野 健治 伊藤 弘人
- 出版者
- Japan Society of Personality Psychology
- 雑誌
- パーソナリティ研究 (ISSN:13488406)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.2, pp.121-132, 2009
- 被引用文献数
- 4 8
本研究は医師が一般診療場面において希死念慮を有した患者にどのようなメッセージを呈しているのかを探索的に検討することを通じ,医師の自殺予防に対する説明モデルを明らかにしようとしたものである。希死念慮者への医師の対応に関する調査において,これまで死にたいと述べる患者に自殺をとどまるようにメッセージを伝えた経験があると回答した166名の医師の自由記述を対象に,テキストマイニングの手法を用いて分析を行った。結果,頻繁に用いられる言葉が同定され,また対応分析により「共感的理解と告白」,「精神科への相談」,「病気の診断と回復の見通し」,「自殺しない約束」,「生の価値と他者への配慮」の5つのクラスターが確認された。さらに得られたクラスター変数と患者の性別および年齢との関連についても検討を行った。
3 0 0 0 2016年熊本地震災害の避難者の特徴:宇城市を事例として
- 著者
- 岩船 昌起
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 日本地理学会発表要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.2016, 2016
<b>【はじめに】</b>2016年熊本地震災害では,九州の県と市町村は,九州地方知事会での決定に基づき「カウンターパート方式」で被災市町村をそれぞれを専属的に支援した。筆者も,鹿児島県担当の宇城市で集中的に支援活動を行い,災害対策本部等に助言している。本発表では,この活動や宇城市提供データに基づき,宇城市での被害や避難者の実態を報告する。<br><b>【地震の概要】</b>2016年4月14日21時26分に熊本県熊本地方を震央とする震源の深さ11kmでM6.5の地震が発生し,益城町では震度7,宇城市では震度6弱が観測された(気象庁)。また,同じく熊本地方を震央とする震源の深さ12kmでM7.3の「本震」が16日1時25分頃に発生し,西原町および益城町で震度7,宇城市で震度6強が観測された。<br> 本震以降,熊本県阿蘇地方や大分県西部および中部でも地震が頻発し,14 日21 時以降6月30日までに震度1 以上を観測する有感地震が1,827 回発生している。これは,平成16年新潟県中越地震(M6.8)など日本で観測された活断層型地震の中で最も多いペースである。<br><b>【熊本地震による被害の概要】</b>熊本地震災害の主要な被災地の熊本県と津波災害が際立った東日本大震災被災地の岩手県とでの被害状況を比較する。人的な被害としては,死者・行方不明者が岩手県の方が桁違いに多いが,負傷者は熊本県が8倍弱多い。地震動による瓦の落下や家具の倒れ込み等で外傷を負った方々が多かったものと思われる。物的被害として,全壊は岩手県の方が7倍程度多いが,一部損壊は熊本県がほぼ倍程度の数となっている。<br> 東日本大震災では,全壊あるいは大規模半壊でも家屋を解体して「滅失」と判定されて応急仮設住宅に入居できた方々が多く,応急対策期の避難所での生活よりも復旧期の仮設住宅での暮らしの中でさまざまな問題が現出した感がある。一方,熊本地震では「一部損壊」認定世帯が被災者の大半を占め,半壊以上ので手厚く施される生活再建支援のさまざまな手立てを熊本地震災害被災者の大半に適用できない可能性が高い。<br> また,熊本地震では,土砂災害で阿蘇地方での大規模崩壊等が注目されているが,ほとんど報道されていない宅地や農地の盛土地等で小規模な崩壊や亀裂が多数生じており,それらの土地所有者の多くがその対処に難儀している。それは,宅地被害でも家屋の破壊に結びつかないと罹災証明で評価され難く,特に私有地の被害が公的支援の対象になり難いからである。盛土地での被害は,1978年宮城県沖地震や2011年東日本大震災でも丘陵地の団地等で繰り返し発生しており,日本列島の造成地では地震動でどこでも生じる可能性が高かい問題であった。<br><b>【避難者の特徴】</b>宇城市提供の避難者数データから, 14日「前震」直後より16日「本震」以降で避難者数が多いことが分かる。17日0時に宇城市内避難所20施設合計で,宇城市人口の2割程度の11,335人が最大の避難者数として記録されている。また,日中には避難者数が減じ,寝泊まりする夜間に増加する傾向がある。<br> 一方,約93年間(1923年~2016年4月13日)の宇城市での最大震度は,震度4であった(気象庁)。従って,「前震」までに震度5弱以上の経験者はごくわずかであり,かつ震度5弱以上の地震は宇城市で発生しないと考えていたようであった。そして,地震災害を身近なものと考えていなかったことから,地震にかかわる科学的な知識や地震から身を守る知識や技術も地震が多発する地域の人びとに比べて相対的に低かったと思われる。<br> 「地震に対する備え」が十分でなかった宇城市民は,14日夜の前震と16日未明の地震で「地震の揺れに対する恐怖心」が強化され,家屋の損壊が酷くなくても自宅に入れない人びとが多数出現した。特に夜に地震に遭ったことから家の中で寝られない人びとが多く,それが避難者数の夜間増加の要因となった。<br> 避難者が抱く「地震に対する恐怖心」を軽減・解消するためには,地震の発生が収まることが最も重要であるが,活断層が存在する熊本では今後も地震が必ず発生し,再び恐怖心が呼び起される可能性が高い。これに対処するには,ソフト面では,心理的なカウンセリング等と並んで,防災教育を通じて「地震を知り,これへ対処できる」知識と技術を「地震を経験した人びと」が身に付ける必要がある。具体的には①市民が地震に関する科学的知識を身に付けること,②家具の固定など被害に遭い難い居住環境を事前に整えておくこと,③地震発生時には自身の安全にかかわる周囲の状況を見極められること,④これに応じて「身を守る」行動を選択実行できることなどに及ぶ。<br><b>【本発表では】</b>今後の防災教育の立案にかかわり,宇城市提供資料の分析や,実施予定の質問紙調査の結果も交えて,本発表時には,熊本地震災害避難者の詳細な特徴を報告する。
- 著者
- 内海 庫一郎
- 出版者
- 土地制度史学会(現 政治経済学・経済史学会)
- 雑誌
- 土地制度史学 (ISSN:04933567)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.3, pp.60-62, 1978-04-20 (Released:2017-10-30)
- 著者
- 楠 俊雄 穂積 香織 小倉 達也 小林 巧 重田 文弥
- 出版者
- 日本皮膚科学会西部支部
- 雑誌
- 西日本皮膚科 (ISSN:03869784)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.1, pp.70-78, 2009-02-01 (Released:2009-04-21)
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 2 2
イトラコナゾール(イトリゾール®カプセル50)は,ベルギー ヤンセン社で合成されたトリアゾール系抗真菌剤である。本邦では2004年2月に爪白癬に対し,本剤400mg/日を1週間服薬した後,3週間休薬するサイクルを3回繰り返す「パルス療法」が承認され,この承認に伴い,爪白癬の治療を受けた患者2000例を対象とした市販後調査を実施し,パルス療法の有効性及び安全性について検討を行った。有効性については,有効性解析対象症例1051例における全般改善度は84.3%であった。また,感染部位,初発・再発,肥厚度,混濁比等,爪白癬の状態や重症度によらず,いずれも80%以上の有効率を示すことが確認された。一方,爪白癬治療の継続状況を検討したところ,治療完結率評価対象症例2394例において,3サイクル分のイトラコナゾール処方が完結した患者の割合は93.0%であった。安全性については,安全性解析対象症例2532例中288例(11.4%)に副作用が認められたが,主な副作用は,既知で軽微な臨床検査値異常であった。以上より,イトリゾール®カプセル50パルス療法は,爪白癬に対して優れた有効性ならびに良好な安全性を有することが確認された。
3 0 0 0 OA 使用性を考慮したボールペンの機能条件に関する研究
- 著者
- 鈴木 剛 上野 義雪
- 出版者
- Japan Ergonomics Society
- 雑誌
- 人間工学 (ISSN:05494974)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.2Supplement, pp.156-157, 2007-06-02 (Released:2010-03-15)
- 参考文献数
- 6
3 0 0 0 OA 在宅酸素療法患者の外出を支援する追従型搬送移動体の開発
- 著者
- 遠藤 玄 谷 篤 福島 E.文彦 広瀬 茂男 入部 正継 田窪 敏夫
- 出版者
- 一般社団法人 日本ロボット学会
- 雑誌
- 日本ロボット学会誌 (ISSN:02891824)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.8, pp.779-787, 2012 (Released:2012-11-15)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 1
Home oxygen therapy (HOT) is a medical treatment for patients suffering from severe lung diseases. Although a walk in an outdoor environment is recommended for the patients to keep physical strength, patients always have to carry a portable oxygen supplier which is not sufficiently light weight for the patients. Our ultimate goal is to develop a mobile robot carrying an oxygen tank and follows a foregoing patient in an urban outdoor environment. We have proposed a mobile robot with a tether interface to detect the relative position of the foregoing patient. In this paper, we improve mobile platform mechanisms and active wheels to maximize the negotiating step height, and to allocate sufficient luggage area in the main body carrying an actual oxygen tank. The following control algorithm is also improved and demonstrate its effectiveness in an outdoor following experiment.
- 著者
- Yuya Suzuki
- 出版者
- Arachnological Society of Japan
- 雑誌
- Acta Arachnologica (ISSN:00015202)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.1, pp.49-54, 2020-06-20 (Released:2020-06-20)
- 参考文献数
- 24
Predatory behavior in Cnodalia harpax is described herein for the first time. Females of the species hanging on two threads span between branches at night were observed in the field. One of them was feeding on a sciarid fly. Observations in the laboratory revealed that C. harpax used its long claws to capture prey by hooking the legs, wings, and body. The impalement of prey by claws, previously described in tetragnathid spiders with long claws, had not been observed in C. harpax.
3 0 0 0 OA 食品添加物関連法規の改正
- 著者
- 日高 徹
- 出版者
- 日本海水学会
- 雑誌
- 日本海水学会誌 (ISSN:03694550)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.6, pp.390-398, 1990 (Released:2013-02-19)
3 0 0 0 OA 中近世北方交易と蝦夷地の内国化に関する研究
- 著者
- 関根 達人 榎森 進 菊池 勇夫 中村 和之 北野 信彦 深澤 百合子 谷川 章雄 藤澤 良祐 朽木 量 長谷川 成一 奈良 貴史
- 出版者
- 弘前大学
- 雑誌
- 基盤研究(A)
- 巻号頁・発行日
- 2010-04-01
中世・近世の多様な考古資料と文献史料の両方から、津軽海峡・宗谷海峡を越えたヒトとモノの移動の実態を明らかにすることで、歴史上、「蝦夷地」と呼ばれた北海道・サハリン・千島地域へ和人がいつ、いかなる形で進出したかを解明した。その上で、「蝦夷地」が政治的・経済的に内国化されていくプロセスを詳らかにし、そうした和人や日本製品の蝦夷地進出が、アイヌ文化の形成と変容にどのような影響を与えたか考察を行った。
- 著者
- HARADA Yayoi ENDO Hirokazu TAKEMURA Kazuto
- 出版者
- Meteorological Society of Japan
- 雑誌
- 気象集誌. 第2輯 (ISSN:00261165)
- 巻号頁・発行日
- pp.2020-062, (Released:2020-08-12)
- 被引用文献数
- 5
To explore large-scale atmospheric factors causing heavy rainfall events that occurred widely in western Japan, a composite analysis of atmospheric fields during the past heavy rainfall events in the region is performed using the Japanese 55-year Reanalysis. During heavy rainfall events, atmospheric fields are characterized by an upper-tropospheric trough over the Korean Peninsula (KP), an upper-tropospheric ridge to the east of Japan, a surface high-pressure system to the southeast of Japan, and southwesterly moisture flux. The composite analysis indicates that a clear wave train due to quasi-stationary Rossby wave-packet propagation (RWPP) along the polar front jet (PFJ) over Siberia tends to occur just before extreme events. Further analysis considering various time-scale variabilities in the atmosphere reveals that surface high-pressure anomalies to the southeast of Japan are dominated by variability with a 25–90-day period, whereas variability with an 8–25-day period dominates lower-pressure anomalies over the East China Sea (ECS) in relation to the development of the upper-tropospheric trough around the KP. We also investigate atmospheric fields during an extreme heavy rainfall event that occurred in early July 2018 (HR18). Atmospheric features during HR18 are generally similar to those of the other heavy rainfall events. However, a remarkable RWPP occurred along the sub-tropical jet (STJ) in late June 2018 and intensified a surface high-pressure system to the southeast of Japan. In addition, a low-pressure system with an 8–25-day period to the south of Japan developed in association with wave breaking induced by the remarkable RWPP along the STJ and propagated northwestward toward the ECS and then to Japan. The simultaneous development of high- and low-pressure systems contributed to the extreme southerly moisture flux into western Japan. HR18 is also characterized by a sharp upper-tropospheric trough over the KP that is dominated by high-frequency variability with a period < 8 days.
3 0 0 0 OA スクワット肢位における足圧中心位置の違いが下肢筋の筋活動に及ぼす影響
- 著者
- 池添 冬芽 市橋 則明 森永 敏博
- 出版者
- 日本理学療法士学会
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.1, pp.8-13, 2003-02-20 (Released:2018-09-25)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 6
本研究の目的は,スクワット肢位における前後方向の足圧中心位置の違いが下肢筋の筋活動量に及ぼす影響について明らかにすることである。対象は健常成人12名であった。筋電図の測定筋は大腿直筋,内側広筋,外側広筋,半膜様筋,大腿四頭筋,腓腹筋(内側頭),前脛骨筋の7筋とした。3種類の膝屈曲角度(漆屈曲30,60,90度位)での両脚スクワット肢位について,それぞれ足圧中心を前方位,中間位,後方位で3秒間保持させたときの筋活動を測定した。大腿直筋,内側広筋,外側広筋,および前脛骨筋の筋活動ではすべての角度で足圧中心位置の違いによる主効果が認められ,いずれも後方位で最も高い値を示した。半膜様筋と大腿四頭筋では膝屈曲30度位においてのみ,腓腹筋ではすべての角度で足圧中心位置の違いによる主効果が認められ,いずれも前方位で高くなる傾向を示したが,これらの筋の筋活動量は20%と低い値を示した。本研究の結果,大腿四頭筋や前脛骨筋においては,足圧中心位置を後方位にして大きい屈曲角度でスクワット肢位を保持することによって高い筋活動量が得られることが示唆された。
3 0 0 0 OA 「世界一低価格で便利な国産ロケット」で小型人工衛星を宇宙へ届ける
- 著者
- 稲川 貴大 青野 祐子
- 出版者
- 公益社団法人 精密工学会
- 雑誌
- 精密工学会誌 (ISSN:09120289)
- 巻号頁・発行日
- vol.86, no.12, pp.917-920, 2020-12-05 (Released:2020-12-05)
3 0 0 0 OA 1965年春季大会記事3
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 地理学評論 (ISSN:00167444)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.6, pp.383-393, 1965-06-01 (Released:2008-12-24)
3 0 0 0 OA 三田土護謨製造株式会社の話
- 著者
- 西岡 正光
- 出版者
- 一般社団法人 日本ゴム協会
- 雑誌
- 日本ゴム協会誌 (ISSN:0029022X)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.1, pp.34-36, 1996 (Released:2007-07-09)
- 被引用文献数
- 2 2
3 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1927年08月13日, 1927-08-13