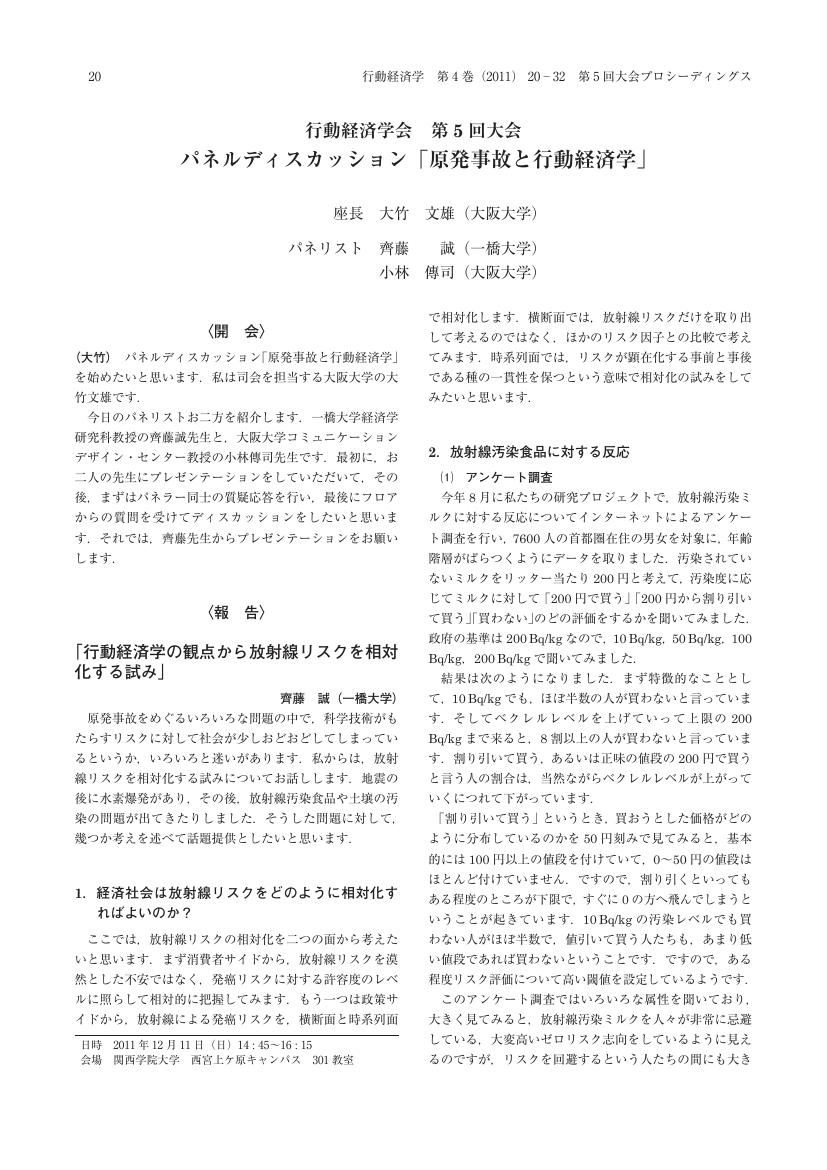86 0 0 0 OA 行動経済学会 第5回大会
86 0 0 0 OA 失われた浅間社の痕跡 城郭と富士塚地名から富士信仰文化圏へ
- 著者
- 大谷 正幸
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.95, no.1, pp.101-126, 2021 (Released:2021-09-30)
浅間社は富士信仰を行うための施設であるが、富士信仰の多様さに合わせてその形態や実際に祀る神はさまざまである。本論ではその諸相を提示し、最終的に、富士山―一次的に富士信仰を受容する大都市文化圏―二次的に受容して独自にローカルな信仰様式・習俗を創り出す文化圏近郊や富士山との中間地帯、という構造が富士山を挟んで東西にあるとする富士信仰の伝播と受容に関するモデルを考えたい。浅間社の諸相として、中世の城郭に浅間社が祀られた事例、富士信仰に因んだ可能性がある地名を中部地方各県から検索し、その中から「フジヅカ」に関する事例、「フジ」という名を持っていても富士信仰かわからない社の事例を挙げる。特に「フジヅカ」については研究史上その定義をめぐって議論があり、議論の有効性に対して疑問を持つ立場から考えてみたいと思う。
86 0 0 0 OA 尺度の作成・使用と妥当性の検討
- 著者
- 吉田 寿夫 石井 秀宗 南風原 朝和
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 教育心理学年報 (ISSN:04529650)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, pp.213-217, 2012 (Released:2013-01-16)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 12 11
86 0 0 0 OA オリゴヌクレオチド(プライマー)合成,早さの秘密
- 著者
- 細野 宏樹 西山 依里
- 出版者
- 公益社団法人 日本生物工学会
- 雑誌
- 生物工学会誌 (ISSN:09193758)
- 巻号頁・発行日
- vol.100, no.11, pp.611-615, 2022-11-25 (Released:2022-11-25)
- 参考文献数
- 9
86 0 0 0 OA 水の情報記憶について
- 著者
- 根本 泰行
- 出版者
- International Society of Life Information Science
- 雑誌
- 国際生命情報科学会誌 (ISSN:13419226)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.1, pp.75, 2016 (Released:2016-08-01)
故・江本勝博士は、水が記憶している情報を可視化する方法として、1994年に水の氷結結晶写真撮影法を開発し、その後の5年にわたる実験結果をまとめて、1999年に水の氷結結晶写真集『水からの伝言』を出版した。『伝言』の要点は、「水は情報を記憶する可能性がある」というところにある。しかしながら、従来科学においては、「水の情報記憶」について、なかなか認められず、結果として「『水からの伝言』は非科学的である」との批判を受けてきた。ところが過去10年ほどの間に、世界のトップレベルの科学者たちから、「水は情報を記憶する」ということを示唆する証拠が提示されてきている。 ワシントン大学のジェラルド・ポラック博士は、水には固体・液体・気体の他に、「第四の水の相」とでも呼ぶべき特殊な「相」があることを発見した。そして博士は「『第四の水の相』を考慮すると、『水からの伝言』で示されている現象を初めて科学的に説明できる可能性がある」という趣旨の発言をしている。その理由として、博士は以下の2つ―すなわち「水が凍る時、水は必ず『第四の水の相』を通過する」ということと、「『第四の水の相』は、水分子がランダムに動いている従来の液体の水のイメージと異なり、極めて秩序正しい形になっているので、実際に情報を記憶する能力を持っている可能性がある」ということ―を挙げている。 本講演においては、『水からの伝言』について簡単に説明した後に、ポラック博士の『第四の水の相』について、専門外の人にも分かりやすく紹介し、それらの間の関連性について議論する。
86 0 0 0 OA 魚肉調理におけるふり塩について
- 著者
- 上柳 富美子
- 出版者
- 一般社団法人 日本調理科学会
- 雑誌
- 調理科学 (ISSN:09105360)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.3, pp.206-209, 1987-11-20 (Released:2013-04-26)
- 参考文献数
- 6
86 0 0 0 OA The 3.11 Disaster and Data
- 著者
- Haruhiko Okumura
- 出版者
- 一般社団法人 情報処理学会
- 雑誌
- Journal of Information Processing (ISSN:18826652)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.4, pp.566-573, 2014 (Released:2014-10-15)
- 参考文献数
- 55
- 被引用文献数
- 2
“3.11”—the worst disaster in postwar Japanese history, consisting of the Great East Japan Earthquake (March 11, 2011), the subsequent tsunami and the nuclear accident at the Fukushima Daiichi power plant—taught us many valuable lessons. This paper reviews the disaster from a computer scientist's perspective, paying special attention to the problem of presenting data to the public, and discusses what we could do and can still do.
86 0 0 0 OA 食品の潜在的価値に関する研究 -調理型ルウカレーがもたらす共感性の要因解析-
- 著者
- 玉置 麻理 岸 さくら 大上 忠宏 清水 愼太郎 神宮 英夫
- 出版者
- 日本感性工学会
- 雑誌
- 日本感性工学会論文誌 (ISSN:18845258)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.3, pp.271-276, 2021 (Released:2021-08-31)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 1
Food quality is often considered to be the only defining factor of food value. In this study, another important aspect of food value is discussed: the social relationships which are commonly fostered by food. The latent value of curry roux for home use was investigated by studying behavior specific to eating curry. It was found that synchronization of spoons (including spoon and chopsticks) per meal time to be an indicator. It is well known that synchronization occurs when empathizing with others, suggesting that creating empathies with others during a meal is the latent value of curry. Also, text data analysis showed that curry is eaten with special and similar positive feelings by home cook and eater, compared to the other meals. These behavioral and psychological specificity supports the creation of empathy by curry.
86 0 0 0 OA キリアツメゴミムシダマシから着想を得た大気からの水回収技術
- 著者
- 平井 悠司 下村 政嗣
- 出版者
- 一般社団法人 表面技術協会
- 雑誌
- 表面技術 (ISSN:09151869)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.3, pp.127-131, 2017-03-01 (Released:2018-03-01)
- 参考文献数
- 12
85 0 0 0 OA [展望講演]石炭燃焼に伴う微量物質排出と最近の話題
- 著者
- 伊藤 茂男
- 出版者
- 公益社団法人 化学工学会
- 雑誌
- 化学工学会 研究発表講演要旨集 化学工学会第42回秋季大会
- 巻号頁・発行日
- pp.346-347, 2010 (Released:2011-01-09)
85 0 0 0 OA ウィークネス・フォビアの形成 ―明治期『少年世界』に見る‘男性性’―
- 著者
- 山口(内田) 雅克
- 出版者
- ジェンダー史学会
- 雑誌
- ジェンダー史学 (ISSN:18804357)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, pp.33-44, 2007 (Released:2011-11-01)
- 参考文献数
- 20
The topic of masculinity has not received much attention in Japan. It tends to be overlooked as an intrinsic or desirable attribute of men, although masculinity can have some influence as an ideology.Considering masculinity as a historical phenomenon, this article attempts to expose its original development, its redefinition during the early twentieth century and its characteristic "weakness-phobia" within a historical context. Shonen Sekai, or Youth World, the most popular magazine among children around the time of the Sino-Japanese and the Russo-Japanese wars, is examined from the angle of masculinity.At the time of the magazine's inception, many expectations and duties were assigned only to boys and statesmen and military personnel were presented as models for boys. Later when girl readers could not be ignored, columns for girls were established. Through short stories and articles, girls' roles and desirable attributes were defined and the gender boundary was clearly drawn. Boys' deviations from that boundary could be judged feminine or weak and undoubtedly put them in an unfavorable light. This insinuates "weakness phobia" into boys.Along with supporting imperialism and colonization in East Asia, Shonen Sekai highlighted gender ambiguity in Korean boys and girls and characterized Chinese boys as cowards. The concept of "a strong masculine Japanese boy" came to be highly valued. In fact, the Russo-Japanese war was justified by the logic that to fight against the strong (Russia) protecting the weak (China, Korea) was "true masculinity."Thus in contrast to the perceived weakness of girls or non-Japanese, the concept of Japanese hegemonic masculinity had been formed, distinguishing itself by "weakness phobia." Masculinity demonstrated its influence in connection with a nation, politics and foreign policy.
- 著者
- Kohei Takikawa Ryosuke Doijiri Naoto Kimura Ako Miyata Takuji Sonoda Naoya Yamazaki Shuhei Egashira Kiyotaka Oi Hiroki Uchida Kanako Kato Momoyo Oda Michiko Yokosawa Takahiko Kikuchi Takayuki Sugawara Hiroaki Takahashi
- 出版者
- Tohoku University Medical Press
- 雑誌
- The Tohoku Journal of Experimental Medicine (ISSN:00408727)
- 巻号頁・発行日
- vol.258, no.4, pp.327-332, 2022 (Released:2022-11-23)
- 参考文献数
- 23
- 被引用文献数
- 4
Antithrombin deficiency is a high-risk factor for venous thromboembolism during pregnancy, whereas cerebral venous thrombosis is rare. Cerebral venous thrombosis related to coronavirus disease 2019 (COVID-19) vaccines has been reported; however, there are a few reports of cerebral venous thrombosis after a messenger RNA (mRNA) vaccination. A 25-year-old female in her sixth week of pregnancy presented with headache 24 days after BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccination. The following day, she presented with altered sensorium and was diagnosed with severe cerebral venous thrombosis. She demonstrated heparin resistance and was found to have an inherited antithrombin deficiency. A heterozygous missense variant in SERPINC1 (c.379T>C, p.Cys127Arg, ‘AT Morioka’) was detected by DNA analysis. Despite intensive care with unfractionated heparin, antithrombin concentrate, and repeated endovascular treatments, she died on the sixth day of hospitalization. Cerebral venous thrombosis in pregnant women with an antithrombin deficiency can follow a rapid and fatal course. Treatment with unfractionated heparin and antithrombin concentrate may be ineffective in severe cerebral venous thrombosis cases with antithrombin deficiency. Early recognition of antithrombin deficiency and an immediate switch to other anticoagulants may be required. Although the association between cerebral venous thrombosis and the vaccine is uncertain, COVID-19 vaccinations may require careful evaluation for patients with prothrombic factors.
- 著者
- 岩佐 佳哉 熊原 康博
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- E-journal GEO (ISSN:18808107)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.2, pp.367-379, 2023 (Released:2023-09-21)
- 参考文献数
- 16
本研究では,広島県東広島市および呉市を対象とした現地調査と法務省が公開した登記所備付地図データを組み合わせることにより,呉市が1943年に敷設した上水道の遺構をマッピングし,その特徴を明らかにした.現地調査の結果,少なくとも192個の遺構が存在することが明らかになった.また,登記所備付地図データを用いることで,遺構に沿って幅3 m程度の細長い区画が長さ約10.7 kmにわたり今も存在することを確認できた.この細長い区画は上水道を敷設するために呉市が取得した土地である.旧呉市上水道の敷設の背景には旧日本海軍鎮守府の協力・支援があり,本研究で明らかにした遺構は,戦闘とは直接関係のない場所にも戦争の影響が及んでいたこと,その影響が現在も継続していることを示す戦争遺跡の一種とみなすことができる.そして,登記所備付地図データを活用することで,閲覧にかかる労力や費用が削減され,より精緻なマッピングが可能となった.
85 0 0 0 OA 大学生の性被害に関する調査報告 警察への通報および求められる援助の分析を中心に
- 著者
- 小西 吉呂 名嘉 幸一 和氣 則江 石津 宏
- 出版者
- 日本精神衛生学会
- 雑誌
- こころの健康 (ISSN:09126945)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.2, pp.62-71, 2000-11-30 (Released:2011-03-02)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 1
実態の解明が不十分な性被害に関するデータを得るとともに, 性被害にともなう具体的援助ニーズを探ることを目的として, 大学生1, 106人を対象に質問紙による調査を実施した (有効回答1, 072人)。その結果, 女性801人中569人, 男性271人中65人が何らかの性被害を経験していることが明らかになった。しかし, こうした性被害のほとんどは警察へ通報されていなかった。「レイプ」もまったく通報されていなかったが, これはすべての「レイプ」が「顔見知り」によって犯されていたことと関係していると考えられた。性被害経験者で何らかの援助を受けた人は634人中427人であり, 援助の種類は友人・知人からのなぐさめやアドバイスといったインフォーマルなものが中心であった。また, 求められる援助についても, 家族や友人などの身近な人に援助を求める傾向が強かった。したがって, 性被害経験に対しては, インフォーマルなサポートにも一定の意味があると考えられた。他方で, 専門的な援助では, 心理療法士 (臨床心理士) によるカウンセリングに最も高い期待が示された。これは, 性被害経験が身体よりも心の傷や心のケアと直結することを端的に示しているといえよう。以上, 予想を上回る多数の人に性被害経験のあることが明らかになったが, そうした被害者への安定した公的専門的援助システムは整備されていないか, または十分に機能しておらず, 身近な人に頼るか, 自分だけで悩む孤立した被害者の姿も浮き彫りにされた。
85 0 0 0 OA 爆発物テロの威力
- 著者
- 中山 良男
- 出版者
- 安全工学会
- 雑誌
- 安全工学 (ISSN:05704480)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.6, pp.427-434, 2016-12-15 (Released:2016-12-15)
- 参考文献数
- 27
火薬,爆薬そして手製爆薬による爆発物テロを想定し,最も脅威となる爆風と爆発飛散物の威力について概説する.最初に,爆発物テロの現状を紹介し,続いて爆発反応の形態に爆燃と爆轟の2 種類があり,爆発の威力が大きく変化することを解説する.次に,TNT 爆発による爆風のピーク静水過圧と正圧相インパルスの距離減衰特性を説明する.TNT 以外の爆発物の爆風威力はTNT 換算薬量で示されるので,その算出方法を解説し,あわせて代表的な爆発物のTNT 換算薬量率を紹介する.爆発飛散物については,金属容器に詰められた爆薬から発生する爆発破片の初速度の評価式を解説する.爆発による人体損傷は一次から四次の爆傷に分類されること,およびそれらの損傷レベルについて紹介する.最後に,テロ時の避難距離と火薬類取締法による各種保安物件までの安全距離などを比較する.
85 0 0 0 OA 日本軍票の貨幣史的考察(二)
- 著者
- 岩武 照彦
- 出版者
- 一般財団法人 アジア政経学会
- 雑誌
- アジア研究 (ISSN:00449237)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.2, pp.43-96, 1980 (Released:2014-09-15)
85 0 0 0 OA 光学的音響計測
- 著者
- 矢田部 浩平 石川 憲治 谷川 理佐子 及川 靖広
- 出版者
- 一般社団法人 電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会 基礎・境界ソサイエティ Fundamentals Review (ISSN:18820875)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.4, pp.259-268, 2019-04-01 (Released:2019-04-01)
- 参考文献数
- 66
- 被引用文献数
- 1
音は空気の疎密変化なので,空気の密度に依存する屈折率を光学系で検出することで,音を非接触に録ることができ,実体の存在するマイクロホンでは扱えない音場も光によって計測することができる.本稿では,筆者らがこれまで取り組んできた「空中可聴音の光学的音響計測」の歴史や原理,用いている2種類の干渉計(レーザドップラー振動計・偏光高速度干渉計)の光学的内容などについて概説し,光でしか計測できない実際の音場への適用例を幾つか紹介する.
85 0 0 0 OA 棘皮動物の自然史科学的研究と日本における振興
- 著者
- 藤田 敏彦
- 出版者
- 日本動物分類学会
- 雑誌
- タクサ:日本動物分類学会誌 (ISSN:13422367)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, pp.4-15, 2018-08-31 (Released:2018-08-31)
- 参考文献数
- 47
The Echinodermata is, in terms of species, one of the largest of animal phyla. They are distributed exclusively and widely in the marine environment, where they occupy important biological and environmental roles. Despite their relevance, relatively few scientists have studied echinoderms in Japan. I have comprehensively surveyed the echinoderm fauna of Japan and adjacent regions, and have discovered diverse and intriguing taxa. My research on these species has utilized diverse approaches, including taxonomy, phylogeny, ecology, morphology and paleontology. I have also initiated educational and outreach activities intended to encourage the study of echinoderm biology and natural history, including an annual scientific meeting emphasizing echinoderm research in Japan. Thanks to collaboration with students in my laboratory, scientific colleagues and “citizen scientists” including fans of echinoderms, we have seen a significant increase in Japanese echinoderm research.
85 0 0 0 OA 小児甲状腺癌の病理組織学的特徴,特にびまん性硬化型乳頭癌に着目して
- 著者
- 菅間 博
- 出版者
- 日本内分泌外科学会・日本甲状腺外科学会
- 雑誌
- 日本内分泌・甲状腺外科学会雑誌 (ISSN:21869545)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.4, pp.281-286, 2013 (Released:2014-01-31)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 1
小児甲状腺癌を理解するために必要な基礎事項を整理するとともに,福島原発事故以前に日本国内の多施設で手術された小児甲状腺癌を集計し,チェルノブイリ原発事故後の小児甲状腺癌と比較した。甲状腺癌の発症は女児の二次性徴がはじまる9歳位から認められ,20歳以下の甲状腺癌185例のうち15歳以下の小児の症例が39例あった。成人同様に女性に多いが,年齢が低いほど性差は少なくなる。小児に特徴的な甲状腺癌の組織型としては,びまん性硬化型乳頭癌DSPCと,充実型乳頭癌があげられる。DSPCは臨床的には橋本病との鑑別が問題となるが,その病理学的な本質は甲状腺の癌性リンパ管症とびまん性リンパ球浸潤と考えられる。充実型乳頭癌はチェルノブイリ原発事故に注目されたが,放射線被曝と関連のない国内でも若年者にみられる。病理組織学的に低分化癌との鑑別が問題となるが,臨床的に治療方針に違いがあることから,区別する必要がある。
85 0 0 0 OA 日常診療でよくみる自己免疫脳症の診察ポイントと治療の実際
- 著者
- 髙嶋 博
- 出版者
- 日本神経治療学会
- 雑誌
- 神経治療学 (ISSN:09168443)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.5, pp.S128-S128, 2016 (Released:2016-10-31)