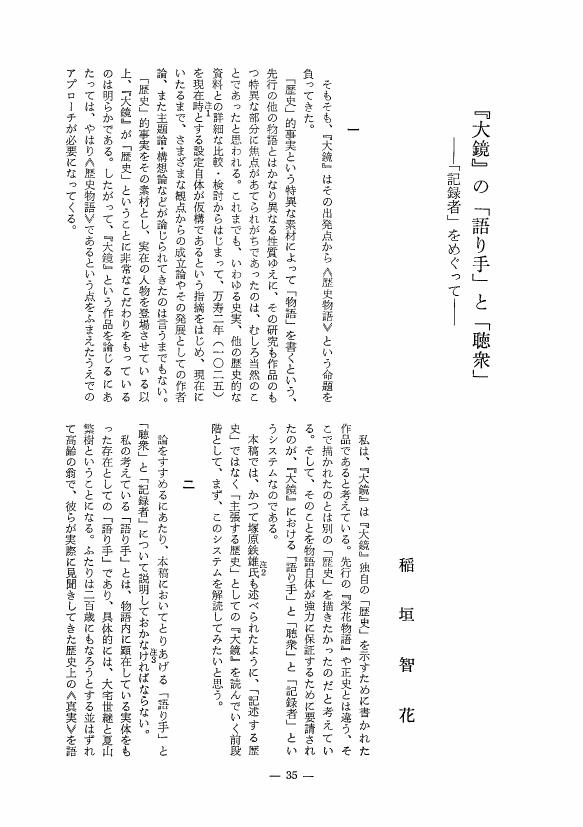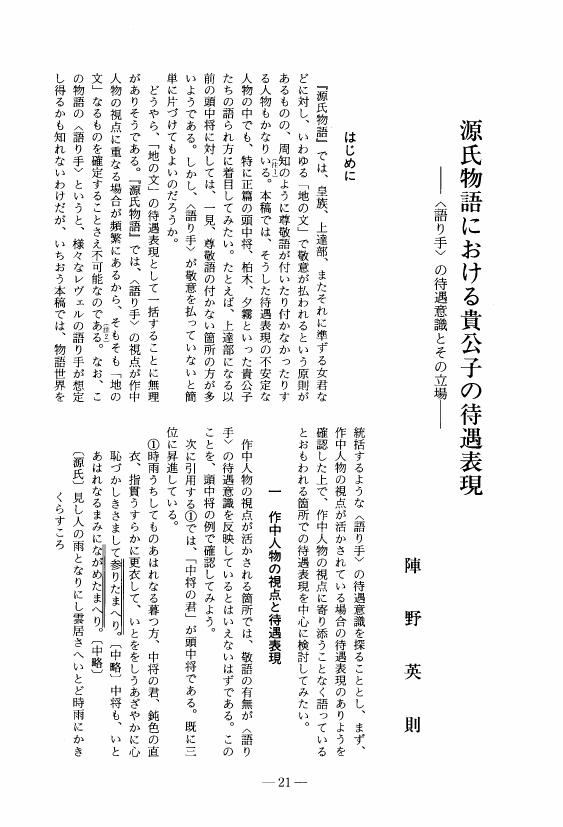2 0 0 0 OA 初対面会話における話題上の聞き手行動の中日比較
- 著者
- 楊 虹
- 出版者
- 公益社団法人 日本語教育学会
- 雑誌
- 日本語教育 (ISSN:03894037)
- 巻号頁・発行日
- vol.162, pp.66-81, 2015 (Released:2017-12-26)
- 参考文献数
- 19
本研究は,話題上の話し手・聞き手の役割交替の様相を分析し,中日母語場面の話題展開のパターン及び中日母語話者の話題上の聞き手としての会話の参加の仕方の相違を明らかにした。分析の結果,1.日本語母語場面と比べ,中国語母語場面では,話し手と聞き手の役割交替が頻繁に見られ,聞き手側だった参加者が話し手役割の発話をする場合が多く見られることがわかった。2.「役割固定型」「協調的役割交替型」「役割回帰型」「話し手役割競合型」という4つの話題展開のパターンが見られ,この4つのパターンの生起分布について,中日母語場面を比較したところ,有意差が見られた。一つの話題が展開していくプロセスにおいて,日本語母語場面では,話題上の話し手と聞き手が比較的固定的であるのに対して,中国語母語場面では,会話参加者の双方が話し手役割をめぐって交渉する場面も多く見られるという中日母語場面の異なる特徴が明らかになった。
2 0 0 0 OA 外傷に伴う低髄液圧症候群:日本と海外論文の比較
- 著者
- 川又 達朗 刈部 博 土肥 謙二 苗代 弘 平林 秀裕 村上 成之
- 出版者
- 一般社団法人 日本脳神経外傷学会
- 雑誌
- 神経外傷 (ISSN:24343900)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.1, pp.21-29, 2007-12-27 (Released:2022-06-27)
- 参考文献数
- 24
- 被引用文献数
- 1
In order to clarify clinical characteristics of "traumatic" intracranial hypotension (TIH) treated in Japan, 100 Japanese articles were reviewed and compared to 201 foreign articles. The results revealed the features of TIH in Japan as follows; 1) prolific numbers of the reported cases (227 cases) (foreign cases; 15 cases), 2) high incidence (69%) of traffic accident as a cause of injury (foreign cases; 20%), 3) long periods from injury to diagnosis; more than 1 year in many cases, 4) CSF leakage from lumber regions in vast majority cases (foreign cases: cervicothoracic regions; 91%), 5) fewer cases (55%) showing postural headache (foreign cases; 86%), 6) fewer cases (49%) showing dural enhancement on Gd-MRI (foreign cases; 93%), 7) fewer cases treated conservatively (foreign cases; 71%), 8) high numbers of blood patch procedure per patient, 9) lower cure rate (22%) by blood patch procedure (foreign cases; 100%). These results suggest that the clinical entity of TIH treated in Japan differs from that treated in foreign countries.
2 0 0 0 OA 高エネルギー粒子線照射による核変換反応を利用した組成制御と新材料
- 著者
- 高橋 平七郎 野田 哲二
- 出版者
- 公益社団法人 日本金属学会
- 雑誌
- まてりあ (ISSN:13402625)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.8, pp.966-968, 1995-08-20 (Released:2011-08-11)
- 参考文献数
- 13
2 0 0 0 OA 植物におけるセレン及びその同族元素の代謝機構
- 著者
- 小椋 康光
- 出版者
- 一般社団法人 日本微量元素学会
- 雑誌
- Biomedical Research on Trace Elements (ISSN:0916717X)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.3, pp.240-246, 2009-10-01 (Released:2009-12-16)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 1
Although selenium (Se) and tellurium (Te) are non-essential elements in plants, they are utilized in metabolic pathways to form the metalloid-containing compounds having carbon-metalloid covalent bond(s) (organic seleno/tellurometabolites). Therefore, it is necessary to identify seleno/tellurocompounds to determine the metabolic pathway of Se and Te, and understand the beneficial or toxicological effects of these compounds. Many literatures showed that the complementary use of HPLC-ICP-MS and HPLC-ESI (APCI)-MS/MS is a powerful tool for the speciation and identification of these metabolites. In this review, our recent works on the complementary use of ICP-MS, ESI-MS/MS and NMR from the viewpoint of identification of unknown seleno/tellurometabolites in plant samples were summarized. In particular, (1) speciation of sulfur (S) and Se-containing amino acids in Allium plants, (2) identification of a novel selenocompound in selenized Japanese pungent radish, (3) evaluation of function and translation efficacy of selenomethionine (SeMet)-containing proteins, (4) identification of SeMet-metabolites in wheat germ extracts, and (5) evaluation of Te metabolism in the Se-accumulating plant were mentioned.
2 0 0 0 OA 持続性知覚性姿勢誘発めまいの最新知見
- 著者
- 八木 千裕 堀井 新
- 出版者
- 一般社団法人 日本めまい平衡医学会
- 雑誌
- Equilibrium Research (ISSN:03855716)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, no.2, pp.62-70, 2020-04-30 (Released:2020-06-02)
- 参考文献数
- 34
- 被引用文献数
- 2 1
Persistent postural-perceptual dizziness (PPPD) is a newly defined diagnostic syndrome that was included in the 11th edition of the World Health Organization's International Classification of Diseases (ICD-11) in 2018. PPPD is characterized by persistent chronic vestibular syndrome, typically preceded by acute vestibular disorders, lasting for >3 months. The core vestibular symptoms of PPPD are dizziness, unsteadiness, and/or non-spinning vertigo and are exacerbated by upright posture/walking, active or passive movements, and exposure to moving or complex visual stimuli. PPPD is classified as a functional disorder, and not as a structural or psychiatric condition. No specific laboratory tests for the diagnosis of PPPD are available, and an assessment of the symptoms, exacerbating factors, and medical history is important for the precise diagnosis of PPPD. Although the exact pathophysiology of PPPD remains to be elucidated, data from physiological investigations and rapidly emerging advanced structural and functional neuroimaging studies have revealed some key mechanisms underlying the development of this disorder, including stiffened postural control, a shift in processing spatial orientation information to favor visual or somatosensory over vestibular inputs, and failure of higher cortical mechanisms to modulate the first two processes. Although PPPD is a relatively new diagnosis and will therefore be unfamiliar to many health professionals, undiagnosed or untreated dizzy patients who have been suffering for many years can be saved. Once recognized, PPPD can be managed by effective communication and individually tailored treatment strategies, including serotonergic medications, vestibular rehabilitation and cognitive behavioral therapy.
2 0 0 0 OA 平和構築支援における開発援助の枠組み ―わが国の取組みを中心として―
- 著者
- 黒澤 啓 小向 絵理
- 出版者
- 国際開発学会
- 雑誌
- 国際開発研究 (ISSN:13423045)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.1, pp.75-89, 2001-06-29 (Released:2020-03-28)
- 参考文献数
- 9
This paper aims to examine the framework and points for consideration associated with development assistance, with particular focus placed on post conflict peacebuilding. The objective of the paper is to provide specific strategies and policies that will allow Japan to actively contribute to peacebuilding as part of its development assistance. Specifically, the paper presents a basic outline of the background and concepts behind peacebuilding, followed by an analysis of the current situation surrounding Japan and JICA's support for this field. On top of this, using the example of Bosnia and Herzegovina, the paper provides an examination of priority support fields associated with implementation of development assistance as well as points for consideration connected with post conflict peacebuilding.In older to respond to the requirements of peacebuilding, which is a relatively new development issue, it is important to determine methods for providing peacebuilding support that have some degree of universality and commonality by drawing out and accumulating lessons gained from individual examples and experiences. Based on the case of Bosnia and Herzegovina as well as on experiences in peacebuilding gained thus far, this paper identifies the following six priority fields associated with post conflict peacebuilding: support for refugees, security control, rehabilitation of social infrastructure, institution-building, promotion of democratization, and economic recovery. The paper points out sustainable implementation of comprehensive support covering all six of these fields, and also a number of areas requiring consideration when providing support for post conflict peacebuilding.
- 著者
- Shota Niwayama Hirokazu Higuchi
- 出版者
- The Japanese Society for Horticultural Science
- 雑誌
- The Horticulture Journal (ISSN:21890102)
- 巻号頁・発行日
- pp.OKD-169, (Released:2018-10-26)
- 被引用文献数
- 7
The suitable soil pH for passion fruit growth has been well studied; however, the optimal soil pH for producing high-quality fruit has not been determined. In this study, the effects of soil acidity on fruit quality were determined. One-year-old passion fruit plants were grown in pots filled with soil adjusted to four pH levels (pH 3.5, 4.5, 5.5, and 6.5). The numbers of flowers and fruits were counted, and the external appearance and juice quality of the harvested fruits was evaluated. Vegetative growth, physiological responses, and leaf mineral contents were also measured. At pH 4.5 and 5.5, fruit were heavier and larger, with a better peel color than the fruit at pH 3.5 and 6.5. As indicators of taste, the titratable acid content was lower and total soluble solid content was higher at pH 4.5 and 5.5, indicating preferable palatability. The sugar/acid ratio was highest at pH 4.5. The numbers of flowers and fruits, vegetative growth, and photosynthetic rate were also higher at pH 4.5 and 5.5. Conversely, soil with a near-neutral pH of 6.5 yielded fruit with a pale peel color, severe peel wrinkles, and a low sugar/acid ratio. Vegetative growth was inhibited, and the photosynthetic rate and leaf water potential were lowest at pH 6.5. The leaf/fruit ratio was lower at pH 6.5. A shortage of photosynthate may have reduced fruit quality. Leaf nitrogen, manganese, and zinc contents, as well as the chlorophyll content (SPAD index), were lowest at pH 6.5. Deficiencies in these minerals may have led to a low photosynthetic rate and SPAD index under the higher pH condition. With excessive acidic soil (pH 3.5), vegetative growth, photosynthetic rate, and the number of flowers were as high as those at pH 4.5, although the fruit-set percentage and fruit quality were lower. Thus, strongly acidic soil around pH 4.5 is recommended for producing high-quality passion fruit.
2 0 0 0 OA アーユルヴェーダは誰のものか : 「伝統」医療・知的財産権・国家
- 著者
- 加瀬澤 雅人
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 文化人類学 (ISSN:13490648)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.2, pp.157-176, 2005-09-30 (Released:2017-09-25)
近年、アーユルヴェーダは世界的な医療となりつつある。南アジア地域固有の医療実践であったアーユルヴェーダは、今日では世界各地に拡大し、それぞれの地域で新たな解釈が加えられ実践されている。インドにおいてもアーユルヴェーダがグローバル化した影響は大きい。多くの患者が海外からインドに訪れるようになり、南インド・ケーララ州では、このような患者のための滞在施設が乱立し、アーユルヴェーダは一大産業となりつつある。世界とのかかわりのなかで、インドのアーユルヴェーダ実践は変容し再構成されているのである。しかし、アーユルヴェーダがグローバルな産業として発展している現状について、インド現地のアーユルヴェーダ関係者の不安もある。海外でアーユルヴェーダが医療ではなく「癒し」術として広がり、その一方でアーユルヴェーダの生薬や治療法にたいしては先進国の企業によって特許が取られていく。このような状況は、インドのアーユルヴェーダ医師や製薬関係者の海外進出を阻み、アーユルヴェーダを彼らの関与できない方向へと転換している。こうした状況のなかで、アーユルヴェーダの知識・技術に関する権利を国家的に保護し、インド主導で医療・産業としての可能性を世界規模で広げていくために、近年ではこれらの知的財産・技術をインドの「ナショナルな資源」として位置づける動きが生まれつつある。
2 0 0 0 OA パブリシティ権侵害の準拠法
- 著者
- 斉藤 邦史
- 出版者
- 公益財団法人 情報通信学会
- 雑誌
- 情報通信学会誌 (ISSN:02894513)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.2, pp.83-92, 2014 (Released:2014-11-27)
著名人の氏名や肖像が宣伝広告や商品事業等に利用された場合に問題となるいわゆるパブリシティ権の侵害における準拠法選択に関しては、市場の横取りという側面を重視し法適用通則法17条の適用範囲に含める見解と、信用毀損との類似や肖像等の人格的側面を考慮して19条の適用範囲に含める見解とが対立している。本稿では、パブリシティ権の侵害における準拠法の選択について、周辺事例に関する裁判例および学説の概観を通じて、見解が分かれている通則法の解釈を検討し、以下の考察を得た。第一に、19条の定める単位法律関係の範囲は、人格的な権利利益の侵害に限定されると解すべきである。第二に、パブリシティ権の侵害における法律関係の性質は、人格権としての氏名権や肖像権との区別に鑑みて、不正競争の一類型と理解すべきである。第三に、パブリシティ権の侵害を理由とする差止請求と損害賠償請求は、いずれも17条および20条により準拠法を決定すべきである。
2 0 0 0 OA 小柴胡湯による薬剤誘起性肺炎の1例
- 著者
- 築山 邦規 田坂 佳千 中島 正光 日野 二郎 中浜 力 沖本 二郎 矢木 晋 副島 林造
- 出版者
- The Japanese Respiratory Society
- 雑誌
- 日本胸部疾患学会雑誌 (ISSN:03011542)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.12, pp.1556-1561, 1989-12-25 (Released:2010-02-23)
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 8
小柴胡湯による薬剤誘起性肺炎の1例を報告した. 症例は71歳, 女性で, 肺炎の診断で入院した. 発熱, 咳嗽, 呼吸困難と胸部X線上両肺野にびまん性粒状網状影を認めた. 夏型過敏性肺臓炎を疑い経過観察としたが, さらに増悪傾向を示したため, 薬剤誘起性肺炎を疑い, 全投薬を中止すると共にプレドニンを投与したところ, 臨床症状, 検査所見, 胸部X線は著明に改善した. 経気管支肺生検では間質性肺炎像を呈し, リンパ球刺激試験では小柴胡湯に対し陽性を示した. チャレンジテストで発熱, 低酸素血症, さらに胸部X線上間質性肺炎像の出現を認めたため, 小柴胡湯による薬剤誘起性肺炎と診断した. 当薬剤による薬剤誘起性肺炎の報告は世界で第1例目と思われる.
2 0 0 0 OA バウムガルテンの美学と形而上学における虚構の真理 可能的なものの存在論をめぐって
- 著者
- 桑原 俊介
- 出版者
- 美学会
- 雑誌
- 美学 (ISSN:05200962)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.1, pp.1, 2017 (Released:2018-07-01)
Alexander Gottlieb Baumgarten (1714-62) hat in seiner Ästhetik die Theorie der „ästhetischen Wahrheit“ (veritas aesthetica) etabliert. Ihre Originalität besteht nicht nur darin, dass sie für die „sinnliche Erkenntnis“ spezifisch ist, sondern auch, dass die Fiktion, besonders die „poetische Fiktion“ (fictio poetica), welche „in dieser Welt als Mögliches keinen Platz hat“, in seiner Ästhetik für „metaphysisch wahr“ anerkannt wird. Diese poetische Fiktion, die bis dahin als ein „nur Mögliches“ (mere possibile) oder ein „Nicht-Seiendes“ (non ens) nicht für wahr gehalten wurde, wurde in seiner Ästhetik auf die metaphysische Wahrheit gegründet und als „Seiendes“ (ens) gültig gemacht, wodurch ihr ein ontologischer Grund der Wahrheit verliehen wurde. Die ästhetische Wahrheit bedeutet hier also nicht nur die „Wahrheit der Erkenntnis“ (veritas cognitionis), sondern auch die „Wahrheit des Seinenden“ (veritas entis). Diese zwei Arten der Wahrheit sind in Baumgartens Ästhetik untrennbar miteinander verbunden. In welchem Sinne wird nun diese Wahrheit der Fiktion, oder die Wahrheit des Möglichen, wissenschaftlich-theoretisch möglich gemacht? Beachtenswert ist hier, dass seine Metaphysik oder Ontologie (wie auch Leibniz’ und Wolffs) auf ganz anderen Ideen als vorhergehende beruht, nämlich als „Wissenschaft der möglichen Dinge“ (scientia possibilium) konzipiert wurde. In dieser Abhandlung wird dieses Thema mit Rücksicht auf eine kleine Begriffsgeschichte von „Möglichkeit“ und „Mögliches“ im Detail behandelt werden.
2 0 0 0 OA 古今集の掛詞をめぐって
- 著者
- 鈴木 日出男
- 出版者
- 中古文学会
- 雑誌
- 中古文学 (ISSN:02874636)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, pp.10-20, 1971-09-30 (Released:2019-03-10)
2 0 0 0 OA 源氏物語の草子地についての一視角 ―その方法的意義―
- 著者
- 池田 和臣
- 出版者
- 中古文学会
- 雑誌
- 中古文学 (ISSN:02874636)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, pp.38-47, 1976-09-30 (Released:2019-03-10)
2 0 0 0 OA 屏風歌の生成と『古今集』
- 著者
- 吉川 栄治
- 出版者
- 中古文学会
- 雑誌
- 中古文学 (ISSN:02874636)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, pp.12-24, 1980-10-25 (Released:2019-03-10)
2 0 0 0 OA 「堀河百首」とその背景 ―周辺の歌学書との関連における―
- 著者
- 鳥井 千佳子
- 出版者
- 中古文学会
- 雑誌
- 中古文学 (ISSN:02874636)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, pp.53-61, 1986-03-15 (Released:2019-03-10)
2 0 0 0 OA 『大鏡』の「語り手」と「聴衆」 ―「記録者」をめぐって―
- 著者
- 稲垣 智花
- 出版者
- 中古文学会
- 雑誌
- 中古文学 (ISSN:02874636)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, pp.35-43, 1990-06-20 (Released:2019-03-10)
2 0 0 0 OA 源氏物語における貴公子の待遇表現 ―〈語り手〉の待遇意識とその立場―
- 著者
- 陣野 英則
- 出版者
- 中古文学会
- 雑誌
- 中古文学 (ISSN:02874636)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, pp.21-29, 1996-11-25 (Released:2019-05-18)
2 0 0 0 OA 主伐方法に対する非専門家の認知・評価傾向
- 著者
- 高山 範理 讃井 知 山浦 悠一
- 出版者
- 一般社団法人 日本森林学会
- 雑誌
- 日本森林学会誌 (ISSN:13498509)
- 巻号頁・発行日
- vol.102, no.3, pp.180-190, 2020-06-01 (Released:2020-09-16)
- 参考文献数
- 59
- 被引用文献数
- 1
主伐の時代を迎えた日本で林業が社会的に受け入れられるためには,伐採地の風景的価値を考慮した上で,生物多様性の保全や林業としての経済的合理性に配慮して,適切な主伐方法を選択する必要がある。そこで本研究では,針葉樹(トドマツ)人工林の皆伐地,群状に植栽木を残した伐採地(群状保持),ha当たり10本,50本,100本の広葉樹を単木的に残した伐採地(単木保持),広葉樹老齢木を残した伐採地,伐採前の人工林の7種類の異なる林分状況からなる写真を刺激として,非専門家が伐採地に懐く風景的価値(認知・評価)を調べ,さらに非専門家と専門家間で生物多様性の保全および林業としての経済的合理性に対する伐採地の評価を比較した。その結果,1) 非専門家は皆伐や老齢木保持をポジティブに認知する一方で,群状保持はネガティブに認知する可能性があること,2) 非専門家は樹木の伐採に抵抗感があるため,主伐の実施にあたってはその必要性や生態系保全への配慮,植林の実施等の情報を供与し理解を求めることが有効であること,3) 林業としての経済的合理性の評価については,非専門家と専門家の間にギャップがあり,非専門家の理解を得るためには情報交換や議論を重ねる必要があることなどが明らかになった。
2 0 0 0 回転超流動ヘリウム3の量子流体(量子渦)の研究
間隔12.5μmの並行平板セルを作成し、その間にある超流動ヘリウム3のNMR信号を観測した。従来、このような間隔のセルの実験においては平行度のよいサンプルを作る事が困難であったが、我々は試料の材質、その加工方法を工夫することで平行度の良い試料容器を作ることに成功した。この結果、超流動ヘリウム3A相においてその秩序変数の方向を均一にそろえることに成功し、その回転変化を精密に測定することに成功した。回転下においてある回転数(〜1rad/s)以上ではNMR信号が変形し、静止下における信号の位置とは異なる周波数位置にNMRの共鳴信号が観測されることが分かった。この信号は並行平板間の秩序変数が回転による常流動速度場と超流動速度場の差により変形したことによるスピン波の信号であると考えられるが、その信号の周波数位置と秩序変数との関係はよくわかっていない。今回の実験では平行度の良いサンプルを用意できたことでこの新しい信号を精密に観測することができたので、数値計算との比較によってその理解が深まると考えている。また、2rad/s以上の回転数においては並行平板間に渦が入り、それが中心で集まっている事がわかった。また、こうしたNMR信号の回転変化は超流動転移温度を通過するときの回転数、磁場の大きさ、およびそれらが平行であるか、反平行であるかによって変化することが分かった。特に、回転(1rad/s以上)と磁場(27mT)の両方をかけた状態で超流動転移温度を通過した後の回転変化においては、常流動速度場による秩序変数の変形が観測できなかった。これは超流動転移温度における条件によって生成される渦が異なりその臨界速度の違いを反映している可能性がある。並行平板という境界条件においては渦量子が通常の1の渦とは別に1/2の渦の存在が予言されており、こうした特異な渦の生成を示唆している可能性がある。
2 0 0 0 OA 新聞報道の誕生
- 著者
- 加藤 裕治
- 出版者
- The Japan Sociological Society
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.2, pp.270-285, 1998-09-30 (Released:2009-10-19)
- 参考文献数
- 22
本稿は明治初期に活躍した二人の新聞記者, 成島柳北と福地源一郎の西南戦争をめぐる報道態度と (新聞) 報道言説に着目し, 「中立的 (ニュートラル) な視点」に基づいて事実を伝達すると想定されている「客観的報道言説」が, 「文学的定型 (物語) に基づく言説」を拒絶する地点で可能になったことを指摘する。その上で, そうした報道言説に含まれているパラドックスの可能性と隠蔽の問題を, タックマンによる「枠組」の概念に基づきながら検討し, こうした「中立的な視点に基づく事実によって出来事を知らせること」を指向しつつ誕生した「客観的報道言説」が, 実際には不可能であることを指摘する。