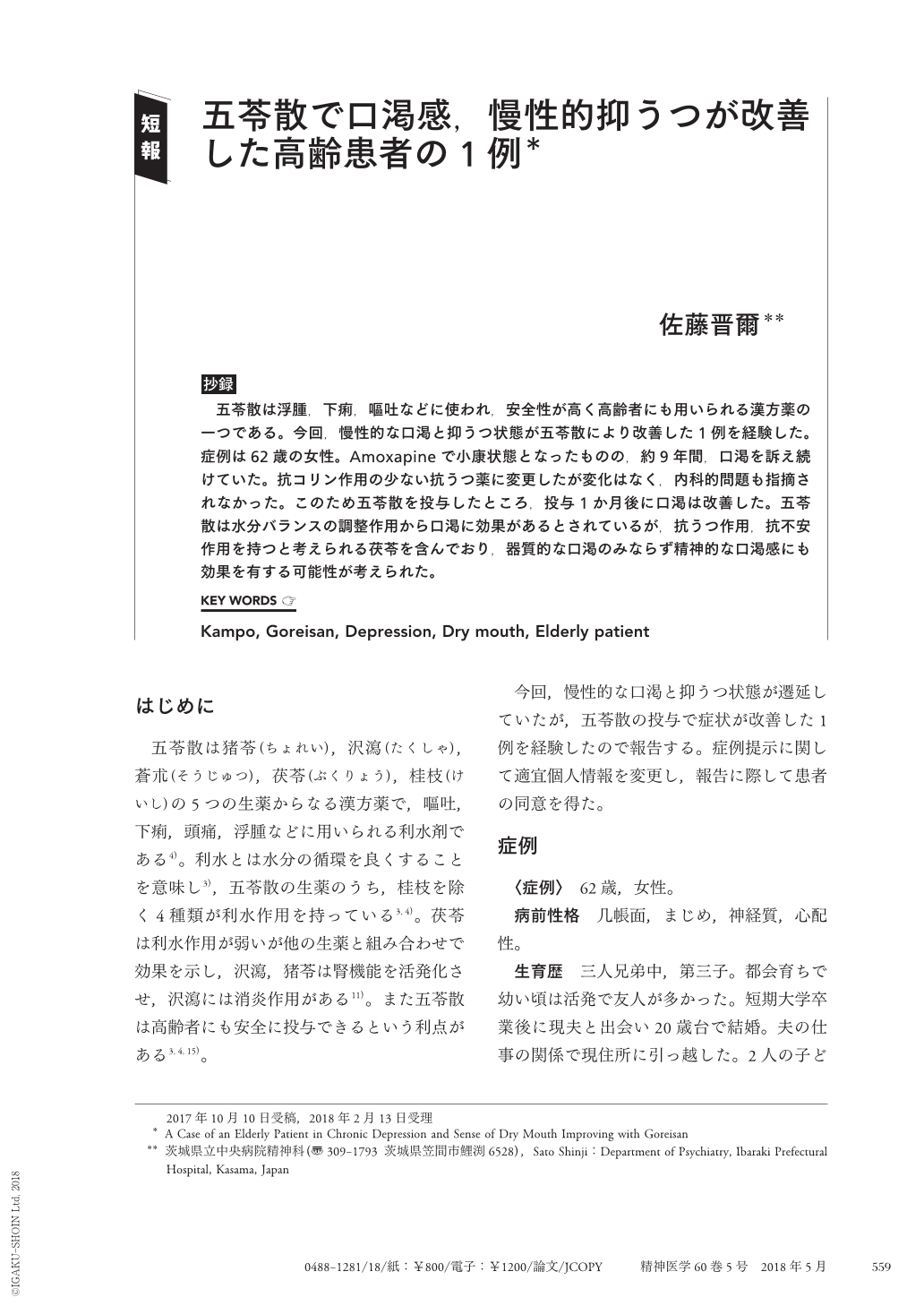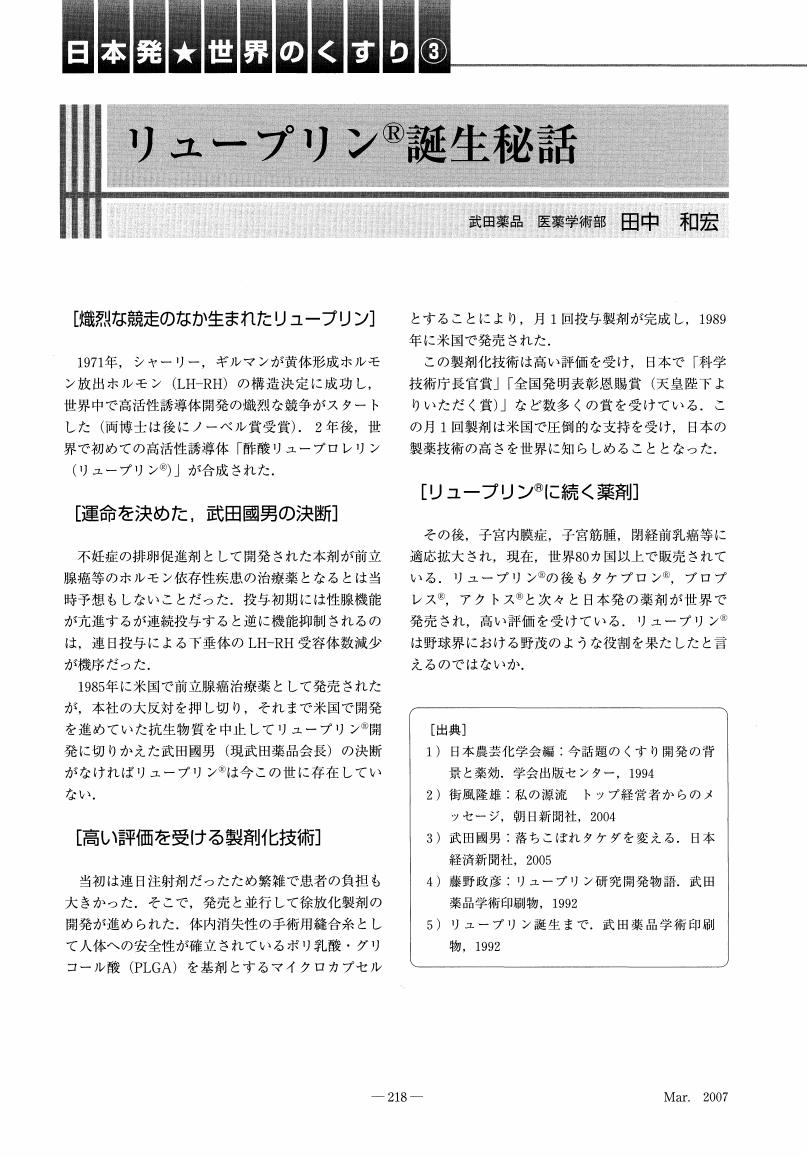2 0 0 0 OA 英国のヒト胚管理制度にみる生命倫理問題の社会的ガバナンスシステム
- 著者
- 牧山 康志
- 出版者
- 科学社会学会
- 雑誌
- 年報 科学・技術・社会 (ISSN:09199942)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, pp.85-108, 2005-06-30 (Released:2022-09-10)
2 0 0 0 OA 【Aufsatz】抽象的な作者をめぐるリュリコロギーと審級理論のあいだの論争について
- 著者
- 小野寺 賢一
- 出版者
- 早稲田ドイツ語学・文学会編集委員会
- 雑誌
- Waseda Blätter (ISSN:13403710)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, pp.25-47, 2023-02-25
2 0 0 0 OA 1923 年関東震災の前展と余震について
- 著者
- 関谷 溥
- 出版者
- Tokyo Geographical Society
- 雑誌
- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, no.3, pp.175-180, 1970-06-25 (Released:2009-11-12)
- 参考文献数
- 7
September 1, 1923, southern Kanto was devastated by a severe earthquake. The main shock of the events, which occurred at 11 h 58 m (JST), was felt all over Japan. The highest seismic intensity is 7 in JMA scale at the southern part of Kanagawa, Tokyo and Chiba prefectures. The epicenter is located on the Sagami-nada. Parameters of the main shock given by the Japan Meteorological Agency are as follows ;origin time : 11 h 58 m, September 1, 1923.epicenter : 35° 20' N, 139° 20' Emagnitude : 7.9The earthquake was accompanied by many fore- and after-shocks. The foreshocks occurred in Kashima-nada. It seems that the foreshock activities began in May 1923 and became vigorous in June 1923 before the occurrence of the main shock.The aftershocks occurred in Kanagawa, Yamanashi, Saitama, Chiba, Ibaraki prefectures and near seas, and the general trend in decrease of daily number of the aftershocks can be explained by Omori's generalized formula.
2 0 0 0 OA 自然および旅行に対する態度が島への訪問意図に与える影響構造分析—八丈島を例に—
- 著者
- 栗栖 聖 齊藤 修 荒巻 俊也 花木 啓祐
- 出版者
- 社団法人 環境科学会
- 雑誌
- 環境科学会誌 (ISSN:09150048)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.5, pp.307-324, 2017-09-30 (Released:2017-09-30)
- 参考文献数
- 31
東京都八丈島を対象に,島への訪問意図を規定する因子の構造をモデル化を通して検討した。特に自然および旅行への態度が,自然環境や地熱発電所といった島の各地域資源への訪問意図を通じて,どのように島への訪問意図に影響を与えているかを明らかにすることを研究目的とした。東京都民を対象にオンラインアンケートを実施し,29,616名のサンプルを得た。八丈島を訪問したいと思うかを尋ねた「八丈島訪問目標意図」では,全体として「やや思う」を少し超えた値となった。同意図は男性の方が女性より有意に高く,50代以上になると年齢とともに有意に意図が上がっていた。同意図へ影響を与える意図としては,自然環境探索意図と温泉訪問意図が高く,また島全般への訪問意図も大きく影響していた。自然への態度としては,「脅威をもたらす存在」「癒しを得る存在」「人により支配される存在」という自然観の3因子が抽出された。また,旅行への態度としては,「健康回復欲求」「文化見聞欲求」「自己拡大欲求」「意外性欲求」の4つの因子が抽出された。これらの因子得点は,性別および年代によって大きく異なっていた。これらの中で,八丈島への訪問意図へ影響を与えるものとしては,自然への態度の中では,「脅威をもたらす存在」および「癒しを得る存在」としての自然観がモデル内に組み込まれたが,その影響は大きくはなかった。一方,旅行に対する態度の中では,「健康回復欲求」と「文化見聞欲求」がモデルに組み込まれ,特に後者が訪問意図に与える影響が大きかった。
2 0 0 0 OA 代謝性・中毒性脳症の脳波
- 著者
- 下竹 昭寛 松本 理器 人見 健文 池田 昭夫
- 出版者
- 一般社団法人 日本臨床神経生理学会
- 雑誌
- 臨床神経生理学 (ISSN:13457101)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.1, pp.40-46, 2019-02-01 (Released:2019-03-08)
- 参考文献数
- 21
意識障害の患者において代謝性脳症は比較的よく遭遇する病態であり, 脳波はその診断と病勢の把握に有用である。代謝性脳症の脳波所見は, 意識障害の程度と関係して, 基礎律動・後頭部優位律動の徐波化や消失, 間欠的律動性または持続性高振幅の全般性デルタ活動, 三相波 (Triphasic wave) を呈する場合もある。三相波は, 陰–陽–陰の三相性からなる特徴的な波形で, 肝性脳症を含む代謝性脳症で認めることが多い。中毒の脳波所見の中に両側同期性の全般性周期性放電 (Generalized Periodic Discharges (GPDs) ) を呈するものがある。薬物関連では, 炭酸リチウム, テオフィリンなどが挙げられ, セフェピム脳症によるものも知られる。三相波/GPDsにおいては, 非けいれん性てんかん重積 (NCSE) の可能性についても常に念頭に置く必要がある。代謝性・中毒性脳症の脳波は原因検索に必ずしも特異的な所見を示すわけではないが, 特徴的な脳波所見を示す場合があり, また非侵襲的に早期から病態の客観的な評価が可能であり, 積極的に活用すべきである。
2 0 0 0 OA 咀嚼筋腱・腱膜過形成症の臨床所見
- 著者
- 有家 巧 覚道 健治
- 出版者
- 一般社団法人 日本顎関節学会
- 雑誌
- 日本顎関節学会雑誌 (ISSN:09153004)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.1, pp.31-34, 2009 (Released:2012-02-15)
- 参考文献数
- 4
- 被引用文献数
- 5
2 0 0 0 OA 香り物質による害虫防除
- 著者
- 大平 辰朗
- 出版者
- 公益社団法人におい・かおり環境協会
- 雑誌
- におい・かおり環境学会誌 (ISSN:13482904)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.1, pp.34-44, 2012-01-25 (Released:2016-04-01)
- 参考文献数
- 63
- 被引用文献数
- 1 1
我々の生活環境に様々な害虫(衛生害虫,貯蔵害虫,農林業害虫等)が存在する.それらは人の衛生面や食物等の品質等の劣化を招き,大きな問題となる.対策としては優れた防除作用を有する合成された化学物質が数多く開発されているが,残留性,安全性等の問題があり,環境に優しい天然物,例えば香り物質を用いる方法が注目されている.植物は一旦,大地に根を張ると身動きがとれない.そのため周辺の微生物,昆虫等による攻撃に対応するための方法として,防除効果や安全性の高い化学物質を生成してきた.ここでは,それらの利用を考慮する為に,植物が作り出した害虫防除機能の高い化学物質に焦点をあて,概説することにする.
2 0 0 0 OA 微高気圧暴露と空気質の調整がヒトの精神気分尺度と自律神経活動に与える影響
- 著者
- 櫻井 博紀 戸田 真弓 戸田 南帆 高橋 吾朗 酒向 慎貴 久野 祐功 渡邉 茂樹 佐藤 純
- 出版者
- 日本生気象学会
- 雑誌
- 日本生気象学会雑誌 (ISSN:03891313)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.1, pp.37-43, 2022-07-30 (Released:2022-09-03)
- 参考文献数
- 21
高気圧環境によるストレス軽減効果を調査するため,被験者(成人男女16名)を微高気圧(大気圧+10 hPa)と空気質(酸素,二酸化炭素濃度)を調整した空間に短期暴露し,精神気分尺度と自律神経系に与える影響について検討した.微高気圧暴露は,「微高気圧」と,空気質も変化させた「微高気圧+酸素付加」,「微高気圧+酸素付加+二酸化炭素抑制」の3条件で行った.測定項目は,不安・抑うつ尺度および気分尺度と,自律神経指標として血圧,心拍数,心拍間隔変動周波数を取得した.微高気圧暴露単独は,気分尺度,抑うつ尺度を改善させ,暴露中に副交感神経活動が賦活された.さらに,空気質を調整することで,微高気圧暴露単独の場合よりもストレス軽減効果および不安・抑うつ尺度の抑制効果が大きかった.これらから,微高気圧に加えて空気質を調整することで,ストレス緩和効果がより強く得られることが明らかになった.
- 著者
- 高木 俊之
- 出版者
- 法政大学大原社会問題研究所
- 雑誌
- 大原社会問題研究所雑誌 (ISSN:09129421)
- 巻号頁・発行日
- no.544, pp.19-37, 2004-03
2 0 0 0 讃美歌略解
- 著者
- 日本基督教団讃美歌委員会編
- 出版者
- 日本基督教団出版局
- 巻号頁・発行日
- 1990
2 0 0 0 ともにうたおう : 新しいさんびか50曲
- 著者
- 日本基督教団讃美歌委員会編
- 出版者
- 日本基督教団出版局
- 巻号頁・発行日
- 1976
2 0 0 0 OA 限定核戦争は可能-限定戦争論 宇宙兵器と国際政治
- 著者
- 佐伯 喜一
- 出版者
- 一般財団法人 日本国際政治学会
- 雑誌
- 国際政治 (ISSN:04542215)
- 巻号頁・発行日
- vol.1958, no.5, pp.40-59, 1958-06-15 (Released:2010-09-01)
- 参考文献数
- 18
2 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1929年07月10日, 1929-07-10
2 0 0 0 OA 本邦におけるメロディックイントネーションセラピーの現況─MIT 全国実態調査─
- 著者
- 佐藤 正之 田部井 賢一 織田 敦子 辰巳 寛 関 啓子
- 出版者
- 一般社団法人 日本高次脳機能障害学会
- 雑誌
- 高次脳機能研究 (旧 失語症研究) (ISSN:13484818)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.1, pp.33-38, 2023-03-31 (Released:2023-04-24)
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 1
メロディックイントネーションセラピー (MIT) は, 1970 年代に米国で開発された失語訓練法である。今回われわれは, 本邦における MIT の現況についてアンケート調査を行った。対象は, 2021 年 3 月末時点で日本言語聴覚士協会のホームページに掲載されていた 3,136 施設。同年 5 月 1 日付けで, 返信用封筒を同封した質問紙を郵送, 各施設の代表の言語聴覚士 (ST) に記入を依頼した。回収期限は同年 6 月末とした。有効発行総数 3,127 件のうち, 1,186 件が回収できた (回収率 37.9%) 。回答者の 81% (955 名) が MIT という用語を聞いたことがあり, そのなかの 85% (800 名) が MIT は運動性失語の発話障害に有効であることを知っていた。しかし, 臨床現場で実際に MIT を行っているのは 9% (90 件) で, MIT 日本語版 (MIT-J) を用いているのは 35% (29 件) であった。MIT-J の正しい手法を学ぶための講習会へのニーズがあると思われた。
2 0 0 0 五苓散で口渇感,慢性的抑うつが改善した高齢患者の1例
抄録 五苓散は浮腫,下痢,嘔吐などに使われ,安全性が高く高齢者にも用いられる漢方薬の一つである。今回,慢性的な口渇と抑うつ状態が五苓散により改善した1例を経験した。症例は62歳の女性。Amoxapineで小康状態となったものの,約9年間,口渇を訴え続けていた。抗コリン作用の少ない抗うつ薬に変更したが変化はなく,内科的問題も指摘されなかった。このため五苓散を投与したところ,投与1か月後に口渇は改善した。五苓散は水分バランスの調整作用から口渇に効果があるとされているが,抗うつ作用,抗不安作用を持つと考えられる茯苓を含んでおり,器質的な口渇のみならず精神的な口渇感にも効果を有する可能性が考えられた。
- 著者
- Tien Quang NGUYEN Yusuke NANBA Michihisa KOYAMA
- 出版者
- Society of Computer Chemistry, Japan
- 雑誌
- Journal of Computer Chemistry, Japan (ISSN:13471767)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.4, pp.111-117, 2022 (Released:2023-05-16)
- 参考文献数
- 24
- 被引用文献数
- 1
Thermodynamic properties and atomic configuration of PdRu alloy were investigated using Wang-Landau Monte Carlo method in combination with a newly-developed universal neural network potential. By using this new potential, excess energy of PdRu alloy was calculated. It is found that PdRu alloy in FCC lattice is unstable in the full range of alloy composition. This agrees with previous study based on density functional theory. The combined method was able to determine the configurational density of states, from which thermodynamic properties of the alloy were derived. It is found that when temperature increases, the excess free energy of the alloy is reduced, increasing the possibility of alloy mixing. Depending on the composition, transition peaks appear at finite temperatures where there are changes of preferable atomic arrangement due to the effect of temperature via the configurational entropy. In addition, the analyses on short-range order parameter and bond fraction show that PdRu alloy prefers to be in segregated form, where Pd and Ru are immiscible at low temperature, consistent with the experimental observations. The random mixing of Pd and Ru atoms in the form of solid-solution can occur at high temperature.
2 0 0 0 OA リュープリン®誕生秘話
- 著者
- 田中 和宏
- 出版者
- 一般社団法人 国立医療学会
- 雑誌
- 医療 (ISSN:00211699)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.3, pp.218, 2007-03-20 (Released:2011-10-07)
2 0 0 0 OA 地域高齢者の外出に対する自己効力感尺度の開発
- 著者
- 山崎 幸子 藺牟田 洋美 橋本 美芽 野村 忍 安村 誠司
- 出版者
- 日本公衆衛生学会
- 雑誌
- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.6, pp.439-447, 2010 (Released:2014-06-12)
- 参考文献数
- 28
- 被引用文献数
- 7
目的 近年,地域で介護予防を進めていくための強化分野の 1 つとして,「閉じこもり予防•支援」が展開されており,その効果を評価する心理的側面を含めた指標が求められている。行動変容の視点によれば,閉じこもりの改善には,外出に特化した自己効力感が潜在的に影響していると想定されるが,評価尺度は未だ存在しない。そこで本研究では,地域高齢者の外出に対する自己効力感を測定する尺度(self-efficacy scale on going out among community-dwelling elderly:以下,SEGE と略す)を開発し,その信頼性と妥当性を検証することを目的とした。方法 都内 A 区在住の地域高齢者18人から項目収集を行い,得られた項目をもとに,某県 O 市の地域高齢者258人に対する予備調査によって,13項目から成る尺度原案を作成した。本調査は,都内 A 区在住の地域高齢者8,000人を無作為抽出し,郵送法による調査を実施した。調査内容は,尺度原案,年齢,性別などの基本属性および妥当性を検討するための評価尺度であった。結果 分析対象者は2,627人(男性1,145人,女性1,482人),平均年齢73.8±6.6歳であった。週 1 回以上,外出していたのは全体の86.1%であった。予備調査で作成した尺度原案について主成分分析を行った結果,1 因子構造が確認された。ステップワイズ因子分析による項目精選を行った結果,6 項目から成る尺度が開発された。これら 6 項目の内的整合性は,α=.96であり,高い信頼性が確認された。外出頻度が低いほど,SEGE 得点も低かった。SEGE と,動作に対する自己効力感,健康度自己評価および健康関連 QOL は有意な相関関係にあり,基準関連妥当性および構成概念妥当性が確認された。さらに,高い相関関係にあった SEGE と動作に対する自己効力感における確証的因子分析を行ったところ,両尺度は相関が高いものの,別々の概念を測定していることを確認した。結論 本研究の結果,高い信頼性および妥当性が確認された 6 項目 1 因子から成る SEGE が開発された。本尺度により,「閉じこもり予防•支援」の心理的側面を測定する新たな効果指標を提案できたと考える。今後,地域で広く活用していくことが求められる。
2 0 0 0 OA シスプラチン使用後に塩類喪失性腎症による著しい低ナトリウム血症を来した中咽頭癌症例
- 著者
- 藤川 太郎 白倉 聡 畑中 章生 岡野 渉 得丸 貴夫 山田 雅人 齊藤 吉弘 別府 武
- 出版者
- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会
- 雑誌
- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)
- 巻号頁・発行日
- vol.118, no.8, pp.1046-1052, 2015-08-20 (Released:2015-09-04)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 1 1
癌治療において低ナトリウム血症はしばしば遭遇する電解質異常である. 今回われわれは, 中咽頭癌進行症例に対してシスプラチン (CDDP) 同時併用放射線治療を行い, 計3回の grade 4 の低ナトリウム血症を経験したので報告する. 初回および2回目の低ナトリウム血症は CDDP 投与後に出現し, 脱水と多尿を伴い, 輸液と塩分の補充により1週間程度で改善した. ナトリウムの排泄過剰の所見から塩類喪失性腎症が原因であると考えられた. 3回目の低ナトリウム血症の原因であった抗利尿ホルモン不適合分泌との比較から, 細胞外液量とナトリウムバランスの評価が低ナトリウム血症の鑑別と適切な治療において極めて重要であると考えられた.
2 0 0 0 OA フェア
- 著者
- 高井 和彦
- 出版者
- 公益社団法人 有機合成化学協会
- 雑誌
- 有機合成化学協会誌 (ISSN:00379980)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.4, pp.323, 2012-04-01 (Released:2012-04-24)