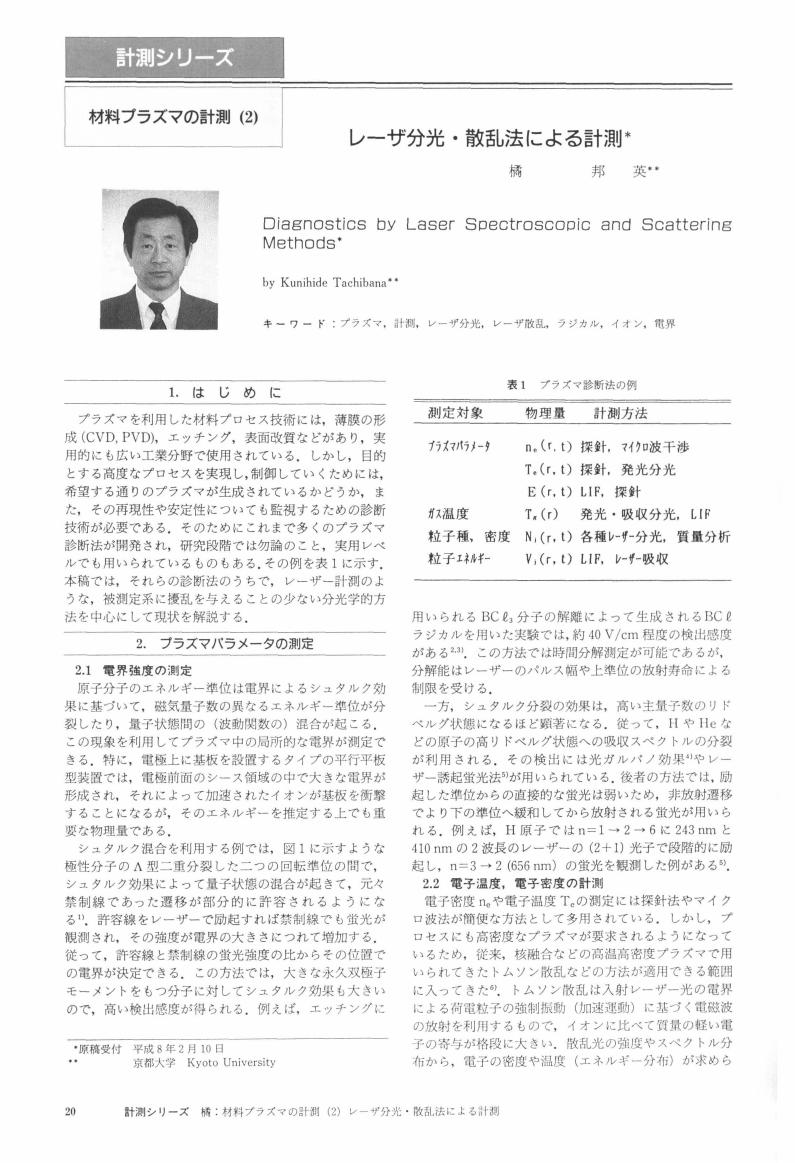2 0 0 0 OA 亜鉛動態におけるメタロチオネインの役割
- 著者
- 神戸 大朋
- 出版者
- 日本毒性学会
- 雑誌
- 日本毒性学会学術年会 第42回日本毒性学会学術年会
- 巻号頁・発行日
- pp.W2-2, 2015 (Released:2015-08-03)
メタロチオネイン(MT)は細胞質に局在し、有害金属毒性の軽減などに働く防御タンパク質として知られるが、亜鉛ホメオスタシス維持にも重要な役割を果たす。近年、このメタロチオネインの働きが、亜鉛トランスポーターの働きと密接に連携していることが明らかにされてきたが、最近、我々は両者の細胞質内亜鉛代謝における協調的な機能が、分泌型亜鉛要求性酵素の活性化に不可欠であることを見出した。 分泌型亜鉛要求性酵素の一つである組織非特異的アルカリフォスファターゼ(TNAP)は、小胞体やゴルジ体といった分泌経路に局在する亜鉛トランスポーター(ZnT5-ZnT6ヘテロ二量体とZnT7ホモ二量体)によって膜輸送された亜鉛を受け取り、活性化される。この過程において、それぞれの二量体は、細胞質内で受け渡された亜鉛を分泌経路内腔に送り込むが、その分子レベルでの知見は、これまで全く得られていなかった。我々は、MT欠損株において、細胞質亜鉛が上昇しているにも関わらず、TNAPの活性化が有意に減少していることを見出した。さらに、MTと同時に細胞質亜鉛の恒常性維持に重要なZnT1やZnT4といった亜鉛トランスポーターを欠損させる(3重欠損株)と、TNAP活性はほとんど検出されなくなった。この3重欠損株では、細胞質内亜鉛が野生株に比べて大きく上昇しているにも関わらず、TNAPを活性化できなかったが、過剰の亜鉛を添加することによって細胞質亜鉛濃度を著しく上昇させると、TNAP 活性は上昇した。また、3重欠損株におけるZnT5-ZnT6ヘテロ二量体とZnT7ホモ二量体の機能は正常であった。これらの結果は、MTを中心とした細胞質内亜鉛動態制御が、ZnT5-ZnT6やZnT7二量体を介したTNAPの活性化に機能することを示しており、MTによる細胞質の亜鉛代謝の厳密な制御が、分泌経路の亜鉛代謝にも重要な役割を果たすことを示している。
2 0 0 0 OA 主観的健康感と居住地周辺の環境認知量との関連 1都3県でのwebアンケート調査を通じて
- 著者
- 髙嶺 翔太 後藤 春彦 林 書嫻 山川 志典
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)
- 巻号頁・発行日
- vol.88, no.807, pp.1690-1701, 2023-05-01 (Released:2023-05-01)
- 参考文献数
- 39
- 被引用文献数
- 1
This paper aims to clarify the association between subjective well-being and quantity of environmental cognition of neighborhood. Online questionnaire for about 2,600 residents in Tokyo, Kanagawa, Saitama, and Chiba prefecture has been conducted. The results of the analysis show the following:1) According to multi regression analysis, quantity of environmental cognition, academic record and household income were independently associated with subjective well-being. People recognizing more places, higher academic record and more household income tend to be better subjective well-being.2) Psychological distress, loneliness, sense of coherence was also associated with quantity of environmental cognition of neighborhood.
2 0 0 0 OA アイヌの衣服に見る藍染め : その役割と象徴性
- 著者
- 深田 雅子
- 出版者
- 文化学園大学
- 雑誌
- 文化学園大学紀要. 服装学・造形学研究 (ISSN:21873372)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, pp.75-80, 2015-01-31
現存するアイヌの衣服の多くには、アツシなどの植物衣や木綿衣の襟ぐり、袖口、裾周りに藍染めの木綿布が使われている。それらは内地で染めたもので、貴重だったと言われている。本研究では、アイヌの衣服に使用された藍染めの木綿布に着目し、なぜ藍染めが多用されたのか、その染色方法と役割、象徴性について明らかにすることを目的とする。研究方法は文献調査と、北海道白老町、登別市、沙流郡二風谷において聞き取り調査を行った。これらの調査から、江戸時代、アイヌは和人との交易や労働の報酬として藍染めの木綿布を手に入るようになり、樹皮衣アツシの補強や、着物に刺繍を施すための土台として切伏せ(アップリケ)のように使用し、その刺繍には魔除けや家族の健康を願う様々な思いが込められていることがわかった。また、藍色そのものも除魔力を持つと考えられており、裾や袖口などの縁に細く切った藍染めの木綿布を縫い付け、悪い神が入らないようにした。布を染めた藍については、内地で染められたという考えのほかに、エゾタイセイ(蝦夷大青)で染めた可能性と、藍以外の草木で彼ら自身が染めた可能性があることがわかった。
2 0 0 0 OA 109 弦のインハーモニシティに関する研究
- 著者
- 中井 幹雄 川口 和也
- 出版者
- 一般社団法人 日本機械学会
- 雑誌
- Dynamics & Design Conference 2006 (ISSN:24242993)
- 巻号頁・発行日
- pp._109-1_-_109-6_, 2006-08-06 (Released:2017-06-19)
- 被引用文献数
- 1 1
ピアノ弦のような曲げ剛性をもつ弦の振動における倍音周波数より高い周波数の系列であるInharmonicityの第1系列と異なる第2の系列について述べる. Inharmonicityの第1系列における第n次の周波数計算では, f_n=nf_0√<1+Bn^2>が一般的に用いられている.ここで, f_0は弦の曲げ剛性を考慮しない場合の固有振動数である.また, Bは非調和度と呼ばれる無次元量である.第1系列と異なる第2の系列では,その非調和度は第1系列の1/4の値となることが経験的にわかっている.打弦および撥弦時のInharmonicityの第2系列の発生機構について実験を行った.周波数スペクトルから各次数のピーク周波数を読み取り,その次数の倍音周波数との差を固有振動数で除し,無次元化した値を各次数について計算する.それらの結果とともに第1系列の周波数値を用いて,和および差の周波数を表す格子線を図A1に示す.実線,点線は第1,2系列を示す.図において,微小なピークはほぼ格子点に一致し,第1系列周波数の和および差の周波数をもつことが明らかとなった.また,この格子線は包絡線をもっており,包絡線周辺は格子点の間隔が狭くなり,数多くのピークが集中することが明らかとなった.この包絡線が,理論的に正確に第1系列の非調和度の1/4の値をもつ曲線となっていることがわかり,第2系列を含むすべての微小なピークの周波数特性が明らかとなった.これらの微小なピークは,弦が大変形するという幾何学的非線形性が原因となって発生すると考えられるので,弦の横振動および縦振動を考慮した次式のような非線形方程式を用いて第2系列について検討した. ρA(∂^2u)/(∂t^2)=EA(∂^2u)/(∂x^2)-(T_0-EA)(∂^2w)/(∂x^2)(∂w)/(∂x) (A1) ρA(∂^2w)/(∂t^2)=T_0(∂^2w)/(∂x^2)-EI(∂^42)/(∂x^4)-C_D(∂w)/(∂t)-(T_0-EA){(∂^2w)/(∂x^2) (∂u)/(∂x)+(∂w)/(∂x) (∂^2u)/(∂x^2)+3/2((∂w)/(∂x))^2(∂^2w)/(∂x^2)} (A2) 図A2(a), (b)は数値計算した横振動と縦振動の変位の周波数分析結果を示す.この図で黒丸が第1系列,白丸が第2系列を示している.この図から,8次モードから第2系列が生じ始めることおよび縦振動のピークと第2系列がほぼ一致していることがわかる.このことは式(A1)におけるwの2次の非線形項が横振動の2つの周波数の和あるいは差をもつ外力として縦振動に作用するとみなすことができることからわかる.さらに,横振動の周波数分析結果に和および差の周波数をもつピークが主に現れることがわかった.しかし,横振動には主に任意の2つの第1系列周波数の和・差の組み合わせ周波数からなる第2系列を含む微小なピークのほかのピークも含まれている.したがって,さらに,横振動については,方程式を検討する必要がある.
2 0 0 0 OA 鵜飼哲+高橋哲哉 編『「ショアー」の衝撃』
- 著者
- 宇野 淳子 Junko Uno
- 出版者
- 学習院大学大学院人文科学研究科アーカイブズ学専攻
- 雑誌
- GCAS report : 学習院大学大学院人文科学研究科アーカイブズ学専攻研究年報 = Graduate Course in Archival Science report (ISSN:21868778)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.68-72, 2012-02
書評
2 0 0 0 OA スポーツの試合中における感情調節方略尺度の作成
- 著者
- 相羽 枝莉子 松田 晃二郎 児玉 亜由実 杉山 佳生
- 出版者
- 日本スポーツ心理学会
- 雑誌
- スポーツ心理学研究 (ISSN:03887014)
- 巻号頁・発行日
- pp.2021-2106, (Released:2022-02-25)
- 参考文献数
- 34
The purpose of this study was to develop the Emotion Regulation Strategies scales in Sports competition (ERSS), and to investigate the patterns of tendency to use emotion regulation strategies during games with the competition results. In Study 1, a total of 513 athletes were investigated using a preliminary scale, and through exploratory factor analysis, six factors (positive refocusing, self-blame, conversion of viewpoint, emotional suppression, problem-solving, and rumination) were extracted, and the ERSS was developed. In Study 2, a total of 327 athletes, who different from the subjects in Study 1, completed the ERSS to confirm its validity, together with its related scales. All the subscales correlated with their relevant subscales in the expected directions, and the test–retest reliability was .41–.71 (p < .01). In addition, we analyzed ERSS subscale scores with cluster analysis, and the participants were classified into four clusters. The first cluster consisted of athletes who were more likely to use all the emotion regulation strategies; the second cluster consisted of athletes who were less likely to use all the strategies; the third cluster consisted of athletes who were more likely to use positive refocusing; and the fourth cluster consisted of athletes who were more likely to use problem-solving and emotional suppression. We conducted a chi-square test to investigate the association between the clusters and the level of competition. While we found no significant differences in any of them, we did identify a marginally significant difference in the first cluster.
2 0 0 0 OA 引き込み現象に基づく講義関心度評価手法
- 著者
- 勝問田 剛 長岡 千賀 小森 政嗣
- 出版者
- ヒューマンインタフェース学会
- 雑誌
- ヒューマンインタフェース学会論文誌 (ISSN:13447262)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.3, pp.275-282, 2011-08-25 (Released:2019-09-04)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 2
In face-to-face communication, it is often observed that the body movements of a listener change almost simultaneously with changes in voice patterns of the speaker. This is referred to as 'entrainment'. The present study examined the relationship between the degree of teacher-student entrainment and students' interest in the lecture. Four university professors gave 60-minute lectures. The body movements of the students were recorded using a video camera located in the front of the lecture room and the voices of the professors were recorded using a microphone. After each lecture, the students were asked to rate their interest in the topic of the lecture. We used a computer-based video analysis to measure the intensity of students' body movements, and examined the temporal relationship between body movements and the intensity of the teacher's voice, by a moving correlation analysis. These coefficients can be regarded as the entrainment levels. In all lectures, there were positive and significant relationships between the level of entrainment and students' interest. These results indicate that temporal changes in the level of entrainment can be used as an indicator of temporal changes in the interest level of students.
- 著者
- 久保 陽一
- 出版者
- 東北哲学会
- 雑誌
- 東北哲学会年報 (ISSN:09139354)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, pp.73-79, 2008-04-25 (Released:2018-02-28)
2 0 0 0 OA Webページからの化学情報抽出による新しい電子状態データベースの開発
- 著者
- 山之内 昭博 杉本 学
- 出版者
- 公益社団法人 日本化学会・情報化学部会
- 雑誌
- ケモインフォマティクス討論会予稿集 第38回ケモインフォマティクス討論会 東京
- 巻号頁・発行日
- pp.92-93, 2015 (Released:2015-10-01)
- 参考文献数
- 6
化合物に関する知識情報をWebページから取得して、我々が開発している電子状態データベースに登録することを目的として、Webページのクローリングとスクレイピングのためのソフトウエアを開発した。
2 0 0 0 OA メタゲノム解析
- 著者
- 楠本 憲一
- 出版者
- 公益社団法人 日本食品科学工学会
- 雑誌
- 日本食品科学工学会誌 (ISSN:1341027X)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.3, pp.136, 2011-03-15 (Released:2011-04-21)
- 参考文献数
- 4
- 被引用文献数
- 1
メタゲノムとは,ある生物の遺伝子全体を意味する「ゲノム(genome)」に,さらに「超越」を意味するメタ(meta-)を融合した造語であり,微生物群集のゲノムを培養に依存することなく網羅的に解析することをメタゲノム解析と呼ぶ.この解析技術の特徴は,試料中の微生物のDNAを混合物として抽出し,このDNA集合体の塩基配列を解読することである.試料中に含まれる微生物(培養法の不明なものを含む)の種類やその存在比率を推定することを目的として実施される.また,これまで知見のない新たな酵素遺伝子の候補を見出すことが可能である.塩基配列を自動的に解読するDNAシークエンサーの開発から20年以上を経て,解読能力が大幅に向上した次世代高速シークエンサーが開発され,ゲノム解析は新たな局面を迎えた.その超高速解読能力を利用し,膨大な遺伝子配列情報が蓄積されつつある.メタゲノム解析は,現在,次世代シークエンサーを利用して行われている.2000年,E. DeLongを中心とする研究グループが,試料中に存在する数十キロ塩基対の長鎖DNAをバクテリア人工染色体ベクターに連結し,これを網羅的に配列解析することで海水中の菌叢解析を実施した1).彼らの研究が実質的なメタゲノム解析の端緒であった.次いで,2004年,J. Venterらはサルガッソ海の海洋細菌群集のメタゲノム解析を行い,合計で1兆塩基対の非重複塩基配列を取得し,それらの解析結果から,少なくとも1800種の細菌種の存在と,148種の未知細菌種の存在を推定した.また,12億種類の未知遺伝子を同定し,Science誌に発表した2).彼らの研究成果から,彼らのようなアプローチが環境中の微生物群集の解析や,新規有用遺伝子の発見につながることが広く認識されるようになった.その後,上述した次世代高速シークエンサーの開発に伴い,239件(平成22年8月現在)のメタゲノムデータが蓄積されている.現在までに公開されたメタゲノムデータは,Genomes Online Database (http : //www.genomesonline.org/cgi-bin/GOLD/bin/gold.cgi)で公表されている.主として海水,ヒト腸内,土壌,淡水,温泉環境中の微生物群集が解析されている.このメタゲノム解析は,次世代シークエンサーと共にバイオインフォマティクスの進展が必須であった.バイオインフォマティクスとは,生物学に関わる情報解析学の総称である.通常のゲノム解析は,1種類の生物の網羅的遺伝子解析であり,得られる遺伝子情報は全てその生物に由来した情報である.一方,メタゲノム解析では,複数の生物種の混合した配列情報が得られる.また,存在比の低い種の情報が得られにくい等,試料に含まれる全ての生物種のDNA情報が取得できるとは言えない.そこで,これまでのゲノム解析と異なる概念が必要となる.ゲノム解析の流れとしては,断片化した個々のDNAの配列からなる生データ取得,これらの中から末端配列が共通している配列同士を順次連結していくアセンブリー,その配列の中から遺伝子をコードする領域を見つけ出す遺伝子予測となる.メタゲノム解析では,遺伝子予測をアセンブリーの前に行う場合と後に行う場合があり,研究目的により使い分けられている.また,メタゲノム解析に特化した遺伝子予測プログラムが開発されている.また,予測した遺伝子が由来する生物種を推定する手法も総説で解説される等,一般化されてきている.注意すべきは,次世代シークエンサーもメーカーと機種によりその塩基配列解読原理が異なり,解読鎖長や精度等が異なるため,目的に応じた機種を選択する必要がある.メタゲノム解析のデータは,次世代シークエンサーの機能改良に伴い,今後急速に増加すると期待される.今後の応用分野としては,エネルギー分野や環境浄化で力を発揮する新規遺伝子資源の開拓3),栄養学・医学分野からのヒトの腸内細菌叢解明4),難培養微生物を含む環境微生物群集の生態解明等であり,基礎研究成果としてメタゲノム解析に関する学術論文数が多数蓄積している.メタゲノムデータの蓄積と,バイオインフォマティクスの発展,他分野との研究連携によるメタゲノム解析技術の発展が,人類の健康や環境,エネルギー問題等,我々社会の課題解決につながることが期待される.
2 0 0 0 OA 近代日本における煩悶青年の系譜 : 相馬御風の『還元録』をめぐって
- 著者
- 加藤 潤
- 出版者
- 名古屋女子大学
- 雑誌
- 名古屋女子大学紀要. 人文・社会編 (ISSN:09152261)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, pp.73-85, 1991-03-05
2 0 0 0 OA 金管楽器吹奏系の音響特性設計に関する研究
2 0 0 0 OA リーザ分光・散乱法による計測
- 著者
- 橘 邦英
- 出版者
- 一般社団法人 溶接学会
- 雑誌
- 溶接学会誌 (ISSN:00214787)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.3, pp.204-209, 1996-04-05 (Released:2011-08-05)
- 参考文献数
- 30
2 0 0 0 OA レーザーによるプラズマ計測
- 著者
- 村岡 克紀 内野 喜一郎 山形 幸彦
- 出版者
- 公益社団法人 応用物理学会
- 雑誌
- 応用物理 (ISSN:03698009)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.2, pp.220, 2004-02-10 (Released:2019-09-27)
- 参考文献数
- 8
パルスレーザーのもつ高いパワーと時間的・空間的な高いコヒーレンスとを組み合わせて,ほかの手法では得られない独特のプラズマ計測法が発展させられてきた.本稿では,その最も代表的な手法であるレーザートムソン散乱法とレーザー蛍光法について,最近の動きを中心に報告する.
2 0 0 0 OA 英米文学鳥類考:鶏について
- 著者
- 桝田 隆宏 Takahiro Masuda
- 雑誌
- 松山大学論集 = Matsuyama University review (ISSN:09163298)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.6, pp.221-270, 2009-02-01
2 0 0 0 感性語を入力とする舞台照明コントローラ
- 著者
- 片岡 真史 岩井 大輔 佐藤 宏介
- 出版者
- 一般社団法人 電気学会
- 雑誌
- 電気学会論文誌C(電子・情報・システム部門誌) (ISSN:03854221)
- 巻号頁・発行日
- vol.132, no.12, pp.1999-2006, 2012-12-01 (Released:2012-12-01)
- 参考文献数
- 9
This paper proposes a novel stage lighting controller in which users can change stage lighting effects by selecting impressions through Kansei words. First, the paper describes a mathematical model that calculates output brightness value of each stage light by emotions to be perceived by audiences and by light information that includes position/orientation, color, and shape of each stage light. Second, a subjective evaluation of stage lightings was carried out in which the subjects observed computer graphics of various stage lightings on a projector screen and answered perceived emotions. Third, a stage lighting system is proposed and implemented, which automatically calculates the output brightness value of each stage light. A user of the system only has to input desired emotions and the light information of each stage light. To evaluate the proposed system, a user study was carried out in which the subjects observed stage lightings generated by the system in a real stage set. The subjects gave positive feedbacks on the usefulness of the system.
2 0 0 0 OA ステロイドによる骨格筋萎縮のメカニズム
- 著者
- 江里 俊樹 田中 廣壽
- 出版者
- 一般社団法人 日本臨床リウマチ学会
- 雑誌
- 臨床リウマチ (ISSN:09148760)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.2, pp.171-174, 2016-06-30 (Released:2016-08-30)
- 参考文献数
- 17
2 0 0 0 OA シイタケの香気成分, レンチオニンに関する研究 (第2報) レンチオニンの食品への利用
- 著者
- 和田 正三 中谷 弘実 戸田 準 芳谷 道男
- 出版者
- 公益社団法人 日本栄養・食糧学会
- 雑誌
- 栄養と食糧 (ISSN:18838863)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.5, pp.360-362, 1968-01-30 (Released:2010-02-22)
- 参考文献数
- 4
- 被引用文献数
- 1 2
シイタケの香気成分, レンチオニンについて, その匂いの性質, 閾値, 食品への利用を検討し次の結果を得た。1) レンチオニンの匂いからシイタケを連想することができる。2) レンチオニンの閾値は水溶液中で, 0.25~0.53ppm, 植物油中で12.5~25ppmである。3) 実際の食品へは1~20ppmの添加で, 食品ヘシイタケフレーバーを付与することができる。