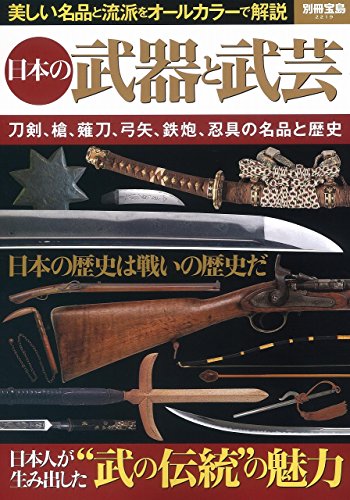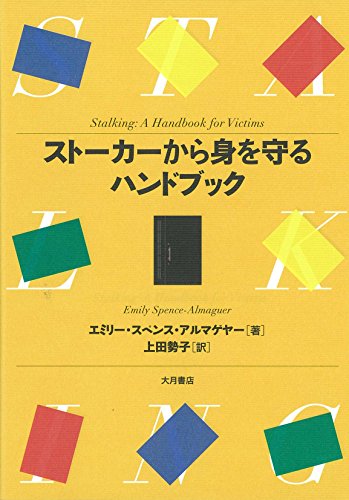- 著者
- 後藤 有里
- 出版者
- 関西大学大学院法学研究科院生協議会
- 雑誌
- 法学ジャーナル (ISSN:02868350)
- 巻号頁・発行日
- vol.2020, no.98, pp.95-131, 2020 (Released:2022-10-19)
2 0 0 0 OA 台湾における名前の日本化 -日本統治下の「改姓名」と「内地式命名」-
- 著者
- 植野 弘子
- 出版者
- アジア文化研究所
- 雑誌
- アジア文化研究所研究年報 = Annual Journal of the Asian Cultures Research Institute (ISSN:18801714)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, pp.97(66)-108(55), 2007
2 0 0 0 OA 医療機関のGoogleレビューにおける評点とクチコミ評価項目の分析:観察研究
- 著者
- 竹久 和志 本田 真也 日比 隆太郎 杉丸 毅 樋口 智也 松井 智子 井上 真智子 大磯 義一郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本プライマリ・ケア連合学会
- 雑誌
- 日本プライマリ・ケア連合学会誌 (ISSN:21852928)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.1, pp.2-11, 2023-03-20 (Released:2023-03-24)
- 参考文献数
- 30
目的:患者は医療機関選択の際にインターネット上の情報を参考にしている.本研究ではGoogleレビュー上の医療機関に対する評価内容を分析した.方法:静岡県の医療機関のGoogleレビューの評点とクチコミを用いた.クチコミはあらかじめ設定した12の評価項目でコード化した上で,ポジティブ,ネガティブ,分類不能,記述なしに分類し,修正ポアソン回帰分析で評点との関連を分析した.結果:対象の医療機関は2,044施設,クチコミ数は13,769件であった.「医師の応対」に触れたクチコミが最も多く(5,035件),ポジティブなクチコミは高評価(偏回帰係数:0.76,95%信頼区間:0.70~0.82)と,ネガティブなクチコミは低評価(-4.65,-5.24~-4.06)と有意な関連があった.結論:Googleレビューにおいては,医師の応対に関するクチコミが評点に影響を与えていた.
- 著者
- 掛水 通子
- 出版者
- 日本スポーツとジェンダー学会
- 雑誌
- スポーツとジェンダー研究 (ISSN:13482157)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, pp.30-39, 2006 (Released:2020-09-30)
- 参考文献数
- 27
2 0 0 0 OA 脳脊髄液検査法
- 著者
- 真下 忠久
- 出版者
- 動物臨床医学会
- 雑誌
- 動物臨床医学 (ISSN:13446991)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.1, pp.17-20, 2009-03-20 (Released:2010-03-16)
- 参考文献数
- 7
2 0 0 0 OA ぐらむ陽性雙球菌ニ就テノ研究 (第3回報告) 毒性竝ニ病原性ニ關スル研究
- 著者
- 石井 四郎
- 出版者
- 日本細菌学会
- 雑誌
- 日本微生物學會雜誌 (ISSN:18836941)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.4, pp.1006-1037, 1927-03-15 (Released:2009-09-03)
- 参考文献数
- 48
2 0 0 0 OA ぐらむ陽性雙球菌ニ就テノ研究 (第1回報告) 細菌學的竝ニ生物學的研究
- 著者
- 石井 四郎
- 出版者
- 日本細菌学会
- 雑誌
- 日本微生物學會雜誌 (ISSN:18836941)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.4, pp.943-986, 1927-03-15 (Released:2009-09-03)
- 著者
- 堀 信行
- 出版者
- 地理科学学会
- 雑誌
- 地理科学 (ISSN:02864886)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.2, pp.143, 2010-04-28 (Released:2017-04-14)
- 著者
- 樋口 麻里
- 出版者
- 北海道大学
- 雑誌
- 北海道大学文学研究院紀要 (ISSN:24349771)
- 巻号頁・発行日
- vol.167, pp.31-74, 2022-07-19
身体的または精神的な脆弱性が相対的に大きく労働が困難な人々は,いかにして「社会に必要な成員」として承認されるのか。本稿は,これらの人々に対するケアの保証を主張するエヴァ・F・キテイのケアの倫理を足掛かりに,精神障がいのある人(以下,精神障がい者とする)にケアを提供する専門職スタッフの経験的データの分析から,この問いへの回答を試みる。ケアの倫理は,身体的または精神的な脆弱性を依存の発生源とみなし,脆弱性に留まる人には他者に「お返し」をする能力がないと捉える。そのため,労働が困難なほどの脆弱性をもつ依存者は,ケアの一方的な受け手と位置づけられる。他方,依存者からの「お返し」に焦点を当てた,実証的研究は十分に行われていない。そこで本稿では,労働が困難で様々な社会関係を喪失している精神障がい者へのケアを行う,フランスの専門職スタッフへのインタビュー調査とケア現場の参与観察調査のラウンデッド・セオリー・アプローチ(GTA)による分析から,ケアの実践を明らかにすることで,依存者から依存労働者に対する「お返し」の有無を考察する。分析の結果,スタッフは本稿で「ユマニテ」と名づける,社会の規範や制度を反省的に捉え直す哲学をケアのお返しとして,精神障がい者から受け取っていた。ユマニテを受け取ることで,スタッフは精神障がい者が社会的に排除される現状に疑問を持ち,社会の全体的な統合には脆弱性をもつ人々の社会的連帯への参加が不可欠であると認識していた。以上から,脆弱性をもつ人々が社会に必要な成員として承認される可能性として,ユマニテの社会への提供が示唆された。
2 0 0 0 IR 演劇とは何か
- 著者
- 安藤 隆之 Takayuki ANDO 中京大学文化科学研究所:中京大学教養部
- 出版者
- 中京大学文化科学研究所
- 雑誌
- 文化科学研究 = Cultural science (ISSN:09156461)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.1, pp.1-16, 1999-12-31
2 0 0 0 OA 明末清初におけるオランダ東インド会社の動向 : 一六五五年の遣清使節を中心に
- 著者
- 岩井 優典
- 雑誌
- 立教史学 : 立教大学大学院文学研究科史学研究室紀要
- 巻号頁・発行日
- vol.3, pp.55-63, 2012-02-29
- 著者
- 古城 健太郎 斎藤 輝男 加瀬 佳年 等 泰三
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬理学会
- 雑誌
- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)
- 巻号頁・発行日
- vol.77, no.6, pp.569-578, 1981 (Released:2007-03-09)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 2 1
投与した色素が気管支腺から排泄されることを利用して気管支分泌量を知ろうとする作野氏法をラットに適用し,N-acetyl-L-cysteine(NAC)および他の既知去痰薬の気道分泌に対する作用を比較検討した.次に直接気道液を定量的に採取し,液量の増減から去痰薬の効果を判定する Perry and Boyd の原法を改良した方法(Engelhorn および加瀬らの方法)を用い,正常ウサギの気道液量に対する NAC の作用を調べた.さらに,ウサギを SO2 ガスに長期間曝露し,亜急性気管支炎に罹患させ,その痰を定量的に採取し,痰の粘度ならびに痰の構成成分に対する NAC の作用を検討した.その結果下記の結論を得た.なお薬物はすべて胃内に投与した.1)正常ラットを用いた作野氏法による実験:各種去痰薬の気道分泌活性を ED35(対照値に比べ35%増加させる量)から比較すると,bromhexine・HCl 4.4mg/kg,pilocarpine・HCl 24mg/kg,potassium iodide 68mg/kg,L-methylcysteine・HCl 720mg/kg,sodiummercaptoethane sulfbnate 750mg/kg,NAC 1050mg/kg,S-carboxymethyl cysteine 1550mg/kg であった.はじめの3者は気道分泌量増加を主作用とし,後の4者は痰の粘度低下を主作用とする去痰作用機序の相違と思われる効果の差がみられた.2)正常ウサギを用いた気道液量測定実験:NAC 500mg/kg では,投薬後2時間目に気道液量が増加する傾向がみられたが有意ではなく,1000mg/kg および 1500mg/kg に増量すると,3~5時間をピークとして気道液量は有意に増加した.500mg/kg 以上の用量を投与すると,投薬後2時間目ごろから気道液の白濁がみられ,NAC が粘稠な気道液を流動化していることが推察された.3)亜硫酸ガス気管支炎ウサギを用いた実験:NAC 1000mg/kg および 1500mg/kg により,投薬後6時間分の痰の粘度は用量依存的に低下し,痰の凍結乾燥物質重量,蛋白質量および糖質量も痰の粘度に比例して減少した.以上の 成績より,NACは痰の粘度を低下させて痰の流動性を増し,さらに気道液量増加による痰の稀釈が加わって痰を出し易くするものと思われる.
2 0 0 0 OA 「性」を〈縛る〉 : GHQ、検閲、田村泰次郎「肉体の門」
- 著者
- 塚田 幸光 Yukihiro Tsukada
- 雑誌
- 関西学院大学先端社会研究所紀要 = Annual review of the institute for advanced social research (ISSN:18837042)
- 巻号頁・発行日
- no.11, pp.47-60, 2014-03-31
2 0 0 0 OA 豆腐と塩類
- 著者
- 長野 隆男
- 出版者
- 日本海水学会
- 雑誌
- 日本海水学会誌 (ISSN:03694550)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.4, pp.205-209, 2007 (Released:2013-02-19)
- 参考文献数
- 7
Tofu is a popular and traditional Japanese food. It is formed by the formation of heat-induced gels of soybean proteins, leading to determine its texture. Salts are used as coagulants on an industrial scale for the preparation of tofu and strongly affect the gel formation of soybean proteins. This article focuses on effects of salts on physical properties and gel structures of tofu. We explain: 1) relationship between physical properties and gel structures of commercial tofu, 2) effect of different coagulants on physical properties and gel structures of tofu, 3) effect of sodium chloride on the gel formation of soybean protein isolate, 4) effect of sodium chloride on physical properties and gel structures of tofu.
2 0 0 0 ストーカーから身を守るハンドブック
- 著者
- エミリー・スペンス・アルマゲヤー著 上田勢子訳
- 出版者
- 大月書店
- 巻号頁・発行日
- 2014
2 0 0 0 OA -酸化ビスマス(III)の新結晶変態の生成-
- 著者
- 真鍋 和夫 御手洗 征明 久保 輝一郎
- 出版者
- 公益社団法人 日本化学会
- 雑誌
- 工業化学雑誌 (ISSN:00232734)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.11, pp.1828-1835, 1968-11-05 (Released:2011-09-02)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 6
酢酸ビスマス(III)(Bi(CH3COO)3)の熱分解の機構を,熱重量分析,示差熱分析,X線分析,質量分析および化学分析の方法で追跡した。結果はっぎの通りである。酢酸ビスマス(III)は,50~200℃ で酢酸を放出して分解し,酢酸ビスムチル(BiOCH3COO)を生成する。酢酸ビスムチルは,280~320℃ でアセトン,炭酸ガス,水などを放出して分解し金属ビスマスとなる。金属ビスマスは空気中の酸素により酸化されて酸化ビスマス(III)となるが,分解温度370℃ 以下では酸化ビスマス(III)の新結晶変態を生成し,分解温度390℃ 以上ではα-酸化ビスマス(III)となる。この結晶転移は, 370~390℃ で生起し, 非可逆的であり, 発熱反応である。この新酸化ビスマス(III)は,酢酸ビスマス(III)の空気中の熱分解で, 分解温度320℃ で純粋なものとして生成する。そして,それはX線回折図形から考えて,歪んだ三二酸化マンガン型の結晶構造(正方晶系)をもつ。
2 0 0 0 OA 滑稽の不在 : 明治文豪の論争
- 著者
- 浦 和男
- 出版者
- 日本笑い学会
- 雑誌
- 笑い学研究 (ISSN:21894132)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, pp.3-16, 2013-08-31 (Released:2017-07-21)
明治になり、日本に近代の文学が確立する時期に、文壇でいろいろな論争が起こった。そのひとつに、「滑稽文学の不在」論争がある。20年代末、「太陽」の編集をしていた若き高山樗牛が、すでに文豪として高名な坪内逍遥のエッセーに対して、そのユーモア観を批難し論争が始まる。その論争は、「ユーモアとは何か」から「滑稽文学の不在」論争となり、やがて「文学における滑稽の不在」が問われ、それが「笑わない国民」という点にまで達した。執拗な樗牛の批判に逍遥は無視を決めていたが、最後には樗牛は「笑殺」、逍遥は「笑倒」という語を使うまでになった。一年ほどで二人の論争は鎮まるが、論争は飛び火し、地方紙でも「滑稽の不在」に関する記事が掲載され、明治末年まで「笑いのない文学」が論じられた。本稿では、「日本人はユーモアがない、笑わない」という問題の起源ともなる、この論争を考証し、近代ユーモア史の一面を明らかにする。