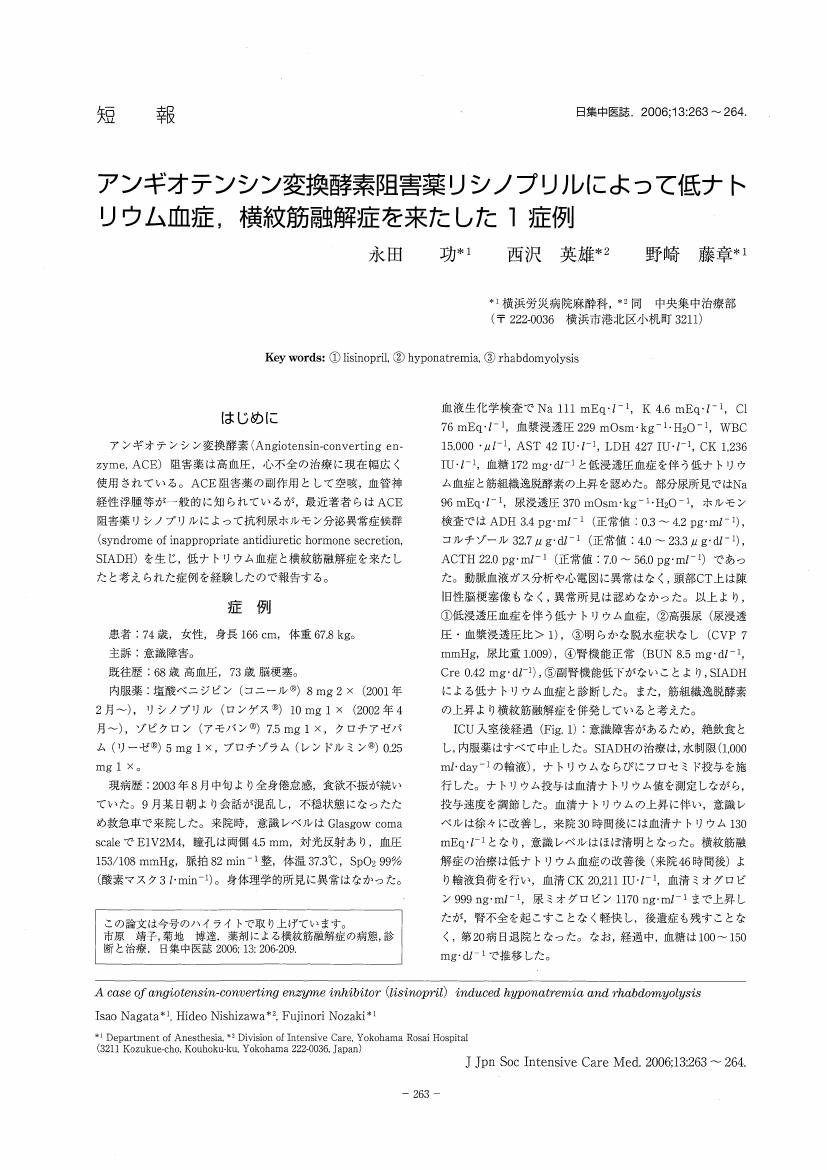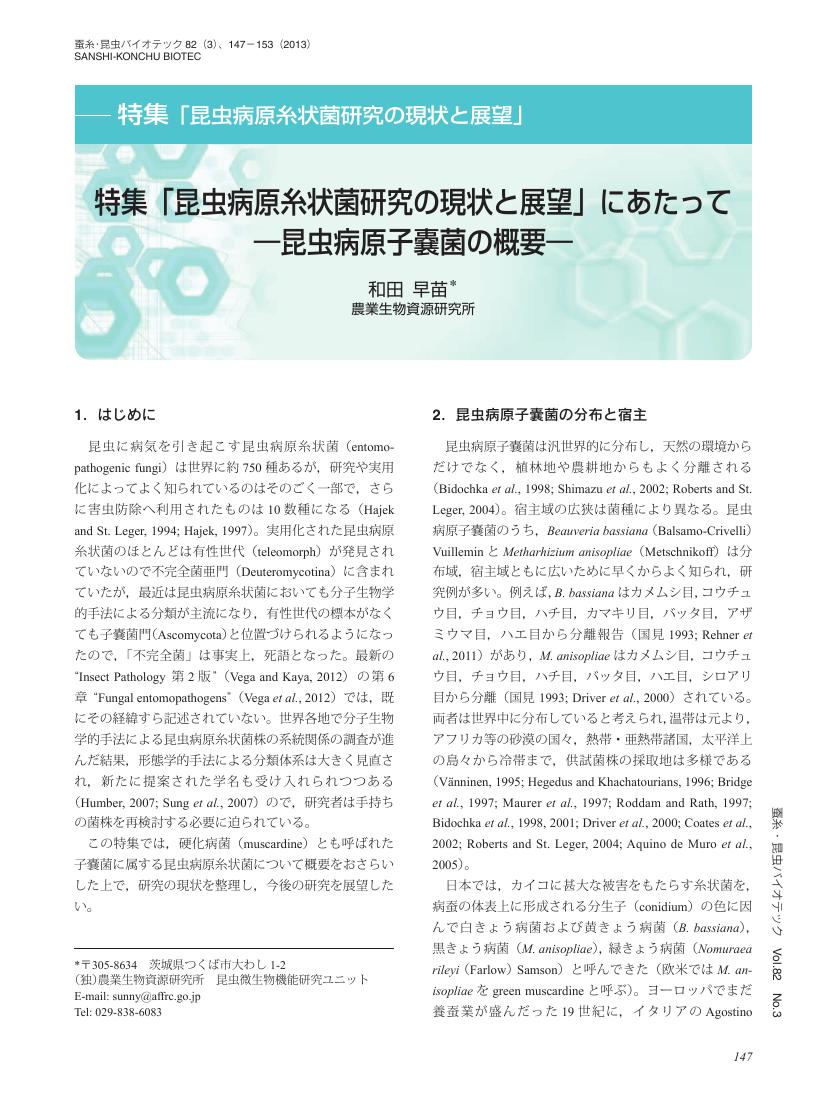- 著者
- Kenji Nakamoto Naka Shiratori Yusuke Nishio Shio Sugimoto Yasuko Takano Masashi Yamazaki Yutaro Tobita Tsutomu Igarashi Hiroshi Takahashi
- 出版者
- The Medical Association of Nippon Medical School
- 雑誌
- Journal of Nippon Medical School (ISSN:13454676)
- 巻号頁・発行日
- vol.88, no.5, pp.506-508, 2021-10-25 (Released:2021-11-17)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 4
Decreased vision and cystoid macular edema (CME) developed in phakic eyes of a patient who underwent laser iridotomy after changing the glaucoma eye drops from carteolol 2% long-acting ophthalmic solution to omidenepag isopropyl 0.002%. CME completely disappeared at approximately 2 months after discontinuation of omidenepag isopropyl in conjunction with the use of bromfenac sodium 0.1%.
- 著者
- 松本 直美
- 出版者
- 日本音楽学会
- 雑誌
- 音楽学 (ISSN:00302597)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.1, pp.56-68, 2011-10-05
The contribution of Marquis Pio Enea degli Obizzi (1592-1674) to the early history of opera was noted first by the 17th-century chronicler Cristoforo Ivanovich. He indicated in his (in) famous Le memorie teatrali di Venezia (first published in 1681) that L'Ermiona, an 'opera torneo' (opera tournament) performed in Padua in 1636, for which the Marquis contributed to the libretto, had been nothing less than the direct impetus for the inauguration of the first-ever commercial opera house in Venice in the following year. This paper will first introduce Obizzi, whose activities have been under-investigated in previous scholarship. Then, it will explore the opera tournaments with which the Marquis was involved during the 1630s and 40s. The paper will argue that this genre did indeed (as Ivanovich implies) directly influence the formation of commercial opera in Venice. Moreover, drawing on little-known sources, Obizzi's vital role - as a plot deviser - in those productions will be indicated and the significant implications concerning this function in our notion of 'authorship' in the early operatic production will be explored. Finally, it will be proposed that a detailed analysis of Obizzi's works not only enables us to trace the crucial transition which opera of that time took - from court to commercial enterprise - but also suggests new perspectives in relation to our understanding of early opera industry as a whole.
2 0 0 0 OA 『夢十夜』成立期への一視点 : <あまのじゃく>という方法
- 著者
- 江藤 正顕
- 出版者
- 九州大学
- 雑誌
- Comparatio (ISSN:13474286)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.27-42, 1997
This essay deals with the literary method of Natsume Soseki's "Ten Nights of Dream". It seems to me that Soseki's method in this work is directly related to that of E.A.Poe's technique of literary 'perversity'. Soseki's diaries and memoranda also provide clues concerning dreams and the imagination as well as scientific or philosophical conceptions, which also relate to the literary method I analyse.
2 0 0 0 OA シェリング芸術哲学における構想力 図式と象徴の関係から見たカントの変容
- 著者
- 八幡 さくら
- 出版者
- 日本哲学会
- 雑誌
- 哲学 (ISSN:03873358)
- 巻号頁・発行日
- vol.2016, no.67, pp.262-276, 2016-04-01 (Released:2017-10-13)
Schelling erklärt das Schema und das Symbol im System des transzendentalen Idealismus (1800) und in der Philosophie der Kunst (1802-03, 1804-05). Sie beziehen sich darauf, wie sich der Begriff oder die Idee mit dem Gegenstand in unserer Anschauung verbinden kann. Das Schema und das Symbol werden durch Kants Kritik der reinen Vernunft (1781) und Kritik der Urteilskraft (1790) beeinflusst. Indem ich die Texte Schellings mit diesen Kritiken Kants vergleiche, zeige ich, wie Schelling von Kant die Begriffe (Schema und Symbol) übernommen und weiterentwickelt hat. Bei Schelling wird ein Gegenstand durch die Einbildungskraft mit einem Begriff oder einer Idee verknüpft und in der ästhetischen Anschauung (der objektiv gewordenen intellektuellen Anschauung) vereinigt. In dieser Anschauung verbindet sich die Einbildungskraft unmittelbar mit den Ideen und das Schöne kann sich von seiner realen, objektiven Seite zeigen. Kant unterscheidet in seiner ersten Kritik das Schema, welches durch die transzendentale Einbildungskraft mit dem Begriff verbunden wird, vom Symbol, das in seiner dritten Kritik durch die ästhetische Urteilskraft mit den Ideen verbunden wird. Diesen Unterschied übernimmt Schelling im System, fügt dann in der Philosophie der Kunst die Allegorie zu diesen zwei Begriffen (Schema und Symbol) hinzu, und definiert Schema, Allegorie und Symbol als drei verschiedene Arten der Darstellung des Absoluten. Bei Schelling sind diese drei auch drei verschiedene Arten der Einbildungskraft, die alle in der intellektuellen Anschauung wirken. Unter intellektueller Anschauung versteht Schelling besondere Gattungen und Formen der Kunst als verschiedene Darstellungen des Absoluten in der realen Welt, wenn Schema, Allegorie und Symbol mit seinen drei Stufen der Potenz übereinstimmen. So kann Schelling in seiner Philosophie der Kunst die Kunst durch die Potenzierung begreifen. Daraus schließe ich, dass Schellings Theorie der Einbildungskraft im System nicht außerhalb des Bereiches der Kantischen Theorien des Schemas und des Symbols liegt, sich aber erst in der Philosophie der Kunst als eine originelle Theorie vollendet.
2 0 0 0 大岡昇平『野火』考--プロメテウスの神学
- 著者
- 渡辺 章夫
- 出版者
- 愛知大学大学院院生協議会
- 雑誌
- 愛知論叢 (ISSN:02896419)
- 巻号頁・発行日
- no.69, pp.232-213, 2000
2 0 0 0 IR 国民の分身像 : 泉鏡花「高野聖」における不気味なもの
- 著者
- 堀井 一摩
- 出版者
- 東京大学大学院総合文化研究科言語情報科学専攻
- 雑誌
- 言語情報科学 (ISSN:13478931)
- 巻号頁・発行日
- no.14, pp.225-240, 2016
本稿は、泉鏡花の「高野聖」における不気味な他者たちの表象が日清日露戦間期の日本社会においてどのような意味を担っていたのかという問題を考察する。まず「高野聖」に書き込まれた近代性の記号、すなわち地図、徴兵制、衛生学の歴史性を追跡し、それらが近代的国民軍の要請によって整備されたものであることを確認する。そのうえで、宗朝と、富山の薬売り・次郎との分身関係を分析することを通じて、「高野聖」が、不気味な動物的他者が表徴する脱国民的身体への憧憬を保存していたという読解を提示する。最後に、孤家の女が統治する「代がはり」の世界の意味を考察し、壮健な男をもはや戦うことのできない動物に変じる女の魔力が、国民国家にとってサブヴァーシヴな力をもつことを明らかにする。鏡花は、このような異界を仮構することで、対外戦争へと向かっていく近代日本の国民の生きる空間を逆照射し、それに異議を申し立てるようなヘテロトピアを描いている。
- 著者
- 永田 功 西沢 英雄 野崎 藤章
- 出版者
- The Japanese Society of Intensive Care Medicine
- 雑誌
- 日本集中治療医学会雑誌 (ISSN:13407988)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.3, pp.263-264, 2006-07-01 (Released:2009-03-27)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 1 1
2 0 0 0 OA 特集「昆虫病原糸状菌研究の現状と展望」にあたって
- 著者
- 和田 早苗
- 出版者
- 社団法人 日本蚕糸学会
- 雑誌
- 蚕糸・昆虫バイオテック (ISSN:18810551)
- 巻号頁・発行日
- vol.82, no.3, pp.3_147-2_153, 2013 (Released:2014-02-28)
- 参考文献数
- 76
2 0 0 0 OA カントの平和の哲学
- 著者
- 宇都宮 芳明
- 出版者
- 北海道大學文學部 = The Faculty of Letters, Hokkaido University
- 雑誌
- 北海道大學文學部紀要 (ISSN:04376668)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.1, pp.55-108, 1988-01-16
2 0 0 0 OA 古代の織物技術
- 著者
- 高野 昌司
- 出版者
- 一般社団法人 日本繊維機械学会
- 雑誌
- 繊維機械学会誌 (ISSN:03710580)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.2, pp.45-48, 1998-02-25 (Released:2009-10-27)
- 参考文献数
- 7
2 0 0 0 OA 足利健亮会長の死を悼んで
- 著者
- 成田 孝三
- 出版者
- 一般社団法人 人文地理学会
- 雑誌
- 人文地理 (ISSN:00187216)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.1, pp.1-4, 2000-02-28 (Released:2009-04-28)
2 0 0 0 OA 3D05 学生の能力を伸ばす企業連携PBL教育の実践
- 著者
- 黄 啓新 金井 徳兼 三栖 貴行 山崎 洋一 杉村 博 安部 惠一
- 出版者
- 公益社団法人 日本工学教育協会
- 雑誌
- 工学教育研究講演会講演論文集 第66回年次大会(平成30年度) (ISSN:21898928)
- 巻号頁・発行日
- pp.426-427, 2018 (Released:2018-10-28)
2 0 0 0 OA 食料安全保障とは何か ―日本と世界の食料安全保障問題―
- 著者
- 大賀 圭治
- 出版者
- システム農学会
- 雑誌
- システム農学 (ISSN:09137548)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.1, pp.19-25, 2014-01-10 (Released:2015-06-04)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 1
「食料安全保障」という政策用語は、1970 年代の世界的な食糧危機の中で使われはじめ、1980 年代にFAO などの場で、日本が主導して、「食料安全保障」についての論議が世界的に進み、1996 年の世界食料サミットでは「食料安全保障」が統一テーマとなった。日本の食料安全保障は、食料自給率の低下、つまり食料供給の海外依存の深まりの下で、国内食料供給の維持・向上と輸入食料の安定確保を課題としている。ヨーロッパの食料輸入国も日本と同様に国内生産の振興、緊急時における需要管理(配給)制度などによって食料危機に対応する食料安保の態勢をとっている。アメリカやEUのような食料輸出国・地域でも、食料不足の事態に対処する手段を制度化している。食料問題が最も深刻な後発途上国の食料問題は、貧困問題解決への国際協力のなかで取り組まれている。世界的な食料需要の増加と地球温暖化による食料・農産物市場の不安定化に対処するため、2011 年G20カンヌ・サミットでは、作物生産予測や気象予報を改善するため、リモートセンシングを活用した国際ネットワーク、「世界農業地理モニタリングイニシアティブ」の計画を進めることが決議された。このような食料安全保障の問題を解決するためのツールとして、リモートセンシングを基礎とする農業情報システムの活用が世界的に期待されている。
2 0 0 0 OA 心理的虐待の定義に関する検討
- 著者
- 池 弘子
- 雑誌
- 聖学院大学論叢 = The Journal of Seigakuin University (ISSN:09152539)
- 巻号頁・発行日
- vol.第19巻, no.第1号, pp.33-46, 2006-11
Research has established that psychological abuse has the longest-lasting and strongest negative effect on children of any type of child abuse. There are many researchers who believe that psychological abuse is a core component of all types of child abuse. But psychological abuse has created so many difficulties and so much confusion for researchers and practitioners, and these difficulties and confusion have led to delays in protective intervention. It is pointed out that one of reasons for these difficulties and confusion lies in the absence of a unified and precise definition. This study reviews the wide range of definitions of psychological abuse and proposes an appropriate direction for defining the term. (a) Psychological abuse should be defined solely by parental behaviour having potential for harm to a child not including observable child harm. (b) Psychological abuse should be limited to nonphysical parental behaviour and nonphysical child outcomes. (c) Parental intent to harm the child is not necessary for the definition. (d) Psychological abuse should include not only repeated patterns of parental behaviour but also singular extreme incident. In addition I propose the following five subtypes of psychological abuse: spurning, terrorizing, isolating, encouraging inappropriate behavior, and denying emotional responsiveness.
2 0 0 0 IR 歴史・民俗 城山三郎と捕虜収容所
- 著者
- 池田 憲一
- 出版者
- 日本福祉大学知多半島総合研究所
- 雑誌
- 知多半島の歴史と現在 = Chita Peninsula, its history and present (ISSN:09154833)
- 巻号頁・発行日
- no.23, pp.125-130, 2019-10
- 著者
- 山田 有策
- 出版者
- 学灯社
- 雑誌
- 国文学 解釈と教材の研究 (ISSN:04523016)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.8, pp.p72-78, 1986-07
2 0 0 0 OA 玄米の長期継続摂取(90日間)による血中コレステロール値低減効果の検証
- 著者
- 横山 千鶴子 前田 雪恵 石川 幸枝 鈴木 司 小林 謙一 辻井 良政 髙野 克己 中川 徹 山本 祐司
- 出版者
- 日本食生活学会
- 雑誌
- 日本食生活学会誌 (ISSN:13469770)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.2, pp.89-95, 2017 (Released:2017-10-31)
- 参考文献数
- 24
Serum cholesterol level reduction is an important factor for preventing lifestyle-related disease. Together, search for food materials which reduces serum cholesterol level have come to people' s attention. In this study, we carried out a large-scale and a long-term study to evaluate the effect of brown rice on serum cholesterol level. In brief, we conducted this study using a cross-over design with 90 days of consuming pregelatinized brown rice against non-brown rice. The following results were obtained.1) There was a low drop-out rate: 2.5% (3 of 120 subjects), and many participants replied that this program was easy to join, because the preparing of brown rice was very easy and the contents of the program were very simple.2) Brown rice intake increased bowel movement and improved the participant' s physical condition.3) Serum cholesterol levels were significantly decreased in the subjects starting with abnormal value of serum cholesterol (over 221 mg/dL) by brown rice intake.4) Brown rice intake decreased serum LDL cholesterol in the subjects with initial level of high serum LDL cholesterol (over 140 mg/dL).5) However, serum HDL cholesterol level of brown rice intake group did not change in the subjects of low serum HDL cholesterol levels (under 40 mg/dL). These large-scale studies suggested brown rice has serum cholesterol decreasing effect in people with high cholesterol level.
2 0 0 0 IR 霊泉・霊湯 : 別府の伝説
2 0 0 0 OA 在日朝鮮文化財問題のアートマネージメントの観点よりの考察 (情報表現学科特集号)
- 著者
- 林 容子
- 雑誌
- 尚美学園大学芸術情報学部紀要 = Bulletin of the Faculty of Informatics for Arts, Shobi University (ISSN:13471023)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.57-79, 2004-12-24
2002年から2004年の夏にかけて、マンスフィールド財団、アジア財団、パシフィックフォーラムという3つの米国系財団の招聘で、日韓の諸問題を討議するリトリートに参加した。安全保障や外交の専門家に加え、NGO、文化、ジャーナリズムを専門とするそれぞれの国の代表が一同に招聘され、自由に討議した。それぞれの視点より、日韓関係を述べることになったとき、筆者のカウンタパートである韓国の美術史家より、「日本は、日帝期時代に多くの朝鮮墳墓を発掘し、朝鮮美術品を不当に日本に持ち帰り、返還していない。日本には、多くの逸品を含む30万点に上る朝鮮文化財があり、韓国の研究者は、自国の文化財なのに、わざわざ日本まで見に行かなければならないし、なかなか見ることができない。」と開口一番に指摘された。文化分野を代表していたものの、私の専門はアートマネージメントであり、朝鮮美術の専門家ではない。これまで、特に朝鮮美術はおろか、日韓関係についても特別の関心は持ってこなかった。彼女が指摘したのは、いわゆる略奪文化財の問題であるが、略奪文化財といえば、それまで私の脳裏に浮かぶのは、大英博物館保有の古代ギリシアの大理石彫刻(別名:エルギンマーブル)やナチスが略奪して、散逸した美術品の数々であり、「日本が朝鮮から美術品を略奪した」といわれても"晴天の霹靂"といわざるをえなかった。その場では、残念ながら日本代表として弁護することも、謝罪することもできず、とにかく自分なりに事実関係を確認し、次に報告すると約束するのが精一杯だった。これが本稿の切掛けとなった。帰国後、このことを日本の様々な知人に話すと様々な反応が帰ってきた。しかし、この件について無知だったのは、私だけでなく、朝鮮美術や東洋美術の専門家の友人を除いて、多くにとって、このことは初耳のようだった。事情を話すと、一般の人は「それなら返還したらいいじゃない。」と別に人事のような反応だった。一方、日本の東洋美術の専門家の友人たちに話すと、「この件は、すでに決着がついているのに、何故いまさらそんな過去のことを調査するのか。日韓の文化交流はとてもよくなっているのに、あなたがしようとしていることは、全くの時間の無駄であり、それよりも何故、もっと前向きなことにエネルギーを使わないのか。」と大変な勢いで抗議された。本問題に関して、両国の国民の間の意識レベルに大きなギャップが存在する。この問題に対する双方の一般国民の意識の低さおよび事実関係の認識の欠如が他の日韓の歴史問題同様に感情論の問題にしてしまい、根本的な問題解決を妨げていることも否めない。その一方で、日本と韓国の交流は、日韓ワールドカップの共催を経て両者の政府の方針もあり急速に高まっている。韓国側でも政府主導の友好的な外交政策がとられ、少なくとも日本では韓国に対する国民感情が少しずつながら好意的なものになっている。結果として85年以降日本人コレクターによる韓国への文化財の恣意的な寄贈も増えている。今、日本は、国交正常化以来の韓国文化ブームに沸いている。また、韓国でも、日本の朝鮮半島占領政策がもたらした経済効果を数字で分析する経済学者1が現れるなど、単なる感情論を越えて、日本の植民地政策を分析しようという動きが出てきている。調査を進めるうち、本問題は、日本の朝鮮植民地政策、日韓条約などの歴史問題に深く関わることはいうまでもないが、さらに、現在の国際法上での略奪美術品の扱いの問題や日本における美術品に関する税制や公開の制度の未整備など、国内外のアートマネージメント上の問題が大きく関わっていることがわかった。そこで本稿では、大きく第一に、在日朝鮮文化財の歴史的経緯、第二に、国際的および日本の国内事情の抱えるアートマネージメント関連の問題の考察、つまり、多くの在日朝鮮美術品の返還と公開に関わる問題を取り上げる。最後に、これらを踏まえた上でのこの問題に対する改善試案を提案する。
2 0 0 0 OA 新・翻刻「春城日誌」(一) -「菰月蘋風楼日録」一~四巻 明治十八・十九年-
- 著者
- 藤原 秀之
- 出版者
- 早稲田大学図書館
- 雑誌
- 早稲田大学図書館紀要 (ISSN:02892502)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, pp.201-275, 2023-03-15