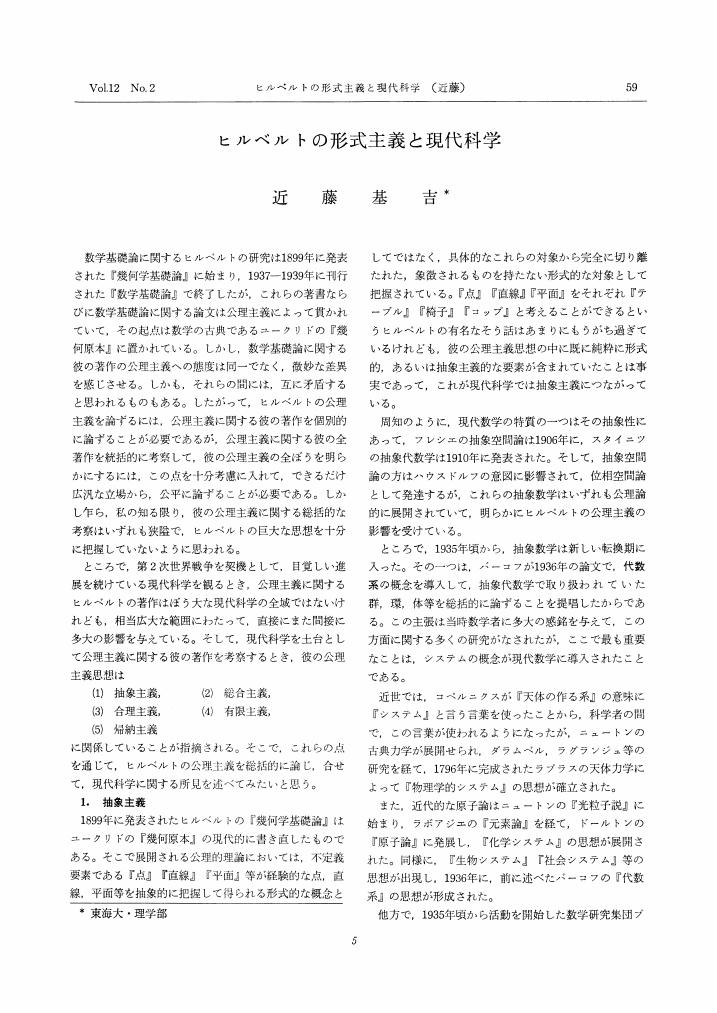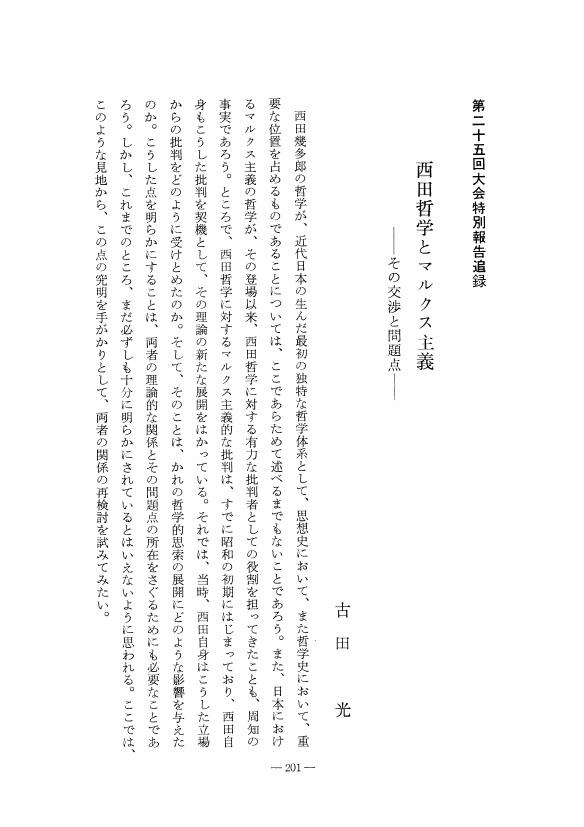2 0 0 0 OA モンゴル西部バヤン・ウルギー県サグサイ村における移動牧畜の現状と課題
- 著者
- 相馬 拓也
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- E-journal GEO (ISSN:18808107)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.1, pp.102-119, 2014-07-04 (Released:2014-07-10)
- 参考文献数
- 28
- 被引用文献数
- 1 1
モンゴル西部アルタイ地域(バヤン・ウルギー県)では伝統的な季節移動型牧畜活動が,アルタイ系カザフ社会の生産体系の根幹をなす.しかし遠隔地かつ少数民族社会であることから,同地域ではいまだ生活形態などの基礎的知見が確立していない.本研究では,同県サグサイ村ブテウ冬営地(BWP)の牧畜開発・地域支援を視座に,滞在型のフィールドワークを行った.長期滞在による参与観察やウルギー県統計局の内部資料を参照し,①世帯毎の所有家畜総頭数・構成率,②家畜飼養・管理方法,③季節移動の現状,についての基礎的知見を明らかとした.その結果,BWPでは6割以上が貧困層世帯であり,最低限の生活水準にあることが確認された.また計画的増産や日々の放牧への人的介入は行われず,牧畜生産性の停滞など,アルタイ系カザフ牧畜社会が抱える現状と課題が明らかとなった.
2 0 0 0 OA ヒルベルトの形式主義と現代科学
- 著者
- 近藤 基吉
- 出版者
- 科学基礎論学会
- 雑誌
- 科学基礎論研究 (ISSN:00227668)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.2, pp.59-64, 1975-03-25 (Released:2009-09-04)
- 参考文献数
- 7
2 0 0 0 OA 術前評価における術前検査の役割
- 著者
- 稲田 英一
- 出版者
- 日本臨床麻酔学会
- 雑誌
- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.7, pp.582-587, 2005 (Released:2005-11-29)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 2 2
術前評価において術前検査のおもな役割は, 病歴や身体所見から示唆される病的状態の程度を評価し, 周術期の管理計画を立てる手がかりとなることである. 術前検査は, 患者のもつ疾患, 予定術式, 検査の特性などから決定される. それぞれ感度や特異度が100%という検査はなく, 偽陽性や偽陰性が起こりうる. さらに, 検査を行う患者群の有病率によっても, 感度や特異度は異なる. 心電図, 胸部X線検査, ヘモグロビン濃度測定などの術前検査はスクリーニング検査としての意義は低く, 病歴や身体所見から示唆されるものについて行うべきである.
2 0 0 0 OA 多角的な価値査定とヘテラルキーの生成 フランス市場における日本酒の普及プロセス
- 著者
- 稲垣 京輔 マーティン ジュリアン
- 出版者
- 日本情報経営学会
- 雑誌
- 日本情報経営学会誌 (ISSN:18822614)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.1-2, pp.75-88, 2020 (Released:2020-09-23)
- 参考文献数
- 35
This study illustrates the value evaluation process of Saké in the French market developing through a review of a survey of Lamont (2012) that attempted to capture value evaluation research from various perspectives. Lamont has derived three evaluation processes: “Categorization and Legitimation”, “Identifying and Producing of Heterarchies”, and “Evaluative practices”. Based on these, we portrayed how Japanese Saké has been evaluated in French market, where a wine value evaluation system has been already established. As a result, it was confirmed that heterarchies that are structured around the spread of Japanese Saké lead to new practices, thereby establishing relationships that share value in other institutional areas under the situation where there is no consistent value evaluation system in the overseas market. In other words, it was confirmed that the evaluation practices legitimate other institutional contexts accompanied the process of expanding and changing the organizational fields.
2 0 0 0 OA パニック値とは〜現代版パニック値の考察〜
- 著者
- 七崎 之利 諏訪部 章
- 出版者
- 一般社団法人 日本臨床救急医学会
- 雑誌
- 日本臨床救急医学会雑誌 (ISSN:13450581)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.3, pp.489-498, 2017-06-30 (Released:2017-06-30)
- 参考文献数
- 19
パニック値の概念は,1972年のLundbergまで遡る。それは,単なる検査値の定義ではなく,システムである。統計的に設定した基準範囲から,大きく外れた検査値である極端値は,検査データの保証を前提に,検査室で種々のエラーを否定した後,パニック値として,臨床へ報告される。パニック値リストやその連絡システムは,臨床と協議の上,作成,構築される。近年のパニック値に関する医療事故は,いずれもLundbergが定義したパニック値の連絡体制の不備に起因する。したがって,この概念は現代も必要不可欠である。一方,救急初期診療の標準化や救急現場へのPOCT(臨床現場即時検査)の導入,検査室のISO15189認定取得などにより,パニック値は,新たな変化が求められている。これからのパニック値は医師や臨床検査技師などの専門知識に関する互いの教育,知識の共有,これらに基づいたより緊密な連携を必要とする。
2 0 0 0 OA 高次脳機能障害者の就労支援 ―外傷性脳損傷者を中心に―
- 著者
- 先﨑 章
- 出版者
- 公益社団法人 日本リハビリテーション医学会
- 雑誌
- The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine (ISSN:18813526)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.4, pp.270-273, 2017-04-18 (Released:2017-06-16)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 1 2
復職や就労の予後を予測できる単一の指標はない.外傷性脳損傷の場合,就労の予後と関連する可能性があるものとして,年齢,教育レベル,受傷前の職業レベル,重症度(昏睡期間の長さ,外傷後健忘期間,入院期間),現状の機能,うつや不安の程度,性別や人種,さまざまな神経心理学検査結果などがあるが決定的なものはない.就労支援に際しては,成功あるいは失敗に至り得る多角的な要因を念頭に置きつつ,必要に応じて多職種で連携して,個別性のある柔軟な介入,長期的な切れ目のない支援が必要である.加えて,小児期発症の高次脳機能障害者に対しては,青年期や就労前時期段階での就労準備支援が必要である.加えて日本での障害者の就労支援は,ハローワーク,地域障害者職業センター,障害者就業・生活支援センター,障害者職業能力開発校,就労移行支援事業所,就労継続支援事業所(A型・B型)が連携して行っている.支援において大切なことは,連携支援,障害認識,周囲の理解とその対応,アセスメントである.職場での配慮事項として,指示の出し方の工夫,本人の特徴に合わせた業務内容,担当者を決める,易疲労性への配慮がある.
2 0 0 0 古代ギリシア史研究と奴隷制
- 著者
- 伊藤 貞夫
- 出版者
- 法制史学会
- 雑誌
- 法制史研究 (ISSN:04412508)
- 巻号頁・発行日
- no.55, pp.121-154,10, 2005
近年におけるギリシア・ローマ経済史研究で目を惹くのは、M・I・フィンリーの古代経済論への諸家の対応である。プリミティヴィズムとモダニズムとの対抗として要約される、この種の研究視角は数多くの成果を生んできたが、そのなかにあってフィンリーの古代史観の一つの軸をなしながら、方法論的に十分な檢討と意義の評価を受けていないのが彼の奴隷制論である。その特徴は、古典期のアテネやローマ盛期のイタリア・シチリアに見られる大量かつ集中的な奴隷使役を、古典古代にあっても特殊な事例と看做し、相対化するところにある。小論は、前五世紀のクレタで刻されたゴルチュンの「法典」を中心に、関連の古典史料や金石文をも勘案しつつ、軍事的征服と負債とにそれぞれ起因する二種の中間的隷属状況の、古代ギリシアにおける広汎な存在を確認し、かつ後者の型の古典期アテネにおける存続を想定するP・J・ローズとE・M・ハリスの説を批判したのちに、都市国家市民団内部の民主化による中間的隷属者の消滅が代替労働力としての典型的奴隷の使役を促したとするフィンリーの試論を、古典古代社会の歴史的展開の理解に有用な視点を供するもの、と積極的に評価する。フィンリー説の背景にあるのは古代オリエントについての知見であるが、加うるに近代以前の中国と日本の身分制に関する研究成果を以てすべし、との提言で小論は閉じられる。
- 著者
- 岩本 夏実 田川 一希
- 出版者
- 一般社団法人 日本生物教育学会
- 雑誌
- 生物教育 (ISSN:0287119X)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.3, pp.167-172, 2021 (Released:2021-12-25)
- 参考文献数
- 22
保育者が,幼児と動物との関わりを支援する際の特徴的な言葉かけとして,動物に対して「さん」「くん」「ちゃん」といった敬称を付けて呼ぶ表現(敬称表現)が挙げられる.保育者83名に対する質問紙調査の結果,幼児と8種類の動物との3種類の関わりの場面について,敬称表現が用いられる場合は60.5%であった.幼児が動物と仲良く遊んでいる場面,動物をいじめている場面では,幼児が動物の生態に興味を持っている場面と比較して,敬称表現が用いられる頻度が高かった.敬称表現の使用のねらいについて,保育者は,幼児の生命尊重や親しみの感情,思いやりの気持ちの育ちを意識していた.
- 著者
- 金澤 貴之 二神 麗子 中野 聡子 KANAZAWA Takayuki FUTAGAMI Reiko NAKANO Satoko
- 出版者
- 群馬大学共同教育学部附属教育実践センター
- 雑誌
- 群馬大学教育実践研究 (ISSN:09123911)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, pp.165-174,
2 0 0 0 OA 被圧地下水の流動にともなう水文地球化学的進化
- 著者
- 山中 勝
- 出版者
- Society of Environmental Conservation Engineering
- 雑誌
- 環境技術 (ISSN:03889459)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.8, pp.575-579, 2005-08-20 (Released:2010-03-18)
- 参考文献数
- 9
2 0 0 0 OA ゲーミフィケーションの倫理ガイドライン 文献レビューを中心とした検討と提案
- 著者
- 井上 明人 高橋 志行
- 出版者
- 一般社団法人 日本デジタルゲーム学会
- 雑誌
- 日本デジタルゲーム学会 年次大会 予稿集 第13回 年次大会 (ISSN:27586480)
- 巻号頁・発行日
- pp.51-56, 2023 (Released:2023-03-30)
- 参考文献数
- 33
本稿では文献レビューを通して、ゲーミフィケーションの倫理的ガイドラインに、どのような内容が多く提案される傾向にあるかを示し、この作業を通じてゲーミフィケーションに取り組む運営者が、実際に配慮すべき現時点の方向性を提供する。また、ゲーミフィケーションに係る倫理的ガイドラインの限界についても見通しを提示する。最後にゲーミフィケーションのガイドラインとして必要最低限と思われる水準の案を提示する。
- 著者
- Boutellier Organvidez Juan Carlos
- 出版者
- 九州地区国立大学間の連携事業に係る企画委員会リポジトリ部会
- 雑誌
- 九州地区国立大学教育系・文系研究論文集 = The Joint Journal of the National Universities in Kyushu. Education and Humanities (ISSN:18828728)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.2, pp.No.5, 2023-03-31
本論文は「九州地区国立大学教育系・文系研究論文集」Vol.9, No.2(2023年/3月)に査読を経て受理された。
2 0 0 0 OA 潤滑油の品質と動向 (9) ―防錆油―
- 著者
- 高島 朗
- 出版者
- 公益社団法人 日本マリンエンジニアリング学会
- 雑誌
- 日本舶用機関学会誌 (ISSN:03883051)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.11, pp.923-927, 1981 (Released:2010-05-31)
- 参考文献数
- 6
2 0 0 0 OA 水道水による腐食
- 著者
- 門井 守夫
- 出版者
- 社団法人 腐食防食協会
- 雑誌
- 防蝕技術 (ISSN:00109355)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.2, pp.51-61, 1972-02-15 (Released:2009-11-25)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 2
2 0 0 0 OA 西田哲学とマルクス主義 その交渉と問題点
- 著者
- 古田 光
- 出版者
- 日本哲学会
- 雑誌
- 哲学 (ISSN:03873358)
- 巻号頁・発行日
- vol.1967, no.17, pp.201-210, 1967-03-31 (Released:2009-07-23)
2 0 0 0 OA 交通地理の方法
- 著者
- 山口 平四郎
- 出版者
- The Human Geographical Society of Japan
- 雑誌
- 人文地理 (ISSN:00187216)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.5, pp.467-494, 1971-10-28 (Released:2009-04-28)
- 参考文献数
- 89
Transportation is one of spectacular phenomena on the earth surface. Such being the case, it is uncommon to pass without saying anything about it at geographical study of various regions. Particularly in our country, specialists in transportation geography are few and even less methodological works in this line had been published. Therefore, it may be necessary for us to treat the true nature of transpotation geography and examine it from a pure theoretical standpoint. I have tried to throw light upon this theme in making comparative study among several methodologies of representative experts such as Kohl, Ratzel, Vidal de la Blache, Hassert and Hettner.J.G. Kohl is known as the founder of transportation geography for his famous lifework which was published at Dresden in 1841. He had for the first time systematically grasped the regional features of the transport phenomenon as a whole, in conformity with its correlation to the physical environment, and then followed up his study on the mutual location between the transport route and the settlement, believing that these two factors make up both sides of the shield in human life. Having scrutinized every environmental conditions in transportation, he came to express with confidence, already about 80 years before the airplane invention, that the most favourable transport route would find itself in the high layer of the atmosphere in the future. It is his unique process to treat deductively the theoretical location and formation of routenets and settlements, with exemplification of a lot of geometrical figures.Friedrich Ratzel took the transportation for a sort of “historical movement” which is the fundamental conception of his geographical thought, and looked with special attention at the correlation between the ever moving human being and the fixed earth. He also pointed out the existence of the “geographical restriction” from the fact that a steady continuity of the routes' location is taken notice of there, in spite of the everlasting development of the transportation efficiency and means. Furthermore he looked on the transportation as “a conqueror of distance”; so his principal concern had been focussed to confirm how the transportation time was shortened at a certain space in examining the effect of the technical transport improvements.It is well-known fact that Ratzel's theory had not been met with warm acceptance in Germany and English-speaking countries, yet it was a little bit another story in France.P. Vidal de la Blache, leader of French school of geography, together with many other historians and sociologists, started to criticize Ratzelian thoughts, and in such process the standpoint of geographic possibilism against the Ratzelian determinism is said to have been built up; peculiarity of Vidal's method is its historico-geographical comprehension of the transport. He noticed that many Eurasian folded mountains would not to be overcome without utilizing of the vital transport spots: “gates”, as ancient geographers termed them, and such recognition got him to hit upon the “principle of continuity”. In addition, he took up the origin of transport animals and vehicles in various lands all over the world, and then the functional correlation between railways and modern roads.K. Hassert was Ratzel's disciple. His method was influenced by his master on the one hand, but at the same time he paid particular attention to the theories of national economists on the other hand. In his two-volumes lifework, a comprehensive survey of past transportation geographical researches, there are found detailed explanations of the transport on roads, railways, inland water ways and ocean routes in various regions on all over the earth surface in close touch with each environmental conditions and regional characteristics.
2 0 0 0 OA フェミニズムと法概念論との対話に向けて ―N.レイシーの法理論を手がかりに―
- 著者
- 池田 弘乃
- 出版者
- 日本法哲学会
- 雑誌
- 法哲学年報 (ISSN:03872890)
- 巻号頁・発行日
- vol.2008, pp.140-147, 2009 (Released:2021-12-29)
In this essay, I shall explore the relationship between feminist legal theory and contemporary studies on the concept of law. I shall then .seek the possibility of more productive dialogue rather than mere accusation among themselves. Feminist legal theorists have fiercely criticized law's claim to neutrality or autonomy. Yet their attitudes toward law are diversified into the broad spectrum from the optimistic reformism within law to the detached pessimism over such legal reforms. I shall argue that feminist legal theory needs to tackle the studies of the concept of law to escape from the predicament caused by rigid dichotomy between legal optimism and pessimism. The main focus of my argument is the thoughts of normative legal positivism. Legal positivism is often caricatured and criticized as a formalistic approach which disguises gender biases behind purportedly value-neutrality. Its worth, however, must not be overlooked. There are the affinities for several themes such as anti-essentialism between legal positivism and feminism (at least concerning its post-modern strands). The appreciations of the affinities and differences deserve to a close research. In the course of argument, we can use the sketch of the problematics figured by feminist legal theorist Nicola Lacey, who has been committed to the tradition of English analytical jurisprudence and at the same time influenced by the deconstructive thought of Drucilla Cornell. To connect Cornell's utopian imagination to the actual institutional reform of the legal system. Lacey scrutinizes the argument of normative positivism, especially ethical legal positivism (EP) set out by Tom Campbell. EP encourages to engage in more radical social reform through democratic process rather than judicial process, although EP's antagonism toward judicial review of democratic legislation has a substantial danger for minority protection against the tyranny of majority. I try to show both EP’s advantages and dangers for feminist legal theory and construct a standpoint for further research.
2 0 0 0 OA 1885 年ザクセン財務省決定における独立企業原則による帰属する所得について
- 著者
- 加野 裕幸
- 出版者
- 関西大学大学院法学研究科院生協議会
- 雑誌
- 法学ジャーナル (ISSN:02868350)
- 巻号頁・発行日
- vol.2023, no.102, pp.1-10, 2023 (Released:2023-01-19)
- 参考文献数
- 17
本稿は、独立企業原則の出現について、1885 年1 月12 日のザクセン財務省決定について分析を行おうとするものである。今回の調査で1885 年1 月12 日のザクセン財務省決定において独立企業原則についての考え方が出現したことがHattinngh などの先行研究により判明した。その先行研究からドイツ領域内で独立企業原則がどのように形成されたのか検討しようとするものである。素材としてザクセン財務省決定について分析を行ったものである。ライヒ裁判所の判例よりも10ヶ月早く示されていることを考えると1885 年1 月12 日ザクセン財務省決定が早い段階で独立企業原則を理論的に明示していたと結論づける。録。
- 著者
- 大森 信 Makoto Omori
- 出版者
- 東京海洋大学
- 雑誌
- 東京海洋大学研究報告 (ISSN:21890951)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.40-86, 2014-02-28
On the occasion of a donation of postage stamps collected by the author to the Museum of Fishery Sciences, Tokyo University of Marine Science and Technology, a checklist of all postage stamps depicting crustaceans from 1871 through 2002 has been completed. In all, 1407 postage stamps with crustaceans have been issued from 217 countries, regions, and organizations excluding local stamps from Russia and others. The number of taxa (species or genus) that were identified in the stamps is 354. The present collection to be donated at the Museum for future reference contains 1313 original stamps including 25 old local stamps from Vessiegonsk, Russia and 114 copies of those that were unavailable to the author.
- 著者
- 油田 健太郎 山場 久昭 片山 徹郎 朴 美娘 岡崎 直宣
- 雑誌
- 情報処理学会論文誌 (ISSN:18827764)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.12, pp.2395-2405, 2015-12-15
現在,P2Pファイル共有ネットワークが世界中で利用されている.しかし,その多くはファイルの流通制御を持たないため,著作権侵害ファイルの流通やコンピュータウイルスによる個人情報の流出などが社会問題となっている.その解決策としてインデックスポイゾニングと呼ばれるファイル流通制御方式が研究されている.しかし,P2Pファイル共有ネットワークへインデックスポイゾニングを適用する際に,トラフィックの増大やインデックスの汚染などの問題が発生することが確認されている.そこで本論文では,ファイルの流通制御を低下させることなく,それらの問題を解決する手法として,P2Pファイル共有でのクラスタリングに着目して,重点的なポイゾニング機能を提案することで従来手法を改善し,その一部をWinnyネットワーク向けに実装することで,提案手法の有効性を評価する.