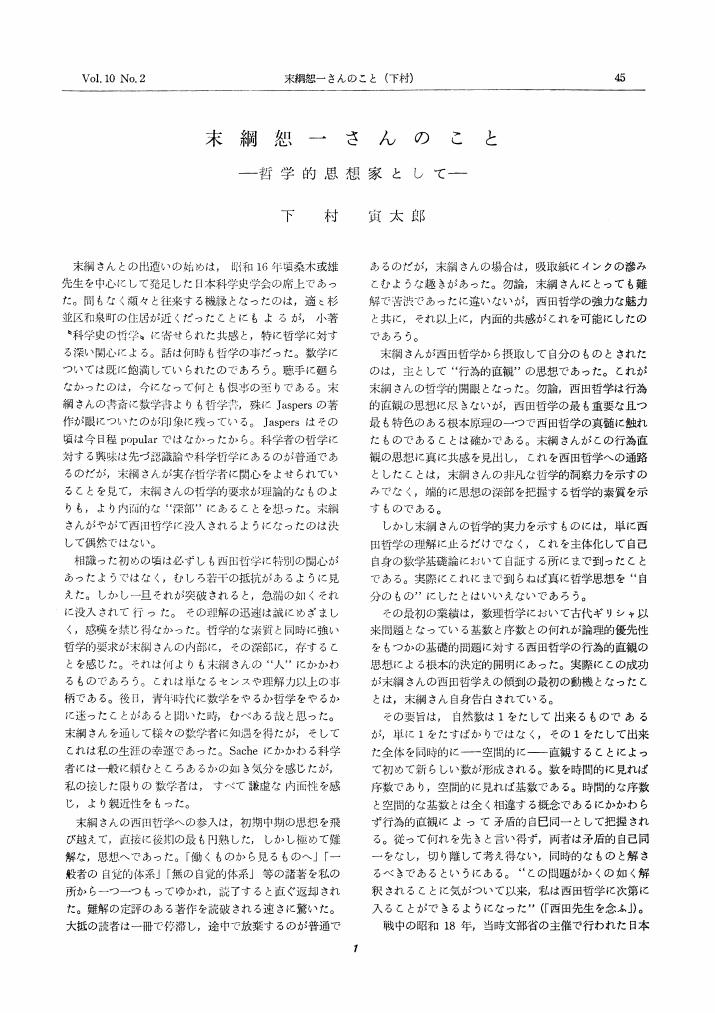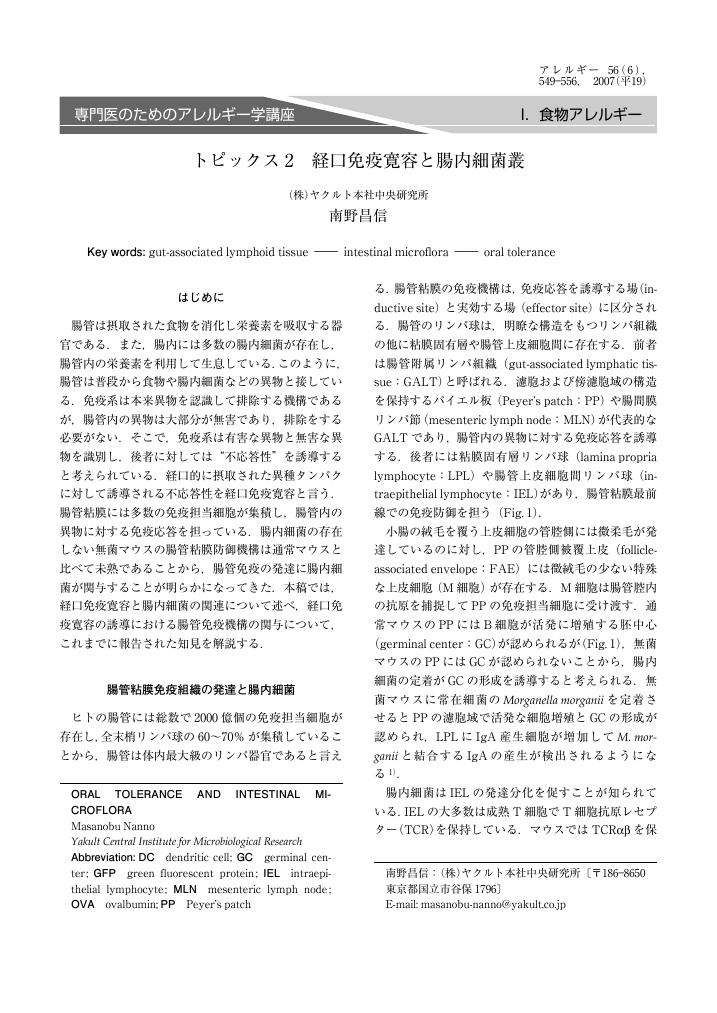2 0 0 0 OA 末綱恕一さんのこと 哲学的思想家として
- 著者
- 下村 寅太郎
- 出版者
- 科学基礎論学会
- 雑誌
- 科学基礎論研究 (ISSN:00227668)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.2, pp.45-48, 1971-03-30 (Released:2014-03-11)
2 0 0 0 OA ウイルス細胞生物学と顕微鏡法
- 著者
- 山内 洋平
- 出版者
- 公益社団法人 日本顕微鏡学会
- 雑誌
- 顕微鏡 (ISSN:13490958)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.1, pp.23-30, 2021-04-30 (Released:2021-05-12)
- 参考文献数
- 22
ウイルスは5–300 nmほどの大きさの粒子状の感染性物質で,遺伝情報(DNAかRNA)をカプシドや脂質二重膜内にカプセル化した構造体を作る.感染された細胞は文字通り乗っ取られウイルス複製工場と化す.ウイルスは自己のみでは増殖することはできず,代謝や移動を宿主側に依存している.そのため細胞の裏表を理解し尽くしており,自由自在に操ることを得意とする.実際,分子生物学の重要な発見はウイルスまたはウイルスと宿主とのせめぎ合いから創出されたものが多い.ノーベル賞を受賞した逆転写酵素やCRISPR/Casなどが良い例である.ウイルスはその均一さと電子密度の高さから光学顕微鏡,電子顕微鏡,クライオ電子顕微鏡,原子間力顕微鏡などで観察するには格好の材料である.我々の研究室はウイルスと細胞との相互作用の仕組みに関心があるため,色々な手法で観察を行ってきたので,それらの研究を中心にウイルスの顕微鏡手法を紹介したい.
2 0 0 0 OA エホバの証人信者での右室二腔症を伴ったバルサルバ洞動脈瘤破裂の1例
- 著者
- 尾形 敏郎 金子 達夫 大林 民幸 佐藤 泰史 村井 則之 垣 伸明 森下 靖雄
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本心臓血管外科学会
- 雑誌
- 日本心臓血管外科学会雑誌 (ISSN:02851474)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.5, pp.317-319, 1999-09-15 (Released:2009-04-28)
- 参考文献数
- 11
症例はエホバの証人信者の45歳の女性で, 動悸および息切れを主訴とした. 右室流出路狭窄を伴うバルサルバ洞動脈瘤破裂の診断のもとに, 手術を施行した. 術中所見からは, 右室二腔症と心室中隔欠損症を合併したバルサルバ洞動脈瘤破裂であった. 無輸血下にバルサルバ洞動脈瘤切除およびパッチ閉鎖, 異常筋束切除および右室流出路パッチ拡大, 心室中隔欠損直接閉鎖を行った. 先天性心疾患の中でバルサルバ洞動脈瘤破裂と成人の右室二腔症はおのおの頻度が少なく, 両者の合併はさらに稀である. 両者を合併したエホバの証人信者の手術症例を経験したので, 若干の文献的考察を加えて報告した.
2 0 0 0 IR 昭和8年3月3日の地震に伴った音響に就いて
- 著者
- 井上 宇胤
- 出版者
- 東京帝國大学地震研究所
- 雑誌
- 地震研究所彙報別冊 (ISSN:09150862)
- 巻号頁・発行日
- no.1, pp.77-86, 1934-03-30
昭和8年3月3日三陸地方津浪に関する論文及報告 第1編 論文
- 著者
- 井川 孝之 Takayuki IGAWA
- 出版者
- 国立社会保障・人口問題研究所
- 雑誌
- 所内研究報告 = IPSS Research Report (ISSN:21860297)
- 巻号頁・発行日
- vol.97, pp.111-153, 2021-03
研究論文
2 0 0 0 OA 都市ごみ焼却炉等から排出されるPM2.5による生徒・児童の喘息発症への影響
- 著者
- 青木 泰 西岡 政子
- 出版者
- 一般社団法人 廃棄物資源循環学会
- 雑誌
- 廃棄物資源循環学会研究発表会講演集 第25回廃棄物資源循環学会研究発表会
- 巻号頁・発行日
- pp.29, 2014 (Released:2014-12-16)
微小粒子状物質(PM2.5)は、中国の大気汚染をきっかけに世に大きく知られることになった。PM2.5は、きわめて小さく吸い込むと肺の奥まで入りやすく、肺がんやぜん息を引き起こすリスクがある。アメリカのEnvironmental Protection Agency(EPA,米環境保護庁)でも、5年に1回環境基準の見直しを行い、昨年3月、年平均15μg/m3から12μg/m3に強化した。日本でも環境省は、注意を要する暫定的な指針値を、「1日平均で1立方メートルあたり70μg」、環境基準値の2倍とした。環境基準や指針値を設け、大気中へのPM2.5の排出を抑えるためには、排出源への対策対処が不可欠である。排出源の一つである都市ごみ焼却炉への対策は、集塵装置(バグフィルター)を備えれば99・9%捕獲できるという発表(1)などもあり、知見に寄れば、具体的な対策は取られてこなかった。しかし都市ごみ焼却炉を有する市町村の清掃工場の周辺では、児童・生徒のぜん息が多発している箇所があり、都市ごみ焼却炉によるぜん息への影響を考えたい。
2 0 0 0 OA 計測制御エンジニアに求められるもの
- 著者
- 永島 晃
- 出版者
- 公益社団法人 計測自動制御学会
- 雑誌
- 計測と制御 (ISSN:04534662)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.5, pp.343-344, 2007-05-10 (Released:2009-11-26)
- 参考文献数
- 8
- 著者
- 井上 達彦 鄭 雅方 坂井 貴之 楊 稼怡
- 出版者
- 日本マーケティング学会
- 雑誌
- マーケティングジャーナル (ISSN:03897265)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.4, pp.29-41, 2022-03-31 (Released:2022-03-31)
- 参考文献数
- 21
ビジネスモデルというのは儲けの仕組みであり,その本質は「価値の創造と価値の獲得」にある。価値の創造と獲得についてはマーケティングでも早くから注目されており,価値創造については顧客との相互作用の視点,価値獲得については価格づけの視点でそれぞれ検討されてきた。しかし,価格づけにおいて「収益モデル」自体を見直すという発想には至らなかったし,価値創造と獲得の視点が統合されることもなかった。そこで本稿では,収益モデルや価値創造の方法に注目する。顧客との活発な相互作用によって価値創造をしている中国のショートムービーアプリを分析することで,価値創造と獲得の整合性と,マーケティング研究におけるビジネスモデル概念の意義を探る。
2 0 0 0 OA 元祿年間水戸藩の神社整理について-水戸藩鎮守帳の分析を中心として
- 著者
- 圭室 文雄
- 出版者
- 駿台史学会
- 雑誌
- 駿台史學 (ISSN:05625955)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, pp.96-115, 1966-03-25
2 0 0 0 OA 岡山藩の寺社整理政策について
- 著者
- 圭室 文雄
- 出版者
- 明治大学人文科学研究所
- 雑誌
- 明治大学人文科学研究所紀要 (ISSN:05433894)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, pp.363-382, 1996-12-25
2 0 0 0 OA ドゥルーズ『シネマ』における結晶的体制と非時系列的な時間について
- 著者
- 大山 載吉 オオヤマ ノリヨシ Noriyoshi Ohyama
- 雑誌
- 立教映像身体学研究 = Rikkyo review of new humanities
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.23-48, 2022
- 著者
- 宮沢 篤 駒野目 裕久
- 出版者
- 一般社団法人情報処理学会
- 雑誌
- 情報処理学会研究報告.IM, [情報メディア]
- 巻号頁・発行日
- vol.96, no.29, pp.9-16, 1996-03-15
ピンポンをもとにした、商業的に成功した初めてのアーケードゲーム「ボン」が、米アタリゲームズ社で発明されてから、既に20年以上の歳月か流れている. 当時のゲームは、汎用ロジックICを組み合わせて設計されており、技術的に見ても未発達で、最も単純な対話型コンピュータグラフィックスの一応用分野でしかなかった。それから現在までに、世界中のさまざまな会社から、その時代の最も進んだコンピュータ技術を取り入れた、非常にたくさんのゲームが発表されてきた。今日のアーケードゲームは、幾多の技術革新を経て進化してきた、全く新しいインタラクティブなメディアである、と言えるかもしれない。本稿では、ゲームマシンのハードウェアを中心に、アーケードゲームを構成するいくつかの基本的な技術について解説する。
2 0 0 0 OA Establishment of a human microbiome- and immune system-reconstituted dual-humanized mouse model
- 著者
- Yuyo KA Ryoji ITO Ryoko NOZU Kayo TOMIYAMA Masami UENO Tomoyuki OGURA Riichi TAKAHASHI
- 出版者
- Japanese Association for Laboratory Animal Science
- 雑誌
- Experimental Animals (ISSN:13411357)
- 巻号頁・発行日
- pp.23-0025, (Released:2023-04-04)
- 被引用文献数
- 1
Humanized mice are widely used to study the human immune system in vivo and investigate therapeutic targets for various human diseases. Immunodeficient NOD/Shi-scid-IL2rγnull (NOG) mice transferred with human hematopoietic stem cells are a useful model for studying human immune systems and analyzing engrafted human immune cells. The gut microbiota plays a significant role in the development and function of immune cells and the maintenance of immune homeostasis; however, there is currently no available animal model that has been reconstituted with human gut microbiota and immune systems in vivo. In this study, we established a new model of CD34+ cell-transferred humanized germ-free NOG mice using an aseptic method. Flow cytometric analysis revealed that the germ-free humanized mice exhibited a lower level of human CD3+ T cells than the SPF humanized mice. Additionally, we found that the human CD3+ T cells slightly increased after transplanting human gut microbiota into the germ-free humanized mice, suggesting that the human microbiota supports T cell proliferation or maintenance in humanized mice colonized by the gut microbiota. Consequently, the dual-humanized mice may be useful for investigating the physiological role of the gut microbiota in human immunity in vivo and for application as a new humanized mouse model in cancer immunology.
- 著者
- 南野 昌信
- 出版者
- 一般社団法人 日本アレルギー学会
- 雑誌
- アレルギー (ISSN:00214884)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.6, pp.549-556, 2007-06-30 (Released:2017-02-10)
- 参考文献数
- 22
- 被引用文献数
- 1
2 0 0 0 OA シマアザミとその近縁種の分類と分布
- 著者
- 門田 裕一
- 出版者
- 国立科学博物館
- 雑誌
- 国立科学博物館専報 (ISSN:00824755)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, pp.51-61, 1990
国立科学博物館が実施した, 「日本列島の自然史科学的総合調査」に参加して, 1990年2月に奄美大島にてアザミ属の調査を実施した。本論文では, この現地調査と標本調査の結果をもとにして, 日本列島のアザミ属の分類学的再検討の一環としつつ, 南西諸島と小笠原諸島を中心としたシマアザミ群に関する分類学的解析の結果を報告する。これまで奄美大島にはアマミシマアザミCirisium brevicaule A. GRAY var. oshimense KITAMURA (1937)が認識されてきた。アマミシマアザミは, 基本変種のシマアザミに対して, 茎と葉の背軸面脈上が有毛である点で区別されてきた。この毛は多細胞の開出毛である。奄美大島の現地調査では, (1)アマミシマアザミはほぼ全島の沿岸に普通に見出され, (2)この茎や葉の有毛性には著しい集団内変異のあることが明らかとなった。すなわち, 1つの集団においても, 茎や葉に上述の開出毛があるアマミシマアザミの形, 無毛のシマアザミの形, そして葉の背軸面の全面が有毛のイリオモテアザミの形が混在するのである。これらの3種類は, 茎や葉の有毛性以外では有意に異ならない。したがって, 茎や葉の有毛性の違いにもとづいて記載されたアマミシマアザミやイリオモテアザミはシマアザミの異名として扱うのが適当と考えられる。また, 台湾南端の鷲巒鼻<鵝鑾鼻, がらんびOluanpi>産の個体にもとづいて記載されたガランビアザミC. albescens KITAMURA (1932)もシマアザミの異名として取り扱うのが正しい。シマアザミの分布域はFig.2に示した。分布域の北限は奄美大島で, 琉球諸島や先島諸島を経て, 台湾南部に分布する。シマアザミ群には, シマアザミの他に, オガサワラアザミ, オイランアザミ, ハマアザミの3種が認められる。これらの区別点については本文中に検索表として記した。
2 0 0 0 OA 非情物の存在を表す「Vテイル」と「アル」の使い分けについて
- 著者
- 渡辺 誠治
- 出版者
- 公益社団法人 日本語教育学会
- 雑誌
- 日本語教育 (ISSN:03894037)
- 巻号頁・発行日
- vol.175, pp.88-99, 2020-04-25 (Released:2022-04-26)
- 参考文献数
- 7
非情物の存在を表す日本語の最も基本的な文の形式に「~ニ ~ガ アル」がある。しかし,現実の言語使用では「アル」の使用に制限が見られ,むしろ「V テイル」が用いられるケースが少なくない。日本語教育の観点から言えば,存在 (表現) は極めて重要な表現の一つであり,「アル」「V テイル」はともに基本的な学習項目であるが,その使い分けの条件は十分に明らかにされていない。 本稿の目的は,非情物の存在を表す「(存在場所) ニ (存在物) ガ{アル/V テイル}」という形の文における「アル」と「V テイル」の使い分けの条件を明らかにすることである。本稿では用例の分析に基づき「移動過程」「意志性」「一体性」という3つの条件が「アル」と「V テイル」の使い分けに強く関与していることを主張する。
2 0 0 0 OA 真空管時代のリーディングエッジ電子機器
- 著者
- 貞重 浩一
- 出版者
- 一般社団法人 映像情報メディア学会
- 雑誌
- 映像情報メディア学会誌 (ISSN:13426907)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.1, pp.70-75, 2001-01-20 (Released:2011-03-14)
真空管応用電子技術は, 第2次世界大戦中に, その参加諸国の国運をわけた努力によって高度成長をとげ, 1950年代にはその黄金時代に達した.半導体に比較すると誠に使用し難い回路素子であるが, 当時の技術者達は, 現在の技術水準で評価しても高度完成品と考えられる電子機器を開発した.第2次大戦の第3の新兵器といわれる近接信管と無線方位測定器を例として, 当時のリーディングエッジテクノロジーを紹介する.
2 0 0 0 OA VI.腸間膜静脈硬化症
- 著者
- 清水 誠治
- 出版者
- 日本大腸肛門病学会
- 雑誌
- 日本大腸肛門病学会雑誌 (ISSN:00471801)
- 巻号頁・発行日
- vol.74, no.10, pp.606-612, 2021 (Released:2021-11-29)
- 参考文献数
- 26
- 被引用文献数
- 1
腸間膜静脈硬化症は右側結腸を中心に慢性静脈性虚血性変化をきたすまれな疾患である.内視鏡所見では特徴的な粘膜色調変化(青銅色~暗紫色),半月ひだの肥厚がみられ,潰瘍を認めることも多い.生検では粘膜固有層の膠原線維沈着がみられる.CT所見では腸管壁内外の静脈の線状ないし樹枝状石灰化と腸管壁肥厚が特徴的である.病因として山梔子を含む漢方薬の長期服用が関与することが明らかとなった.症状は腹痛,下痢が多いが無症状例も少なくない.病変が進行し通過障害が高度になると手術が必要になる場合があり,これまでに約20%の症例で手術が施行されている.山梔子を含む漢方薬服用が確認されれば中止により病変の改善とともに手術を回避できることが多い.炎症性発癌の可能性は低いと考えられているが,今後癌の合併も注視していく必要がある.
2 0 0 0 OA 日本語における失文法―統語処理から見た障害特徴
- 著者
- 菅野 倫子
- 出版者
- 一般社団法人 日本高次脳機能障害学会
- 雑誌
- 高次脳機能研究 (旧 失語症研究) (ISSN:13484818)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.2, pp.212-220, 2013-06-30 (Released:2014-07-02)
- 参考文献数
- 27
- 被引用文献数
- 1
失文法は脳病変により生じる文法の障害である。日本語における失文法は英語などの各言語と同様に, 発話における格助詞の脱落や誤用にとどまらず, 動詞の脱落や誤用, 文構造の単純化, および多くの例で構文理解障害を呈する。我々は文の理解や発話に文法的誤りを呈した左前頭葉主病変7 例と左側頭葉主病変3 例に動詞を与えて文の発話を求め, 格助詞や項の誤りが消失するかどうかについて検討を行った。 その結果, 左側頭葉限局病変の1 例では動詞があることにより格助詞と項の誤りはすべて消失したが, 他の症例では格助詞と項の誤りは残存した。誤りが残存した症例の病変部位は, 左前頭葉主病変例では左下前頭回皮質・皮質下白質を含み, 左側頭葉主病変例では左側頭葉および頭頂葉を含む広範な領域であった。 結果より, 今回の症例では左側頭葉病変が文発話における動詞の喚語に関わること, 統語処理の過程には左前頭葉病変のみならず左側頭葉・頭頂葉病変が関わることが考えられた。