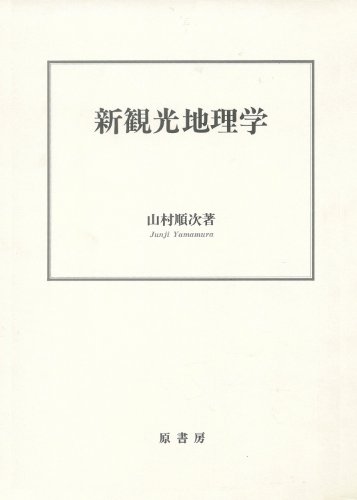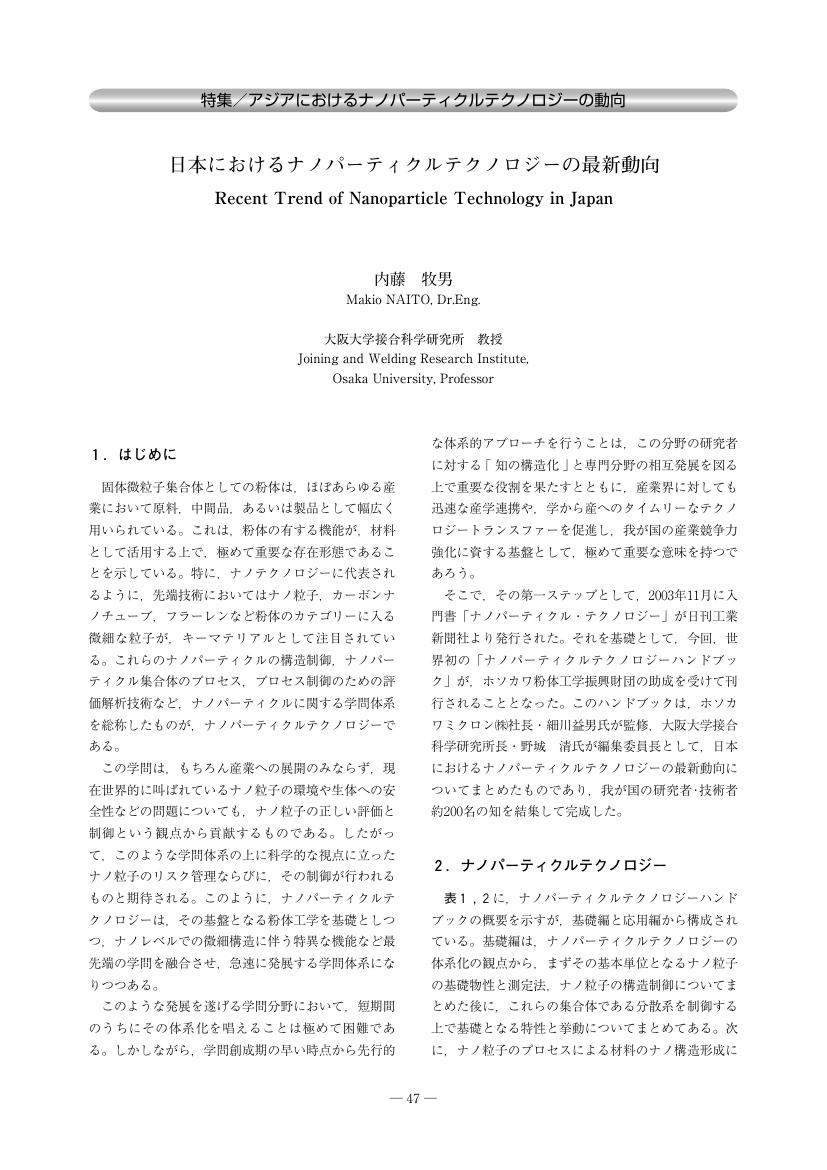2 0 0 0 OA Control of Black Spot Disease by Ultraviolet-B Irradiation in Rose (Rosa × hybrida) Production
- 著者
- Ayumu Kono Ayumu Kawabata Akira Yamazaki Yuma Ohkubo Adriano Sofo Munetaka Hosokawa
- 出版者
- The Japanese Society for Horticultural Science
- 雑誌
- The Horticulture Journal (ISSN:21890102)
- 巻号頁・発行日
- pp.QH-037, (Released:2022-11-30)
We investigated the effect of ultraviolet-B (UV-B) irradiation on the development of black spot disease caused by Diplocarpon rosae Wolf., which is a major problematic disease in rose (Rosa × hybrida) production. The growth of D. rosae colonies was suppressed on potato dextrose agar (PDA) medium under UV-B irradiation (peak wavelength: 310 nm; full width at half maximum: 30 nm) at an intensity of 15 μW·cm−2 with 1 h daily treatment. In addition, black spot conidia were inoculated to the rose ‘Danjiri Bayashi’ leaves and the effective growth suppression of black spot symptoms was observed on the leaves under UV-B irradiation. Next, various rose cultivars were planted in two greenhouses: one for supplemental UV-B irradiation treatment and one as a control without the treatment. In the UV-B irradiation greenhouse, the roses were irradiated at an intensity of 3–5 μW·cm−2 every day from 23:00–23:30 and 0:00–0:30 (total: 1 h). No chemical pesticides other than a starch agent for aphid control were used throughout the experiment. With the exception of the data for ‘Papa Meilland’ in 2019, UV-B irradiation significantly reduced the number of leaves infected with black spot disease. In September 2019, the non-UV-B irradiated ‘Danjiri Bayashi’ and ‘Papa Meilland’ had severe black spot symptoms on over 20 leaves. The number of plants with black spot symptoms increased in July 2020 compared to 2019. On the other hand, in UV-B irradiated plants, fewer black spot symptoms were observed than in non-UV-B irradiated plants. Although some visible damage was observed in the UV-B irradiated plants, the chlorophyll and carotenoid contents in the leaves decreased, indicating that UV-B irradiation had a certain negative effect on the photosynthetic apparatus. Over a five-month period, the cumulative number of flowers in the UV-B irradiation greenhouse did not decrease, and actually increased, depending on the cultivar, compared to the control treatments. Our results suggest that supplemental UV-B irradiation is effective at suppressing black spot disease in roses and can contribute to the production of pesticide-free edible rose production.
2 0 0 0 OA 算数・数学教育における問題解決学習の研究(13) ─算数の学習規範の育成に関する研究─
- 著者
- 重松 敬一 佐藤 学
- 出版者
- 奈良教育大学教育学部附属教育実践総合センター
- 雑誌
- 教育実践総合センター研究紀要 (ISSN:13476971)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, pp.61-66, 2010-03-31
本研究は、児童が主体的に取り組む算数学習のあり方を追究するため、教師と学習集団によって協定される算数の学習規範がどのように内面化するのか、児童の様相からとらえていくことを目的としている。本稿では、先行研究を基に、算数の学習規範の枠組み作成に向けた考察を試みる。その結果、低学年という発達段階では算数の学習規範も、教師という権威が強く働くことが明らかになった。その定着については、1つの方法を伝達するよりは、児童の考えをもとにした話し合いの場が設定されることが効果的であった。また、第1学年であっても、内面化し自律的な行為へと向かうに当たって、必要な、数学的価値を見出すことが可能であることも事実として、見て取ることができた。
- 著者
- 勝野 頼彦
- 巻号頁・発行日
- 2014-03
本調査研究は,平成21~25年度を研究期間として,「社会の変化の主な動向等に着目しつつ,今後求められる資質や能力を効果的に育成する観点から,将来の教育課程の編成に寄与する選択肢や基礎的な資料を得る」ことを目的に,文部科学省との関係部局との連携を図りながら進めてきた。平成24年度に刊行した報告書5で提案した将来の教育課程の基準編成の基本原理や資質・能力育成像「21世紀型能力」(試案)に対しては,大きな反響が寄せられ,その中には,本提案への学問的・理論的な根拠付けを求める声があった。このため,本報告書7は,理論的検討に実証的な事例研究を加え,本提案の背景や学問的・理論的な根拠を詳細に検討するとともに,我が国の教育課程の基準や実践の改善に向けた論点等を提案するものである。具体的には,現行学習指導要領の記述の確認,諸外国との比較(オーストラリア,ニュージーランド,フィンランド,イギリス等),学習理論及び資質・能力育成の実践例の検討を,特に資質・能力の育成可能性を高める教育内容や方法等に着目しつつ行い、それらを踏まえて論点等を検討した。
2 0 0 0 OA (特集:歴史資料の現在)史料をなぜ分類するのか 「限界リテラシー」という切り口
- 著者
- 大黒 俊二
- 出版者
- 日本西洋史学会
- 雑誌
- 西洋史学 (ISSN:03869253)
- 巻号頁・発行日
- vol.268, pp.92, 2019 (Released:2022-05-10)
2 0 0 0 OA 深層学習を利用した沿線カメラ画像による積雪深評価方法の検討
- 著者
- 阿部 雅人 杉崎 光一 中村 一樹 上石 勲
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- AI・データサイエンス論文集 (ISSN:24359262)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.J1, pp.217-220, 2020-11-11 (Released:2020-11-18)
- 参考文献数
- 15
積雪状態を評価することは,建物の屋根の雪下ろしや路上などでは除雪など路面状態の管理のために重要である.特に積雪深の評価は目視で行う以外にはレーザーなど高価なセンサを利用する必要がある.近年深層学習などの画像処理技術が向上しており,監視カメラなどの画像を利用して積雪状態を評価する検討が多く行われている.特に,沿線カメラによる路面や路肩の監視画像は,撮影場所が固定されているため位置情報は明確であり,画角の変化も比較的少ない.本研究では,監視カメラを利用した路肩にある積雪の積雪深の評価についてAI手法を適用した.
2 0 0 0 OA AI技術を活用した冬季道路路面判別の効率化
- 著者
- 李 瑾 阿部 雅人 杉崎 光一 中村 一樹 上石 勲
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- AI・データサイエンス論文集 (ISSN:24359262)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.J1, pp.210-216, 2020-11-11 (Released:2020-11-18)
- 参考文献数
- 13
近年、低頻度降雪地域では、降雪の際に、道路での車両の大規模滞留が見られる。道路管理者による異常事態の監視や路面状態の判別は、主に目視で行われているため、異常検知の効率がやや低い。本研究は、道路管理者が迅速に異常検知や処理判断をするための支援ツールとして、ドライブレコーダーの画像をもちいて、道路路面を「乾燥」、「湿潤」、「浸水・冠水」、「湿雪」、「圧雪」の 5種類へ目視分類した教師データを作成した。また、自動で路面状態を判別する AIモデルを構築し、昼と夜を合わせた 26199枚の画像で検証した結果、概ね 85%の正答率であった。
2 0 0 0 OA 農村における伝染病・寄生虫
- 出版者
- 一般社団法人 日本農村医学会
- 雑誌
- 日本農村医学会雑誌 (ISSN:04682513)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.6, pp.721-738, 1974-06-01 (Released:2011-02-17)
2 0 0 0 OA Ernst Haeckel’s mysterious species, Part II: African Chirodropida (Cnidaria, Cubomedusae)
- 著者
- Ilka Straehler-Pohl Gisèle Flodore Youbouni Ghepdeu Durane Tchatchouang Chougong François Tchoumbougnang André Carrara Morandini
- 出版者
- The Plankton Society of Japan, The Japanese Association of Benthology
- 雑誌
- Plankton and Benthos Research (ISSN:18808247)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.4, pp.406-429, 2022-11-30 (Released:2022-11-30)
- 参考文献数
- 73
Ernst Haeckel described four new chirodropid species in 1880. Chirodropus gorilla was seen only on a few occasions along the Western coasts of Africa, while Chirodropus palmatus (from St. Helena Island) was never recorded again. Type specimens of both species are lost, leading some scientists to doubt the validity of C. palmatus. New specimens assignable to C. gorilla from European and South African Museum collections shed light on the identification of both species. Among the C. gorilla samples, small mature individuals with more pedalial branches than in the larger specimens were discovered. Further observations on living specimens of the smaller chirodropid from Cameroon suggested that they must be C. palmatus because there were only two chirodropid species described from West African waters; comparison with Haeckel’s descriptions and drawings confirmed the identification. Additionally, our data showed that Chirodropus palmatus must be classified into the family Chiropsalmidae and accommodated in its own genus, Chimaerus gen. nov. We also revised definitions of the families Chirodropidae and Chiropsalmidae and re-described both species.
2 0 0 0 OA 日本におけるナノパーティクルテクノロジーの最新動向
- 著者
- 内藤 牧男
- 出版者
- ホソカワミクロン株式会社
- 雑誌
- 粉砕 (ISSN:04299051)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, pp.47-51, 2006-10-30 (Released:2018-10-03)
2 0 0 0 OA 多可郡誌
- 著者
- 兵庫県多可郡教育会 編
- 出版者
- 兵庫県多可郡教育会
- 巻号頁・発行日
- 1923
- 著者
- 栗岡 幹英
- 出版者
- 関西社会学会
- 雑誌
- フォーラム現代社会学 (ISSN:13474057)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, pp.141-143, 2017 (Released:2018-06-13)
- 著者
- 野村 岳志
- 出版者
- 日本臨床麻酔学会
- 雑誌
- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.4, pp.612-618, 2013 (Released:2013-09-13)
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 1
腹直筋鞘ブロック,腹横筋膜面ブロック,傍脊椎ブロックは胸壁,腹壁の体性痛管理に用いられている.特に超音波ガイド法の普及によって安定した効果発現と合併症の低下を認め,近年広く普及してきた.硬膜外ブロックに比べて鎮痛作用は劣るものの創痛管理中の副作用は少ない.最近推奨されている多様性(multimodal)疼痛管理の一法として,これらのブロックを併用すると,早期離床に向けた優れた術後痛管理が可能となる.しかし,比較的簡便な手技とはいえ,コンパートメントブロックのため局所麻酔薬の1回投与量は多い.異所投与では効果不十分で,局所麻酔薬中毒の可能性のみ高くなる.より安定した手技となるよう解剖学的構造や超音波画像の理解が重要である.
2 0 0 0 OA 網膜疾患治療の現状とアミロイドβの関与
- 著者
- 嶋澤 雅光 原 英彰
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬理学会
- 雑誌
- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)
- 巻号頁・発行日
- vol.134, no.6, pp.309-314, 2009 (Released:2009-12-14)
- 参考文献数
- 49
我が国の中途失明疾患には,緑内障,糖尿病網膜症,加齢黄斑変性症(age-related macular degeneration:AMD)および網膜色素変性症などがある.これらの失明性疾患の多くは網膜細胞の変性に起因することが知られている.しかしながら,それらの病態の機序については十分には解明されていない.一方,最近これらの眼疾患の一部とアルツハイマー病(Alzheimer disease:AD)との関連が指摘されている.すなわち,AD患者において網膜機能の低下,網膜神経節細胞の減少および視神経変性が高率に認められている.さらに,AD患者における緑内障の発症率が高いことが明らかにされた.ADは認知機能の低下,人格の変化を主な症状とする認知症の一種であり,その発症には脳内のアミロイドβペプチド(Aβ)の凝集・蓄積が引き金となり,神経細胞の変性・脱落が惹起されると考えられている(アミロイド仮説).現在,本仮説に基づいてAD患者の脳内におけるAβの産生または蓄積を抑える様々な治療法が試みられている.最近,我々は緑内障および糖尿病網膜症患者の硝子体液中のAβ1-42の著明な低下およびタウタンパクの上昇を見出した.これらの変化はAD患者脳脊髄液中の変動と類似していた.また,AMDにおける唯一の前駆病変と考えられるドルーゼン中の構成成分としてAβが高頻度に存在することが報告された.これらの知見はこれらの網膜疾患とADの間に共通の病態発症機序が存在し,とくにAβが網膜疾患の病態に深く関わっている可能性を示唆している.本稿では網膜疾患のなかでADとの関連がとくに示唆されている緑内障および加齢黄斑変性症について,治療の現状とその病態の発症におけるAβの関与並びにアミロイド仮説に基づいた治療の可能性について概説する.
2 0 0 0 OA ラフカデイオ・ハ-ン作品における霊の表象について
- 著者
- 茶谷 丹午 CHATANI Tango
- 出版者
- 金沢大学大学院人間社会環境研究科
- 雑誌
- 人間社会環境研究 = Human and socio-environmental studies (ISSN:18815545)
- 巻号頁・発行日
- no.34, pp.1-11, 2017-09-29
本稿ではラフカデイオ・ハー ンにおける二つの文学的表象, 青空と霊を取り上げる。 これらは彼の紀行文や幽霊物語だけでなく, 思弁的な内容のエッセイにも現れるものである。 彼はこの二つの表象を用いて, 人間における個人性を否定する議論を展開する。 ハー ンは言う。 人間のうちには無数の死者すなわち霊が存在しており, 人間とはいわば集合体である。 また人間にとって,青空をみて憧れ, 自分が青空に融け入り. いまある個人的な自己を失うことを願うのは, 賢明であり合理的である、と。しかしその一方で彼は、他者との倫理的関係を結ぽうとする主体としての「私」を認めているようでもある。 ハー ンのエッセイは夢想的であり晦渋でもあるけれども,その目指すところはおそらく人間存在の二面性の把握にあるのであり その点で彼は和辻哲郎の立場に近いように思われる。 そこで試みに和辻倫理学を補助線として用いて, 幽霊の登場する作品の一つである『人形の墓』を分析し、そこからハーンの哲学的議論における霊と、文芸作品における霊との連続性を考察する。
2 0 0 0 OA 青森港と函館港における北洋漁業の歴史的意義 : 青函圏における港湾の産業経営史的研究
- 著者
- 四宮 俊之
- 出版者
- 弘前大学人文学部経済学科特定研究事務局
- 巻号頁・発行日
- pp.43-62, 1992-03-19
- 著者
- 中澤 高志
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 地理学評論 Series A (ISSN:18834388)
- 巻号頁・発行日
- vol.88, no.1, pp.49-70, 2015-01-01 (Released:2019-10-05)
- 参考文献数
- 32
本稿では,高度成長期の勝山産地において,「集団就職」が導入され終焉に至るまでの経緯を分析する.進学率の上昇や大都市との競合により,労働力不足に直面した勝山産地の機屋は,新規中卒女性の調達範囲を広域化させ,1960年代に入ると産炭地や縁辺地域から「集団就職者」を受け入れ始める.勝山産地の機屋は,自治体や職業安定所とも協力しながらさまざまな手段を講じ,「集団就職者」の確保に努めた.「集団就職者」の出身家族の家計は概して厳しく,それが移動のプッシュ要因であった.勝山産地の機屋が就職先として選択された背景としては,採用を通じて信頼関係が構築されていたことが重要である.数年すると出身地に帰還する人も多かったとはいえ,結婚を契機として勝山産地に定着した「集団就職者」もいたのである.高度成長期における勝山産地の新規学卒労働市場は,国,県,産地といった重層的な空間スケールにおける制度の下で,社会的に調整されていた.
- 著者
- Daisuke NISHIO–HAMANE Koichi MOMMA Masayuki OHNISHI Sachio INABA
- 出版者
- Japan Association of Mineralogical Sciences
- 雑誌
- Journal of Mineralogical and Petrological Sciences (ISSN:13456296)
- 巻号頁・発行日
- vol.117, no.1, pp.220728, 2022 (Released:2022-11-29)
- 参考文献数
- 24
- 被引用文献数
- 1
Oxyyttrobetafite–(Y) is the first member in the betafite group of the pyrochlore supergroup found in albite–rich pegmatite from Souri Valley, Komono, Mie Prefecture, Japan. This new mineral occurs as small anhedral grains with sizes of 20 to 200 µm in cylinder–shaped aggregates with a substrate of thalénite–(Y) and synchysite–(Y). Small amounts of aeschynite–(Y), thorianite, and thorite are also associated in the same occurrence with oxyyttrobetafite–(Y), and gadolinite–(Y) is also included at the boundary between the aggregate and albite. The physical properties are: brown in color, brittle, transparent, non–fluorescent, vitreous luster, white streak with a Mohs hardness of 5, and a calculated density of 5.54 g·cm−3. Oxyyttrobetafite–(Y) is an optically isometric material with brown color under the microscope with a refractive index of n = 2.3 calculated using the Gladstone–Dale relationship. The empirical formula of oxyyttrobetafite–(Y) calculated on the basis of B = 2 with A2B2X6Y composition is (Y1.58Dy0.13Yb0.07Er0.06Tm0.05Gd0.04Ho0.03Sm0.02Tb0.02Eu0.01Lu0.01)Σ2.02(Ti1.85Ta0.09Fe0.05Sn0.02Nb<0.01)Σ2O7.05 and leads to the ideal formula of Y2Ti2O6O, which requires TiO2 41.44 wt% and Y2O3 58.56 wt%, total 100 wt%. The structure is isometric cubic with the space group Fd3m and unit cell parameters of a = 10.11090(10) Å, V = 1033.64(3) Å3, and Z = 8 by single crystal X–ray diffraction measurements. The seven strongest peaks in the powder X–ray diffraction pattern [d in Å (I/I0) hkl ] were 2.918(100) 222, 2.527(18) 400, 2.321(13) 331, 1.788(53) 440, 1.525(46) 622, 1.162(13) 662, and 1.033(9) 844 with unit cell parameters of a = 10.121(3) Å, V = 1036.6(9) Å3, and Z = 8. The crystal structure was refined to R1 = 0.018 for 159 observed reflections with the criteria of I > 2σ (I ). Oxyyttrobetafite–(Y) is characterized by Y dominance at the A sites, Ti dominance at the B sites, and O dominance at the X and Y sites in the A2B2X6Y pyrochlore–type formula.