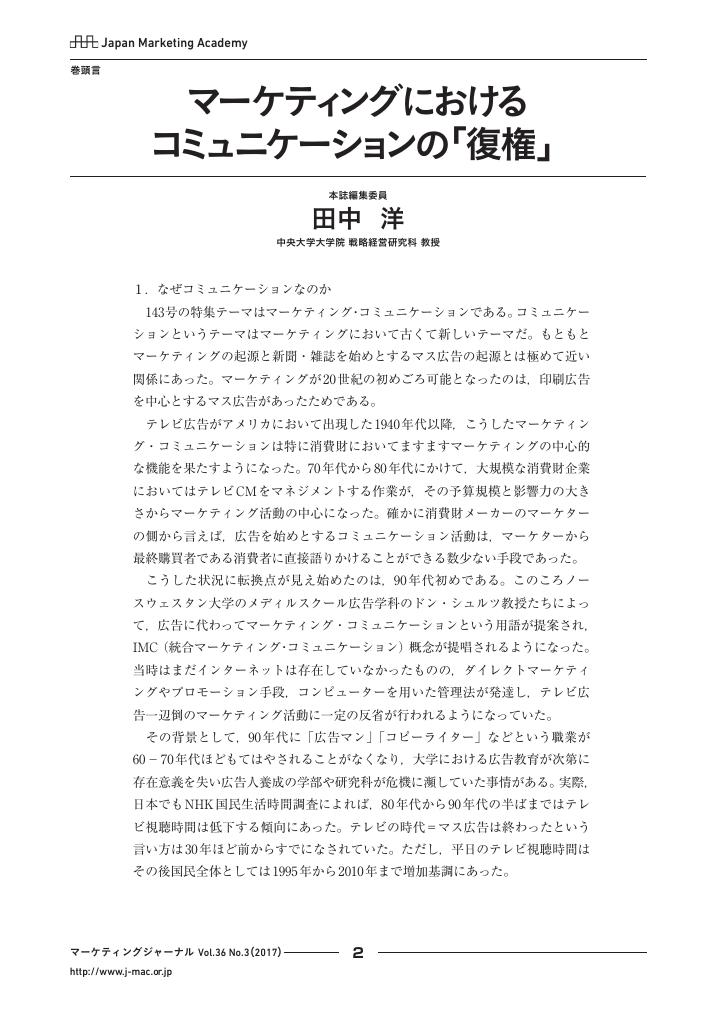2 0 0 0 OA 食飼料素材中の有害物質
- 著者
- 葛西 隆則
- 出版者
- 日本農薬学会
- 雑誌
- Journal of Pesticide Science (ISSN:1348589X)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.2, pp.S61-S68, 1993-05-20 (Released:2010-08-05)
- 参考文献数
- 15
2 0 0 0 IR 刑事訴訟手続きにおける人権保障の日米比較
- 著者
- 梅山 香代子
- 出版者
- 東洋学園大学
- 雑誌
- 東洋学園大学紀要 (ISSN:09196110)
- 巻号頁・発行日
- no.10, pp.125-136, 2002-03
2 0 0 0 OA 医療デバイスの進歩~糖尿病治療用注射製剤のペン型注入デバイスの変遷と療養指導の関係~
- 著者
- 朝倉 俊成
- 出版者
- 日本DDS学会
- 雑誌
- Drug Delivery System (ISSN:09135006)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.5, pp.408-422, 2016-12-25 (Released:2017-02-25)
- 参考文献数
- 28
- 被引用文献数
- 2 1
日常生活において厳格に血糖をコントロールするために、インスリン療法の基本として、生理的インスリン分泌に近いbasal-bolus療法が行われている。インスリン療法には頻回インスリン療法(MDI)と持続皮下インスリン注入療法(CSII)があり、MDIではペン型注入デバイス、CSIIではポンプ式注入デバイスによって行われる。インスリンを皮下に適正に注入するには高精度で高品質な注入デバイスが必要で、同時に患者にとって操作性や認知性、快適性、そして信頼性などが得られるものでなければならない。注入デバイスの開発は、長い期間と段階を経てこれらの項目について改良が加えられてきたが、今後は患者の手技においてもより適正性が確保できるような補助機能の追加や今まで以上の携帯性の向上、患者個々の糖尿病療養生活の細部に対応したプログラム機能を有するなど、「個」に対応可能なデバイスの開発が期待される。
2 0 0 0 OA 夜間実業教育
- 著者
- 文部省実業学務局 編
- 出版者
- 全国夜間実業学校聯合会
- 巻号頁・発行日
- 1935
- 著者
- 村田 志保
- 雑誌
- 人間文化研究 (ISSN:13480308)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, pp.119-133, 2012-12-21
「お忙しいですね。」「お元気ですか。」など、ごく自然に会話のなかで使われる。これらは形容詞の敬語表現であり使用頻度も高いのだが、日本語教育において、形容詞の敬語教育を体系的に導入している教材は数少ない。また「お/ご」の選択に関しても、「お」は和語で「ご」は漢語であるといった語種による判別しか今のところ基準はないので、その基準を導入せざるを得ない。しかし実際には語種だけでは判別しにくい、「?おおもしろい」「?おシンプルな」「?ご危険な」というような、「お/ご」の付きにくい例もある。本稿では初級教材で扱われている形容詞を抽出した約150語を初級形容詞とし形容詞の意味的な側面、そして文法的な側面より「敬語としての形容詞分類」、「形容詞の敬語表現」、「「お/ご」の付加」の3点を軸に考察を進め、2つの考察結果が得られた。「(お/ご)~ て/でいらっしゃる」は「?社長のおかばんは大きくていらっしゃる。」のように、高めようとする人を主語にはせず、「もの」のときには「お/ご~ です」を選択する傾向が強いことがわかった。また「お/ご」は初級形容詞の範囲では「外来語」「「お」で始まる語」には付かず、その他の条件である「モーラ数の多い語」「悪感情を持つ語」「ある意味の語」はあくまで付かない傾向にあるというに留まり、条件として提示するには例外も多いことがわかった。
2 0 0 0 OA 酔っ払いの戯れ ―Mattavilāsa 和訳―
- 著者
- 堀田 和義
- 出版者
- 大谷大学佛教学会
- 雑誌
- 佛教学セミナー = BUDDHIST SEMINAR (ISSN:02871556)
- 巻号頁・発行日
- no.110, pp.1-32, 2019-12-30
2 0 0 0 ブランド・メモリーズ:ブランド記憶メカニズムの探索的研究
- 著者
- 田中 洋 丸岡 吉人
- 出版者
- 日本消費者行動研究学会
- 雑誌
- 消費者行動研究 (ISSN:13469851)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.2, pp.23-36, 1995
- 著者
- 久井 貴世
- 出版者
- 公益財団法人 山階鳥類研究所
- 雑誌
- 山階鳥類学雑誌 (ISSN:13485032)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.1, pp.9-38, 2013
- 被引用文献数
- 1
江戸時代に著された史料を用いた調査に基づき,江戸時代の史料に記載されたツル類の名称のうち,タンチョウ<i>Grus japonensis</i>に関連する六つの名称について整理と再考察を行った。江戸時代の日本では,当時の西洋や現代とは異なる独自の分類体系が有効に機能していたが,史料中では多様なツルの名称が用いられていた。記載された名称と種の対応は著者や時代によっても解釈が異なり,史料によって齟齬が生じることが明らかとなった。さらに,一般名と一致しない地方名も存在し,地域による定義の違いも確認できる。本草学的には「鶴」の代表はタンチョウである場合が多いが,地域によってはマナヅル<i>G. vipio</i>やソデグロヅル<i>G. leucogeranus</i>を表わす場合があった。「丹鳥」は現在では単線的にタンチョウと結びつけられているが,史料によって多様な解釈がみられ,明確な種の特定にはいたらなかった。「白鶴」はほとんどの場合ソデグロヅルを指すが,地域によってはタンチョウを表わす場合もあった。「琉球鶴」は特定の一種を指す名称ではなく,琉球を経て日本へもたらされた外国のツルの総称であると推測できる。「朝鮮鶴」はタンチョウを指す事例が確認できたが,朝鮮に由来するツルの総称として用いられていた可能性が高い。江戸時代の名称を現代の種に対応させる際には,史料による同定の不一致や地域による定義の差異などに留意する必要がある。
2 0 0 0 OA マーケティングにおけるコミュニケーションの「復権」
- 著者
- 田中 洋
- 出版者
- 日本マーケティング学会
- 雑誌
- マーケティングジャーナル (ISSN:03897265)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.3, pp.2-5, 2017-01-10 (Released:2020-03-31)
- 参考文献数
- 3
2 0 0 0 IR 研究業績とは何(であるべき)か?
- 著者
- 佐倉 統
- 出版者
- 東京大学大学院情報学環
- 雑誌
- 情報学研究 : 学環 : 東京大学大学院情報学環紀要 (ISSN:1880697X)
- 巻号頁・発行日
- no.100, pp.1-18, 2021-03-31
教員研究論文
- 著者
- Eri Kamon Chihiro Noda Takumi Higaki Taku Demura Misato Ohtani
- 出版者
- Japanese Society for Plant Biotechnology
- 雑誌
- Plant Biotechnology (ISSN:13424580)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.3, pp.331-337, 2021-09-25 (Released:2021-09-25)
- 参考文献数
- 52
- 被引用文献数
- 4
Secondary cell walls (SCWs) accumulate in specific cell types of vascular plants, notably xylem vessel cells. Previous work has shown that calcium ions (Ca2+) participate in xylem vessel cell differentiation, but whether they function in SCW deposition remains unclear. In this study, we examined the role of Ca2+ in SCW deposition during xylem vessel cell differentiation using Arabidopsis thaliana suspension-cultured cells carrying the VND7-inducible system, in which VND7 activity can be post-translationally upregulated to induce transdifferentiation into protoxylem-type vessel cells. We observed that extracellular Ca2+ concentration was a crucial determinant of differentiation, although it did not have consistent effects on the transcription of VND7-downstream genes as a whole. Increasing the Ca2+ concentration reduced differentiation but the cells could generate the spiral patterning of SCWs. Exposure to a calcium-channel inhibitor partly restored differentiation but resulted in abnormal branched and net-like SCW patterning. These data suggest that Ca2+ signaling participates in xylem vessel cell differentiation via post-transcriptional regulation of VND7-downstream events, such as patterning of SCW deposition.
2 0 0 0 OA 南海トラフ地震の評価に時間予測モデルを適用することに妥当性はあるか?
- 著者
- 橋本 学
- 雑誌
- JpGU-AGU Joint Meeting 2020
- 巻号頁・発行日
- 2020-03-13
地震調査委員会は,南海トラフにおいて今後30年間にM8〜9クラスの地震発生確率が70〜80%(2019年時点)と評価している.最近,地震発生確率が「水増し」された,との報道があった.筆者は,2011年からの南海トラフ地震の長期評価に分科会委員として関わった.その中で,さまざまな点,特に時間予測モデルを用いた確率評価について問題点を指摘した.この評価に関する問題点をまとめておく必要性を感じたので報告する. 南海トラフの長期評価は第1版が2001年に公表された[地震調査委員会,2001].M8クラスの東南海・南海地震,連動すれば最大M8.7の地震が,今後30年間に60〜70%の確率で発生すると評価された.確率の計算には,Shimazaki and Nakata(1980)による時間予測モデルが採用された.東日本大震災を受けて,この評価が見直され,2013年に第2版が公表された.最大地震規模はM9.1になり,個別の地震に対する評価はなく,多様性が強調された.しかし,地震発生確率の評価においては,2001年と同じく時間予測モデルを採用した.ただし,第2版において,時間予測モデルによる確率評価に使用されたデータは,室津港のデータのみである.すなわち,宝永1.8 m,安政1.2 m,昭和1.15 mの隆起量である.そして,これらの数値を時間予測モデルに当てはめて,昭和の地震から次の地震までの発生間隔(88.2年)を推定している.この値を用いて計算をすると,標記の確率が算出される. 計算の元になった室津港のデータは,宝永・安政については今村(1930),昭和については沢村(1953)が原典である.今村(1930)は,地元に残る古文書の記載から,安政の地震では約4尺海面が低下したことと,宝永地震から52年後の宝暦9年(1759年)までの間に約5尺の変動があったことを発見した.Shimazaki and Nakata (1980)は,室津周辺の水準測量から推定されている沈降率(5〜7 mm/年)を用いて補正し,宝永地震直後の変動としている.一方,沢村(1953)のデータは,旧汀線の高度の実測である. ところが,再来間隔の計算では測定誤差を一切考慮していない.宝永と安政の地震については,(1)計測方法や地点に関する情報がないため,計測誤差の評価ができない,(2)計測日時の記載がないため,月齢による潮位変動を見積もることができない,(3)波浪等気象・海象に関する記載もない,等の問題点がある.また,宝永の地震については,地震発生から計測時までの約50年間の変動の補正において,余効変動を考慮していない.一方,沢村(1953)の昭和の地震のデータも,水準測量と同程度の精度があるとは考えられないので,大きな誤差が伴うと考えるのが妥当である.試みに昭和の隆起量に10cm,安政と宝永に30 cmのランダムな誤差を加えて計算すると,次の地震発生は2020年代から2050年代まで大きくばらつく.このばらつきを考慮すると,確率はもっと低くなるであろう. 時間予測モデルによる再来間隔の推定には,平均隆起速度が重要で,室津港のデータに対しては13 mm/年となる.Shimazaki and Nakata (1980)では,これが応力蓄積速度に対応するものと考えられている.一方,弾性反発説に従えば,地震間の応力蓄積速度は室戸岬周辺の水準測量や験潮による沈降速度に比例する.しかし,これは前述のように5〜7 mm/年であり,平均隆起速度と大きな差がある.室戸岬周辺の地震時隆起には,弾性反発による隆起と残留隆起(=塑性変形)が含まれる.弾性変形は5〜7 mm/年の沈降速度に等しいと考えられるので,これを除いた量が塑性変形となる.余効変動を無視すると,宝永地震では最大約0.7 m,安政地震は約0.6 mの残留隆起があることになる.前杢(2001)の室戸岬周辺のヤッコカンザシの化石群体データからは,1,000年以内に1m以上の隆起は確認できない.また,塑性の力学に従うと,降伏応力を超えると変形と応力の比例関係は崩れるので,単純に残留隆起と地震の規模等との比を取ることは適切でない. 第2版の議論では,Scholz(1990)の時間予測モデルに否定的な研究なども取り上げられた.さらに,南海トラフ全体をひとまとめにして扱うことにしたので,第1版と同じ考え方で時間予測モデルを適用するのはおかしい,という指摘もあった. これらの批判的な議論が大勢を占め,分科会は時間予測モデルの採用に反対した.そして,他の海溝型地震や活断層の評価と同様に,再来間隔の平均値を用いた確率評価を使うべきであると結論した.この場合,確率は大きく低下する.このため,その後の地震調査委員会と政策委員会関係者の会議において,時間予測モデルの結果を採用する方針が決まった.筆者は,科学者と防災政策関係者との会議で,このような判断をしたことを批判するものではない.南海トラフの地震サイクルについての科学的知見が十分でなく,実際に90年で再来した事実がある以上,防災政策面からの議論が優先しても致し方ない,と考える.しかし,報告書にはこの経緯が記載されていない.筆者はこの経緯の記載を強く主張したが,受け入れられなかった.結果的に,あたかも科学的な判断のみで結論されたと見做される状況を招いてしまった.このことこそ,批判されるべきである.
2 0 0 0 OA 未踏分子ナノカーボンの創製
2 0 0 0 OA 熟練訪問看護者の意思決定の構造 : 在宅療養者の自己決定への支援
- 著者
- 松村 ちづか 川越 博美
- 出版者
- 一般社団法人 日本地域看護学会
- 雑誌
- 日本地域看護学会誌 (ISSN:13469657)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.1, pp.19-25, 2001-03-01 (Released:2017-04-20)
本研究の目的は,在宅療養者の自己決定と家族の意向が不一致な状況において,熟練訪問看護者がその不一致を解決し,療養者の自己決定を実現するためにどのような意思決定をしているのか,構成要素および構造を明確にし,療養者の自己決定を支えるための訪問看護者の意思決定のあり方の示唆を得ることである.対象は5名の熟練訪問看護者で,継続的な家庭訪問での参加観察とインタビューを用いた質的記述研究を行った.その結果,熟練訪問看護者が認識した療養者の自己決定と家族の意向が不一致である内容としては,療養者の日常のケア,治療,生き方に関するものがあった.また,不一致の根底にある療養者と家族の関係性として,家族が療養者を大切に思うがゆえに不一致が生じているものと過去からの関係性の困難さから不一致が生じているものがあった.熟練訪問看護者の意思決定の構成要素として,訪問看護者としてのあり方を意味する2コアカテゴリー【訪問看護者としての生き方】【個人としての生き方】,意思決定のプロセスを意味する10コアカテゴリー【役割認識をもつこと】【了解すること】【自己関与させること】【自己と対話すること】【支援目標をもつこと】【見通すこと】【決断すること】【働きかけのタイミングを掴むこと】【働きかけ方の選定をすること】【支援について省みること】が抽出された.これらのコアカテゴリーを各熟練訪問看護者の意思決定の経時的プロセスに当てはめてみた結果,熟練訪問看護者の意思決定の全体を構造化することができた.以上の結果から,訪問看護者が在宅療養者の自己決定と家族の意向が不一致な状況を解決し療養者の自己決定を支えるためには,療養者と家族が共に納得できるような方向性の家族ケアを提供する必要性が示唆された.そして,訪問看護者の意思決定のあり方として,療養者の自己決定する権利を認識し,療養者の心身の利益の優先という倫理的,かつ自己のあり方を問う自律的な意思決定をしていく重要性が示唆された.
2 0 0 0 OA 昭和恐慌後における佐々木要右衛門家事業の展開 -広島県備後織物業史の研究-
- 著者
- 山崎 広明
- 出版者
- 経営史学会
- 雑誌
- 経営史学 (ISSN:03869113)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.2, pp.3-26,95, 2006-09-25 (Released:2009-11-06)
The purpose of this article is to analyze the development of entrepreneurial activities of the Youemon Sasaki family at Shin'ichi in Bingo region which is located in the eastern part of Hiroshima Prefecture during the period after the Showa panic (1930-31) until the wartime (July, 1937-August, 1945). The author utilized such various materials as the oral history, the printed matters and the Sasaki archives to accomplish the above purpose.Youemon Sasaki, successful local wholesale merchant, were seriously hit by the Showa panic, and thereafter, the restructuring by the young leader, Gi'ichi Sasaki, became unavoidable. Gi'ichi closed the weaving factories established in 1915, began sewing business, came to sell new commodities such as wide cloths and garments to the local areas and continued seeking such gains as dividends and rents of land and houses.At the wartime Gi'ichi greatly committed himself to sewing business and kept the wealthy local businessman by becoming a salaried manager in Bingo Tokumen Kasuri Moto Haikyu Kabusiki Kaisha (Bingo Kasuri Distribution Company) and Huhaku Seihin Chuo Seizo Haikyu Tosei Kabushiki Kaisha (Cloth Goods Central Manufacturing Distribution Company). He also earned lots of money through dividends of shares during wartime.In recent years many economic and business historians in Japan are making great efforts to describe the local entrepreneurial activities in the prewar years, and this article is also included in such an academic trend.
2 0 0 0 OA 犯罪事件報道におけるメディア・フレーミングについて : 交通事犯を取り上げて
- 著者
- 松嶋 祐子
- 出版者
- 専修大学人間科学学会
- 雑誌
- 専修人間科学論集. 心理学篇 (ISSN:21858276)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, pp.1-9, 2021-03-15
犯罪報道については,古くから事前に事件についての情報を知ることで,公判前に特定の印象形成をさせるのではないかとの問題視がある。メディア研究では,メディア報道の在り方が議論の争点づけを行うことをメディア・フレームという。本稿では,新聞による犯罪報道が事件により取り上げられ方が異なっていないかどうか,交通事犯を報じた記事を取り上げて検討した。東池袋自動車暴走事故と,神戸市バス事故を報じられ方(掲載件数,時期,新聞記事のテーマなど)から比較を行った。その結果,事故自体については新聞は淡々と報じていることが読み取れたが,東池袋自動車暴走事故については,高齢者の運転の安全性への疑問,特に自動車運転免許返納の議論へと発展しており,メディアでの露出度が高いことがわかった。
本論文では,パソコンを利用した作業時のキー入力を身体動作で置き換えることにより,運動不足を解消するシステム,DeskWalkを提案する.長時間の座位作業は健康に悪影響がある.歩行や立ち上がりを行うことでその影響を低減できるが,これらは作業の中断をともなう.DeskWalkは下肢に取り付けたストレッチセンサで歩行と同等に筋肉が動く動作を認識し,それらの対象動作にあらかじめ割り当てたキーの入力を行う.これにより,ユーザは座位作業を続けながら運動ができる.さらに,日常生活での運動を記録しておき,座位作業時にDeskWalkを用いて不足分の運動を補わせるアプリケーションを提案,実装した.評価実験の結果,DeskWalkは対象動作を平均F値0.98と高精度に認識できた.システム使用時は未使用時と比較して2割から3割程度入力速度が減少したが,通常のパソコン作業において問題のない速度で入力ができていた.
2 0 0 0 星条旗はためく下で : 米比戦争における残虐行為と聖戦意識
- 著者
- 大井 浩二
- 出版者
- アジア系アメリカ文学研究会
- 雑誌
- AALA journal (ISSN:13408496)
- 巻号頁・発行日
- no.19, pp.31-41, 2013
2 0 0 0 OA 学制の主導者的研究 : 特に洋行/洋学者
- 著者
- 原田 忠四郎
- 出版者
- 日本体育大学
- 雑誌
- 日本体育大学紀要 (ISSN:02850613)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, pp.87-101, 1973-06-10