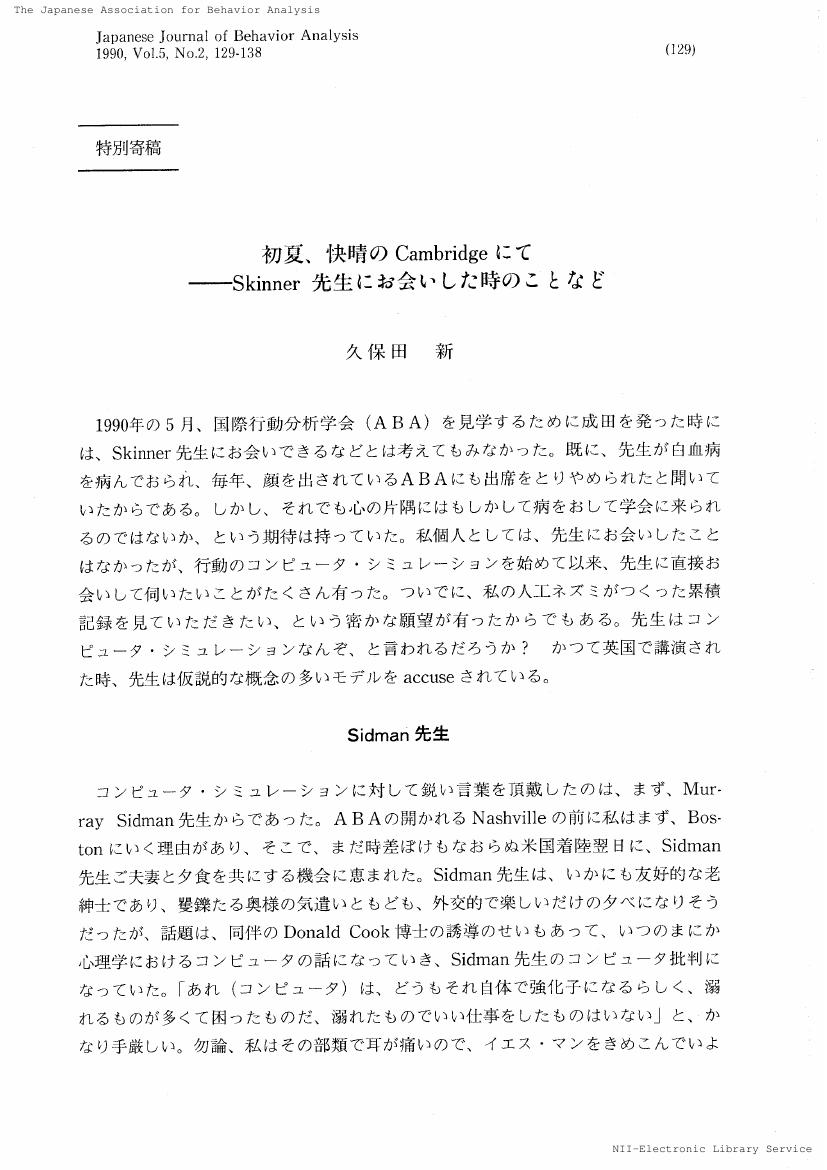8 0 0 0 OA 椎間板性腰痛の慢性化機序に関する考察
- 著者
- 宮城 正行 内田 健太郎 中脇 充章 川久保 歩 井上 玄 高相 晶士
- 出版者
- 一般社団法人 日本脊椎脊髄病学会
- 雑誌
- Journal of Spine Research (ISSN:18847137)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.6, pp.878-882, 2020-06-20 (Released:2020-06-20)
- 参考文献数
- 19
椎間板は非特異的腰痛の一因となる.腰痛のほとんどは自然に改善するが,臨床上問題となるのは腰痛が慢性化する病態である.腰痛の慢性化の機序については,急性腰痛が遷延化した病態と,持続的にトリガーとなる損傷が繰り返し起こる病態の可能性がある.これらの病態に,椎間板内への神経伸長,椎間板内に発現する炎症性サイトカインや神経成長因子といった疼痛関連物質とその発現に関与するマクロファージ,椎間板に持続的に加わるメカニカルストレスが関与している可能性がある.
8 0 0 0 IR 五代友厚の欧行と、彼の滞欧手記『廻国日記』について
- 著者
- 大久保 利謙
- 出版者
- 立教大学
- 雑誌
- 史苑 (ISSN:03869318)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.2, pp.20-41, 1962-01
- 被引用文献数
- 1
8 0 0 0 OA 水戸市中心部におけるマンション購入世帯の現住地選択に関する意思決定過程
- 著者
- 久保 倫子
- 出版者
- The Association of Japanese Geographers
- 雑誌
- 地理学評論 (ISSN:13479555)
- 巻号頁・発行日
- vol.81, no.2, pp.45-59, 2008-02-01 (Released:2010-03-12)
- 参考文献数
- 32
- 被引用文献数
- 4 3
本研究は, 水戸市中心部に立地するマンションに居住している世帯の現住地選択に関する意思決定過程の分析を行った. 水戸市中心部におけるマンション居住者の多くは, 周辺地域からの住み替え世帯であり, 核家族世帯や中高年夫婦世帯が多い傾向がある. マンションの選択は, 水戸市中心部への選好と密接に結びついている. つまり, マンション自体への評価と水戸市中心部への志向によって中心部のマンション需要が生まれている. マンションが評価されているのは, 将来的な賃貸や売買のしやすさ, 戸建住宅や賃貸住宅と比較しての購入しやすさ, セキュリティや維持管理の容易さ, そして立地的優位性である. マンション購入世帯の意思決定過程の特徴は, 居住形態の決定の段階によって意思決定のパターンや転居先の選択要因, 転居先の探索地域に差異がみられることである. また, 居住形態の選択要因は, 世帯の経済状況や世帯構成, 親族との関係などを反映している.
8 0 0 0 OA サツマイモのβ-アミラーゼが米飯に及ぼす影響について
- 著者
- 露久保 美夏 石井 克枝
- 出版者
- 日本調理科学会
- 雑誌
- 日本調理科学会大会研究発表要旨集 創立40周年日本調理科学会平成19年度大会
- 巻号頁・発行日
- pp.45, 2007 (Released:2007-08-30)
【目的】 サツマイモはβ―アミラーゼを含み、加熱により活性化しイモの澱粉をマルトースへと分解するため甘味が増すことが知られている。本研究では澱粉を多く含む米とサツマイモを共に加熱調理するサツマイモ飯に注目し、イモ飯の炊飯時にβ―アミラーゼがイモの澱粉に加えて米の澱粉も分解して飯の甘味増強につながるかどうかを検討した。【方法】 サツマイモ(ベニアズマ)20gを5mm角に切り、純水100mlに20分間浸漬し、イモを取り除き液体のみ遠心分離を行った後100mlに定容しサツマイモ粗酵素液とした。β―アミラーゼの活性温度の測定は0.5%可溶性澱粉液を用い、30、40、50、60、70、80℃で10分間反応後、ソモギ・ネルソン法を用いて還元糖量を測定した。また、炊飯中の米への影響についてはビーカーに米30gを入れ、粗酵素液45mlを、対照として純水45mlを加え炊飯器で炊飯し、飯の還元糖量を比較した。他に、サツマイモのあく抜きの有無による粗酵素液のβ―アミラーゼ活性を調べた。そして、それらの飯の味について官能検査を行った。【結果】 β―アミラーゼの至適温度は50℃付近であった。水および粗酵素液で米を炊飯すると、粗酵素液で炊飯した飯の方が還元糖量が多く、β―アミラーゼが飯の澱粉を分解していることが確認できた。また、イモのあく抜きの有無では、あく抜きによりβ―アミラーゼが流出し、炊飯後の飯の糖量はあく抜き無しのものに比べて、還元糖量が少なくなった。官能検査の結果、イモ粗酵素液で炊いた飯は対照の飯より甘く、あく抜き無しが最も甘いと評価され、β―アミラーゼによる飯の甘味増加は官能的にも違いが確認できた。また、甘い飯の方が好まれる傾向にあった。
8 0 0 0 OA 初夏、快晴のCambridgeにて : Skinner先生にお会いした時のことなど
- 著者
- 久保田 新
- 出版者
- 一般社団法人 日本行動分析学会
- 雑誌
- 行動分析学研究 (ISSN:09138013)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.2, pp.129-138, 1991-03-31 (Released:2017-06-28)
8 0 0 0 IR 国語教材としての「近世俳諧」:文学史的指導上の問題点と「俳言」
- 著者
- 大久保 順子
- 出版者
- 福岡女子大学国際文理学部
- 雑誌
- 文芸と思想 = Studies in the humanities : 福岡女子大学国際文理学部紀要 (ISSN:05217873)
- 巻号頁・発行日
- no.83, pp.19-41, 2019
8 0 0 0 OA CKD を合併した心不全カヘキシアに対して栄養療法と運動療法の併用が著効した一例
- 著者
- 山本 実穂 野添 匡史 大西 晶 桝矢 璃央 大澤 摩純 久保 宏紀 山崎 允 間瀬 教史 島田 眞一
- 出版者
- 日本理学療法士学会
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- pp.11639, (Released:2019-11-27)
- 参考文献数
- 34
【目的】慢性腎臓病(以下,CKD)を合併した心不全カヘキシア症例に対して,分岐鎖アミノ酸(以下,BCAA)を含むたんぱく質摂取を中心とした栄養療法と運動療法によって身体機能の大幅な改善が得られたので報告する。【症例紹介】心不全(CKD stage3b 合併)を発症後1 ヵ月間の中心静脈栄養管理となり20 kg の体重減少を招いた。身体機能の改善を目的に理学療法が処方されたが,第76 病日時点で疲労感が強く,運動耐容能(6 分間歩行距離150 m)も低下していることからカヘキシアの状態と考えられた。【経過】BCAA を含むたんぱく質の摂取量を1.2 g/kg/ 日まで漸増し,運動療法はレジスタンストレーニングを中心に行った。約3ヵ月間で体重は8.4 kg 増加し6 分間歩行距離は557 m まで改善した。【結論】CKD を合併した心不全カヘキシア例であっても,たんぱく質摂取量を増やした栄養療法と運動療法の併用は有効と考えられた。
8 0 0 0 OA 人工炭酸浴に関する研究
- 著者
- 萬 秀憲 久保 裕一郎 江口 泰輝 河本 知二 砂川 満 古元 嘉昭
- 出版者
- 一般社団法人 日本温泉気候物理医学会
- 雑誌
- 日本温泉気候物理医学会雑誌 (ISSN:00290343)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.3-4, pp.130-136, 1984 (Released:2010-08-06)
- 参考文献数
- 2
Increase in dermal blood flow by the artificial CO2-bathing was confirmed by means of a Thermocouple flow meter and by a Laser doppler velocimeter.The artificial CO2-bath was prepared with 50g tablet, made from sodium bicarbonate and succinic acid, putting simply in plain water at 38°C.Dermal blood flow was increased nearly 5-fold by the simple bathing, and was further enhanced 1.3-fold by the artificial CO2-bathing.It has been definitely shown by the artificial CO2-bathing that an increase in oral, finger tip, and forehead temperature and transepidermal water loss is significant compared to the plain bathing, so that the thermal effect equivalent to carbon-dioxated spring will be obtained.
8 0 0 0 OA アレグザンダー・ポウプ「サンズの幽霊」(翻訳と解題)
- 著者
- 大久保 友博
- 出版者
- 京都橘大学研究紀要編集委員会
- 雑誌
- 京都橘大学研究紀要 = Memoirs of Kyoto Tachibana University (ISSN:18830307)
- 巻号頁・発行日
- no.45, pp.19-28, 2019-02-15
8 0 0 0 OA 学校適応はどのようにとらえられるのか(10)
企画趣旨 学校適応に関する研究は近年ますます活発になり,小学校・中学校・高校・大学と各学校段階における学校適応研究が蓄積されてきている。学校段階によって学校環境や児童・青年の発達の様相は異なるといえ,学校適応研究においても学校段階を意識することが重要だといえる。こうした問題意識から,企画者らは2017年度は小学校段階に焦点をあてて学校適応について検討を行った(大久保・半澤・岡田,2017)。本シンポジウムでは,中学校段階に注目し,主に友人関係の観点から学校適応にアプローチする。 先行研究では中学生の学校適応に影響を与える様々な要因について検討されてきたが,その中でも友人やクラスメイトとの関係は学校への適応に大きなインパクトがあることが示されてきた(岡田,2008;大久保,2005など)。 中学校段階は心理的離乳を背景に友人関係の重要度が増すとともに,同性で比較的少人数の親密な友人関係である,チャムグループを形成する時期であるとされる(保坂・岡村,1986)。そして,この時期の友人関係では,内面的な類似性が重視され,排他性や同調圧力が強くなるといった特徴のあることが指摘されている。このような友人関係を形成することは発達的に重要な意味がある一方で,中学校段階において顕在化しやすい学校適応上の諸問題と密接に関連していると考えられる。 以上の問題意識から,本シンポジウムでは友人という観点を含めながら中学生の学校適応について研究をされてきた登壇者の話題提供をもとに,この問題について理解を深めてゆきたい。中学生の「親密な友人関係」から捉える青年期の学校適応中井大介 近年,青年期の友人関係に関する研究では青年が親密な関係を求めつつも表面的で希薄な関係をとることや状況に応じた切替を行うといった複雑な様相が指摘されている(藤井,2001;大谷,2007)。その中で,依然として「親友」と呼ばれるような「親密な友人関係」が青年期の学校適応や精神的健康に影響することも指摘されている(岡田,2008;Wentzel, Barry, & Caldwell, 2004)。 一方で,このように重要とされている青年期の親密な友人関係であるが,そもそも青年にとって,このような親密な友人関係がどのようなものであるかを検討した研究は少ない(池田・葉山・高坂・佐藤,2013;水野,2004)。その中でこのような青年期の親密な友人関係をとらえる枠組みの一つとして,近年,青年期の友人に対する「信頼感」の重要性が指摘されている。 しかし,この青年期の友人に対する「信頼感」については,質的研究は行われているものの量的研究が少ないため未だ抽象的な概念である。この点を踏まえれば青年期の親密な友人関係について主体としての青年自身が信頼できる友人との関係をどのように捉えているのかを量的研究によって検討する必要があると考えられる。 加えて上記のように中学生にとって親密な友人関係が学校適応や精神的健康に影響を及ぼすことを踏まえれば,友人に対する信頼感と学校適応の関連を詳細に検討する必要性があると考えられる。しかし,これまで友人に対する信頼感が学校適応とどのような関連を示すかその詳細は検討されていない。そのため生徒の学年差や性差などによる相違についても検討する必要がある。 そこで本発表では中井(2016)の結果をもとに,第一に,「生徒の友人に対する信頼感尺度」の因子構造と学年別,性別の特徴を検討し,第二に,友人に対する信頼感と学校適応との関連を学年別,性別に検討する。これにより中学生の学校適応にとって「親密な友人関係」がどのような意味を持つかについて今後の研究課題も含め検討したい。スクールカーストと学校適応感の心理的メカニズムと学級間差水野君平 思春期の友人関係では,「グループ」と呼ばれるような同性で,凝集性の高いインフォーマルな小集団が形成されるだけでなく(e.g., 石田・小島, 2009),グループ間にはしばしば「スクールカースト」という階層関係が形成されることが指摘されている(鈴木, 2012)。スクールカーストは,生徒の学校適応やいじめに関係することが指摘されている(森口, 2007;鈴木, 2012)。中学生を対象にした水野・太田(2017)では学級内での自身の所属グループの地位が高いと質問紙で回答した生徒ほど,集団支配志向性という集団間の格差関係を肯定する価値観(Ho et al., 2012;杉浦他, 2015)を通して学校適応感に関連することを明らかにした。このように,スクールカーストに関する心理学的・実証的な知見は未だに少ないことが指摘されているが(高坂, 2017),スクールカーストと学校適応の心理的プロセスが少しずつ示されてきている。 また,個人内の心理的プロセスだけでなく,学級レベルの視点を取り入れた研究も必要であると考えられる。なぜなら,学校適応とは「個人と環境のマッチング」(近藤, 1994;大久保・加藤, 2005)と言われるように,個人(児童や生徒)と環境(学級や学校)の相性や相互作用によって捉える議論も存在するからである。さらに,近年のマルチレベル分析を取り入れた研究から,学級レベルの要因が個人レベルの適応感を予測することや(利根川,2016),学級レベルの要因が学習方略に対する個人レベルの効果を調整すること(e.g., 大谷他,2012)のように,日本においても学級の役割が実証的に示されてきているからである。 本発表では中学生のスクールカーストと学校適応の関連について,スクールカーストと学校適応の関連にはどのような心理的メカニズムが働いているのか,またどのような学級ではスクールカーストと学校適応の関係が強まってしまう(反対に弱まってしまう)のかを質問紙調査に基づいた研究を紹介して議論をすすめたい。友人・教師関係および親子関係と学校適応感林田美咲 従来の学校適応感に関する多くの研究では,友人や教師との関係が良好であり,学業に積極的に取り組む生徒が最も学校に適応していると考えられてきた。しかし,学業が出来ていない生徒や教師との関係がうまくいっていない生徒が必ずしも不適応に陥っているとは限らない。そこで,今回は学校適応感を「学校環境の中でうまく生活しているという生徒の個人的かつ主観的な感覚(中井・庄司,2008)」として捉え,検討していく。 友人関係や教師との関係が学校適応感に及ぼす影響については,これまでも検討されてきている (例えば,大久保,2005;小林・仲田,1997)。さらに,家族関係も学校適応感と関連することが示されており,学校適応について検討する際には家族関係やクラス内にとどまらない友人関係も考慮するという視点が必要であると指摘されている (石本,2010)。人生の初期に形成される親子関係は,後の対人関係を形成する上での基盤となることが考えられる。そこで,親への愛着を家族関係の指標とし,友人関係,教師との関係と合わせて,学校適応感にどのような影響を及ぼすのかについて検討した(林田,2018)。 その結果,愛着と学校内の対人関係はそれぞれに学校適応感に影響を及ぼすだけでなく,組み合わせの効果があることが示唆された。親子関係が不安定なまま育ってきた生徒であっても,友人関係や教師との関係に満足していることが補償的に働き,学校適応感が高められることや,友人関係や教師との関係に満足できていない場合,親への愛着の良好さに関わらず,高い学校適応感が得られにくいことが示唆された。つまり,学校適応感を高めるためには,友人関係や教師との関係が満足できるものであることが特に重要であると考えられる。 本発表では,親への愛着や友人関係,教師との関係といった中学生を取り巻くさまざまな対人関係が学校適応感にどのような影響を及ぼしているのかについて,研究結果を紹介しながら考えていきたい。
- 著者
- 中西 康裕 三宅 好子 川田 耕平 久保 友美子 今中 淳二 廣田 雅彦 後藤 淳宏 今村 知明
- 出版者
- 一般社団法人 日本医療情報学会
- 雑誌
- 医療情報学 (ISSN:02898055)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.3, pp.123-134, 2016 (Released:2017-09-11)
- 参考文献数
- 29
本研究では,800床規模の高機能を持つ平均的な大病院をモデルケースとして,まず薬剤収益を求める収益計算の一般的な線形式を作成した.その線形式を基に,後発医薬品導入率,院外処方率および薬剤値引き率等を変数として,変数の増減による薬剤収益の変動を分析した.後発医薬品導入率が0%から100%へ増加することで,収益は約2億1,143万円上昇した.DPCに包括される薬剤が後発医薬品に置き換えられることによって入院薬剤経費が削減され,さらに後発医薬品係数の上昇により診療報酬が増加した.しかし,院外処方率が10%から90%へ増加することで,後発品導入による収益増と同程度の約2億442万円の収益が減少した.院内処方を堅持している病院は,院外処方に切り替えた病院と比較してより多くの薬剤収益を上げていることが本分析によって示された.国の政策として,後発医薬品の推進は経済的インセンティブが有効に機能していると言える.だが,院外処方の推進については,すでに院外処方が主流であるものの経済的インセンティブが働いているとは言い難い状況であろう.
8 0 0 0 ディープラーニングによるパターン認識
- 著者
- 久保 陽太郎
- 出版者
- 情報処理学会 ; 1960-
- 雑誌
- 情報処理 (ISSN:04478053)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.5, pp.500-508, 2013-04-15
8 0 0 0 IR 教育実践レポート 図書館スタッフによる学習支援の実践 : プレゼン入門 話す基本技術
- 著者
- 久保山 健 クボヤマ タケシ Kuboyama Takeshi
- 出版者
- 大阪大学全学教育推進機構
- 雑誌
- 大阪大学高等教育研究 = Osaka University higher education studies (ISSN:21876002)
- 巻号頁・発行日
- no.1, pp.77-83, 2012
- 著者
- 田中 吉輝 長久保 麻子 東城 幸治
- 出版者
- 日本陸水学会
- 雑誌
- 陸水学雑誌 (ISSN:00215104)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.2, pp.129-146, 2010 (Released:2011-08-25)
- 参考文献数
- 24
- 被引用文献数
- 1 2
北米・フロリダ地方原産のフロリダマミズヨコエビは,1989年に日本(千葉-茨城県境の古利根沼:利根川の河跡湖)で初見された外来ヨコエビである。様々な環境への適応性や繁殖力が強く,現在まで,急激に分布を拡大し,日本広域に棲息している。在来の淡水ヨコエビ類が棲息しないような新しいハビタットにも侵入・定着し,また在来ヨコエビ類の棲息ハビタットへも侵入している。本研究では,在来種のオオエゾヨコエビが棲息するハビタットに外来種フロリダマミズヨコエビが侵入・定着した,長野県安曇野市の蓼川を調査地として,年間を通したそれぞれの個体群動態を調査した。同所的に棲息してはいるものの,棲み場所として利用する沈水植物種レベルでの違いが認められるなど,マイクロハビタット・レベルでのニッチ分割が認められた。また,両種が同所的に棲息することで,それぞれの繁殖時季に若干の相互作用が生じている可能性も示唆された。種間における強い排他性のある競争関係は認められなかったが,これは互いの体サイズに大きな相違があることや,蓼川においては,充分な棲み場環境や餌条件が揃っているためであると考えられる。
7 0 0 0 OA ダニ媒介性感染症—国内に常在する感染症を主に—
- 著者
- 佐藤(大久保) 梢 高野 愛 高娃 安藤 秀二 川端 寛樹
- 出版者
- 日本衛生動物学会
- 雑誌
- 衛生動物 (ISSN:04247086)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.1, pp.3-14, 2019-03-25 (Released:2019-04-18)
- 参考文献数
- 130
- 被引用文献数
- 6 7
Tick and mites have many endogenous microorganisms, some of which are pathogen. Recently, emerging and re-emerging infectious diseases have been reported in Japan, and prevention and control of the disease have been taken. In this session, we would like to introduce the outline of tick-borne infectious diseases reported in Japan from the viewpoint of medical entomology.
7 0 0 0 OA 広島市消防局における蘇生処置中止希望を表明した心停止傷病者38例の報告
- 著者
- 細川 康二 西田 優衣 吉野 雅人 岸田 正臣 久保 富嗣 山賀 聡之 志馬 伸朗
- 出版者
- 一般社団法人 日本臨床救急医学会
- 雑誌
- 日本臨床救急医学会雑誌 (ISSN:13450581)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.3, pp.513-516, 2019-06-30 (Released:2019-06-30)
- 参考文献数
- 10
背景:広島市消防局では,心停止傷病者で主治医から心肺蘇生を行わない(DNAR)よう指示されれば蘇生処置を中止する運用がされてきた。本調査の目的は,現状を把握し課題の有無を明らかとすることである。方法:2015年4月からの2年間,同局管内で医療機関搬送までに蘇生処置中止希望が表明された心停止傷病者について,救急救命処置録等の情報を解析した。結果:対象は38例であった。蘇生処置中止希望は文書で1例,ほかは口頭で確認され,87%で主治医か主治医の属す医療機関の医師から確認された。医師よりDNAR指示が出されたのは63%であり,37%で主治医が現場に出向するため不搬送となった。結語:広島市消防局において救急要請後に蘇生処置中止希望が確認される事例では,蘇生処置の中止希望は文書で確認された1例を除くすべてが口頭で確認され,約6割で医師よりDNAR指示が出されていた。救急要請される背景をさらに調査し対策する必要がある。
7 0 0 0 OA 熊本市河内町におけるミカン産地の維持とその要因
- 著者
- 川久保 篤志
- 出版者
- The Association of Japanese Geographers
- 雑誌
- 地理学評論 (ISSN:13479555)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, no.9, pp.455-480, 2006-08-01 (Released:2008-12-25)
- 参考文献数
- 31
- 被引用文献数
- 4 2
本稿では,系統外出荷組織の1形態である集出荷業者の集荷・販売活動の特徴と産地維持に果たしてきた役割の解明を試みた.事例地域はミカンの集出荷業者の集積が著しい熊本市河内町である.その結果,集出荷業者の集荷・販売活動の特徴である農家からミカンを集荷する際の契約事項(集荷する品種や量,期日・時間帯,家庭選別基準など)の簡素さが,ミカン価格低迷下での農家の営農継続に大きく寄与していたことが判明した.簡素な荷の受委託は,大規模に出作地を経営する農家や労働力基盤の弱体化した農家にとって,収穫・選別・出荷作業を省力化できる点で農協共選より好ましかったのである.しかし,1990年代に入りミカンの市場環境が変化すると,集出荷業者が苦境に立たされる一方で農協は糖度センサー選果機の導入を機に糖度別出荷を徹底して販売成績を上げたため,出荷委託先を農協に変更する農家も増え始めた.今後の熊本市河内町では,販売面で優位に立った農協を中心に産地再編が進むと思われるが,集出荷業者も農家ニーズに応じた多様なサービスの継続によって産地維持に一定の役割を果たし続けるものと考えられる.
7 0 0 0 OA Lichenは如何にして地衣と翻訳されたか
- 著者
- 久保 輝幸
- 出版者
- 日本科学史学会
- 雑誌
- 科学史研究 (ISSN:21887535)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.249, pp.1-10, 2009 (Released:2021-08-04)
Chii, the Japanese term for 'lichen', is widely used in contemporary East Asia. However, precisely when and by whom this term was first used to refer to lichen is not known. In addition, Japanese botanists from the 1880s to the 1950s had doubts regarding whether Chii was an accurate translation of lichen, given that Chii originally referred to moss that grows on the ground, whereas most species of lichens grow on barks of trees or on rocks. In this paper, the author shows that Li Shanlan and A. Williamson et al., in the late Qing dynasty of China, first used the term Chii to refer to lichen in Zhiwuxue, published in 1858. In Japan, Tanaka Yoshio, who was influenced by Zhiwuxue, first used the term Chii in 1872. However, further investigations led to the discovery that ITO Keisuke translated lichen as Risen in 1829. In 1836, UDAGA WA Yoan also translated lichen as Risen by using a different kanji (Chinese character) to represent sen. In 1888, in his article, MIYOSHI Manabu suggested a new equivalent term, Kisoukin, to refer to lichen (algae-parasitized fungi). In the article, he proposed the term Kyosei as the Japanese translation of symbiosis. Ever since the late 1880s, Kyosei has been used as the Japanese biological term for symbiosis.
- 著者
- 稲木 健太郎 泰山 裕 大久保 紀一朗 三井 一希 佐藤 和紀 堀田 龍也
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育工学会
- 雑誌
- 日本教育工学会論文誌 (ISSN:13498290)
- 巻号頁・発行日
- pp.S47055, (Released:2023-09-04)
- 参考文献数
- 8
本研究は,思考ツールの選択に関するメタ認知にクラウドで共有した他者の振り返りの参照が与える影響を検討することを目的とした.小学校第4学年児童を対象に,思考ツールの選択に関する振り返りをクラウドで学級内へ共有し,参照させ,改めて自覚したことがある場合は振り返りを追記させた.参照前の振り返りにおいてメタ認知に該当する記述数の多かった群を高群,少なかった群を低群とし,記述の分析とインタビューにより参照の影響を検討した.結果,参照が高群と低群のメタ認知を促すこと,参照により,低群では特に自覚が困難だった経験が,高群では特に無自覚になっていた経験が想起され,メタ認知につながったことが示唆された.
- 著者
- 渡邊 貴博 高林 知也 渡部 貴也 久保 雅義
- 出版者
- 日本バイオメカニクス学会
- 雑誌
- バイオメカニクス研究 (ISSN:13431706)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, pp.52-61, 2022 (Released:2022-09-08)
- 参考文献数
- 29
To prevent chronic ankle instability (CAI) and understand why outcomes vary among patients with a lateral ankle sprain, it is important to examine the differences in movement patterns between copers without recurrent ankle sprain and those who develop CAI. The differences in coordination between both groups are unclear, even though abnormal movements of the rearfoot may affect the forefoot through coupling. Therefore, the purpose of this study was to investigate the coordination between the rearfoot and forefoot of CAI, coper groups. Twelve individuals with CAI, 12 copers, and 12 controls ran on a treadmill at a fixed speed of 2.5 m/s. Kinematic data of the rearfoot and forefoot were measured using a three-dimensional motion analysis system. The coupling angle between the rearfoot and forefoot was calculated using the modified vector coding technique and was classified into four coordination patterns. During early stance, the coper group showed a significantly greater proportion of anti-phase with distal dominancy than the CAI group (p<0.05), and in-phase with distal dominancy approached to decrease than the CAI group (p=0.052). During midstance, the CAI group approached to increase proportion of anti-phase with distal dominancy than the control group (p=0.053). During late stance, the coper group showed a significantly decreased proportion of anti-phase with distal dominancy than the control group (p<0.05). This study may provide in-depth knowledge of motor-behavioral characteristics of coper and CAI.