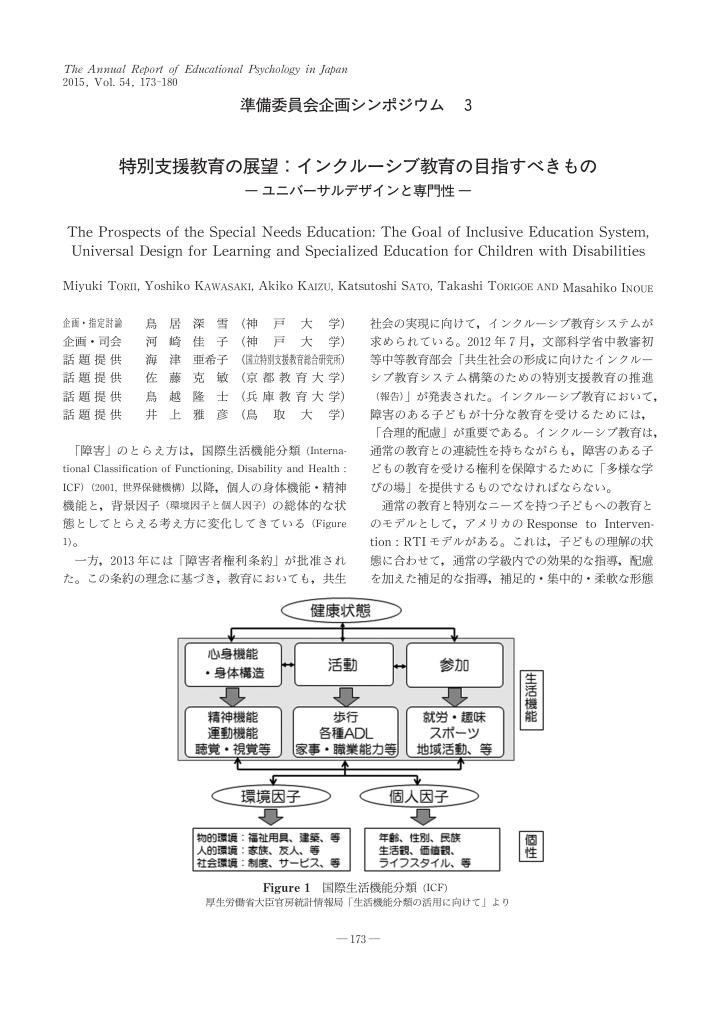1 0 0 0 OA 資料 池島炭鉱における坑内湧水について
- 著者
- 林 幸司 内野 健一 井上 雅弘
- 出版者
- 公益社団法人 日本地下水学会
- 雑誌
- 地下水学会誌 (ISSN:09134182)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.1, pp.117-127, 2005-02-25 (Released:2012-12-11)
- 参考文献数
- 19
池島炭鉱は1959年8月から2001年11月に閉山するまでの42年間採掘を続けた炭鉱で,主に島の南西部の海底下で採掘を行っていた.採炭の奥部化に伴い坑内湧水の量も増え,出水によって作業を中断したこともあった.当炭鉱の湧水の特徴として,以前から時間の経過と共に水量が減少すること,同一箇所においては水質が変化しないことなどが知られていた.これらの事象を整理し,実測のデータから当炭鉱の坑内湧水の特徴を検討した.その結果,(1)湧水箇所では溶存イオン濃度の関係から,3つの型に分類できること,(2)湧水量は指数関数的に減少すること,(3)池島南西沖では,主要坑道の西側に多量の水を含む帯水領域が存在し得ることを示した.
1 0 0 0 OA シンポジウム:世界から見た日本の炭鉱技術 : 炭鉱保存と技術の継承
1 0 0 0 OA 潰瘍性大腸炎に伴う難治性十二指腸潰瘍の2症例
- 著者
- 久保 晴丸 森下 慎二 原口 絋 浅井 玄樹 岡崎 明佳 山川 元太 木原 俊裕 井上 雅文 松本 政雄 新村 和平
- 出版者
- 一般社団法人 日本消化器内視鏡学会 関東支部
- 雑誌
- Progress of Digestive Endoscopy (ISSN:13489844)
- 巻号頁・発行日
- vol.90, no.1, pp.108-109, 2017-06-09 (Released:2017-07-19)
- 参考文献数
- 6
A 38-year-old woman and a 29-year-old man were referred to our hospital for abdominal pain. In both cases, gastroendoscopy revealed a duodenal ulcer. H. pylori and NSAIDs (Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs) intake history were negative in both cases. These duodenal ulcers were refractory even with PPI (Proton Pump Inhibitor) treatment for a few months. Colonoscopies were performed for further evaluation, and they showed vascular pattern loss and fine granular mucosal pattern. From colonoscopy and histopathological examination of the colon, we diagnosed them as ulcerative colitis. Mesalazine therapy was started, and mucosal inflammation of the duodenum and colon gradually subsided. Histopathological examinations of duodenal biopsy showed basal plasmacytosis and crypt distorsion, which is characteristic in gastroduodenitis associated with ulcerative colitis. Therefore, we diagnosed these duodenal ulcers as gastroduodenitis associated with ulcerative colitis. When we see a refractory duodenal ulcer without H. pylori infection and NSAIDs intake, we should consider the coexistence of ulcerative colitis.
1 0 0 0 OA 自閉症早期家庭療育のための集団親指導プログラム
- 著者
- 藤坂 龍司 井上 雅彦
- 出版者
- 一般社団法人 日本認知・行動療法学会
- 雑誌
- 行動療法研究 (ISSN:09106529)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.1, pp.57-70, 2012-01-31 (Released:2019-04-06)
- 被引用文献数
- 2
自閉症早期療育に取り組む親の会に所属する11組の親子を二組に分け、不連続試行法(DTT)を中心とする行動療育の知識と技法に関する親講習会を、時期をずらして約1カ月間実施した。その結果、親の教育技法、子どもの獲得スキルともに、トレーニング後におおむね向上し、半年後、1年後のフォローアップでもそれが維持された。親の精神健康度は講習会後改善したが、1年後は一部の親で再び悪化した。家庭療育を1年未満で中断する親も少なくなかった。これらのことから、約1カ月の親講習会はDTTを中心とする行動療育の技法を親に習得させるためには効果的だが、その後1年間にわたって安定的に家庭療育を維持させるためには不十分であることが示唆された
1 0 0 0 大学教育のデジタルトランスフォーメーション
- 著者
- 井上 雅裕 角田 和巳 長原 礼宗 八重樫 理人 石崎 浩之 丸山 智子
- 出版者
- 公益社団法人 日本工学教育協会
- 雑誌
- 工学教育 (ISSN:13412167)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.3, pp.3_3-3_8, 2022 (Released:2022-05-20)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 2
The digital transformation of society and universities has been accelerating in the COVID-19 pandemic. The digital transformation of education will advance beyond distance and time by utilizing digital technology and develop international and industry-university collaboration. The Japanese Society for Engineering Education initiated a survey and research committee in April 2021. First, the direction of the digital transformation of engineering education will be presented through a multifaceted survey of social needs, information technology, international collaboration, and industry-academia-government collaboration. Secondly, as an advanced model, the realization of graduate and recurrent education in international inter-university and industry-academia collaboration is investigated. This paper is an interim report.
- 著者
- 除村 健俊 小林 真也 飯尾 淳 井上 雅裕
- 出版者
- 一般社団法人 PMI日本支部
- 雑誌
- プロジェクトマネジメント研究報告 (ISSN:24362115)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.1, pp.16-23, 2022-04-20 (Released:2022-04-22)
- 参考文献数
- 10
2020年初頭から始まった新型コロナウイルスの影響で大学教育も大きな影響を受けた.キャンパスは閉鎖され,対面授業ができなくなりオンライン授業が急激に導入された.大学教育は報告時点(2021年7月)までで,半期の授業が3回行われた.この間,授業形態の改善もなされ,対面授業と比較した学生の心理的影響や理解度など,多くの知見が蓄積され,多くの報告が行われている.本報告は,2021年7月に行われたPMI日本フォーラムのアカデミックセッションで実施されたパネルディスカッションをまとめたものであり,コロナ禍の中で実際に授業を実施してきた大学教員の視点から見た,授業形態の変遷や,対面授業との比較,課題,及び,後に実施されたアンケートの結果と考察などを論述する.
1 0 0 0 OA 構造曖昧文の理解におけるガーデンパス現象
- 著者
- 井上 雅勝 中島 義明
- 出版者
- 心理学評論刊行会
- 雑誌
- 心理学評論 (ISSN:03861058)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.2, pp.169-187, 1997 (Released:2019-04-23)
- 著者
- 上田 三穂 小林 裕 吉森 邦彰 高橋 由布子 近山 達 池田 元美 魚嶋 伸彦 木村 晋也 田中 耕治 和田 勝也 小沢 勝 近藤 元治 河 敬世 井上 雅美
- 出版者
- 一般社団法人 日本血液学会
- 雑誌
- 臨床血液 (ISSN:04851439)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.8, pp.657-662, 1997 (Released:2009-04-28)
- 参考文献数
- 15
Chronic active Epstein-Barr virus infection(以下CAEBV)の経過中にEBV感染T細胞の腫瘍化を起こした1例を経験した。症例は20歳女性で発熱,陰部潰瘍,口腔内潰瘍などのベーチェット病様症状で来院した。頚部リンパ節腫脹を認め,生検では炎症性変化であった。EBV抗体価よりCAEBVと診断し,PSL, acyclovirの投与をおこなった。一旦症状は改善したが,発症約10カ月後に汎血球減少を呈し,骨髄にて異常細胞を35%認めた。TCR-β遺伝子の再構成を認めT細胞腫瘍と診断した。化学療法にて骨髄は寛解となったが,全身のリンパ節の再腫脹を認め,約3カ月の経過で治療抵抗性のため死亡した。骨髄中の腫瘍細胞でのEBVのterminal probeを用いたSouthern blottingにてsingle bandが検出され,単クローン性が証明されたことより,EBV感染T細胞の腫瘍化と考えられた。本邦の成人例では稀であり,報告した。
1 0 0 0 OA アルツハイマー型痴呆老人に対する臨床動作法の効果(原著)
- 著者
- 竹田 伸也 井上 雅彦
- 出版者
- 一般社団法人 日本認知・行動療法学会
- 雑誌
- 行動療法研究 (ISSN:09106529)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.2, pp.59-69, 2001-09-30 (Released:2019-04-06)
本研究では、アルツハイマー型痴呆老人へ臨床動作法を実施し、認知機能、姿勢に対する効果を検討した。対象は、特別養護老人ホーム入所中のアルツハイマー型痴呆老人3名であり、2名が重度、1名が中等度であった。週に2回、所定の場所で約30分間の介入を4か月間行い、MMSEとN式精神機能検査を用いて、認知機能と背面・側面の立位姿勢を評価した。その結果、対象者3名中2名においてMMSEとN式精神機能検査の得点が上昇し、残る1名は得点に大きな変動を認めなかった。この効果は、介入終了後3か月を経過した時点においてもおおむね維持されていた。また、姿勢についても、肩の緊張と円背の改善が認められた。以上より、アルツハイマー型痴呆老人の認知機能の維持あるいは改善、および姿勢の改善に対して臨床動作法が有効である可能性が示唆された。
- 著者
- 井上 雅博
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経コンピュ-タ (ISSN:02854619)
- 巻号頁・発行日
- no.631, pp.58-61, 2005-07-25
ヤフーがあおぞら信託銀行への出資を通じて、銀行業務に進出する。井上雅博社長は、オークションやショッピングなどのEC(電子商取引)事業をさらに拡大するには、「もっと安心して利用でき、ネット利用者が便利に使える決済手段が必要だった」と参入の理由を説明する。2006年春の開業を目指し、9カ月という短期の勘定系システム開発に挑む。—ヤフーが銀行に参入する狙いは何ですか。
- 著者
- 関野 登 井上 雅文 山内 秀文
- 出版者
- 社団法人日本材料学会
- 雑誌
- 材料 (ISSN:05145163)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.4, pp.415-420, 2001-04-15
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 1
Mechanical properties of particleboards such as surface hardness, modulus of elasticity (MOE), bending strength (MOR) can be improved by high densification of its face layers. One of the effective ways for this purpose is introducing a steam pre-treatment technique into preparations of wood furnish for face layers, because steaming wood at high temperature increases wood compressibility. Also steam treated and then compressed particles show much less irreversible swelling than ordinary particles. This excellent dimensional stability would contribute to reductions of panel thickness swellings.<br>Three-layered particleboards with a density ranging 0.5-0.8g/cm<sup>3</sup>, a face to core ratio of 2/3, and a thickness of 12mm were manufactured from Sugi (<i>Cryptomeria japonica D. Don</i>) face strands (75mm×9.0mm×0.67mm) and core particles (14.9mm×2.9mm×0.97mm). The face strands were steam pre-treated in an autoclave by introducing high pressure steam at 210°C for 10 minutes. Phenol-formaldehyde resin was used as a binder. The manufactured panels showed the following characteristics, when compared to control panels with non-treated face strands: 1) the maximum density through the thickness increased by 10-15 percent, 2) surface hardness increased by 30 percent, 3) thickness swellings were greatly improved, this being pronounced at higher density panels, 4) however, the reduction of linear expansion was not obvious because this layer structure showed excellent resistance against for in-plane swelling, 5) in spite of face layer's high densification, MOE and proportional limit stress in bending were almost the same as the controls, 6) MOR and withdrawal resistance of wood screw decreased at most by 30 percent due to the reduction of wood cohesion itself caused by steaming.
1 0 0 0 OA 生-権力の臨界 : アメリカの大学警察を人類学する
- 著者
- 井上 雅道
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 文化人類学 (ISSN:13490648)
- 巻号頁・発行日
- vol.77, no.4, pp.499-522, 2013-03-31 (Released:2017-04-03)
帝国の時代にあって、生-権力は、多様な身体・意識・行為によって構成されるマルチチュードとの交渉の中で、いかにセキュリティを構築し自らを形成しているのか。本稿では、現実の世界がさまざまな出来事を通じて演劇的に構成される仕方を分析する「ドラマトゥルギー」の手法=視点を用いながら、アメリカの大学警察(ケンタッキー大学警察部)の史的かつ民族誌的記述を通してこの問いを考察したい。この目標に向けまず、大学警察が「いれば煙たがられ、いなければ文句を言われる」二律背反に直面するようになった経緯を、1960年代から1970年代にかけての学生運動とその後の歴史的文脈の中で検証する。続いて、いなくて文句を言われることがないよう警察が被疑者・犯罪者を「見る・排除する」プロセスが、いることで煙たがられることのないよう警察が自らをキャンパス共同体(マルチチュード)に「見せる」プロセスといかに交錯しているかを分析し、警察が被疑者・犯罪者とキャンパス共同体を含む三者関係の中で、死に対する(=排除する)権利を行使する「見る主体」と生に対する権力を行使する「見せる主体」とを統合するようになったこと、またこの統合が大学における生-権力=セキュリティの強化をもたらしていること、を明らかにする。その後「生-権力は際限なく強化され、私たちを無力化している」という先行研究の議論の妥当性を検討すべく、近年-特に9・11同時多発テロ以降-セキュリティが強化されたまさにそれゆえに、警察官の意識・行為において見る主体(「死に対する(=排除する)権利」)と見せる主体(「生に対する権力」)の統一が崩れ、そこにある種の危機が現れていることを明らかにする。更にこの危機を「生-権力の臨界」として概念化し、それが呼び起こすマルチチュードの新しい自由・自律への含意を論じた後、この含意を「大学のエスノグラフィー」の可能性の中で検討する。
- 著者
- 國武 真史 胤末 亮 井戸川 友樹 篠原 道雄 井上 雅文 白濵 正博 志波 直人
- 出版者
- 西日本整形・災害外科学会
- 雑誌
- 整形外科と災害外科 (ISSN:00371033)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.3, pp.474-476, 2019-09-25 (Released:2019-12-17)
- 参考文献数
- 7
大腿骨頚部骨折に対するTresLock(以下T群),Prima Hip Screw(以下P群)を用いた骨接合術の治療成績を比較検討した.対象は2016年8月から2018年3月に手術を行ったT群7例,P群16例である.平均手術時間はT群:43.1分,P群:24.9分で統計学的に有意差を認めた(P<0.001).Garden Alignment Index変化量や歩行再獲得率に有意差はなかったが,平均telescoping量はT群で少ない傾向を認めた.術後合併症はP群で大腿骨転子下骨折を2例認めた.2群間で統計学的な差があったのは手術時間のみであったが,T群でtelescoping量が少ない傾向を認めた.TresLockは強固な固定力があり,日本人の大腿骨頚部骨折に対して,有用な内固定材料であると考えられた.
1 0 0 0 OA 前十字靭帯再建術後の運動能力の回復を受傷前と比較できた1例
- 著者
- 宮川 博文 池本 竜則 井上 雅之 中田 昌敏 下 和弘 大須賀 友晃 赤尾 真知子 本庄 宏司
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.41 Suppl. No.2 (第49回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.0033, 2014 (Released:2014-05-09)
【はじめに,目的】膝前十字靭帯(以下ACL)再建術後のリハビリテーション(以下リハビリ)において,受傷前レベルの競技復帰を目標とした場合,膝関節筋力,可動域など傷害部位局所の運動能力の回復に加え瞬発力,全身持久力など全身的な運動能力の回復が必要となる。今回,ACL受傷前の健常な状態での膝関節筋力及び全身的な運動能力測定を実施できたバスケットボール選手の再建術後の運動能力の回復についてフォローアップすることができたので,考察を加え報告する。【方法】症例は19歳女性,WJBLバスケットボール選手であり,バスケットボール試合中に左膝を捻って受傷(非接触型損傷)。受傷後6週で患側骨付き膝蓋腱採取(BTB)による靭帯再建術を施行した。術後リハビリは愛知医科大学ACL再建術後リハビリプログラムに従い,関節可動域エクササイズ,筋力増強トレーニング,スポーツ動作トレーニングそして競技復帰に向けた再発予防プログラムを再建靭帯への保護という観点から,段階的に実施した。運動能力の測定項目は1.等速性膝伸展・屈曲筋力,2.瞬発力,3.全身持久力とした。等速性筋力はCYBEX社製NORMを用い角速度240・180・60deg/secにおける膝伸展,屈曲筋力(Nm/kg)を,瞬発力はコンビ社製パワーマックスを用い最大無酸素パワー(watts/kg)を,全身持久力はフクダ電子社製マルチエクササイズテストシステムML-1800を用い予測最大酸素摂取量(ml/kg/min)を測定した。測定時期は,①受傷2ヵ月前,②術前(受傷後1ヵ月),③術後8ヵ月(チーム復帰時),④術後12ヵ月(チーム復帰後4ヵ月),⑤術後20ヵ月(チーム復帰後12ヵ月)とした。等速性膝筋力は全ての時期に,瞬発力,全身持久力は②術前を除く4つの時期に測定した。【倫理的配慮,説明と同意】症例報告として紹介する対象者については,本研究の趣旨,内容,倫理的配慮および個人情報の取り扱いに関し,十分な説明を行い,書面にて研究協力の同意を得た。【結果】1.等速性膝伸展・屈曲筋力:測定時期①~⑤の60deg/secにおける膝伸展筋力(Nm/kg)は①患側2.03/健側2.33,②0.84/2.36,③2.54/3.04,④2.39/2.34,⑤2.81/2.81であり,患側,健側共に術後8ヵ月には受傷前以上に回復し,その後も維持され,チーム平均より優れていた。屈曲筋力においても同様の結果であった。2.瞬発力:最大無酸素パワー(watts/kg)は①11.8,③12.4,④12.7,⑤14.5であり,膝筋力と同様,術後8ヵ月には受傷前以上に回復した。3.全身持久力:最大酸素摂取量(ml/kg/min)は①50.5,③47.4,④44.6,⑤51.1であり,膝筋力,瞬発力と異なり,受傷前はチーム平均より高値であったが,術後8ヵ月では受傷前レベルに回復せず,チーム平均より低値であった。術後12ヵ月ではさらに低下を示し,術後20ヵ月で受傷前レベルに回復した。【考察】術後機能評価は一般的に術前との比較を基本とする。しかし,この術前は受傷後であり,筋力において患側は傷害に伴い機能低下し,健側であっても受傷後の安静,運動制限期間により機能低下し健常な状態ではない可能性がある。本症例は受傷2ヵ月前の健常な状態でのチームメディカルチェックによる運動能力テスト結果と術後運動能力の回復を比較し得た希少な症例であった。膝筋力,瞬発力は術後8ヵ月で,受傷前の健常レベル以上に回復し,我々のACL再建術後リハビリプログラムの有効性が確認できた。しかし,全身持久力は術後8,12ヵ月において受傷前レベルに回復しなかった。今回,全身持久力トレーニングは,自転車エルゴメーター,ステップマシン,トレッドミル,水中運動を用い再建靭帯への負荷に注意し,段階的に実施したが,筋力,瞬発力で行っているような定期的な評価を実施せず行ったことが,回復を遅らせた一因と考える。通常,ACL再建術後は手術部位に着目した局所の安定性や可動性,筋力,さらに瞬発力までの評価に止まりがちであり全身持久力まで評価することは少ない。今回の報告は,一例ではあるものの,チーム復帰時に元の競技レベルと比べ,最大酸素摂取量つまり全身持久力が改善されていないことが示され,スポーツ復帰における全身持久力評価の重要性が示唆された。今後は,術後プログラムに競技特性を考慮し,筋力,瞬発力,ステップワーク等の無酸素性運動能力に加え,全身持久力を向上させるため,局所負荷に応じた有酸素性運動プログラムを評価に基づき取り入れることが重要と考える。【理学療法学研究としての意義】本症例より,ACL再建術後の競技復帰を目標としたリハビリは,膝関節機能に加え,競技特性を考慮した無酸素及び有酸素運動能力の評価,トレーニングの重要性が示唆された。今後,特にこの有酸素運動能力について検討を進め,より安全な競技復帰に寄与したいと考える。
- 著者
- 竹田 伸也 井上 雅彦 金子 周平 南前 恵子
- 出版者
- 一般社団法人 日本認知・行動療法学会
- 雑誌
- 行動療法研究 (ISSN:09106529)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.1, pp.63-72, 2016-01-31 (Released:2019-04-27)
本研究の目的は、子どもに応じたアセスメントから対応まで実施できる認知行動療法プログラムを作成し、養護教諭のストレス反応や自己効力感に与える影響について検討することであった。19名の介入群と27名の統制群からなる46名の養護教諭を対象とした。介入群の養護教諭に対して、認知行動療法を応用した子どもの抱える問題のアセスメントと対応についての2時間からなるワークショップと90分からなるフォローアップ研修を実施した。その結果、本プログラムは子どもへの対応についての自己効力感を改善させることが示唆された。一方、無気力と一般性自己効力感は介入群と統制群双方で向上し、無気力以外のストレス反応は介入群と統制群双方で変化を認めなかった。
1 0 0 0 OA 職業としてのアスリートとプロスポーツの諸問題
- 著者
- 井上 雅雄
- 出版者
- 日本スポーツ社会学会
- 雑誌
- スポーツ社会学研究 (ISSN:09192751)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.2, pp.33-47, 2009-09-30 (Released:2016-10-05)
- 参考文献数
- 17
1990年代以降とくに顕著となった企業スポーツの危機は、従業員の一体感や凝集性を高めるための福利厚生施策の一環として誕生したという成立の経緯そのものにあり、その後企業の広告・宣伝の役割も付加されたり、あるいはCSR(企業の社会的責任)の観点から位置づけ直されたりするようになったとはいえ、それ自体、費用対効果の点から企業業績に左右される不安定性を内包するものであった。この企業スポーツの衰退は、それを有力な人的供給源とするプロスポーツの弱体化を招き、地域社会の疲弊を加速しかねない重大な問題である。それゆえに企業スポーツを個別の経営から自立させるために、地域を主体としたクラブチームへの移行やプロリーグへの発展が追求されてきたのであり、サッカーのJリーグと野球の独立リーグの誕生はその成果であった。しかし、それらがビジネスモデルとするべき日本のプロ野球は、最近一部に変化の動きはあるものの、長期にわたって「戦力の均衡」に基づく試合のダイナミズムを創出できなかったばかりか、企業経営としての自立性の欠如や権威主義的労使関係など多くの問題をかかえたままであった。 しかもわが国にあってプロスポーツ選手の法的地位は、他の先進諸国に比べ不安定であり、それが選手たちの職業としての安定性に深い影を落としている。むろんプロ野球選手の一部に特徴的な高額な年俸は、その高い身体能力とスキルに対する報酬ではあるが、その現役期間の短さを考慮すれば彼らにあっても選手生活の後の社会生活が問題であり、当然にもセカンドキャリアが重要となる。とりわけプロスポーツ選手に固有の専門スキルは、所属球団やクラブに限定されないいわば職業特殊的なものであり、一般企業に適用可能なスキルではないゆえにその緊要性は一層高い。この意味においてJリーグが先鞭をつけた選手に対するセカンドキャリア支援の試みは、注目に値する。 その上で看過してはならないことは、瞬時の決断力や高度な集中力あるいは克己心や耐久力、旺盛な行動力など、厳しい戦いの世界で培われたスポーツ選手のいわば人間力は、第二の職業世界においても確かな優位性をもつということである。今日、プロスポーツは、市場経済システムの猛威の果てに疲弊の度が一層深まっている地域社会の、コミュニティとしての再生を担う役割を期待されている。
1 0 0 0 OA 道路橋設計照査制度の日米欧比較分析
- 著者
- 井上 雅夫 小澤 一雅 藤野 陽三
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 土木学会論文集F4(建設マネジメント) (ISSN:21856605)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.3, pp.190-203, 2013 (Released:2013-12-20)
- 参考文献数
- 36
- 被引用文献数
- 1
近年,我が国では設計技術の変化,設計業務の入札契約方式の変化など多くの要因により土木設計照査制度のあり方が問題となっている.日本,米国,英国,ドイツ等において行政が運用する道路橋設計照査制度について,監査論等を参考に視点を設定し比較整理した.その結果,米国,英国,ドイツの照査制度では,発注者の照査義務の内容,受注者等による照査の信頼性などは異なるが,1)発注者の照査義務が明確,2)発注者における照査担当組織の整備,3)受注者等による照査の履行の担保,が共通してなされていることがわかった.国土交通省の照査制度では,1)~3)がなされていない.発注者および受注者等による照査の履行が担保されておらず,そして,受注者等による照査の信頼性が低いと考えられる.
1 0 0 0 OA ポスト占領期における映画産業と大映の企業経営(上)
- 著者
- 井上 雅雄 イノウエ マサオ Masao Inoue
- 雑誌
- 立教經濟學研究
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.1, pp.55-76, 2015-07
1 0 0 0 OA 「失われた」40年 : 戦後労働の精神史
- 著者
- 井上 雅雄 イノウエ マサオ Masao Inoue
- 雑誌
- 立教經濟學研究
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.1, pp.1-18, 2010-07-20