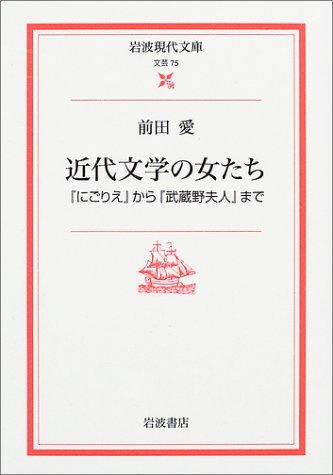1 0 0 0 OA ディーゼル噴霧火炎における壁面熱損失に関する研究
- 著者
- 巽 健 前田 篤志 宮田 哲次 小橋 好充 桑原 一成 松村 恵理子 千田 二郎
- 出版者
- 公益社団法人 自動車技術会
- 雑誌
- 自動車技術会論文集 (ISSN:02878321)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.6, pp.1291-1296, 2016 (Released:2018-01-29)
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 9
ディーゼル機関は高い熱効率を有しているが,投入熱量の20~30%が冷却損失として失われており,熱効率を向上させる上で壁面熱伝達メカニズムの解明は重要である.そこで壁面挿入型定容燃焼容器を用いて火炎直接撮影および熱流束測定を行なうことでディーゼル火炎と壁面熱損失の相関性を調査した.
フュージョンパートナー細胞SPYMEGを用いてヒトのモノクローナル抗体が作製できるか否かを検討した。健常人の末梢血よりリンパ球を得てSPYMEGとPEG法を用いて融合させ、HAT存在下にてハイブリドーマ細胞を培養した。融合細胞を768ウエルに播種したところ、コロニー形成率は平均28%(2回の融合)であった。IgG産生能をサンドイッチELISAにて測定した結果、コロニーが形成されたウエル中27%で陽性であった。これは既報のパートナー細胞Karpasを用いた成績に極めて近い値であった。ヒトのIgGを産生している細胞を限界希釈し単クローンにし、IgGを精製したところ、H-鎖、L-鎖ともに発現しており、完全なIgGが合成されていることが分った。抗体産生能はハイブリドーマに依存するがよく産生するクローンで2〜10μg/ml程度であった。ハイブリドーマはセルバンカーを用いて1ヶ月凍結保存し、その後再び培養を再開しても抗体産生能は凍結前に比べ変化はなかった。この結果から、かなり安定したヒトのモノクローナル抗体が作製できることが明らかになった。そこで、ヒトの特異的モノクローナル抗体を作製するために、ヒトに投与できる抗原としてインフルエンザワクチンを用いた。インフルエンザワクチン投与した場合、投与後1ヶ月以内に末梢血リンパ球を得てSPYMEGと融合させ、HAT存在下にてハイブリドーマ細胞を培養した。またインフルエンザに自然感染した健常人についても検討した。融合細胞を384ウエルに播種し、インフルエンザワクチン抗原AとBの混合液ををELISAプレートにコートし、スクリーニングを行なった。その結果、自然感染の健常人からのリンパ球を用いたときインフルエンザ抗原に陽性に反応するモノクローナル抗体が14クローンが陽性であり、最終的に2クローンが得られた。インフルエンザワクチンを投与したとき、121クローンが陽性であった。このうち最終的に12クローンが得られた。同手法を用いて、血小板のGPIIb/IIIa複合体に対する抗体を産生している自己免疫疾患患者から抗体の作製を行なった。その結果、2クローンが健常人の血小板に反応しIIb/IIIaを免疫沈降してくることがわかった。これらの結果から、SPYMEGはヒトのモノクローナル抗体の作製が可能でり、臨床と基礎医学研究に役立つと考えられた。
1 0 0 0 OA ギャップ結合チャネルの構造基盤
- 著者
- 前田 将司
- 出版者
- 日本結晶学会
- 雑誌
- 日本結晶学会誌 (ISSN:03694585)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.1, pp.25-30, 2010-02-28 (Released:2011-02-25)
- 参考文献数
- 27
Here we describe the long awaited atomic structure of the gap junction channel. The structure reveals intra-/inter- monomer interactions, which stabilize the channel structure, and intercellular interactions between two apposing hemichannels. The structure also reveals the pore structure in detail, charge distribution, pore-lining residues and so on. The novel structure, pore funnel, is found on the top of the pore and the relationship with channel gating could be inspected.
1 0 0 0 OA インターネットを介した精神疾患を患う人々のセルフヘルプ
- 著者
- 前田 至剛
- 出版者
- 社会学研究会
- 雑誌
- ソシオロジ (ISSN:05841380)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.3, pp.53-68,127, 2011-02-28 (Released:2015-05-13)
- 参考文献数
- 24
This paper aims to clarify the formation and characteristics of new Internet-related self-help activities for people who suffer from mental illnesses. First, these activities are not organized by existing self-help groups outside the Internet; and secondly, the relationship between the participants is very fluid. The participants use the Internet as a tool to contact each other without having recourse to any sort of intermediary services such as medical and welfare agencies. They themselves select people with whom to talk, and decide what to do at their own discretion. When starting such activities, it may happen that they do not trust each other at first, because their communication starts with anonymous Internet BBS on which verbal abuse and aspersions are posted frequently. But if they manage to hit it off with other people at offline meetings planned online anonymously, it becomes a precious experience for them in creating new intimate relationships that - among other things - might prevent the participants from committing suicide. They encourage each other, relieve their loneliness, and help each other to live with, and to manage, their illnesses. However,if these intimate relationships develop into a fixed relationship, then that may create a greater risk of trouble. In such cases, people tend to return to anonymous online communications as a sort of risk aversion. On the other hand, this also gives them another chance for precious experiences in finding a kindred spirit among other participants. Such activities create opportunities for socially vulnerable people to maintain their self-identity as a kind of reflexive project such as is imposed on all people in individualized societies, along with a chance for risk aversion among peer helpers. In this way, they use the Internet to enhance their discretionary power to continue self-help activities.
1 0 0 0 OA PAUL LEYHAUSEN : 猫の行動研究
- 著者
- 前田 嘉明
- 出版者
- 日本動物心理学会
- 雑誌
- 動物心理学年報 (ISSN:00035130)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.97-102, 1957-04-25 (Released:2009-10-14)
1 0 0 0 OA 溶血と混濁の生化学検査への影響―岡山県の近隣施設における血清情報の実態調査―
- 著者
- 古川 聡子 河口 勝憲 加瀬野 節子 前田 ひとみ 末盛 晋一郎 通山 薫
- 出版者
- 一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会
- 雑誌
- 医学検査 (ISSN:09158669)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.5, pp.648-654, 2014-09-25 (Released:2014-11-10)
- 参考文献数
- 3
- 被引用文献数
- 1
溶血・混濁は測定値に影響を与えるため,血清情報(溶血・混濁)を臨床側に報告することは病態把握および検査値を解釈する上で必要である.しかし,血清情報に関しては各施設任意の判定基準を採用しており,標準化が行われていないのが現状である.そこで,現状把握のため調査を実施した.調査内容はアンケート調査,溶血・混濁の希釈系列を用いたコメント付加開始点の調査(岡山県近隣施設の施設間差と目視判定の個人差)および測定値への影響について行った.アンケート調査では,約7割の施設が自動分析装置で血清情報の測定を行っており,報告形態は定性値の軽度(弱または微)・中度・強度の3段階が最も多く使用されていた.溶血のコメント付加開始点の調査ではヘモグロビン(Hb)濃度40~50 mg/dLでの設定が多く,Hb濃度50 mg/dLにおける測定値の変化はLD:53.0 U/L(+29.7%),K:0.16 mEq/L(+4.2%),AST:2.5 U/L(+10.2%)の上昇であり,その他の項目では影響(変化率:4%未満)は認めなかった.混濁のコメント付加開始点はイントラリポス濃度0.02%前後の設定が多く,イントラリポス濃度0.02%では測定値の変化は認められなかった(変化率:4%未満).また,溶血・混濁のコメント付加開始点は施設間で異なり,目視判定も個人の認識に差があることが明らかとなった.
1 0 0 0 4弁に発症した乳頭状線維弾性腫の1手術例
- 著者
- 安藤 美月 喜瀬 勇也 前田 達也 稲福 斉 山城 聡 國吉 幸男
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本心臓血管外科学会
- 雑誌
- 日本心臓血管外科学会雑誌 (ISSN:02851474)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.4, pp.245-249, 2019
- 被引用文献数
- 2
<p>原発性心臓腫瘍は稀な疾患であり,その発症率は剖検例の0.0017~0.33%とされているが,心臓超音波検査の進歩および普及による診断学の発展に伴い,その診断率は年々上昇している.乳頭状線維弾性腫は粘液腫についで多い心臓原発性良性腫瘍で,多くは大動脈弁および僧帽弁に単発で生じることが多い無血管性乳頭腫であり,4弁すべてに発生した症例報告はない.今回われわれは意識消失を契機に発見された,若年女性の4弁すべてに発生した乳頭状線維弾性腫の1例を経験したので文献的考察を加え報告する.</p>
1 0 0 0 OA 生菌製剤投与が健常犬の消化管に及ぼす影響に関する基礎的検討
- 著者
- 福島 建次郎 大野 耕一 小田巻 俊孝 高津 善太 前田 真吾 辻本 元
- 出版者
- 日本ペット栄養学会
- 雑誌
- ペット栄養学会誌 (ISSN:13443763)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.1, pp.13-19, 2018-04-10 (Released:2018-05-18)
- 参考文献数
- 8
近年、炎症性腸疾患(IBD)の病態や治療に関連して、腸内細菌叢や消化管粘膜の免疫寛容などに関しての関心が高まっている。しかしながら日本国内において、プロバイオティクスやプレバイオティクスの投与が動物の消化管に及ぼす影響に関する基礎的な研究は限られている。本研究では健常犬6頭にビフィズス菌・乳酸菌製剤(ビヒラクチンDXTM)およびサイリウムを2週間同時投与し、投与前、投与後の腸内細菌叢および腸粘膜における制御性T細胞(T-reg)数の変化について検討した。腸内細菌叢の解析では、投与後に Firmicutes門が減少し、Fusobacterium門および Bacteroides門の菌の構成比が増加していた。 また6頭中5頭で、投与後の細菌構成比が類似したパターンへと変化したことが明らかとなった。しかしながら消化管粘膜におけるTreg数については、有意な変化は認められなかった。今後はT-regの制御に関わるとされる短鎖脂肪酸の解析も実施し、また症例犬を用いた臨床的な検討も必要であると思われる。
1 0 0 0 IR 近代(モダン)の構造と身体性 : 器官なき身体にみる内在的な生成性と変革性
- 著者
- 前田 雅司 Maeda Masaji マエダ マサジ
- 出版者
- 大阪大学人間科学部社会学・人間学・人類学研究室
- 雑誌
- 年報人間科学 (ISSN:02865149)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, pp.65-84, 2004
- 著者
- 前田 珠里 吉村 基 福本 有花 中城 満
- 出版者
- 一般社団法人 日本科学教育学会
- 雑誌
- 日本科学教育学会研究会研究報告
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.7, pp.39-42, 2015
本研究では、理科授業における測定誤差の扱い方に焦点を当て、測定誤差を解消するための具体的な手法について明らかにすることを目的とした。そこで、測定誤差を克服するための仮説として、「実験精度の向上」と「子どもの納得」という二つの視点に着目し、実際の授業記録から実験方法や指導方法の妥当性を分析・検討した。その結果、「あえて実験の精度を落とすこと」や「実験結果を一覧にし、客観的に考察させること」、「測定誤差の範囲をあらかじめ設定すること」などが測定誤差を克服するために効果的な手立てであるということが明らかになった。
1 0 0 0 OA 北海道のエゾタヌキにおけるイヌジステンパーウイルス感染に関する疫学調査
- 著者
- 佐鹿 万里子 阿部 豪 郡山 尚紀 前田 健 坪田 敏男
- 出版者
- 日本霊長類学会
- 雑誌
- 霊長類研究 Supplement 第29回日本霊長類学会・日本哺乳類学会2013年度合同大会
- 巻号頁・発行日
- pp.256, 2013 (Released:2014-02-14)
【背景】近年,エゾタヌキ Nyctereutes procyonoides albusの地域個体数減少が報告されており,この原因として疥癬やジステンパーなどの感染症や外来種アライグマの影響が考えられているが,その原因は明らかとなっていない.そこで本研究では,エゾタヌキ(以下,タヌキとする)を対象に,ホンドタヌキで集団感染死が報告されているイヌジステンパーウイルス(Canine distemper virus:以下,CDVとする)について疫学調査を行った.【材料と方法】調査地域は,2002~ 2004年に重度疥癬タヌキが捕獲され,さらにタヌキ個体数減少も確認されている北海道立野幌森林公園を選定した.2004~ 2012年に同公園内で捕獲されたタヌキ 111頭において麻酔処置下で採血を行うと同時に,マイクロチップの挿入と身体検査を行った.血液から血漿を分離し,CDVに対する中和抗体試験を行った.【結果】CDVに対する抗体保有率は 2004年:44.4%,2005年:8.3%,2006年:14.3%,2007年:11.1%,2008年:7.7%,2009年:54.5%,2010年:8.3%,2011年:0%,2012年: 0%であった.また,同公園内では 2003年に 26頭のタヌキが確認されたが,2004年には 9頭にまで激減し,その後,2010年までは 10頭前後で推移していた.しかし,2011年は 18頭,2012年には 16頭のタヌキが確認され,タヌキ個体数が回復傾向を示した.【考察】抗体保有率は 2004年および 2009年に顕著に高い値を示したことから,同公園内では 2004年と 2009年に CDVの流行が起きた可能性が示唆された.また,2002~ 2004年には,同公園内で疥癬が流行していたことが確認されているため,同公園内では CDVと疥癬が同時期に流行したことによってタヌキ個体数が減少したと考えられた.
1 0 0 0 近代文学の女たち : 『にごりえ』から『武蔵野夫人』まで
1 0 0 0 たたかいの言論人--桐生悠々
- 著者
- 前田 雄二
- 出版者
- 日本新聞協会
- 雑誌
- 新聞研究 (ISSN:02880652)
- 巻号頁・発行日
- no.130, pp.48-53, 1962-05
- 著者
- 浅田 恭生 鈴木 昇一 藤井 茂久 小林 正尚 伊藤 美由起 伊藤 勝祥 前田 繁信 澤井 智子 林口 あかね 白川 秀紀
- 出版者
- 公益社団法人 日本放射線技術学会
- 雑誌
- 放射線防護分科会会誌 (ISSN:13453246)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, pp.48, 2003-10-10 (Released:2017-12-29)
1 0 0 0 OA 第4.5手根中手関節の脱臼骨折の4例
- 著者
- 高野 純 伊集院 俊郎 佐久間 大輔 前田 昌隆 東郷 泰久 小倉 雅 永野 聡 瀬戸口 啓夫 小宮 節郎
- 出版者
- 西日本整形・災害外科学会
- 雑誌
- 整形外科と災害外科 (ISSN:00371033)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.3, pp.447-450, 2016-09-25 (Released:2016-12-06)
- 参考文献数
- 8
第4.5手根中手関節(以下CM関節)は,第4.5中手骨長軸方向への外力が加わった時に脱臼骨折を起こしやすい.2010年から2015年までの6年間に当院にて治療を行なった第4.5手根中手関節の脱臼骨折は6例であった.そのうち保存治療1例,フォローアップ出来なかった1例を除外し手術を行った4例を対象とした.脱臼骨折の原因として,右尺側Rolando骨折1例,左尺側Bennett骨折1例,有鈎骨体部骨折1例,有鈎骨体部骨折と有頭骨骨折,第3中手骨基部骨折を合併するもの1例であった.観察期間は平均2年8ヶ月(9ヶ月~5年1ヶ月)であった.結果は,整復位は良好で全例に骨癒合が得られた.尺側Bennett骨折や尺側Rolando骨折は優位に握力低下がおこりやすいと言われているが,当院の症例でも尺側Rolando骨折1例で握力低下を認めた.解剖学的正確な整復と手術による強固な固定が必要である.
1 0 0 0 IR 近世日本教育史序説 : 「教育」概念を中心に
- 著者
- 前田 勉
- 出版者
- 愛知教育大学日本文化研究室
- 雑誌
- 日本文化論叢 (ISSN:09191151)
- 巻号頁・発行日
- no.24, pp.35-58, 2016-03
1 0 0 0 IR 細井平洲における教育と政治 ―「公論」と「他人」に注目して―
- 著者
- 前田 勉
- 出版者
- 愛知教育大学
- 雑誌
- 愛知教育大学研究報告. 人文・社会科学編 (ISSN:18845177)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, pp.53-61, 2014-03-01
1 0 0 0 HBs抗原およびHBs抗体のSubtypeに関する疫学的検討
- 著者
- 前田 淳 林 直諒 小幡 裕 竹本 忠良 関根 暉彬 西岡 久寿弥 松野 堅 上地 六男 山内 大三 山下 克子 横山 泉 市岡 四象 本池 洋二 藤原 純江
- 出版者
- 一般社団法人 日本肝臓学会
- 雑誌
- 肝臓 (ISSN:04514203)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.12, pp.907-913, 1976
東京女子医大,成人医学センターの定期検診受診者1,391名および同消化器内科に肝疾患のため入院した発端者20名(急性肝炎8名,慢性肝炎6名,肝硬変3名,肝癌3名)の家族90名を対象としHBs抗原およびHBs抗体についてsubtypeを中心に検討を加えた.<BR>定期検診受診者の抗原陽性看は1.4%,抗体陽性者は27.4%であり,肝疾患患看家系では抗原陽性者は41.1%,抗体陽性者は34.4%で定期検診受診者より明らかに高率であり,特に抗原の陽性率が高い.<BR>subtypeでは定期検診受診者,肝疾患患者家系とも抗原はadr,抗体はRが優位であり,定期検診受診者で6ヵ月間隔で2度施行できたものでsubtypeの変動したものはなかった.肝疾患患者家系では肝硬変,肝癌群に兄弟,子供に抗原,抗体の集積がみられ,subtypeでは抗原がadwの家系は急性肝炎の1例のみで,他は抗原はadr,抗体はRであり,同一家族内でsubtypeの異なるものはなかった.
1 0 0 0 大学生バドミントン選手の傷害と熱中症に関する研究
- 著者
- 利根川 直樹 浦辺 幸夫 前田 慶明 沼野 崇平 辰巳 廣太郎 橋本 留緒
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement
- 巻号頁・発行日
- vol.2016, 2017
<p>【はじめに,目的】</p><p></p><p>バドミントン競技では,前後左右への機敏なフットワークが要求され,スマッシュなどストローク時に上肢の爆発的な力が必要となる。外傷は捻挫や肉離れなど下肢に多く,障がいは肩・肘関節など上肢に多いといわれているが(村尾,2012),その受傷機転を調査したものは少ない。さらに,競技中は風の影響を避けるため,真夏でも窓を閉め切る必要があり,苛酷な暑熱環境下でのプレーとなる。そのため熱中症発生の危険性が高いが(倉掛,2003),バドミントンの熱中症の発生状況に関する研究は少ない。</p><p></p><p>本研究の目的は,大学生バドミントン選手の傷害とその受傷機転,そして熱中症発生の実態を把握し,今後の予防対策の一助とすることとした。</p><p></p><p>【方法】</p><p></p><p>中国・四国地方のバドミントン部に所属する大学生577名にインターネットによるアンケートを実施し,有効回答の得られた218名(男子111名,女子107名)を対象とした。アンケート回収率は37.8%であった。</p><p></p><p>調査項目は身長,体重,競技経験年数,練習時間,外傷の有無と部位,外傷名,障がいの有無と部位,障がい名,受傷位置と動作,熱中症の有無・自覚症状・時期とした。熱中症の重症度は,自覚症状の回答から先行研究の判別方法を参考に,I度(軽度),II度(中等度),III度(重度)に分類した(坂手ら,2013)。</p><p></p><p>統計学的解析には,各項目について外傷経験のあり群,なし群の群間比較と,障がい経験のあり群,なし群の群間比較にMann-WhitneyのU検定,χ<sup>2</sup>検定を用いた。いずれも危険率5%未満を有意とした。</p><p></p><p>【結果】</p><p></p><p>選手218名中のべ75名(男子35名,女子40名)に外傷経験があり,のべ75名(男子44名,女子31名)に障がい経験があった。外傷部位は足関節が51件と最も多く,外傷名は捻挫が43件と最多であった。障がい部位は下腿前面が24件と最も多く,障がい名はシンスプリントが19件と最多であった。コート内の受傷機転は,非利き手側後方での外傷の割合が25.2%と最も高かった。外傷経験あり群は練習時間が有意に長く(p<0.01),外傷経験あり群および障がい経験あり群は,競技経験年数が有意に長かった(p<0.01)。</p><p></p><p>過去1年間の熱中症発生件数は52件であり,7月が最多で20件であった。熱中症経験者のうちI度は10.3%,II度86.2%,III度3.5%であった。</p><p></p><p>【結論】</p><p></p><p>本研究から,大学生バドミントン選手では外傷,障がいともに下肢に多い傾向がみられた。受傷機転では,非利き手側後方での受傷割合が高いことが明らかとなった。非利き手側後方ではオーバーヘッドストローク後に片脚着地となることが多く,傷害リスクの高い動作である可能性が示唆された。</p><p></p><p>大学生のスポーツ活動時の熱中症の調査と比較すると(坂手ら,2013),本研究ではIII度の割合が低値を示したものの,II度の該当率が高く,重症化させないように注意喚起を行う必要がある。</p><p></p><p>本研究によって,大学生バドミントン選手のある程度詳細な調査結果を得られた意義は大きい。</p>
- 著者
- 岸本 恵一 神田 かなえ 日下 昌浩 大槻 伸吾 大久保 衞 前田 正登 柳田 泰義
- 出版者
- 一般社団法人 日本アスレティックトレーニング学会
- 雑誌
- 日本アスレティックトレーニング学会誌 (ISSN:24326623)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.1, pp.67-70, 2017
<p>アメリカンフットボール競技の現場で重症度判定が適切でなかった熱中症の症例を経験した.主訴は全身性筋痙攣であり,当初は意識清明であるとの評価から軽症な熱中症を疑ったが,採血結果から重症熱中症(III度熱中症/熱射病)と診断された.スポーツ現場で利用可能な重症度判定指標は限られるため,暑熱環境下での体調不良は重症熱中症の可能性を疑い,可及的早期に病院を受診することが望ましい.</p>