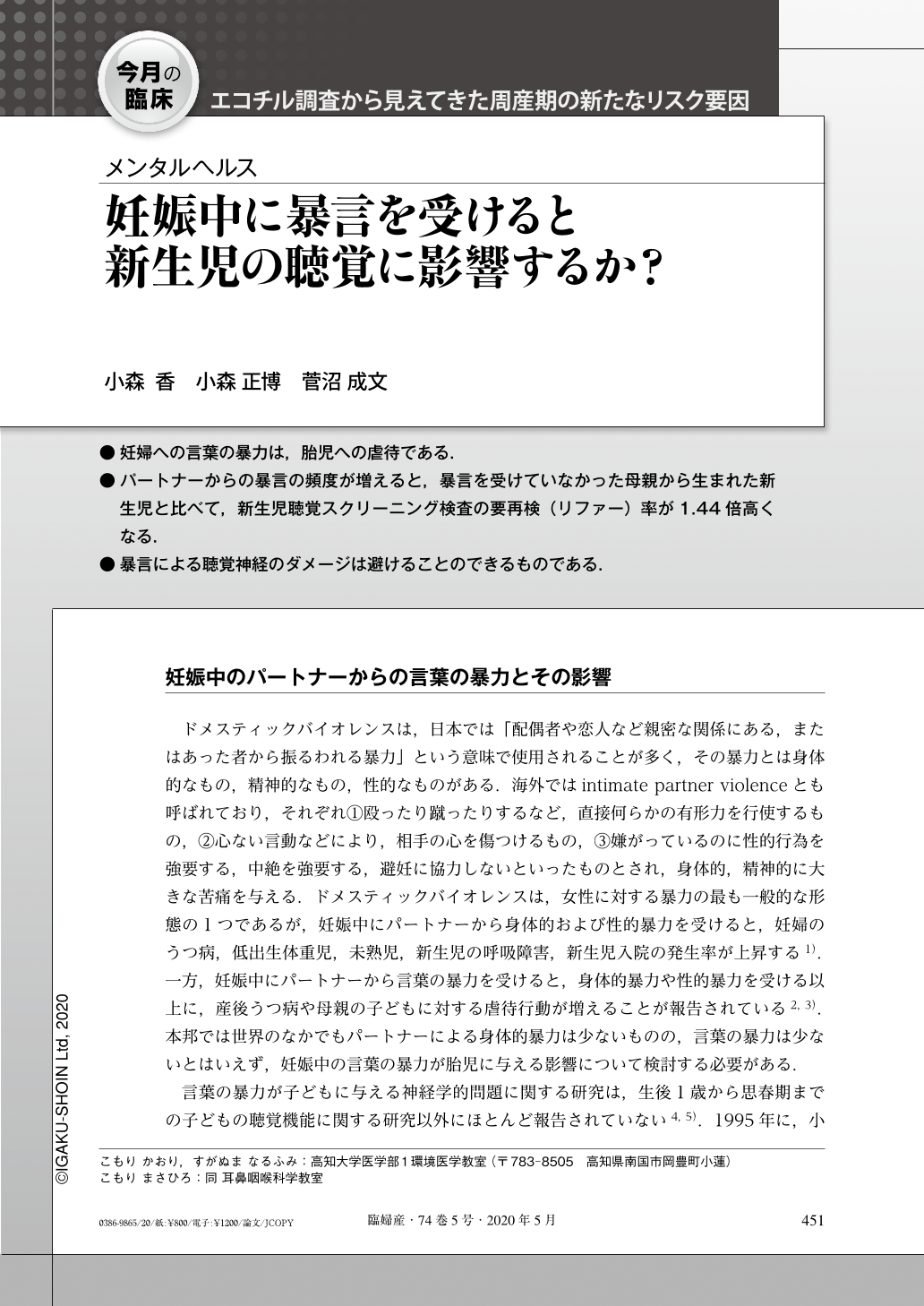1 0 0 0 OA カキの汚損果防止に関する研究 (2)
- 著者
- 濱地 文雄 恒遠 正彦 森田 彰
- 出版者
- [福岡県農業総合試験場]
- 巻号頁・発行日
- no.5, pp.15-20, 1985 (Released:2011-03-05)
- 著者
- 浜地 文雄 恒遠 正彦 森田 彰
- 出版者
- [福岡県農業総合試験場]
- 雑誌
- 福岡県農業総合試験場研究報告 B(園芸) (ISSN:02863030)
- 巻号頁・発行日
- no.5, pp.p15-20, 1985-12
1 0 0 0 OA 塗膜の硬化過程における架橋密度の追跡手法
- 著者
- 森 寛爾
- 出版者
- 一般社団法人 色材協会
- 雑誌
- 色材協会誌 (ISSN:0010180X)
- 巻号頁・発行日
- vol.86, no.4, pp.123-127, 2013-04-20 (Released:2013-07-20)
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 1 3
水酸基含有アクリル樹脂とイソシアネート硬化剤の混合物をモデル塗料として,140℃での硬化にともなう粘弾性変化を振り子式粘弾性測定装置で,反応率の変化をIR分析でそれぞれ測定した。その結果,相対貯蔵弾性率はS字型の変化を示し,イソシアネートと水酸基の反応は,初期の下に凸である部分では網目構造の生成とともに鎖延長反応にも費やされ,これに続く上に凸である部分では架橋生成のみに費やされると考えられた。このうち上に凸である部分では相対貯蔵弾性率とイソシアネートの反応率とは直線関係であった。このことから,塗膜の貯蔵弾性率は架橋密度に比例することがわかった。これはまた,振り子式粘弾性測定装置によって硬化中の架橋密度変化を実時間で観測できることも意味する。また架橋密度の増加に寄与しない反応が樹脂分子量から計算される理論値よりはるかに多いことがわかった。
1 0 0 0 OA 関係性攻撃の被害経験に対する認知と過剰適応傾向との関連
- 著者
- 森川 知美 茅野 理恵
- 出版者
- 信州大学大学院教育学研究科心理教育相談室
- 雑誌
- 信州心理臨床紀要
- 巻号頁・発行日
- vol.18, pp.41-50, 2019-06-01
大学生を対象に,過去の関係性攻撃の被害経験についての自責傾向と他責傾向を調査した。その結果,過去の関係性攻撃の被害を自責的に捉えている群のほうが他責的に捉えている群よりも過剰適応尺度の「自己不全感」において有意に得点が高いという結果となった。このことから,過去の関係性攻撃の被害経験を自責的に捉えることがその後の精神的健康に負の影響を及ぼす可能性があることが示唆された。学校現場における関係性攻撃による被害者への対応として,攻撃を受けた要因について自責的に捉えないような支援が必要であることが明らかとなった。
- 著者
- 森 勇太
- 出版者
- 関西大学国文学会
- 雑誌
- 国文学 (ISSN:03898628)
- 巻号頁・発行日
- no.104, pp.516-501, 2020-03
- 著者
- 森 茂暁
- 出版者
- 青木書店
- 雑誌
- 歴史学研究 (ISSN:03869237)
- 巻号頁・発行日
- no.861, pp.33-35, 2009-12
1 0 0 0 ライフヒストリーを基軸とした,中近世日本人骨の生物考古学的研究
目的:本研究では、日本人の死亡年齢構成の時代変化と気候変動の関係を探った。中世終わりから江戸時代にかけて小氷期による寒冷化が世界中で起き、ヨーロッパでは低身長化に見られるように健康状態が悪化したという。本研究では、弥生時代から江戸時代にかけて、古人骨の死亡年齢構成を復元することで、気候変動の影響が強かった中世から江戸時代の健康状態の変化を追跡した。方法:指標としたのは仙腸関節にある腸骨耳状面であり、若年個体では滑らかであるが高齢になると骨棘や孔が多く現れる。バックベリーらの腸骨耳状面に基づく死亡年齢の推定方法は、腸骨耳状面の溝、テクスチャー、骨棘、孔から1~7の7段階(数字が小さいほど骨が若い状態である)に分類し、その後年齢に対応させるという手順をとる。弥生時代、鎌倉・室町時代、江戸時代の古人骨を資料に、腸骨耳状面段階の構成を直接比較した結果:本研究では、弥生時代から江戸時代にかけての死亡年齢構成を復元し、時代による健康状態の変化を調査した。その結果、中世において短命のピークを迎え、江戸時代にかけて徐々に回復する傾向が明らかになった。考察:死亡年齢構成の時代推移と寒冷化の傾向は一致しなかった。その理由として、都市の衛生環境の改善や農耕技術の発展が挙げられる。しかし、その結果は気候変動が日本人の健康状態に影響を与えていないわけではない。江戸時代前期はストレスマーカー(クリブラ・オルビタリア)の頻度が最も高く低身長を特徴とする。死亡年齢構成と寒冷化が一致しない理由としては、むしろ自然災害や戦乱などにより、人骨の死亡年齢構成が若齢化したことが想定できる。
下層大気の気圧変動が重力音波モートで上空に伝搬し、電離層高度で反射され発生する約3分-4分周期の共鳴振動の存在が推測されている。当研究では、日食時の総合的観測から、重力音波共鳴の特性とそれが電離層や固体地球におよぼす効果を定量的に解明することを目的とした。微気圧観測システムをトカラ列島(諏訪瀬島、中之島)、桜島、および屋久島の京都大学防災研究所の関係施設4ケ所、沖縄・琉球大学瀬底実験所、および奄美大島北高等学校、上海近郊2ケ所の計8ケ所に皆既日食前に設置、観測を開始した。諏訪瀬島、中之島、および沖縄にはフラックスゲート磁力計、諏訪瀬島および中之島にはGPS受信機も設置した。また、沖縄および阿蘇火山研究センターにはHFドップラー観測用アンテナおよび受信装置を設置した。上海近郊で得られた微気圧観測データおよびHF-Doppler観測データには、明瞭な音波共鳴周期に対応するスヘクトルビークが検出された。また、上海近郊の地磁気観測所で得られた磁場観測データにも音波共鳴に対応する周期にピークが見られた。ただし、地上の微気圧データに見られたピークは基本共鳴周期(fundamental made=約265秒)であるのに対し、電離層高度の震動を見ていると考えられるHF-Doppler観測データや地磁気観測データには、第一高調波(first overtone=約225秒)にピークが現れた。これは、微気圧震動が、電離層高度での電磁気的震動と比較して、局在化しているためか、あるいは振幅の高度変化と電離周電気伝導度の高度変化との位置関係によるものではないかと推測される。トカラ諸島や沖縄、屋久島等で行った観測では、上記共鳴周期付近にスヘクトルピークが現れる傾向が見られたが、必ずしも明瞭ではなかった。また、広帯域地震計のデータには、皆既口食に対応すると考えられる振動は検出できなかった。
1 0 0 0 OA 千葉県市川市柏井町四丁目における不耕作農地の形成と農業経営
- 著者
- 森本 健弘
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 地理学評論 Ser. A (ISSN:00167444)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.9, pp.515-539, 1993-09-01 (Released:2008-12-25)
- 参考文献数
- 26
- 被引用文献数
- 5
本研究では,大都市周辺の集約的農業地域における不耕作農地の形成について,その実態と形成要因の解明を土地利用と個別経営の調査によって試みた.研究対象地域とした千葉県市川市柏井町四丁目では, 1970年代から兼業化・脱農化の一方,残存した専業農家・第1種兼業農家は経営の重点を施設園芸や梨栽培へ移してきた.この変化と並行して不耕作農地が形成され,台地では不耕作農地が施設と混在し,低地ではその大部分が不耕作農地となる景観が形成された.研究対象地域の農家による不耕作農地のおもな形成要因は,施設園芸や梨栽培への集約的な労働投入による農業労働力の相対的な不足であり,また田の環境の悪化,および農外就業の進展であった.不耕作農地の形成の基盤には,市街化調整区域における農地の転用規制,圃場条件の悪さ,農地地価の上昇と農地貸借の困難さがあった.研究対象地域以外の居住者へ所有権の移転した不耕作農地も多く存在した.この場合には,兼業化・脱農化がおもな形成要因であること,農地転用に伴う代替農地の取得が関与した事例の多いことが推測された.
1 0 0 0 OA 補綴歯科治療病名システムの信頼性と妥当性の検討
- 著者
- 松香 芳三 萩原 芳幸 玉置 勝司 竹内 久裕 藤澤 政紀 小野 高裕 築山 能大 永尾 寛 津賀 一弘 會田 英紀 近藤 尚知 笛木 賢治 塚崎 弘明 石橋 寛二 藤井 重壽 平井 敏博 佐々木 啓一 矢谷 博文 五十嵐 順正 佐藤 裕二 市川 哲雄 松村 英雄 山森 徹雄 窪木 拓男 馬場 一美 古谷野 潔
- 出版者
- 公益社団法人 日本補綴歯科学会
- 雑誌
- 日本補綴歯科学会誌 (ISSN:18834426)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.3, pp.281-290, 2013 (Released:2013-11-06)
- 参考文献数
- 3
- 被引用文献数
- 2 1
目的:(社)日本補綴歯科学会は病態とその発現機序の把握に基づく適切な補綴歯科治療を国民に提供するために,補綴歯科治療における新たな病名システムを提案した.これは患者に生じている「障害」を病名の基本とし,この障害を引き起こしている「要因」を併記して病名システムとするものであり,「A(要因)によるB(障害)」を病名システムの基本的な表現法としている.本研究の目的は考案した方法に従って決定した補綴歯科治療における病名の信頼性と妥当性を検討することである.方法:模擬患者カルテを作成し,(社)日本補綴歯科学会診療ガイドライン委員会で模範解答としての病名(以下,模範病名)を決定した.その後,合計50 名の評価者(日本補綴歯科学会専門医(以下,補綴歯科専門医)ならびに大学病院研修歯科医(以下,研修医))に診断をしてもらい,評価者間における病名の一致度(信頼性)ならびに(社)日本補綴歯科学会診療ガイドライン委員会による模範病名との一致度(妥当性)を検討した.結果:評価者間の一致度を検討するための算出したKrippendorff’s αは全体では0.378,補綴歯科専門医では0.370,研修医では0.401 であった.Krippendorff’s αは模範病名との一致度の高い上位10 名の評価者(補綴歯科専門医:3 名,研修医:7 名)では0.524,上位2 名の評価者(補綴歯科専門医:1 名,研修医:1 名)では0.648 と上昇した.日常的に頻繁に遭遇する病名に関しては模範病名との一致度が高かったが,日常的に遭遇しない病名は模範病名との一致度は低い状況であった.さらに,模範病名との一致度とアンケート回答時間や診療経験年数の関連性を検討したところ,相関関係はみられなかった.結論:全評価者間の一致度を指標とした本病名システムの信頼性は高くはなかったが,模範病名との一致度の高い評価者間では一致度が高かった.日常的に遭遇する補綴関連病名については模範病名との一致度が高かった.以上から(公社)日本補綴歯科学会の新しい病名システムは臨床上十分な信頼性と妥当性を有することが示唆された.
1 0 0 0 阪神 淡路大震災に係る都市公園緊急利用実態調査
1 0 0 0 OA 学生食堂におけるヘルシー定食提供の試み
- 著者
- 森脇 弘子 山崎 初枝 前大道 教子
- 出版者
- 一般社団法人 日本調理科学会
- 雑誌
- 日本調理科学会誌 (ISSN:13411535)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.6, pp.359-365, 2010 (Released:2014-08-22)
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 1
本研究では,学生食堂でヘルシー定食を提供し,より健康的な学生食堂のメニューについて検討することを目的とした。ヘルシー定食を食事バランスガイドより検討した結果,副菜が多かった。ヘルシー定食を日本人の食事摂取基準2005より検討した結果,カルシウム量が少なかった。「ヘルシー料理を今後も利用したい」と回答した者は93.8%で,その理由をテキストマイニング手法により集計した結果,「おいしい」,「バランス」,「良い」という言葉が高頻度で出現した。これらのことより,ヘルシー定食は,カルシウムの摂取量を増やす献立を作成することが課題であることがわかった。喫食者からの評価が極めて高く,この試みを日常の学生食堂のメニューに生かしていきたい。
- 著者
- 増田 朋美 青山 和宏 森永 敦樹 山本 武寿 天羽 康
- 出版者
- 愛知教育大学附属高等学校
- 雑誌
- 研究紀要 (ISSN:09132155)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, pp.53-67, 2016-03-31
現在、「データの分析」は、知識の伝達だけに偏らず、学ぶことと社会とのつながりをより意識した指導が期待されている。一方、高等学校教育課程としては約40年ぶりに導入された本単元には、現場からの戸惑いの声も多く、まだまだ課題が山積している。そこで本研究では、基礎的な知識・技能の習得することとともに実社会や実生活の中でいきる統計的思考力を育成することを目標に、テクノロジー活用を前提とした多変数のデータセットからなる教材を開発し、実践した。本教材を生徒たちがどう学習したか、その様相を明らかにすることを通して、「学ぶ統計」から「使う統計」へ、学習の転換を提案したい。
1 0 0 0 OA 衛生新篇
- 著者
- 森林太郎, 小池正直 著
- 出版者
- 南江堂[ほか]
- 巻号頁・発行日
- vol.明治29年, 1897
1 0 0 0 妊娠中に暴言を受けると新生児の聴覚に影響するか?
- 著者
- 八木 光晴 福森 香代子 小山 耕平 森 茂太 及川 信
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.1, pp.103-112, 2013-03-30 (Released:2017-04-28)
- 参考文献数
- 97
- 被引用文献数
- 5
生物の個体当たりのエネルギー代謝速度と個体サイズ(体サイズ)の関係(代謝スケーリング:metabolic scaling)を探る研究の歴史は古く、生理学、生態学、農学、水産学や薬理学など様々な学問の基礎をなしてきた。代謝スケーリング関係には、異なる体サイズを示す種の集団(代謝速度の系統発生)を対象とする場合と、ある種における様々な体サイズからなる個体の集団(代謝速度の個体発生)を対象とする場合とがある。過去の研究の多くは、哺乳類や鳥類などの代謝速度の系統発生を対象としてきており、代謝速度の個体発生は無視されるか、代謝速度の系統発生と同じであるかのように曖昧に扱われてきた。その一方で、代謝速度の系統発生と代謝速度の個体発生の生物学的な意味は明確に異なっており、両者は厳密に区別されるべきとの指摘もなされてきている。そこで本論では、代謝速度の系統発生と個体発生の違いの整理を試みる。さらに、代謝速度の個体発生が、これまで生態学において重視されてきた「食う-食われるの関係」をはじめとする生物間相互作用と密接に関係し合っていることの実証例を紹介し、今後の研究の方向性について議論する。
1 0 0 0 OA 多量の水を含むNa2O・3SiO2ガラスのガラス転移点
- 著者
- 友沢 稔 高田 雅介 John ACOCELLA E. Bruce WATSON 高森 剛
- 出版者
- 公益社団法人 日本セラミックス協会
- 雑誌
- 窯業協會誌 (ISSN:00090255)
- 巻号頁・発行日
- vol.91, no.1056, pp.377-383, 1983-08-01 (Released:2010-04-30)
- 参考文献数
- 31
- 被引用文献数
- 7 9
約8wt%までの水を含むNa2O・3SiO2ガラスを高温高圧下で合成し, そのガラス転移点 (Tg) をDTA法により測定した. ガラス中の水はTgより高温で発泡を伴って溶離した. ガラス転移点と発泡温度はともに含水量の増加につれて減少した. 含水量の変化に対するガラス転移点の変化を高分子の可塑剤に対する種々の方程式と比較し, OHと分子状H2Oの両方の寄与を考慮に入れた方程式により, 最もよく記述されることを見出した. OHはTgを急激に下げ, 一方分子状H2Oは単にガラスを薄める効果によりわずかにTgを下げることが結論付けられた.
1 0 0 0 IR ソクラテス以前哲学者の解明 : DK.断片とカント
- 著者
- 森 哲彦
- 出版者
- 名古屋市立大学大学院人間文化研究科
- 雑誌
- 名古屋市立大学大学院人間文化研究科人間文化研究 (ISSN:13480308)
- 巻号頁・発行日
- no.18, pp.167-192, 2012-12
ヨーロッパ哲学は、古代ギリシアに始まる。古代ギリシア哲学の3つの時期区分のうち、ホワトヘッドは「プラトン的」立場から、プラトンを含む第二期に注目し、第一期のソクラテス以前哲学者達を顧慮しない。これに対し、第一期ソクラテス以前哲学者達を高く評価する哲学者達が、数名挙げられる。本論では、西洋哲学の起源は、その哲学者達が指摘するように、第一期ソクラテス以前哲学者達に有ると考え、それらの第一期哲学者達の解明を、試みるものである。なお本論では、副題で示すように、ディールス-クランツ『断片』とカント批判哲学の論述を用いるものとする。本論文の構成について、哲学の兆候を示す哲学以前、前期自然哲学で自然の原理を問うミレトス学派、また別個にピュタゴラス学派、ヘラクレイトスを取り上げる。更に存在と静止のエレア学派、後期自然哲学の多元論と原子論、そして認識論のソフィスト思潮の特質をそれぞれ論述する。この試論は、「哲学的自己省察」の一つである。
1 0 0 0 OA 個人の自転車利用履歴が違法駐輪に及ぼす影響に関する研究
- 著者
- 山下 晴美 古池 弘隆 森本 章倫
- 出版者
- Japan Society of Civil Engineers
- 雑誌
- 土木計画学研究・論文集 (ISSN:09134034)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, pp.539-544, 2004-09-30 (Released:2010-06-04)
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 1 1
わが国における放置自転車問題は深刻化している。そこで今後の取り組みとして個人が自転車を放置しないという意識を持たせる事も重要であると考えられる。よって本研究では、アンケート対象者を自転車利用頻度の高い高校生とし、自転車放置行為を抑制する意識が、成長過程においてどのように形成されているかについて検討を行う。結果として二つの意識の形成が重要であると分かった。マナー意識を持たせることとルールの遵守の心を持たせることである。特にルールの遵守のためには自転車利用範囲の限定経験や自転車利用時にヘルメットの着用経験をすることが重要であることが分かった。これらの経験が有る人は違法駐輪しない傾向にある。
1 0 0 0 OA 膝関節痛と Hamstrings Tightness
- 著者
- 七森 和久 鳥巣 岳彦 長井 卓志 村重 光哉
- 出版者
- West-Japanese Society of Orthopedics & Traumatology
- 雑誌
- 整形外科と災害外科 (ISSN:00371033)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.3, pp.1050-1054, 1987-04-25 (Released:2010-03-16)
- 参考文献数
- 4
Among the patients visiting our clinic complaining of gonalgia, those who had pain around the patella, compression pain of the patella, but no other symptoms, exhibited hamstring tightness.We had them do hamstring stretching exercises, and followed the changes in the gonalgia and hamstring tightness.To examine the hamstring tightness, the angle of knee flexion was measured with a goinometer after passive knee extension with the hip flexed to 90 degree.In 10 cases involving 13 joints, pain around the patella or compression pain of the patella was relieved with the decrease in the hamstring tightness following the stretching exercises.