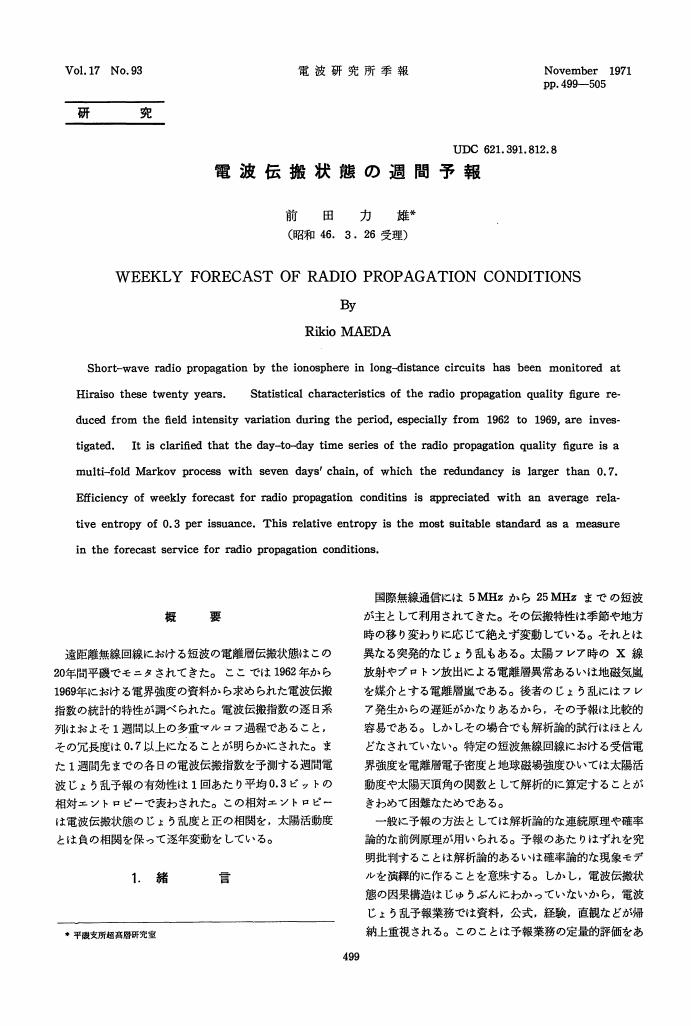1 0 0 0 IR マナス(こころ)の原風景〈下〉 ――『リグ・ヴェーダ』・トリックスターの誕生――
- 著者
- 久保田 力
- 巻号頁・発行日
- 1993-04-01
1 0 0 0 IR サハリン交流研究の成果と展望
- 著者
- 浅尾 秀樹 須田 力
- 出版者
- 北海道女子大学北方圏生活福祉研究所
- 雑誌
- 北方圏生活福祉研究所年報 = Bulletin of Northern Regions Research Center for Human Service Studies (ISSN:1342761X)
- 巻号頁・発行日
- no.4, pp.23-27, 1998
「近くて遠い国」ロシア,サハリンと北海道の中高齢者を対象とした比較研究を始めて6年が経過した。前半の3年では共同研究体制づくりが課題であり,後半の3年はユジノ・サハリンスク市の住民を対象とした調査・測定やシンポジウムなどによる研究活動であった。ロシア国立ユジノサハリンスク教育大学(現サハリン大学)の体育教員スタッフとの研究交流を積み上げて今日に至った。これらについて, AOC生涯学習センター公開講座「生活を科学する(雪国の人々の健康)」などで報告してきたが,これまでの成果と今後の展望について紹介する。I,生活福祉に立った研究の推進2,共同研究体制の確立3,北海道女子大学生涯学習システム学部の役割と今後の展望
1 0 0 0 きく6号の楕円軌道における通信実験の概要
- 著者
- 原田 力 高畑 博樹 北原 弘志
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会技術研究報告. SANE, 宇宙・航行エレクトロニクス
- 巻号頁・発行日
- vol.95, no.213, pp.51-58, 1995-08-23
- 被引用文献数
- 3
技術試験衛星VI型(ETS-VI)は、平成6年8月28日に種子島宇宙センターからH-IIロケットにより打上げられ、トランスファー軌道投入後「きく6号」と名付けられた。きく6号は、2トン級の静止三軸衛星として開発されたが、アポジエンジンの噴射異常により静止軌道に到達することができず長楕円軌道を周回することとなった。きく6号は衛星間通信用の機器を搭載しているが、地上との通信のためのアンテナは静止衛星対応で固定であるため、楕円軌道に置いては通信回線を確立することができないものであったが、搭載コンピュータのソフトウェアを書き換えることにより、楕円軌道上における通信を可能にした。本論文では、楕円軌道上における通信の問題点を明らかにし、それを克服し通信実験を実現するための方法を紹介し、併せて実験の評価結果を報告する。
1 0 0 0 調理条件を変えることによる小麦粉調理品中の抗原量の変化
- 著者
- 赤石 記子 舛田 美和 岩田 力 長尾 慶子
- 出版者
- 一般社団法人 日本調理科学会
- 雑誌
- 日本調理科学会誌 = Journal of cookery science of Japan (ISSN:13411535)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.3, pp.231-235, 2013-06-05
- 参考文献数
- 22
本研究では小麦粉製品として代表的なパンとソースを取り上げ,小麦アレルギー患者でも食べられる調理条件を追究した。市販キット(FASPEK)を使用し,抗原量を測定し,低アレルゲン化の指標とした。パンの調製条件は一般的に使用されているドライイーストを対照に,米麹,ヨーグルトをスターターとして得られる発酵液を小麦粉に加え,パンを調製した。ソースの調製条件はルウの加熱温度を非加熱,120℃,160℃,210℃とした。その結果,ドライイーストパンに比べヨーグルト発酵液を用いて中種法で調製したパンで抗原量は有意に低下した。ルウの調製条件を変えたソースではブールマニエ(非加熱試料)に比べブラウンソース(210℃加熱試料)で抗原量は有意に低下していた。スペルト小麦で調製したブラウンソースが特に低値を示した。
1 0 0 0 IR 大学生の身体活動と体力の発達
- 著者
- 須田 力 室木 洋一
- 出版者
- 北海道大學教育學部
- 雑誌
- 北海道大学教育学部紀要 (ISSN:04410637)
- 巻号頁・発行日
- no.48, pp.p161-185, 1986
- 著者
- 須田 力 穆 子彦 室木 洋一
- 出版者
- 一般社団法人 日本体育学会
- 雑誌
- 体育学研究 (ISSN:04846710)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.4, pp.359-370, 1992
The purpose of this study was to investigate physical activity levels of Chinese students in comparison with Japanese students. First, a questionnaire on exercise habits was distributed among the students of 4 universities in China and 6 national unversities in Japan. Answers were obtained from 1,262 Chinese students (771 males and 491 females) and 1,409 Japanese students (1,282 males and 127 females). Second, eighteen healthy male students (9 Chinese and 9 Japanese) who did not participate in athletic clubs were selected as subjects for the measurement of daily activity levels. The heart rate of the subjects were recorded daily during the daytime by using Heart Rate Memory (TKK Instrument Co.). Measurements were taken both in China and Japan to determine the heart rate levels of each subjects and these were compared to the %V^^.O_2 max of different workload levels determined by a Monark ergometer. The results are summarized as follows: 1. The Chinese students tended to engage in exercise more than Japanese students in that (1) fewer complained about lack of exercise, and (2) a higher percentage of the population exercised habitually. Nevertheless, they did not have sufficient oppotunities for sports activity judging from the facts that (1) they had shorter exercise period (2) a lower rate of the population participated in athletic clubs and (3) fewer had experiented sufficient amount of exercise. 2. Although, in general; the Chinese subjects revealed higher rates of activity level exceeding 7O %V^^.O_2 max than the Japanese subjects, the durations of their exercise periods did not allow them to attain an essential time to improve aerobic power, except for one subject; while none of the Japnnese subjects fulfilled these conditions.
1 0 0 0 848 北海道出身北大生の持久性不足について
1 0 0 0 学生時代から31-33年後の体力
- 著者
- 須田 力 室木 洋一 中川 功哉 安藤 義宣 西薗 秀嗣 吉田 敏雄
- 出版者
- 一般社団法人 日本体育学会
- 雑誌
- 体育学研究 (ISSN:04846710)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.4, pp.255-265, 1988
The purpose of this study was to evaluate the maintenance of fitness with aging. The subjects were 59 men of 49-55 years of age, who entered to Hokkaido University and once had been examined for their fitness between the years of 1950-1952. They were reexamined to determine the maintenance of fitness with age in 1983. After 31-33 years, declination of the mean values in fitness shows from 50.9 to 42.1cm in vertical jump, from 154 to 143kg in back strength, from 4.35 to 3.73L in vital capacity and from 8.4 to 3.2 times in pull-ups. Grip strength was increased from 44.0 to 47.1kg. The correlation coefficients of the values between the time they were freshmen and the present time, were relatively higher in vertical jump (r=0.61, p<0.01), moderatory higher in back strength (r=0.50, p<0.01), grip strength (r=0.48, p<0.05) and vital capacity (r=0.46, p<0.05), but lower in pull-ups (r = 0.17, not significant). Back strenght and grip strength were maintained better in a group who had been engaged in daily physical activity than those who had been inactive. But the differences in the rate of decline were not significant in vertical jump; pull-ups and vital capacity. It was noticed that 14 (23.7%) of the 59 subjects indicated that walking was felt to be the most effective factor to maintain fitness.
1 0 0 0 堀田力氏(いんたびゅー-6-)
- 著者
- 堀田 力 松浦 弘行
- 出版者
- 第一法規
- 雑誌
- 労働時報 (ISSN:13425277)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.11, pp.p32-35, 1993-11
1 0 0 0 OA 除草剤抵抗性雑草の進化生態学的研究の現状と今後の展望
- 著者
- 林 薫 三舟 求真人 七条 明久 鈴木 博 松尾 幸子 牧野 芳大 明石 光伸 和田 義人 小田 力 茂木 幹義 森 章夫
- 出版者
- 長崎大学熱帯医学研究所
- 雑誌
- 熱帯医学 (ISSN:03855643)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.3, pp.p129-142, 1975-12
1973年2月3日から18日の間,新生成虫が検出されない時期に野外で捕集した冬期のコガタアカイエカ1083個体,8プールから4株のウイルスを分離し,日本脳炎(日脳)ウイルスと同定された.この事実は,越年蚊体内でウイルスが持ち越されたものと考えられる.そして1973年には年間を通じて,蚊一豚の感染環が証明され,奄美大島,瀬戸内地域における日脳ウイルスの特異な撒布状況が観察された.この所見は我国で初めてのことである.しかしながら,1974年では,コガタアカイエカから7月上旬にはじめてウイルスが分離されると共に,これと平行して豚の新感染も同時に証明された.この事は蚊一豚の感染環,特に蚊によるウイルスの越年が中絶したことを意味すると共に,奄美大島の調査地域へのウイルスの持込みがあったに違いないことを物語るものであろう.換言すれば,奄美大島の調査地域では環境条件さえよければウイルスの土着が可能であるが,条件が悪いと蚊によるウイルスの越年は中絶し,流行期に再びウイルスの持込みが行われるであろうことを推定してよいと思われる.1973年7月24日夜半から25日未明にかけて奄美大島名瀬港及び鹿児島港の中間の海上で,船のマスト上にとりつけられたライトトラップ採集でコガタアカイエカ数個体を捕集した.この事実はコガタアカイエカが洋上を移動していることを意味しているものと考えられる.1975年7月下旬,奄美大島から鹿児島(九州南域)に向け,標色コガタアカイエカの分散実験を試みたが,遇然に実験地域を通過した台風2号で阻止され不成功に終った.しかし,分散実験日の約10日前にフイリッピンからの迷蝶が鹿児島南端に到達していることから気流によるコガタアカイエカの移動は決して否定出来ない.
1 0 0 0 OA 急性肝不全患者における特殊組成アミノ酸製剤投与による肝性脳症増悪の危険性
- 著者
- 井上 和明 与 芝真 関山 和彦 黄 一宇 藤田 力也
- 出版者
- 一般社団法人 日本肝臓学会
- 雑誌
- 肝臓 (ISSN:04514203)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.7, pp.401-407, 1995-07-25 (Released:2009-07-09)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 2 1
肝性脳症用特殊組成アミノ酸輸液(Fischer液)が劇症肝炎の予後を悪化させると報告されている.今回同液がurea cycle機能の障害の強い急性重症肝障害例の臨床症状とN処理能に与える影響を知る目的で,劇症肝炎3例,急性肝炎重症型1例にFischer液500mlを2時間で点滴静注し,投与前後での臨床症状,血中の尿素,アンモニア(NH3),グルタミン(Gln),アラニン(Ala)の各値の推移を検討した.一旦肝性脳症から完全に覚醒した劇症肝炎亜急性型の1例で投与後昏睡0度からIV度に悪化し,1例はIV度のまま不変,回復期の2例は0度だがnumber connection testが悪化した.全例で投与直後に血中NH3, Gln, Alaの異常高値が認められ,尿素生成の不良な2例では高値が持続した.urea cycle機能の高度に障害された急性重症肝障害例では他のN処理系を含めたN処理能を上回った量のアミノ酸輸液を行った場合,Fischer液の形でもNH3を増加させ,脳症を悪化させる危険がある.
1 0 0 0 OA ドイツにおける住民参加のまちづくり ―ハイデルベルク,フライブルク,ベルリンの事例―
- 著者
- 由井 義通 フンク カロリン 川田 力
- 出版者
- 日本都市地理学会
- 雑誌
- 都市地理学 (ISSN:18809499)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.46-56, 2007-03-15 (Released:2020-03-11)
- 参考文献数
- 12
Im Rahmen der Diskussion um eine bürgernahe Stadtentwicklung wird im Japanischen häufig das Wort machizukuri verwendet. Wörtlich bedeutet es, eine Stadt/ eine Stadtteil/ eine Nachbarschaft zu kreieren, herzustellen. Es umfasst sowohl städtebauliche Maßnahmen für eine hohe Wohnqualität und ein attraktives Stadtbild als auch soziale Bereiche wie Kommunikation und Kooperation innerhalb der Nachbarschaft sowie zwischen Bürgern und Verwaltung. In diesem Beitrag werden Beispiele aus den deutschen Städten Freiburg, Heidelberg und Berlin vorgestellt, wo Bürger bereits im Planungsstadium an Stadtentwicklungsprojekten beteiligt werden oder sich in Form eines Quartiersmanagements in der Verbesserung des Wohnumfeldes engagieren. An hand dieser Beispiele werden Probleme und Möglichkeiten aktiven Bürgerengagements in der Stadtentwicklung analysiert, um daraus Hinweise für die zukünftige Gestaltung der Stadtentwicklung in Japan zu gewinnen.
1 0 0 0 OA 和漢生薬の血液凝固学的研究, 特に艾葉の抗凝固能について
- 著者
- 桜川 信男 湯浅 和典 近藤 信一 丹羽 正弘 横田 力
- 出版者
- The Japanese Society on Thrombosis and Hemostasis
- 雑誌
- 血液と脈管 (ISSN:03869717)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.2, pp.228-230, 1983-06-01 (Released:2010-08-05)
- 参考文献数
- 5
Crude drugs of Wakan-Yakus (traditional herbal drugs) such as Gaiyoh (Artemisiae folium), Sanshishi (Gardeniae fructus), Taiso (Zizyphi fructus), Kizutsu (Aurantii fructus immaturus) and Akyoh (Glutinum) were investigated to analyse the effects on blood coagulation system.(1) Gaiyoh (Artemisiae folium) showed the effects of anticoagulant, antifibrinolytic and anti-platelet aggregation, and the anticoagulant effect was strong prominently. When the crude drug of Gaiyoh was purified by the Sephadex G-100 column chromatography, four peaks were found. The strong antocoagulant effect was found to the third peak. We settled “Inhibition unit” of Gaiyoh from statistic studies, and 2.5mg/ml of Gaiyoh in the final concentration was evaluated to be 10 inhibition units.(2) Sanshishi (Gardeniae fructus) showed strong fibrinolytic effect characteristically.
1 0 0 0 OA 043G01 『アルペンスキー滑降競技・公式練習』における筋電図的研究
- 著者
- 加藤 満 須田 力 川初 清典
- 出版者
- 社団法人日本体育学会
- 雑誌
- 日本体育学会大会号
- 巻号頁・発行日
- no.40, 1989-09-10
- 著者
- 川田 力
- 出版者
- 地理科学学会
- 雑誌
- 地理科学 (ISSN:02864886)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.3, pp.137-146, 2007-07-28 (Released:2017-04-15)
- 参考文献数
- 24
1 0 0 0 IR 記号放逐法によるイエバエの分散実験
- 著者
- 小田 力
- 出版者
- 長崎大学風土病研究所
- 雑誌
- 長崎大学風土病紀要 (ISSN:00413267)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.3, pp.136-144, 1966-10
長崎県大瀬戸町松島の外平部落(115戸)で1961年9月(実験1)に,長崎市郊外の六枚板部落(27戸)で同年10月(実験2)に,及び外平部落で1963年7月(実験3)に,計3回の記号放遂法によるイエバエの分散実験を行なった.放遂バエは25℃の実験室で飼育,羽化後4~6日目のもので,放遂前24時間, P^<32>を含む餌を与えて記号を附し,更に実験3では3ケ所から略同時に放遂したハエを区別できるように,3種類の色素の2%水溶液を噴霧した.放遂後6日間毎日(実験2では放遂後1, 2, 3, 5, 8日に),屋内に設置したハエトリガミとハエトリリボンに附著した記号バエ数及び無記号バエ数を記録した.これらの実験結果から次のことがわかった.1.記号バエの回収数は,放遂後の日数の経過に伴なって減少する.2.記号バエは一般に放遂場所に近い人家で多く回収されるが,放遂場所からの距離が同じ場合には,無記号バエの採集数から判断して,屋内への侵入が容易でありハエの餌が散在している,人家で,回収バエが多く得られる.3.記号バエの分散距離は,放遂地点が人家に囲まれている場合には短かく,放遂地点の一方にのみ人家がある場合や,特に放逐地点が人家から離れている場合には長い.4.イエバエの分散には,ランダムな行動に基づく比較的小規模の分散と,分散飛翔とも呼ぶべきものによる,より規模の大きい分散とがあると推測され,後者は,放遂地点が人家と畠地や荒地との境にある場合や,人家から離れている場合に見られるようである.Dispersal experiments with Musca domestica vicina were conducted by a mark-and-release technique at Hokabira Village (115 houses) in a small island, Nagasaki Prefecture in September 1961 (Exp. 1), at Rokumaiita Village (27 houses) near Nagasaki City in Oc
1 0 0 0 OA 岩石鉱物学・地質学的にみた骨材の選択
- 著者
- 丸 章夫 柳田 力
- 出版者
- 公益社団法人 日本コンクリート工学会
- 雑誌
- コンクリート工学 (ISSN:03871061)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.11, pp.85-89, 1981-11-15 (Released:2013-04-26)
- 参考文献数
- 12
1 0 0 0 OA 電波伝搬状態の週間予報
- 著者
- 前田 力雄
- 出版者
- 国立研究開発法人 情報通信研究機構
- 雑誌
- 情報通信研究機構研究報告 (ISSN:2187767X)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.93, pp.499-505, 1971 (Released:2019-08-31)
1 0 0 0 OA 金星気球のモデル試験
- 著者
- 西村 純 矢島 信之 藤井 正美 横田 力男 Nishimura Jun Yajima Nobuyuki Fujii Masami Yokota Rikio
- 出版者
- 宇宙科学研究所
- 雑誌
- 宇宙科学研究所報告. 特集: 大気球研究報告 (ISSN:02859920)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, pp.13-19, 1990-12
この論文では金星大気の運動や組成を観測する金星気球を開発するため, 金星気球のモデル試験の方法を提案する。金星浮遊気球としては, いくつかの形態が提唱されてきたが, ここでは適当な液体をつめた相転移気球について詳しく検討する。金星大気の主成分は炭酸ガスで, 高度が下がるとともに温度が上昇するので, 気球内に入れた液体が蒸発して浮力を生ずる。ある高度を境として蒸発と液化が起こるので, 気球は一定高度に安定に浮遊することができる。金星大気から金星気球への熱伝達について詳しく解析するとともに, 温度勾配をつけた小型の水槽にモデル気球を浮かべて, 相転移気球の試験を行えることを実証した。