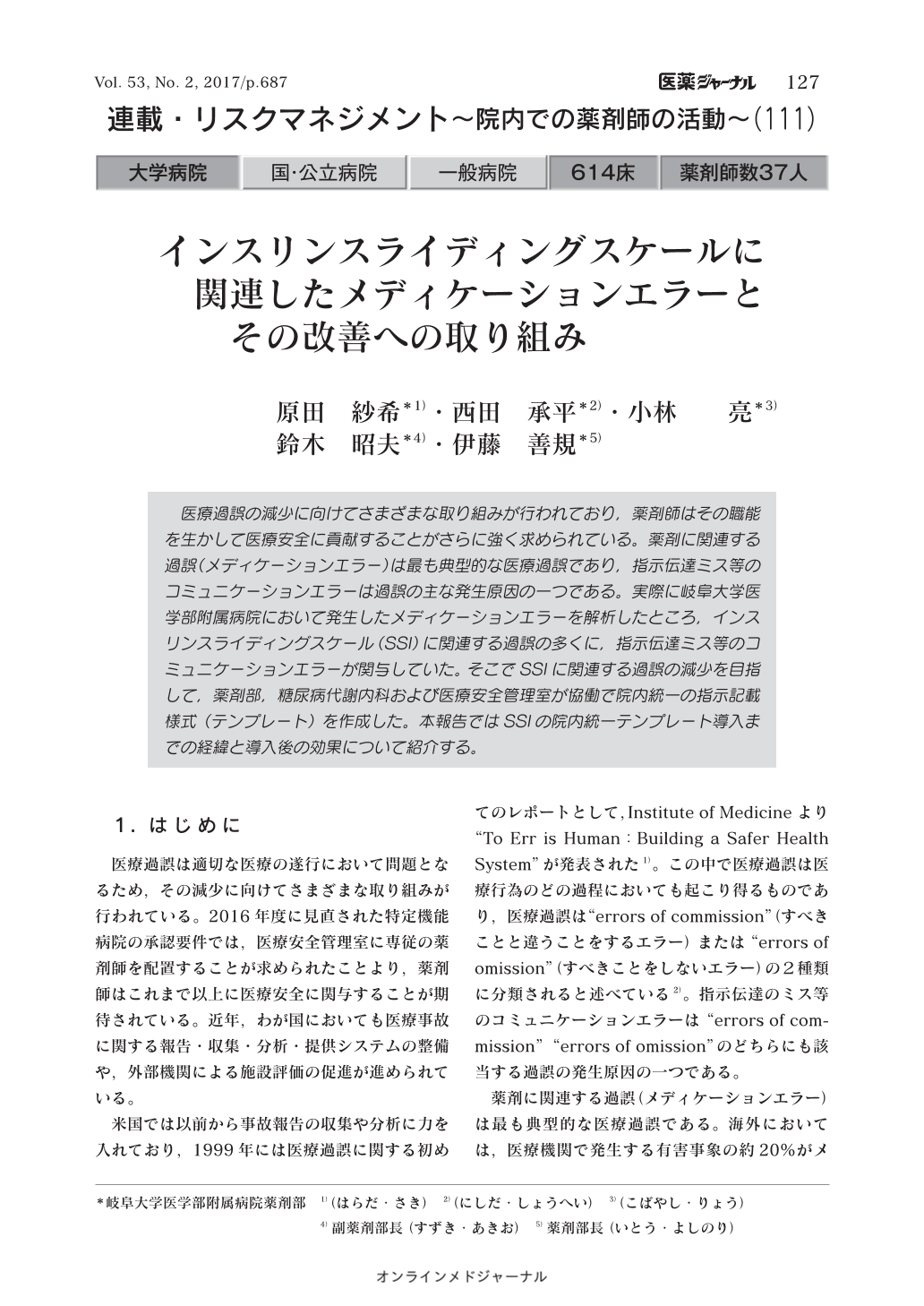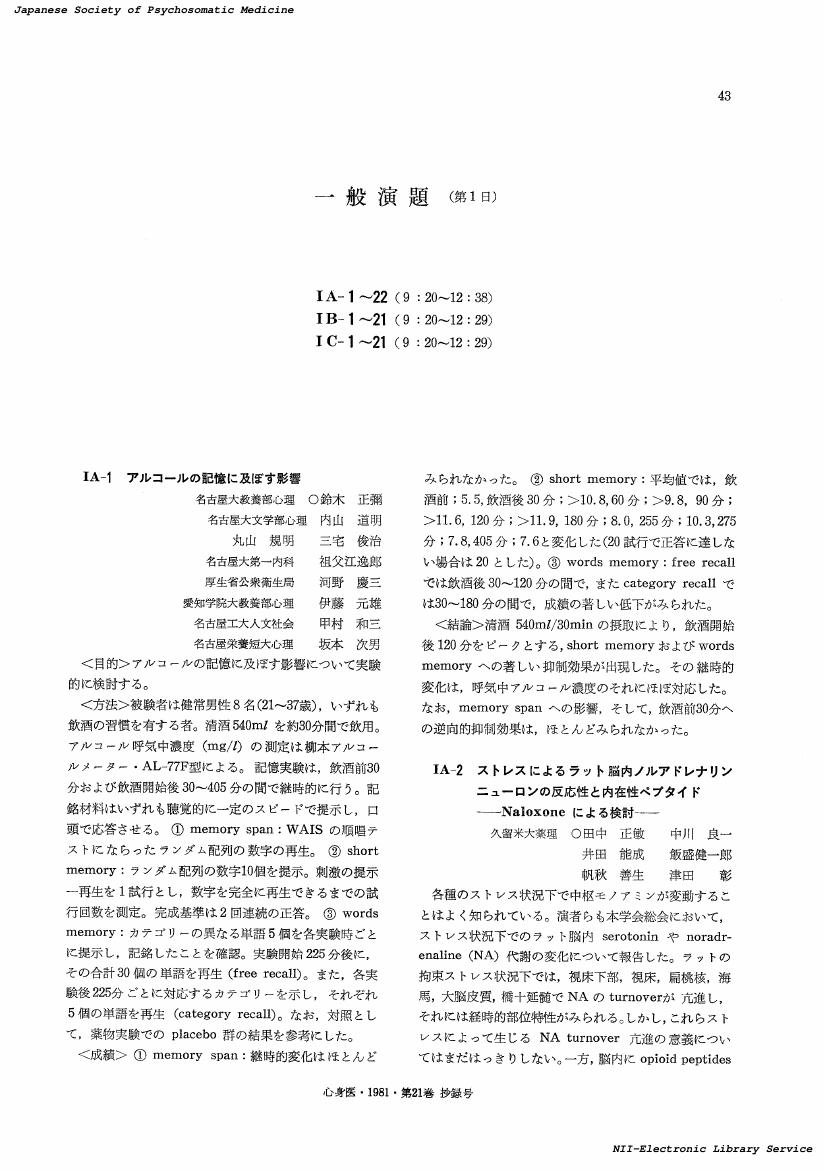1 0 0 0 黒耀石産地推定分析からみた長野県矢出川1遺跡出土細石核の構成
- 著者
- 島田 和高 鈴木 尚史 飯田 茂雄 杉原 重夫
- 出版者
- 明治大学
- 雑誌
- 明治大学博物館研究報告 (ISSN:13420941)
- 巻号頁・発行日
- no.11, pp.1-28, 2006-03
Yadegawa sites, which have yielded many localities of microblade assemblage are located at Minamimaki village, Minami-saku county, Nagano prefecture. Microblade industries are distributed widely throughout Japan in the final stage of Late Paleolithic period. In Yadegawa sites, Yadegawa I site is a place of the first discovery that maicroblade industry exists in Japan in 1954. Afterward, Yadegawa I site was excavated twice in 1954 and 1963, and assemblages composed of microblades, microcores, scrapers and flakes and chips were recovered. Now the mass of them are garnered at Meiji University Museum. In this article, we would report a result of obsidian source analysis by using X-ray fluorescent (EDXRF). The materials are thirty-nine microcores excavated at Yadegawa I site. The analysis of EDXRF was operated at Meiji University Cultural Properties Laboratory. As a result of analysis, it proves that seventeen of microcores are identified with obsidian that came from Onbase Island, nine from Tsumetayama/Mugikusa pass, six from west Kirigamine, two from Wada pass/Takayama, one from Omekura and four were not identified. Onbase Island is situated in the Pacific at a distance of about 50km from the edge of Izu peninsula. Of course some kinds of the voyage technology might had existed for obsidian transportation from the Pacific to the main land. In addition, it has a distance of about 150km from the edge of Izu peninsula to Yadegawa sites. Other obsidian sources mentioned earlier are located at the central highlands in Nagano prefecture, the region of which is close to Yadegawa sites westward beyond Yatsugatake mountain range. It has a distance of about 20-40km. Based on these results, we attempted to do comparative studies in the technology and the form of microcores between those made from "exotic obsidian" and from "local obsidian". A category of "Ryo-chu type microcore" is applicable to them likewise. When "exotic obsidian" and "local obsidian" are compared in this context, some distinct chracteristics become apparent as follows. Whereas thick flakes are applied to microcores made from "exotic obsidian" as blanks, the numbers of microcores made from "local obsidian" were manufactured from small size of obsidian rocks directly. This represents that the differences of obsidian source bring large varieties into the technology and the form of "Ryo-chu type" microcores. In addition, this implicates the existence of a complex obsidian circulation network between areas of the mountain and the ocean in the final stage of Japanese Late Paleolithic period as well.
医療過誤の減少に向けてさまざまな取り組みが行われており,薬剤師はその職能を生かして医療安全に貢献することがさらに強く求められている。薬剤に関連する過誤(メディケーションエラー)は最も典型的な医療過誤であり,指示伝達ミス等のコミュニケーションエラーは過誤の主な発生原因の一つである。実際に岐阜大学医学部附属病院において発生したメディケーションエラーを解析したところ,インスリンスライディングスケール(SSI)に関連する過誤の多くに,指示伝達ミス等のコミュニケーションエラーが関与していた。そこでSSIに関連する過誤の減少を目指して,薬剤部,糖尿病代謝内科および医療安全管理室が協働で院内統一の指示記載様式(テンプレート)を作成した。本報告ではSSIの院内統一テンプレート導入までの経緯と導入後の効果について紹介する。
- 著者
- 鈴木 素子
- 出版者
- 素粒子論グループ 素粒子論研究 編集部
- 雑誌
- 素粒子論研究 (ISSN:03711838)
- 巻号頁・発行日
- vol.105, no.2, 2002
1 0 0 0 OA IA-1 アルコールの記憶に及ぼす影響(神経薬理・化学)
1 0 0 0 放射線照射による持続的老化様増殖停止の誘導と生物学的意義
- 著者
- 鈴木 啓司 鈴木 正敏
- 出版者
- Journal of Radiation Research 編集委員会
- 雑誌
- 日本放射線影響学会大会講演要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.2010, pp.19, 2010
放射線照射により細胞死が引き起こされることは広く知られた事実であるが、その死の分子メカニズムについては未だに不明な点が多い。我々は、特に付着系の細胞で、非アポトーシス性の細胞死が、放射線による主要な細胞死のモードであることを報告してきた。正常ヒト二倍体細胞を用いた実験から、放射線照射後に残存するDNA損傷が持続的にATM-p53経路依存的G1チェックポイントを活性化し、その結果、細胞はG1アレストの持続を経て老化様形質を発現するようになる。一方、がん細胞でも、放射線照射による老化様増殖停止の誘導が確認された。従来、がん細胞では放射線によるアポトーシスの誘導が報告されるが、その割合は細胞の致死率を説明できる程高くはなく、非アポトーシス性の細胞死モードとして老化様増殖停止が注目されるようになってきた。がん細胞では、G1アレストが十分に誘導されず、またG2アレストの持続にも異常があることから、多くの細胞はDNA二重鎖切断をもちながら細胞分裂期に入っていく。その結果、染色体断片や染色体架橋が生じ、このような細胞は分裂異常、いわゆるmitotic catastrophe(MC)を起こす。MCを起こした細胞は多くが細胞分裂を完遂できず、微小多核細胞などになって次のG1期に留まる。これ以外にも、細胞分裂を経ずに細胞周期を進行させた細胞は、巨核細胞になってG1期に留まり、いずれの場合も、この過程で老化様増殖停止を誘導することが明らかになった。以上のように、老化様増殖停止は、組織によっては放射線による細胞死の主要なモードになっており、その理解は、より効果的な放射線治療法の確立に貢献すると期待される。さらには、老化様増殖停止を誘導した細胞は、液性因子の分泌を介して周辺の細胞に影響を及ぼすことも明らかになりつつあり、放射線照射を受けた組織全体の応答を理解する上でも重要なキーになると考えられる。
1 0 0 0 IR パラレルワールドの変容--村上春樹と社会言語的状況の現在(3-1)
- 著者
- 鈴木 智之
- 出版者
- 法政大学社会学部学会
- 雑誌
- 社会志林 (ISSN:13445952)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.1, pp.26-64, 1999-09
1 0 0 0 OA マイクロ波を用いた非接触による血圧変動推定方法の開発
本研究では,マイクロ波を用いた完全な非接触での生体計測手法を応用し,血圧変動を推定する手法の確立を目指すことを目的とした.手法の有効性の確認のための,①推定法の理論的検討,②システムの試作,③実験室内における試作したシステムの評価実験,を実施した.さらに,臨床的知見の蓄積とシステムの問題点の確認のため,④医療現場における心不全患者へ適用した実証実験,の4点の実施を目標とした.結果として,理論構築およびシステム試作,さらに評価実験を行い,ある程度良好な結果を得た.一方で,臨床的知見の蓄積のための調査については,安全性と精度に課題があったため十分な実施が出来ず見送る結果となった.
- 著者
- 鈴木 巧 柿本 益志
- 出版者
- 一般社団法人 日本機械学会
- 雑誌
- 熱工学コンファレンス講演論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.2013, pp.39-40, 2013
A numerical study has been done for natural convection heat transfer in the joint part of a cylindrical thermal insulation structure with a metallic outer shell. If the joint is relatively narrow, the effect of natural convection which occurs inside the joint on the thermal insulation performance is small. Although the heat transfer rate increases as joint width becomes large, the increase in the heat transfer rate is less than 10 percent, even when the joint width is 10mm.
1 0 0 0 OA 3Dプリント連続炭素繊維強化熱可塑複合材料の引張試験特性
- 著者
- 轟 章 大浅田 樹 水谷 義弘 鈴木 良郎 上田 政人 松崎 亮介 平野 義鎭
- 出版者
- 一般社団法人 日本複合材料学会
- 雑誌
- 日本複合材料学会誌 (ISSN:03852563)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.4, pp.141-148, 2019-07-15 (Released:2020-07-29)
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 1
Continuous carbon fiber composites can be printed with 3D printers. Many studies detailing elucidations of the mechanical properties of such 3D printed composites have been published, all of which employed a conventional tensile specimen configuration with surface resin layers. In the present study, 0º, 90º, ±45º, and lay-up direction type specimens were newly designed for 3D printed composites without surface layers. Using the 3D printer, both conventional and newly designed specimens with serpentine folded fiber bundles were fabricated and investigated experimentally. The lay-up direction specimen was fabricated using 800 layers. The specimens without the serpentine folded fiber bundles were experimentally shown to be adequate for tensile tests. The lay-up direction specimen had the lowest strength and stiffness, which seems to be related to its surface roughness.
- 著者
- 木村 晋介 鈴木 利廣 中谷 瑾子
- 出版者
- 大東文化大学
- 雑誌
- 大東文化大学法学研究所報. 別冊
- 巻号頁・発行日
- no.6, pp.1-34, 1997-03
1 0 0 0 IR FETO事件後のトルコ : 宗務庁による公共秩序の防衛に関する一考察
- 著者
- 鈴木 慶孝
- 出版者
- 慶應義塾大学大学院法学研究科内『法学政治学論究』刊行会
- 雑誌
- 法学政治学論究 : 法律・政治・社会 (ISSN:0916278X)
- 巻号頁・発行日
- no.128, pp.1-31, 2021
一 はじめに二 トルコの政教関係・世俗主義三 宗教搾取 : 国家機関によるFETÖへの批判から四 宗務庁長官ならびに宗務庁組織によるFETÖへの見解 (一) 宗務庁によるFETÖ批判 (二) 宗務庁長官の見解五 宗務庁や関係省庁による対FETÖ戦略六 宗務庁による宗教心管理の困難さ七 国家権力と結びつく宗務庁 (一) 国家安全保障組織としての宗務庁 (二) 象徴的暴力としての宗務庁八 結語
1 0 0 0 OA 学術と行政の連携のあり方:学術行政連携検討委員会活動報告
- 著者
- 古城 隆雄 尾島 俊之 中俣 和幸 家保 英隆 田中 剛 牧野 伸子 鈴木 孝太 平山 朋 山本 光昭 鶴田 憲一
- 出版者
- 日本公衆衛生学会
- 雑誌
- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.6, pp.385-392, 2021-06-15 (Released:2021-06-25)
目的 公衆衛生の進歩発展および向上のためには,科学的な根拠に基づく政策の展開が求められ,学術と行政の連携が重要である。そこで,日本公衆衛生学会を活用しながら,学術と行政のさらなる連携の推進方策を検討することを目的に,日本公衆衛生学会学術行政連携検討委員会(委員長:鶴田憲一)の活動を行った。方法 学術行政連携検討委員会を2018年度~2019年度の2年間に3回開催し,さらにメールによる意見交換を行った。また,2019年10月24日に第78回日本公衆衛生学会総会において「根拠に基づく公衆衛生政策(EBPM)の具体的事例とノウハウ(学術行政連携検討委員会)」と題したシンポジウムを開催し,学術と行政の両者から,これまでの連携の具体的事例とノウハウについて発表し,参加者との質疑を通じて今後の課題についても議論した。活動報告 学術行政連携検討委員会の検討では,日本公衆衛生学会の運営における連携,行政業務データの精度に関する共通認識,行政におけるデータ活用の推進,人材確保と育成による連携の重要性があげられた。シンポジウムでは,委員長から学術行政連携検討委員会の設立経緯と趣旨を説明した後,データの活用に関する行政と学術のギャップについて,目的,研究の位置づけ,データ形式,人材,データ提供への課題の5点について整理した。続いて,行政の観点から,都道府県行政と公衆衛生学会の連携,地方行政職員の演題発表の変化,災害対応における学術への期待について,学術から,大学による行政の調査研究の支援,行政と連携したエビデンスづくりについての報告と質疑が行われた。結論 学術と行政の連携により,行政にとっては,根拠に基づく政策形成の深化とそのための人材育成が推進できる。また,日本公衆衛生学会総会開催は,公衆衛生従事者の資質の向上と経済効果につながる。学術にとっては,求められる研究内容の把握やデータ活用が推進できる。
- 著者
- 鈴木 雅暢
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経パソコン = Nikkei personal computing (ISSN:02879506)
- 巻号頁・発行日
- no.749, pp.95-98, 2016-07-11
第1回自作パソコンはOSも自分でインストールする。むしろ、ここからが本番と言ってもよい。今回はその前後に行う作業のポイントを解説する。
- 著者
- 寺嶋 芳江 渡辺 智子 鈴木 亜夕帆 白坂 憲章 寺下 隆夫
- 出版者
- 一般社団法人 日本木材学会
- 雑誌
- 木材学会誌 (ISSN:00214795)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.3, pp.170-175, 2009
シイタケ培地へトレハロースを0.5,1,2,3,4%添加して栽培し,子実体の収量,トレハロース含有量,鮮度保持,食味への影響を試験した。その結果,収量には有意差のある変化を生じなかったが,0.5,1,2,3%添加培地から1回目に発生したMサイズ以上の子実体の個数割合が多くなった。無添加に比べて,2,3,4%添加培地からの子実体のトレハロース含有量は3回目までのいずれの発生回でも多くなった。鮮度については,2%添加ではいずれの発生回でも高い保持効果が認められ,特に4%添加では1回目に有意に高かった。官能検査では,2%と3%添加の場合に摂取時の「香り」,「食感」,「味」と「総合評価」が比較的高かった。
1 0 0 0 ナメコの化学成分組成に及ぼす栽培時のオゾン暴露の影響
- 著者
- 渡辺 智子 土橋 昇 高居 百合子 大政 謙次 田中 浄 鈴木 彰
- 出版者
- 社団法人 日本食品科学工学会
- 雑誌
- 日本食品工業学会誌 (ISSN:00290394)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.1, pp.7-16, 1993
- 被引用文献数
- 1
ナメコ栽培におけるO<SUB>3</SUB>暴露(対照区およびO<SUB>3</SUB>試験区:0.03ppm区,0.1ppm区,0.3ppm区)の影響を化学成分面から検討した. <BR>O<SUB>3</SUB>暴露により有意に増加した成分は,傘では水分,脂質,炭水化物,V.B1およびV.C,柄では水分およびV.C,全子実体では水分,脂質およびV.Cであった.O<SUB>3</SUB>暴露により有意に減少した成分は,傘では重量,タンパク質,灰分,Fe, Na, KおよびZn,柄では重量,灰分,KおよびZn,全子実体では重量,灰分,Na, KおよびZnであった. <BR>O<SUB>3</SUB>暴露濃度との間に有意な正の相関を示したものとして,傘では水分および脂質,柄では水分,タンパク質およびV.C,子実体では水分と脂質およびV.B<SUB>2</SUB>であった.O<SUB>3</SUB>暴露濃度との間に有意な負の相関を示したものとして,傘では重量,タンパク質,灰分,NaおよびZn,柄では重量,炭水化物および灰分,全子実体では重量,灰分,NaおよびZnであった. <BR>通常環境(対照区)の栽培において,ナメコの傘は柄に比較して,炭水化物以外のすべての一般成分,Fe, Na, K, Zn, V.B<SUB>1</SUB>, V.B<SUB>2</SUB>およびV.Cを多く含有していた.
1 0 0 0 生元素安定同位体比解析によるコシヒカリの産地判別の可能性
- 著者
- 鈴木 彌生子 中下 留美子 赤松 史一 伊永 隆史
- 出版者
- 公益社団法人 日本食品科学工学会
- 雑誌
- 日本食品科学工学会誌 : Nippon shokuhin kagaku kogaku kaishi = Journal of the Japanese Society for Food Science and Technology (ISSN:1341027X)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.5, pp.250-252, 2008-05-15
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 8 14
コメの産地偽装問題が起きており,コメの産地を科学的根拠に基づいて判別する技術が必要とされている.本研究は,日本産,豪州産,米国産コシヒカリを用いて,炭素・窒素・酸素安定同位体比解析を行い,安定同位体比解析によるコメの産地判別の可能性を検証した.解析の結果,日本産のコメの安定同位体比は,平均値で,炭素では米国産よりも0.7‰,窒素では豪州産よりも3.8‰低く,酸素では豪州産と米国産よりもそれぞれ12.6‰,3.5‰低い値を示した.安定同位体比から,日本産のコメは,他国産のコメと識別できることが明らかになった.安定同位体比解析は,DNA判別や微量無機元素測定などの他の技術と相補的に利用すれば,強力な産地判別技術になる可能性がある.
- 著者
- 大山 奈緒美 鈴木 孝樹 小竹 恵子
- 出版者
- メディカ出版
- 雑誌
- Brain nursing = ブレインナーシング (ISSN:09108459)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.1, pp.105-114, 2010-01
1 0 0 0 教育学における論理の問題
- 著者
- 上田 薫 鈴木 順子
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 日本教育学会大會研究発表要項
- 巻号頁・発行日
- vol.21, pp.8-11, 1962