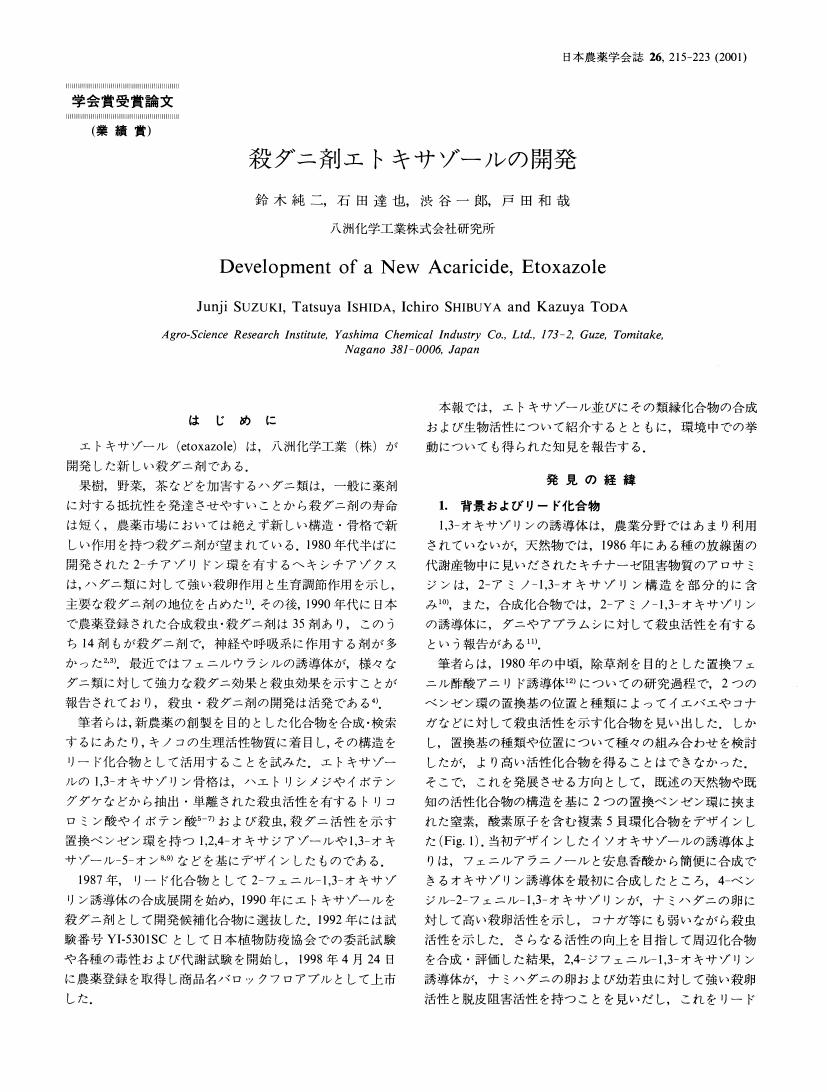1 0 0 0 OA 殺ダニ剤エトキサゾールの開発
- 著者
- 鈴木 純二 石田 達也 渋谷 一郎 戸田 和哉
- 出版者
- 日本農薬学会
- 雑誌
- Journal of Pesticide Science (ISSN:1348589X)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.2, pp.215-223, 2001-05-20 (Released:2010-08-05)
- 参考文献数
- 26
- 被引用文献数
- 24 25
1 0 0 0 OA ヒトの臨床と動物の心電図 比較病態生理学の立場から
- 著者
- 関 一郎
- 出版者
- 日本獣医循環器学会
- 雑誌
- 家畜の心電図 (ISSN:02870762)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.6, pp.1-8, 1973 (Released:2010-03-05)
- 参考文献数
- 35
1 0 0 0 大阪市立大学学生寮の歴史
- 著者
- 藤田 庄市
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.84, no.2, pp.619-625, 2010-09-30 (Released:2017-07-14)
1 0 0 0 OA 付録 4 : バリデーション研究におけるサンプルサイズ
1 0 0 0 OA 聴覚・言語障害児の診断と訓練における動作性知能検査の臨床的意義と問題点
- 著者
- 森 寿子
- 出版者
- The Japan Society of Logopedics and Phoniatrics
- 雑誌
- 音声言語医学 (ISSN:00302813)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.2, pp.157-171, 1981-04-25 (Released:2010-06-22)
- 参考文献数
- 53
- 被引用文献数
- 1
Investigation of clinical sense and the problem of non-verbal intelligence testing was undertaken for 45 cases of hearing and speech handicapped children. All test cases were under the age of 12 and had speech training for more than three years. Non-verbal intelligence testing was effective for evaluating their intelligence and the effects of speech training.1) (a) None of the 45 cases underwent non-verbal intelligence testing previous to visiting our clinic, and as a result 90% of them had been evaluated as having lower intelligence, while 10% were judged to be mentally deficient. Following non-verbal intelligence tests at our clinic, of 39 cases who had been diagnosed mentally deficient in addition to other lesion, 36 cases showed normal non-verbal intelligence and 3 cases showed border-line intelligence. On the other hand, 6 cases who had been diagnosed as having a hearing loss only or a cleft palate only were shown to be mentally deficient as well.(b) As concerns the cause of impaired speech for the 45 cases, of 36 cases with normal non-verbal intelligence, 21 cases showed perceptive hearing loss, 7 cases were obscurr, 5 cases were epileptic, and 3 cases resulted from other causes. Three cases of border-line non-verbal intelligence showed impaired speech in addition to abnormal behavior whose cause was obscure. Six cases of retarded non-verbal intelligence showed mental deficiency in addition to hearing loss or cleft palate.2) As a result of our speech training extending over more than three years, of 27 cases (60% of total), 26 cases of normal non-verbal intelligence and 1 case of border-line intelligence were developed, and verbal intelligence reached a level equal to that of non-verbal intelligence.3) Non-verbal intelligence testing is important as a basic discernment test on speech handicapped children and as a clinical method for evaluating learning, hearing and speech ability.4) There remain certain problems and limitations as the results of speech training are evaluated by non-verbal intelligence testing only. The role of non-verbal intelligence in the speech learning process must also be defined in relation to speech learning ability. New tests should be designed for this purpose.
1 0 0 0 OA 慢性結核性膿胸に併発した胸壁原発悪性リンパ腫の1例
- 著者
- 吉田 亜由美 松本 博之 飯田 康人 高橋 啓 藤田 結花 辻 忠克 藤兼 俊明 清水 哲雄 小笠原 英紀 斉藤 義徳
- 出版者
- THE JAPANESE SOCIETY FOR TB AND NTM
- 雑誌
- 結核 (ISSN:00229776)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.6, pp.415-421, 1996-06-15 (Released:2011-05-24)
- 参考文献数
- 10
The patient was 69-year-old male. He had a history of treatment for tuberculosis by artificial pneumothorax about 47 years ago. He was admitted an another hospital under the diagnosis of tuberculous pyothorax. He was transferred to our hospital because of chest pain and fever. Laboratory findings on the admission were as follows: ESR was 120 mm/hr, CRP was 20.22mg/dl and other data were almost within normal limits. Chest X-ray showed a massive shadow in the right lower lung field, adjacent to the chest wall. Computed tomography (CT) showed tumor shadow with low density and invasions into the adjacent chest wall. Histological examination of surgically excised tumor biopsy revealed malignant lymphoma. The patient's condition improved and the size of tumor decreased temporarily by chemotherapy. Then, he began to complain of chest pain and high fever, and tumor in the chest wall invaded into the whole chest wall. He died of disseminated. intravascular coagulation despite continuing chemotherapy. Postmortem examination re vealed the following findings: the tumor existed mainly in the parietal pleura or the chest wall, adjacent to the lesion of pyothorax, and immunohistochemical examination showed that tumor was malignant lymphoma, diffuse, large B-cell type. Recent studies have shown a close association between EBV infection and pyothorax-associated lymphoma. We have to keep in mind the possible development of malignant lymphoma following tuberculous pyothorax, when we see patients complaining of fever or chest pain with tuberculous pyothorax.
1 0 0 0 OA 和太鼓のインパクト時の「脱力」技能の定量化
- 著者
- 中塚 智哉 松田 浩一
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会第二種研究会資料 (ISSN:24365556)
- 巻号頁・発行日
- vol.2017, no.SKL-23, pp.02, 2017-03-03 (Released:2021-08-31)
本研究では,和太鼓における重要な技能である「脱力」の学習支援のための,インパクト時の脱力技能の定量化アルゴリズムを提案する.定量化結果と指導者の知見の比較により,アルゴリズムの妥当性を確認した.
1 0 0 0 OA LNG冷熱利用の空気分離
- 著者
- 松本 尚徳
- 出版者
- CRYOGENICS AND SUPERCONDUCTIVITY SOCIETY OF JAPAN
- 雑誌
- 低温工学 (ISSN:03892441)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.1, pp.35-42, 1984-03-10 (Released:2010-02-26)
- 参考文献数
- 8
Cold Air Products Company, Ltd. (CAP) was established in May, 1975, in order to produce Liquid Oxygen, Liquid Nitrogen and Liquid Argon utilizing the cold of LNG (-160°C) imported by Osaka Gas Company.The utilization of LNG cold reduces greatly the electric power comsumption as compared with conventional processes. This feature will contribute to the savings in energy and natural resources which is a world wide requirement.In this report, the utilization of LNG cold for air separation plants is described.
1 0 0 0 OA ピラミッド型構造物の未知なる機能の実験による発見
- 著者
- 高木 治 坂本 政道 世一 秀雄 小久保 秀之 河野 貴美子 山本 幹男
- 出版者
- International Society of Life Information Science
- 雑誌
- 国際生命情報科学会誌 (ISSN:13419226)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.1, pp.60, 2019 (Released:2019-12-29)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 3
我々はピラミッド型構造物 (pyramidal structure: PS)の未知なる機能について2007年以来、10年以上研究を続けている。PSの研究方法として、PS内部に人間が入り瞑想をした。PSの未知なる機能を明らかにする手段として生体センサ (キュウリ果実切片) から放出されたガス濃度を測定した。生体センサの作成、設置、ガス測定は、零点同時補正法 (simultaneous calibration technique: SCAT) によって行われた。この方法は、国際総合研究機構 (International Research Institute: IRI) で研究開発され、ヒーラーに関わる多くの研究成果を得ている。ピラミッド型構造物と人間とが関わった実験において、次の2つの結果を得ることが出来た。(1) PS内部に人間が入り瞑想する以前に、人間の無意識 (フォースタイプI) による、生体センサに対する未知なる遠隔作用 (6 km以上離れた地点から生体センサに対して、遅延なく影響を与える長距離の非接触効果) が検出された。(2) PS内部に人間が入り瞑想した後、人間による何らかの影響 (フォースタイプII) によって、10日間以上続く遅延を伴った非接触効果 (PS内部の人間と生体センサの距離が0.5 mである短距離の非接触効果) が検出された。これらの結果から、ピラミッド型構造物と人間との関わりにおいて、人間から発する2つの異なるフォースタイプがあることが示唆された。しかし、2つの異なるフォースタイプは、PSによって変換速度は異なるが、どちらも生体センサが反応し得るエネルギーに変換され、非接触効果として検出されたと考えられる。ピラミッドパワー (効果) に関する学術的な研究において、統計的に高い有意性のある実験データを示した研究は、我々のグループ以外では皆無である。
1 0 0 0 OA 国際放送における命令放送制度
- 著者
- 清水直樹
- 出版者
- 国立国会図書館
- 雑誌
- 調査と情報 (ISSN:13492098)
- 巻号頁・発行日
- no.574, 2007-03
1 0 0 0 OA 憲政会総務のメディア・パフォーマンス : 「弾劾演説家」関和知の政治活動
- 著者
- 河崎 吉紀 Yoshinori Kawasaki
- 出版者
- 同志社大学社会学会
- 雑誌
- 評論・社会科学 = Hyoron Shakaikagaku (Social Science Review) (ISSN:02862840)
- 巻号頁・発行日
- no.141, pp.1-30, 2022-05-31
本稿は,1921年から1923年における憲政会の政治活動を,総務である関和知を例に,メディア・パフォーマンスの観点から捉えることを目的とする。与党である政友会を不名誉な多数と批判して衆議院を騒然とさせた関和知は,加藤友三郎内閣に対し,日支郵便約定で政府の過失を疑い,軍艦天城建造の不正を追及,内閣不信任案を提出して「弾劾演説家」と報じられるようになった。メディアを通して政党のプレゼンスを大衆に確保することは,普通選挙を目前に控えたパフォーマンスとして冷静な戦術であるように見える。なぜなら,臨時法制審議会では派手な演説ではなく,理性的な討論が行われ,普通選挙法案の実質が検討されるからである。
1 0 0 0 OA 主成分分析 : 社会調査データの多変量解析(2)
- 著者
- 小林 久高 Hisataka Kobayashi
- 出版者
- 同志社社会学研究学会
- 雑誌
- 同志社社会学研究 = The Doshisha Shakaigakukenkyu (Doshisha review of sociology) (ISSN:13429833)
- 巻号頁・発行日
- no.26, pp.31-72, 2022-03-31
主成分分析は計量的社会調査データの分析でよく用いられる手法の1つである。本稿では相関行列を用いた主成分分析の手法について多くの図を用いて解説している。
1 0 0 0 OA 恐怖管理理論に基づく性役割ステレオタイプ活性の促進要因の検討
- 著者
- 野寺 綾 唐沢 かおり 沼崎 誠 高林 久美子
- 出版者
- 日本社会心理学会
- 雑誌
- 社会心理学研究 (ISSN:09161503)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.2, pp.195-201, 2007-11-10 (Released:2017-02-08)
The purpose of this study is to examine the promoting effect of a fear of death on the activation of gender role stereotypes. Terror management theory proposes that when mortality is salient, people heighten the tendency to support their cultural worldview. Since stereotypes are considered to represent cultural worldview, a fear of death should increase the responses consistent with the stereotype. In this study, the activation of stereotypes regarding gender roles (e.g., "Housekeeping is a job for women.") was measured with an Implicit Association Test (IAT). Participants were 48 male undergraduate and graduate students. The results showed that the participants who completed the questionnaire implying mortality had a larger IAT effect than those who completed the questionnaire unrelated to mortality, and that death-related anxiety led to the activation of gender role stereotypes. It is claimed that terror management theory has theoretical value for studies on stereotype activation, as well as a function in justifying a system such as gender role in stereotype activation.
1 0 0 0 OA 平和構築のためのメディア支援
- 著者
- 清水直樹
- 出版者
- 国立国会図書館
- 雑誌
- レファレンス (ISSN:1349208X)
- 巻号頁・発行日
- no.674, 2007-03
1 0 0 0 OA 孝明天皇紀
- 著者
- 宮内省先帝御事蹟取調掛 編
- 出版者
- 先帝御事蹟取調掛
- 巻号頁・発行日
- vol.第1(巻第1-2), 1906
1 0 0 0 OA 研究大学の自律と統制 カリフォルニア大学を例に
- 著者
- 中世古 貴彦
- 出版者
- 日本高等教育学会
- 雑誌
- 高等教育研究 (ISSN:24342343)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, pp.195-212, 2018-05-25 (Released:2019-05-25)
- 参考文献数
- 41
本稿は,近年深刻な財政難に苦しむカリフォルニア州の高等教育における公立研究大学と州議会との対立に注目し,機能別分化政策的な解釈,大学理事会と政府との葛藤を直視しない立場,政策転換自体が必要とする観点からは見出し難い,同州のモデルが含意する大学の自律性の現代的な意義を検討する.財政難の中で州民への背信ともとれる行動をとったカリフォルニア大学に対し,州議会は統制強化を試みた.だが,公的使命の遵守を求めた公権力の介入は,大学が公的使命を果たすことを一層困難にしようとしていた.こうした対立を乗り越え,旗艦州立大学が卓越性追求を維持しつつ社会的使命を果たし続けるためには,政治的独立性に裏打ちされた真正な自律性が極めて重要であったことが明らかとなった.
1 0 0 0 OA 異種金属接触腐食
- 著者
- 川本 輝明
- 出版者
- Japan Society of Corrosion Engineering
- 雑誌
- 防食技術 (ISSN:00109355)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.8, pp.478-479, 1984-08-15 (Released:2009-10-30)
- 参考文献数
- 4
1 0 0 0 OA 進行性多巣性白質脳症(概説と最近の話題)
- 著者
- 雪竹 基弘
- 出版者
- 日本神経感染症学会
- 雑誌
- NEUROINFECTION (ISSN:13482718)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.1, pp.72, 2020 (Released:2020-05-13)
- 参考文献数
- 30
【要旨】進行性多巣性白質脳症(progressive multifocal leukoencephalopathy、以下 PML)の概説と、最近の話題を論じた。PML 診療は病態修飾療法(disease modifying therapy、以下 DMT)関連 PML に対応する時代であり、特に多発性硬化症(multiple sclerosis、以下 MS)の DMT 関連 PML が注目されている。MS における新規 DMT は本来 PML の基礎疾患ではない MS に、その薬剤自体が単剤で PML を発生させるという意味で重要である。薬剤関連 PML においては免疫抑制剤等による日和見感染症としての PML のみでなく、DMT 関連 PML という新たな要因が加わった。その他、PML に特徴的とされる MRI 所見の提示と、PML 治療の可能性に関してマラビロクとペムブロリズマブによる PML 治療の報告を紹介した。