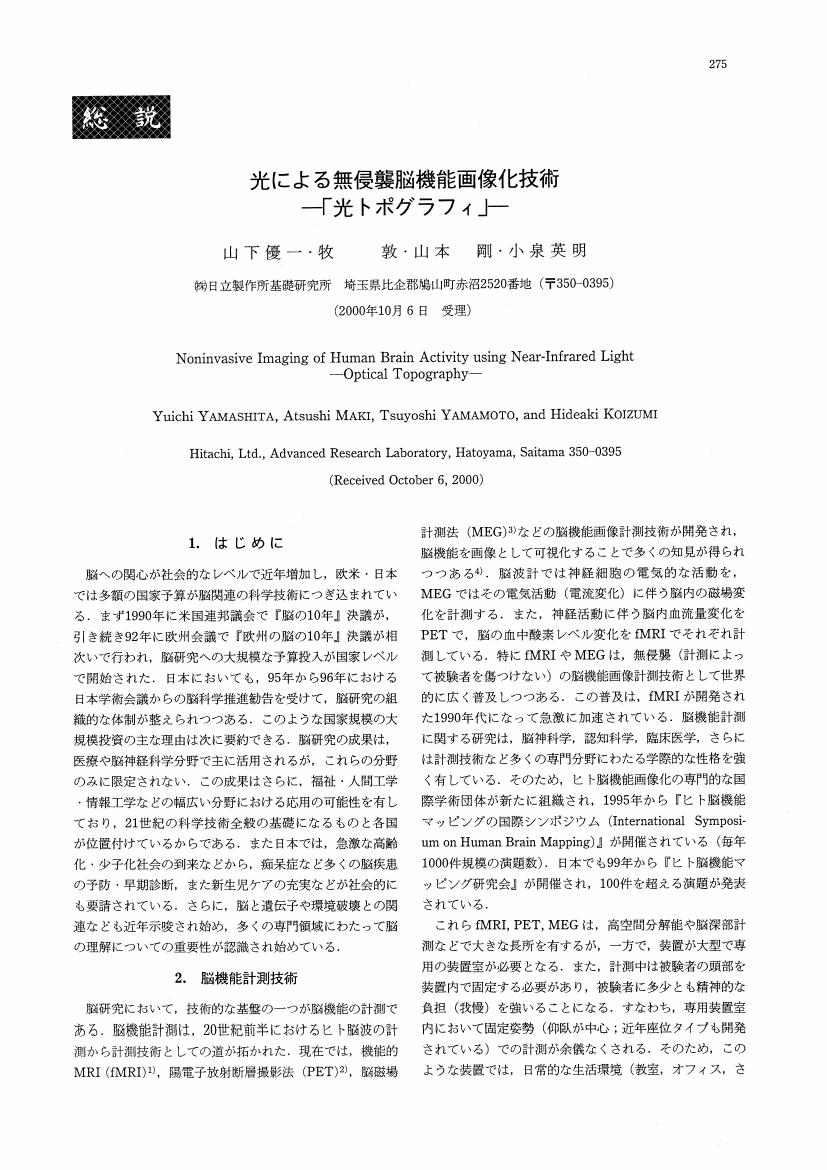1 0 0 0 西欧の正義日本の正義
1 0 0 0 OA 大学生の「キャリアに対する希望の明確さ」に影響を及ぼす要因
- 著者
- 矢野 香
- 出版者
- 長崎大学教育開発推進機構
- 雑誌
- 長崎大学教育開発推進機構紀要 = Journal of the Office for Academic Education and Development Nagasaki University (ISSN:24362999)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, pp.1-13, 2022-03-01
This study examined the factors that might influence whether university students had clear future career preferences. The same set of questions were asked to the first year students before and after the Introduction to Career course for comparison. In-person lectures (2019-20) and online lectures (2021-22) were also compared to examine whether they had the same effect. First, we examined whether or not the lectures had influence on students to have goals for their university life. The result indicated that both in-person and online lectures led more students to have such goals. Next, a multiple regression analysis was conducted to identify the factors that would influence whether students had clear future career preferences. The result indicated that, for both pre- and post-course comparison and lecture type comparison, the factors that corelated with the clarity of future career preferences were highly consistent. Specifically, “having a clear idea of which area of study to focus on” and “having specific goals in university life” were particularly significant factors. The study therefore suggested that students are likely to have clearer ideas about their future career preferences if the university curriculum links career education subjects with each department’s lectures and increases opportunities for new students to set specific goals for their university life.
1 0 0 0 OA 札幌学院大学における発達障害学生支援に向けた全学必修型FD/SD研修会の効果と課題
- 著者
- 末吉 彩香 田中 敦士
- 出版者
- 札幌学院大学総合研究所 = Research Institute of Sapporo Gakuin University
- 雑誌
- 札幌学院大学総合研究所紀要 = Proceedings of the Research institute of Sapporo Gakuin University (ISSN:21884897)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.3-10, 2022-03-20
札幌学院大学における発達障害を含む多様な学生支援の拡充に向け,全教職員を対象に「令和3年度発達障がいのある学生への教育支援FD/SD研修会」を実施した.本稿の目的は,参加者向け事後アンケートの結果から本研修会が発達障害学生支援に関して教職員に与えた効果を評価し,今後の学内研修の展開を示すことである.オンラインで実施された研修会終了後に参加者(132名)に事後アンケート(WEB)への回答を求め,71名の教職員が回答した.事後アンケートの結果,全教職員を対象としたことが多様な学生に対する支援に向けた全学的な理解啓発に寄与したことが推察された.また研修会参加前と比較し,参加後の方が発達障害学生支援に関する知識について参加者の自信が高まり,本研修会が発達障害学生支援に関する基礎的な知識提供の場として機能した可能性が示された.一方で発達障害学生支援に関する知識に一定程度自信がある場合でも実際の学生対応には自信がない教職員の存在もうかがえ,今後の学内研修会では知識を実際の支援の場に結び付けるための工夫が必要であると考えられた. The ‘FY2021 FD/SD Workshop on Educational Support for Students with Developmental Disabilities’ was held for all faculty and staff to expand support for students, specifically those with developmental disabilities, at Sapporo Gakuin University. This paper aims to evaluate the effect of the FD/SD workshop on faculty and staff. It also provides recommendations for the future development of training within the university. After the workshop, participants were asked to fill up a web-based questionnaire. Seventy-one faculty members provided a response. Based on their responses, it was inferred that targeting all faculty and staff could contribute to university-wide understanding and awareness of the need for supporting students with diverse needs. The participants were also more confident about their knowledge of supports for students with developmental disabilities at the end of the workshop than at the beginning, indicating that the workshop may have functioned as a space for providing basic knowledge on the subject. Still, there were some faculty members who were confident in their knowledge of supports for students with developmental disabilities but not about the actual supports that could be provided to such students.
1 0 0 0 OA 大学の合理的配慮と身体介助の支援
- 著者
- 松川 敏道
- 出版者
- 札幌学院大学総合研究所 = Research Institute of Sapporo Gakuin University
- 雑誌
- 札幌学院大学総合研究所紀要 = Proceedings of the Research institute of Sapporo Gakuin University (ISSN:21884897)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.35-40, 2022-03-20
身体介助を必要とする障害のある学生にとって,介助は教育を受けるうえで不可欠の要素である.本稿では,大学内での介助と合理的配慮をめぐる全国の動向を概観するとともに,この過程で新設された「重度訪問介護利用者の大学修学支援事業」に対する本学の対応と課題について検討した.そして,障害のある学生の「教育を受ける権利」が,身体介助の制約によって侵害されてはならないことを指摘した. Physical assistance is one of the essential elements for collage students with disabilities in order for them to receive collage education without difficulties. In this report, we as a university thoroughly reviewed the national trend with regard to reasonable accommodation and physical assistance provided to students with disabilities on collage and university campuses throughout Japan and examined as to how to utilize the newly-established system for the above-mentioned matter and how to deal with the issues that arise in the new system. In conclusion, we pointed out that “the right to receive collage education” guaranteed to collage students with disabilities should never be infringed in any ways.
1 0 0 0 OA <卒業生の満足度調査>卒業時の学生の満足度等の変化―卒業生アンケートの分析―
- 著者
- 辻 竜平
- 出版者
- 近畿大学総合社会学部
- 雑誌
- 近畿大学総合社会学部紀要 : 総社る = Kindai Applied Sociology Review : Social (ISSN:21866260)
- 巻号頁・発行日
- vol.10周年記念号, pp.87-89, 2022-03-31
1 0 0 0 OA 高温超伝導マイクロSQUID磁束計による単一微小試料測定
- 著者
- 柿木 隆介 渡邊 昌子 金桶 吉起
- 出版者
- 岡崎国立共同研究機構
- 雑誌
- 萌芽研究
- 巻号頁・発行日
- 2001
本研究に用いたMicro-SQUIDは特注で製作した世界唯一の機器であり、まさに萌芽的研究の主旨にかなった研究テーマであった。この3年間は実用化における諸問題の解決に力点を置いて研究を行なった。すなわち、SQUID自体の問題に加え、磁気シールドルーム(これも世界で最も小型のものを特注した)にも多くの問題が発生した。さらにソフトウェアの多くも新たに作成したが、初期マイナートラブルが多く発見され、それを1つずつ解決せねばならなかった。昨年夏にはようやく実用化が可能となり実験を開始する事ができた。先ず末梢神経の記録を行った。指を刺激して手首部を上行する活動電位の計測を行った。Micro-SQUIDの極めて高い空間分解能は、上行する刺激信号が4双極子であること、またその伝導時間が平均58.7m/secであることを明らかにした。信号が上行する状況をmsec単位で明確かつ詳細に記録したもので、世界で初めての報告であった。また同様の刺激条件時に頭皮上にMicro-SQUIDを置いて初期大脳皮質反応の記録に成功した。現在は、さらに聴覚、視覚などの刺激による反応記録も行っている。現在はヒトを対象とした研究が主体であるが、今後はさらにサルでの実験も考慮している。さらに交通事故による「引き抜き症候群」患者の検索を目的として、先ず健常人を対象として腕神経叢より頚部神経節に至る末梢神経近位部の検索を行なった。Micro-SQUIDの極めて高い空間分解能は、上行する刺激信号が4双極子であること、またその伝導時間が平均約60m/secであることを明らかにした。来年度は多数の臨床例を対象として検査を行なっていく予定である。
本研究は、仮現運動知覚および第2次運動知覚について、生理学的研究を脳磁図および機能的磁気共鳴画像にて行った。ランダムドットパターンを用いた仮現運動刺激では、ちらつきと運動の知覚を外的刺激を変化させずに与えることができる。よって刺激によらず運動知覚に伴う内的な脳機能の違いを検討することができた。結果は、運動知覚が惹起されるときはちらつきが惹起されるときと比して100ms前後から高い神経活動を示した。これは両者の知覚が視覚系の早い段階から競合しながら形成されていくことを示唆する。また、第2次運動知覚に関わる脳部位を機能的磁気共鳴画像を用いて検討した。第2次運動とは、明るさの時間変化を検出して運動を知覚する第1次運動知覚に対する概念で、物体の模様やコントラストなどの全般的な要素の位置の変化を検出することによって初めて知覚される。これまでにも同様の試みは多くなされてきたが、第2次運動知覚のみに特異的に関わる部位の同定はできておらず、臨床例の研究との結果に乖離があった。我々は、第2次運動知覚をもたらす視覚刺激を2003年に新たに創作した。この刺激は、第1次運動の影響を理論的に皆無にし、また第2次運動知覚の中でももっともその特徴を有するという性質を持つ。この刺激を用いて、脳磁図にて初めて第1次と第2次運動に対する反応の違いを明らかにした。今回は、この刺激を機能的磁気共鳴画像実験に応用した。視認性の影響を調べるために、第2次運動より見にくい第1次運動と、第2次運動、そして第2次運動と同程度の見易さの第1次運動、さらに第1次と第2次運動の両者の性質を持つ混合運動の刺激を用いて、それぞれに反応する脳部位を検索した。その結果、第2次運動に特異的に反応する部位は、上側頭溝後部にあった。この部位に障害を起こした臨床例が、第2次運動に特異的に知覚障害を起こしたことが報告されており、その結果とみごとに一致する。また、同部位は、biological motionや表情の変化にも特異的に反応することが知られており、高次の運動知覚に広く関わることが示された。
1 0 0 0 OA 視覚誘発電位を手掛りとした注意の向きが視知覚反応に及ぼす影響に関する研究
- 著者
- 秋田 剛 平手 小太郎 安岡 正人
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会環境系論文集 (ISSN:13480685)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.567, pp.79-86, 2003-05-30 (Released:2017-01-27)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 2 1
Effects of attention on visual perception are investigated by means of analysis of visual evoked potentials that reflect visual information processing in brain. For the purpose, an experiment is carried out on two experimental conditions. The first condition requires subjects to watch visual stimuli that are presented to them repeatedly, and the second requires them to do auditory tasks while watching visual stimuli. Results of the experiment show that response quantity of visual information processing is diminished when auditory tasks that attract subject's attention to hearing are imposed on them, even if they see visual stimuli using their central vision.
1 0 0 0 OA 新しい実在論の理論的射程と美術の探究
- 著者
- 小松 佳代子 橋本 大輔
- 出版者
- 長岡造形大学
- 雑誌
- 長岡造形大学研究紀要 = Nagaoka Institute of Design Bulletin (ISSN:13499033)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, pp.6-13, 2019-03-01
The philosophical movement of the Speculative Realism together with New Materialism has deeply influenced on art in this decade. These theories criticized the correlationism and tried to consider the possibility of the world without human-beings. This article summarized this philosophical trend in relation to art, and examined the theoretical range of it. In response to these theories we tried to rethink the possibility of the inquiry in art.
1 0 0 0 OA 光による無侵襲脳機能画像化技術 光トポグラフィ
- 著者
- 山下 優一 牧 敦 山本 剛 小泉 英明
- 出版者
- 社団法人 日本分光学会
- 雑誌
- 分光研究 (ISSN:00387002)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.6, pp.275-286, 2000-12-15 (Released:2010-06-28)
- 参考文献数
- 59
- 被引用文献数
- 6 2
1 0 0 0 高校生のスクール・エンゲージメント尺度の開発と健康との関連性
- 著者
- 山岸 鮎実 朝倉 隆司
- 出版者
- 一般社団法人 日本学校保健学会
- 雑誌
- 学校保健研究 (ISSN:03869598)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.4, pp.218-232, 2022-01-20 (Released:2022-02-11)
- 参考文献数
- 49
Background: School engagement (SE) is a comprehensive concept encompassing the active engagement of children and students with their school lives in three respects: behavior, emotion, and recognition. This key concept can solve contemporary educational challenges. In Japan, a few earlier studies have specifically examined elementary and junior high school students and university students but no report of the relevant literature describes a study of senior high school students. Moreover, no report describes a study assessing correlation between SE and health. Objective: This research was conducted to develop SE scales fit for Japanese high school students, to confirm their validity and reliability and to elucidate the correlation between the SE scales and health indicators. Methods: Based on the literature review and group interviews conducted of high school students (15 in all), we designed SE scales (53 items) comprising behavior SE (15 items), emotion SE (19 items), and recognition SE (19 items), and conducted an anonymous self-administered questionnaire of first-year and second-year students (1,030 in all) of two metropolitan high schools. As the analytical method, we first identified the factor structure using exploratory factor analysis and subsequently examined their construct validity using the confirmatory factor analytic procedure. Additionally, we examined their criterion validity in terms of correlation between academic competence, health and safety behaviors (health-promoting and devastating behaviors). We confirmed the reliability of the scales using Cronbach's coefficient α. At last, we explored the correlation between SE scales and health indicators (physical symptoms and depression) using a generalized linear model. Results: According to factor analysis results, the behavior SE scales comprised 15 items categorized into five factors: extracurricular activities, class or school events, relationships with friends, academic work, and discipline. The emotion SE scales included 18 items of five factors: academic work, class, extracurricular activities, relationships with friends, and school. The recognition SE scales had 13 items of two factors: fostering of qualities and knowledge acquisition. Collectively, they were 46 items. In terms of the goodness of fit of each SE scale measurement model, RMSEA was less than or equal to 0.08; CFI was greater than or equal to 0.95, meaning that the construct validity was good. In terms of the criterion validity, the SE scales showed significant relations to academic achievement and health-promoting behaviors, by which the findings of earlier studies were able to be represented to a certain degree. The internal consistency of the scales was good, with α coefficients greater than or equal to 0.9. The considerations above allowed us to judge the reliability and validity of the SE scales as generally good. After adjusting for confounding variables, we examined the association between the SE scales and health indicators. Results show that the behavior SE was significantly and negatively associated with physical symptom scores and depression scale. Conclusion: The high-school students' SE scales have been developed to approach their school life and demonstrated the validity and reliability comprehensively and successfully. By exploring further the structure of the relationship between the SE scales and health among high school students, we can contribute to solutions of educational problems and health promotion for them.
1 0 0 0 OA いわゆる「大陸制度」<Continental System>の歴史的意義(2)
- 著者
- 吉田 静一
- 出版者
- 關西大学經済學會
- 雑誌
- 關西大學經済論集 (ISSN:04497554)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.6, pp.613-645, 1961-02-20
1 0 0 0 OA 島嶼環境においてヒメネズミはオニグルミを採食するのか?
- 著者
- 小林 郁奈 松尾 歩 廣田 峻 陶山 佳久 阿部 晴恵
- 出版者
- 日本森林学会
- 雑誌
- 日本森林学会大会発表データベース 第130回日本森林学会大会
- 巻号頁・発行日
- pp.425, 2019-05-27 (Released:2019-05-13)
堅い殻に包まれたオニグルミ種子は、一般にアカネズミには採食されるが、より小型のヒメネズミには採食されない。しかし、アカネズミの分布しない新潟県粟島ではオニグルミ種子がヒメネズミに採食されると言われている(林ら、私信)。私たちの予備的観察では、佐渡島や粟島で小型のオニグルミ核果が多く観察されたため、オニグルミとヒメネズミの共進化が起こっているのではないかと予測した。そこで本研究では、島嶼3集団(粟島、佐渡島、金華山)および本州の7集団でオニグルミ核果を採取してサイズを計測し、さらに各集団から採取したオニグルミ計80個体を対象として、MIG-seq法を用いた集団遺伝学的解析を行うことで、島嶼と本州間での遺伝的分化と核果サイズ変異との関係を調査した。その結果、島嶼ではオニグルミの核果サイズが多様で、本州集団と比較すると小型だった。一方で島嶼と本州のオニグルミは遺伝的に分化しておらず、核果サイズ変異と遺伝的変異との関係は確認できなかった。また、野外にセンサーカメラを設置しヒメネズミがオニグルミ核果を持ち去るかどうかを撮影したところ、粟島では持ち去りが確認されたが、佐渡島では確認できなかった。
1 0 0 0 OA 高齢者の活動と居住環境 生きがい向上と医療サービス利用の適正化に向けて
- 著者
- 三村 泰広
- 出版者
- 一般社団法人 日本福祉のまちづくり学会
- 雑誌
- 福祉のまちづくり研究 (ISSN:13458973)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.Paper, pp.1-13, 2021-05-10 (Released:2021-05-10)
- 参考文献数
- 27
本研究では高齢者の生きがいを支え、医療サービス利用の適正化につながるような「活動」を維持するうえにおいて、より重視すべき居住環境の姿を考察した。愛知県内に居住する60歳以上の方(n=1,250)を対象に、「普段の活動実態」、「居住する地域の環境」、「医療サービスの利用実態」、「生きがい」についてアンケート調査を実施した。結果、「ベンチ等休憩場所がない」、「公共交通が整備されていない」、「病院が少ない」、「散歩・運動のできる公園が少ない」が複数の高齢者の活動に影響を与えており、そしてそのほとんどで当該施設が少なくなるほど、活動量が有意に少なくなることを示した。また、普段の多くの活動量は高齢者の生きがいと強く結びついている一方、医療サービスの利用とはほとんど関連がないことを示した。