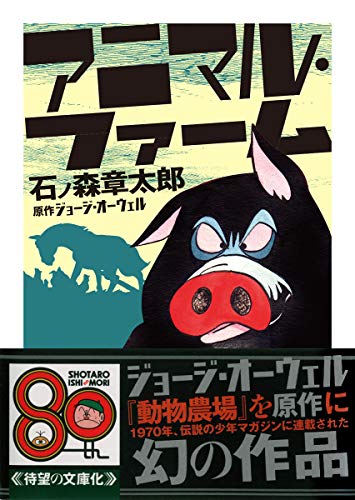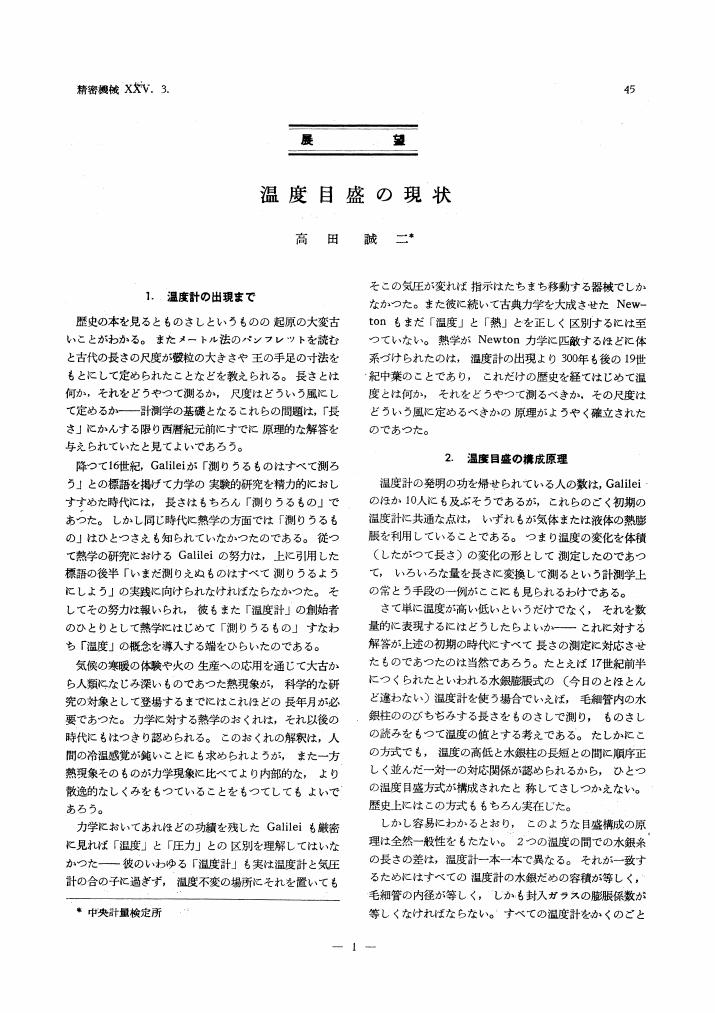1 0 0 0 OA 日本人の家族主義神話 ――「われわれ」の社会心理史・私試論――
- 著者
- 藤田 正
- 出版者
- 心理学評論刊行会
- 雑誌
- 心理学評論 (ISSN:03861058)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.3, pp.425-459, 1993 (Released:2019-07-24)
1 0 0 0 OA 中国人留学生の漢字・書字に対する意識 : アンケートとインタビューをもとに
- 著者
- 小山 真理
- 出版者
- 文化学園大学・文化学園大学短期大学部
- 雑誌
- 文化学園大学・文化学園大学短期大学部紀要 (ISSN:24325848)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, pp.111-125, 2020-01-31
近年、中国からの留学生が急増し、その影響なのか、以前より抱いていた疑問を強く感じるようになった。そ れは「なぜ中国人留学生は文字を、とりわけ漢字を丁寧に書かないのか」というものだ。その答えを探るため、 まず、日中両国の初等教育における漢字・文字教育を概観し、手書きの書字・字形等について、どのような指導 を受けてきたかを比較した。その上で、漢字・書字に対する意識が、日本語を学ぶ際、どう影響しているかについて、アンケートとインタビューにより分析し考察した。その結果、多くが小学校で厳しく指導され、丁寧な書字、筆順の順守を当然と考えていることがわかった。だが、成長するにつれて筆順を忘れ、自己流の書き方に慣れてくると、改めて日本の漢字を学ぶのは小学生のようだと抵抗感を示した学生も多くいた。さらに、既有の漢字知識があるため、「日本の漢字は少なくて簡単だ」と捉えがちで、特に、集中力や慎重さに欠け、成績の芳し くない学生は文字を乱雑に書く傾向があった。漢字・書字に対する意識に個人差はあるが、日中の漢字の差異は学生自身では気づきにくいことも明らかとなり、教師が注意して訂正させることは、今後も必要不可欠であることが確認できた。
1 0 0 0 OA ホッブズ-リヴァイアサンと平和概念の転換-
- 著者
- 佐藤 正志
- 出版者
- JAPANESE POLITICAL SCIENCE ASSOCIATION
- 雑誌
- 年報政治学 (ISSN:05494192)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, pp.19-34, 1992-12-22 (Released:2009-12-21)
- 著者
- 厚東 芳樹 森下 純弘
- 出版者
- 大妻女子大学人間生活文化研究所
- 雑誌
- 人間生活文化研究 (ISSN:21871930)
- 巻号頁・発行日
- vol.2020, no.30, pp.549-559, 2020-01-01 (Released:2020-09-24)
- 参考文献数
- 32
本研究では,小学校低学年(2年生)の子どもを対象に,ボール操作を伴わずに相手との駆け引きが存在する鬼遊びゲーム教材「カバディ」の体育授業を実施し,単元内で子どもたちがどのような「戦術の立案」をいくつ考えるのか,また「戦術の実行数」はどうかといったチーム戦術を事例的に検討することで,低学年で「ゴール型」ゲームにつながる戦術学習の導入可能性を明らかにすることを目的とした. まず,態度測定による体育授業診断の結果,男女共に比較的高い評価になった.これより,実施した「カバディ」の単元計画は低学年2年生にとってある程度妥当な内容であったことがわかる.また,「プレイ数」「戦術(ゲーム様相毎も含む)の立案数」「戦術の実行数」は,単元計画や企図した戦術的気づきに関わった内容構成とよく対応していた.これらより,実施した鬼遊びゲーム教材「カバディ」の体育授業は,低学年の子どもたちに戦術学習の「わかる」と「できる」の両面を保証できていた可能性が示唆された.以上のことから,低学年の体育授業でも「ゴール型」ゲームにつながる戦術学習を導入することは可能であることが示唆された.
- 著者
- 渡邉 聡子 勅使川原 早苗 國方 友里亜 三嶋 麻揮 田原 稔久 今井 佑輔 金藤 光博 田村 友和 桃木 律也 小武 和正 利根 淳仁 中塔 辰明
- 出版者
- 一般社団法人 日本糖尿病学会
- 雑誌
- 糖尿病 (ISSN:0021437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.4, pp.188-194, 2022-04-30 (Released:2022-04-30)
- 参考文献数
- 15
メトホルミンの過量服薬を契機に乳酸アシドーシス,急性腎不全を呈した2型糖尿病の1例を経験したので報告する.症例は50歳代男性.入院2週間前より気分の落ち込み,食欲不振を認めていた.入院2日前の採血で血清Cre 1.50 mg/dL,血糖247 mg/dL,血液ガス分析では異常を認めず,入院前日の採血ではCre 1.42 mg/dLであった.入院前日の夜にメトホルミンを推定4000 mg服用し,嘔気嘔吐,下痢が出現したため,翌日当院へ救急搬送となった.血液ガス分析でpH 6.91,乳酸25.0 mmol/L,採血でCre 4.39 mg/dLと,乳酸アシドーシス,急性腎不全を認めた.来院後速やかに緊急血液透析を開始することで救命し得た.メトホルミンの過量服薬後に急激な腎機能悪化を認めた経過から,メトホルミンによる直接的な腎障害が示唆された.迅速な血液透析が治療に有効であったので報告する.
1 0 0 0 OA 視聴覚情動刺激下での脳波パワースペクトル解析―携帯端末を用いた場合―
- 著者
- 鴨 宏一 村松 歩 多屋 優人 横山 浩之 浅川 徹也 林 拓世 水野(松本) 由子
- 出版者
- 一般社団法人 日本臨床神経生理学会
- 雑誌
- 臨床神経生理学 (ISSN:13457101)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.4, pp.193-201, 2013-08-01 (Released:2013-11-01)
- 参考文献数
- 22
- 被引用文献数
- 2
本研究では携帯端末による情動刺激下での脳波を用いた脳機能の評価を目的とした。被験者は健常成人24 名で,Cornell Medical Index(CMI),日本版State-Trait Anxiety Inventory(STAI),簡易ストレス度チェックリスト(SCL)によって心身状態を評価し,心理検査低値群と心理検査高値群に分類した。情動刺激は,情動的視聴覚セッション(安静,快,不快)と情動的文章セッション(快文章,不快文章)を用意し,携帯端末からの視聴覚刺激として被験者に提示し,脳波を計測した。脳波は離散フーリエ変換を行い,パワースペクトル値を算出した。α2 帯域の結果から,心理検査高値群は不快刺激および不快文章刺激時に側頭部でスペクトル値が高値を示した。以上より,携帯端末による情動刺激が精神安定度と関連して,脳機能の反応に影響を及ぼすことが示唆された。
1 0 0 0 OA 絶食療法の脳波学的研究 : 特に脳波パワースペクトルの変動について
- 著者
- 山本 晴義
- 出版者
- 一般社団法人 日本心身医学会
- 雑誌
- 心身医学 (ISSN:03850307)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.4, pp.325-335, 1980-08-01 (Released:2017-08-01)
- 被引用文献数
- 3
In order to ascertain whether or not the therapeutic mechanism of fasting therapy lies within the changes occurring within the central nervous system, an electroencephalogram was recorded before, during and after fasting therapy. This therapy consisted of complete fasting for 10 days with subsequent resumption of regular meals for 6 days. EEG data was passed to the computer using a Sanei Model Signal Processor 7TO7. The resultant power spectrum covered the frequency range from D.C. to 25Hz with 0.195Hz resolution. Such spectra were obtained from the left occipital region at various stages of the therapy. During the experiment, patients were awake with their eyes closed. Changes in EEG power spectra through therapy were examined by peak frequency and percent energy. The average peak frequency of forty patients was 10.3Hz before fasting, but it decreased to 9.5Hz following 10-day fasting. After the recovery phase, it again increased to 10.1Hz. This decrease in peak frequency through fasting correlates statistically with a decrease in blood sugar level (r=+0.36,P<0.05). Subsequently, the percent energy was obtained at a frequency range of 4 to 20Hz. This range was divided into three parts : 'theta' with a range of 4 to 8Hz, 'alpha' with a range of 8 to 13Hz, and 'beta' ranging from 13 to 20Hz. The average percent energy of 40 patients for 'theta', 'alpha' and 'beta' was, respectively, 16%, 63%, 21% before fasting, 18%, 65%, 17% after 10-day fasting, and 15%, 70%, 15% after the recovery phase. The percent energy of 'alpha' after fasting therapy was significantly higher than that of the pre-fasting stage (P<0.001), while the percent energy of 'beta' after fasting therapy was significantly lower than that of the pre-fasting stage (P<0.001). The significantly higher percent energy of alpha waves indicates the stable psychological state of the post-fasting period. On the other hand, the beta waves decreased during the fasting period, and they did not reappear again in the same fashion even after the recovery phase. As these waves indicate psychological conditions of anxiety, tension and irritation, their decrease may imply objectively that fasting can ease these symptoms. These neurophysiological findings imply that Altered States of Consciousness, or ASC, have much to do with the psychotherapeutic effect. Since ASC can be attained easily through fasting, it is suggested that fasting therapy is an effective somatopsychic approach.
1 0 0 0 OA 脳波のスペクトル分析
- 著者
- 徳力 幹彦
- 出版者
- 獣医疫学会
- 雑誌
- 獣医科学と統計利用 (ISSN:18845606)
- 巻号頁・発行日
- vol.1981, no.7, pp.7-11, 1981-12-20 (Released:2010-05-31)
- 参考文献数
- 3
1 0 0 0 OA α波のwaxing and waningに関する臨床脳波学的研究
- 著者
- 秋元 勇治
- 出版者
- 日本医科大学医学会
- 雑誌
- 日本医科大学雑誌 (ISSN:00480444)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.1, pp.1-19, 1969-02-15 (Released:2010-12-22)
- 参考文献数
- 43
- 被引用文献数
- 2
1) The “waxing and waning”(w-w) was studied on 479 normal healthy subjects and 2, 264 patients with mis-cellaneous neuro-psychiatric disorders. All the subjects were over 16 years of age.2) The w-w has been considered as the rhythmicity of normal cerebral activity, but this is uncertain. The auth-or attempts to examine it's properties in this report. The characteristics of the w-w represented at least 40μV of it's maximum amplitude, ca. 1-2 sec. of it's duration, and two or three times difference between maximum and minimum amplitude, and the w-w is mo-re clear and typical by biporal than monoporal recording.3) The w-w can be seen more clearly and typically at the stage of drowsiness or relaxation, and it is more pro-minent in hyperventilation than in bemegride or pentetrazol provocation.4) There is no specificity of age. The w-w was observed in 11.3% of normalhealthy subjects.5) The w-w was markedly observed in the subjects with miscellaneous autonomic disturbances, migraine, arter-iosclerosis, neurotic states and brain damage or posttraumatic complaints.But with statistical procedures, es-pecially, it had much more dominance in the subjects with migraine, miscellaneous autonomic disturbances and posttraumatic complaints at the level of X2<0.01.6) In almost all the cases with posttraumatic complaints, the w-w may decrease or diminish during continuous observation, but in other cases (ex. neurotics, with miscellaneous autonomic disturbances) it may be contin-uous at all times whether symptoms are remaining or not.7) There were no significant changes of the w-w produced by any medications.8) Therefore the w-w is not an abnormal sign, but the “significant sign”, indicating the relationship between the “certain cerebral function” and some clinical conditions.
1 0 0 0 OA Neurological emergencyにおけるモニタリングと急性期治療戦略
- 著者
- 横堀 將司 山口 昌紘 五十嵐 豊 亦野 文宏 廣中 浩平 恩田 秀賢 桒本 健太郎 荒木 尚 布施 明 森田 明夫 横田 裕行
- 出版者
- 一般社団法人日本脳神経外科コングレス
- 雑誌
- 脳神経外科ジャーナル (ISSN:0917950X)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.3, pp.220-228, 2016 (Released:2016-03-25)
- 参考文献数
- 27
頭部外傷や脳卒中, 心停止後症候群 (post cardiac arrest syndrome : PCAS) など, 神経救急疾患において脳保護・脳蘇生を指向したモニタリングの重要性が強調されている. また, 依然challengingではあるが, 各種モニタリングを治療方針決定に生かす試みも始まっている. 新しいモニタリングとしてPCAS患者でのaEEG・rSO2による予後予測, 神経外傷モデルによるバイオマーカー (UCH-L1, GFAP) 測定などが挙げられる. これらモニタリングと治療の往復がさらなるエビデンス構築に寄与すると期待される. 本稿は神経救急分野におけるモニタリングの重要性と, それらを加味した治療戦略確立の重要性を提示する. 救急脳外科疾患における “判断と行動” の一助になれば幸いである.
1 0 0 0 OA 脳波モニターを正しく使うために
- 著者
- 萩平 哲
- 出版者
- 日本臨床麻酔学会
- 雑誌
- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.2, pp.79-87, 2004 (Released:2005-03-31)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 2 2
近年BISモニターなどの脳波(EEG)モニターが普及しつつあるが, 残念ながら現状では適切に使用されているとはいえない. これは麻酔中の脳波に対する基本的な知識の欠如によると考えられる. 本稿では脳波モニターを適切に使用するための基本的な知識を整理し, どのような戦略を用いれば麻酔中の脳波から必要な情報が得られるかについて解説した. 麻酔中の脳波には麻酔薬の作用だけでなく手術刺激の影響やそれを抑制する鎮痛薬の効果も反映されるため, このことを念頭におかなければ脳波モニターを活用することは困難である. またBIS値を含めた脳波パラメータによる判定には限界があるため, 必要に応じて脳波波形で判断することも大切である.
1 0 0 0 OA 最優秀論文賞:風車のソリディティとエネルギー変換効率の関係
- 著者
- 岡本 遼太郎
- 出版者
- 一般社団法人 電気学会
- 雑誌
- 電気学会論文誌B(電力・エネルギー部門誌) (ISSN:03854213)
- 巻号頁・発行日
- vol.136, no.3, pp.NL3_3-NL3_6, 2016-02-01 (Released:2016-03-01)
- 参考文献数
- 6
Today, we must develop alternative energies. However, Japan does not have enough land to build large power plant. Therefore we studied about small-sized wind power generation for the purpose of developing a windmill which is suitable for the wind condition of its installed location.
1 0 0 0 アニマル・ファーム
- 著者
- ジョーヂ・オーウェル著 永島啓輔訳
- 出版者
- 大阪教育図書
- 巻号頁・発行日
- 1949
1 0 0 0 アニマル・ファーム
- 著者
- ジョージ・オーウェル原作 石森章太郎画
- 出版者
- 角川グループパブリッシング (発売)
- 巻号頁・発行日
- 2008
1 0 0 0 アニマル・ファーム
- 著者
- 石ノ森章太郎著 ジョージ・オーウェル原作
- 出版者
- 筑摩書房
- 巻号頁・発行日
- 2018
1 0 0 0 イギリス名作集・アメリカ名作集
- 著者
- [スティーヴンソンほか著] 朱牟田夏雄他訳
- 出版者
- 中央公論社
- 巻号頁・発行日
- 1966
- 著者
- Risa Tamagawa-Mineoka Koji Masuda Akiko Yagami Masashi Nakamura Nayu Sato Kayoko Matsunaga Norito Katoh
- 出版者
- Japanese Society of Allergology
- 雑誌
- Allergology International (ISSN:13238930)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.3, pp.427-429, 2018 (Released:2018-07-28)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 8
1 0 0 0 日本ヘリコプタ技術協会会報
- 出版者
- 日本ヘリコプタ技術協会
- 巻号頁・発行日
- 0000
1 0 0 0 OA 温度目盛の現状
- 著者
- 高田 誠二
- 出版者
- 公益社団法人 精密工学会
- 雑誌
- 精密機械 (ISSN:03743543)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.289, pp.45-49, 1959-02-05 (Released:2009-06-30)