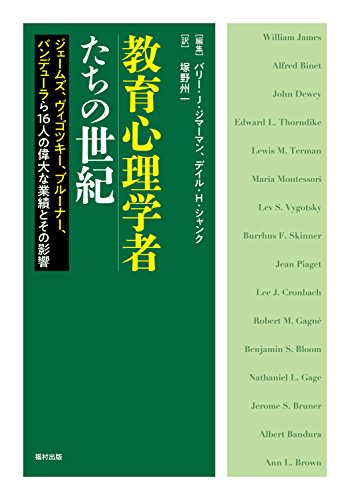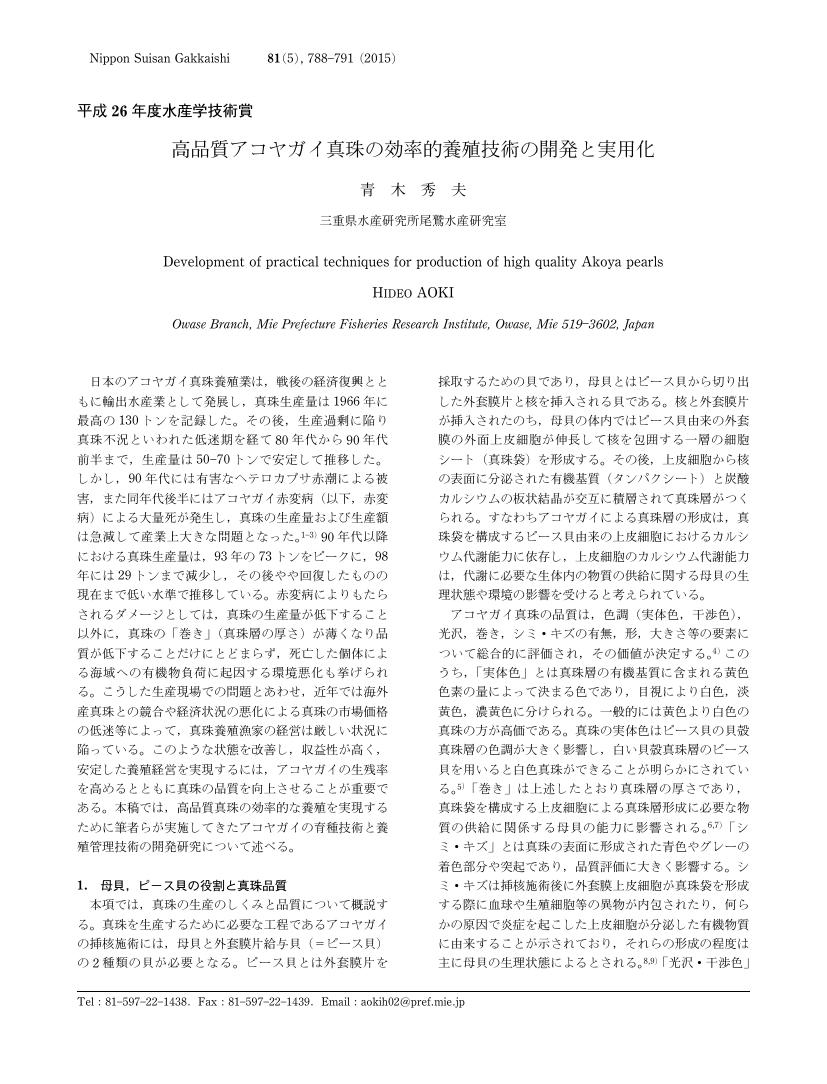1 0 0 0 OA 糸状菌の極性生長 細胞骨格と形質膜の相互作用による極性の制御
- 著者
- 竹下 典男
- 出版者
- 公益社団法人 日本農芸化学会
- 雑誌
- 化学と生物 (ISSN:0453073X)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.12, pp.809-820, 2013-12-01 (Released:2014-12-01)
- 参考文献数
- 59
- 被引用文献数
- 1
糸状菌は,菌糸の先端を伸長させることで生長する.その生長様式は,極性生長の解析に適したモデルであり,糸状菌の病原性や高い酵素分泌能にも関連している.菌糸生長には,菌糸先端での持続的な極性の維持が必要である.その極性を制御するため,菌糸先端の形質膜における位置情報を介して,微小管とアクチン細胞骨格が協調的に機能することが明らかとなってきた.本稿は,糸状菌の細胞骨格と形質膜ドメインの役割を概説するとともに,極性の維持・確立・焦点化・再構築という各々の現象に着目し,極性生長の総合的な理解を目指すものである.
- 著者
- 村上 覚 種石 始弘 鈴木 公威 佐々木 俊之 橋本 望
- 出版者
- 一般社団法人 園芸学会
- 雑誌
- 園芸学研究 (ISSN:13472658)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.2, pp.117-125, 2019 (Released:2019-06-30)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 1
開花期が早い ‘レインボーレッド’ においても自然受粉を可能とする雄品種として ‘にじ太郎’ を育成した.‘にじ太郎’ は ‘レインボーレッド’ の偶発実生から選抜した二倍体品種である.花粉品質は,酢酸カーミン染色率はやや低いものの,発芽率は他品種と同程度であった.一方で,‘トムリ’ と比べると,採葯量および採取純花粉量は少ないため,花粉採取用としては適さないと考えられた.‘にじ太郎’ の花粉で受粉した ‘レインボーレッド’ 果実は,‘トムリ’ 花粉で受粉した果実と比べて,結実率や果実品質に差はみられなかったものの,黒色の充実した種子が増えた.開花期は ‘レインボーレッド’ と重なるため,‘レインボーレッド’ を自然受粉させることができる.3年間の自然受粉栽培について検討した結果,1.0~1.5 mの1年生側枝を ‘レインボーレッド’ に高接ぎして配置した場合,枝から2 mの範囲内では概ね80%の結実率を確保でき,果実品質も比較的良好であったが,それよりも離れると結実不良や果実の肥大不良が懸念された.このことから,4 m間隔で ‘にじ太郎’ の枝を高接ぎし配置することが望ましいと考えられた.以上のことから ‘にじ太郎’ は ‘レインボーレッド’ の自然受粉に有効であると考えられ,‘レインボーレッド’ の安定生産に寄与することが期待できる.
1 0 0 0 OA 近現代における両刃鋸の変遷について
- 著者
- 船曳 悦子
- 出版者
- 公益財団法人 竹中大工道具館
- 雑誌
- 竹中大工道具館研究紀要 (ISSN:09153685)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, pp.49-59, 2010 (Released:2021-03-22)
- 参考文献数
- 24
本稿では、文献資料と古写真、及び実物資料の分析を通して、両刃鋸の発達の経緯について以下の内容を明らかにした。 1 明治10 年の時点では、東京において鋸の先が二つに割れた細工鋸の形状の両刃鋸を文献で確認できた。 2 明治前期には、出現していたと推定できる両刃鋸は、鋸用鋼材としての玉鋼を使用していることを実物で確認した。 3 両刃鋸は明治35 年には商店で購入可能であった。 4 明治期と推定される写真には両刃鋸の使用は見られない。 5 両刃鋸の普及の背景には、鋸用鋼材としての洋鋼( 東郷鋼) と製作技術として油焼入れの一般化、そして利便性への追求があった。
1 0 0 0 OA 大腸菌の多次元表現型計測に基づく適応度地形の推定
- 著者
- 古澤 力 岩澤 諄一郎 前田 智也
- 出版者
- 一般社団法人 日本生物物理学会
- 雑誌
- 生物物理 (ISSN:05824052)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.5, pp.263-265, 2023 (Released:2023-11-25)
- 参考文献数
- 9
適応度地形を推定することは,進化過程の理解に大きく貢献する.しかしゲノム配列空間においてその推定を行うことには,膨大な実験データが必要となり困難が伴う.本稿では,大腸菌の抗生物質耐性進化の過程において,複数薬剤への耐性能を経時的に計測し,その表現型データに基づいて適応度地形を推定する手法を紹介する.
1 0 0 0 OA 書籍紹介/『それでも日本人は「戦争」を選んだ』加藤陽子著
- 著者
- 慶松 勝太郎
- 出版者
- LEC東京リーガルマインド大学院大学
- 雑誌
- LEC会計大学院紀要 (ISSN:21865302)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, pp.127-143, 2020 (Released:2020-01-30)
1 0 0 0 OA 直管路内の乱流 (第二種二次流れの数値解析)
- 著者
- 中山 顕
- 出版者
- 社団法人 日本伝熱学会
- 雑誌
- 伝熱研究 (ISSN:09107851)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.100, pp.57-64, 1987 (Released:2010-12-16)
- 参考文献数
- 28
- 著者
- Takashi ITO Chiê NARA
- 出版者
- The Mathematical Society of Japan
- 雑誌
- Journal of the Mathematical Society of Japan (ISSN:00255645)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.4, pp.697-720, 1986 (Released:2006-10-20)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA 乳幼児の心理的発達に関わる美術館における鑑賞プログラムの分析と開発
「超初期学習者」である乳幼児の心理的発達に、「美術館」環境、「アート作品」、それらに関わる「人」が寄与すると仮定し、それらが発する情報を乳幼児が取得する教育プログラムをデザイン・実施し、彼らの反応を映像記録し、保護者、主催者から聞き取りを行った。その結果、主に次の3点が観察できた。乳幼児は、1.色や線、形といった造形要素、照明、床、家具といった建築的要素、周囲の人的刺激に反応する、2.反応に個人差がある、3.過去の経験や記憶と受けた刺激を関連づけている可能性があるそこから、「美術館」は乳幼児の心理的発達に寄与する可能性があるとし、成果を印刷物にまとめ、国内の美術館、自治体に配布・共有した。
- 著者
- Eisuke Adachi Amato Otani Hiroshi Yotsuyanagi Masayuki Saijo Tomoya Saito
- 出版者
- National Center for Global Health and Medicine
- 雑誌
- Global Health & Medicine (ISSN:24349186)
- 巻号頁・発行日
- pp.2023.01089, (Released:2023-11-27)
- 参考文献数
- 12
At the beginning of the mpox (disease caused by monkey pox) epidemic, there was no platform in Japan to provide appropriate information on emerging and re-emerging infectious diseases (EIDs), and the number of accesses to bioterrorism-related information sites increased rapidly. Even though the interest in mpox was much smaller than in coronavirus infectious disease, emerged in late 2019 (COVID-19), the increase in the number of views were much greater than during the COVID-19 epidemic. This may not be because mpox is bioterrorism-related as an analog of smallpox, but rather because there were no other websites providing information on mpox. For future crisis management, there should be a platform to provide information on possible epidemics of EIDs from normal times in Japan.
- 著者
- 森 将輝
- 出版者
- 日本基礎心理学会
- 雑誌
- 基礎心理学研究 (ISSN:02877651)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.1, pp.50-58, 2022-09-30 (Released:2022-12-16)
- 参考文献数
- 53
When conducting experimental psychology, psychological phenomena are often described in mathematical terms and logic. How practical is the mathematical approach in experimental psychology? This paper aims to explain plain linguistic and mathematical expressions, how psychological phenomena are expressed mathematically in experimental psychology and how mathematical models are constructed, using examples of psychological phenomena related to sensation, perception, and cognition. First, it outlined the perspective, thinking, and utilization of mathematical models in experimental psychology, using some psychological phenomena. Second, it was introduced that several previous studies dealt with spatial properties of perceptual and cognitive phenomena, including the author’s studies. It is hoped that this paper will increase familiarity with and opportunities to utilize mathematical models in experimental psychology.
1 0 0 0 OA 「強い」停戦合意協定は持続的な平和を導くか
- 著者
- 千葉 大奈
- 出版者
- 一般財団法人 日本国際政治学会
- 雑誌
- 国際政治 (ISSN:04542215)
- 巻号頁・発行日
- vol.2015, no.181, pp.181_89-181_102, 2015-09-30 (Released:2016-06-08)
- 参考文献数
- 39
Although there are theoretical reasons to expect that stronger agreements promote durable peace,the extant empirical research provides mixed support for this expectation. This paper reexamines this argument empirically, addressing two inferential problems overlooked in the past studies. First, since the strength of cease-fire agreements is endogenous to the baseline prospect for peace, I employ a copula-based estimation that explains agreement strength and peace duration jointly. Second, I allow the effect of agreement strength to vary over time. This is important because agreement strength matters little right after the war, for there exists a rough consensus among the ex-belligerents about the likely outcome of a next war. As time passes, however, the effect of agreement strength will start to show because there will be a greater chance that some exogenous shocks distort this consensus. Analyzing the duration of postwar peace from 1914 to 2001, I demonstrate that stronger cease-fire agreements indeed stabilize peace after war.
- 著者
- 酒井 潔
- 出版者
- 日本ライプニッツ協会
- 雑誌
- ライプニッツ研究 (ISSN:21857288)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.75-77, 2022-12-20 (Released:2023-11-14)
1 0 0 0 OA 南泉と趙州
- 著者
- 平野 宗浄
- 出版者
- Japanese Association of Indian and Buddhist Studies
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.1, pp.273-276, 1971-12-31 (Released:2010-03-09)
- 著者
- バリー・J.ジマーマン デイル・H.シャンク編集 塚野州一訳
- 出版者
- 福村出版
- 巻号頁・発行日
- 2018
1 0 0 0 OA 心肺停止例の病院前救護における脳内酸素飽和度上昇に影響を与える要因の検討
- 著者
- 原 正浩 長山 英太郎 印藤 昌智 森出 智晴 菩提寺 浩 坂東 敬介 稲童丸 将人 岡本 征仁
- 出版者
- 一般社団法人 日本臨床救急医学会
- 雑誌
- 日本臨床救急医学会雑誌 (ISSN:13450581)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.4, pp.578-583, 2018-08-31 (Released:2018-09-01)
- 参考文献数
- 12
目的:病院前救護における脳内酸素飽和度(tissue oxygen index。以下,TOI)の上昇に影響を与える要因を明らかにする。方法:2015年9月1日〜2016年1月31日の間,心肺停止傷病者に対しNIRO-CCR1を用いてTOIを測定した。結果:データが取得できた109症例でTOI上昇を従属変数としたロジスティック回帰分析を行い,「発症目撃あり,応急手当あり,気管挿管あり,薬剤(アドレナリン)投与あり,医師同乗あり,胸骨圧迫交代あり,胸骨圧迫比率」は1より大きなオッズ比を示し,「男性,心原性,初期波形VF,除細動あり」は1を下回るオッズ比であったが,いずれも統計学的に有意な結果とはならなかった。結論:TOIに与える要因として気管挿管やアドレナリン投与にTOIを上昇させる可能性があり,除細動に胸骨圧迫中断を反映してTOI上昇が得られにくい可能性が示唆されたが統計学的に有意な結果とはならなかった。TOIに与える影響やその先にある心拍再開の期待値などを確立するためには,さらなる臨床研究が望まれる。
1 0 0 0 OA 高品質アコヤガイ真珠の効率的養殖技術の開発と実用化
- 著者
- 青木 秀夫
- 出版者
- 公益社団法人 日本水産学会
- 雑誌
- 日本水産学会誌 (ISSN:00215392)
- 巻号頁・発行日
- vol.81, no.5, pp.788-791, 2015 (Released:2015-10-16)
- 参考文献数
- 30
- 被引用文献数
- 1 1
- 著者
- 原 正浩 上村 修二 大西 浩文
- 出版者
- 一般社団法人 日本臨床救急医学会
- 雑誌
- 日本臨床救急医学会雑誌 (ISSN:13450581)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.5, pp.827-836, 2022-10-31 (Released:2022-10-31)
- 参考文献数
- 13
目的:ウツタイン統計データから,院外心肺機能停止症例の社会復帰率の都道府県間格差に影響を与える地域要因を明らかにする。方法:2006年4月1日〜2015年12月31日の全国ウツタインデータから分析を行った。結果:都道府県における社会復帰率が中央値の6.8%以上と中央値未満の2群で社会復帰率高値群・低値群を従属変数とした多重ロジスティック回帰分析を行い,バイスタンダーによる心肺蘇生法実施率(オッズ比:1.194)および覚知から傷病者接触までの平均時間(オッズ比:0.015)が選択され,ともに有意な結果となった。決定木分析においても,もっとも重要な要因は覚知から傷病者接触までの平均時間(カットオフ値:8.95分)であり,次に重要な要因はバイスタンダーによる心肺蘇生法実施率(カットオフ値:51.05%)となった。結論:覚知から傷病者接触までの時間の短縮とBS-CPR実施率の向上に地域で取り組むことは社会復帰率向上につながる可能性が示唆された。
1 0 0 0 OA 平成6年渇水時における琵琶湖の水環境
- 著者
- 岡本 誠一郎 宇野 孝一
- 出版者
- Japan Society of Civil Engineers
- 雑誌
- 環境システム研究 (ISSN:09150390)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, pp.360-365, 1995-08-15 (Released:2010-03-17)
- 被引用文献数
- 1 1
The life of inhabitants was influenced by the drought and water shortage in 1994 in various places of Japan. Lake Biwa also became an abnormal water shortage and recorded the lowest water level. Then, we carefully controlled the water level of Lake Biwa and other dams. Moreover, to evaluate the influence on the environment by the drought and water shortage, we did an overall environmental investigation of Lake Biwa.To advance‘wise use’of Lake Biwa further, These results can be used.
1 0 0 0 OA 体験欠乏症と創造力の考察
- 著者
- 稲垣 行一郎 加城 貴美子
- 出版者
- 一般社団法人 日本デザイン学会
- 雑誌
- 日本デザイン学会研究発表大会概要集 46
- 巻号頁・発行日
- pp.172-173, 1999-10-15 (Released:2017-11-08)
Students are increasing they study creativities, however their mind are poor and weak for consideration of their problem. That can make it up through communication with physical experience and appreciate the feeling. Above these less experience make students immature for self-formation also undevelopping creativities. Their family drawing indicate less consciousness to their father. In 17% of their answer of SCT also indicate similar result. It has become clear that because of less communication between father and children, the study of human relationship through family could not be real. Apply for creativity study.
- 著者
- Koji HAYASHI Ryo ISHII Tosihiki TAKAMIZAWA Shunichi SUDA Ryota AOKI Kana HAYASHI Atsushi KAMIMOTO Masashi MIYAZAKI
- 出版者
- The Japanese Society for Dental Materials and Devices
- 雑誌
- Dental Materials Journal (ISSN:02874547)
- 巻号頁・発行日
- pp.2023-073, (Released:2023-11-23)
- 参考文献数
- 29
This study aimed to evaluate the influence of surface pretreatment on the shear bond strength of resin luting cement to saliva-contaminated resin core foundation. The surface free energy (γS) of the adherent surfaces was examined. The two-way analysis of variance revealed that the surface pretreatment and storage conditions had a significant effect on the strength of the bond to resin core foundation. The γS values of the saliva-contaminated group were significantly lower than those of the other groups, and they tended to improve after surface pretreatment. The tendency of improvement in γS values differed depending on the type of pretreatment agents. Surface treatment with solutions containing functional monomers is effective in removing saliva contaminants from the resin core foundation surfaces and in creating an effective bonding surface for the resin luting cement.