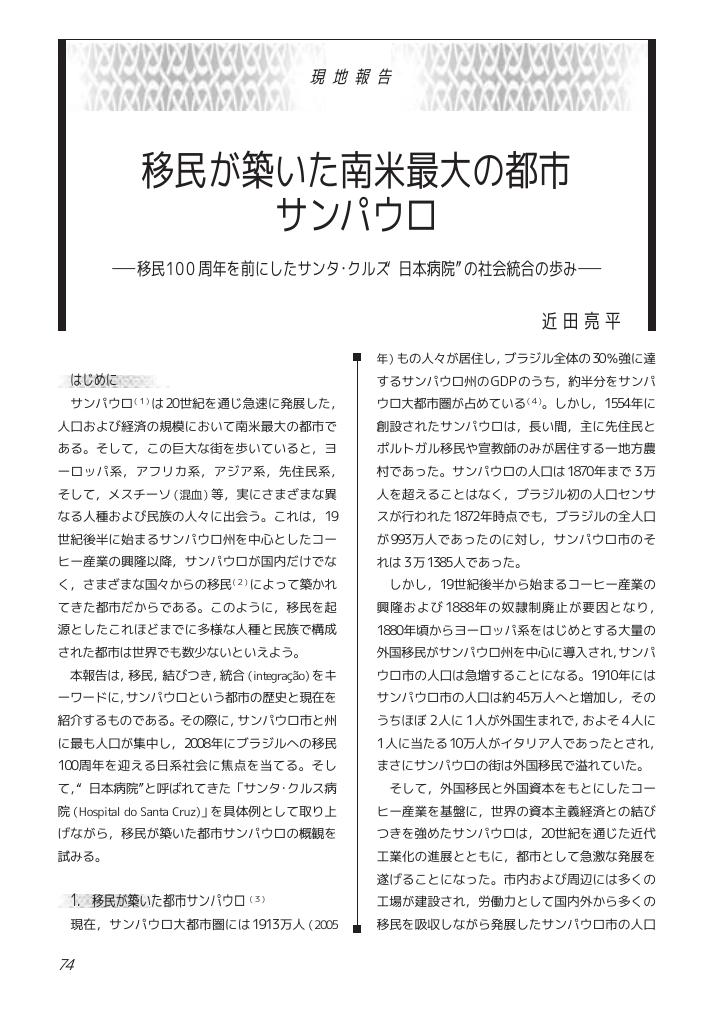1 0 0 0 OA 大学教員人材の流動性に関する実証的研究
- 著者
- 細坪 護挙
- 出版者
- 文部科学省科学技術政策研究所
- 雑誌
- 若手研究(B)
- 巻号頁・発行日
- 2007
本研究では、政府からの研究開発資金の多くを使用しているという観点から、研究者のうち、特に国公立大学教員に焦点を合わせ、その流動性が何を意味するのかを実証的に明らかにすることを目的とする。具体的には、「全国大学職員録」(廣潤社)の掲載情報を電子化し、その属性別の時系列的変化から研究者の流動性の意味を実証的に分析した。なお、本研究の目的は特定個人の状況追跡ではない。また、研究にあたっては個人情報を取り扱うことから、その漏洩防止に万全を期することとする。
1 0 0 0 質の高い心臓マッサージの習得に向けた練習キット
- 著者
- 伊豆 裕一 鈴木 美香
- 出版者
- 一般社団法人 日本デザイン学会
- 雑誌
- デザイン学研究作品集 (ISSN:13418475)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.1, pp.1_48-1_53, 2019-03-31 (Released:2019-03-19)
- 参考文献数
- 5
突然心停止を起こした人を救うために必要な措置である心臓マッサージを、小中学生から高齢者までが興味を持って正しく習得できる学習教材としての、心臓マッサージ練習キットを開発した。 心臓マッサージの実地練習には、従来、人体マネキンが使用されるものの、心臓の圧迫により血液を送り出す仕組みを理解しにくく、また、参加者全員の実習機会が作りにくいとの課題が指摘されてきた。Dock-kun(ドックン)と名付けた本練習キットは、ポンプと透明な浮き輪形状のバルーンを組み合わせることで、水を使った血液の流れや空気の出入りによる、呼吸との連動による心臓マッサージの仕組みの見える化を図った(図1)。さらに、親しみやすい外観デザインと比較的安価な価格を実現することで、指摘されてきた課題を解決した。
1 0 0 0 OA Doc2VecとBERTを用いた日本語作品の著者推定
- 著者
- 清水 大志
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会全国大会論文集 第34回 (2020) (ISSN:27587347)
- 巻号頁・発行日
- pp.3Rin478, 2020 (Released:2020-06-19)
あるテキストをもとに,その著者を推定するという研究は古くから行われている.日本語で書かれたテキストにおいては,単語の使用頻度や品詞のn-gramの分布,読点前の文字の分布といった特徴量に注目した手法が行われてきた.また判別モデルについてもランダムフォレスト法やニューラルネットワークといった様々な機械学習手法が用いられている.ここで本研究では,2014年に提案されたDoc2Vecと2018年に提案されたBERTに注目し,これらとニューラルネットを用いた教師あり学習を行って著者推定を行なった.学習データ及びテストデータとして使用する作品はインターネット上で公開されている青空文庫から取得した.Doc2Vecにおいては作品を数値ベクトルに変換し,それをニューラルネットの入力としている.Doc2Vecにおいては84.89%,BERTにおいては55.43%の精度が達成できた.
1 0 0 0 OA 農業集落排水施設における嫌気る床槽の窒素除去性能に関する一考察
- 著者
- 中野 拓治 北尾 高嶺 糸井 徳彰 堀込 英司
- 出版者
- 社団法人 農業農村工学会
- 雑誌
- 農業土木学会論文集 (ISSN:03872335)
- 巻号頁・発行日
- vol.2001, no.215, pp.573-581,a1, 2001-10-25 (Released:2011-08-11)
- 参考文献数
- 10
嫌気ろ床接触曝気方式の農業集落排水施設から得られたデータを用いて, 嫌気ろ床槽の窒素除去と影響要因を検討したところ, 窒素除去性能には, 流入水のNOx-N存在率 (NOx-N濃度×100/流入水T-N濃度), 流入水のBOD/T-N濃度比, 水量負荷, 流入水のT-N濃度, SS除去, 及び水温が関係しており, これらを説明変数とする重回帰式を用いて嫌気ろ床槽のT-N除去率を推定できることが確認された.嫌気ろ床槽においては, 酸化態窒素の還元反応による脱窒作用以外に, 汚水中の浮遊物質の沈殿・捕捉による浄化作用と槽内に蓄積された物質等の溶出作用が生じており, 複雑な浄化機構が存在しているものと考えられる。嫌気ろ床槽の窒素除去性能の安定を図るためには, 流入水中の酸化態窒素濃度を高めることと併せて, 水素供与体, 水温, 水理学的滞留時間等の確保を通じて酸化態窒素の円滑な還元作用を進めるとともに, 汚水中のSS除去によりSS由来の窒素を適切に除去することが重要であるといえる.
本研究の目的は、生活習慣病のリスクを高める量の飲酒を行っている過剰飲酒者に対して、微アルコール飲料の提供でアルコール摂取量が減るのかを介入試験で検証することである。過剰飲酒は危険な飲酒パターンの一つであり、生活習慣病以外にもアルコール依存症、がんなどの慢性的な健康障害が惹き起こされる。本研究では、地球規模課題である過剰なアルコール摂取の改善を図るための有用な資料を世に提供することで、政策提言を含む効果的な対策を行うことが可能となる。新型コロナ流行に伴い、飲酒量の増加とアルコール関連問題の増加が世界中で確認されており、本研究のテーマは非常に重要であり、かつ喫緊の課題と考えられる。
1 0 0 0 OA 漢方生薬配合薬の抗真菌活性と牛白癬の治療効果
1 0 0 0 OA 自殺関連血中バイオマーカーからの自殺予測およびパターンの探索
- 著者
- 土嶺 章子
- 出版者
- 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター
- 雑誌
- 若手研究(B)
- 巻号頁・発行日
- 2015-04-01
1)健常男性において新奇性追求の一部の項目である浪費のスコアとフリーテストステロンに正の相関が見られた。フリーテストステロンの量が多い男性では衝動性が高い可能が示唆された。2)児童思春期のうつ病患者では血中のアラキドン酸(AA)、ドコサヘキサエン酸(DHA)、葉酸が低値を示した。しかし脳由来神経栄養因子(BDNF)に差は認められなかった。3)うつ病、躁うつ病、統合失調症の患者では血中オレキシン濃度の低下が認められた。特に躁うつ病では顕著であった。
1 0 0 0 OA タイ国の紙パルプ産業の現状と展望 (その2)
- 著者
- 小林 良生
- 出版者
- JAPAN TECHNICAL ASSOCIATION OF THE PULP AND PAPER INDUSTRY
- 雑誌
- 紙パ技協誌 (ISSN:0022815X)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.8, pp.1173-1179, 2002-08-01 (Released:2009-11-19)
- 参考文献数
- 16
The shift of the policy of pulp and paper industries from non-woody raw materials such as kenaf and bagasse to wood chips accelerated plantation of eucalyptus, especially Eucalyptus camldulensis in North-East in Thailand. Phoenix Pulp and Paper Co., Ltd. switched from kenaf to eucalyptus and bamboo after several years' operation in 1987. Advance Agro Co. belonging to Soon Hua Seng Conglomerate has entered in these industries in the late 1980 s and the early 1990 s with plantation of eucalyptus in their own farmers' network fields. In spite of strong farmers' resistance movement against the plantation, eucalyptus plantation is gradually and steadily prevailing in North-East Area in Thailand. FAO organized a symposium to confirm scientifically the evaluation of eucalyptus plantation. The conclusive argument pro and con eucalyptus plantation provided by FAO was introduced. Finally research organizations concerning pulp and paper as well as afforestation were also mentioned.
- 著者
- 横堀 將司 藤倉 輝道
- 出版者
- 日本医科大学医学会
- 雑誌
- 日本医科大学医学会雑誌 (ISSN:13498975)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.2, pp.129-134, 2022-04-25 (Released:2022-05-12)
- 参考文献数
- 3
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA 沙漠緑化の新展開を考える
- 著者
- 近田 亮平
- 出版者
- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所
- 雑誌
- ラテンアメリカ・レポート (ISSN:09103317)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.2, pp.74-78, 2006 (Released:2022-05-26)
1 0 0 0 OA 「坂東曲」伝説の一考察(第六部会,<特集>第六十七回学術大会紀要)
- 著者
- 御手洗 隆明
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.82, no.4, pp.1169-1170, 2009-03-30 (Released:2017-07-14)
1 0 0 0 OA 統計熱力学計算と進化分子工学を用いたGPCR安定化変異体の創出手法
- 著者
- 安田 賢司
- 出版者
- 一般社団法人 日本生物物理学会
- 雑誌
- 生物物理 (ISSN:05824052)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.5, pp.252-256, 2023 (Released:2023-11-25)
- 参考文献数
- 20
Gタンパク質共役型受容体(GPCR)は重要な創薬標的であるが,本質的に不安定あり,すぐに変性してしまうことが研究の大きな障害となっている.本稿では,統計熱力学に基づく独自の理論的手法と進化分子工学を組み合わせることにより構築した,安定化変異体の創出手法について紹介する.
1 0 0 0 OA ATP合成酵素から進化したマイコプラズマ滑走モーターの構造
- 著者
- 豊永 拓真 宮田 真人
- 出版者
- 一般社団法人 日本生物物理学会
- 雑誌
- 生物物理 (ISSN:05824052)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.5, pp.270-272, 2023 (Released:2023-11-25)
- 参考文献数
- 9
魚病原菌であるマイコプラズマ・モービレの滑走運動は,ATP合成酵素から進化したと考えられるモーターによって駆動されている.私たちはその特殊なモーターを単離し,電子顕微鏡解析によってその三次元構造を明らかにした.その構造はATP合成酵素の二量体が鎖状に連なったような新奇なものであった.
1 0 0 0 OA 今がチャンス!
- 著者
- 村田 武士
- 出版者
- 一般社団法人 日本生物物理学会
- 雑誌
- 生物物理 (ISSN:05824052)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.5, pp.243, 2023 (Released:2023-11-25)
1 0 0 0 OA ロスレススナバを用いたソフトスイッチング形単相高力率コンバータ
- 著者
- 谷口 勝則 西山 訓央 木村 紀之
- 出版者
- The Institute of Electrical Engineers of Japan
- 雑誌
- 電気学会論文誌D(産業応用部門誌) (ISSN:09136339)
- 巻号頁・発行日
- vol.115, no.1, pp.84-85, 1994-12-20 (Released:2008-12-19)
- 参考文献数
- 3
- 被引用文献数
- 6 9
1 0 0 0 OA 1950年のモスクワ放送日本語番組――冷戦期の日本語放送に対する評価と改革提言
- 著者
- 島田 顕
- 出版者
- 早稲田大学アジア太平洋研究センター
- 雑誌
- アジア太平洋討究 (ISSN:1347149X)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, pp.85-101, 2022-02-28 (Released:2022-03-24)
- 参考文献数
- 42
The broadcast of the Japanese programs to Japan by Moscow Radio, which started in April 1942 during World War II, had various defects. However, the broadcast itself continued without any improvement. Then, in the postwar Cold War period, the Japanese programs of Moscow Radio became a part of communist propaganda to the “West”. What points have come to be emphasized in the radio broadcast to Japan by Moscow Radio during the postwar Cold War period? In addition, have the various shortcomings of Japanese programs that have been overlooked so far been overcome? How has postwar Japanese broadcast changed compared to broadcast during WWII?The purpose of this paper is to clarify the role played by the Japanese programs by Moscow Radio during the postwar Cold War period and the points to be improved in the broadcast programs in line with them, and to consider their meanings. How was the Cold War trying to change Japanese broadcasting?This paper consists of six sections: first, summary of study of the Radio Moscow and broadcast programs in Japanese from WWII to period of Cold War; second, criticisms and improvements of defects in the Cold War; third, persons involved in the improvement; fourth, frequencies and broadcast times of Japanese programs; fifth, relation of Japanese programs to Cold War; sixth, generalization of radio broadcast of Japanese programs to Japan in 1950.
1 0 0 0 OA Virtual Reality技術を活用した外科系臨床実習
- 著者
- 進士 誠一 横堀 將司 清水 哲也 神田 知洋 林 光希 安康 勝喜 吉田 寛
- 出版者
- 日本医科大学医学会
- 雑誌
- 日本医科大学医学会雑誌 (ISSN:13498975)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.1, pp.98-104, 2022-02-20 (Released:2022-03-15)
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 2
During their clinical clerkships (CCs) in surgery, medical students are generally introduced to such areas as surgical indications, surgical techniques, and perioperative management through rounds and practical skills training on wards and in operating rooms. Given the technological advances made in virtual reality (VR) over recent years and its increasing use in education and corporate training, we decided to try using VR for the benefit of students on surgical CCs. To this end, we developed what we termed a "VR surgery tour" in the field of gastrointestinal surgery, which involved students using VR goggles to view edited 3D images. We then asked 26 fifth- and sixth-year medical students at Nippon Medical School assigned to CCs in gastrointestinal surgery between November 2020 and September 2021 to evaluate the VR surgery tour via a questionnaire survey. The questionnaire included questions using a five-point Likert scale and space for free comments. Our results showed that all respondents felt satisfied with the VR surgery tour, with 96% of them indicating it was a viable alternative to clinical training; moreover, about 90% of the students found it useful as a teaching aid for pre-learning and requested that VR teaching materials be made available in other fields as well. We concluded that our VR surgery tour is a valuable supplement to practical training in gastrointestinal surgery and that it increases medical students' motivation to learn. We believe VR is an effective teaching aid and that there will be increasing demand for its use in various education and training programs.
1 0 0 0 OA 火の玉とプラズマ
- 著者
- 大槻 義彦
- 出版者
- 一般社団法人 電気学会
- 雑誌
- 電氣學會雜誌 (ISSN:00202878)
- 巻号頁・発行日
- vol.109, no.5, pp.367-370, 1989-05-20 (Released:2008-04-17)
- 参考文献数
- 2