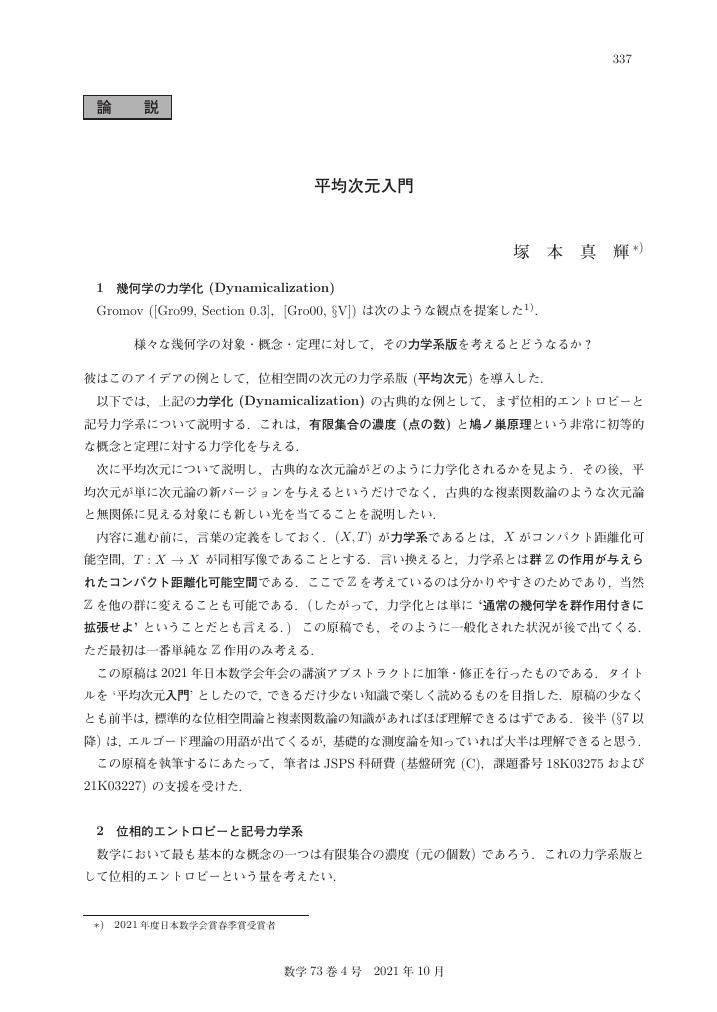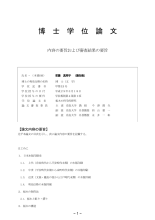1 0 0 0 OA QRS時間の延長が意味するもの
- 著者
- 岡村 祥央 中野 由紀子
- 出版者
- 一般社団法人 日本不整脈心電学会
- 雑誌
- 心電図 (ISSN:02851660)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.1, pp.58-65, 2023-04-04 (Released:2023-04-07)
- 参考文献数
- 12
QRS時間の延長は脚ブロックなどの心室内伝導障害だけでなく,副伝導路症候群や心室不整脈など,様々な病態で目にする.12誘導心電図のQRS波形を読み解くことで,心室内刺激伝導系の遅延伝導部位や副伝導路の局在,および心室不整脈の起源を評価することが可能であり,正常心電図を含めたQRS波形を理解することが重要である.さらに背後に隠れている基礎心疾患の鑑別も重要であり,特に心室内伝導障害や心室不整脈の原因にはサルコイドーシスのような早期治療介入により心筋障害が改善する疾患も存在する.QRS時間の延長は独立した予後不良因子であり,特に左脚ブロックに関しては心臓再同期療法などの治療介入により,積極的にQRS時間の短縮を目指す必要がある.また副伝導路症候群や心室不整脈に対しては,症例ごとにカテーテルアブレーションや植込み型除細動器の適応を検討すべきである.
- 著者
- Yuki Sakurai Yoshitaka Furuto Takahiro Saito Akio Namikawa Hiroko Takahashi Yuko Shibuya
- 出版者
- The Japanese Society of Internal Medicine
- 雑誌
- Internal Medicine (ISSN:09182918)
- 巻号頁・発行日
- pp.1413-22, (Released:2023-05-10)
- 参考文献数
- 31
- 被引用文献数
- 1
A 79-year-old man experienced a fever and immobility after receiving 6 doses of Bacillus Calmette-Guerin (BCG) intravesical instillation therapy for bladder tumor. Rhabdomyolysis and acute kidney injury occurred; therefore, hemodialysis was performed. His kidney function was restored. However, he exhibited an inflammatory reaction that was resistant to broad-spectrum antibiotics and eventually developed interstitial pneumonia. Corticosteroid treatment partially relieved the symptoms of interstitial pneumonia, although disuse syndrome persisted. He was diagnosed with disseminated BCG infection through sputum culture. BCG infection shows various symptoms and is difficult to diagnose microbiologically. It should be suspected when systemic symptoms occur after BCG intravesical instillation therapy.
1 0 0 0 OA 食事中トランス脂肪酸による肝発癌促進機構の解明と予防法の開発
トランス脂肪酸は日常生活で我々が頻繁に食する脂肪酸である。米国ではトランス脂肪酸摂取が禁止されているが、我が国ではトランス脂肪酸の健康被害に関する科学的根拠が乏しいとの理由で、その摂取に注意が払われていない。我々はトランス脂肪酸が肝癌を促進させる可能性を見出したが、そのメカニズムは不明である。本研究では、食事中トランス脂肪酸が肝臓に与える影響を多角的に解析し、その毒性を機能性食品で軽減する方法も探索する。トランス脂肪酸毒性に関する明確な科学的根拠とその予防戦略を提示できれば、国民の食生活の改善や健康寿命延伸、新規産業創出につなげられる可能性があると考えている。
1 0 0 0 パソコンアニメ入門
- 著者
- オフケンアート研究会編
- 出版者
- コンピュータ・エージ社
- 巻号頁・発行日
- 1983
1 0 0 0 ナトリウム利尿ペプチドによる熱産生作用とインスリン抵抗性改善効果
ナトリウム利尿ペプチドは不全心筋より分泌される抗心不全ホルモンとして知られているが、脂肪組織への作用は明らかではない。当施設の先行研究では、循環不全による組織低温環境やインスリン抵抗性をきたす重症心不全、さらには肥満・糖尿病などの病態に対して、このホルモンがこれまで知られていなかった治療効果(熱産生効果・インスリン抵抗性改善)をもたらす可能性がある。本研究は基礎研究と臨床研究の両面からアプローチし、心臓-脂肪連関という新たな病態概念の確立を目的とする。本研究成果は心不全治療の概念を変え、肥満治療という観点や心不全治療へのResponderを見出すことで新たな治療戦略を提示できるものと考える。
1 0 0 0 OA 交流電気車の進歩
- 著者
- 入江 則公
- 出版者
- 一般社団法人 電気学会
- 雑誌
- 電氣學會雜誌 (ISSN:00202878)
- 巻号頁・発行日
- vol.83, no.895, pp.423-432, 1963-04-01 (Released:2008-11-20)
- 参考文献数
- 1
1 0 0 0 Hinduism and tribal religions
- 著者
- Jeffery D. Long ... [et al.] editors
- 出版者
- Springer
- 巻号頁・発行日
- 2022
1 0 0 0 OA 八条宮智仁親王サロンの主要な活動と構成員
- 著者
- 町田 香
- 出版者
- 公益社団法人 日本造園学会
- 雑誌
- ランドスケープ研究 (ISSN:13408984)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.5, pp.371-374, 2003 (Released:2003-09-24)
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 1 1
I make clear character and existence significance of a Imperial Prince Toshihito salon at dawn of the Kanei culture from main activity and member of a salon so that early modern times early days Imperial Court garden cultural history positions existence of Imperial Princes Toshihito Hachijou-no-Miya aloft. As a result of I collected evidence of activity and a member of a salon from a handwriting of the Imperial Prince Toshihito and the inside of a diary class of the same period, and having compared it with “the Imperial Prince Toshihito annuals” that I could judge will of the Imperial Prince Toshihito to be reflected powerfully, the salon did an activity of composing a poem with the subject, and the original character that a renga poet Satomura family was a main member became clear. In addition, it was a member of the royalty, and this salon which the Imperial Prince Toshihito who was an aspect biography person of ancient and modern times instruction sponsored was able to point out the important significance that was existence to take a one axis of classic revival activity in the Imperial Court.
1 0 0 0 OA 評価倫理における「評価協力者の尊重」の検討 -心理学分野の研究倫理からの示唆-
- 著者
- 小林 信行
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本評価学会
- 雑誌
- 日本評価研究 (ISSN:13466151)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.1, pp.1-14, 2020-03-31 (Released:2023-06-01)
- 参考文献数
- 24
本稿は、心理学分野の研究倫理における研究協力者への配慮を視座に、評価倫理における基本原則「人々への敬意」に関する論考を行う。そして、その論考を踏まえ、日本評価学会の「評価倫理ガイドライン」で今後反映すべき事項に関する示唆を導出する。心理学分野では、研究は実践活動よりも高リスクと見なされ、研究に先立ち倫理審査が求められる。同様に、評価協力者に著しいリスクが生じる可能性がある場合、類似する審査が望まれ、その要否の判断基準が検討課題となる。「評価倫理ガイドライン」は、評価が介入の割り付けを決定する状況を想定しないため、前記の状況でのインフォームド・コンセント、許容される統制群の設定も検討課題となる。研究倫理の「実践」から、幾つかの課題も明らかとなった。倫理審査が調査手法の選定に影響し、特定の手法を忌避する傾向が見られた。また、「理論」が提示する複数の基本原則どうしが衝突し、倫理的な判断が困難となった結果、倫理面の配慮が研究協力者の負担を重くするケースも生じている。
1 0 0 0 OA 平均次元入門
- 著者
- 塚本 真輝
- 出版者
- 一般社団法人 日本数学会
- 雑誌
- 数学 (ISSN:0039470X)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.4, pp.337-359, 2021-10-22 (Released:2023-10-23)
- 参考文献数
- 31
1 0 0 0 OA 西南日本外帯花崗岩の下には何があるか:熊野酸性岩を例として
- 著者
- 中島 隆 下司 信夫 及川 輝樹
- 出版者
- 一般社団法人 日本地質学会
- 雑誌
- 日本地質学会学術大会講演要旨 第117年学術大会(2010富山) (ISSN:13483935)
- 巻号頁・発行日
- pp.255, 2010 (Released:2011-03-31)
- 参考文献数
- 4
1 0 0 0 OA 沖縄県久米島近世人骨の距骨蹲踞面形状と 脛骨蹲踞面形状の関係
- 著者
- 蔵元 秀一 譜久嶺 忠彦 久高 将臣 西銘 章 石田 肇
- 出版者
- 一般社団法人 日本人類学会
- 雑誌
- Anthropological Science (Japanese Series) (ISSN:13443992)
- 巻号頁・発行日
- vol.117, no.2, pp.55-63, 2009 (Released:2009-12-25)
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 2 2
久米島近世の成人距骨193個体343側,脛骨151個体227側を用い,距骨蹲踞面形状を5型{ストレート型,内側関節面前方延長型,内側蹲踞面型(複合1),内側蹲踞面型+外側滑車面前方延長型(複合2),内側関節面前方延長型+外側滑車面前方延長型(複合3)}に,脛骨は外側蹲踞面有りと無しの2型に分類した。結果,1)男性は女性より,複合2と複合3の出現頻度が高い傾向にあり,複合2の右側で男性の頻度が有意に高い。2)左右差では,女性の複合1で右側の頻度が有意に高い。3)脛骨外側蹲踞面の出現頻度も男性が女性に比べて高い。4)脛骨外側蹲踞面が存在する時は,距骨に外側滑車面前方延長型を伴うことが多い。距骨および脛骨蹲踞面出現頻度から,久米島近世人骨では男性の方が女性よりも蹲踞姿勢を習慣的にとっていると考えられた。距骨蹲踞面形成を運動学的に解釈すると,内側蹲踞面は足関節が伸展(以下,背屈)することにより,距骨内側部と脛骨下端部に靭帯や関節包などの軟部組織がはさまれて形成される。足関節がさらに背屈すると,距骨外側滑車面前方部と脛骨下端前縁部外側が衝突し,距骨の外側蹲踞面が形成されると思われる。本土の縄文時代,江戸時代および近代人骨よりも,距骨蹲踞面と脛骨外側蹲踞面の出現頻度が低いことから,久米島近世人骨においては習慣的な蹲踞姿勢が少なかった可能性を示した。
1 0 0 0 OA 院外心肺停止症例に対する救急救命士の治療介入の年次推移の検討
- 著者
- 山田 哲久 名取 良弘 熊城 伶己 三股 佳奈子 松元 宗一郎 香月 洋紀
- 出版者
- 日本脳死・脳蘇生学会
- 雑誌
- 脳死・脳蘇生 (ISSN:1348429X)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.2, pp.58-61, 2020-08-11 (Released:2020-08-11)
- 参考文献数
- 11
[Purpose] Our hospital is the only emergency and critical care center in the region serving a population of 420,000. The number of emergency transports is 7,000-7,500 annually, and the number of cardiopulmonary arrest cases is 250-300. Early intervention is necessary to return of spontaneous circulation in patients with cardiopulmonary arrest. Herein, we analyzed the transition of treatment interventions by emergency medical service paramedics annually and examined pre-hospital interventions for return of spontaneous circulation before arriving at the hospital.[Methods] We included 2,010 adults with out-of-hospital cardiopulmonary arrest between 2011 and 2018. We conducted an annual review on the following aspects: number of cases per year, rate of return of spontaneous circulation before arrival at hospital, rate of bystander witness, rate of bystander cardiopulmonary resuscitation, rate of cardioversion by paramedics, rate of securing venous access by paramedics, rate of adrenaline administration by paramedics, and rate of advanced airway management by paramedics.[Results] The number of cases remained approximately 250, and the rate of return of spontaneous circulation before arrival at the hospital increased. As for treatment by a paramedic, the cardioversion rate remained unchanged at 10-15%, and the venous access rate and adrenaline administration rate increased. There was no change in the rate of advanced airway management, and it remained at approximately 10%.[Conclusion] To return of spontaneous circulation before arriving at the hospital, it was considered for the paramedic to perform venous access and administer adrenaline.
- 著者
- 平松 佑一 山脇 正嗣 田頭 直樹 北川 照晃
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- AI・データサイエンス論文集 (ISSN:24359262)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.3, pp.897-908, 2023 (Released:2023-11-14)
- 参考文献数
- 22
近年の建設分野ではBIM/CIMが推進されており,そこでは3次元点群データの有効活用が大きく寄与する.一方で,大容量の点群情報の取り扱いは課題が多く,計算負荷を抑制しながら効率的に処理する必要がある.そこで本研究では,AI(Artificial Intelligence)技術の一種である深層学習(Deep Learning)を用いて,点群をクラス分けする技術である点群セグメンテーションを適用した.実務上のニーズを踏まえ,河川構造物設計および維持管理分野での活用を想定した点群のサーフェスモデル化を検証した.実データを用いて実際のモデル化の流れを提示し,必要な情報を失うことなく効率的にモデル化することで,3Dモデリングによる高度化および省力化に寄与する可能性を示した.
1 0 0 0 OA 繊維が生体に及ぼす影響《繊維反応性疾患》
- 著者
- Chris L. Ludlow
- 出版者
- 日本ペット栄養学会
- 雑誌
- ペット栄養学会誌 (ISSN:13443763)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.Supplement, pp.32-36, 1999-06-21 (Released:2012-09-24)
1 0 0 0 OA AED実施に先行する長時間の適正な胸骨圧迫が良好な神経学的転帰の鍵となった心肺停止の1例
- 著者
- 吉川 恵次 高橋 将史 行田 祐樹 川井 桂 羽柴 正夫
- 出版者
- 一般社団法人 日本救急医学会
- 雑誌
- 日本救急医学会雑誌 (ISSN:0915924X)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.4, pp.219-228, 2008-04-15 (Released:2009-07-19)
- 参考文献数
- 21
症例は58歳,男性。アルコール依存症で某精神病院に入院中。原因不明の心肺停止(CPA)を来した時期は抗酒薬の投与で無症状,安定期にあった。某日,午前 6 時55分,病棟ホールでCPAとなった。CPAの 1 分後から,胸骨圧迫の中断をできる限り少なくした心肺蘇生(CPR)を開始,継続した。卒倒から14分後に初回のAED通電, 3 回目の通電が心肺停止後30分での自己心拍再開に繋がった。転院先病院での低体温療法を併用しない集中治療の後,患者の神経学的所見はCPA前の程度にまで回復,良好な神経学的転帰が得られた。本症例はCPAからAED実施まで経過時間が長い場合でも,適正なCPRが実施されれば脳血流の維持による良好な神経学的転帰が期待できることを示した症例と考えられる。AED心電図では心室細動に対するアドレナリン投与の有効性が示唆された。
- 著者
- Hitomi Numamoto Koji Fujimoto Kanae Kawai Miyake Yasutaka Fushimi Sachi Okuchi Rimika Imai Hiroki Kondo Tsuneo Saga Yuji Nakamoto
- 出版者
- Japanese Society for Magnetic Resonance in Medicine
- 雑誌
- Magnetic Resonance in Medical Sciences (ISSN:13473182)
- 巻号頁・発行日
- pp.mp.2023-0102, (Released:2023-11-10)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 1
Purpose: To compare image distortion and reproducibility of quantitative values between reverse encoding distortion correction (RDC) diffusion-weighted imaging (DWI) and conventional DWI techniques in a phantom study and in healthy volunteers.Methods: This prospective study was conducted with the approval of our institutional review board. Written informed consent was obtained from each participant. RDC-DWIs were created from images obtained at 3T in three orthogonal directions in a phantom and in 10 participants (mean age, 70.9 years; age range, 63–83 years). Images without distortion correction (noDC-DWI) and those corrected with B0 (B0c-DWI) were also created. To evaluate distortion, coefficients of variation were calculated for each voxel and ROIs were placed at four levels of the brain. To evaluate the reproducibility of apparent diffusion coefficient (ADC) measurements, intra- and inter-scan variability (%CVADC) were calculated from repeated scans of the phantom. Analysis was performed using Wilcoxon signed-rank test with Bonferroni correction, and P < 0.05 was considered statistically significant.Results: In the phantom, distortion was less in RDC-DWI than in B0c-DWI (P < 0.006), and was less in B0c-DWI than in noDC-DWI (P < 0.006). Intra-scan %CVADC was within 1.30%, and inter-scan %CVADC was within 2.99%. In the volunteers, distortion was less in RDC-DWI than in B0c-DWI in three of four locations (P < 0.006), and was less in B0c-DWI than in noDC-DWI (P < 0.006). At the middle cerebellar peduncle, distortion was less in RDC-DWI than in noDC-DWI (P < 0.006), and was less in noDC-DWI than in B0c-DWI (P < 0.0177).Conclusion: In both the phantom and in volunteers, distortion was the least in RDC-DWI than in B0c-DWI and noDC-DWI.
1 0 0 0 OA 「アメリカ」を語ることから〈文化〉を問う
- 著者
- 吉見 俊哉
- 出版者
- 関東社会学会
- 雑誌
- 年報社会学論集 (ISSN:09194363)
- 巻号頁・発行日
- vol.2005, no.18, pp.2-15, 2005-08-05 (Released:2010-04-21)
In the field of cultural studies, I have been tackling the problem of Americanism in East Asia. My focus is on the everyday cultural reception of “America” among the people of East Asia since the end of the Second World War. I have been reviewing the relationship with America built up especially during the period of the Cold War from a comprehensive regional perspective, taking into account the level of people's everyday consciousness and culture along with the military and politico-economic aspects. Despite the evident importance of research on such a wide-ranging and complex phenomenon, hardly any attempt has been made until very recently to study the significance of “America” in a region-wide context. The new approach we need relates to the field of post-colonial studies in East Asia. The postwar dominance of America in East Asia is, in a certain sense, a reconstruction of the Japanese imperial order that existed until the end of the war. It is essential that the mediating role of “America” be considered in investigations of the further postwar development of colonial consciousness and practice in Asia under the Cold War order.
1 0 0 0 OA 映像メディア視聴者の情動制御のための物理特徴量の抽出
- 著者
- 入江 健介 中田 俊史 中岡 伊織 李 林甫 高木 英行
- 出版者
- 日本知能情報ファジィ学会
- 雑誌
- 日本知能情報ファジィ学会 ファジィ システム シンポジウム 講演論文集 第22回ファジィ システム シンポジウム
- 巻号頁・発行日
- pp.48, 2006 (Released:2007-05-30)
マルチメディア視聴者の情動生理に影響を与える物理特徴量候補を生理計測なしで抽出する方法を提案し,映像メディアから抽出した.マルチメディア視聴者の生理状態を制御しメディア効果を強調するためには,第1段階として,生理反応に影響を与えるであろう物理特徴量を抽出する必要があるが,考えられる限りの物理特徴量を1つずつ生理計測しながら特定することは現実的ではない.そこで,生理反応に直接対応すると思われる緊張_-_弛緩軸と爽快_-_鬱屈軸からなる情動平面を考え,心理評価によって60の映画シーンを情動平面に割り付ける.76個の物理特徴量を考え,これらの特徴量と2軸との相関係数を求め,危険率1%で有意に相関がある場合,生理反応に影響を与える物理特徴量候補として抽出した.このように時間のかかる生理計測なしで,生理反応に影響を与える物理特徴量候補を26+2個特定したので,今後の生理実験で検証していく.