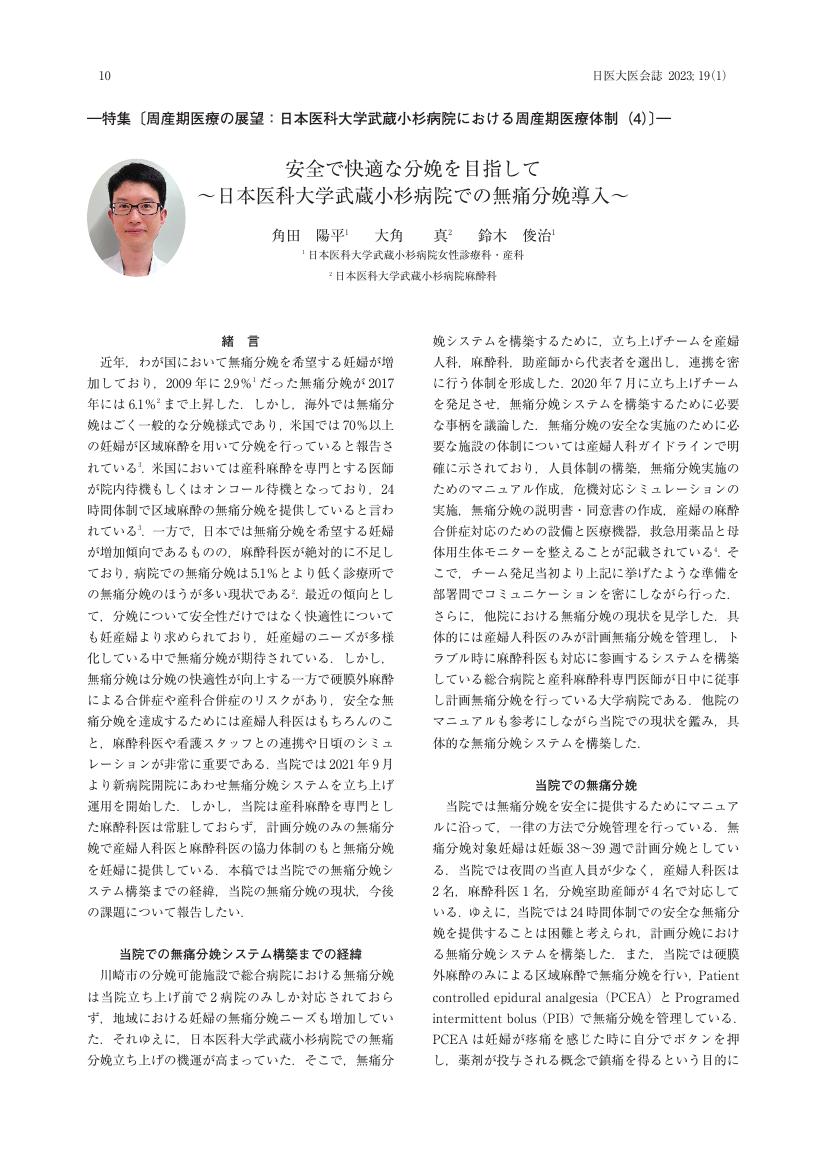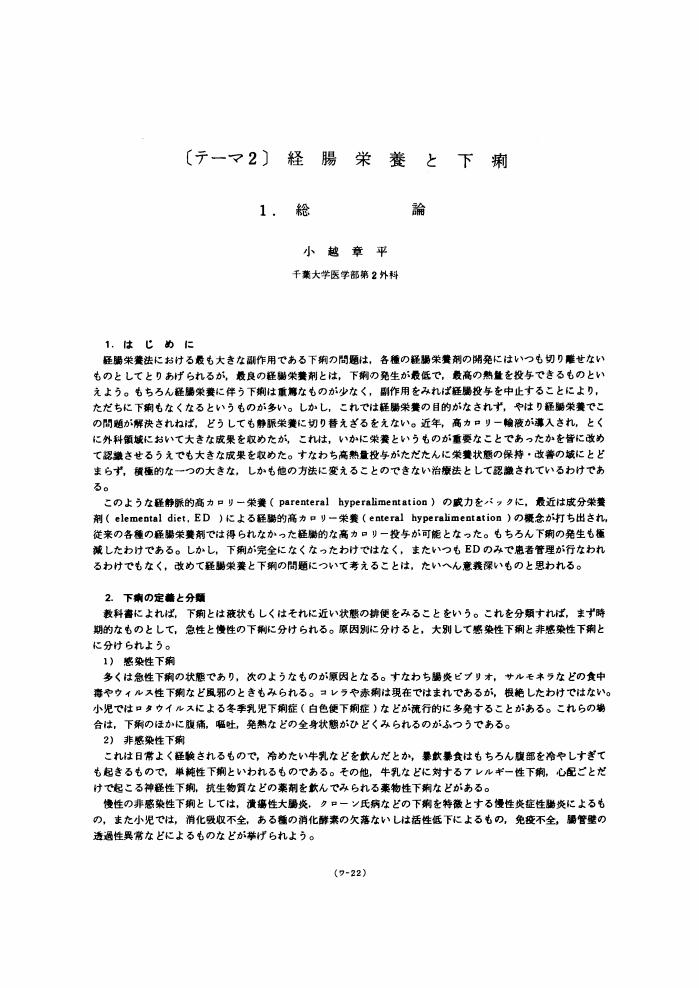1 0 0 0 OA 歯による個人識別におけるDNA分析の有用性
- 著者
- 渡邉 麻子
- 出版者
- Japanese Association for Oral Biology
- 雑誌
- 歯科基礎医学会雑誌 (ISSN:03850137)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.4, pp.241-248, 1998-08-20 (Released:2010-06-11)
- 参考文献数
- 38
- 被引用文献数
- 1
法医実務において, 死体の個人識別に伴う, 性別, ABO式血液型の特定は最も基本的な作業である。近年, それらの作業にDNA分析が取り入れられ, PCR法の応用が主流となりつつある。特に歯は保存性の高さからDNA抽出源として重要性を増している。本研究では髄壁象牙質に残った髄壁細胞からDNAを抽出し, PCR法による性別判定およびABO式遺伝子型判定を試みた。神奈川県在住の患者から抜歯された性別既知の40歯を用いたところ, 性別は抜去歯すべてにおいて正確に判定された。またABO式遺伝子型は, 40歯中35歯の判定が可能であった。遺伝子頻度は, A (p); 0.443, B (q); 0.214, そしてO (r); 0.343であり, 日本人の平均遺伝子頻度に比べ, r遺伝子が低い傾向を示したが, PCR法で判定不可能であった5歯について, 歯髄を用いた解離試験の結果 (すべてO型) を参考にすれば, ほぼ平均的な遺伝子頻度となり, 分析結果の確実性を証明した。
- 著者
- Zhu Wenrui Miura Makoto
- 出版者
- Japanese Society for Food Science and Technology
- 雑誌
- Food Science and Technology Research (ISSN:13446606)
- 巻号頁・発行日
- pp.FSTR-D-23-00167, (Released:2023-11-29)
Milk proteins play an essential role in yogurt manufacture, by adsorbing onto the fat globule interface. This study aims to clarify the impacts of milk fat globules on the physicochemical properties of stirred yogurt, by modifying the particle size distribution of fat globules in reconstituted milk. The results show that high-pressure homogenization increased the association between milk proteins and milk fat globules. The zeta potential and protein surface hydrophobicity of reconstituted milk samples increased. Stirred yogurt prepared with reconstituted milk homogenized at high pressure (≥ 20 MPa) exhibited a fine mesoscopic structure with higher water holding capacity and apparent viscosity. Based on transmission electron microscopy and atomic force microscopy, the milk fat globules tended to form effective connections with casein micelles, giving the yogurt a finer network structure and higher viscosity. These findings reveal that controlling milk fat globule size can effectively improve stirred yogurt quality.
1 0 0 0 OA 教育社会学研究 総目次(第50~99集)解説 ――教育社会学の研究動向――
- 著者
- 丹治 恭子
- 出版者
- 日本教育社会学会
- 雑誌
- 教育社会学研究 (ISSN:03873145)
- 巻号頁・発行日
- vol.100, pp.215-222, 2017-07-28 (Released:2019-03-08)
- 参考文献数
- 4
1 0 0 0 OA 楽器用材の利用 : ピアノ製造業を事例として
- 著者
- 大代 朋和
- 出版者
- 応用森林学会
- 雑誌
- 森林応用研究 (ISSN:13429493)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, pp.13-18, 1999-03-25 (Released:2018-01-16)
楽器用の木材は音響上高品質が要求される。本研究では日本国内で大量に生産されているピアノに注目し,ピアノに使用される木材,特に響板材料がどのように変化しているのか明らかにする。日本においてピアノ生産が本格的に開始されたのは戦後のことである。特に昭和30年代後半からピアノの生産量は急増した。このピアノ生産量の増加に対応するために原材料,特に木材の安定供給が必要不可欠であった。当時日本で一般的に使用されていた響板材料であるエゾマツは資源量が減少し,伐採量も急激に落ち込み始めていた。しかし昭和36年に木材の輸入が自由化され,エゾマツの代替材としてシトカスプルースが使用され始めた。現在ではシトカスプルースが供給の安定性という点で主流となっている。しかしながら,量的には少なくなっているがエゾマツの利用が続いているほか,近年ではヨーロピアンスプルースやチャイニーズスプルースの利用が始まっている。ピアノ製造業では,ピアノ需要の落ち込みによる生産量減少に対応するため,グレードの違う木材を利用することで幅広いユーザーの獲得を目指している。
1 0 0 0 OA 安全で快適な分娩を目指して~日本医科大学武蔵小杉病院での無痛分娩導入~
- 著者
- 角田 陽平 大角 真 鈴木 俊治
- 出版者
- 日本医科大学医学会
- 雑誌
- 日本医科大学医学会雑誌 (ISSN:13498975)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.1, pp.10-14, 2023-02-20 (Released:2023-03-11)
- 参考文献数
- 12
1 0 0 0 犯罪の可視化-ニュース言説における逸脱と統制の研究
本研究は、昨年度から継続しており、犯罪事件のニュース言説において「犯罪」がいかに語られ、「犯罪」のリアリティはどのように社会的に構築され、可視化されるか、構築主義の視点から考察するものである。本年度(1998年度)においては、1997年に引き続き、神戸で起きた小学生殺害事件に関する資料収集、新聞記者へのインタビュー、さらに、1998年夏に和歌山県で起きた殺人事件に関する資料収集並びにその関係者へのインタビューなどを行った。いかなる事件であろうと、記者たちは日常の取材活動のルーティンにしたがっている。情報源が警察に偏っていることは、従来からも指摘されているが、ルーティン以外での情報収集がなされても、記事化されにくい。神戸の事件に関しては、被疑者が少年であること自体が、報道機関の情報源を限定させた。記事のニュースストリーの構成は通常の犯罪報道と変わりはない。「残虐」性を強調する報道、被害者の権利の強調する報道は、やがて、少年法「改正」議論の報道へとつながり、「改正」派の言説にとって言語的資源となった。少年事件の「凶悪化」は、情報源である警察庁などの統制機関と報道機関とが、少年事件のリアリティをどう見るのかについての定義づけであり、「凶悪」な事件の存在の境界を恣意的に設定した結果である。報道機関は単に情報源機関からの情報をストーリー化するだけでなく、自らも統制の役割を果たすようなニュース言説を構成する。被疑者に関する適性手続に関してはストーリー化されにくい。「子ども」に関する言説も、事件の枠組に適応するように恣意的に構築される。98年度後半から和歌山県内で起きた「毒物混入殺人事件」についても、資料収集やインタビューを続けいているが、この件についての研究はまだ未完であり、「犯罪事件」の社会的構築についての研究は今後も継続する。
1 0 0 0 「個人参加型フットサル」についての社会学的研究
本研究は、「個人参加型フットサル」を社会学的に検討するものである。これまで社会学では、スポーツなど趣味をきっかけにした「コミュニティ形成」について関心が寄せられ、「社会関係資本」などの視点から研究が行われてきた。だが、特定の人間関係に基づくはずのチームスポーツを、あえて匿名の「個人」のままでプレーする「個人参加型フットサル」という参与形態は、「コミュニティ形成」や「社会関係資本」の視点だけでは説明できない。よって本研究では、「個人参加型フットサル」という形態がなぜ生まれ、都市空間と地域社会のなかでそれぞれどのように実践されているのかについて、実地調査と文献調査から明らかにする。
1 0 0 0 OA 評価と脳画像から見た歩行能力の予後予測
- 著者
- 大村 優慈
- 出版者
- 日本義肢装具学会
- 雑誌
- 日本義肢装具学会誌 (ISSN:09104720)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.3, pp.194-198, 2022-07-01 (Released:2023-07-15)
- 参考文献数
- 31
脳卒中患者の装具療法を進める上で,歩行能力の予後予測は重要である.予後に関連する因子としては日常生活活動能力,下肢の運動麻痺,発症前の歩行能力,年齢,意識障害,合併症,脳画像所見などが示されており,最近では下肢装具の作製判断に関する研究報告もなされている.脳画像を読影する際は,病巣の大きさを把握するだけでなく,皮質脊髄路や皮質網様体路といった,歩行に関連する領域の損傷の有無を確認することが重要である.なお,脳梗塞では梗塞巣がさらに拡大する可能性を残す発症当日や,fogging effectによって梗塞巣が不明瞭になる発症2〜3週に撮影された画像は,損傷領域の同定に適さないため注意が必要である.
1 0 0 0 日本のフェミニズム : 150年の人と思想
1 0 0 0 OA 「触発するゴフマン」と「使えるゴフマン」のあいだ
- 著者
- 奥村 隆
- 出版者
- 日本社会学理論学会
- 雑誌
- 現代社会学理論研究 (ISSN:18817467)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.165-169, 2016 (Released:2020-03-09)
1 0 0 0 OA 表面プラズモン共鳴センサの医療分野への応用
- 著者
- 外山 滋 大出 明 オルガ フェドセーバ
- 出版者
- The Institute of Electrical Engineers of Japan
- 雑誌
- 電気学会論文誌E(センサ・マイクロマシン部門誌) (ISSN:13418939)
- 巻号頁・発行日
- vol.121, no.8, pp.430-433, 2001-08-01 (Released:2009-04-01)
- 参考文献数
- 34
- 被引用文献数
- 1 1
1 0 0 0 OA 地デジアンテナを作ろう ~100均で作る地デジアンテナ~
- 著者
- 辻 宏之
- 出版者
- 一般社団法人 電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会 通信ソサイエティマガジン (ISSN:21860661)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.4, pp.326-327, 2012-03-01 (Released:2012-06-01)
- 参考文献数
- 1
1 0 0 0 OA ワークショップ [テーマ2]結腸栄養と下痢
- 出版者
- 公益社団法人 日本栄養・食糧学会
- 雑誌
- 栄養と食糧 (ISSN:18838863)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.2, pp.w22-w37, 1981 (Released:2009-11-16)
1 0 0 0 OA 「VR/AR技術を用いたフィードバック動画教材」による「能動型見学実習」の試み
- 著者
- 織田 順 三苫 博
- 出版者
- 日本医学教育学会
- 雑誌
- 医学教育 (ISSN:03869644)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.3, pp.253-258, 2021-06-25 (Released:2021-07-22)
- 参考文献数
- 6
救急医学の見学型実習で, 全天球カメラを用いて救急初療の様子を記録し, 学習の助けとなる字幕や診療情報を加える編集を行い, VR/AR技術を用いてVRヘッドセットで視聴する動画教材を開発した. 学習者は対象の診療場面の基本知識を予習した上で視聴した. 指導医はミラーリング画像による視線の動きから学習者の理解度を把握し, リアルタイムにフィードバックを行った. VR/AR技術に, 予習動画教材と視聴中の理解度の計測を組み合わせることにより, 見学型実習に能動的な要素を取り入れることができた. また本システムは安価に活用することが可能で, 教育施設を越えたプラットフォームを構築することも期待される.
1 0 0 0 OA 雑誌流通システムの空間特性とその変容
- 著者
- 秦 洋二
- 出版者
- 地理科学学会
- 雑誌
- 地理科学 (ISSN:02864886)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.2, pp.45-64, 2007-04-28 (Released:2017-04-15)
- 参考文献数
- 27
本稿の研究目的は,取次会社が構築した雑誌物流システムの空間特性を,小売業者が構築する物流システムとの比較によって明らかにすることである。雑誌流通は,出版社と小売業者が小規模多寡であるのに対して,中間部門が寡占状態にあり,流通チャネル内において主導権を握っている。雑誌流動の空間的特徴は,生産者である出版社と中間部門である取次会社が東京とその周辺に集中しているのに対して,小売業者である書店・コンビニは全国に分散しており,商品は東京から全国へ流れる点にある。本稿では雑誌物流システムの送品部門と返品部門について,大手取次会社X社や九州雑誌センターの事例をもとに分析を行った。送品部門に関して,X社は1990年代に入って新たな物流センターを建設しているが,その背景には,コンビニ店舗の急増がある。また,返品システムの合理化には情報化の動きが関係している。雑誌物流システムを小売チェーンの物流システムと比較すると,小売チェーンの共同配送はチェーン毎に行われるのに対して,雑誌の共同配送は県毎にまとまって行われる点で異なる。さらに,物流拠点とリードタイムの関係を見ると,小売チェーンの物流システムが,リードタイムの遵守を第一に考えて物流拠点を設置するのに対して,雑誌物流システムでは物流拠点の立地が東京近辺に集中しているため,東京からの縁辺地域ほどリードタイムが長くなる。流通業全体では川下への主導権の移動によって物流システムの再編が進んだが,雑誌流通では,川下へのパワーシフトが進んでおらず,取次会社が流通チャネル内において主導権を握っている。雑誌物流システムの諸特徴には,このことが大きく影響していると考えられる。
1 0 0 0 OA ゲームという認識の枠組み -日本の先行研究を中心に-
- 著者
- 井上 明人
- 出版者
- 日本デジタルゲーム学会
- 雑誌
- デジタルゲーム学研究 (ISSN:18820913)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.1, pp.46-53, 2007 (Released:2021-06-01)
ゲームを成立させている認識を問うことを中心に国内のゲームの先行研究を整理する。
- 著者
- Komugi Okeya Yukio Kawagishi Emiri Muranaka Toshihide Izumida Hiroshi Tsuji Shinichi Takeda
- 出版者
- The Japanese Society of Internal Medicine
- 雑誌
- Internal Medicine (ISSN:09182918)
- 巻号頁・発行日
- pp.2892-19, (Released:2019-07-22)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 9 12
Hyperprogressive disease (HPD) is a paradoxical phenomenon involving the acceleration of tumor progression after treatment with immune checkpoint inhibitors (ICIs). A 66-year-old male smoker with advanced lung adenocarcinoma started pembrolizumab for progressive disease following first-line chemotherapy. He developed HPD after two cycles, and a re-biopsy revealed transformation to small-cell carcinoma. He subsequently underwent two lines of chemotherapy for small-cell carcinoma until progression and ultimately died. Transformation to small-cell carcinoma may be a cause of HPD during ICI therapy. The possibility of pathological transformation should be considered in cases of HPD with resistance to ICI therapy.
1 0 0 0 OA 土壁の調湿特性に及ぼす土の寝かしの影響
- 著者
- 塩野 剛司 佐藤 ひろゆき 森谷 幸紀 岡本 泰則
- 出版者
- 公益社団法人 日本材料学会
- 雑誌
- 材料 (ISSN:05145163)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.6, pp.409-412, 2010-06-15 (Released:2010-06-19)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 1 1
Tsuchi-kabe (called as soil wall or mud wall in English) utilized in Japanese traditional buildings is well known to have the characteristics of humidity conditioning. However, the characteristics have not been well examined. For preparing tsuchi-kabe material, soil, sand and rice straw are well mixed with water and then kept from a few weeks to months to promote fermentation. This aging process that is called as “Nekashi” gives plasticity to the material and is very important to construct tsuchi-kabe. In the present study, effect of “Nekashi” on the characteristics of humidity conditioning was examined. Long period of “Nekashi” enhanced the characteristics in nakanuri-kabe with a smaller amount of clay component.
1 0 0 0 OA 東アジアにおける双翅目昆虫サシチョウバエ種多様性の解明
- 著者
- 三條場 千寿 Chi-Wei-Tsai Zhang Ling-Min
- 出版者
- 東京大学
- 雑誌
- 基盤研究(C)
- 巻号頁・発行日
- 2016-04-01
日本産サシチョウバエ、Sergentomyia squamirostrisは北海道を除く本州、四国、九州、沖縄に広く分布することが本研究により明らかとなった。成虫の発生は気温が20℃を超える6月から9月であり、爬虫類に対しての嗜好性があることが示唆された。南西諸島においては、S. squamirostrisと形態学的・遺伝的に異なる種の存在が明らかとなった。中国、モンゴル、台湾における採集調査および台湾に生息するSergentomyia属サシチョウバエとの分子系統解析の結果より、東アジアにおいてS. squamirostrisは、中国の一部地方と日本のみに生息する可能性が高い。