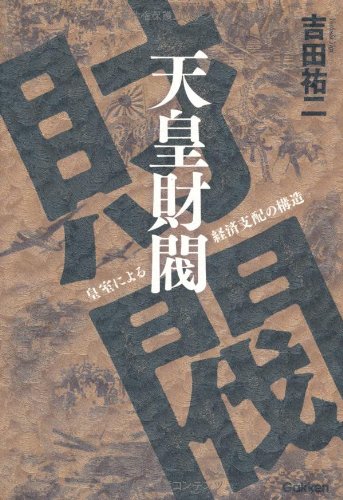1 0 0 0 OA OCTガイド冠インターべーション
- 著者
- 湊口 信吾
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本冠疾患学会
- 雑誌
- 日本冠疾患学会誌 (ISSN:24342157)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.12-17, 2023 (Released:2023-09-25)
- 参考文献数
- 38
1 0 0 0 OA IVUSガイド冠インターベンション
- 著者
- 吉田 明弘 本多 康浩
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本冠疾患学会
- 雑誌
- 日本冠疾患学会誌 (ISSN:24342157)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.6-11, 2023 (Released:2023-09-25)
- 参考文献数
- 38
1 0 0 0 OA イチジク葉片浸漬法によるイチジクヒトリモドキの薬剤殺虫効果
- 著者
- 網谷 龍介
- 出版者
- 国立大学法人 東京大学社会科学研究所
- 雑誌
- 社会科学研究 (ISSN:03873307)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.2, pp.67-91, 2006-01-31 (Released:2021-02-09)
1 0 0 0 オス支配突然変異と分子進化
一般に進化に寄与する突然変異の主要因はDNAの複製の際に生じるエラ-であると考えられている。もし、この仮定が正しければ、一般にオスの生殖細胞の分裂数がメスのそれ(前者の後者に対する比をαとする)よりずっと大きいと考えられているので、進化に寄与する突然変異の大部分はオスに由来する、という重要な結論へと導く。本研究は、このことを明らかにすることを目的として行われた。オスとメスの生殖細胞の分裂数に差があると、突然変異率が染色体間で異なることを理論的に導いた。すなわち、α>>1の場合、XX/XY型では突然変異率の比は、常染色体:Z染色体:Y染色体=1:2/3:2となる。興味あることに鳥類などのZW/ZZ型ではこの比がXX/XY型と比べて逆転することが示される:常染色体:Z染色体:W染色体=1:4/3:0(1/α)(0(1/α)は非常に小さな値)である。ここでXはZに、YはWに対応する。すなわち上記の仮定から、常染色体に対するX及びYの相対突然変異率(それぞれRx、Ryと書く)が哺乳類と鳥類で逆転する。この理論的結果を確認するために塩基配列の比較が行われた。遺伝子ごとにヒトとマウス(あるいはラット)の間で塩基配列を比較し、機能的制約がほとんど働いていない同義座位の置換率Ksを求めた。本研究では、常染色体遺伝子が35、X染色体遺伝子が6、Y染色体遺伝子が1つ解析され、常染色体遺伝子に対するX及びY染色体遺伝子の相対進化速度(R´x、R´y)が計算された。その結果、R´x=0.58、R´y=2.2となった。この結果は、理論的期待値Rx=2/3、Ry=2に非常に近い。以上のことから、我々は、進化に寄与する突然変異の大部分はオスによって生成されると結果した。我々は、鳥類でもこの結論を確認するため、Z及びW染色体遺伝子のクロ-ニングを試みた。残念ながら、クロ-ニングはまだ成功していない。今後も引続き続行する予定である。
1 0 0 0 天皇財閥 : 皇室による経済支配の構造
- 著者
- 吉田祐二著
- 出版者
- 学研マーケティング (発売)
- 巻号頁・発行日
- 2011
- 著者
- 津田 みわ
- 出版者
- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所
- 雑誌
- アフリカレポート (ISSN:09115552)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, pp.53, 2023-09-16 (Released:2023-09-16)
1 0 0 0 IR 韓国の国立大学における教養科目の日本語教科書語彙分析
Studies on Japanese textbooks in Korea have been focused on or limited to the high school textbooks for Japanese that are customarily chosen in accordance with the guidelines or curricula made by the Ministry of Education. The purpose of this paper, acknowledging such limitations, is to investigate the difference in vocabulary or lexicon used in the university textbooks for Japanese as part of general education to help students learn about Japan and Japanese. University textbooks unlike high school ones have no definite guidelines when selected, so as to make difference or irregularity with regards to vocabulary or lexicon. This paper compared and analyzed such difference of vocabulary based on a glossarial index of 1,023 basic words understood as a part of 2007 Revised Curriculum. The textbooks to be compared are being used in five national universities having a Japanese department. As a result, 54.1% is the highest rate for vocabulary agreement of textbook comparison while the least is 26.2%. It proves a great discrepancy in selecting and using textbook vocabulary.
- 著者
- Kazuki Yamada Hiroaki Yaguchi Kaede Ishikawa Daiki Tanaka Yuki Oshima Keiichi Mizushima Hisashi Uwatoko Shinichi Shirai Ikuko Iwata Masaaki Matsushima Keiko Tanaka Ichiro Yabe
- 出版者
- The Japanese Society of Internal Medicine
- 雑誌
- Internal Medicine (ISSN:09182918)
- 巻号頁・発行日
- pp.2569-23, (Released:2023-09-22)
- 参考文献数
- 14
A 74-year-old man experienced diplopia, generalized muscle weakness, and acute respiratory failure. He was diagnosed with Lambert-Eaton myasthenic syndrome (LEMS) and treated with immunotherapy, but no improvement was observed, and additional symptoms, including central apnea and hallucinations, appeared. Subsequent serum and cerebrospinal fluid (CSF) analyses confirmed the presence of GABAB receptor antibodies, indicating the coexistence of autoimmune encephalitis. Although there were no findings of malignancy, it is highly likely that occult small-cell lung carcinoma was present. When atypical symptoms occur in patients with LEMS, it is important to consider the possibility of concomitant autoimmune encephalitis.
1 0 0 0 OA 全球凍結からカンブリア爆発へ:地球環境変動と生態系進化のリンケージ解明に向けて
- 著者
- 大路 樹生 井龍 康文 高柳 栄子 長谷川 精 Dornbos Stephen Q. Gonchigdorj Sersmaa
- 出版者
- 名古屋大学
- 雑誌
- 基盤研究(B)
- 巻号頁・発行日
- 2015-04-01
モンゴル西部ズーン・アツのエディアカラ系より藻類化石を発見し、その特徴的な保存状態に関して化学分析と考察を行った結果、バージェス頁岩タイプの堆積岩であることが判明した。またバヤンゴル渓谷のエディアカラ系より垂直構造を持つ生痕化石を発見した。これは海底下4㎝まで潜りU字状の形態をもった生痕で、おそらく前後に伸びた体制と深く底質を掘り込むことが可能な筋肉組織をもった左右相称動物によって形成されたもので、また捕食動物の存在も示唆される。このようにカンブリア紀より前に深く潜る生痕化石を報告し、左右相称動物と捕食動物の存在を示唆する成果が得られたことは、従来の学説を大きく変えるものとなった。
1 0 0 0 OA 思考のカスケードと出会った微生物代謝産物
- 著者
- 大村 智
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- MEDCHEM NEWS (ISSN:24328618)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.2, pp.9-11, 1996-05-15 (Released:2021-09-01)
- 参考文献数
- 7
1 0 0 0 OA 小型シギ類における未知の餌の探究を通じた干潟生態系の再生
- 著者
- 桑江 朝比呂 三好 英一
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 土木学会論文集B2(海岸工学) (ISSN:18842399)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.2, pp.I_1176-I_1180, 2012 (Released:2012-11-15)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 1 1
Our empirical multi-disciplinary study shows that shorebird reliance on biofilm, a ubiquitous, previously unsuspected food comprised of microbes, their extracellular mucus substances, and detritus, is universal. The reliance was dependent on the environment that determines biofilm density. These findings revise shorebirds' trophic position and reveal new food web structures. Also, the study can assist in recovering worldwide declines in shorebird biodiversity as well as conservation and restoration of the integrity of intertidal flat ecosystems. We propose ideal configurations applied to the planning and designing of intertidal flat restoration projects, in the light of shorebird foraging ecology.
1 0 0 0 OA 戦後日本建築の評価に関する資料調査 その2:丹下健三と米雑誌編集者との応答書簡
- 著者
- 豊川 斎赫
- 出版者
- 一般社団法人 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会技術報告集 (ISSN:13419463)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.72, pp.1098-1103, 2023-06-20 (Released:2023-06-20)
- 参考文献数
- 16
The influence of American magazines is one of the factors behind the global rise of Japanese architecture’s reputation after World War II. In this report, we examine various letters exchanged between American magazine editors and architect Kenzo Tange, from the 1950s through to the early 1960s. This analysis examines the process by which Tange’s works were published in magazines, along with how his interactions with American magazine editors affected his overseas activities and broader international reputation. Time, Architectural Forum, and Architectural Record are the magazines covered in this report.
1 0 0 0 OA 職業威信と安全性拡充のための社会心理学的装置の検討
- 著者
- 下村 英雄 堀 洋元
- 出版者
- 社会技術研究会
- 雑誌
- 社会技術研究論文集 (ISSN:13490184)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.258-267, 2003 (Released:2009-08-19)
- 参考文献数
- 40
- 被引用文献数
- 4
本研究では,職業威信に関する先行研究を検討することによって,安全性拡充のための社会心理学的な装置の可能性を探索することを目的とした.まず,従来の職業威信に関する社会学的な研究を検討した.その結果,職業威信は各国間,世代間で不変であるという特徴がみられた.次に,職業威信に関する社会心理学的な研究を概観した.社会心理学では,職業威信はおもにジェンダーやキャリアガイダンスとの関連で論じられていた.最後に,認知された職業威信として,自分の職業に対する誇りの変数に焦点を当てた.いくつかの調査研究をもとに誇りの変数が,年齢や性別によって異なること,違反や事故と関連がみられる可能性があることなどを論じた.
- 著者
- 石山 裕菜 及川 昌典 及川 晴 鈴木 直人
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育工学会
- 雑誌
- 日本教育工学会論文誌 (ISSN:13498290)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.4, pp.409-420, 2020-03-20 (Released:2020-03-30)
- 参考文献数
- 37
本研究では,表現筆記はクラスメイトとの葛藤の解決を促すことで,人間関係やストレスを改善させ,学力の向上を導くこと,また,文章がそれぞれの項目(他者視点,因果,内省,感情,まとまり)において構造化している場合,効果が促進される可能性があることを検討した.79名の小学生にクラスメイトとの葛藤体験について1日おきに15分間,合計3回書き綴らせた.ストレス反応が減少し,一部のテストパフォーマンスが向上した.また,感情を多く筆記した児童はそうではない児童と比較して算数の知識理解の項目の得点が高かった.よって,クラスメイトとの葛藤表現筆記は,小学生のストレス反応の減少だけでなく,テストパフォーマンスの向上を促す可能性が示唆されたが,より効果的な筆記に関してさらなる詳細な検討が必要である.
1 0 0 0 OA 航空性中耳炎について
- 著者
- 岡田 諄
- 出版者
- 耳鼻咽喉科展望会
- 雑誌
- 耳鼻咽喉科展望 (ISSN:03869687)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.6, pp.657-663,3, 1976-12-15 (Released:2011-08-10)
- 参考文献数
- 16
Although aerotitis is a disorder of the middle ear precipitated by rapid barometric changes, it is rarely seen in modern air passengers despite the tremendous increase in air travel because of the smooth and automatic control of changes in pressurization in large passenger planes.However, among airplane personnel it still occurs in a fairly high incidence and is a hazard to which those whose occupation involves flying are exposed.The author has compiled a list of 403 cases of aerotitis media among commercial airplane personnel in our country during a recent 3-year-period and has analysed the data concerning any difference in incidence between cockpit and cabin crews, tendencies to onset, predisposing factors, and has reviewed in detail the flight patterns and pressure changes in the interi Qr of the planes, in orderto pinpoint someol the factors that may be responsible tor the reiativeiy nign inclaence.The literature on this subject is reviewed and the main points and problems in the therapy of this disorder are discussed.
1 0 0 0 OA CUDAによる高速フーリエ変換(<特集>GPGPUコンピューティングの数理)
- 著者
- 額田 彰
- 出版者
- 一般社団法人 日本応用数理学会
- 雑誌
- 応用数理 (ISSN:24321982)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.2, pp.125-131, 2010-06-25 (Released:2017-04-08)
- 参考文献数
- 6
Latest GPUs have not only high computation power but also high memory bandwidth required to accelerate memory intensive computations like FFT. This paper presents a high performance FFT library for CUDA GPUs. It is important to use auto-tuning to exploit the best performance. As a result, the library achieved much higher than other existing libraries.
1 0 0 0 OA 日本脳炎とその対策 歴史と現状
- 著者
- 髙崎 智彦
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- ファルマシア (ISSN:00148601)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.5, pp.366-370, 2021 (Released:2021-05-01)
- 参考文献数
- 15
日本脳炎(日脳)は、アジア地域における最も重要なウイルス性脳炎で、日脳ワクチンは、1954年に中山株を用いたマウス脳由来不活化ワクチンとして日本で開発され、その製造技術はアジア諸国に供与された。細胞培養不活化ワクチンが2009年に製造承認され、市場に供給された。世界的には不活化ワクチンだけでなく、中国で開発された弱毒生ワクチンも使用されている。日脳患者が減少した要因は、冷房等による生活環境の変化や養豚場が居住地から離れたことも挙げられるが、ワクチン接種による予防措置の貢献は大きい。東アジア、東南アジアでは遺伝子I型が流行しているが、近年V型株がしばしば検出されている。