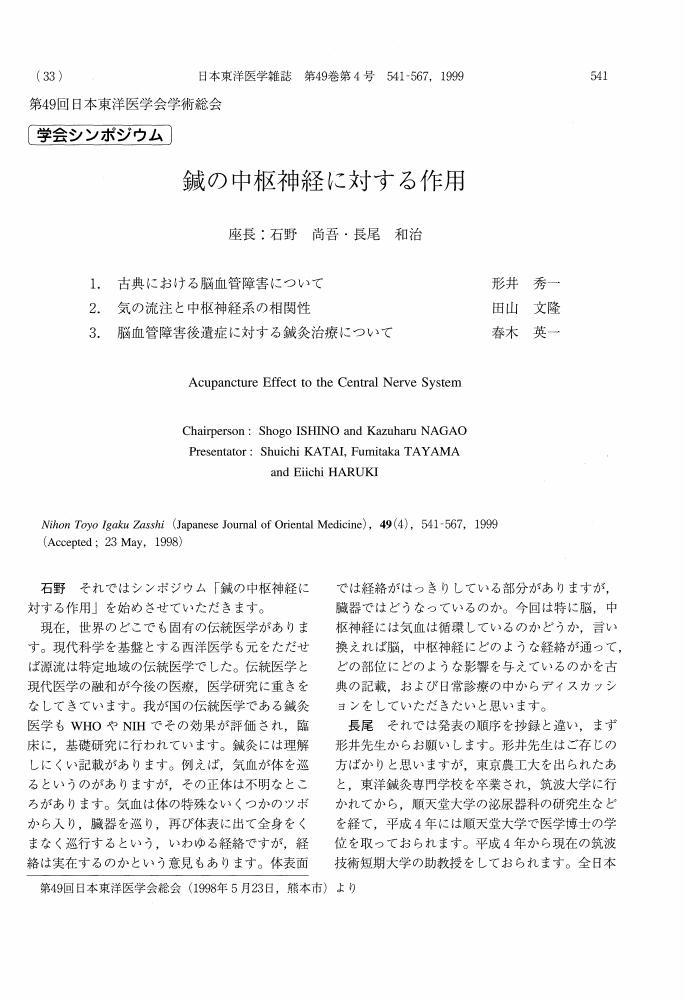1 0 0 0 OA 薩摩半島南岸から得られた鹿児島県本土初記録のナミフエダイ
- 著者
- 石原 祥太郎 本村 浩之
- 出版者
- 国立大学法人 鹿児島大学総合研究博物館
- 雑誌
- Ichthy, Natural History of Fishes of Japan (ISSN:24357715)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, pp.31-34, 2021 (Released:2021-11-21)
1 0 0 0 OA 身体所有感が手容積に与える影響 ―ラバーハンド錯覚を用いて―
- 著者
- 湯田 智久 大住 倫弘 前岡 浩 森岡 周
- 出版者
- 日本理学療法士協会(現 一般社団法人日本理学療法学会連合)
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.42 Suppl. No.2 (第50回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.1328, 2015 (Released:2015-04-30)
【はじめに,目的】Complex regional pain syndrome(CRPS)患者や脳卒中患者の障害側上肢には浮腫が生じ,浮腫は関節可動域制限や疼痛と関連することが報告されている(Shimada 1994,Isaksson 2014)。浮腫の原因は自律神経障害や静脈欝血とされることが多いが,明確な成因や治療手段は明らかにされていない。Moseley(2008)は,身体所有感が浮腫に関連することを示唆しているが,これらの関連は調査されていない。そこで本研究では,身体所有感の生起プロセスの調査を行う実験手法とされているラバーハンド錯覚(Rubber Hand Illusion:RHI)を用いて,身体所有感の変化が手容積に与える影響について調査することを目的とした。【方法】対象はRHIが未経験の健常成人21名(男性12名,女性9名,平均年齢26±3.85歳)とした。RHIとは隠された本物の手と偽物の手(Rubber Hand:RH)が同時に刺激されると,RHが自己の手のように感じる身体所有感の錯覚現象である。今回は2分間(1Hzの速度)絵筆による触刺激を隠された本物の左手とRHに同時に与える同期条件,交互に刺激を与える非同期条件,RHのみに刺激を与える視覚条件の3条件(各7名)に振り分けた。手容積の測定は,RHI前後で手容積計を用いて行った。客観的な錯覚の評価として,Skin Conductance Response(SCR)と脳波を測定した。SCRはProcomp2(ソートテクノロジー社)を用い,右第2,3指に貼付した電極間の電位差を測定し,RHI後にRHへ針刺激を与える場面を見せ,その直後から5秒間のSCRの最大振幅とした。SCRの振幅が大きい程RHへの錯覚が強く,身体所有感が低下していることを表している(Armel 2003)。脳波は高機能デジタル脳波計Active two system(Bio semi社)を用い,拡張10-20法に準じた電極配置による64電極にて安静座位,RHI時の60秒間を測定した。解析対象chはC3,C4とし,RHI時のα帯の平均パワー値を安静時のα帯の平均パワー値で除し,そのLog値をα帯の変化量とした。なお,Log比が負の値である程身体所有感の低下を表している(Evans 2013)。また,自律神経活動の変化の指標としてRHI前後で皮膚温,情動喚起の指標としてRHI後に不快情動の測定も行った。皮膚温はProcomp2(ソートテクノロジー社)を用いて,左第2指掌側で30秒間5set計測し,その平均値とした。不快情動はNumeral Rating Scaleを用いて測定した。統計解析は,各パラメータの条件比較を一元配置分散分析(多重比較検定法Bonferroni法)を用いて行った。また,手容積変化率との関連要因を検討するために,全被験者の各項目間の相関分析をPerson積率相関係数にて求めた。その後手容積変化率を目的変数に,C4Log比,SCR,皮膚温変化量,不快情動を説明変数として重回帰分析(変数増減法)を行った。有意水準は5%未満とした。【結果】手容積は条件内比較で有意差を認めなかった。手容積の変化率(%)は同期条件で0.31±1.41,非同期条件で-0.42±1.66,視覚条件で0.6±0.6であり,条件間においても有意差を認めなかった。SCR,C3Log比,C4Log比は条件間で有意な差を認めなかったが,同期条件のSCRで最も高値を示した。相関分析において,手容積変化率は皮膚温変化量(r=.44,p<.05),不快情動(r=.55,p<.01),C4Log比(r=.5,p<.05)と正の相関を認めた。また,皮膚温変化量はC4Log比と正の相関(r=-.44,p<.05),SCRと負の相関(r=-.53,p<.05)を認め,C4Log比は不快情動と正の相関(ρ=.61,p<.01),SCRと負の相関(r=-.46,p<.05)を認めた。重回帰分析の結果では,不快情動(標準偏回帰係数:0.47,p<.05)が抽出された。【考察】SCR,脳波で条件間の差を認めなかった。Honma(2009)らは本研究の視覚条件と同様の条件にて身体所有感の錯覚が生じることを報告しており,本研究では同期条件以外の被験者でも錯覚が生じていたことが考えられる。これらは手容積変化率で条件間の差を認めなかった要因として考えられる。しかし,相関分析でC4Log比と手容積の間に関連を認めていることから,本結果はRHIの実施方法の差異ではなく,身体所有感の低下が手容積の減少に関連することを示している。また,C4Log比と不快情動に相関を認め,重回帰分析で不快情動が抽出されたことは,身体の錯覚に関連した不快情動の喚起は手容積の増大に影響することを示唆している。【理学療法学研究としての意義】本研究結果は,浮腫の発生要因として末梢の影響以外にも,自己の手に対する知覚的側面や情動的側面が影響することを示唆しており,浮腫に対する理学療法介入の一助になると考える。
1 0 0 0 OA 高温度条件下の生理的反応の性差
- 著者
- 石川 清文
- 出版者
- 昭和大学学士会
- 雑誌
- 昭和医学会雑誌 (ISSN:00374342)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.12, pp.737-742, 1968-12-28 (Released:2010-09-09)
- 参考文献数
- 36
1 0 0 0 OA 先進諸国における住宅の必要換気量の基準に関する調査(環境工学)
- 著者
- 吉野 博 村上 周三 赤林 伸一 倉渕 隆 加藤 信介 田辺 新一 池田 耕一 大澤 元毅 澤地 孝男 福島 明 足立 真弓
- 出版者
- 一般社団法人 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会技術報告集 (ISSN:13419463)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.19, pp.189-192, 2004-06-20 (Released:2017-04-14)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 2 1
The purpose of this survey is to clarify the status of standards on ventilation requirements for residential buildings in European and North American countries. This paper reports the minimum ventilation rate for the residential buildings in eleven countries which are described in the literatures. The airflow rate and air change rate are calculated for a model house proposed by The Architectural Institute of Japan. As a result, the values of air change rate is around 0.5 ACH in almost all countries.
1 0 0 0 OA 脈波を用いた自律神経機能推定に向けた脈波伝搬時間の変動に関する検証
- 著者
- 前田 祐佳 関根 正樹 田村 俊世 水谷 孝一
- 出版者
- 公益社団法人 日本生体医工学会
- 雑誌
- 生体医工学 (ISSN:1347443X)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.6, pp.261-266, 2016-12-10 (Released:2017-03-17)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 3
This study evaluated the effect of pulse arrival time (PAT) on the difference between heart rate variability (HRV) and pulse rate variability (PRV). HRV is the degree of fluctuation in the time intervals between heart beats obtained from ECG, and is a global measure of autonomic nervous system (ANS) function. PRV is obtained from photoplethysmogram (PPG), and several researchers have attempted to use PRV instead of HRV for ANS monitoring, because measuring PPG is easier than measuring ECG. PPG reflects the change in blood volume ejected from the heart. Therefore, there is a strong correlation between the HRV and the PRV, and the PRV is regarded as an acceptable alternative to HRV at rest in ANS evaluation. In this study, we focused on the influence of change of body position on PRV, and we evaluated the effect of PAT on the difference between HRV and PRV. PAT is the sum of pulse transit time (PTT) and the pre-ejection period. Therefore, we used PAT to verify the difference between HRV and PRV. Seven healthy volunteers participated in this experiment. Their ECG and PPG were simultaneously recorded for 5 min before and 5 min after standing up from a chair. The results of the correlation coefficient indicated a strong correlation (r=0.9) between the HRV and the PRV in both sitting and standing positions. In contrast, the results of high-frequency spectral component showed a significant difference while standing, suggesting the influence of PAT on PRV. These results indicate that PRV is not identical to HRV, and that we should pay attention to use PRV instead of HRV for measuring ANS function.
1 0 0 0 OA 日本とブラジルの協力によるセラード農業開発とその評価
- 著者
- 村田 稔尚
- 出版者
- 公益社団法人 農業農村工学会
- 雑誌
- 農業農村工学会誌 (ISSN:18822770)
- 巻号頁・発行日
- vol.87, no.6, pp.483-488,a2, 2019 (Released:2022-06-20)
- 参考文献数
- 7
ブラジルは1970年代から急速に農業生産を伸ばし,今日では世界農産物市場において輸出額で米国に次ぐ第2位で9%のシェアをもつ農業大国となった。この躍進を大きくけん引したのが,1970年代半ばから進められた同国中西部に広がるセラードと呼ばれる広大な未開サバンナ地域での農業開発である。たとえば,同国の大豆の生産は,1990年代から2017年にかけ8倍強の10,800万tに増大したが,そのうち60%がセラード地域産で占められた。日本は,このセラード農業開発を促進するためのパイロット事業(PRODECER)に官民挙げて協力し多大な成果をあげた。本報はこの協力事業を現時点で総括し国際的な標準とされる経済協力開発機構(OECD)の評価基準に照らし評価するものである。
1 0 0 0 OA 糖尿病ラットにおける有茎皮弁生着過程の微細血管構築について
- 著者
- 柚木 大和
- 出版者
- 大阪歯科学会
- 雑誌
- 歯科医学 (ISSN:00306150)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.2, pp.g65-g66, 1993-04-25 (Released:2017-03-02)
顎口腔領域における悪性腫瘍切除後の広範囲な軟組織欠損に対する再建には, しばしば有茎皮弁が用いられる. 糖尿病患者の場合, 術後感染や創傷治癒遅延を起こしやすく, 糖尿病性細小血管症による微小循環障害がその原因の一つといわれているが, その詳細ほいまだ明らかでない. そこで今回, ストレプトゾトシン誘発糖尿病ラット背部皮膚に有茎皮弁を作製し, 糖尿病性細小血管症における皮弁先端部の生着過程の変化を観察し, 検討した. 実験方法および観察方法 生後6週齢Wistar系雄性ラット(体重180g)を用い, ストレプトゾトシン(SIGMA社製, 以下STZと略す.)を大腿静脈より1回投与(60mg/kg)し, STZ投与前の平均血糖値145.6mg/dlの約2倍(300mg/dl以上)の血糖値を示したラットを糖尿病発症ラットとした. 糖尿病発症後8週, 16週(以下DM8週群, DM16週群と略す.)の各時期に, 尾側に茎をもつ, 3×1cmの有茎皮弁を作製した. 皮弁は, 筋肉層(Panniculus carnosus)直下の疎性結合組織層で剥離挙上後, 元の位置に復位しナイロン糸にて縫合した. なお, STZ非投与群を対照群とした. 術後3, 5, 7日および2週に屠殺し, 10%中性ホルマリンで固定したのちセロイジン包埋し, 薄切後ヘマトキシリン・エオジン染色を施し, 組織学的に観察した. また太田ら(1990)の方法を用いて上行大動脈より樹脂を注入し, 樹脂硬化後5%水酸化ナトリウムにて軟組織を除去し, 乾燥させ血管鋳型標本を作製した. 同標本に金蒸着を行い, 走査電子顕微鏡(JSM-T300, JEOL)にて観察した. 結果 1)対照群 術後3日には, 創は表皮で覆われ, 真皮上行血管の分枝に新生洞様血管が形成され術後5日には表層付近の真皮上行血管から伸展した新生洞様血管が裂隙を横切って吻合していた. 術後7日には接合部の乳頭層血管網が形成され, 真皮上行血管も新生血管によって吻合していた. 術後2週では乳頭層血管網の血管の太さを増し, その数を減じ, 接合部の境界は不明瞭になっていた. 2)実験群 DM8週群は, 組織学的には術後2週まで炎症性細胞がわずかに残存し, 対照群と比較してやや遅延していたが, 血管構築においては対照群とほぼ同様であった. DM16週群では, 術後5日で表皮は厚みを増して連続性を回復し, 真皮層では炎症性細胞が密にみられ, 術後2週では真皮層の炎症性細胞は, 表皮直下ではほとんど消失し, 深層では散在性に残存していた. 電子顕微鏡学的には, 術後5日に真皮上行血管の分枝に新生洞様血管が形成されていたが, 裂隙を横切る吻合はなく, 術後7日には裂隙を横切って吻合している新生洞様血管もみられ, 術後2週では真皮上行血管から伸展した新生洞様血管が裂隙を横切って互いに吻合していた. 対照群, DM8週群と比較すると, 組織学的においても, 血管構築においても治癒が遅延していた. 以上の結果より, 実験群では対照群と比べると, 炎症性細胞が術後2週まで残存し, さらに糖尿病性罹病期間が長期になると, 残存している炎症性細胞の数が多くみられ新生血管形成も遅れていた. また, 皮弁移植手術の創傷治癒過程において糖尿病性罹病期間が長期になると, 線維芽細胞の増殖および新生血管形成の遅延がみられ, 表皮直下に比べると真皮深層の治癒が遅れる点に留意して治療にあたる必要があると考えられた.
1 0 0 0 OA 法益主体の自律と刑法理論
1 0 0 0 OA マジック課題を用いた予期しない現象の原因同定過程の分析
- 著者
- 寺井 仁 三輪 和久 柴田 恭志
- 出版者
- 日本認知科学会
- 雑誌
- 認知科学 (ISSN:13417924)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.2, pp.146-163, 2012 (Released:2014-07-22)
- 参考文献数
- 16
When a system gives outputs that you do not predict,you regard those as unexpected events and try to identify the causes affecting those events. In this study,we try to understand how people identify the causes affecting unexpected events by using a card magic called the three card monte as an experimental material.In our experiments,the participants were required to find out the tricks by watching a video in which a magician plays the magic.We focused on two cluesrelated tocause identification.The first is distinctiveness of events; and the second is availability of feedback information.The results of the experimentsshowed that the distinctiveness of events affected the performance of cause identification,whereas the availability of feedback information did not. The processanalyses revealed that even if feedback information was not directly given,the participants could perform reasoning for cause identification based on hypothetical information not observed.
1 0 0 0 OA フグの胃の膨張機構
- 著者
- 山元 憲一 半田 岳志
- 出版者
- Japanese Society for Aquaculture Science
- 雑誌
- 水産増殖 (ISSN:03714217)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.1, pp.11-18, 2012-03-20 (Released:2015-03-23)
- 参考文献数
- 9
トラフグの口腔内圧,鰓腔内圧,口腔と鰓腔の圧差,胃内圧,口からの吸入水量,口からの排出水量および胃の膨張度合いを連続測定した。色素を鰓腔へ注入し,胃から採水して,水の移動を観察した。これらの結果から,鰓換水および胃の膨張機構を解析し,モデル化した。トラフグは,口腔内圧,鰓蓋内圧およ口腔と鰓腔の圧差を利用し,口腔弁,鰓蓋弁および食道括約筋を能動的に開閉することによって,胃の膨張および膨張からの収縮を行っていることが明らかとなった。
1 0 0 0 OA 有機リン系およびジチオカーバメイト系化学物質の神経毒性
- 著者
- 紺野 信弘
- 出版者
- The Japanese Society for Hygiene
- 雑誌
- 日本衛生学雑誌 (ISSN:00215082)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.4, pp.645-654, 2003-01-15 (Released:2009-02-17)
- 参考文献数
- 82
- 被引用文献数
- 4 4
The neurotoxicity of organophosphorus compounds (OPs) including leptophos, TOCP and triphenyl phosphite and dithiocarbamate compounds were reviewed in this study. The major neurotoxicities of OPs were acute toxicity produced by the acetylcholine esterase (AChE) inhibiting action of OPs and delayed neurotoxicity produced by such OPs as leptophos and TOCP. The direct action of OP on the muscarinic and/or nicotinic acethylcholine receptors in the synaptic membranes have lately attracted attention in relation to acute toxicity. Delayed neurotoxicity is a delayed onset of prolonged locomotor ataxia resulting from a single or repeated exposure to an OP. Although neurotoxic esterase (NTE) inhibition might be related to the onset of organophosphate-induced delayed neurotoxicity (OPIDN), the precise mode of action is not yet clear.The effect of dithiocarbamates on the nervous system is also mentioned, because the compounds are currently suspected not only for neurotoxicity, but also as endocrine-disrupting chemicals. Although dithiocarbamates showed weak neurotoxicity in adult animals, we need to pay more attention to developmental neurotoxicity.
1 0 0 0 OA 音楽が亡びるとき ―このローファイの時代に
- 著者
- 今田 匡彦
- 出版者
- 日本音楽教育学会
- 雑誌
- 音楽教育実践ジャーナル (ISSN:18809901)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.1, pp.120-129, 2011 (Released:2017-05-30)
- 参考文献数
- 19
1 0 0 0 OA 写真撮影モデル依頼による認知的負荷とダイエット経験が食行動に及ばす影響について
- 著者
- 田中 久美子
- 出版者
- 一般社団法人 日本健康心理学会
- 雑誌
- 健康心理学研究 (ISSN:09173323)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.1, pp.41-48, 2002-06-25 (Released:2015-01-07)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 1
This study examined the effects of subjective differences in cognitive demand on eating control mechanisms. As a task with high cognitive demand, 53 female students were asked to have their photographs taken. Forty-five students who accepted the request were classified into four categories, 2 (high cognitive demand, low cognitive demand) × 2 (dieter, non-dieter). The results indicated that the “high demand-dieter” group significantly decreased eating restraint under pressure, whereas the “high demand-non-dieter” group actively restrained eating through self-regulation of food intake. Moreover, there were differences in the high and low demand diet groups in terms of motivation, strategy, and the condition after the diet.
- 著者
- Alexis Guerin-Laguette
- 出版者
- The Mycological Society of Japan
- 雑誌
- Mycoscience (ISSN:13403540)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.1, pp.10-28, 2021-01-20 (Released:2021-01-20)
- 参考文献数
- 168
- 被引用文献数
- 10 12
The cultivation of edible mycorrhizal fungi (EMF) has made great progress since the first cultivation of Tuber melanosporum in 1977 but remains in its infancy. Five cultivation steps are required: (1) mycorrhizal synthesis, (2) mycorrhiza development and acclimation, (3) out-planting of mycorrhizal seedlings, (4) onset of fructification, and (5) performing tree orchards. We provide examples of successes and challenges associated with each step, including fruiting of the prestigious chanterelles in Japan recently. We highlight the challenges in establishing performing tree orchards. We report on the monitoring of two orchards established between Lactarius deliciosus (saffron milk cap) and pines in New Zealand. Saffron milk caps yields reached 0.4 and 1100 kg/ha under Pinus radiata and P. sylvestris 6 and 9 y after planting, respectively. Canopy closure began under P. radiata 7 y after planting, followed by a drastic reduction of yields, while P. sylvestris yields still hovered at 690 to 780 kg/ha after 11 y, without canopy closure. The establishment of full-scale field trials to predict yields is crucial to making the cultivation of EMF a reality in tomorrow’s cropping landscape. Sustainable EMF cultivation utilizing trees in non-forested land could contribute to carbon storage, while providing revenue and other ecosystem services.
- 著者
- Wakana Ogawa Naoki Endo Yumi Takeda Miyuki Kodaira Masaki Fukuda Akiyoshi Yamada
- 出版者
- The Mycological Society of Japan
- 雑誌
- Mycoscience (ISSN:13403540)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.1, pp.45-53, 2018 (Released:2023-03-07)
- 被引用文献数
- 11
Species of fleshy yellow Cantharellus are known as chanterelles, which are among the most popular wild edible mycorrhizal mushrooms in the world. However, pure culture isolates of Cantharellus are rare. We report an efficient isolation technique of the Japanese golden chanterelle, Cantharellus anzutake, from its ectomycorrhizal root tips. Field-sampled fresh ectomycorrhizal root tips of C. anzutake on various hosts such as pines, spruce, and oaks were vortexed with 0.005% Tween 80 solution, surface sterilized with 1% calcium hypochlorite solution, rinsed with sterilized distilled water, and placed on modified Norkrans’ C (MNC) agar plate medium. Most ectomycorrhizal root tips of C. anzutake produced yellowish mycelial colonies within a few months. In contrast, tissue isolation from basidiomata provided limited cultures of C. anzutake but much contamination of bacteria and molds, even on media that contained antibiotics. The established C. anzutake cultures had clamp connections on the hyphae and contained intracellular oily droplets. These cultured isolates were identified as C. anzutake by sequence analysis of the rRNA internal transcribed spacer (ITS) region and translation elongation factor EF1-alpha (tef-1) genes.
1 0 0 0 OA 機械刺激による筋萎縮軽減の分子メカニズム
- 著者
- 縣 信秀
- 出版者
- 日本基礎理学療法学会
- 雑誌
- 日本基礎理学療法学雑誌 (ISSN:21860742)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.2, pp.3-8, 2012 (Released:2018-09-28)
1 0 0 0 OA 学会シンポジウム
- 出版者
- The Japan Society for Oriental Medicine
- 雑誌
- 日本東洋医学雑誌 (ISSN:02874857)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.4, pp.541-567, 1999-01-20 (Released:2010-03-12)
- 著者
- Yoshitaro Nosé Ayako Kushida Teruyuki Ikeda Hideo Nakajima Katsushi Tanaka Hiroshi Numakura
- 出版者
- The Japan Institute of Metals and Materials
- 雑誌
- MATERIALS TRANSACTIONS (ISSN:13459678)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.12, pp.2723-2731, 2003 (Released:2005-09-06)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 33 39
The phase boundaries pertaining to γ2 (FePt) and γ3 (FePt3) phases in the Fe-Pt system have been re-examined by measuring (1) the compositions of interphase boundaries in diffusion couples, (2) the equilibrium compositions in two-phase alloys and (3) the electrical resistivity as a function of temperature. The results obtained by the three methods are consistent with each other. The γ (fcc solid solution) ↔ γ2+γ3 eutectoid has been found to be located at a point higher in Pt concentration and lower in temperature than in the currently adopted phase diagram, the stability range of the γ2 phase exhibits considerable asymmetry. Other phase boundaries, as well as the ferromagnetic ↔ paramagnetic transition in the γ2 phase detected by the resistivity measurements, are in fair agreement with the data in the literature.