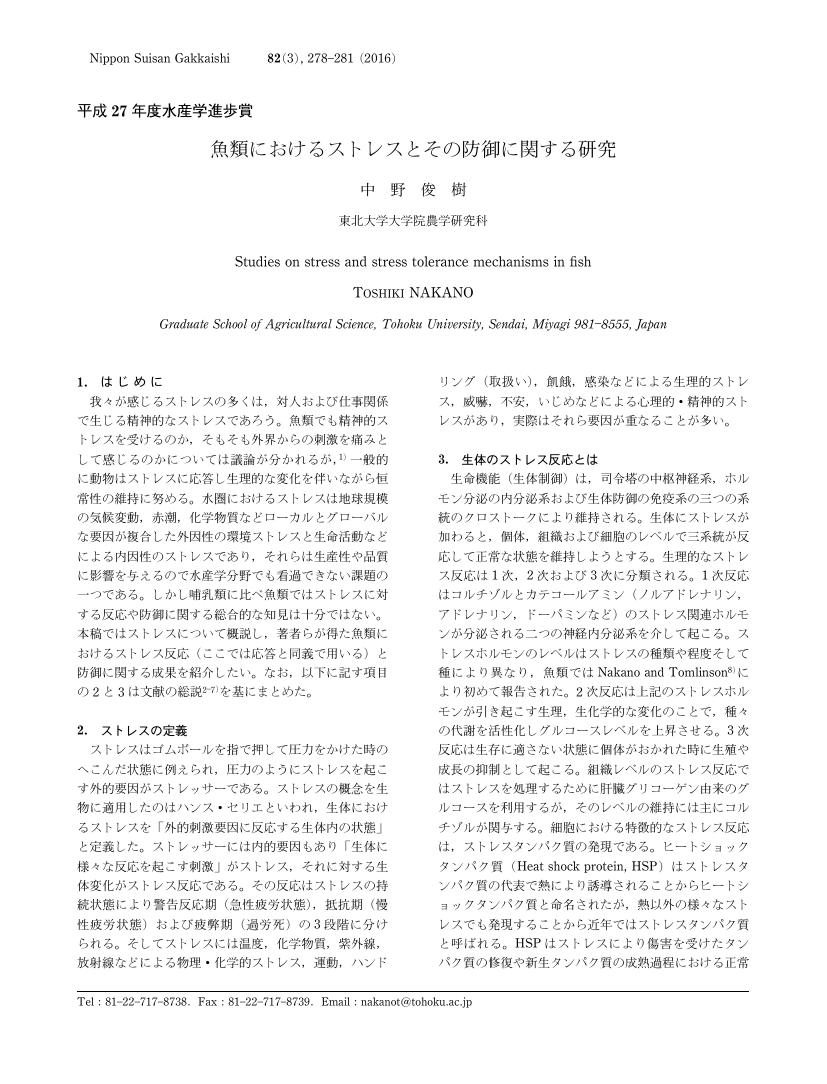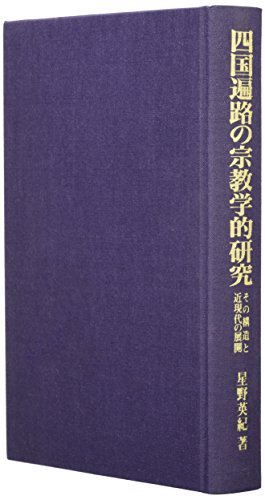1 0 0 0 OA 魚類におけるストレスとその防御に関する研究
- 著者
- 中野 俊樹
- 出版者
- 公益社団法人 日本水産学会
- 雑誌
- 日本水産学会誌 (ISSN:00215392)
- 巻号頁・発行日
- vol.82, no.3, pp.278-281, 2016 (Released:2016-06-07)
- 参考文献数
- 37
- 被引用文献数
- 2 6
1 0 0 0 OA リハビリテーション実施中に転倒した事例の特性:インシデントレ ポートを利用した調査
- 著者
- 太田 幸將 宇田 和晃 髙橋 静子 彦田 直 宮越 浩一
- 出版者
- 一般社団法人 日本予防理学療法学会
- 雑誌
- 日本予防理学療法学会雑誌 (ISSN:24369950)
- 巻号頁・発行日
- pp.JPTP-D-23-00005, (Released:2023-09-12)
- 参考文献数
- 23
【目的】リハビリテーション実施中に転倒した事例の特性と歩行練習中の転倒状況を明らかにすること。【方法】2016 要旨 年4 月1 日~2020 年8 月31 日にリハビリテーション実施中に転倒した患者の年齢,診療科,対応療法士の経験年数,練習内容,インシデントレベルを調査した。歩行練習中の転倒に関し,方向・要因・介助方法を調査した。また対象期間内のリハビリテーション処方数・実施時間を調査した。【結果】438,593.7 時間の実施のうち転倒は124 件であった。転倒発生率は65 歳未満で0.43/1,000 人・時間,65 歳以上で0.25/1,000 人・時間であった。診療科は血液腫瘍内科で0.47/1,000 人・時間,療法士の経験年数は1-3 年目の0.37/1,000 人・時間で最大であった。歩行練習中の転倒は,前方,躓き,監視で多かった。【考察】転倒特性を明らかにすることで,転倒予防に役立つ可能性がある。
- 著者
- 薬師寺 浩之
- 出版者
- 観光学術学会
- 雑誌
- 観光学評論 (ISSN:21876649)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.2, pp.197-213, 2017 (Released:2020-01-13)
本稿では、カンボジア・シェムリアップ市における孤児院で行われている日本人が参加するボランティアツアーを事例として、孤児院ボランティアツアーにおける演出とパフォーマンスについて考察を試みる。孤児院ボランティアツアーとは、ツアー参加者がボランティアという行為を通して孤児の貧困や不幸という「ダークネス」にまなざしを向け、さらに自身のリアリティを充足する、という一連の行為である。本来なら福祉施設の一形態である孤児院は観光資源の対極に位置付けられるべきものであるが、市場化・観光資源化されて観光者に開放されている孤児院も見られる。ボランティアツアーを受け入れている孤児院では、ツアー参加者がリアリティを充足したり自分の存在意義を再確認したりできるように、様々な演出がツアー催行業者や孤児院運営者によって行われ、さらにツアー催行業者や孤児院運営者の指示のもと孤児はパフォーマンスをしている。さらにツアー参加者自身も孤児院でのボランティア活動中、利他的・博愛的なボランティア活動実践者として相応しい振る舞いをするように自らを演出している。
1 0 0 0 OA 孤児院ボランティアツーリズムを問い直す : 規範的アプローチを超えて
- 著者
- 薬師寺 浩之
- 出版者
- 立命館大学人文科学研究所
- 雑誌
- 立命館大学人文科学研究所紀要 (ISSN:02873303)
- 巻号頁・発行日
- vol.134, pp.183-213, 2023-01
1 0 0 0 OA 海産生物による放射性ヨウ素の濃縮に及ぼす安定ヨウ素の影響
- 著者
- 平野 茂樹 松葉 満江 小柳 卓
- 出版者
- 公益社団法人 日本アイソトープ協会
- 雑誌
- RADIOISOTOPES (ISSN:00338303)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.8, pp.353-358, 1983-08-15 (Released:2010-09-07)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 4 3
安定および放射性ヨウ素の化学形と, その濃度を調整した人工海水中で海産生物による, 放射性ヨウ素の取り込みと排出を検討した。これらの生物による放射性ヨウ素の濃縮係数は飼育水中のヨウ化物イオンの濃度により変化するが, ヨウ素酸イオンの濃度は放射性ヨウ素の取り込み排出に影響を与えなかった。飼育水中のヨウ化物イオンの濃度が高いほど放射性ヨウ素の生物学的半減期が短くなり, したがって, 濃縮係数が低くなるということが観察された。
- 著者
- Shin-Ichi SEKI
- 出版者
- The Ornithological Society of Japan
- 雑誌
- ORNITHOLOGICAL SCIENCE (ISSN:13470558)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.2, pp.137-150, 2023 (Released:2023-08-01)
- 参考文献数
- 66
The Ryukyu Robin species complex, including the Ryukyu Robin Larvivora komadori and the Okinawa Robin L. namiyei, is endemic to the islands of the Ryukyu Archipelago. Population genetic structure and gene flow within this complex were investigated using 14 nuclear microsatellite markers. Distinct genetic differentiation was detected between the Ryukyu and Okinawa robins, and the Ryukyu Robin was further differentiated into four regional groups belonging to the Danjo Islands, Tokara Islands, Oh-shima with some adjacent islands, and Tokuno-shima. Contemporary gene flow among these regional groups was restricted overall, but outflow from the Tokara Islands group to the other three groups was exceptionally high. This asymmetric pattern may have been affected by differences in the isolation distance, migratory habits, and population size. The Ryukyu Robin species complex was long considered a single polytypic species; however, it has recently been classified as two independent species, mainly owing to the deep mitochondrial DNA divergence between them and a phenotypical re-examination. The genetic structure inferred from the nuclear loci strongly supports their genetic independence. The Okinawa Robin provides the first case among birds for which the splitting of sister species both endemic to the Ryukyu Archipelago is supported by all of the morphological, behavioral, ecological, and genetic evidence. Such recognition appears preferable in avian conservation and biogeography studies. Currently, the Ryukyu Archipelago includes an Endemic Bird Area and two Natural World Heritage sites, making the reliable delimitation of endemic species all the more important. Comprehensive genetic investigation, together with phenotypical re-examination is necessary, even for closely resembling but allopatric sister forms in this region.
1 0 0 0 OA 葛の葉の化學的成分に就て
- 著者
- 佐々木 林治郎
- 出版者
- 公益社団法人 日本農芸化学会
- 雑誌
- 日本農芸化学会誌 (ISSN:00021407)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.11, pp.1183-1190, 1927 (Released:2008-11-21)
- 参考文献数
- 8
1 0 0 0 OA 脳卒中重度片麻痺者の歩行再建をめざした生活期の理学療法
- 著者
- 芝崎 淳
- 出版者
- 一般社団法人日本理学療法学会連合
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.5, pp.491-498, 2020 (Released:2020-10-20)
- 参考文献数
- 23
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA エイジズム研究の動向とエイジング研究との関連:エイジズムからサクセスフル・エイジングへ
- 著者
- 竹内 真純 片桐 恵子
- 出版者
- 心理学評論刊行会
- 雑誌
- 心理学評論 (ISSN:03861058)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.4, pp.355-374, 2020 (Released:2022-02-05)
- 参考文献数
- 135
Ageism, negative attitudes toward elderly individuals, is the third great “ism” in society. Compared to other prejudices, it is unique because most individuals will become elderly adults through aging. Therefore, the phenomenon of ageism is inherently linked to aging. However, ageism and aging studies have previously been conducted in different contexts—the former primarily in psychology and the latter in gerontology. In this paper, we classify and organize ageism research from the perspective of aging. First, we show how ageism appears in workplace, medical, and nursing care situations and in psychological research settings. Second, we present several theories explaining the occurrence of ageism, including those focusing on aging, highlighting the physical characteristics of elderly individuals, and explaining prejudice in general. Third, we present from a gerontological perspective the problem of elderly people’s adaptation to old age: we argue how ageism hinders the acceptance of old age and successful aging. Finally, we describe ageism from an aging perspective by discussing the possibility of eradicating ageism and show how ageism and aging affect each other.
1 0 0 0 四国遍路の宗教学的研究 : その構造と近現代の展開
1 0 0 0 OA 奈良県島の山古墳の被葬者をめぐって
- 著者
- 直木 孝次郎
- 出版者
- 学校法人 甲子園短期大学
- 雑誌
- 甲子園短期大学紀要 (ISSN:0912506X)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, pp.85-93, 1997-03-01 (Released:2022-07-17)
- 著者
- 松本 麻人
- 出版者
- 日本比較教育学会
- 雑誌
- 比較教育学研究 (ISSN:09166785)
- 巻号頁・発行日
- vol.2020, no.61, pp.183-205, 2020 (Released:2023-07-19)
About 40% of private 4-year universities in South Korea are Christian. Although half are ex-Christian theological seminaries, the transformative development process that was involved in their establishment as universities has not been discussed thus far. This paper focuses on the fact that the seminaries, which were unrecognized in the 1980s, were approved as miscellaneous schools as part of a government-controlled, pre-university promotion process. The purpose of this paper is to clarify the influence that these schools later exerted on Christian universities’ development by examining the offensive and defensive process between national policies on unrecognized seminaries, the various strategies that seminaries used, and the transformation that has taken place with. We will discuss how the seminaries’ transformation into miscellaneous schools has contributed to establishment Christian universities. In this paper, we use Barton R. Clark’s triangle model as a theoretical framework. This model sets the state, society, and university as influential factors in the transformation of higher education organizations. This paper adds religious society as an influential factor in the transformation of seminaries. Relevant literature was reviewed in order to explore the details that pertain to government measures and responses from affected seminaries. We referred to published parliamentary minutes, government documents and statistics, and historical school materials. We obtained public government documents that have not been released to the public by requesting the information from government records archives. Moreover, in order to clarify the seminaries’ correspondence, we referred to literature that was in addition to each university’s school history. The 1970s, increase in the number of Christians coupled with the government’s growing restrictions on higher education meant that minister training was outpaced, resulting in many unrecognized seminaries. The government complained that these seminaries were recruiting students for themselves as “schools” and illegally granting degrees. The government then formulated a plan to control such seminaries. An announcement was made that seminaries that meet certain standards would be promoted to universities or miscellaneous schools, and the rest would be closed. The government has also sought to incorporate high-quality seminaries into their higher education system, increasing their capacities and providing financial support. Many seminaries applied for approval given the importance of their maintenance as minister-training schools. In addition, the recognition of the state as a higher education institution has been important for establishing schools’ social status. Obtaining a status that facilitates senior school entrance is useful for effective functioning as an educator training system since educators would obtain future degrees. It is also evident that the various Christian societies place great importance on the maintenance of their seminaries. However, only a few seminaries have been approved. Christian society revolted over the repeal of many seminaries, but some seminaries supported the government. Therefore, the government succeeded in dividing Christianity society. Seminaries in transition were obliged to comply with laws and regulations relating to facilities and equipment, staffing, teacher qualifications, and curricula. The schools had to include Korean history, national ethics and physical education as required subjects. Despite this, the schools became miscellaneous schools because it was possible to maintain the theology department and the essential function of minister training. (View PDF for the rest of the abstract.)
1 0 0 0 OA 1H05 技術革新と経済発展の循環と相関(研究・イノベーション政策(1),一般講演)
- 著者
- 弘岡 正明
- 出版者
- 研究・イノベーション学会
- 雑誌
- 年次大会講演要旨集 29 (ISSN:24327131)
- 巻号頁・発行日
- pp.232-235, 2014-10-18 (Released:2018-01-30)
1 0 0 0 OA 根源的人間 エックハルトに於ける「真人」(ein wâr mensche) について
- 著者
- 上田 閑照
- 出版者
- 密教研究会
- 雑誌
- 密教文化 (ISSN:02869837)
- 巻号頁・発行日
- vol.1973, no.101, pp.31-45, 1973-01-15 (Released:2010-03-12)
- 著者
- 松中 亮治
- 出版者
- 公益社団法人 日本都市計画学会
- 雑誌
- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)
- 巻号頁・発行日
- vol.43.3, pp.811-816, 2008-10-25 (Released:2017-01-01)
- 参考文献数
- 39
本研究では、LRT導入による影響を明らかにするため、LRTが導入され都市内交通として定着しているフランスのストラスブールと、LRTの導入が予定されているミュールーズを調査対象とし、ストラスブールおよびミュールーズのLRT導入に関する事前・事後調査報告書の記述内容を精査し、LRT導入による交通行動や社会経済に対する影響について評価項目ごとに整理している。その結果、自動車交通については、LRTの導入や交通サーキュレーションなどの影響を受け減少傾向にあることが明らかとなった。しかし、中心部の商業や賃貸料への影響については、十分に明らかにされておらず、その点には留意する必要がある.
1 0 0 0 OA 憲法上の平等原則の実体的価値と司法審査
- 著者
- 井上 一洋 Kazuhiro Inoue
- 出版者
- 同志社法學會
- 雑誌
- 同志社法學 = The Doshisha Hogaku (The Doshisha law review) (ISSN:03877612)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.4, pp.853-879, 2020-10-31
本稿では、Peter WestenやKenneth L.Karstらの論稿を手がかりに憲法上の平等原則の実体的価値について考察を行うとともに、アメリカとの比較法の観点から平等が問題となった事件における判例理論について検討を行う。
1 0 0 0 OA 統計的多重性の問題と多重比較の方法
- 著者
- 緒方 裕光
- 出版者
- 日本健康教育学会
- 雑誌
- 日本健康教育学会誌 (ISSN:13402560)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.3, pp.173-179, 2023-08-31 (Released:2023-09-17)
- 参考文献数
- 32
統計的多重性の問題と多重比較の方法は,データ解析における重要課題の1つである.1950年代から現在に至るまで,一元配置分散分析の結果に応じて複数群の平均値を比較する方法として,様々な多重比較の方法が開発されてきた.近年,臨床試験において複雑な研究デザインが用いられるようになり,統計的多重性の問題はさらに重要になっている.多重比較は統計的多重性の問題を解決するためのアプローチであり,研究の科学的意義を高めるためにも研究計画の段階から適切な多重比較の方法を選択する必要がある.本稿では,統計的多重性の問題の基本的考え方を述べるとともに,多重比較の代表的方法の特徴と留意点について概説する.
1 0 0 0 OA 質的研究の特長—量的研究との相違点と共通性—
- 著者
- 青柳 健隆
- 出版者
- 日本健康教育学会
- 雑誌
- 日本健康教育学会誌 (ISSN:13402560)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.3, pp.166-172, 2023-08-31 (Released:2023-09-17)
- 参考文献数
- 15
学術誌等において質的な手法を用いた研究を目にする機会も増えてきたが,いまだに質的研究が広く,そして適切に理解されているとは言い難い.本稿では,質的研究と量的研究の比較を通して,質的研究の特長を明示することを主目的とした.また,エビデンスレベルや質的研究の特長に基づく量的研究との使い分け,混合研究法としての質的研究と量的研究の相互補完的な活用方法についても報告する.加えて,そもそも「質的」とはどういうことなのかについても検討した.まとめると,質的研究とは探索的・仮説生成的であり,俯瞰的・抽象的な範囲を取り扱うことを得意とし,要素や関係性の「存在」を重視するという特徴を持っている研究手法であった.対する量的研究は,検証的・確認的で,限定的な範囲について結論づけることに適しており,「数」を重要視するパラダイムを有していることが確認された.両者それぞれに特長があるため,研究分野のエビデンスレベルや研究目的,データの性質などに応じて妥当かつ信頼性の高いものを選択または組み合わせて用いることで研究のクオリティを高めることが可能となる.
1 0 0 0 OA 中学生の教師に対する信頼感と学校適応感との関連
- 著者
- 中井 大介 庄司 一子
- 出版者
- 一般社団法人 日本発達心理学会
- 雑誌
- 発達心理学研究 (ISSN:09159029)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.1, pp.57-68, 2008-05-10 (Released:2017-07-27)
- 被引用文献数
- 18
本研究の目的は,学校教育における教師と生徒の信頼関係の重要性と,思春期における特定の他者との信頼関係の重要性を踏まえ,中学生の教師に対する信頼感と学校適応感との関連を実証的に検討することであった。中学生457名を対象に調査を実施し,「生徒の教師に対する信頼感尺度」と「学校生活適応感尺度」との関連を検討した。その結果,(1)生徒の教師に対する信頼感は,生徒の「教師関係」における適応だけではなく,「学習意欲」「進路意識」「規則への態度」「特別活動への態度」といった,その他の学校適応感の側面にも影響を及ぼすこと,(2)各学年によって,生徒の教師に対する信頼感が各学校適応感に与える影響が異なり,1年生では教師に対する「安心感」が一貫して生徒の学校適応感に影響を与えていること,(3)一方,2年生,3年生では「安心感」に加えて,「不信」や「役割遂行評価」が生徒の学校適応感に影響を与えるようになること,(4)各学年とも,生徒の教師に対する信頼感の中でも,教師に対する「安心感」が最も多くの学校適応感に影響を及ぼしていること,(5)「信頼型」「役割優位型」「不信優位型」「アンビバレント型」といった生徒の教師に対する信頼感の類型によって生徒の学校適応懸か異なること,といった点が示唆された。
- 著者
- .*田戸岡 好香 小森 めぐみ
- 雑誌
- 日本心理学会第87回大会
- 巻号頁・発行日
- 2023-08-03