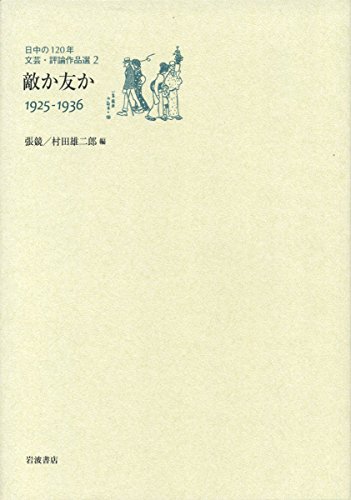1 0 0 0 OA 乳牛における乳量と心拍数の関係
1 0 0 0 敵か友か : 1925-1936
1 0 0 0 〈母〉の時間を求めて : 谷崎潤一郎『細雪』論
- 著者
- 神田 茜
- 出版者
- 早稲田大学大学院教育学研究科千葉・金井・石原研究室
- 雑誌
- 近代文学. 第二次. 研究と資料
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.114-132, 2016-03
1 0 0 0 OA モダニズム文学にみるモダンガール
- 著者
- 豊田 かおり
- 出版者
- 文化学園大学
- 雑誌
- 文化学園大学紀要. 人文・社会科学研究 (ISSN:21871124)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, pp.101-114, 2014-01-31
大正末期から昭和初期にかけて,日本は近代化が進展し,西欧の文化や思想が一般に浸透しはじめた。第一次世界大戦後,女性の進学や就職の増加に伴い,上流階級ばかりではなく,一般の女性たちがシンプルで機能的な洋服を着用しはじめ,西欧のファッションが同時代的に取り入られていくようになった。さらに1923(大正12)年の関東大震災を契機に合理的・近代化の象徴である洋服の着用がメディアによってさらに促進された。女性たちは長い黒髪を切り,洋服を着こなし,「モダンガール(通称モガ)」と呼ばれるようになった。しかし,さまざまな分野で注目を浴びたモダンガールは,東京人のパーセンテージにすれば,ごくわずかであった。やがてモダンガールには「毛断」ガールという蔑称までつき,その自由で活発な行動が非難されはじめた。本研究では,「モダンガール」が文学作品においてどのように描かれていたか見ていくべく,龍胆寺雄の『放浪時代』,広津和郎の『女給』を取り上げた。
1 0 0 0 OA 丸菱呉服店の出現と消失 : 百貨店経営参入への模索
- 著者
- 関 智子 Tomoko Seki
- 雑誌
- 共立女子大学家政学部紀要 = Bulletin of the faculty of home economics Kyoritsu Women's University
- 巻号頁・発行日
- vol.69, pp.21-35, 2023-01
- 著者
- Orianne Derrier 岡田 真弓
- 出版者
- 北海道大学観光学高等研究センター
- 雑誌
- CATS 叢書 (ISSN:21853150)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, pp.1-50, 2023-03-31
- 著者
- 中村 健 佐伯 拓也 折津 英幸 山村 芽衣
- 出版者
- 公益社団法人 日本リハビリテーション医学会
- 雑誌
- The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine (ISSN:18813526)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.1, pp.52-57, 2023-01-18 (Released:2023-03-23)
- 参考文献数
- 10
1 0 0 0 映像メディアでの共感的理解における「背後霊的視点」の効果
- 著者
- 宮崎 清孝
- 雑誌
- 大妻女子大学紀要. 家政系
- 巻号頁・発行日
- vol.30, pp.161-173, 1994-03
1 0 0 0 有島武郎『生れ出づる悩み』論--「私」の言葉の行方
- 著者
- 石橋 紀俊
- 出版者
- 有島武郎研究会
- 雑誌
- 有島武郎研究 (ISSN:13430394)
- 巻号頁・発行日
- no.2, pp.19-26, 1998-11
1 0 0 0 OA 「京都府行政文書」の史料学的検討― 構成と伝来の他事例との比較から ―
- 著者
- 安江 範泰
- 出版者
- 国文学研究資料館
- 雑誌
- 国文学研究資料館紀要 アーカイブズ研究篇 = The Bulletin of The National Institure of Japanese Literature, Archival Studies (ISSN:24363340)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.18, pp.149-158, 2022-03-18
本論文は、国重要文化財「京都府行政文書」を検討素材として、地方自治体が残す歴史的行政文書の史料学的な分析方法を提起する。 まず、京都府行政文書を個別文書別・時代別・事務別に分節化し、観点ごとにその構成を把握した。次いで、各府県が保有する同様の文書群との比較を通じて、明治期文書や農林・商工関係文書の構成比が小さい、残存する郡役所文書が少ない、昭和戦前期の文書の残存状況が良好、といった特徴が照射された。その上で、明治から太平洋戦争敗戦に至る京都府における行政活動や行政文書の蓄積・廃棄の歴史的経験を参照すると、以上にみた、京都府行政文書の構成上の諸特徴が形成される経緯を特定することがある程度まで可能であることが判明した。また各府県の事例の比較から、文書管理上の経験の共通性と差異、そしてそれが各府県の行政文書の現状にどのような影響を与えたのかも示唆された。 こうした検討事例を踏まえ、文書の内容構成の分析結果、文書の伝来に関する歴史的情報、文書間の比較から判明する情報を有機的かつ効果的に組み合わせるという方法をとることが、当該歴史的行政文書に対する史料学的理解を深め、従来の見解を乗り越える上で必要であることを問題提起する。 This paper proposes an approach to analysis historical documents of local governments, dealing withKyoto Prefectural Administrative Documents, a national important cultural property as example.First, we grasp the construction of the documents from plural viewpoins of kinds of includeddocuments, era and affairs. Secondly, by comparison with documents of other governments, the feature hasbecome clear that a rate of existing documents made in Meiji period, ones related to affairs of commerce,industry, agriculture and forestry, and ones of the Gun-offices is low, on the other hand a rate of ones made inShowa period is high. In addition, referring to the administrative activities and the record of management ofthe documents from Meiji to the defeat in WW2, we can guess to a certain extent how the above feature hasformed. And we can know community and difference of experiences of the management of documents, andwhat effect they had on present condition of each document.Through the above examination, we can say that it is necessary to effectively combine pieces ofinformation gained from analysis of the construction and transmission about the documents and comparisonwith others in order to develop an understanding on historical materials study.
1 0 0 0 OA 項目反応理論を用いた幼児および小学校低学年用短縮版感情語彙尺度の開発
- 著者
- 浜名 真以 分寺 杏介
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.1, pp.51-61, 2023-03-30 (Released:2023-03-25)
- 参考文献数
- 31
感情語を獲得することは子どもの社会化や感情経験の発達に重要な役割を持つ。本研究の目的は,幼児および小学校3年生までの児童を対象とする短縮版感情語彙尺度を開発することである。研究1では,年少児から小学3年生までの子どもを持つ母親からデータを収集し,項目反応理論を用いて幼児用および小学校低学年用の感情語彙尺度を開発し,情動コンピテンスとの関連を調べた。研究2では,幼児用感情語彙尺度で測定される感情語彙能力と一般的な言語能力や社会的コンピテンスとの関連,研究3では,低学年用感情語彙尺度で測定される感情語彙能力と一般的な言語能力との関連を検討した。感情語彙能力と子どもの一般的な言語能力や社会情動的コンピテンスの関連から,本尺度の妥当性の証拠が確認された。
1 0 0 0 OA さよなら撒里失爾酸
- 著者
- 村上 英也
- 出版者
- 公益財団法人 日本醸造協会
- 雑誌
- 日本釀造協會雜誌 (ISSN:0369416X)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.10, pp.757-762, 1973-10-15 (Released:2011-11-04)
- 参考文献数
- 65
1 0 0 0 OA 生薬の修治-蜜炙法による免疫賦活作用発現の分子機構の解明
本研究では、生薬を蜂蜜と共に加熱する加工(蜜炙)に注目し、科学的エビデンスを得ることを目的とした。培養マウス消化管上皮細胞(MCE301細胞)に各種蜂蜜または含有する糖類の加熱処理品の熱水抽出エキスを添加し、培地中に放出されるG-CSF (granulocyte-colony stimulating factor) 濃度をELISA法により測定した。蜂蜜の加熱によりG-CSF産生誘導活性が発現し、isomaltoseが本活性に寄与していた。180℃では1時間、200℃では15~30分加熱した時、活性が最大であった。以上、isomaltose含量の高い蜂蜜が蜜炙に適していることが示唆された。
1 0 0 0 OA 精神疾患におけるエピゲノム解析─セロトニントランスポーターにおける解析例から
- 著者
- 柳田 悠太朗 仲地 ゆたか 文東 美紀 岩本 和也
- 出版者
- 日本生物学的精神医学会
- 雑誌
- 日本生物学的精神医学会誌 (ISSN:21866619)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.1, pp.2-6, 2023 (Released:2023-03-25)
- 参考文献数
- 13
DNAメチル化やヒストンタンパク質の修飾など,エピジェネティックな状態には遺伝環境相互作用が反映されており,精神疾患の病因・病態の理解のためにきわめて重要であると考えられている。セロトニントランスポーターは繰り返し配列の多型領域とDNAメチル化による転写制御を受けることから,遺伝環境相互作用研究のためのよいモデルであると考えられる。本稿では,高齢者コホート検体を利用し,正常加齢に伴う認知機能の低下や抑うつ傾向について検討した筆者らのセロトニントランスポーターでの研究例を紹介する。研究の背景と共に,臨床所見とMRI画像による脳体積およびジェノタイピングデータやDNAメチル化状態を統合することで明らかになりつつある結果を紹介し,現状の課題と今後の展望を述べる。
1 0 0 0 OA 目次/ミニ特集にあたって/表紙の説明
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- ファルマシア (ISSN:00148601)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.8, pp.698-699, 2021 (Released:2021-08-01)
ミニ特集:植物バイオが切り拓く生合成研究ミニ特集にあたって:植物が生産する二次代謝(特化代謝)成分は,その生物活性から医薬品原料などに用いられる.これらの成分の生合成経路は,薬剤師国家試験でも出題されることからも分かるように薬学教育における学びの重要な1領域であるが,遺伝子工学をはじめとする植物バイオテクノロジーの発展により,本研究領域は飛躍的な進展を遂げている.近年では,オミクス解析などを用いることで遺伝子レベルやタンパク質レベルでの詳細な経路解明が進み,同定された生合成遺伝子の微生物への導入による物質生産や,逆にゲノム編集によって生合成遺伝子を破壊することによる毒性物質含量の低減など,様々な形での応用に発展している.本ミニ特集では,これら植物バイオによる生合成研究の最新の成果を,最前線で活躍されている先生方に紹介していただいた.表紙の説明:今月の表紙は,クズを題材にした「夏葛の絶えぬ使のよどめれば事しもあるごと思ひつるかも」である.これは,大伴家持の叔母にあたる大伴坂上郎女の作で,大伴宿禰駿河麿への相聞歌とされている.またまた男女の歌である.電子付録では,二人の思いを妄想しつつ,民間薬や食用としてのクズ,植物としてのクズの仲間,クズと同じく夏から初秋の草原で見られる花についても紹介したい.
- 著者
- Yuki Mizumoto Yoshinori Sasaki Hikaru Sunakawa Shuichi Tanese Rena Shinohara Toshinari Kurokouchi Kaori Sugimoto Manao Seto Masahiro Ishida Kotoe Itagaki Yukino Yoshida Saori Namekata Momoka Takahashi Ikuhiro Harada Shoko Sasaki Kiyoshi Saito Yusuke Toguchi Yuki Hakosima Kumi Inazaki Yuta Yoshimura Masahide Usami
- 出版者
- National Center for Global Health and Medicine
- 雑誌
- Global Health & Medicine (ISSN:24349186)
- 巻号頁・発行日
- pp.2022.01034, (Released:2023-03-23)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 2
During the COVID-19 pandemic, the incidence of eating disorders (ED) has increased not only in Japan but also worldwide. This online survey for pediatricians showed that caregivers tend to visit specific pediatric institutions or child psychiatry departments when children under junior high school age develop eating disorders. There are few pediatric institutions regarding treatment acceptance for children with ED. Of the 34 respondents, 16 (47.1%) answered that the number of visits for children with eating disorders had "stayed the same", one answered it had "decreased" and 17 (50.0%) answered it had "increased" or "increased very much". In addition, 28 of the 34 respondents (82.3%) experienced difficulties with psychotherapy for children with ED. For treating children with ED, pediatricians usually conducted physical examination and have some clinical burden. ED are increasing in the COVID-19 pandemic. Because children with severe ED need to be hospitalized, child and adolescent psychiatric wards are overcrowded and some children with other mental disorders can't be admitted.
1 0 0 0 OA 2015 4 紀要22
- 巻号頁・発行日
- 2015-04-01
- 著者
- 広瀬 和佳子
- 出版者
- 公益社団法人 日本語教育学会
- 雑誌
- 日本語教育 (ISSN:03894037)
- 巻号頁・発行日
- vol.174, pp.1-15, 2019-12-25 (Released:2021-12-26)
- 参考文献数
- 14
本稿は,ピア・レスポンス (以下,PR) 実践研究の文献レビューを通して,教師のPR実践に対する評価観を分析した。CiNiiでの検索結果から,論文著者が教師としてPR実践を考察している論文を抽出し,68編 (異なり著者数44) を分析対象とした。PRはプロセス重視と協働の理念の下,様々な教育機関で実践されるようになったが,実践研究論文の多くは依然として作文の変化や自己推敲力の向上など認知的側面に及ぼす効果を分析していた。PRのプロセスや協働の意義など社会的側面に焦点をあてた研究のうち,実践者の教育観が明確であり,書くことの意欲や表現する喜び,学習者同士の関係構築を第一に評価し,相互行為そのものに価値をおいている論文は3編だった。実践者によってPRの意義づけは大きく異なる。実践者は何を目的にどのようなPRを実践したのか,自身の教育観を具体的な実践の文脈において自覚的に記述することが今後のPR実践研究に求められる。
1 0 0 0 OA 化学物質に対する非特異的な過敏状態の解明とその改善方法に関する研究
ベースライン調査として、化学物質過敏症の患者群10名および性別と年齢を患者群と一致させた健常者群9名に対し、においスティックによる臭い負荷を行い、負荷時および負荷前後の前頭前皮質の脳血流状態を近赤外光脳機能イメージング装置で計測した。また上記検査と同時に末梢動脈血酸素飽和度、自律神経状態をモニタリングして計測データを得た。その後の1年間のうちの約2ヶ月半、これらの患者群のうち6名に対してLカルニチンを投与、1名は酸素療法を試み、3名は非介入群とし、同様の嗅覚負荷検査等を実施した。その結果、総じて化学物質過敏状態について、明白な改善はみられなかったが、比較的症状が重い一部では改善傾向がみられた。
1 0 0 0 OA スポーツにおける競争の社会的意味 -ジンメルの『競争の社会学』に見る両義性-
- 著者
- 釜崎 太
- 出版者
- 日本体育・スポーツ哲学会
- 雑誌
- 体育・スポーツ哲学研究 (ISSN:09155104)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.2, pp.133-146, 2019 (Released:2020-03-10)
- 参考文献数
- 56
Research in Japan to date that has analyzed sport from the perspective of Simmel's theory of competition understands the theory as supportive of only the positive meaning of competition in sport. However, Simmel had a keen appreciation of the issues of modern society and addressed matters incidental to actual competition.Contemporary society differs from Gemeinschaft(traditional local communities) with their fixed interpersonal relationships, and from the system of slavery, in which people were owned as if machines. While people now possess a sense of inalienable personhood, interaction between them has become shallower. Simmel saw competition in Gesellschaft(modern society) as effectively providing opportunities for people to bond.For example, an essential element of sport is its ability to excite large numbers of people. As such, it bonds not only coaches and players, players within a team, and competing teams, but, by involving “the advantage of a third person”, creates a bond between all involved in competition and the masses, too. Yet, at the same time, this type of competition inverts the respective positions of the expert and the masses, making it more likely that a young pitcher, for example, may ignore the warnings of the experts and, in deference to public demand, waste his or her talent at national tournaments by pitching incessantly.This paper attempts to clarify the social significance of sporting competition in Gesellschaft (modern society) from the perspective of such amphibolousness in the positives and negatives of competition.