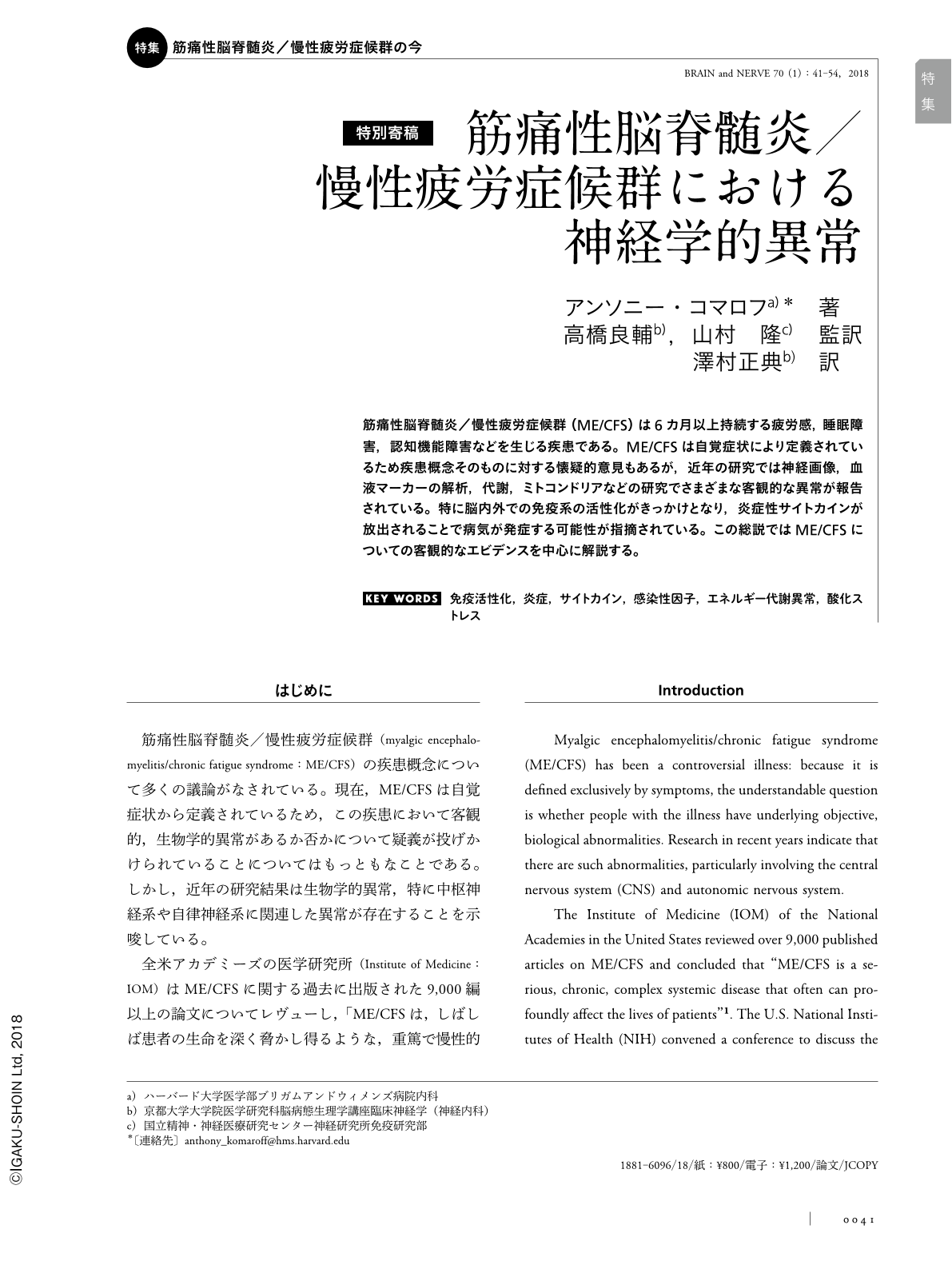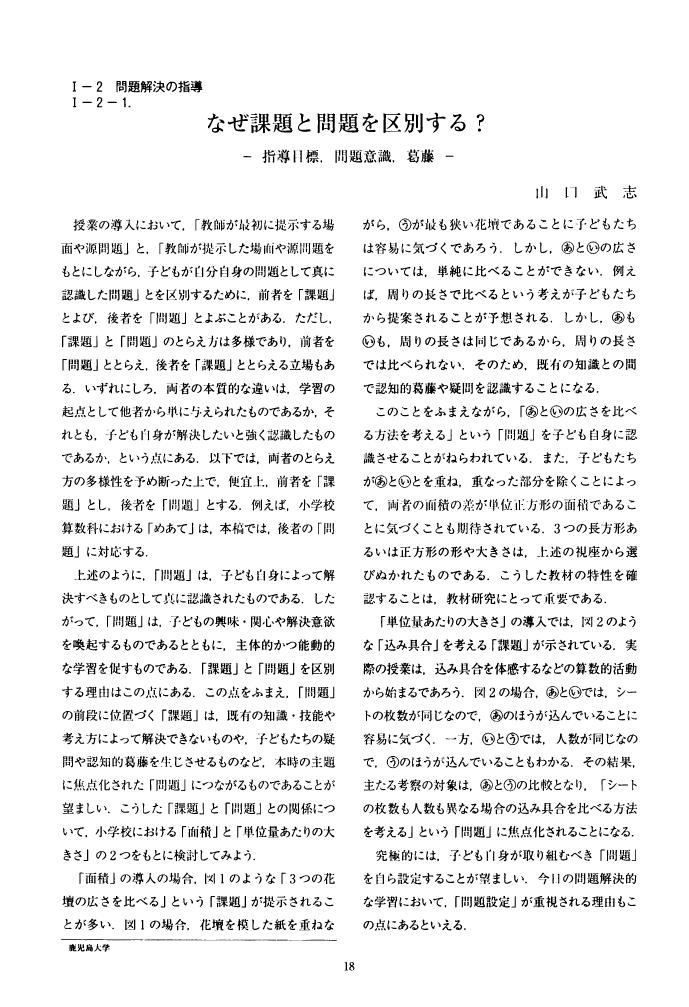- 著者
- 森 貴史
- 出版者
- 關西大學文學會
- 雑誌
- 關西大學文學論集 (ISSN:04214706)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.1, pp.1-23, 2016-07
8 0 0 0 OA ブルデューとスポーツ社会学
- 著者
- 磯 直樹
- 出版者
- 日本スポーツ社会学会
- 雑誌
- スポーツ社会学研究 (ISSN:09192751)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.1, pp.73-87, 2011-03-20 (Released:2016-09-13)
- 参考文献数
- 50
- 被引用文献数
- 1
ブルデューはスポーツに長く関心を抱いていたが、それについて論じた論稿は3つしかなく、スポーツ社会学について体系的な研究を残したわけではない。にもかかわらず、フランスのスポーツ社会学にはブルデューが多大な影響を及ぼしてきた。本稿では、このようなブルデューとスポーツ社会学の関係について考察する。 ブルデューがスポーツについて問うたことは、その独自の社会学と深く結びついている。ブルデューはスポーツの歴史的・社会的条件は何かと問い、各々のスポーツ種目をめぐる実践と消費の分析に関心を抱いていた。また、スポーツに固有の空間の特性について考察を試みた。こうしたブルデューの問題関心は、彼の社会学を支えるいくつかの概念、例えばハビトゥス、資本、界、社会空間などとつながっている。ブルデューのスポーツに関する問題提起を受けつつ、その社会学をスポーツ研究に応用したのがポシエロやドゥフランスであった。彼らによって、ブルデューの社会学を応用したスポーツ社会学の体系が構想されていった。つまり、「ブルデュー派」スポーツ社会学は、ブルデュー自身によってではなく、彼に近いスポーツ社会学者たちによって担われていたのである。 ブルデュー自身とスポーツ研究の関係は限定的であったため、ブルデューの社会学を従来とは違った方法でスポーツ研究に応用することは十分に可能である。そうした新しい応用の方法については、一方ではブルデュー自身がオリンピック論で示したような国際的・グローバルなスポーツ研究が考えられ、また一方では、ヴァカンがシカゴの黒人ゲットーで行ったボクシングのエスノグラフィのような生身の人間と向き合う局地的な研究が考えられる。ブルデューの社会学を部分的に受容することももちろん可能であり、スポーツ社会学においてブルデューを受容する方法は、各々に自由な選択として開かれている。
8 0 0 0 OA 呉茱萸湯で効果不十分な月経関連片頭痛患者に五苓散を月経周期に合わせて投与した症例の検討
- 著者
- 木村 容子 田中 彰 佐藤 弘 伊藤 隆
- 出版者
- 一般社団法人 日本東洋医学会
- 雑誌
- 日本東洋医学雑誌 (ISSN:02874857)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.1, pp.34-39, 2017 (Released:2017-07-05)
- 参考文献数
- 28
- 被引用文献数
- 1 1
背景:月経時片頭痛は他の時期の発作に比べて治療抵抗性であることが多い。呉茱萸湯で効果不十分な月経時の片頭痛に黄体ホルモンによる水滞の病態に着目して五苓散を併用した。対象と方法:呉茱萸湯を3ヵ月間投与し,月経時の片頭痛が残存した陰証の月経関連片頭痛患者37名(中央値37歳,範囲23—48歳)を対象とした。呉茱萸湯の服用は継続し,残存する月経時の頭痛に対して月経1週間前から月経終了時まで五苓散を追加した。結果:月経時の片頭痛が軽快した症例は26例(70%)。改善群では,発作時の随伴症状として頭重感(p = 0.003),浮腫(0.006),めまい(0.014),尿不利(0.014)が有意に認められ,雨前日に頭痛の悪化を認めることも多かった(0.004)。結語:発作時に頭重感や尿不利など水滞症状が顕著な場合は,呉茱萸湯に五苓散を月経周期に合わせて投与することが有効であると考えられた。
8 0 0 0 OA 個人データの保護に関する法律
- 著者
- 安藤英梨香
- 出版者
- 国立国会図書館
- 雑誌
- 外国の立法 : 立法情報・翻訳・解説 (ISSN:13492071)
- 巻号頁・発行日
- vol.(月刊版. 277-1), 2018-10
8 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1943年06月05日, 1943-06-05
8 0 0 0 OA 生物多様性ビッグデータに基づいたネイチャーの可視化:その現状と展望
- 著者
- 久保田 康裕 楠本 聞太郎 塩野 貴之 五十里 翔吾 深谷 肇一 高科 直 吉川 友也 重藤 優太郎 新保 仁 竹内 彰一 三枝 祐輔 小森 理
- 出版者
- 日本計量生物学会
- 雑誌
- 計量生物学 (ISSN:09184430)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.2, pp.145-188, 2023 (Released:2023-06-28)
- 参考文献数
- 110
Biodiversity big data plays an essential role in better understanding of biodiversity pattern in space and time and its underpinning macroecological mechanisms. Biodiversity as a concept is inductively quantified by the measurable multivariate data relative to taxonomic, functional and phylogenetic/genetic aspects. Therefore, conservation is also argued by using particular biodiversity metrics, context dependently, e.g., spatial conservation prioritization, design of protected areas network.Individual descriptive information accumulated in biogeography, ecology, physiology, molecular biology, taxonomy, and paleontology are aggregated through the spatial coordinates of biological distributions. Such biodiversity big data enables to visualize geography of 1) the richness of nature, 2) the value of nature, and 3) the uncertainty of nature, based on statistical models including maximum likelihood, machine learning, deep learning techniques. This special issue focuses on statistical and mathematical methods in terms of the quantitative visualization of biodiversity concepts. We hope that this special issue serves as an opportunity to involve researchers from different fields interested in biodiversity information and to develop into new research projects related to Nature Positive by 2030 that aims at halting and reversing the loss of biodiversity and ecosystem service.
8 0 0 0 OA 「北海道旧土人保護法」・「旧土人児童教育規程」下のアイヌ学校
- 著者
- 小川 正人
- 出版者
- 北海道大學教育學部
- 雑誌
- 北海道大學教育學部紀要 (ISSN:04410637)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, pp.197-266, 1992-06
8 0 0 0 OA 渋滞のサイエンスとその解消法(身近な現象の物理,話題)
- 著者
- 西成 活裕
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.3, pp.170-173, 2016-03-05 (Released:2018-07-20)
8 0 0 0 OA 酵素法により製造されたイヌリンと低脂肪食品への利用
- 著者
- 和田 正 田中 彰裕
- 出版者
- 公益社団法人 日本農芸化学会
- 雑誌
- 化学と生物 (ISSN:0453073X)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.6, pp.376-382, 2013-06-01 (Released:2014-06-01)
- 参考文献数
- 29
- 被引用文献数
- 1
筆者らは,スクロースをイヌリンに変換する酵素生産細菌 Bacillus sp. 217C-11 株を見いだすことに成功した.この酵素は,イヌロスクラーゼに分類される新規な糖転移酵素であることが明らかになった.また,酵素の反応条件を任意に選択することによって合成されるイヌリンの平均鎖長を制御できることもわかった.こうして作られたイヌリンは,植物由来のイヌリンに比べて水溶性が高く,食品加工特性に優れるものであった.近年では,脂肪に似た食感のゲルを形成する性質を利用して,油脂含有食品の低脂肪化のための素材としての利用が拡大している.
8 0 0 0 OA CFAフラン圏の輸出競争力 ―1999-2006期間の実質実効為替レートからの検証―
- 著者
- 正木 響
- 出版者
- 国際開発学会
- 雑誌
- 国際開発研究 (ISSN:13423045)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.2, pp.101-118, 2010-11-15 (Released:2019-12-25)
- 参考文献数
- 43
The CFA Franc was introduced to the formerly French-ruled African Countries in 1945, on the day previous to the French accession to IMF. There actually exist two totally different currencies called the CFA franc: The Communauté Financière d'Afrique Franc, which is shared among eight Western African countries and Coopération Financière en Afrique centrale Franc for six Central African countries. Each currency is issued and controlled by its own central bank and the value of both currencies is pegged to the French Franc (or the Euro since 2002) at the same rate.However, with the appreciation of the Euro, the appreciation of these two CFA Francs has become a problem of deep concern. Despite the fact that the Sub Saharan African countries had also faced to the same economic crisis since the 1980's, CFA Franc countries are thought to have had far more serious difficulty in adjusting their economies. In this paper, we first identify the institutions of the CFA Franc Zone as well as a range of problematic issues pointed out in empirical research. Second, we calculated the Real Effective Exchange Rates (REER) for those countries based on quarterly data from 1999 to 2006 and compared them with those of neighbor countries.Our results show that the REER of most CFA Franc countries did not appreciate because they had succeeded in keeping their price levels sufficiently low. However, most of their neighboring countries, which continued to devaluate their currencies due to instability of their economies were much more competitive. Since the financial crisis of the year 2008, the effect of the exchange rate systems on economic growth attracted the heightened attention. This paper shows some important issues when we will grapple with the development of the CFA Franc Zone Countries.
8 0 0 0 OA 犯罪,警察,サモスード : ロシア革命下ペトログラードの社会史への一試論
- 著者
- 長谷川 毅
- 出版者
- 北海道大学スラブ研究センター
- 雑誌
- スラヴ研究 (ISSN:05626579)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, pp.27-55, 1987
- 著者
- 中尾 麻衣子 国分 峰樹
- 出版者
- 日本広告学会
- 雑誌
- 広告科学 (ISSN:13436597)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, pp.127-149, 2008 (Released:2017-10-25)
8 0 0 0 OA 自傷による腹部多臓器損傷の1救命例
- 著者
- 髙須 香吏 中山 中 窪田 晃治
- 出版者
- 信州医学会
- 雑誌
- 信州医学雑誌 (ISSN:00373826)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.5, pp.249-257, 2020-10-10 (Released:2020-11-11)
- 参考文献数
- 34
A 40-year-old woman who had undergone long-term hospitalization for schizophrenia was discharged. Four days later, she impulsively self-injured, was hospitalized with a prolapsed intestinal tract, and underwent emergency surgery. The wound on the left side penetrated the upper jejunum, mesenteric vessels, hilar region of the left kidney, iliopsoas, and a paravertebral nerve. The right involved the duodenum and vena cava. We repaired the each damage and performed left nephrectomy. The deadly triad was inferred, so we closed the wounds and transferred her to the ICU. Hemorrhagic shock continued for 31 hours, improved with massive blood transfusion. She then suffered from liver dysfunction, jaundice, renal insufficiency, hydrothorax and atelectasis, and abscess due to duodenal ruptured suture. Continuing care included dialysis, mechanical ventilation, thoracic and abdominal drainage, and nutritional management worked. The acute and subacute care ceased in week 12, and after rehabilitation, she was discharged by foot.We encountered an alive case suffered from definitive operation for multiple abdominal wound. We report it with inquest of the tactics and strategy.
8 0 0 0 OA ロック音楽文化の構造分析
- 著者
- 南田 勝也
- 出版者
- The Japan Sociological Society
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.4, pp.568-583, 1999-03-30 (Released:2010-11-19)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 2
本稿は, 20世紀後半を代表する音楽文化, 若者文化であるロック (Rock) を, 諸個人の信念体系や社会構造との関係性の分析を中心に, 社会科学の対象として論述するものである。ロックはその創生以来, 単なる音楽の一様式であることを越え, ある種のライフ・スタイルや精神的態度を表すものとして支持されてきた。それと共に, 「ロックは反逆の音楽である」「破壊的芸術である」「商業娯楽音楽である」といったように, さまざまにその “本質” が定義されてきた。ここではそれらの本質観そのものを分析の対象とし, 諸立場が混合しながらロック作品を生産していく過程について考察する。そのような視点を用いた論理展開をよりスムーズに行うために, ピエール・ブルデューの〈場〉の理論を (独自の解釈を施したうえで) 本論考に援用する。「ロック」という名称を共通の関心とする人々によって構成され, [ロックである/ロックでない] という弁別作業が不断に行われ, ロック作品がその都度生産されていく (理念的に想定した) 空間を「ロック〈場〉」と呼び, 〈場〉の参与者の社会的な配置構造とそこに生じるダイナミズムを論述することを主たる説明の方法とする。これらの考察を基にして, 最終的に汎用度の高いモデル図を作成し, 社会と音楽の関係性を総合的かつ多角的に把握するための一つの視座を提出する。
- 著者
- 上段固体モータ信頼性研究グループ 上段固体モータ信頼性研究グループ Upper Stage Solid Motor Reliability Research Group Upper Stage Solid Motor Reliability Research Group
- 出版者
- 航空宇宙技術研究所
- 雑誌
- 航空宇宙技術研究所報告 = Technical Report of National Aerospace Laboratory (ISSN:03894010)
- 巻号頁・発行日
- vol.1298, pp.1-62, 1996-06
国産・自主技術で進めたH-1ロケット用第3段モータおよびアポジ・モータの開発において重要な要素である信頼性の確立を図るため、航空宇宙技術研究所(NAL)と宇宙開発事業団(NASDA)が研究グループ「上段固体モータ信頼性研究グループ」を結成し、共同研究「上段固体ロケットモータの信頼性評価基準に関する実験的研究」を1980年度から1984年度まで行った。そしてその主体である推進薬の欠陥許容判定基準の研究および推進薬の欠陥検出法の研究についての成果をその後の研究成果も含めて3部作の報告書にまとめた。なお、本共同研究はNAL特別研究「上段モータの信頼性評価基準に関する研究」と緊密な関係のもとで行われた。本報告書では、国産開発のH-1アポジ・モータの1/4縮尺モータなどの小型モータに、推進薬気泡、インシュレーション・推進薬間剥離、推進薬ノッチなどの人工欠陥を付し、欠陥の燃焼への影響を調べた結果について述べる。
8 0 0 0 OA 信者が「世代」を語る時 : 「エホバの証人」の布教活動に現れたカテゴリー化実践の分析
- 著者
- 兼子 一
- 出版者
- 「宗教と社会」学会
- 雑誌
- 宗教と社会 (ISSN:13424726)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.39-59, 1999-06-03 (Released:2017-07-18)
- 被引用文献数
- 2
本論文は、「エホバの証人」(ものみの塔聖書冊子協会)の信者による布教活動がどのように行われているのか、という観点から信者の実践活動に関するフィールドワークの一部をまとめたものである。なお、この調査は1992年から1998年にかけて実施している。この研究は、エスノメソドロジーという研究方法を使用することで、「信仰」というものを相互行為と考え、「布教と受容」の相互反映的なプロセスとして解明することを目指している。ところで、エスノメソドロジーの主な分析方法としては、「会話分析」と「ワークの分析」と呼ばれるものがある。そこで、この論文では、「ワークの分析」と呼ばれる方法を採用することにした。論点として、信者が布教プロセスにおいて、相手を納得させるために、どのようにカテゴリー群を使用していくのか。そして、その語用法が参与観察者である「私」にどのような受容プロセスとして立ち現れていたのか。これらの相互作用プロセスに焦点をあてた。なお、会話分析については別稿を用意している。
8 0 0 0 【特別寄稿】筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群における神経学的異常
- 著者
- コマロフ アンソニー 高橋 良輔 山村 隆 澤村 正典
- 出版者
- 医学書院
- 巻号頁・発行日
- pp.41-54, 2018-01-01
筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(ME/CFS)は6カ月以上持続する疲労感,睡眠障害,認知機能障害などを生じる疾患である。ME/CFSは自覚症状により定義されているため疾患概念そのものに対する懐疑的意見もあるが,近年の研究では神経画像,血液マーカーの解析,代謝,ミトコンドリアなどの研究でさまざまな客観的な異常が報告されている。特に脳内外での免疫系の活性化がきっかけとなり,炎症性サイトカインが放出されることで病気が発症する可能性が指摘されている。この総説ではME/CFSについての客観的なエビデンスを中心に解説する。
8 0 0 0 OA なぜ課題と問題を区別する? 指導目標,問題意識,葛藤
- 著者
- 山口 武志
- 出版者
- 公益社団法人 日本数学教育学会
- 雑誌
- 日本数学教育学会誌 (ISSN:0021471X)
- 巻号頁・発行日
- vol.92, no.11, pp.18, 2010 (Released:2021-04-01)
- 著者
- 吉田 航
- 雑誌
- 2023年度組織学会研究発表大会
- 巻号頁・発行日
- 2023-05-24
- 著者
- 大城 正巳 廣末 雅幸 平安山 睦美 上間 昇 久田 友治
- 出版者
- 一般社団法人 日本輸血・細胞治療学会
- 雑誌
- 日本輸血細胞治療学会誌 (ISSN:18813011)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.4, pp.759-765, 2019-08-25 (Released:2019-09-19)
- 参考文献数
- 15
人口当たりの年齢別輸血頻度と主な診療科の輸血単位数の変化について詳細を明らかにすることを目的として,輸血用血液製剤の使用状況調査を行った.輸血用血液製剤供給上位19施設から2012,2017年度の輸血情報(輸血年月日,製剤名,製造番号,診療科,患者識別番号(匿名化),輸血時年齢)を電子データで収集した.2017年度の輸血頻度の最頻値年齢は,赤血球製剤が89歳,血漿製剤が78歳,血小板製剤が82歳であった.年度間で50歳以上の輸血頻度が,有意に減少していた.その増減率中央値は赤血球製剤が-21.1%,血漿製剤が-23.1%,血小板製剤が-28.0%であった.多くの診療科で使用量は減少していたが,救急集中治療科は全ての製剤が増加していた.赤血球製剤の輸血単位数は,68,352Uから64,200Uに減少していたが,患者実人数は,8,377名から8,882名に増加していた.その内訳は,2単位輸血の患者実人数は増加し,4~8単位は減少していた.その傾向は,内科一般,外科一般,心臓血管外科,整形外科で強かった.これらの状況から,高齢化による患者数の増加はあるものの,患者一人当たりの輸血量は抑制されていることが確認できた.