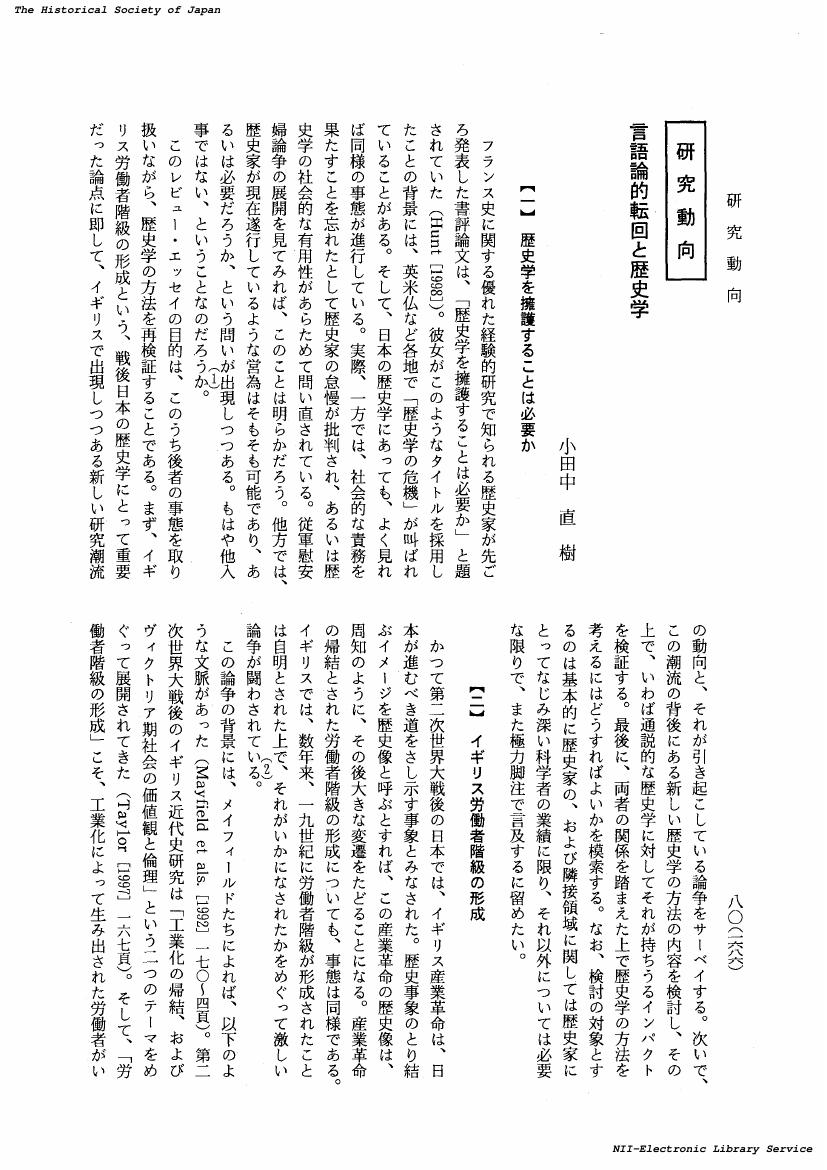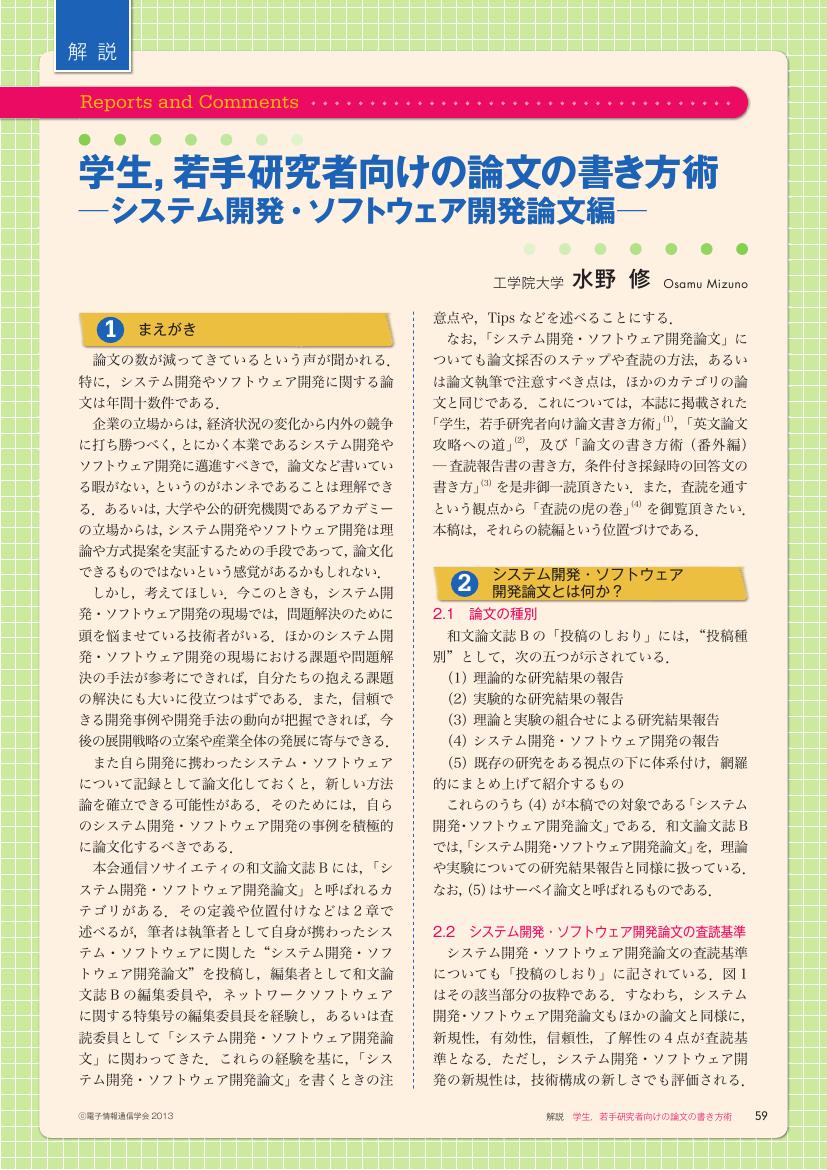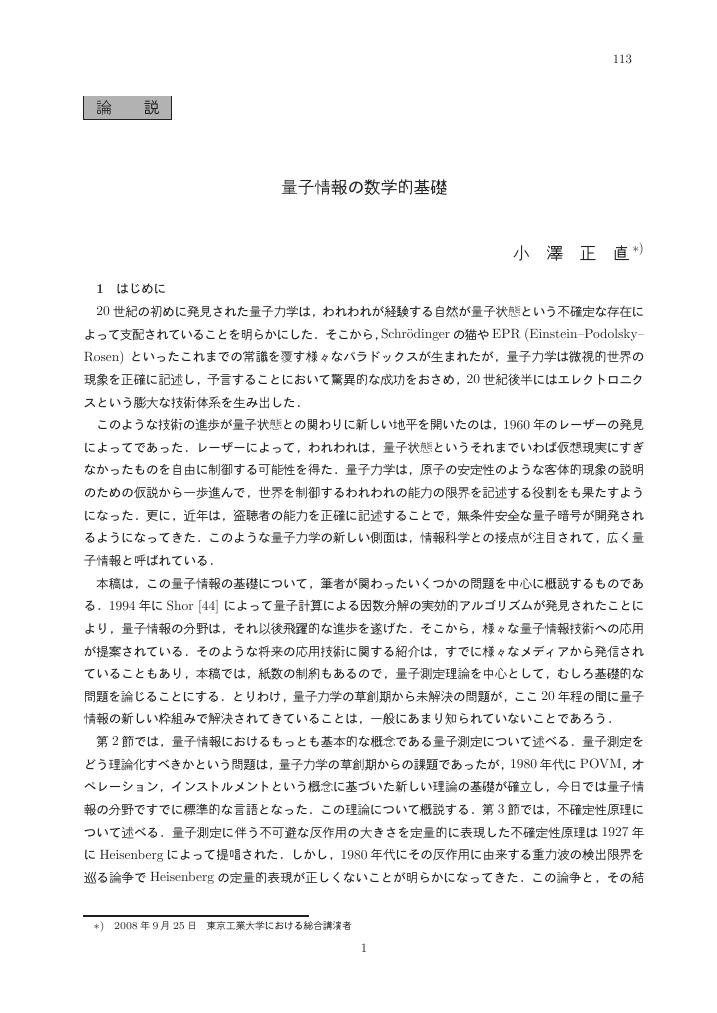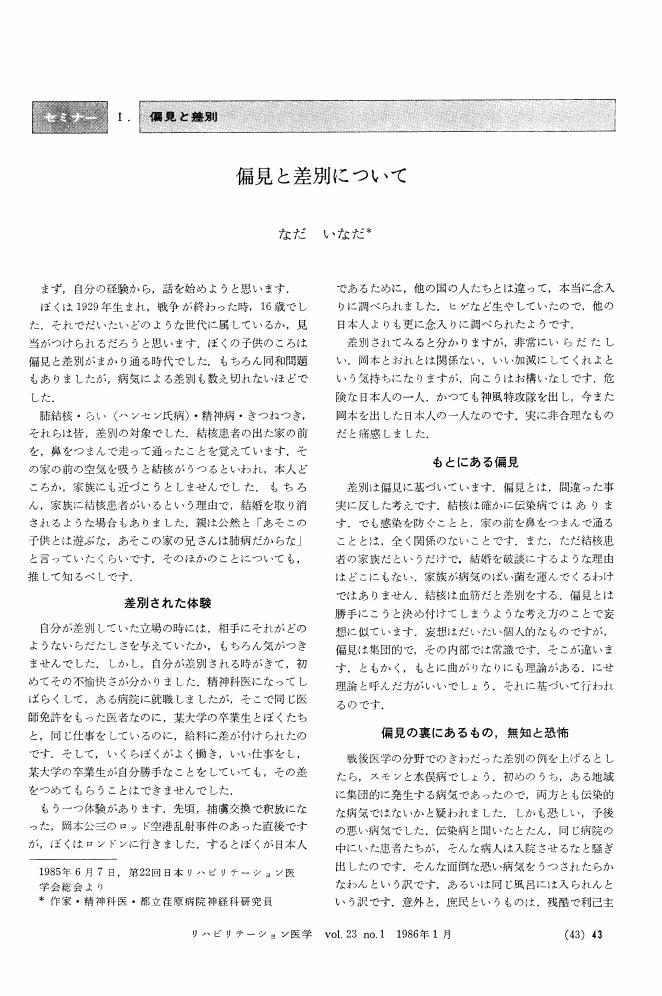31 0 0 0 OA 超音速自由噴流のレーザー分子分光学への応用
- 著者
- 三上 直彦
- 出版者
- 公益社団法人 応用物理学会
- 雑誌
- 応用物理 (ISSN:03698009)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.8, pp.802-812, 1980-08-10 (Released:2009-02-09)
- 参考文献数
- 35
- 被引用文献数
- 1
A supersonic free expansion of polyatomic molecules seeded in an inert carrier gas has been regarded as an excellent technique to produce the isolated and ultracold molecules which satisfy the requirements of an ideal spectroscopic sample. The cooling effects in the supersonic molecular beam are briefly summarized. An experiment on aniline with a simple pulsed supersonic nozzle combined with a pulsed tunable UV light source is described as an example of the fluorescence excitation spectroscopy. Recent progress on the optical spectroscopy of polyatomic molecules by use of the seeded supersonic free jets is reviewed from the photochemical and the photohysical point of view. The molecular structures and the dynamical behaviors in the excited states of the stable molecules and the van der Waals complexes are discussed.
- 著者
- Tomoharu Kuboyama Chihiro Tohda Katsuko Komatsu
- 出版者
- The Pharmaceutical Society of Japan
- 雑誌
- Biological and Pharmaceutical Bulletin (ISSN:09186158)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.6, pp.892-897, 2014-06-01 (Released:2014-06-01)
- 参考文献数
- 60
- 被引用文献数
- 58 97
Neurodegenerative diseases commonly induce irreversible destruction of central nervous system (CNS) neuronal networks, resulting in permanent functional impairments. Effective medications against neurodegenerative diseases are currently lacking. Ashwagandha (roots of Withania somnifera Dunal) is used in traditional Indian medicine (Ayurveda) for general debility, consumption, nervous exhaustion, insomnia, and loss of memory. In this review, we summarize various effects and mechanisms of Ashwagandha extracts and related compounds on in vitro and in vivo models of neurodegenerative diseases such as Alzheimer’s disease and spinal cord injury.
31 0 0 0 OA 言語論的転回と歴史学
- 著者
- 小田中 直樹
- 出版者
- 公益財団法人 史学会
- 雑誌
- 史学雑誌 (ISSN:00182478)
- 巻号頁・発行日
- vol.109, no.9, pp.1686-1706, 2000-09-20 (Released:2017-11-30)
31 0 0 0 OA コリノソーマ症:鰭脚類を終宿主とするあまり知られていない人獣共通寄生虫症
- 著者
- 片平 浩孝 藤田 朋紀 中尾 稔 羽根田 貴行 小林 万里
- 出版者
- 日本哺乳類学会
- 雑誌
- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.2, pp.361-365, 2017 (Released:2018-02-01)
- 参考文献数
- 26
鰭脚類を終宿主とする寄生虫(Corynosoma spp.)の人体感染が北海道で生じ,その症例報告が消化器病学および寄生虫学の専門誌に相次いで掲載された.感染例はこれに留まらず,引き続き新たな患者が確認されている.本寄生虫症はいずれも虫体が小腸に長期間潜伏し,適切な診断や処置の遅れに繋がりやすい特徴を有していた.感染数増加の背景を理解することや今後の動向監視を含め,本寄生虫症に対するさらなる情報の蓄積が望まれる.
31 0 0 0 OA 学生,若手研究者向けの論文の書き方術 —システム開発・ソフトウェア開発論文編—
- 著者
- 水野 修
- 出版者
- 一般社団法人 電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会 通信ソサイエティマガジン (ISSN:21860661)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.1, pp.59-63, 2013-06-01 (Released:2013-09-01)
- 参考文献数
- 4
- 被引用文献数
- 1 1
31 0 0 0 OA 選挙地理学の近年の研究動向
- 著者
- 高木 彰彦
- 出版者
- The Human Geographical Society of Japan
- 雑誌
- 人文地理 (ISSN:00187216)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.1, pp.26-40, 1986-02-28 (Released:2009-04-28)
- 参考文献数
- 103
- 被引用文献数
- 3
31 0 0 0 OA 駅との位置関係からみた地方都市中心市街地のにぎやかさを分析する手法の開発と適用
- 著者
- 対馬 銀河 吉川 徹 讃岐 亮
- 出版者
- 一般社団法人 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会技術報告集 (ISSN:13419463)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.54, pp.667-670, 2017 (Released:2017-06-20)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 4
The purpose of this report is to develop a method to analyze the relationship between the centers of cities and the commercial districts near the main stations. The classification using the proposed indexes revealed that the centers of the 66 local cities in Japan have been declining compared with the commercial districts near the stations. Multiple regression analysis showed, that the centers of the cities are likely to decline, if the populations are small, the distances to the main stations are large, the numbers of railway passengers are large, and the prefectural and city halls are far from the centers.
31 0 0 0 OA 量子情報の数学的基礎
- 著者
- 小澤 正直
- 出版者
- 一般社団法人 日本数学会
- 雑誌
- 数学 (ISSN:0039470X)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.2, pp.113-132, 2009 (Released:2012-01-31)
- 参考文献数
- 51
31 0 0 0 OA 遺伝子多型性と農薬の慢性影響
- 著者
- 永美 大志
- 出版者
- 一般社団法人 日本農村医学会
- 雑誌
- 日本農村医学会雑誌 (ISSN:04682513)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.4, pp.683-692, 2014 (Released:2015-03-10)
- 参考文献数
- 31
近年, 遺伝子に関する検査技術の発達は目を見張るものがあり, 農薬の人体への慢性影響についても, 化学物質の代謝と細胞膜の通過を司る遺伝子の多型性との関係を研究した報告が増加している。このあたりを中心に文献的考察を行なった。 発癌に関する研究では, 様々な農薬曝露指標と遺伝子多型との間に交互作用を認めていた。胆嚢癌, 前立腺癌, 腎癌, 乳癌, 膀胱癌, 小児白血病, 小児脳腫瘍などの多様な発癌が対象となっていた。農薬曝露指標としては, 血清DDTレベル, マラチオン, DDVPなどの農業使用, 職業歴, 小児期の殺虫剤曝露, 出生前殺虫剤曝露などについて関係が認められていた。遺伝子多型としては, シトクロムP450, グルタチオン-S-転移酵素, P糖タンパク質, フラビン含有モノオキシゲナーゼ, キノンオキシドレダクターゼなどについて関係が認められていた。 パーキンソン病についても, 農薬曝露と, パラオキソナーゼ, ドーパミントランスポーター多型との交互作用を認める報告があった。 出生障害と小児発達についても, ①有機塩素農薬曝露とシトクロムP450の多型と早産, ②有機リン曝露とパラオキソナーゼ多型と出生頭囲の低下または小児発達の遅延, など関係を認める報告があった。 化学物質過敏症についても, いくつかの遺伝子多型との関係を認める報告があった。農薬曝露との交互作用を含めて, 疫学的に検討が進められることが望まれる。
31 0 0 0 OA 大学生の独り言的ツイートは独り言なのか――発話傾向との関連から
- 著者
- 澤山 郁夫 三宅 幹子
- 出版者
- 日本パーソナリティ心理学会
- 雑誌
- パーソナリティ研究 (ISSN:13488406)
- 巻号頁・発行日
- pp.27.1.5, (Released:2018-04-05)
- 参考文献数
- 23
本研究の目的は,大学生を対象とした質問紙調査を行い,独り言的ツイート頻度と社会的発話傾向および私的発話傾向の関連から,大学生の独り言的ツイートがそのどちらの性質をより強くもつものであるのか検討することであった。結果,2012年12月に得たサンプルでは,独り言的ツイート頻度は私的発話傾向と関連していた一方で,2016年1月に得たサンプルでは,社会的発話傾向と関連傾向にあった。さらに,経年変化として,独り言的ツイートの代替手段として「メモに書く」をあげる者の割合が減少傾向に,また「他者に話す」を挙げる者の割合が増加傾向にあることが示された。これらの結果から,Twitterで表出される大学生の独り言的ツイートは,私的発話としてとらえられるものから,社会的発話として捉えられるものへと変化しつつあると示唆された。
31 0 0 0 OA なぜ浜松で歴代最高気温41.1℃が観測されたか? —実況と過去の高温事例との比較による考察—
- 著者
- 髙根 雄也 伊藤 享洋
- 出版者
- 公益社団法人 日本気象学会
- 雑誌
- 天気 (ISSN:05460921)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.3, pp.149-163, 2021 (Released:2021-04-30)
- 参考文献数
- 42
2020年8月17日に静岡県浜松市で観測された日最高気温の歴代最高タイ記録41.1℃について,関連する観測データの特徴を調査した.まず,高温の背景要因を考察した結果,鯨の尾型に準ずる夏型気圧配置の出現とそれに伴う850hPa面の高温・概ね北西の一般風,東海地方における梅雨明け以降の連続晴天がその要因として示唆された.次に,高温の直接的な要因を考察したところ,伊吹山地を吹き下りる気流に伴うフェーン現象と,その後この気流が名古屋都市圏の地表面付近を吹走する際の顕熱供給(非断熱加熱)で気流そのものが高温化するメカニズムで浜松の高温がある程度説明できることが明らかになった.この高温化した風が浜松へ侵入し,浜松のすぐ東側の南風と収束したことが,浜松で最も気温が高くなった要因とみられる.以上のメカニズムは過去の国内における高温事例のメカニズムと類似していることから,上記の背景要因と直接的要因を兼ね備えうる他の地域においても今後40℃を超える高温が発生する可能性がある.
31 0 0 0 OA 情報論議 根掘り葉掘り 偽書あれこれ
- 著者
- 名和 小太郎
- 出版者
- 国立研究開発法人 科学技術振興機構
- 雑誌
- 情報管理 (ISSN:00217298)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.1, pp.61-65, 2016-04-01 (Released:2016-04-01)
- 参考文献数
- 19
31 0 0 0 OA 海産メイオベントス(小型底生動物)の採集および抽出方法
- 著者
- 山崎 博史 藤本 心太 田中 隼人
- 出版者
- 日本動物分類学会
- 雑誌
- タクサ:日本動物分類学会誌 (ISSN:13422367)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, pp.40-53, 2019-02-28 (Released:2019-03-23)
- 参考文献数
- 80
- 被引用文献数
- 2
Meiobenthos is a term usually referring to microscopic benthic organisms which pass through a 1 mm mesh sieve and are retained on a 32–63 μm one. Meiobenthos occurs in any aquatic environment, shows high species diversity as well as high biomass, and often plays an important role in ecological and evolutionary studies. However, the species diversity of these animals in Japanese waters has been insufficiently investigated. Here we review several methodologies for collecting extant meiobenthos from the marine environment, including the method for sampling sediments in various environments, extracting meiobenthos from the sediment samples, and some tips for sorting, fixation, and observation of them.
31 0 0 0 ロボットの動作生成のための強化学習
- 著者
- 太田 佳
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能 (ISSN:21882266)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.4, pp.499-506, 2022-07-01 (Released:2022-07-01)
31 0 0 0 OA 消費税の「社会保障目的税化」「社会保障財源化」の検討
- 著者
- 梅原 英治
- 出版者
- 大阪経大学会
- 雑誌
- 大阪経大論集 (ISSN:04747909)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.2, pp.253, 2018 (Released:2019-03-06)
31 0 0 0 OA サンスクリーンの長期使用効果
- 著者
- 水野 誠
- 出版者
- 日本香粧品学会
- 雑誌
- 日本香粧品学会誌 (ISSN:18802532)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.2, pp.113-118, 2017-06-30 (Released:2018-06-30)
- 参考文献数
- 37
Continuous use of sunscreen products prevents not only sunburn or suntan, but also signs of photo-aging such as wrinkles or pigmentation spots. In the U.S., sunscreen products are categorized as over-the-counter drugs. If certain conditions are fulfilled, statements on the preventive efficacies against skin cancer and early skin aging are allowed on the package insert. The EU commission also stated “sunscreen products can prevent the damage linked to photo-ageing.” Application of sunscreens is strongly recommended for the prevention of photo-aging or skin cancer in these countries. However, statements on the preventive effects of sunscreen cosmetics against photo-aging or skin cancer are not approved in Japan because their efficacies in Japanese people are unclear because of the lack of reliable data. This article reviews the studies that demonstrated the preventive effects of continuous application of sunscreens on photo-aging, and also describes our three-year study on sunscreen application for Japanese elderly subjects, which is probably the first long-term, interventional, clinical study conducted in Japanese people. The results of our clinical study showed that continuous application of the appropriate amount of sunscreen prevents photo-aging signs such as a change in skin color tone uniformity, similar to that seen in Caucasians. Our study investigating the relationship between efficacy and the amount of sunscreen applied, in order to examine the appropriate use of sunscreens to achieve a sufficient effect, is also introduced here.
31 0 0 0 OA 偏見と差別について
- 著者
- なだ いなだ
- 出版者
- 社団法人 日本リハビリテーション医学会
- 雑誌
- リハビリテーション医学 (ISSN:0034351X)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.1, pp.43-45, 1986-01-18 (Released:2009-10-28)
- 著者
- Atsushi Mizuno Jeffrey Rewley Takuya Kishi Chisa Matsumoto Yuki Sahashi Mari Ishida Shoji Sanada Memori Fukuda Tadafumi Sugimoto Miki Hirano Koichi Node
- 出版者
- The Japanese Circulation Society
- 雑誌
- Circulation Reports (ISSN:24340790)
- 巻号頁・発行日
- pp.CR-21-0063, (Released:2021-06-30)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 6
Background:The relationship between Twitter ambassadors and retweets has not been fully evaluated for “tweet the meeting” activity.Methods and Results:We collected data on the number of tweets and retweets during the Japanese Circulation Society’s (JCS) annual meetings in 2019, 2020, and 2021. After adjustment, JCS Twitter Ambassadors, selected by the JCS to increase the meeting’s visibility, increased the total number of retweets by 9%.Conclusions:This is the first report on the numerical relationship between JCS Twitter Ambassadors and the total number of retweets during an annual congress. Original tweets by JCS Twitter Ambassadors increased the number of retweets, but retweets by influencers were more effective at stimulating social media engagement.
31 0 0 0 OA 日本近海の海水温変動と北半球気候変動との共時性
- 著者
- 小泉 格 坂本 竜彦
- 出版者
- 公益社団法人 東京地学協会
- 雑誌
- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)
- 巻号頁・発行日
- vol.119, no.3, pp.489-509, 2010-06-25 (Released:2010-08-30)
- 参考文献数
- 113
- 被引用文献数
- 7 8
Annual sea-surface temperatures (SSTs) (°C) were derived from a regression analysis between the ratio of warm- and cold-water diatoms (Td' ratio) in 123 surface sediment samples around the Japanese Islands and measured mean annual SSTs (°C) at the core sites. The cross spectra between the atmospheric residual 14C (‰), and annual SSTs (°C) of cores DGC-6 (Japan Sea) and MD01-2421 (off Kashima), respectively, consist of five dominant periods: 6000, 2400, 1600, 950, and 700 years. The amplitude of fluctuations of annual SSTs (°C) in the millennial time scale during the Holocene after the Younger Dryas is within 6-10°C. Periodic variations of annual SSTs (°C) can be correlated within error to abrupt climatic events reported from different paleoclimatic proxy records in many regions of the Northern Hemisphere. The cooling time of annual SSTs (°C) also corresponds to the triple events of high 14C values in the atmospheric residual 14C records, as well as the Bond events in the North Atlantic.
31 0 0 0 OA 隣接領域との競争と共創が促す統計学の力強い発展
- 著者
- 樋口 知之
- 出版者
- 一般社団法人 日本統計学会
- 雑誌
- 日本統計学会誌 (ISSN:03895602)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.2, pp.213-244, 2022-03-03 (Released:2022-03-10)
- 参考文献数
- 78
2012年,一般物体認識の精度を競う国際コンテストILSVRC (ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge) で,他のチームがエラー率26%前後のところ,トロント大学チームが深層学習によりエラー率17%弱とダントツの認識率を示した.また,オバマ政権がビッグデータ研究開発のための戦略プラン(通称,ビッグデータイニシアティブ)を発表したのも2012年である.よって2012年は,第三次AI ブームの起点と断言できる.現在,それからまだ10年しかたっていない.特にこの数年間のデータ分析手法の著しい発展は,学生の頃から統計的データ分析を実際に携わっていた私にとって最大の衝撃である.本稿では,1980年代から統計学および周辺分野の研究に関わってきたあくまでも“私の視点”から,この40年間の統計学の発展を振り返る.前半は自伝的内容が中心であるが,今後の統計学にかかわる人材育成のヒントがもしあれば,筆者としては望外の喜びである.後半は,私がこだわってきた帰納推論と演繹推論の統合の一実現形である,データ同化および深層学習について概説する.本稿が,今後の統計学の動向を考える上で少しでも参考になることを期待してやまない.