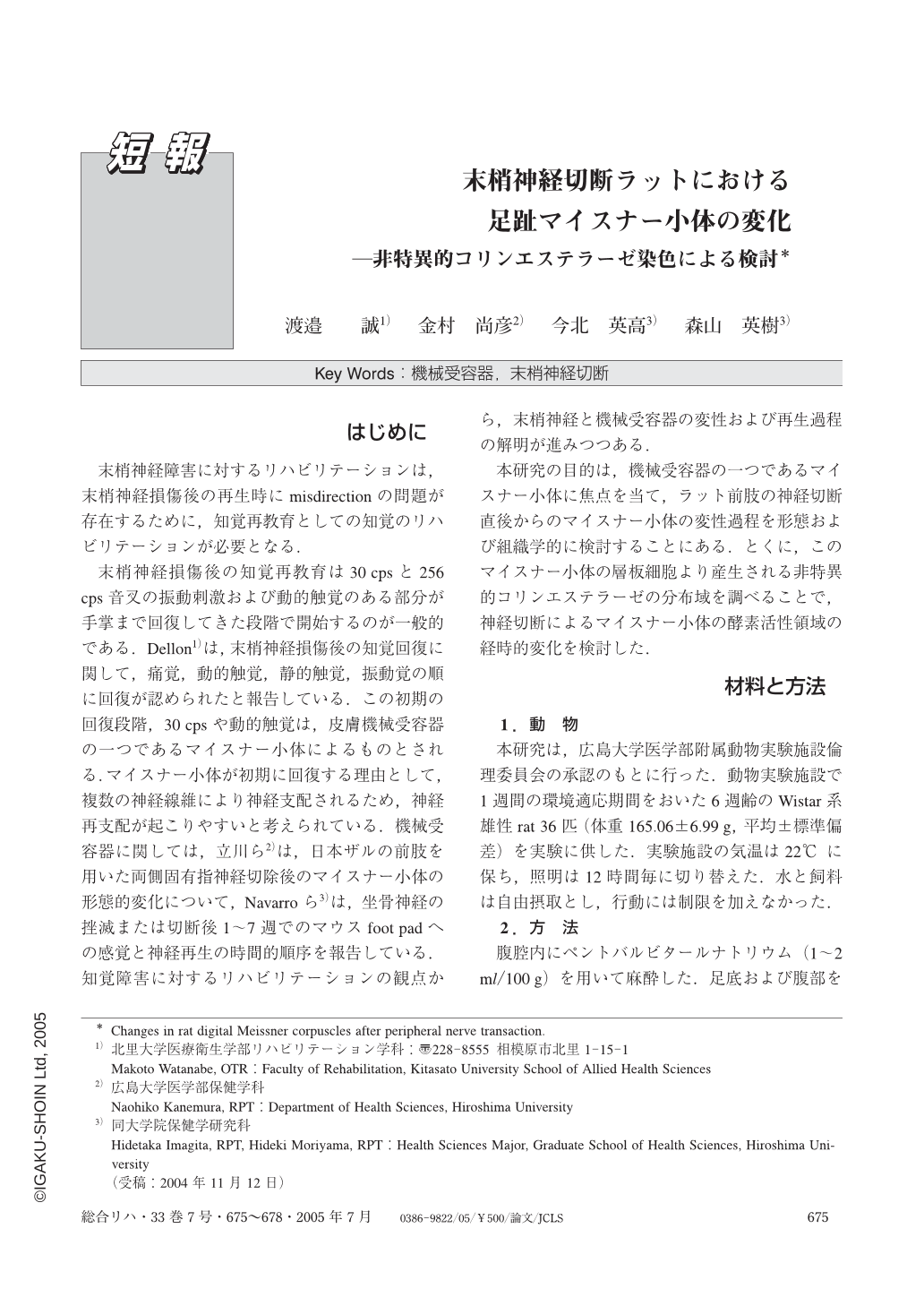- 著者
- 上田 匠 Zhdanov Michael S.
- 出版者
- 社団法人 物理探査学会
- 雑誌
- 物理探査 (ISSN:09127984)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.3, pp.295-306, 2009-06-01
- 参考文献数
- 31
- 被引用文献数
- 1
 本論文では,近年海洋石油ガス探査に利用されている海洋人工(制御)電流(信号)源電磁探査 (Marine CSEM, MCSEM) 法の逆解析へのTikhonov正則化 (regularization) と電磁 (EM) マイグレーションの適用について詳細に検討した。MCSEM法データの3次元解析は,取得データ量の増加や解析領域の複雑化による計算コスト上昇のために非常に困難な数値計算問題の一つとなっている。<br>  この問題に対処するために,本稿では電磁マイグレーションによってヤコビアン行列を計算するTikhonov正則化法の適用を試みた。また,より安定した解を得るために正則化逆解析の解法として共役勾配法を採用した。さらに反復計算における順解析部分には,高速化のために多重格子準線形 (Multigrid Quasi-Linear, MGQL) 近似 (Ueda and Zhdanov, 2006) を使用した。本稿で開発した手法を,海底下の3次元高比抵抗異常領域を想定した数値モデルを用いて検証した。その結果, MCSEM法データの解釈へ適用可能なことがわかった。<br>
1 0 0 0 近代日本の公衆衛生・労働衛生思想における体力観
- 著者
- 瀧澤 利行
- 出版者
- 日本スポーツ社会学会
- 雑誌
- スポーツ社会学研究 (ISSN:09192751)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.1, pp.15-30, 2009
体力の概念は、前近代日本の健康思想の展開においては決して一般的ではなかった。明治維新以前の日本においては、養生が健康の維持と寿命の延長に関わる基本的な思想であった。 養生は、東洋文化における生命の賦活と日常生活における摂生のための思想である。日本においても、 江戸時代(1603-1867)の間、養生論の刊行は次第に増加していった。<br> 明治新政府は、個人の健康維持に関わる概念として養生に代わって衛生を採用した。明治前半期の衛生思想の下では、「体力」は人々がどの程度働くことができたかを示す概念としてみなされていた。明治後半期になると養生や衛生の本質は、社会や国家の事項を包含すべく敷衍されていった。 伊東重は、『養生哲学』と題された著書を刊行し、その著書において、政府が「国家の養生」を実施すべきであると主張した。また、衛生局長を務めた後藤新平は、彼の主著である『国家衛生原理』において、富国強兵のための健康管理と衛生行政の理論を創出した。後藤や伊東に代表される明治期の衛生思想の基本原理は、主として社会ダーウィニズムと社会進化論に基づいていた。この理論の下では、個人の健康は国家経済の発展と軍事力の増大に関連するとみなされたのである。<br> 他方では、国民総体の健康について考えるという視点は、彼らの健康水準を平等化することを目的とした社会衛生思想を受容する契機となった。社会衛生学・労働科学の先駆者であった暉峻義等は、産業国家の発展の立場から、労働者における体力を充実させる必要性を指摘した。その暉峻は第2次世界大戦の下では、労働者が国家における人的資源であることを認識し、また、労働の体力は日本の軍事力そのものであると主張した。このように、社会衛生の理論は、次第に人間の健康を国家の資本として見なす側面を含んでいった。<br> 日本における社会衛生から公衆衛生への主潮の変化は、予防医学と健康教育に重点を置いていたアメリカ合衆国の公衆衛生政策の影響を受けた。それは次第に国際的な公衆衛生運動としてのヘルスプロモーション運動に展開していった。その過程で、体力の問題は、生活習慣病の予防と個人的な活動的な生活の文脈に向かって個人化されてきた。 そのような状況の下では、体力の社会的かつ文化的な側面から再考することが不可欠である。
- 著者
- 竹内 幹太郎 阿部 宏史 氏原 岳人 金野 裕一
- 出版者
- 公益社団法人 日本都市計画学会
- 雑誌
- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.3, pp.1039-1044, 2012-10-25 (Released:2012-10-25)
- 参考文献数
- 7
産業集積などの衰退により都市内部で発生しているエリアレベルの低・未利用地(例えば、空き工場群など)において、新たな店舗集積の形成を検討する際に有用な情報を提供するため、本研究では、用途転換の取り組みにより空き倉庫・事務所群を活用した新たな店舗集積が形成されている岡山市北区問屋町の卸商業団地を事例に、その特性を来訪者へのアンケート調査結果を用いて分析した。具体的には、まず、どのような来訪者が問屋町内の出店店舗にとって利点となる行動をするのかその関係性を分析した。そして、問屋町における出店店舗にとって利点となる行動の発生には、来訪者の"居住地"や"同伴者"の要素が総体的に関係しているとわかった。次に、既存店舗集積と比較して、問屋町が店舗集積としてどのように評価されているのかを分析した。その結果、問屋町は、中心市街地と郊外ショッピングセンターそれぞれにおける店舗集積としての"不足部分(自動車の交通利便性や店舗の魅力など)"を、同時に特長として有することで、都市内部における新たな店舗集積としての位置づけを見出していると考えられることが明らかになった。
1 0 0 0 世界における日本の海難:-安全文化はいかに伝播するか-
- 著者
- 種市 雅彦
- 出版者
- 公益社団法人 日本航海学会
- 雑誌
- 日本航海学会誌 NAVIGATION (ISSN:09199985)
- 巻号頁・発行日
- vol.196, pp.89-98, 2016
1 0 0 0 OA 小児慢性便秘症に対するプロバイオティクスの投与効果
- 著者
- 田附 裕子 前田 貢作 和佐 勝史 飯干 泰彦 藤元 治朗
- 出版者
- 日本静脈経腸栄養学会
- 雑誌
- 静脈経腸栄養 (ISSN:13444980)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.4, pp.929-934, 2010 (Released:2010-08-25)
- 参考文献数
- 29
- 被引用文献数
- 2
小児外科外来では、ヒルシュスプルング病・類縁疾患などとの鑑別を含め慢性便秘症の症例に多く遭遇する。基礎疾患が除外された慢性便秘症の多くは生活習慣による機能性便秘であり、排便習慣が確立するまでの根気強いフォローが必要となる。近年、予防医学の観点からプロバイオティクスの効果が報告されている。小児の慢性便秘に対してもプロバイオティクスの臨床的な投与効果が期待される。
はじめに 末梢神経障害に対するリハビリテーションは,末梢神経損傷後の再生時にmisdirectionの問題が存在するために,知覚再教育としての知覚のリハビリテーションが必要となる. 末梢神経損傷後の知覚再教育は30 cpsと256 cps音叉の振動刺激および動的触覚のある部分が手掌まで回復してきた段階で開始するのが一般的である.Dellon1)は,末梢神経損傷後の知覚回復に関して,痛覚,動的触覚,静的触覚,振動覚の順に回復が認められたと報告している.この初期の回復段階,30 cpsや動的触覚は,皮膚機械受容器の一つであるマイスナー小体によるものとされる.マイスナー小体が初期に回復する理由として,複数の神経線維により神経支配されるため,神経再支配が起こりやすいと考えられている.機械受容器に関しては,立川ら2)は,日本ザルの前肢を用いた両側固有指神経切除後のマイスナー小体の形態的変化について,Navarroら3)は,坐骨神経の挫滅または切断後1~7週でのマウスfoot padへの感覚と神経再生の時間的順序を報告している.知覚障害に対するリハビリテーションの観点から,末梢神経と機械受容器の変性および再生過程の解明が進みつつある. 本研究の目的は,機械受容器の一つであるマイスナー小体に焦点を当て,ラット前肢の神経切断直後からのマイスナー小体の変性過程を形態および組織学的に検討することにある.とくに,このマイスナー小体の層板細胞より産生される非特異的コリンエステラーゼの分布域を調べることで,神経切断によるマイスナー小体の酵素活性領域の経時的変化を検討した.
1 0 0 0 OA 縦隔内甲状腺腫を合併した巨大胸腺脂肪腫の1例
- 著者
- 坂口 昌幸 新宮 聖士 春日 好雄 小林 信や 天野 純 保坂 典子 野村 節夫
- 出版者
- Japan Surgical Association
- 雑誌
- 日本臨床外科学会雑誌 (ISSN:13452843)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.12, pp.3021-3026, 1998-12-25 (Released:2009-01-22)
- 参考文献数
- 52
症例は45歳女性.検診で前頸部腫瘤を指摘され,縦隔内甲状腺腫と診断された.この時に胸部X線で右横隔膜の挙上を指摘され, CT, MRIにて右肺下面と横隔膜との間に巨大な腫瘤を認め,右肺中葉を圧排していた. CT値より脂肪腫,胸腺脂肪腫が疑われた.これらの腫瘍を摘出した.縦隔内甲状腺腫は256g,縦隔内巨大腫瘤は2,000gで,病理組織学的にはそれぞれ腺腫様甲状腺腫,胸腺脂肪腫と診断された.縦隔内甲状腺腫を合併した胸腺脂肪腫は極めて稀で,われわれが検索しえた限りでは,本症例1例のみであった.
1 0 0 0 OA 腸内細菌からのメッセージ 短鎖脂肪酸の生理的役割
- 著者
- 坂田 隆
- 出版者
- 公益社団法人 日本農芸化学会
- 雑誌
- 化学と生物 (ISSN:0453073X)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.1, pp.23-31, 1994-01-25 (Released:2009-05-25)
- 参考文献数
- 22
- 被引用文献数
- 2 1
1 0 0 0 テスト項目作成時のテストベース理解戦略の分析
- 著者
- 佐々木 方規 森崎 修司
- 雑誌
- 研究報告ソフトウェア工学(SE) (ISSN:21888825)
- 巻号頁・発行日
- vol.2021-SE-207, no.38, pp.1-6, 2021-02-22
受け入れテストやシステムテストは,開発担当者のチームから独立した組織で実施されることが多い.テスト担当者は開発担当者とは異なる背景,技術的視点,マインドセットを持つため,開発担当者とは異なる種類の欠陥を検出できる.一方で,ソフトウェアの内部構造や振る舞いに関して知見が無い状態でテストベースの理解を深めなければならないことも多い.テストのエキスパートは,仕様書に記述された内容以外のソフトウェアの利用シーンや環境などからテストベースの理解を進めるが,その理解戦略は明らかになっていない.そこで,豊富なテスト知識を有する 3 名のエキスパートが与えられたテストベースをどのような戦略で理解しているかを分析する.
1 0 0 0 IR 展示室で写真が撮りたい!-博物館展示室での写真撮影対応に関する現状整理―
- 著者
- 千葉 毅
- 出版者
- 考古形態測定学研究会
- 雑誌
- 考古学・文化財のためのデータサイエンス・サロン : 考古学・文化財のためのデータサイエンス・サロンonline予稿集#5
- 巻号頁・発行日
- no.15, pp.28-38, 2020-12-31
1 0 0 0 OA 日本の援助の源流に関する歴史比較制度分析
- 著者
- 下村 恭民
- 出版者
- 国際開発学会
- 雑誌
- 国際開発研究 (ISSN:13423045)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.1, pp.117-131, 2014-06-15 (Released:2019-09-27)
- 参考文献数
- 62
The objective of this article is to give a fresh insight into the origin of Japan's aid. More specifically, it attempts to analyze why Japan intended to start aid giving in the early post-war era, in spite of its devastated economy and very low per capita GNP, which was much lower than Malaya. While existing literatures argue that Japan's aid began out of joining the Colombo Plan or war reparations, this article stresses the role of widely shared policy thinking as the engine of the pursuit of aid giving; the policy makers in those days put emphasis on trade and development cooperation with South East Asia. The article attempts to explore the reason why this policy thinking was prevalent among the policy makers in those days, using Avner Greif's theory of comparative and historical institutional analysis. It was found that the widely shared cognition model was closely related to their experiences during the war era. The emphasis on the trade with South East Asia was inherited from the past, as the natural resources of South East Asia was crucial in the war era; a typical case of path dependence is observed. On the other hand, the idea of development cooperation, paying due attention to job creation and raising living standard was new, as the war-time policy objective had been narrowly scoped and concentrated on securing resources. The article confirms that a lot of policy makers had regarded it neither advisable nor sustainable, and they introduced a new approach when they got the drivers' seets; this is the case of Greif's endogenous institutional change. The case of Japan implies that the motive of a new donor is embedded in their own socio-economic system.
1 0 0 0 OA 2次推進系
- 著者
- 斎藤 紀男
- 出版者
- 公益社団法人 計測自動制御学会
- 雑誌
- 計測と制御 (ISSN:04534662)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.1, pp.123-128, 1984-01-10 (Released:2009-11-26)
1 0 0 0 教師の発言 : 国語教育・今日の問題
- 著者
- 岩船 昌起
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 日本地理学会発表要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.2011, pp.100153, 2011
新燃岳(1,421m)は,霧島屋久国立公園の核心地である「えびの高原」から東南約6?qに位置する。2011年1月以降の火山活動の活発化で立入規制区域が拡大し,3月後半以降では規制が解除されつつある。しかし,噴火時に噴石から身を隠すシェルターがない韓国岳等では登山者の安全が確実に担保されたとは言い難く,入山規制の解除には至っていない。本研究では,噴火活動の推移とそれに対応した危機管理をまずは概観する。そして,えびの高原の諸施設関係者が構築した「自主防災的な避難行動マニュアル」の検証を行い,避難対象者の体力を想定した実験結果を交えてえびの高原での避難行動の時空間的な展開を検討し,新燃岳周辺地域での危機管理を総合的に考察する。<br> 新燃岳の火山活動が活発化した1月26日以降2月半ばまでの危機管理については,火山活動の実態把握に関わる観測網の未整備,新燃岳周辺地域の人々への噴火情報の周知の遅れ,諸機関での「噴火警戒レベル」や「噴火警戒範囲」の理解の不一致などから,噴火活動に応じた危険域を見極めての立入規制等を迅速に実施する対応が十分であったとは言い難かった。一方,噴火活動が見かけ上沈静化してきた3月半ば以降では,規制解除の方向へと動き,鹿児島県等では立入規制区域を半径3km圏内に縮小した。そして,6月1日に県道等の一部の通行規制が解除され,高千穂河原でも昼間の利用が可能になった。しかし,新燃岳に近い韓国岳等への登山では安全対策が不十分であり,噴石等への対策が講じられるまで規制を継続する意向が示されている。<br> そのような中で,えびの高原では,環境省自然保護官事務所を中心に高原内の諸施設が連携して自主防災的に「避難マニュアル」を作成した。これに沿った防災対応は6月29日の噴火時に実施され,噴火後約10分で施設周辺にいた全ての人々を建物内に避難させた。これは,えびの高原の施設関係者等で連携したほぼ「満点」での避難誘導であった。鹿児島県と宮崎県にまたがり,霧島市やえびの市や小林市などに区分される山岳地域という特性から,霧島山では危機管理を統一して実施する難しさがあるが,両県および各市町,国立公園行政を広く管轄する環境省は,密に連携して一つにまとまり,火山地域の安全体制を構築する必要がある。<br> 当日は,避難対象者の体力を想定した避難行動に関わる実験結果なども交えて総合的に考察します。
1 0 0 0 正倉院南倉の銀壺について
- 著者
- 吉澤 悟
- 出版者
- 宮内庁正倉院事務所
- 雑誌
- 正倉院紀要 = Bulletin of Office of the Shosoin Treasure House (ISSN:13431137)
- 巻号頁・発行日
- no.39, pp.1-26, 2017-03
1 0 0 0 新たな外科専門医制度について
- 著者
- 松田 暉
- 出版者
- 一般社団法人日本外科学会
- 雑誌
- 日本外科学会雑誌 (ISSN:03014894)
- 巻号頁・発行日
- vol.104, no.3, pp.285-289, 2003-03-01
- 参考文献数
- 5
- 被引用文献数
- 2
1 0 0 0 OA 電波監理委員会の意義・教訓
- 著者
- 原田祐樹
- 出版者
- 総務省
- 雑誌
- 情報通信政策レビュー
- 巻号頁・発行日
- no.2, 2011-01-31
1 0 0 0 卒後臨床研修必須化と外科研修の問題点
- 著者
- 松田 暉
- 出版者
- 一般社団法人日本外科学会
- 雑誌
- 日本外科学会雑誌 (ISSN:03014894)
- 巻号頁・発行日
- vol.104, no.4, pp.341-344, 2003-04-01
- 参考文献数
- 4
- 被引用文献数
- 2