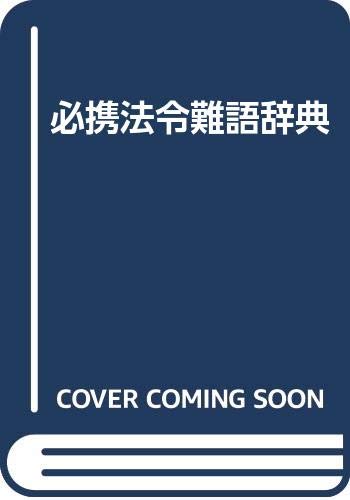1 0 0 0 必携法令難語辞典
- 著者
- 浅野一郎 田島信威 岩崎隆二編
- 出版者
- 三省堂
- 巻号頁・発行日
- 2003
1 0 0 0 高次脳機能障がい者の認知機能向上を目的としたグループ運動の実践
- 著者
- 野々村 和子
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement
- 巻号頁・発行日
- vol.2015, 2016
【はじめに,目的】大阪市長居障がい者スポーツセンターでは,平成19年より高次脳機能障がいに特化したグループ運動を行っている。発症から1年以上経過する在宅生活者である。高次脳機能障がいの症状が表出するため,当事者・家族・周囲の人たちが戸惑い,医療機関や施設から当センターへ紹介されるケースが多い。もともと運動好きである,在宅では易疲労性,発動性が低く何とか運動して活動性を上げてほしいという家族の願いもあって来館されるケースが多い。運動を継続することによって,脳の血流量が増加し,認知機能にも関わっている事が明らかになってきている。高次脳機能障がい者の認知機能向上を目的に,グループ運動を実践し,認知機能面での変化について考察を加えて報告する。【方法】高次脳機能障がい者11名,66歳~27歳平均年齢47.5歳,脳卒中の後遺症,事故による外傷性脳損傷者を対象として,1回90分週1回12週,グループでの認知機能向上運動プログラム実践する。運動の内容は,①準備体操 ②スクエアステップエクササイズ(注意力・記憶力向上の目的)③フライングディスク(集中力・持続力向上の目的)④フロアホッケー(技術やルールの記憶・ゲームに参加する遂行機能・周囲への配慮,周囲への注意力・協調性向上の目的)運動介入前後に,認知機能検査MMSE,注意力検査TMT-A TMT-Bでの評価を行った。【結果】運動介入前後の認知機能検査MMSEでは,11名中5名までが全体的な点数の増加があった。MMSEの項目の中で,時間,場所の見当識・計算・短期記憶の改善がみられた。注意力検査TMT-A TMT-Bでも11名中6名までが反応の速さに向上がみられた。【結論】身体運動による認知機能へのアクセスできる研究成果が次々に伝えられている。脳損傷後の運動は,損傷を逃れた脳部位に可塑的な変化を生じ,失われた運動を取り戻すために新たなネットワークが形成することが知られている。これは,運動の効果が末梢の運動機能回復にとどまらず中枢神経システム再構築まで貢献できることを示唆している。本研究も一定の期間運動を継続することによって,認知機能面での変化がみられた。グループ運動介入する前は,固い表情や覚醒レベルが低い,注意が転導して落ち着かない,人の話に集中できない,他者の発言中に自分の意見を発言するなど高次脳機能障がいの症状が表出される場合があったが,運動を実践することで,表情や感情が安定し活動性の向上,周囲への配慮,反応の改善へとつながる場合があった。日常生活での変化は,長期間必要とされ今後の課題と考えられる。
1 0 0 0 IR 奨励賞論文 認知症介護予防モデル事業の紹介と成果について
- 著者
- 田平 隆行 榊原 淳 沖 英一 田中 浩二
- 出版者
- 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科保健学専攻
- 雑誌
- 保健学研究 (ISSN:18814441)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.2, pp.19-24, 2008
- 被引用文献数
- 2
本稿では,長崎市における特定高齢者施策「うつ・閉じこもり・認知症予防事業」の開始へ向けた認知症介護予防モデル事業の紹介と介入成果について報告する.対象は,軽度認知症及びその疑い者82名の内,事業参加が5/9回以上の52名を有効対象者とした.開催頻度は,2回/1月(隔週),事業回数は,評価2回,介入7回の計9回とした.プログラム内容は,学習療法,拮抗体操・記憶ゲーム等を用いたレクリエーション療法,創作活動とした.その結果,注意配分機能,短期記憶の認知機能と自己効力感が向上した.認知症の早期に障害される注意配分機能や短期記憶に視点をおいたプログラムや達成感や有能感を得るような活動を実施することが重要であることが示唆された.
1 0 0 0 OA 経口摂取したメラミンおよびシアヌル酸の相互作用による急性毒性
- 著者
- 井上 達志 菰田 俊一 千葉 絵理
- 出版者
- 日本毒性学会
- 雑誌
- 日本トキシコロジー学会学術年会 第36回日本トキシコロジー学会学術年会
- 巻号頁・発行日
- pp.3022, 2009 (Released:2009-07-17)
メラミンおよびシアヌル酸は単独では毒性は低いが、両者が体内に同時に存在すると毒性が高くなる可能性がある。そこで、マウスにメラミン(M)およびシアヌル酸(C)の単独、等量交互、等量混合の経口連続強制投与試験を行い、メラミンとシアヌル酸の相互作用による急性毒性について検討した。 C3N/HeNマウス20頭を対照区、M単独区、C単独区、MC交互区およびMC混合区に分け(n=4)代謝装置内で単飼した。それぞれの日投与量はいずれの区も合計12mg(300mg/kgbw)を生食1.2mlに懸濁させ(対照区は生食のみ)、11時から2時間おきに4回に分け7日間連続行った。これらの投与前後の2時間は絶食絶水とした。摂水量と排尿量は対照区、M単独区およびC単独区では大差なかったが、MC混合区では対照区の約2倍量となり(p<0.05)、MC交互区では1日後の量は多かったものの、その後急激に低下し4日後ではほぼ尿閉となった。また、MC交互区および混合区では腎重量が対照区、M単独区およびC単独区に比べ有意に重く(p<0.05)、BUNでは405mg/dlと、MC混合区の147 mg/dlあるいは正常範囲以内の他区に比べて上昇していた(p<0.01)。同様にCREではMC交互区が2.60 mg/dl、MC混合区が1.08 mg/dlと他区に比べて高く(p<0.01)、これらの区においては腎不全が示唆された。肝重量では全区とも大差なかったが、GOTはMC交互区では181U/Lと他区に比べ軽度の上昇が見られた(p<0.05)。また、腎組織像では、M単独区およびC単独区では正常であったが、MC交互区およびMC混合区では組織の壊死が認められ、MC混合区ではより高度であった。さらに、これらの区では組織内に茶褐色のメラミンシアヌレートと考えられる結晶の散在が認められ、これらは蛍光顕微鏡下では緑色蛍光として観察された。
1 0 0 0 IR Feminist pedagogyの視点から考えるCollaborative learning : bell hooksとPatti LatherのFeminist pedagogiesを中心に
- 著者
- 友野 清文
- 出版者
- 昭和女子大学近代文化研究所
- 雑誌
- 学苑 (ISSN:13480103)
- 巻号頁・発行日
- no.912, pp.1-14, 2016-10
1 0 0 0 OA ウマは同齢の同種他個体に視覚的選好を示すか 類似性の原則に着目した実験的検討
- 著者
- 鎌谷 美希 瀧本-猪瀬 彩加
- 出版者
- 北海道心理学会
- 雑誌
- 北海道心理学研究 (ISSN:09182756)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, pp.1-15, 2021-03-31 (Released:2021-03-31)
- 参考文献数
- 33
ヒトを含む社会的動物は,同種他個体と親密で永続的な関係(以下,社会的絆)を築く。この社会的絆を強く築く個体は繁殖において有利であることが報告されてきている(e.g., Cameron, Setsaas & Linklater, 2009)。また,de Waal & Luttrell(1986)では,個体は自分と類似した集団内の他個体を親和的な相互作用の相手として選び,社会的絆を形成し始める可能性が示唆されている。実際,ウマ(Equus caballus)においてはより年齢の近い個体間で強い社会的絆が築かれる(ワイルズ,2019)。しかし,ウマが他個体と相互作用をする前に,似た年齢の個体を選好しているかどうかは明らかになっていない。本研究では,ウマが,年齢の異なる未知のウマの顔写真(幼若・同齢・老齢)を単呈示された時に,同年齢の同種他個体に対して視覚的選好を示すかどうかを検討した。その結果,写真のウマの年齢は参加個体の刺激に対する注視行動・接近行動・接触行動に影響しなかった。これらの結果は,ウマは相互作用をする前に,その顔写真に対して同齢他個体への視覚的選好を示さないことを示唆している。
- 著者
- 木元 一広 Kimoto Kazuhiro
- 出版者
- 宇宙航空研究開発機構(JAXA)
- 雑誌
- 宇宙航空研究開発機構研究開発報告 = JAXA Research and Development Report (ISSN:13491113)
- 巻号頁・発行日
- vol.JAXA-RR-15-003, pp.1-15, 2015-12-15
Redmineはさまざまな業務に利用できる優れたチケット管理システムで,近年注目されているOSSの一つである.JAXA スーパーコンピュータ活用課では,2014年のJSS2 SORAスーパーコンピュータ導入を機にRedmineをベースにしたCODAシステムを構築・運用している.本稿では,Redmineの利用事例としてCODAを紹介する.合わせて,Redmineを一層効果的に活用するため,CODAの構築・運用経験から見いだされた定義や設定,運用の工夫を紹介する.
1 0 0 0 OA 教員の職務環境の変化と教師教育の課題 生徒指導をめぐる状況を中心に
- 著者
- 新井 肇
- 出版者
- 日本学校教育学会
- 雑誌
- 学校教育研究 (ISSN:09139427)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, pp.57-69, 2014-08-08 (Released:2017-07-28)
1 0 0 0 IR ステップファミリーにおける親子関係に関する研究 : 子どもの視点からの検討
- 著者
- 勝見 吉彰
- 出版者
- 県立広島大学
- 雑誌
- 人間と科学 : 県立広島大学保健福祉学部誌 (ISSN:13463217)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.1, pp.129-136, 2014-03
ステップファミリーでの生活経験のある青年期女性2名との面接結果を提示し,ステップファミリーにおける親子関係のあり方について,子どもの視点からの検討を行った。提示された2事例では,再婚により新しい関係が始まった時点から,継親との関係は対照的に展開していった。1例目は継父との関係を築くことには消極的で,継父を" 単なる同居人" としか見ていないこと,2例目では継父との関係は初めから肯定的であり,自分の親として認知していることが明らかとなった。いずれの事例においても別れた実親への思いが整理されないままであり,子どもの心の成長という点から,別れた実親をめぐる体験についても家族間で整理される必要性が検討された。親の再婚後に生ずる同居する親との関係の変化に注目することの重要性が指摘された。資料
1 0 0 0 OA 中学校の運動部活動顧問の指導に対する主観的負担感と担当教科ならびに専門競技との関連
- 著者
- 長野 康平 中村 和彦
- 出版者
- 日本スポーツ教育学会
- 雑誌
- スポーツ教育学研究 (ISSN:09118845)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.2, pp.77-87, 2020-12-31 (Released:2021-03-31)
- 参考文献数
- 19
Background: Regarding the burden of teachers in school athletic club activities, it is often argued that it is a burden because time of school athletic club activities related to working hours is long. However, factors related to the perceived burden of school athletic club activities have not been considered. The purpose of this study was the following three. 1) To clarify the rate of complaints about the perceived burden of teaching school athletic club activities among junior high school teachers in Yamanashi Prefecture. 2) To examine the relationship between teaching specialized competition and perceived burden. 3) To examine the relationship between the subject and the teaching specialized competition with the perceived burden.Method: We got data from 1,068 teachers who teaching school athletic club activities at junior high school in Yamanashi prefecture. Using a logistic regression analysis, we investigated a complex relationship between subject, involvement in specialized competition, and a perceived burden for teaching of school athletic club activities.Result: The accused rate of perceived burden to the teaching of school athletic club activities was 72.3%,21.3% of which had a sense of burden of high intensity. Odds ratio which has perceived burden so much that it is not involved in own specialized competition was high. Participation in the subject and specialized competitions was combined with complaints of perceived burden.
- 出版者
- 日本アプライド・セラピューティクス(実践薬物治療)学会
- 雑誌
- アプライド・セラピューティクス (ISSN:18844278)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.1, pp.4-8, 2010 (Released:2021-03-31)
1 0 0 0 OA あらためて考える日常診療とEBM Pros:「日常診療にはEBMが大切である」
- 出版者
- 日本アプライド・セラピューティクス(実践薬物治療)学会
- 雑誌
- アプライド・セラピューティクス (ISSN:18844278)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.1, pp.54-58, 2011 (Released:2021-03-31)
- 出版者
- 日本アプライド・セラピューティクス(実践薬物治療)学会
- 雑誌
- アプライド・セラピューティクス (ISSN:18844278)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.1, pp.59-62, 2011 (Released:2021-03-31)
- 著者
- Masatoki Nakaza Mitsuo Matsumoto Tetsuro Sekine Tatsuya Inoue Takahiro Ando Masashi Ogawa Makoto Obara Olgierd Leonowicz Shinichiro Kumita Jitsuo Usuda
- 出版者
- Japanese Society for Magnetic Resonance in Medicine
- 雑誌
- Magnetic Resonance in Medical Sciences (ISSN:13473182)
- 巻号頁・発行日
- pp.mp.2020-0170, (Released:2021-03-31)
- 参考文献数
- 40
- 被引用文献数
- 19
Purpose: The purpose of the current study was to clarify the blood flow pattern in the left atrium (LA), potentially causing the formation of thrombosis after left upper lobectomy (LUL). The blood flow in the LA was evaluated and compared between LUL patients with and without thrombosis. For the evaluation, we applied highly accelerated 4D flow MRI with dual-velocity encoding (VENC) scheme, which was expected to be able to capture slow flow components in the LA accurately.Methods: Eight volunteers and 18 patients subjected to LUL underwent dual-VENC 4D Flow MRI. Eight patients had a history of thrombosis. We measured the blood flow velocity and stasis ratio (proportion in the volume that did not exceed 10 cm/s in any cardiac phase) in the LA and left superior pulmonary vein (LSPV) stump. For visual assessment, the presence of each collision of the blood flow from pulmonary veins and vortex flow in the LA were evaluated. Each acquired value was compared between healthy participants and LUL patients, and in LUL patients with and without thrombosis.Results: In LUL patients, blood flow velocity near the inflow part of the left superior pulmonary vein (Lt Upp) and mean velocity in the LA were lower, and stasis ratio in the LA was higher compared with healthy volunteers (Lt Upp 9.10 ± 3.09 vs.13.23 ± 14.19 cm/s, mean velocity in the LA 9.81 ± 2.49 vs. 11.40 ± 1.15 cm/s, and stasis ratio 25.28 ± 18.64 vs. 4.71 ± 3.03%, P = 0.008, 0.037, and < 0.001). There was no significant difference in any quantification values between LUL patients with and without thrombosis. For visual assessment, the thrombus formation was associated with no collision pattern (62.5% vs. 10%, P = 0.019) and not with vortex flow pattern (50% vs. 30%, P = 0.751).Conclusion: The net blood flow velocity was not associated with the thrombus formation. In contrast, a specific blood flow pattern, the absence of blood flow collision from pulmonary veins, correlates to the thrombus formation in the LA.
- 著者
- 松尾 賢司 高木 幸一 小池 淳 松本 修一
- 出版者
- 一般社団法人 映像情報メディア学会
- 雑誌
- 映像情報メディア学会技術報告 (ISSN:13426893)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, pp.13-18, 2002
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 4
MPEG-4のFGSは,可変ビットスケーラビリティを実現し,ネットワーク上での帯域変動に対して高い適応力を持った動画像伝送を可能とする.しかし,FGSで用いられるビットプレーン符号化方法は,下位プレーンにおいて符号化効率が低下するという問題があった.そこで本稿では,ビットプレーン符号化の効率を改善する方法を提案する.まず,有意係数の分布に基づいてDCT係数の各ビットを有意ビット群と既有意ビット群に分類する.次に,それぞれのビット群に対して最適な効率を実現する符号化方法を適用する.この際,符号化の順序は,復号画像の品質を向上させる度合いの高い情報から順番に行う.本提案方式により符号化効率は改善され,復号画像品質はFGSと比較して0.2dB程度向上する.
1 0 0 0 OA 哀れな男たち : 一人二役で演じられるダーリング氏とフック船長
- 著者
- 沢辺 裕子 Yuko Sawabe
- 雑誌
- 北海道武蔵女子短期大学紀要 = Memoirs (ISSN:03899586)
- 巻号頁・発行日
- vol.(43), pp.111-143, 2011-03-15
- 著者
- 三木 保
- 出版者
- 日本臨床麻酔学会
- 雑誌
- 日本臨床麻酔学会誌 = The Journal of Japan Society for Clinical Anesthesia (ISSN:02854945)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.3, pp.483-492, 2013-05-15
- 参考文献数
- 12
「東京医大病院 細管誤挿入で脳死状態 50代主婦 胸腔に点滴液たまる」.2003年11月11日の産経新聞の社会面のトップ記事は,東京医科大学病院の全職員を震撼させた.また,これが一連のマスコミを騒がす東京医科大学の医療安全体制の不備の露呈の始まりで,2004年の心臓外科の手術の医療事故(心臓手術で同一医師による4例の死亡例)から主任教授辞任,2005年の特定機能病院指定取り消しと,負のスパイラルへのプロローグになろうとは誰も想像はできなかった.当初これはごく一部の単なる医療事故のように見えた.しかしその本質は組織の単純なミス,油断ではなく,組織全体の虚構の医療安全体制の露呈であった.失った信頼を取り戻すためには,長い時間と多くの努力を要した.今回の東京医科大学病院でのわが国初のCVラインセンターの設置プロジェクトは,まさに真の医療安全文化構築への挑戦であった.
1 0 0 0 IR 安岡正篤の「東洋的な牧民思想」と内務官僚
- 著者
- ブラウン ロジャー H.
- 出版者
- 埼玉大学教養学部
- 雑誌
- 埼玉大学紀要. 教養学部 (ISSN:1349824X)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.1, pp.103-126, 2019
日本政治思想史研究では昭和初期における安岡正篤と内務省のいわゆる「新官僚」との関係が長く重視されてきた。また近年の研究において内務官僚の「牧民官」意識の重要性が認められている。しかし、この官僚の意識と安岡の官治論との関係、そして歴史的意義は明らかにされていない。本稿は、安岡と内務官僚の交流に焦点を当て、当時「東洋的な牧民思想」と呼ばれた安岡の官治論を考察する。この思想は、儒教の徳治主義的観点により政党政治を非難し、日本の国体に相応しい政治とは優れた「官」による国民の教化であるということを唱えたのである。安岡の「東洋思想」におけるこの牧民思想は内務官僚から支持を継続的に受け、戦間期に政党内閣の凋落を促進し、国民精神総動員運動に至った教化総動員運動の一要素になった。したがって、近世の牧民思想に基づいた近代の内務省の「牧民官」意識とそれらを取り入れた安岡の「東洋的な牧民思想」が、近代日本の官僚政治思想の一つの重要な要素であったと言える。
- 著者
- 藤代 裕之
- 出版者
- 一般社団法人 社会情報学会
- 雑誌
- 社会情報学 (ISSN:21872775)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.2, pp.143-157, 2019
<p>本研究は,2018年に行われた沖縄県知事選挙に関するフェイクニュース検証記事を事例に,地方紙である沖縄タイムスのニュース制作過程を,地方紙のニュースバリューである「地域性」,「取材先」,「社内」,「同業他社」をインターネットメディアとの関係性を考慮に入れながら明らかにしたものである。3人の記者の聞き取り調査から,フェイクニュースを取材することで,これまでは異なると考えられていた既存メディアとインターネットメディアのニュースバリューが重なり,インターネットメディアであるバズフィード日本版が「同業他社」として位置づけられたことが分かった。これにより,候補者間で偏りが生じないよう報道するという記者が捉えていた選挙報道のニュース制作過程の公平性の「原則」が揺らぐことになった。また,地理的環境に左右されないインターネットメディアにより,地方紙が重視するニュースバリュー「地域性」に二重性が生じた。これらの変化が,これまでの地方紙のニュースバリューで取材を進める記者に戸惑いを生むことになった。選挙時のフェイクニュース検証記事における課題として,公平性についての議論が必要である。本研究の調査対象者は限られており,フェイクニュース検証記事の制作過程を一般化することは難しいが,フェイクニュース検証というソーシャルメディア時代の新たなニュース制作過程を明らかにしたという点で意義がある。</p>
- 著者
- 岡田 貴憲
- 出版者
- 人間文化研究機構国文学研究資料館
- 雑誌
- 国文学研究資料館調査研究報告 = Report on Investigation and Research (ISSN:02890410)
- 巻号頁・発行日
- no.41, pp.79-126, 2021-03-31