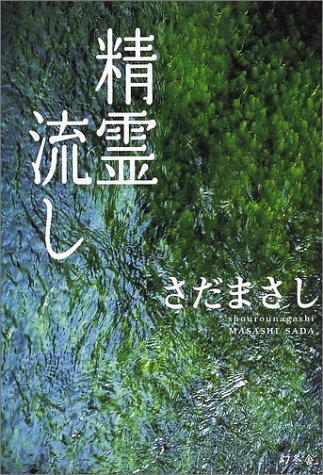1 0 0 0 OA デイヴィッド・ロッジ『交換教授』にみる70 年代文学部の英米比較 学内作家の視点から
- 著者
- 高橋 まりな
- 出版者
- 日英教育学会
- 雑誌
- 日英教育研究フォーラム (ISSN:13431102)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, pp.79-86, 2019 (Released:2020-01-04)
- 参考文献数
- 12
David Lodge (1935-) is an Emeritus Professor of English Literature at the University of Birmingham. Changing Places: A Tale of Two Campuses (1975) is based on his own academic life at Birmingham and experience at the Berkeley as visiting Associate Professor in 1969. The teaching of writing fiction and producing new literature in universities hadn’t been popular in the UK until 70s, but expansion of higher education brought the situation that many writers stayed in university as students or academic staff. Their observations and thoughts at that time still remain in their novels. The purpose of this article is to explore the Lodge’s comparative framework that construct the Changing Places’ imaginary world. Through this case study of interpreting fiction, I tried to identify the limitation of the interpreting fictional text as the data of comparative education. In the first half of this article, I described Lodge as the cultural observer and comparatist. His novel Changing Places has been read as a story that has certain connection with the real world of 1969. The latter is a practical part of an interpretation of fictional text as comparative educational literature. Changing Places is about a story of academic life of the UK and the US. It has two protagonists and both of them are the professors of English. Their universities have an annual professional exchange scheme and they are chosen for this program. The characteristic features of social and vocational life in each country were made amusing by the foreign observer. This study revealed the following two characteristics in Lodge’s comparative strategies. First, he emphasized the cultural differences between the UK and the US, but this story is about a possibility of exchange still. Cultural differences are mentioned as a kind of interruption on the discussion of the educational borrowing, but in this story, remarkable differences aren’t necessarily fatal for exchange. This framework of comparison suggests the reconsideration when we see and try to control the differences. Second, comparisons by Lodge is not fixed by the single binary opposition. Describing people and their culture as the collection of contrasts enable the author to capture the changing world as it is.
1 0 0 0 OA 社会心理学によるデマ・炎上・差別の背景
- 著者
- 三浦麻子
- 出版者
- 国立国会図書館
- 雑誌
- コロナ時代のソーシャルメディアの動向と課題 : 科学技術に関する調査プロジェクト報告書
- 巻号頁・発行日
- 2021-03
- 著者
- 有馬 正和 鄭 瑛 秋山 真哉 船坂 徳子 阪本 信二 水口 博也
- 出版者
- 公益社団法人 日本船舶海洋工学会
- 雑誌
- 日本船舶海洋工学会講演会論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.22, pp.135-136, 2016
1 0 0 0 OA パンタグラフと剛体架線の衝突振動に与える付加系の影響
- 著者
- 西山 直杜 山下 清隆
- 出版者
- 一般社団法人 日本機械学会
- 雑誌
- 日本機械学会論文集 (ISSN:21879761)
- 巻号頁・発行日
- vol.86, no.881, pp.19-00251, 2020 (Released:2020-01-25)
- 参考文献数
- 8
The railway current collection system consists of a line and a pantograph. We take up the problem of the contact loss between a rigid conductor line and a pantograph. In order to avoid the damage on the line surface by the electric ark, it is important to prevent the contact loss. From the series of experiments with an actual pantograph system, an essential model that regards the contact loss as impact oscillations between a rigid conductor line and a pantograph was proposed. This model consists of a spring supported mass and an external exciting source that is pushed against the mass. In this paper, in order to suppress the impact oscillations, we add an oscillatory system coupled to the spring-mass system. Then, we consider the impact oscillations between the excitation source and the main mass in the two-degrees-of-freedom system. We numerically investigate the problems and obtain the bifurcating motions. When the exciting frequency is near the second mode natural frequency in the two-degrees-of-freedom system, the impact oscillations between the main mass and the external excitation source is suppressed. We conducted a series of experiments in order to verify the theoretical results. The experimental results also reveal the suppression of the impact oscillations. The experimental results qualitatively well agreed with the theoretical predictions.
- 著者
- 村井 源 松本 斉子 佐藤 知恵 徃住 彰文
- 出版者
- 情報知識学会
- 雑誌
- 情報知識学会誌 (ISSN:09171436)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.1, pp.6-17, 2011
- 被引用文献数
- 1
本論文では,計量的な物語構造の分析を実現するために,人文的な物語分析の古典的手法であるプロット分析を援用し,分析結果に対する計量的解析を行った.プロット分析は人文学的手法であるが,一致度の計算を実施することでプロット分割と分類の正当性の数値的評価を行った.プロット分類の結果に対してn-gram分析を行うことで物語構造の連続的パターンを抽出した.また同様にχ二乗検定を用いて頻出プロットの時代的変化を抽出した.さらに,テーマとプロットの関係を分析するために計量的手法で物語のテーマ語を抽出し,作品をテーマごとに分類した.このテーマの分類結果を用いて,各テーマのプロット的な特徴を抽出した.本論文での分析はプロットへの分割と分類を計量的指標を用いつつも人手で行うという点で,完全な自動化の実現ではないが,本論文の成果は将来的な物語分析の完全な自動化の基礎になると期待される.
1 0 0 0 PET薄板を使った「ついたて」の製作
- 著者
- 勝亦 徹 相沢 宏明 蒲生 美香 吉本 智巳
- 雑誌
- 2021年第68回応用物理学会春季学術講演会
- 巻号頁・発行日
- 2021-01-26
1 0 0 0 OA 居室内騒音
- 著者
- 平松 友孝
- 出版者
- The Institutew of Noise Control Engineering of Japan
- 雑誌
- 騒音制御 (ISSN:03868761)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.4, pp.275-280, 2005-08-01 (Released:2009-10-06)
- 参考文献数
- 3
- 出版者
- 公益社団法人 日本経営工学会
- 雑誌
- 日本経営工学会論文誌 (ISSN:13422618)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.2, pp.App13, 2012-07-15 (Released:2017-11-01)
1 0 0 0 OA イメージを生む脳のはたらき―機能局在論を超えて
- 著者
- 長谷川 功
- 出版者
- 日本神経心理学会
- 雑誌
- 神経心理学 (ISSN:09111085)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.3, pp.184-189, 2018-09-25 (Released:2018-10-11)
- 参考文献数
- 8
現代の神経科学は,『脳の特定の解剖学的区分に限局する細胞の性質がその脳区分に宿る機能を表す』とする機能局在論のパラダイムのもと,目覚ましい発展を遂げてきた.しかし,複雑系としての脳の動作原理を説明するのに,機能局在論に基づく細胞活動記録や脳機能マッピングのアプローチだけでは限界があることは否めない.筆者は,視覚認知の基盤をなす大脳の巨視的ネットワークにおける信号の流れや分散的・同期的な神経表現の解明を目指している.本稿では,脳の表面に柔軟な電極を張り巡らせるメッシュ型皮質脳波(ECoG)の技術を活かして,皮質に分散した視覚カテゴリー認知に関わる微細機能構築の非線形的・動的な性質を明らかにすることにより,機能局在論と全体論の発展的統合を目指そうとする最近の試みについて紹介する.
1 0 0 0 視覚的イメージ想起時の脳活動に関する一研究
- 著者
- 張 トウ 境田 英昭 河野 貴美子 山本 幹男 町 好雄
- 出版者
- 国際生命情報科学会
- 雑誌
- 国際生命情報科学会誌 (ISSN:13419226)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.2, pp.400-406, 2000
気功、瞑想時によく使用されている視覚的イメージ想起による脳活動に関して、特定イメージ(花)想起課題と休息を交互に行う形式で、fMRIによる測定を試みた。SPM99による画像解析では、休息時と比較して、イメージ想起の場合、右後頭部のBroadmann17第一次視覚野において、統計的有意な賦活が観察された。
1 0 0 0 IR 改正民法セミナー
- 著者
- 高須 順一 水野 紀子 石川 信
- 雑誌
- 白鴎大学法政策研究所年報 = Law and Policy Institute journal, an annual (ISSN:18820735)
- 巻号頁・発行日
- no.13, pp.63-96, 2020-03
開催日:2019年11月27日
- 著者
- 広田 麻未
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 日本地理学会発表要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.2016, 2016
<b>Ⅰ はじめに<br></b>現代の国際的労働力移動は,かつてない規模で,かつ質的な変化をともないながら展開している.大規模な人の国際的移動は,複雑な経済的,社会的,そしてエスニックなネットワークのなかに埋め込まれており,移民は,野放しに自由なのではなく,大きな制約を受け,構造化されている. 熟練性や言語などが問われない単純労働は,世界中誰でも従事することが可能であるといえ,低賃金で社会的地位の低い労働として捉えられている.先進国においてはこういった仕事の多くを途上国からの移民が担っており,国際的労働力移動における先進国と途上国の間の問題としてしばしば議論されている. 英語教師としての出稼ぎは,労働力の送出国と受入国の間の英語力の差を背景として移動が発生しており,経済格差を背景とした,先進国への安い労働力としての出稼ぎとは異なる出稼ぎと捉えることができる.そこで本稿では,フィリピンからカンボジアへの英語教師としての労働力移動に着目し,先進国への非熟練労働者の出稼ぎとのキャリア形成における共通点及び相違点を明らかにする. <br><b><br>Ⅱ カンボジアにおける英語教育サービスの成長<br></b>カンボジアの英語教育サービスは,公教育の不備を補うように発展しており,就学前児童および義務教育段階の子どもを対象とした英語学校が主体となっている.カンボジア教育省が,初等教育における遅延入学,留年,中退といった課題の解決のため,就学前教育を推進していること,また,教育省の認可によって,民間の英語学校が,義務教育にあたる「クメール語教育」を提供できることが背景にある. また,調査を行った41校の英語学校のうち36校は外国人の教師を,23校はフィリピン人教師を雇用しており,そのうち11校では外国人のうち3分の2以上がフィリピン人であった. <br><b><br>Ⅲ 出稼ぎ英語教師のキャリア形成</b><br>フィリピン人の英語教師としての出稼ぎは,性別,結婚歴で異なるキャリアがあることがわかった.男性は,世帯内での経済貢献意識が強くなく,稼業目的以上に「英語力をいかしたい」,「海外で挑戦してみたい」といった個人的な動機付けが強く,カンボジアを移住先に選んでいた.女性にとっては,これまで指摘されてきた「矛盾した階級移動」を経験することなく,学歴や前職との関連のある仕事によって経済的地位を向上させることができる出稼ぎとなっていた.また,ASEAN域内での移動であり,地理的な近さとビザ取得の容易さから,定期的にフィリピンに帰国することができ,既婚者(特に母親)がその出稼ぎを正当化することができていた. 彼らは移住先社会で,経済的・社会的地位が比較的高い仕事に従事しているといえ,先進国での自己犠牲的な出稼ぎのイメージとは異なる出稼ぎである.しかし,カンボジアの英語教育においては,ネイティブ・スピーカーであることや,白人であること,欧米諸国出身であることがよしとされる価値観があり,フィリピン人教師は,彼らの補佐的・代理的な役割を担っていることが明らかになった.英語力や教師としての能力・経験ではなく,国籍や見た目によって「人材の価値」が決められており,途上国間の移動であっても,労働市場においては先進国(欧米諸国)と途上国間の「人材の階層化」がなされていることが見て取れた.
1 0 0 0 OA 第2章 高齢者の暮らしを支える技術の最新動向
- 著者
- 二瓶美里
- 出版者
- 国立国会図書館
- 雑誌
- 高齢者を支える技術と社会的課題 : 科学技術に関する調査プロジェクト報告書
- 巻号頁・発行日
- 2021-03
1 0 0 0 母親同席の乳幼児ふれあい学習における高校生の学びに関する考察
目的:昨年の報告において、保育実習の効果的な指導の工夫として、母親も同席した授業環境での乳幼児とのふれあい学習を提案した。本研究では、提案した保育実習における高校生の学びを人との関わり方および学習した内容の分析から明らかにするとともに、ふれあい学習の成果を検証することを目的とする。<BR>方法:分析対象は長崎県立N高等学校の乳幼児ふれあい学習に参加した生徒302名が反省や感想を自由に記入したプリントである。人との関わり、学習した内容を示した語句や文章を抽出·分類し、「子ども理解」「将来親となる」などの視点で分析した。参加した母親の感想も考察の参考にした。<BR>結果:(1)提案したふれあい学習における生徒の学びには、「子どもと遊ぶ」「子どもを観察する」「育児体験をする」「子育て体験談を聞く」の4つがみられ、単独型の生徒と複合型の生徒が存在する。 (2)生徒の学習した内容は、育児の大変さ、子育てへの夫の協力の必要性、母親の偉大さ、乳幼児の心身の発達の様子や子どもの個人差や個性である。 (3)生徒の学びは子ども理解や子育て体験にとどまらず、自分と親との関係、将来親となる自分の姿を考えるという学びの広がりと、これまでの保育に関わる学習の内容を再確認し、乳幼児の心身の成長·発達の様子を実感するという学びの深まりとがみられる。
- 著者
- 丸山 智彰 鈴木 真由子
- 出版者
- 日本家庭科教育学会
- 雑誌
- 日本家庭科教育学会大会・例会・セミナー研究発表要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.51, pp.67, 2008
【目的】<BR> 家庭科における「福祉」は、特別な支援を必要とする社会的弱者のみならず、すべての生活者(個人・家族・コミュニティ)を対象にした広義の概念と考える。その場合、「福祉」をすべての領域に通低する"視点"として捉える必要があり、そのためには、福祉の視点を取り入れた授業が検討されなければならない。<BR> 我々は2007年7月、教員養成系大学における家庭科専攻学生に対し、「調理実習」の授業において、試食時に食事介助体験を導入し、学習の意義や可能性について検討した<SUP>1</SUP>。介助体験について自由記述で回答を求めた結果、食事を快適にする介助技術や被介助者に対する配慮等の記述が散見された。また、中高生が食事介助を体験することは、福祉の視点を身につけるために有意義であるとの指摘があった。<BR> そこで、本報告は、高等学校における調理実習の試食時に食事介助体験を導入する可能性について検討することを目的とする。<BR>【方法】<BR> 大阪府立N高等学校における『家庭総合」の調理実習の試食時に食事介助体験を設定し、前後に自記式質問紙法調査を行った。<BR>1)事前調査<BR>1.調査期間:2007年10月<BR>2.調査対象:普通科2年生全クラス240名、回収数220票、有効回答数(有効回答率)203票(男子93名女子110名)(84.6%)<BR>3.調査項目:「食事介助の経験の有無」「食事介助に気をつける点」「高齢者のイメージ」等<BR>2)食事介助体験実習<BR>1.実習期間:2007年11月<BR>2.実施方法:介助役→被介助役→介助役をA、被介助役→介助役→被介助役をBとし、二人一組あるいは三人一組で実施<BR>3.メニュー:ロールパン、コーンポタージュ、サケのホイル焼き<BR>3)事後調査<BR>1.調査期間:食事介助体験実習と同日<BR>2.調査対象:回収数208票、有効回答数(有効回答率)206票(85.8%)<BR>3.調査項目:<BR>A「介助時の気持ち」「被介助時の気持ち」「被介助後の介助変化」等<BR>B「被介助時の気持ち」「被介助後の介助変化」「Aの介助変化」等<BR>【結果】<BR>・食事介助経験がある生徒は20名(9.9%)、被介助経験がある生徒は8名(3.9%)と少なかった。<BR>・高齢者について、ポジティブなイメージを持っている生徒75名(36.9%)に対して、ネガティブなイメージを持っている生徒は134名(66.0%)と3割以上多かった。なお、このうち両方のイメージを併記していた生徒も26名(12.8%)いた(重複カウント)。<BR>・「被介助時の気持ち」については、「食べにくい」「恥ずかしい」「自分で食べたい」「怖い」等の回答が多かった。<BR>・「被介助経験後の介助」は、被介助時に不快に感じたことを通じて「被介助者の経験をしたから」「自分がされて不安だったから」何らかの変化を伴ったとの回答がほとんどであった。<BR>・食事介助体験の感想には、「汁物は食べさせ難い(食べ難い)」等、介助技術に関する記述が多かったが、介助する側・される側の困難を体験し、相手の立場を思いやることの重要性の指摘も散見された。<BR>【引用文献】<BR><SUP>1</SUP>丸山智彰 鈴木真由子「調理実習の試食における食事介助体験導入の可能性~教員養成カリキュラムでの試みより~」生活文化研究 大阪教育大学 Vol.47 2007年(印刷中)
1 0 0 0 IR 肺悪性腫瘍に対するラジオ波凝固療法
- 著者
- 豊島 正実 松岡 利幸 大隈 智尚 山本 晃 大山 嘉将 田中 佐織 中村 健治 山田 龍作 井上 佑一 井上 清俊 西田 達 臼杵 則朗 Toyoshima Masami Matsuoka Toshiyuki Ohkuma Tomohisa Yamamoto Akira Ohyama Yoshimasa Tanaka Saori Nakamura Kenji Yamada Ryusaku Inoue Yuichi Inoue Kiyotoshi Nishida Tatsuya Usuki Noriaki トヨシマ マサミ マツオカ トシユキ オオクマ トモヒサ ヤマモト アキラ オオヤマ ヨシマサ タナカ サオリ ナカムラ ケンジ ヤマダ リュウサク イノウエ ユウイチ イノウエ キヨトシ ニシダ タツヤ ウスキ ノリアキ
- 出版者
- 日本医学放射線学会
- 雑誌
- 日本医学放射線学会雑誌 (ISSN:00480428)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.14, pp.836-838, 2002-12-25
1 0 0 0 OA 酵素1分子検出から生まれたインフルエンザデジタルアッセイ
- 著者
- 田端 和仁
- 出版者
- 一般社団法人 日本生物物理学会
- 雑誌
- 生物物理 (ISSN:05824052)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.2, pp.095-101, 2021 (Released:2021-03-25)
- 参考文献数
- 24
Digital assays, which have evolved from single-molecule detection technology, are attracting attention as a new method of measuring individual cells, proteins, and nucleic acids. The digital assays are characterized by their ability to directly measure individual molecules, enabling us to perform absolute quantification without the need for calibration curves and to determine the heterogeneity of a population. We first developed a digital assay for enzymes and applied the principle to digital ELISA and digital influenza assays. We demonstrate that the digital assays for enzymes are not only a new enzymology tools, but also have a wide range of applications such as elucidating the nature of viral populations. We will discuss how these new analytical techniques are opening up uncharted territory.