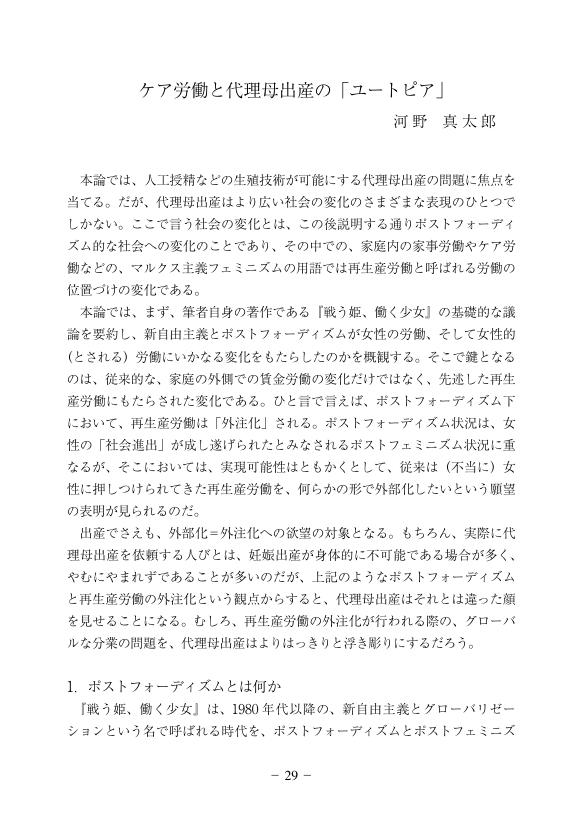1 0 0 0 フルフルプロピオン酸エステルの接觸的還元
- 著者
- 朝比奈 泰彦 柴田 文一郎
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- 藥學雜誌 (ISSN:00316903)
- 巻号頁・発行日
- vol.1917, no.423, pp.400-403, 1917
焦性粘液酸及フラーンケトンは白金黒及水素によりて四水素化物に還元せられざるにフルフルプロピオン酸エステルは容易に四水素化抱合物を生ずることを記せり
1 0 0 0 OA 下方リスクとボラティリティの関係
- 著者
- 石部 真人 角田 康夫 坂巻 敏史
- 出版者
- 行動経済学会
- 雑誌
- 行動経済学 (ISSN:21853568)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, pp.230-234, 2010 (Released:2011-06-27)
- 参考文献数
- 8
ボラティリティの高い銘柄は相対的に低リターンであるというボラティリティ効果の原因を探るために,下方リスクの性質を調べた.下方リスク測定の基準として,平均,ゼロ,相対の3つを調べた結果,この中でプロスペクト理論の損失回避概念と最も整合的なゼロが基準として適していることが分かった.上方リスクの性質も調べた結果,将来リターンとの関係は下方リスクではトレードオフ,上方リスクでは逆トレードオフとなることが確かめられた.結局,リターンリバーサル効果は下方および上方リスクの複合効果として説明可能である.また,これら3つのリスク相互の影響関係を調べると,下方リスクと上方リスクはそれぞれ固有の効果を持つが,ボラティリティはこの2つのリスクの反映に過ぎないという可能性が高まった.
- 著者
- 木島 泰三
- 出版者
- 法政大学文学部
- 雑誌
- 法政大学文学部紀要 = Bulletin of the Faculty of Letters, Hosei University (ISSN:04412486)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, pp.59-76, 2016-03-30
In the first section, we review the outline of Spinoza's project of a naturalistic ethics that does not presuppose any natural teleology. We show that Spinoza's conatus is a non-teleological, inertia-like power (though it is not the same as inertia itself) that plays important roles in his ethical project. We also point out that his project provides several conclusions that are similar to Epicurean hedonist ethics, and this similitude seems to be rooted in their shared non-teleological naturalistic worldview and shared naturalistic view of humanity. In the second section, we begin by analyzing distinct, though related, senses of the concept of contingency in his Ethics. According to Spinoza, "contingent" means "whose causes we are ignorant of." In this sense, contingency amounts to unpredictability, and thus for finite beings, the destiny of each finite being is contingent or unpredictable because of the unpredictability of the course of the "common natural order" on which our destiny depends. On another occasion, Spinoza characterizes our knowledge wiiich depends on the "common natural order" as "fortuitous" with a very negative emphasis. Here, Spinoza shares his negative evaluation of the purposelessness of the natural necessity with teleologists by taking the standpoint of finite individuals that seek naturalistic goodness for their own sake, which is explained by his conatus doctrine non-teleologically. Doubtlessly, these two overlapping implications of Spinozistic con tingency for finite beings are of a negative or detrimental character, yet it is another Spinozistic conclusion that this unpredictable and fortuitous character of the "common natural order" is the sole source of novelty that can provide finite beings with growth and improvement. This is understandable because such unpredictability and fortuitousness are the very aspects of the divine infinite purpose-free productiveness, and it is here that we find an instance of the creative combination of contingency with necessity in Spinozistic finite beings. In the third section, we find a deeper instance of such a combination of contingency and necessity in the very possibility of the existence of finite complex beings. To make this clear, we look over a few modern Epicurean speculations attempted by La Mettrie and Hume that precedeDarwin. In them we find a combination of: (1) the huge random "trial and error" process done by Nature itself, and (2) the resulting self-subsisting structure. We can find both components in Spinoza's text: (1) Nature is infinitely productive and each individual is contingent in the sense that it does not necessarily exist, and (2) each existent being is self-preserving to some degree. Such considerations solve a puzzling question about Spinoza's theory of complex individuals: namely, why Spinoza does not assign any particular causes that combine constituents into an individual. Lastly, we reconfirm the strong affinity between Spinoza and Epicureans, but notice that there may be disagreement over whether Nature itself is contingent or not.
- 著者
- 木島 泰三
- 出版者
- 法政哲学会
- 雑誌
- 法政哲学 = 法政哲学 (ISSN:13498088)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, pp.1-12, 2016-03-20
- 著者
- 上田 哲行 架谷 成美 西屋 馨 宮川 泰平 嶋田 敬介 福富 宏和 水田 陽斗 酒井 亮輝
- 出版者
- 石川県立大学
- 雑誌
- 石川県立大学研究紀要 = Bulletin of Ishikawa Prefectural University (ISSN:24347167)
- 巻号頁・発行日
- no.2, pp.1-10, 2019-03
絶滅危惧種イカリモンハンミョウは、日本では九州と本州だけに分布する。本州では能登半島の1カ所の海岸にのみ生息する。能登半島では一時絶滅したと考えられていたが、1994 年に現生息地の海岸で再発見された。2012 年から2018 年に行った成虫調査では、再発見当初1800 頭近い個体数が記録されていた海岸北部で最初の3年間はほとんど発見されない状態が続き、その後、緩やかに増え始め2018 年に急増したことが確認された。海岸南部と中央部では、最初の2年間は発見当初とほぼ同じ個体数が維持されており、2014 年から急速に増えたことが確認された。このように能登半島の個体群は、ここ数年は増加傾向にあるが、2010 年前後の著しい個体数低下がボトルネックとなり、遺伝的多様性が低下していることが示唆されている。
- 著者
- von Hartmut Boockmann
- 出版者
- Vandenhoeck & Ruprecht
- 巻号頁・発行日
- 1972
1 0 0 0 新幹線用電圧変動補償装置の開発と実用化
- 著者
- 兎束 哲夫 池戸 昭治 上田 啓二 持永 芳文 船橋 眞男 井手 浩一
- 出版者
- The Institute of Electrical Engineers of Japan
- 雑誌
- 電気学会論文誌. B (ISSN:03854213)
- 巻号頁・発行日
- vol.125, no.9, pp.885-892, 2005
- 被引用文献数
- 8 7
In AC electric Railway, three-phase voltage is changed into the single-phase circuit of two circuits with the Scott-connected transformer. If it becomes large unbalancing of the load between single-phase circuits, voltage fluctuation becomes large on three-phase side. Then, Railway Static Power Conditioner (RPC) was developed for the purpose of controlling voltage fluctuation on three-phase side. An RPC is comprised of a pair of self-commutated PWM inverters. These inverters connect the main phase and teaser feeding buses, coupled with a DC side capacitor such as a Back-To-Back (BTB) converter. In this way, the two self-commutated inverters can act as a static var compensator (SVC) to compensate for the reactive power and as an active power accommodator from one feeding bus to another.<br>20MVA/60kV RPCs started commercial operation in 2002 at each two substations on the newly extended Tohoku Shinkansen for compensating voltage fluctuation on three-phase side caused by traction loads, absorbing harmonic current. The results of operational testing indicate that an RPC can accommodate single-phase loads such as those of PWM-controlled Shinkansen and thyristor phase-controlled Shinkansen, and handle the exciting rush current of transformers, as well as compensate for harmonics successfully.
1 0 0 0 IR 北海道の地名--地理学からの接近-序論-
- 著者
- 小林 和夫
- 出版者
- 北海道大学教養部人文科学論集編集委員会
- 雑誌
- 北海道大学人文科学論集 (ISSN:03856038)
- 巻号頁・発行日
- no.10, pp.291-313, 1973-12
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA ブリュエル・ケアー社によって紹介された古代中国の音響建造物
- 著者
- 松下電器貿易株式会社
- 出版者
- 一般社団法人 日本音響学会
- 雑誌
- 日本音響学会誌 (ISSN:03694232)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.6, pp.317-318, 1972-06-01 (Released:2017-06-02)
1 0 0 0 OA 伝統の仕掛けの音
- 著者
- 岩瀬 昭雄
- 出版者
- The Institutew of Noise Control Engineering of Japan
- 雑誌
- 騒音制御 (ISSN:03868761)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.3, pp.198-201, 2000-06-01 (Released:2009-10-06)
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA 庭園の水琴窟について
- 著者
- 平山 勝蔵
- 出版者
- 社団法人 日本造園学会
- 雑誌
- 造園雑誌 (ISSN:03877248)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.3, pp.14-17, 1959-01-31 (Released:2011-04-13)
1 0 0 0 内分泌撹乱物質のノン・エストロジェニック中枢作用
本研究は、申請代表者の「内分泌撹乱物質は、ノン・エストロジェニック中枢作用により、特に前頭葉機能に影響を及ぼし、学習獲得能力を障害する」という仮説を検証するために行った。卵巣摘除成熟ラットに、40mg/kgのビスフェノールA(BPA)、ノニルフェノール(NP)、もしくはオクチルフェノール(OP)を投与して24時間後に、PR mRNA発現量が変化するか否か、ノーザンブロットにより検討した。その結果、前頭葉新皮質ではBPA、NPおよびOP投与によりPR mRNAの発現が有意に増加した。さらに、側頭葉新皮質ではBPAのみがPR mRNAの発現を有意に低下させた。頭頂葉新皮質ではいずれの内分泌撹乱物質も有意な変化を惹起しなかった。BPAの作用の時間経過を検討した結果、前頭葉新皮質のPR mRNA発現はBPA投与6時間後の時点で既に有意に増加し、24時間後の時点でも、発現量は有意に増加していた。エストロジェンもBPAと同様に前頭葉新皮質のPR mRNA発現を有意に増加させたが、その効果は一過性で、24時間後には、もとのレベルまで減少することが明らかとなった。BPAは、後頭葉のPR mRNA発現には影響を及ぼさなかったが、側頭葉では時間経過とともに有意な減少、海馬では24時間後においてのみ有意な増加を惹起した。これらのことから、エストロジェンと異なり、前頭葉新皮質では、内分泌撹乱物質の影響が長期間残存することが、エストロジェン作用との異同であり、また、記憶・学習に関与する海馬に内分泌撹乱物質がなんらかの影響を及ぼすことが明らかとなった。
1 0 0 0 OA ケア労働と代理母出産の「ユートピア」
- 著者
- 河野 真太郎
- 出版者
- 日本ヴァージニア・ウルフ協会
- 雑誌
- ヴァージニア・ウルフ研究 (ISSN:02898314)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, pp.29-44, 2018 (Released:2018-12-11)
- 参考文献数
- 23
1 0 0 0 「はやぶさ2」地球帰還!–リュウグウの石に聞いてみたいこと
- 著者
- 橘 省吾
- 雑誌
- 日本地球惑星科学連合2021年大会
- 巻号頁・発行日
- 2021-03-24
1 0 0 0 OA 横風時の自動車まわりで発生する風切り音の数値解析
- 著者
- 加藤 由博 河上 充佳 槇原 孝文 寺門 晋
- 出版者
- 公益社団法人 自動車技術会
- 雑誌
- 自動車技術会論文集 (ISSN:02878321)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.3, pp.932-937, 2019 (Released:2019-05-24)
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 2
Aピラー・ドアミラーまわりで発生する風切り音を非線形音場方程式を用いた手法で計算した.特に,横風のある場合と無い場合を比較したところ,Aピラー下部およびドアミラーからの音波の強まりが見られた.音波の伝播の様子を可視化したところ,サイドウィンドウへ到達する音波はドアミラー起源の音が主要であった.
1 0 0 0 OA ディスプレイスメントマッピングを目的とした点群データからの表面形状の抽出
- 著者
- 大坪 真之 村木 祐太 西尾 孝治 小堀 研一
- 出版者
- 一般社団法人 映像情報メディア学会
- 雑誌
- 映像情報メディア学会年次大会講演予稿集 一般社団法人映像情報メディア学会 (ISSN:13431846)
- 巻号頁・発行日
- pp.22C-2, 2017 (Released:2020-01-23)
- 参考文献数
- 3
Recently, practical application of 3D scanners promotes use of point cloud. It is necessary to manually create a surface shape in order to represent concave - convex surface profile of the 3D model. Our method can automatically extract the concave - convex surface shape from the point cloud data.
1 0 0 0 IR 症例報告 身元不明患者への医療費請求方法としての相続財産管理人の利用
1 0 0 0 OA 故佐藤昭夫先生の研究成果から見た自律神経と鍼灸
- 著者
- 佐藤 優子 内田 さえ 野口 栄太郎 今井 賢治 小俣 浩
- 出版者
- 社団法人 全日本鍼灸学会
- 雑誌
- 全日本鍼灸学会雑誌 (ISSN:02859955)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.4, pp.672-692, 2010 (Released:2011-01-20)
- 参考文献数
- 49
- 著者
- 川本 晃平 金澤 浩 白川 泰山
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement
- 巻号頁・発行日
- vol.2012, pp.48101846, 2013
【はじめに、目的】 スポーツ選手はスポーツ外傷および障害を予防するために、日々のコンディショニングが必要不可欠であり、その手段の一つとして物理療法が挙げられる。筆者らがコンディショニングに積極的に用いる機器の一つにINDIBA activ(インディバ・ジャパン)がある。この装置の特徴は0.5MHzの周波数を発し、コンデンサーの原理により温熱刺激を発生させるため、皮膚付近にハイパワーの集中照射をせずに、体内深部の組織まで生体刺激を生み出すことができる点である。また骨や腱など抵抗の高い部位に用いるレジスティブモードと軟部組織やレジスティブモードの前処置に用いるキャパシティブモードの2種類のモードがあり、治療目的によってこれらのモードを組み合わせて実施する。筆者らはこの装置を筋緊張の軽減や疼痛の緩和を目的に軟部組織に用いることで、良好な治療成績を得ている。 本研究では、INDIBA activと他の温熱療法とを比較し、軟部組織の筋硬度および筋伸張性への即時効果の有効性を検証することを目的とした。【方法】 対象は、下肢に整形外科疾患のない健常成人男性10名とした。対象の年齢は24.8±1.9歳、身長は170.5±8.7cm、体重は59.8±1.7kgであった。INDIBA activおよびホットパック(Cat-berry、山一株式会社)を用いた2種類の方法と、コントロールを比較した。方法は、ベッド上にて10分間安静腹臥位となり、大腿長の遠位50%部位の大腿二頭筋の筋硬度の評価を軟部組織硬度計 (伊藤超短波株式会社、OE-220)を用いて行った。また大腿二頭筋の伸張性評価として膝関節伸展位における股関節最大屈曲位での他動的股関節屈曲角度(以下SLR)を測定し、その際の大腿二頭筋の伸張痛をVisual Analog Scale(以下VAS)を用いて評価した。評価後、それぞれの方法を20分間実施し、終了後、評価前と同様に3項目の評価を行い、実施前後での各評価項目および各評価項目の変化率の比較を行った。それぞれの方法について、INDIBA activでは始めの10分間はキャパシティブモードを使用し、その後10分間はレジスティブモードを行った。ホットパックでは20分間バンドを用いて大腿部に固定して行い、コントロールは20分間安静腹臥位をとった。実施時の室温および測定時刻を統一し、各施行の間隔は3日以上あけ、順序は無作為にて決定し、1日に1回のみ実施した。また対象には測定2日前より過度な運動は避けさせるようにし、測定時に大腿二頭筋に疲労感がないことを確認した。 統計学的分析にはそれぞれの方法の実施前後の各評価項目の比較に対応のあるt検定を、各評価項目の変化率の比較に一元配置分散分析を用い、危険率5%未満を有意とした。【倫理的配慮、説明と同意】 対象にはあらかじめ本研究の趣旨、および測定時のリスクを十分に説明したうえで同意を得た。本研究は、医療法人エム・エム会マッターホルンリハビリテーション病院倫理委員会の承認を得て行った(承認番号MRH120015)。【結果】 それぞれの方法の実施前後での各評価項目について、ホットパックおよびINDIBA activでは3項目全てにおいて実施前後で有意に改善がみられた(p<0.01)。コントロールでは筋硬度およびVASにて有意に変化がみられ(p<0.05)、SLRは変化がみられなかった。変化率について、筋硬度ではINDIBA activがホットパックおよびコントロールに比べて有意な低下がみられた(p<0.01)。またホットパックがコントロールと比較して有意に低下した(p<0.05)。SLRでも同様にINDIBA activがホットパックおよびコントロールに比べて有意な改善がみられ(p<0.01)、ホットパックがコントロールと比較して改善がみられた(p<0.01)。VASについて、INDIBA activがコントロールと比較して有意に改善がみられたが(p<0.01)、INDIBA activとホットパックおよびホットパックとコントロールでは差はみられなかった。【考察】 本研究では、2種類の方法による筋硬度および筋伸張性の即時効果の比較を行った。温熱療法によって軟部組織の温度が上昇すると粘弾性が低下し、軟部組織の伸張性が増加することから(鳥野、2012)、今回の結果より大腿二頭筋に対して十分な温熱刺激を与えることができたと考える。特にINDIBA activでは筋硬度およびSLRがホットパックとコントロールと比較し、有意に改善した。このことからINDIBA activ は2種類のモードを組み合わせて温熱刺激を加えることで、ホットパックと比較して筋硬度および筋伸張性が改善したことが考えられた。【理学療法学研究としての意義】 臨床で各種物理療法を行う際は、即時的な効果が期待できることが重要である。今回の研究よりINDIBA activが一般的に温熱療法として多用されているホットパックに比べ、筋硬度およびSLRを有意に改善させることが示されたことから、特に筋緊張の軽減やストレッチの前処置などに有用な手段の一つになると考える。