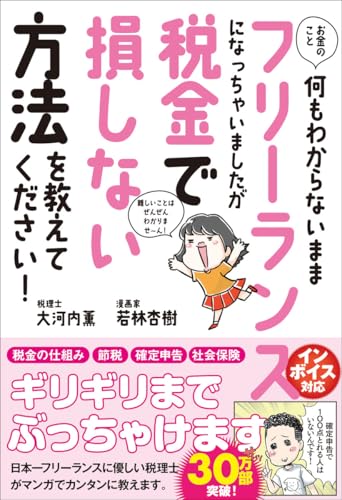1 0 0 0 IR 許可制度の法学的再構成
- 著者
- 土井 翼
- 出版者
- 一橋大学大学院法学研究科
- 雑誌
- 一橋法学 (ISSN:13470388)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.2, pp.23-37, 2019-07-10
This paper discusses the tentative reconstruction of permission from a legal perspective, and a legal criterion that can differentiate various permissions by introducing a distinction between possession and title. Under private law, the possessor is free to act within his or her territory, while the creditor is subject to various restrictions under contract law in relation to others. In response to the logic of private law, permission by an administrative agency will also be differentiated. That is to say, in the former, there is a substantial danger to being subject to the permission system, but in the latter, the regulation from the viewpoint of establishing a public space in which private persons can connect, the relation can be accepted more widely.
1 0 0 0 OA 血管作動薬の基礎と臨床
- 著者
- 川崎 孝一 上村 裕一
- 出版者
- THE JAPAN SOCIETY FOR CLINICAL ANESTHESIA
- 雑誌
- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.10, pp.297-307, 2003-12-15 (Released:2008-12-11)
- 参考文献数
- 29
周術期の循環管理においては,カテコラミンをはじめとした種々の血管作動薬が用いられる.これらの薬物は血管収縮薬と血管拡張薬に大別され,その作用は血管平滑筋を収縮あるいは弛緩するという点では同じであるが,血管平滑筋の収縮弛緩過程における作用機序は異なっている.また,心臓を含めた血管以外への作用もそれぞれ異なる.したがって,血管作動薬を用いる際には作用点である血管平滑筋の収縮弛緩機序を理解するとともに,薬理作用(作用機序,臨床効果,使用量,副作用)を熟知して循環動態に合った適切な薬物を選択する必要がある.本稿では,まず血管平滑筋の収縮弛緩機序について概説し,次に現在使用されている代表的薬物の作用機序と臨床的効果および臨床使用法について述べる.
1 0 0 0 OA 小胞体ストレスとメタロチオネイン
- 著者
- 佐藤 政男 鈴木 真也
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- YAKUGAKU ZASSHI (ISSN:00316903)
- 巻号頁・発行日
- vol.127, no.4, pp.703-708, 2007-04-01 (Released:2007-04-01)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 6 6
Much attention has been paid to lifestyle-related diseases including type 2 diabetes mellitus, cardiovascular disease, hypertension, and hyperlipidemia because the incidence rates of these diseases are increasing in developed countries. Elucidation of factors contributing to the development of obesity and insulin resistance is needed. Metallothionein (MT), a ubiquitous metal-binding protein, is induced not only by heavy metals but also by various kinds of stresses. Endoplasmic reticulum (ER) stress is caused by accumulation of misfolded proteins in ER. Recently, increased ER stress by obesity and impairment of insulin action by ER stress have been reported. Exposure to ER stress increased induction of MT synthesis, and an enhanced response to ER stress evaluated as expression of Bip/GRP78mRNA was observed in the liver of MT-null mice, suggesting that MT attenuates expression of ER stress. MT may prevent ER stress and thereby modulate the development of obesity and insulin resistance. A possible role of metallothionein in response reaction for ER stress is discussed.
1 0 0 0 OA フィンセント・ファン・ゴッホと太陽の美学 : フランス現代思想の視点から
- 著者
- 酒井 健
- 出版者
- 法政大学言語・文化センター
- 雑誌
- 言語と文化 = Language and Culture (ISSN:13494686)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, pp.1-30, 2019-01-18
1 0 0 0 OA フランス現代思想とエロティシズムの問題 : ジョルジュ・バタイユが切り拓いた地平
- 著者
- 酒井 健
- 雑誌
- 科学研究費助成事業 研究成果報告書
- 巻号頁・発行日
- pp.1-4, 2017-06-09
研究成果の概要 (和文) : フランス現代思想のパイオニアであるジョルジュ・バタイユのエロティシズム論を出発点にして、のちの世代の現代思想の担い手たちが展開した性の思想を検証した。三年間にわたる本研究は初年度にバタイユのエロティシズム論の解明に向かい、次年度にブランショなどのポスト・バタイユ世代の性の思想の解明に向かった。最後の三年度においては今現在活躍を続けているナンシー、キニャールといった思想家の発言に視野を広げながら、先行2世代の性の思想と合わせて、現代に有効な新たな人間論を構築した。成果は国内外の学会発表、国内外の学術誌における論文発表、さらに著作の刊行などを通して積極的におこなった。
1 0 0 0 OA プラトンとフランス現代思想 : シェストフ,バタイユ,デリダ
- 著者
- 酒井 健
- 出版者
- 法政大学文学部
- 雑誌
- 法政大学文学部紀要 = Bulletin of the Faculty of Letters, Hosei University (ISSN:04412486)
- 巻号頁・発行日
- vol.78, pp.31-49, 2019-03-18
Cet article a pour but de montrer les traits distinctifs de la philosophie platonicienne, vue par les penseurs français contemporains dont Georges Bataille et Jacques Derrida. En effet, on peut considérer Bataille comme représentant typique de la première génération de la pensée post-moderne française. Cette génération s’éveillait à la pensée philosophique au lendemain de la première guerre mondiale et, par suite de ce désastre inouï tout à fait européen, mettait en question les fondements de la civilisation occidentale moderne. Tandis que Derrida, comptant parmi la seconde génération, a recours surtout aux textes de Bataille pour s’acquérir sa critique radicale du modernisme aux dépens des dogmatismes idéologiques : ceux-ci dominaient la scène philosophique après la deuxième guerre mondiale.Ainsi, Bataille et Derrida, chacun à sa manière, mettaient en cause «un Platon français». Il s’agit d’un Platon rationaliste et idéaliste que les philosophes académiques depuis le 19ème siècle ont formé comme prédécesseur de Descartes. Alors, dans cette mise en cause du «Platon français», on peut faire grand cas d’un rôle que Léon Chestov a joué dans le milieu des intellectuels français. En effet, ce philosophe russe immigré cherchait, au courant des années 1920 et 30, à les éveiller à l’autre de la raison comme à un Platon profond qui fait face à ce qui est foncièrement énigmatique. À partir de cet enseignement de Chestov, le jeune Bataille a repris un sujet important de ce philosophe grec : «fixer le soleil». Quant à Derrida, il est question de ressaisir la notion platonicienne de «Khôra» pour démontrer la «déconstruction» du platonisme, faite par Platon lui-même.En fin de compte, cet article vise à mettre en lumière l’ambition de la pensée française contemporaine à l’égard de Platon. Il s’agit de le donner pour un Janus errant qui envisage à la fois le système rationnel de sa philosophie et le dehors irrationnel de celle-ci. Tout cela se résume par cette parole de Bataille : «Il (Platon) tente d’établir autant qu’il peut un édifice rationnel, et qu’il y a pourtant quelque chose au-delà...»
1 0 0 0 OA 線形予測理論とその応用
- 著者
- 小畑 秀文
- 出版者
- 公益社団法人 計測自動制御学会
- 雑誌
- 計測と制御 (ISSN:04534662)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.6, pp.481-491, 1977-06-10 (Released:2009-11-26)
- 参考文献数
- 32
1 0 0 0 OA 真空技術における潜在的な危険と安全対策
- 著者
- 後藤 康仁
- 出版者
- 一般社団法人 日本真空学会
- 雑誌
- Journal of the Vacuum Society of Japan (ISSN:18822398)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.7, pp.184-191, 2016 (Released:2016-07-16)
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 2
In this article, potential dangers of vacuum technologies are revealed, and safety measures for these dangers have been suggested. These dangers include considerable difference between the vessels' inner and outer pressures, condensation of flammable gases to the pump, electric shock due to a high voltage or electric leakage, involution to mechanical motion, touching of a high temperature during baking. Furthermore, many dangers exist when the system is under repair or maintenance. In addition to the vacuum system itself, the materials used for its operation such as liquid cryogen and organic solvents are more hazardous. Finally, some of the safety measures are proposed for the aforementioned dangers.
- 著者
- 金 銀珠
- 出版者
- 日本語学会
- 雑誌
- 日本語の研究 (ISSN:13495119)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.2, pp.123-137, 2006-04-01 (Released:2017-07-28)
近代文法学における「形容詞」は,江戸時代以来の伝統的な形容詞論をスタートラインにおけば,その規定が最初は名詞修飾機能中心へと移行し,次は叙述機能中心へと移行しながら,成立したものである。このような二度の移行に関わっていたのが西洋語のAdjective解釈である。本稿は,近代文法学における「形容詞」「連体詞」概念がどのように成立したのかを,西洋文法におけるAdjectiveとの関連から考察した。近代文法学の「形容詞」概念がAdjectiveを名詞修飾だけに極度に限定していきながら成立し,その結果として,今日の学校文法における「連体詞」が登場する過程を示した。
1 0 0 0 OA 港湾都市の盛衰 : 神戸と堺の比較から
- 著者
- 橋本 行史
- 出版者
- 関西大学政策創造学部
- 雑誌
- 政策創造研究 (ISSN:18827330)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, pp.1-40, 2019-03-29
本論文では、港湾都市としての視点から神戸と堺の関係を歴史的に考察する。神戸市と堺市は、ともに港湾主導で発展してきた港湾都市である。しかし近隣の大都市である大阪市の直近の人口は増加し、加えて京都市の人口が横ばいないし微増であるにもかかわらず、神戸市と堺市の人口は減少している。その原因は、地域の成長を牽引する産業が育っていないことにあり、現在の両市は、次の発展段階を臨む踊り場に立っている。港湾都市は、取り扱う旅客や貨物を外部の地域に依存するがゆえに盛衰の幅が大きい。海港に空港も含めて両市を港湾都市としてみるならば、神戸も堺もともに大阪の外港としての機能を持っており、両市の盛衰は大阪との関係性によって左右される「シーソーゲーム」である。
1 0 0 0 OA 膜脂質の流動性と膜タンパク質の動態
- 著者
- 荒磯 恒久
- 出版者
- 日本膜学会
- 雑誌
- 膜 (ISSN:03851036)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.1, pp.3-13, 1994-01-01 (Released:2011-08-16)
- 参考文献数
- 26
- 被引用文献数
- 1 1
In order to understand the fluid nature of biomembrane, which plays crucially important role in many aspects of life phenomena, the molecular motion of phospholipid and membrane protein is discussed in this review. It is shown that the primary determinant for the fluidity in the lipid bilayer and the rate for diffusive motion of lipid and protein molecules is the width and rate of wobbling motion of phospholipid acyl-chain in the nanosecond time region. For the lateral and rotational diffusion rate of membrane proteins, however, interaction between protein and cytoskeleton is also important as the secondary determinant. The rate of segmental motion of protein is partly governed by the surrounding phospholipid species, suggesting that specific phospholipids support the optimum conditions in protein structure to develop its action.Consequently, the term “membrane fluidity” is complex conception having a hirarchical structure which consists of lipid and protein molecules.
1 0 0 0 気流下の着衣人体における各部位の対流熱伝達率と着衣抵抗
- 著者
- 大黒 雅之 アレンズ エドワード デディア リチャード チャン ウイ 片山 忠久
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.561, pp.21-29, 2002
- 被引用文献数
- 2 22
1.はじめに 裸体人体については、部位別の対流熱伝達の研究例も多い。しかし、着衣人体について、有風時を対象として部位別の着衣表面での対流熱伝達率や着衣熱抵抗を測定した例は非常に少ない。2.研究方法 (1)直接法による着衣熱抵抗の評価 人体各部の熱抵抗は(1)式で表され、サーマルマネキンで熱量と皮膚温度が解っていれば、着衣の表面温度を測定することにより、着衣抵抗が直接算出できる。(2)対流熱伝達率の評価 サーマルマネキンにおける人体各部の熱損失は(2)(3)式で表され、各部の総合熱伝達率から放射熱伝達率を差し引くことにより各部の対流伝達率が算出できる。(3)放射熱伝達率の評価 サーマルマネキンにおける人体各部の放射熱伝達率は(4)式で表され、有効放射面積率より各部の放射熱伝達率が算出できる。3.計測方法 (1)サーマルマネキン 計測に用いたマネキンは皮膚温度可変型の女性体のサーマルマネキンで、主に室内の不均一温熱環境の評価用として開発されたものである。部位の分割数は16であり、表面積は表-1、有効放射面積率は表-2のよう求められている。(2)着衣 計測に用いた着衣は下着、綿100%の長ズボン、および綿100%の長袖シャツ、靴下、靴である。頭にはセミロングのかつらを取りつけ、着衣の一つとして評価した。また、人体各部の着衣からの熱損失量を明確にするため、マネキンの各部位の境界をビニールテープで縛り、着衣内での部位間の熱の移動がないよう配慮した。図-1に写真を示す。(3)着衣面積率の計測 立位マネキンを対象とし、2m離れた位置から、裸体、着衣時の双方について、水平方向に45°毎に8方位から撮影し、投影面積の比を平均することにより着衣面積率を算出した。(4)風洞実験手順 風洞の測定部(高さ1.5m、幅2.1mにマネキンを設置した。風洞上流側には、乱れをつくるための高さ1m、直径0.5mの円柱を測定部の上流7mの位置に設置した。表面温度測定は、熱画像をマネキン正面と背面から測定した。熱画像を解析することにより、各部位の正面と背面の着衣表面温度を求め、それらを平均することにより各部位の着衣表面温度とした。実験条件としては、裸体および着衣のマネキンそれぞれについて、正面および背面から風を当てて測定した。設定風速は0.2、0.5、0.8、1.2、2.0、3.0、5.5m/s (裸体では0.8、2.0、5.5m/sのみ)である。4.結果および考察 (1)着衣面積率 部位毎の着衣面積率を表-3に示す。(2)立位の対流熱伝達率 図-2(a)(b)に立位での前方からの風および後方からの風の時の、裸体時と着衣時の対流熱伝達率を示す。裸体では、手の値が大きい。着衣時は全般的に裸体時より大きくなる傾向がある。特に頭や風に対抗した時の胸や背中では裸体時の2倍以上になる。0.8m/s程度ではその差は小さいが、風速が大きくなるに従い、その差は大きくなる傾向にある。その差は正面からの風の時の頭が最も大きい。その他の部位では正面からの風の時の胸、および背後からの風の時の背中での差が他の部位に比べると大きい。(3)座位の対流熱伝達率 図-3(a)(b)に座位の対流熱伝達率お結果を示す。着衣時については、立位と同様裸体時より大きくなる傾向がみられる。着衣時については、立位と同様裸体時より大きくなる傾向がみられる。立位との主な差異は、前方からの風で大腿での裸体時との差が大きい点と、後方からの風の時に頭の裸体時との差が小さい点である。全身の値で比較すると裸体時、着衣時とも、立位と座位あるいは前方からの風と後方からの風で大きな差はみられない。一方、着衣時の値は裸体時より30〜50%大きい。(4)着衣熱抵抗 着衣熱抵抗の測定結果を図-5、6に示す。前方からの風での部位別(図-5)では、大腿、胸、上腕では座位の方が熱抵抗が高く、腰、頭、前腕では座位の方が低い。全身(図-6)の値で比較すると立位と座位で大きな差はみられない。(5)対流熱伝達率と着衣熱抵抗のモデル 表-4〜7に対流伝達率のモデルを示す。モデルはべき乗則(h_c=a(v)^b)で近似される。部位別ではべき指数bが0.4〜0.8とばらつく。全身ではべき指数0.60〜0.69と立位と座位、風向、裸体と着衣で大きな差はない。対流熱伝達の裸体と着衣の差は主に定数aに反映されている。着衣熱抵抗のモデルを表-8、9に示す。モデルは対数則(I_<cl>=a ln(v)+b)で近似される。部位別では定数aが-0.01〜-0.26とばらつく。全身では-0.076〜-0.096と立位と座位、風向、裸体と着衣で特に大きな差はない。5.まとめ 有風時の部位別の着衣抵抗と着衣表面の対流熱伝達率を着衣の表面温度計測により求めた。着衣時は裸体時に比較して対流熱熱伝達率の増大が認められた。また、部位別および全身について対流熱伝達率と着衣抵抗の近似モデルを示した。本論文で求めた対流熱伝達率や着衣抵抗は通気の影響を含むものであり、同タイプの着衣にのみ適用すべきである。
- 著者
- 野﨑 秀正 川瀬 隆千 立元 真 後藤 大士 岩切 祥子 坂邉 夕子 岡本 憲和 Hidemasa NOSAKI Takayuki KAWASE Sin TATSUMOTO Hiroshi GOTO Shoko IWAKIRI Yuko SAKABE Norikazu OKAMOTO 宮崎公立大学人文学部 宮崎公立大学人文学部 宮崎大学 都城新生病院 いわきりこころのクリニック 細見クリニック カリタスの園 Miyazaki Municipal University Faculty of Humanities Miyazaki Municipal University Faculty of Humanities Miyazaki University Miyakonojo Shinsei Hospital Iwakiri Mental Care Clinic Hosomi Clinic
- 雑誌
- 宮崎公立大学人文学部紀要 = Bulletin of Miyazaki Municipal University Faculty of Humanities (ISSN:13403613)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.1, pp.105-120, 2021-03-10
本研究では、子育て支援サービスを提供する公的相談機関に対する母親の援助要請に焦点を当て、母親の育児に対する感情(育児感情)と信念(母性愛信奉)が、援助要請態度を媒介して援助要請意図に影響を及ぼす一連のプロセスを示した仮説モデルを検証することを目的とした。宮崎市内及びその近郊にて就学前の幼児(3 歳以上)の育児に携わる母親1000名に調査協力を依頼した。質問紙が返送され、かつ回答に不備のなかった470 名の回答を分析対象とした。仮説モデルに従い共分散構造分析を行った結果、育児感情及び母性愛信奉から3 つの援助要請態度を媒介して援助要請意図に影響を及ぼすいくつかのプロセスが明らかになった。このうち、利益とコストの態度を媒介したプロセスについては、いずれも子どもにとっての利益とコストを媒介したパスが有意であり、母親自身にとっての利益とコストの態度を媒介したパスはいずれも有意ではなかった。これらの結果より、子育ての悩みに関する母親の公的相談機関に対する援助要請については、母親の精神状態の解決に動機づけられているというよりも、その原因となっている子どもの問題を解決させることに動機づけられていることが明らかになった。こうした結果は、公的相談機関に対する母親の援助要請促進を促すには、援助要請が子どもにもたらすポジティブな影響を強調することや子どもと担当職員間の良好な関係づくりなど、子どもに焦点を当てたアプローチが有効になることを示唆した。
1 0 0 0 OA ドックにおける総胆管径計測および拡張例の検討
- 著者
- 小松 淳子 折津 政江
- 出版者
- 公益社団法人 日本人間ドック学会
- 雑誌
- 健康医学 (ISSN:09140328)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.1, pp.53-56, 1998-05-30 (Released:2012-08-27)
- 参考文献数
- 8
総胆管拡張は肝胆膵の病変の早期発見に重要な所見だが,軽度拡張例の評価は難しい。ドック受診者の検討では,総胆管径には性別,年齢体格,他の超音波所見,既往歴が関与した。8mm以上は5.6%で,経過中8%に新たな超音波所見がみつかったが,ほとんどが8-9mmの軽度拡張例であった。ドックでみられる無症候性の軽度拡張例においては,他の超音波所見を見落とさないよう念入りな経過観察を行うことが重要と考える。
1 0 0 0 OA 良導絡と漢方処方薬
- 著者
- 小田 博久 佐藤 暢
- 出版者
- 日本良導絡自律神経学会
- 雑誌
- 日本良導絡自律神経雑誌 (ISSN:05575729)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.3-4, pp.67-70, 1984-04-15 (Released:2011-10-18)
1 0 0 0 OA 清水幾太郎における文体の変遷
- 著者
- 大久保 孝治
- 出版者
- 早稲田大学大学院文学研究科
- 雑誌
- 早稲田大学大学院文学研究科紀要 (ISSN:24327344)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, pp.17-32, 2020-03-15
- 著者
- ヒワティグ エイプリル・ダフネ・フロレスカ ファウスティーノ ジョエル・ベルナール 隅田 学 PAWILEN Greg Tabios FUJITA Atsuko KUMAGAI Takashi
- 出版者
- 愛媛大学教育学部
- 雑誌
- 愛媛大学教育学部紀要 (ISSN:13497243)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, pp.101-110, 2011-10
1 0 0 0 OA 脱コモディティ化戦略における顧客像の探究
- 著者
- 東 利一