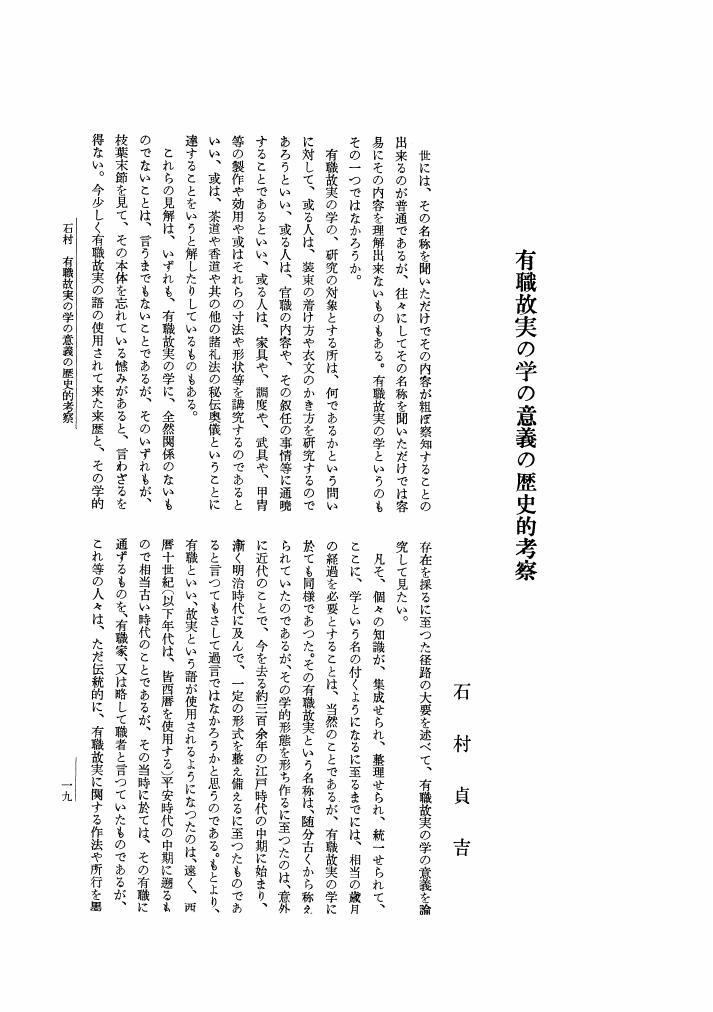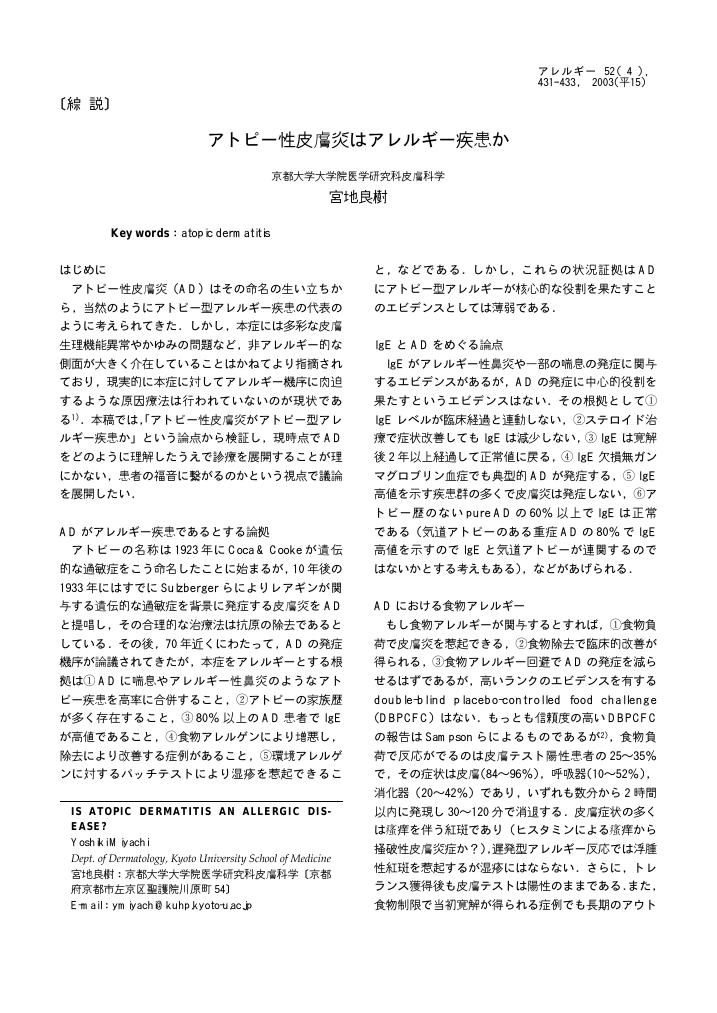3 0 0 0 OA 武道史史料として絵葉書がもつ可能性について
- 著者
- 太田 順康
- 出版者
- 日本武道学会
- 雑誌
- 武道学研究 (ISSN:02879700)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.Supplement, pp.S_18, 2018 (Released:2019-09-04)
3 0 0 0 OA 有職故実の学の意義の歴史的考察
- 著者
- 石村 貞吉
- 出版者
- 日本学士院
- 雑誌
- 日本學士院紀要 (ISSN:03880036)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.1, pp.19-38, 1954 (Released:2007-05-30)
- 著者
- 大泉 伝 斉藤 和雄 Le DUC 伊藤 純至
- 出版者
- Meteorological Society of Japan
- 雑誌
- 気象集誌. 第2輯 (ISSN:00261165)
- 巻号頁・発行日
- vol.98, no.6, pp.1163-1182, 2020 (Released:2020-12-17)
- 参考文献数
- 34
- 被引用文献数
- 5
数値気象予測モデルの要素が豪雨のシミュレーションに与える影響を調べるため、広い領域を対象とした超高解像度実験を2014年8月の広島の豪雨事例で行った。本研究はPart 1 の2013年10月伊豆大島での研究に続くものであり同様の実験を行った。これらの研究から豪雨のシミュレーションにおいて広い領域で高解像度モデル(解像度500m以下)を用いる有用性を示した。 広島の事例では降水帯の位置や強度はモデルの解像度に影響を受けることがわかった。解像度2kmの実験では降水帯は再現されたがその位置は北東にずれていた。解像度500mと250mの実験ではこの降水帯の位置ずれは軽減された。最も降水帯の位置と強度をよく再現したのは解像度250mの実験であった。降水帯に対する境界層スキームの影響は小さく、この点は伊豆大島の事例と異なっていた。 本研究では対流コア数のモデル解像度依存性についても調査した。モデルの解像度に対する対流コア数の変化率は解像度500mで小さくなる事がわかった。この結果は、対流コア数は解像度500mより高解像度になると収束する可能性を示す。
3 0 0 0 OA 家禽の雄性生殖器とその作用の特色
- 著者
- 西山 久吉
- 出版者
- 日本暖地畜産学会
- 雑誌
- 西日本畜産学会報 (ISSN:09143459)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, pp.1-6, 1982-07-27 (Released:2010-08-25)
- 参考文献数
- 8
3 0 0 0 OA アトピー性皮膚炎はアレルギー疾患か
- 著者
- 宮地 良樹
- 出版者
- 一般社団法人 日本アレルギー学会
- 雑誌
- アレルギー (ISSN:00214884)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.4, pp.431-433, 2003-04-30 (Released:2017-02-10)
- 参考文献数
- 4
- 被引用文献数
- 1
3 0 0 0 OA 酵母におけるワクチン関連遺伝子の発現と応用
- 著者
- 今村 隆幸
- 出版者
- 公益社団法人 日本農芸化学会
- 雑誌
- 日本農芸化学会誌 (ISSN:00021407)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.6, pp.961-964, 1993-06-01 (Released:2008-11-21)
- 参考文献数
- 11
3 0 0 0 OA “しとぎ” と古代の酒
- 著者
- 上田 誠之助
- 出版者
- 公益財団法人 日本醸造協会
- 雑誌
- 日本醸造協会誌 (ISSN:09147314)
- 巻号頁・発行日
- vol.91, no.7, pp.498-501, 1996-07-15 (Released:2011-09-20)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 2 2
原始社会において食物は最大の関心事であった。その食物の安定確保を左右するものとして天候, 気候があり, この管理しがたい事象を人間側に有利ならしめるものとLて神まつりがあった。餅と酒は人間側に立つ神を元気付けるもの, あるいは人間に敵対する神を懐柔するためのものであった。餅には2種類あリ, 普通の餅は丸米をついて造るが, しとぎは米粉をこねて造る。筆者は神の食物であるしとぎと酒の関係について研究している。古代の酒造りにも思いを巡らしていただきたい。
3 0 0 0 OA 近年の課程認定政策と大学の自主性・自律性
- 著者
- 木内 剛
- 出版者
- 日本教師教育学会
- 雑誌
- 日本教師教育学会年報 (ISSN:13437186)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, pp.32-39, 2013-09-15 (Released:2020-08-18)
- 参考文献数
- 8
- 著者
- 益谷 真
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 日本教育心理学会総会発表論文集 第62回総会発表論文集 (ISSN:21895538)
- 巻号頁・発行日
- pp.195, 2020 (Released:2021-02-10)
- 著者
- 島 一則
- 出版者
- 日本教育行政学会
- 雑誌
- 日本教育行政学会年報 (ISSN:09198393)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, pp.27-61, 2018 (Released:2019-09-20)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 1
The purpose of this paper is to : ⑴ identify the “Standards” at the national level in the Basic Plan for Promoting Education ; ⑵ clarifying changes of the “Standards” at the national level from the 1st term to 3rd terms of the Basic Plan for Promoting Education ; and ⑶ comparing the standards between elementary / secondary education levels and post-secondary education level, to identify the advantages and disadvantages of the “Standards” at the national level in the Basic Plan for Promoting Education.The Basic Plan for Promoting Education (2008-2012, 2013-2017, 2018-2022) are used as text data, applying the text mining approach. The research results are summarized as follows. ⑴ Section 3 clarifies that there are three types of the “Standards” at the national level in the Basic Plan for Promoting Education (“Law” type, “Guide line” type, and “Index type”) Next identified are the “Index” type of “Standards” at the national level, which represents the national goals of education in a numerical manner, as research objects for section 5 & 6. ⑵ There were huge changes in “Index” type of “Standards” at the national level in both quantitative and qualitative ways from 2008-2012 to 2013-2017, and also 2013-2017 to 2018-2022. ⑶ The “Index” type of “Standards” at the national level were introduced to the Basic Plan for Promoting Education a bit further into elementary / secondary education levels than the post-secondary education level.The “Index” type of “Standards” at the national level may have advantages for promoting some national goals of education, for example the student test scores. At the same time, they have numerous problems : ⑴ inadequate definition of the index problem, ⑵ unstable index problem, ⑶ vague responsible actor problem for index, ⑷ legal compatibility of index, ⑸ integrity among indices, ⑹ validity and reliability of the index, and ⑺ data and statistics for the index.Even though there are many problems in terms of “Standards” at the national level, educational administration research must face and overcome these problems in order to improve the quality of education.
3 0 0 0 OA 産学連携の政策過程――技術科学大学の設立を事例として――
- 著者
- 二宮 祐
- 出版者
- 日本公共政策学会
- 雑誌
- 公共政策研究 (ISSN:21865868)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.136-146, 2006-12-10 (Released:2019-03-18)
- 参考文献数
- 36
従来の教育政策研究の多くは,保守陣営と革新陣営との対立や教育分野の陣営と教育分野外の陣営との対立によって政策過程を把握してきた。しかし,産学連携に関連する政策はこのような対立枠組みでは把握されず,政策過程研究は不十分である。そこで,1970年代の国立の技術科学大学2校の設立を事例として検討する。分析枠組みとして,サバティア(Paul A. Sabatier)による唱道連携フレームを用いる。このフレームは,「政策サブシステム」内部における「政策志向学習」か,長期間にわたる政策変化に影響を及ぼすことに着目するものである。技術科学大学設立の「政染サブシステム」には,文部省や自由民主党のみならず,国立高等専門学校協会や日本経営者団体連盟が参人していた。そして,「政策サブシステム」内部において,各アクターは信念システムを変化させることによって政策形成を導いた。この政策は,複線型の学制を意図していた高等専門学校を再び単線型の進学コースに取り込む点で重要てあった。従来の政策形成が文部省の一貫した方針の下にあるという理解は,1970年代の少なくとも事例の1つにおいては,修正の必要が存在する。
3 0 0 0 OA 大学生の進路選択自己効力と関連要因の変化 教員養成学部の学生のキャリア意識について
- 著者
- 寺本 妙子
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 日本教育心理学会総会発表論文集 第62回総会発表論文集 (ISSN:21895538)
- 巻号頁・発行日
- pp.61, 2020 (Released:2021-02-09)
3 0 0 0 OA How has workcation evolved in Japan?
- 著者
- Tatsuya Yoshida
- 出版者
- Global Business Research Center
- 雑誌
- Annals of Business Administrative Science (ISSN:13474464)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.1, pp.19-32, 2021-02-15 (Released:2021-02-15)
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 10
The workcation, wherein people combine work with vacation, is a concept that originated in the United States and Europe with the spread of information and communications technology (ICT). Although it is considered a workstyle for independent people as epitomized by freelancers and the like, in Japan, the term has come to convey something different from its original meaning, taking a unique direction in which some types of training programs are referred to as workcation. How did this change come about? This study, based on surveys of three regions, examines the origin and development of satellite office workcation and learning workcation to ascertain the following. (1) In Japan, people with workcation are assumed to be employees. (2) Therefore, the workcation is heavily influenced by local governments' intentions (wanting to associate with exchange populations) and companies' intentions (it is difficult to dispatch employees to outlying areas without a work-related purpose). (3) Therefore, the workcation has evolved into something that aims to enhance creativity, learning, and introspection through close ties with communities.
- 著者
- 木田 竜太郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 日本教育学会大會研究発表要項 (ISSN:2433071X)
- 巻号頁・発行日
- vol.77, pp.125-126, 2018 (Released:2019-12-05)
3 0 0 0 OA 大学縮小期における借入金マネジメント
- 著者
- 西井 泰彦
- 出版者
- 日本高等教育学会
- 雑誌
- 高等教育研究 (ISSN:24342343)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, pp.135-161, 2019-05-31 (Released:2020-06-03)
- 参考文献数
- 8
本稿の目的は,1960年から現在に亘る文部科学省と日本私立学校振興・共済事業団の財務上の統計資料を利用して,私立大学の借入金を巡る動向とを振り返り,借入金に関する問題点と意義を分析することである. 日本の私立大学は,二度に亘る学生急増期と減少期を経過する中で,借入金を活用して施設設備を取得して,大学の規模の拡大を図ってきた. 借入金の比重が増大したが,その後,学生数が増加するとともに,財政上の改善が進み,自己資金が増加して借入金の返済が可能となった. しかし,近年,私立大学の拡張が止まり,財政が再び悪化している.学生数の長期的な減少が予測されており,私立大学が安定的な経営を持続するための借入金のあり方と課題を検証する.
- 著者
- Hidemasa Nakaminami Hinako Kawasaki Shunsuke Takadama Hiroshi Kaneko Yoshiko Suzuki Hiroshi Maruyama Norihisa Noguchi
- 出版者
- National Institute of Infectious Diseases, Japanese Journal of Infectious Diseases Editorial Committee
- 雑誌
- Japanese Journal of Infectious Diseases (ISSN:13446304)
- 巻号頁・発行日
- vol.74, no.1, pp.82-84, 2021-01-29 (Released:2021-01-22)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 8
In the last decade, methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) has been identified in livestock animals, such as swine, poultry, and veal calves, and has been termed livestock-associated MRSA (LA-MRSA). LA-MRSA sequence type (ST) 398 strains can effectively infect and colonize humans, with subsequent human-to-human transmission in both community and hospital settings. Unlike other countries, LA-MRSA had not been reported in Japanese patients until 2019. However, we recently reported a case of intractable arthritis caused by an LA-MRSA CC398 (ST1232) clone, which is a single-locus variant of ST398, in a patient in Tokyo, Japan, with no animal contact (Nakaminami H, et al. Emerg Infect Dis. 2020; 26: 795-7.). Uniquely, the strain was positive for Panton-Valentine leukocidin. Here, we report the second such case in Japan. To prevent the dissemination of LA-MRSA in the Japanese community, the prevalence of the CC398 MRSA clone should be closely monitored in the future.
3 0 0 0 OA 井浪真吾著『古典教育と古典文学研究を架橋する―国語科教員の古文教材化の手順―』
- 著者
- 内藤 一志
- 出版者
- 全国大学国語教育学会
- 雑誌
- 国語科教育 (ISSN:02870479)
- 巻号頁・発行日
- vol.88, pp.48-50, 2020-09-30 (Released:2020-10-23)
- 参考文献数
- 4
3 0 0 0 OA 男子大学生の男性役割態度と関連する親の要因
- 著者
- 渡邊 寛
- 出版者
- 日本パーソナリティ心理学会
- 雑誌
- パーソナリティ研究 (ISSN:13488406)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.1, pp.28-41, 2019-07-01 (Released:2019-07-06)
- 参考文献数
- 49
本研究では,現代の男子大学生を対象に,以下2点を検討した。第1に,男子大学生が認知する親の男性役割期待の実態を検討した。その結果,男子大学生は,父親の伝統的な男性役割期待をあまり感じず,父母の新しい男性役割期待を強く感じていた。第2に,親の属性(学歴と就労状況)や親の男性役割期待認知が,男子大学生の男性役割態度に与える影響を検討した。その結果,学歴や働き方は父親の影響が強く,男性役割期待は母親の影響が強かった。これらの結果から,男子大学生は,父親の働き方や生き方を手本とする一方で,母親からの期待の影響を直接受けていると示唆された。これらの結果を踏まえて,本研究の意義と今後の課題が議論された。
3 0 0 0 OA 精神医療と〈文学〉 の形成
- 著者
- 鈴木 晃仁
- 出版者
- The Philosophy of Science Society, Japan
- 雑誌
- 科学哲学 (ISSN:02893428)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.2, pp.33-51, 2014-12-20 (Released:2015-11-08)
This paper examines the relationship between psychiatric practice and literature. Those materials that suggest patients' “literary” activities, both in narrow and wide senses of the term, have been selected from an archive of a private hospital in Tokyo before the Second World War and their meanings and functions in and out of the psychiatric hospital are discussed. The two apparently contradictory forces of producing patients' discourse and forbidding their subjectivity are present and did somehow contribute to the making of the “literature” of the mental patients.
3 0 0 0 OA JRR-1記念展示館
- 著者
- 今井 栄一
- 出版者
- 一般社団法人 日本原子力学会
- 雑誌
- 日本原子力学会誌 (ISSN:00047120)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.2, pp.167-170, 1979-02-28 (Released:2009-04-21)