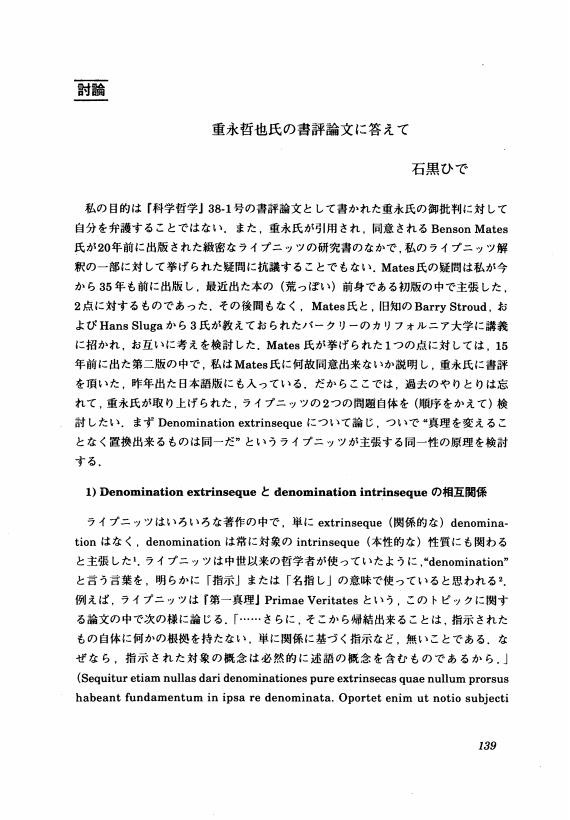3 0 0 0 OA 高校英語「読むこと」において生徒の読みを促進する発問とは
- 著者
- 山岡 大基
- 出版者
- 中国四国教育学会
- 雑誌
- 教育学研究ジャーナル (ISSN:13495836)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, pp.41-50, 2014-11-30 (Released:2017-02-22)
- 参考文献数
- 31
This article casts doubt on the current tendency of high school English language teachers to ask questions which require the understanding of the meaning of passages (i.e. comprehension questions) in reading classes. The author concedes that the tendency has not emerged without reason; it is in accordance with the communicative orientation of the English language teaching in Japanese schools in that those questions are intended to direct learners' attention to the content or message that the text carries. However, those questions are based on the specific content of a particular text, and thus less likely to help the students acquire generalizable linguistic skills applicable to different texts. In seeking alternative ways of question making, the author refers to the teaching of Japanese as the first language as an advanced model in terms of its primary focus on language, as observed in the national course of study. Based on the implications from Japanese language teaching, the author proposes a distinction between content questions and form questions, and he argues that the latter is more effective in developing students' generalizable linguistic skills. A report from a reading class which utilized form questions supports the case for varying question types in teaching reading.
3 0 0 0 OA 討論
- 著者
- 石黒 ひで
- 出版者
- 日本科学哲学会
- 雑誌
- 科学哲学 (ISSN:02893428)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.2, pp.139-143, 2005-12-25 (Released:2009-05-29)
3 0 0 0 OA 小麦全粒粉配合パンの食後血糖値上昇抑制効果
- 著者
- 青江 誠一郎 野崎 聡美 菊池 洋介 福留 真一
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本栄養改善学会
- 雑誌
- 栄養学雑誌 (ISSN:00215147)
- 巻号頁・発行日
- vol.76, no.1, pp.20-25, 2018 (Released:2018-03-12)
- 参考文献数
- 21
【目的】小麦全粒粉パン摂取後の血糖値上昇が,小麦粉パン摂取後と比較して抑制されるか検証する。【方法】空腹時の血糖値が正常な成人19名(男性10名,女性9名)を試験対象とした。糖質 50 gを含む小麦全粒粉パン(試験食)または小麦粉パン(対照食)を摂取し,摂取前および摂取後15分,30分,45分,60分,90分,120分の血糖値を測定した。試験はプラセボ対照無作為化単盲検クロスオーバー試験とし,主要評価項目はGlycemic Index(GI値),副次評価項目を各時点の血糖上昇値,最大血糖上昇値,血糖値上昇曲線下面積(IAUC)とした。【結果】グルコース溶液を基準とした場合,小麦全粒粉パンのGI値は65.2,小麦粉パンのGI値は73.0であり,小麦全粒粉パンは小麦粉パンよりもGI値が有意に低かった。小麦全粒粉パンを摂取した場合,小麦粉パンを摂取した場合と比較して最大血糖上昇値が有意に低く,IAUCが有意に小さかった。【結論】小麦全粒粉パンの摂取は,小麦粉パンの摂取と比較して健常者の食後血糖値の上昇を抑制する効果が確認された。
3 0 0 0 OA 薬理学研究での統計手法の実態
- 著者
- 浜田 知久馬 赤澤 理緒 西沢 友恵
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬理学会
- 雑誌
- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)
- 巻号頁・発行日
- vol.133, no.6, pp.306-310, 2009 (Released:2009-06-12)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 1 2
浜田等は薬効・薬理試験でよく用いられる統計手法の現状分析を行なうため,日米欧の代表的な薬理学雑誌について,1996年公表された論文について使用されている統計手法の文献調査を行い,統計手法の不適切な使用・記載の典型例を指摘した.この調査から,10年が経過したので,最近の薬効・薬理試験の統計解析法の動向を調べるため,Journal of Pharmacological Sciencesについて再度,文献調査を行い,1996年の調査結果と比較して,この10年間の統計解析法の変遷について評価した.また,統計手法の記述内容の適切性を評価した.このジャーナルのHPでPDFファイル化されている電子ジャーナルから,統計解析(Statistical Analysis)の節に記載されている統計解析の手法を抽出し,集計した.調査対象の論文数は(1996年1月~12月,134報),(2002年1月~12月,148報),(2007年1月~12月,133報)となった.結果は次のようになった.1)Student t test(t検定)の使用の割合が減少し,ANOVA(分散分析)の使用の割合が増加した.2)多重比較法では,Dunnett法が減りTukey法,Bonferroni法が増加した.3)Scheffe法,Newman-Keuls法,Fisher(P)LSD法,Duncan法の不適切な多重比較法も依然として用いられていた.4)検定の両側・片側の区別,ソフトウエアについては記載されていない場合が多かった.本論文では,以上の結果から,薬理学雑誌の統計の質を高め,適正化するための方法について考察し,提言を行う.
3 0 0 0 OA 全国調査による日本人の胸やけ・逆流性食道炎に関する疫学的検討
- 出版者
- 一般財団法人 日本消化器病学会
- 雑誌
- 日本消化器病学会雑誌 (ISSN:04466586)
- 巻号頁・発行日
- vol.102, no.11, pp.1482-1486, 2005 (Released:2005-12-27)
(誤)table1 (正)table1に誤りがあったので差し替えました。
3 0 0 0 OA 通信放送融合時代のテレビをめぐる論点:4K・8K,同時配信を中心に
- 著者
- 村上 圭子
- 出版者
- 国立研究開発法人 科学技術振興機構
- 雑誌
- 情報管理 (ISSN:00217298)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.11, pp.721-731, 2017-02-01 (Released:2017-02-01)
- 参考文献数
- 5
地上波放送の完全デジタル化が終了して5年を超え,テレビ,放送を取り巻く環境は様変わりした。端末のマルチデバイス化,伝送路のブロードバンド化,サービスのプラットフォーム化が進み,インターネット上には放送事業者以外による多種多様な動画配信サービスが乱立してきた。視聴者のテレビ離れの傾向はもはや若者だけのものではなくなっている。総務省では2015年11月に「放送を巡る諸課題に関する検討会」を設け,2016年9月から個々のテーマ別に議論が開始された。本稿ではまず,テレビを取り巻く昨今の変化と放送政策との関係について確認したうえで,4K・8K放送と動画配信(特に同時配信)の2点に絞って課題を論じたい。
3 0 0 0 OA ディープラーニングによる組織識別率の検証
- 著者
- 足立 吉隆 田口 茂樹 弘川 奨悟
- 出版者
- 一般社団法人 日本鉄鋼協会
- 雑誌
- 鉄と鋼 (ISSN:00211575)
- 巻号頁・発行日
- vol.102, no.12, pp.722-729, 2016 (Released:2016-11-30)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 21
Deep learning by convolution neural network (CNN) was applied to recognize a microstructure of steels. Three typical CNN-models such as LeNet5, AlexNet, and GoogLeNet were examined their accuracy of recognition. In addition to a model, an effect of learning rate, dropout ratio, and mean image subtraction on recognition accuracy were also investigated. Through this study, the potency of deep learning for microstructural classification is demonstrated.
- 著者
- Junya Sado Kosuke Kiyohara Taku Iwami Yuri Kitamura Emiko Ando Tetsuya Ohira Tomotaka Sobue Tetsuhisa Kitamura
- 出版者
- The Japanese Circulation Society
- 雑誌
- Circulation Journal (ISSN:13469843)
- 巻号頁・発行日
- vol.82, no.3, pp.919-922, 2018-02-23 (Released:2018-02-23)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 7
Background:We assessed whether the occurrence of out-of-hospital cardiac arrest (OHCA) with cardiac origin increased in the disaster areas during the 3-year period after the Great East Japan Earthquake (GEJE).Methods and Results:From the OHCA registry in Japan, yearly changes in occurrence after the GEJE were assessed by applying Poisson regression models. The risk ratio of the first year after the earthquake was significantly greater in both men and women, but the difference disappeared in the second and third years.Conclusions:The GEJE significantly increased the occurrence of OHCA with cardiac origin in the first year after the earthquake.
3 0 0 0 OA 福島原発事故後に仮設住宅等に転居している児童のメンタルヘルス
- 著者
- 三浦 正江 三浦 文華 岡安 孝弘
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 心理学研究 (ISSN:00215236)
- 巻号頁・発行日
- pp.89.16333, (Released:2018-03-10)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 6
This study compared the psychological health of children who moved to temporary housing following the Fukushima nuclear accident with those who stayed in their own houses. The questionnaire was designed to measure stress responses, positive events in daily life, positive affect, and social support. It was completed by 28 children who had evacuated from the affected area and lived in temporary housing; 106 children living in their own houses in Fukushima Prefecture; and 321 children living in a nonaffected area in Saitama Prefecture. The results showed that children who moved to temporary housing experienced more frequent bullying and play-related stressors, had less positive experiences related to events with family members and during lessons, and received less support from their teachers and friends than other children. However, the differences in living environments did not affect their stress responses or positive affect. These findings suggest the importance of providing temporary housing environments that enable children to experience close interactions with friends and adequate support from teachers.
3 0 0 0 OA 記念碑と場所の関係
- 著者
- 大平 晃久
- 出版者
- 人文地理学会
- 雑誌
- 人文地理学会大会 研究発表要旨 2009年 人文地理学会大会
- 巻号頁・発行日
- pp.59, 2009 (Released:2009-12-16)
人文地理学において記念碑を対象とした研究は隆盛をみているが、個別の記念碑研究ではなく、記念碑と場所の関係の一般化を指向する研究は少ない。本発表では,まず,既存のモニュメントを否定するアンチ・モニュメントの事例,とりわけベルリン・バイエルン地区の「追憶の場」を紹介し,そこにみられる記念碑と場所との関係を考える。その上で,バイエルン地区「追憶の場」の事例から,場所間の見立てという記念碑の働きに注目する。 アンチ・モニュメントとは,ドイツにおいてナチスの記憶と向き合う中で生まれた,従来の記念碑の概念を打ち崩そうとする作品群に与えられた名称である。ザールブリュッケンやカッセルの不可視の「記念碑」,ベルリン・ゾンネンアレのセンサーが感知したときのみ説明文が浮かび上がる「記念碑」、ホロコースト記念碑の計コンペで落選した、ブランデンブルク門を破壊してその破片をばらまくというプラン,ブランデンブルク門南の敷地にヨーロッパ各地の強制収容所跡地行きのバスが発着するバスターミナルを建設し,アウシュヴィッツなどの行き先を表示した真っ赤なバスが市内を毎日行き来すること自体を「記念碑」とするプラン,アウトバーンの一部区間を走行速度を落とさざるを得ない石畳にすることで「記念碑」とするプランなどが事例としてあげられる。 ベルリンの「バイエルン地区における追憶の場」はそうしたアンチ・モニュメントの系譜に位置づけられるプロジェクトである。戦前にアインシュタイン,アーレントなど中流以上のユダヤ系住民が数多く暮らしていたこの地区では,地域の歴史を掘り起こす住民運動が起こった。その結果,1993年に記念碑の設計コンペが実施され,シュティ, R.とシュノック, F.によるプランが1位となった。閑静な住宅地区であるここバイエルン地区では,あちこちの街灯に妙な標識が取り付けられている。全部で80枚のそれらの標識は,例えば片面がカラフルなパンのイラスト,もう片面には「ベルリンのユダヤ人の食料品購入は午後4時から5時のみに許可される。1940. 4. 7」というナチス時代のユダヤ人を迫害する法令の文章が記され、,標識の下に簡潔な記念碑としての説明が取り付けられている。商店の看板とみまがうようなポップなイラストと恐ろしい文言からなる標識群は,その形態からも,またそれらが日常の生活の場にあり生々しい過去と日々向かい合うように設けられている点からも,まさに既存の記念碑を否定するアンチ・モニュメントといえよう。 これらのアンチ・モニュメントにおける,場所と記念碑の関係を検討すると,まず,脱中心的であったり不可視であったりすることから,そもそも場所との位置的な対応を問うこと自体が無効である可能性がある。一方で,アンチ・モニュメントが決まったメッセージを伝えるのではなく,記念碑をめぐる実践が意味を作り出す点は場所的な特性として指摘できる。このようにアンチ・モニュメントは場所と記念碑の関係に新たな視点をもたらすものなのである。 バイエルン地区「追憶の場」については、個々の標識については第三帝国当時ではなく現在の景観とおおむね対応している点も特徴的である。過去におけるパン屋や病院など小スケールの事物を記念するというオンサイトの記念碑の文法に則りながら,通常の意味でオンサイトの記念碑ではない点は訪れる者を戸惑わせるものである。しかし,歴史地理的な探索ではなく,現代における実践を誘うものとしてこの記念碑(標識群)は捉えられるべきであろう。現代のスーパーマーケットの前の標識をみてナチス期の商店を想起するという実践は,場所間の見立てであり、バイエルン地区の標識は,そうした見立てを誘うものとして捉えられることを指摘したい。そして,管見の限り,アンチ・モニュメントはいずれも場所間の見立てである一方,大半の記念碑はそうではない。例外は記念碑としては周辺的である文学碑の一部と,聖地など宗教関係の記念碑に限定されると考えられる。 ここで垣間みた場所間の見立ては記念碑の対場所作用の一例に過ぎない。そうしたレトリカルな分析の可能性,また広義の記念碑=「記憶の場」まで含めた考察の必要性を試論的に指摘しておきたい。
3 0 0 0 OA 研究用原子炉等を用いた工業生産
- 著者
- 河村 弘
- 出版者
- 公益財団法人 日本学術協力財団
- 雑誌
- 学術の動向 (ISSN:13423363)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.6, pp.6_32-6_38, 2015-06-01 (Released:2015-10-02)
- 参考文献数
- 10
3 0 0 0 OA 貨物蒸氣船金城山丸の汽機汽罐に就て
- 著者
- 大野 省三
- 出版者
- The Japan Society of Naval Architects and Ocean Engineers
- 雑誌
- 造船協會會報 (ISSN:18842054)
- 巻号頁・発行日
- vol.1936, no.59, pp.59-83, 1937-02-20 (Released:2009-07-23)
The “Kinjosan Maru” is the first ship equipped with Howden Johnson improved Scotch boiler and Gotaverken turbo-compressor. The propelling machineries consist of two sets of boilers designed for working pressure 16 kg/cm2and steam temperature 315°C, and one set of triple expansion surface condensing reciprocating steam engine specially designed to suit Gotaverken turbo-compressor and superheated steam. The engine develops a normal output of 1950 I.H.P. at 82 r.p.m.The trials were carried out at a light loaded condition and the results were quite satisfactory. The maximum speed of 14-5075 Knots was recorded at 89·75 r.p.m. and 2, 324 I.H.P. and the coal consumption trial shows reasonable results and the mean consumption was 0.445 kg/I.H.P.-Hr.
- 著者
- Stephen A. McCullough Michael A. Fifer Pouya Mohajer Patricia A. Lowry Caitlin O’Callaghan Reen Aaron L. Baggish Gus J. Vlahakes Yuichi J. Shimada
- 出版者
- The Japanese Circulation Society
- 雑誌
- Circulation Journal (ISSN:13469843)
- 巻号頁・発行日
- pp.CJ-17-0959, (Released:2018-03-09)
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 8
Background:The clinical characteristics associated with elevated right atrial pressure (RAP) in hypertrophic cardiomyopathy (HCM) are unknown. Few data exist as to whether elevated RAP has prognostic implications in patients with HCM. This study investigated the clinical correlates and prognostic value of elevated RAP in HCM.Methods and Results:This retrospective cohort study was performed on 180 patients with HCM who underwent right heart catheterization between 1997 and 2014. Elevated RAP was defined as >8 mmHg. Baseline characteristics, mean pulmonary artery pressure, and mean pulmonary capillary wedge pressure (PCWP) were assessed for association with elevated RAP. The predictive value of elevated RAP for all-cause mortality and the development of atrial fibrillation (AF), ventricular tachycardia/fibrillation (VT/VF), and stroke was evaluated. Elevated RAP was associated with higher New York Heart Association class, dyspnea on exertion, orthopnea, edema, jugular venous distention, larger left atrial size, right ventricular hypertrophy, higher pulmonary artery pressure, and higher PCWP. RAP independently predicted all-cause mortality (adjusted hazard ratio [aHR] 2.18 per 5-mmHg increase, 95% confidence interval [CI] 1.05–4.50, P=0.04) and incident AF (aHR 1.85 per 5-mmHg increase, 95% CI 1.20–2.85, P=0.005). Elevated RAP did not predict VT/VF (P=0.36) or stroke (P=0.28).Conclusions:Elevated RAP in patients with HCM is associated with left-sided heart failure and is an independent predictor of all-cause mortality and new-onset AF.
- 著者
- Yuki Minamoto Kotaro Nakamura Minrui Wang Kei Kawai Kazuma Ohara Jun Noda Enkhbaatar Davaanyam Nobuo Sugimoto Kenji Kai
- 出版者
- Meteorological Society of Japan
- 雑誌
- SOLA (ISSN:13496476)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, pp.33-38, 2018 (Released:2018-03-01)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 16
A large-scale dust event occurred in East Asia during early May 2017, and transported dust was measured all over Japan. We performed an analysis of the entire dust event using multiple sources: a local ceilometer measurement, measurements from an optical particle counter in the Gobi Desert (Dalanzadgad, Mongolia), a study of Dust RGB imagery obtained from Himawari-8, lidar measurements from Japan, and meteorological data. Our results show that three extratropical low pressure systems occurred consecutively in Mongolia and generated dust storms in the Gobi Desert. The dust generated by the third low pressure system was transported to Japan by a cold front and two pressure troughs, which were associated with the low pressure system. Remarkably, the Dust RGB imagery shows both the occurrence and the transportation of the dust, and was able to detect two dust outbreaks in the Horqin Sandy Land of Northern China and their transportation to eastern Japan; this shows that the Horqin Sandy Land was one of the source regions of this dust event.
3 0 0 0 OA 小学校段階におけるプログラミング教育の実践に向けた教員の課題意識と研修ニーズとの関連性
- 著者
- 黒田 昌克 森山 潤
- 出版者
- 日本教育工学会
- 雑誌
- 日本教育工学会論文誌 (ISSN:13498290)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.Suppl., pp.169-172, 2018-03-01 (Released:2018-03-01)
- 参考文献数
- 5
本研究では,全国の小学校教員を対象にプログラミング教育の課題や教員研修に対する意識を調査した(n =522).その結果,全体の92.0%がプログラミング教育に関する自己の知識・理解の不足に課題を感じていた.教員研修で得たい情報としては,81.4%がモデル授業の実践事例が必要と回答した.しかし,現任校の情報機器整備の不十分さに課題意識を持っている小学校教員がプログラミング教育のカリキュラム案に必要性を感じる傾向が強いなど,教員研修の内容に対するニーズは,課題意識の持ち方によって異なっている傾向が示された.
- 著者
- Kengo Maeda Tomoyuki Shiraishi
- 出版者
- The Japanese Society of Internal Medicine
- 雑誌
- Internal Medicine (ISSN:09182918)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.5, pp.745-750, 2018-03-01 (Released:2018-03-01)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 3
Japanese people born before World War II learned Japanese kana (Japanese syllabograms) writing in a style that is not currently used. These individuals had to learn the current style of kana orthography after the war. An 85-year-old man was taken to our hospital by his family who were surprised by his diary. It was written with kanji (Japanese ideograms) and katakana using the prewar style. A neuropsychological examination revealed impaired recall of hiragana. Neuroimaging studies revealed atrophy of the left fronto-parietal lobe and hypoperfusion of the left frontal lobe. His allographic agraphia might have resulted from the disturbance of the current style of kana orthography.
3 0 0 0 OA 内分泌異常による性機能障害
- 著者
- 角谷 秀典 始関 吉生 小竹 忠 高原 正信 島崎 淳
- 出版者
- 一般社団法人 日本泌尿器科学会
- 雑誌
- 日本泌尿器科学会雑誌 (ISSN:00215287)
- 巻号頁・発行日
- vol.82, no.7, pp.1091-1096, 1991-07-20 (Released:2010-07-23)
- 参考文献数
- 15
内分泌異常による性機能障害19例について臨床的検討をおこなた. 性腺機能低下症によるものは, 低ゴナドトロピン性13例, 高ゴナドトロピン性3例の16例であり, 高プロラクチン血症6例 (うち3例は, 低ゴナドトロピン性性腺機能低下症合併) であった. 主訴は, 性欲低下11例, 勃起不全12例, 射精障害14例であった. 性腺機能低下症では射精の障害されている例が多く, 一方高プロラクチン血症では射精の保たれているものが比較的多かった. 性腺不全症における血清テストステロン値は200ng/dl以下であり, 100ng/dl以下になると, 性欲低下を高率にみとめ, 勃起は保たれている例をみたが, 1例を除く全例で射精障害をみた. 低ゴナドトロピン性性腺機能低下症例のゴナドトロピン療法の効果は, hCG負荷試験の反応良好なもの, 精巣容積の保たれている例では, 良好であった.
- 著者
- Yoshiharu Kawaguchi
- 出版者
- The Japanese Society for Spine Surgery and Related Research
- 雑誌
- Spine Surgery and Related Research (ISSN:2432261X)
- 巻号頁・発行日
- pp.2017-0007, (Released:2018-02-28)
- 被引用文献数
- 23
This is a review paper on the topic of genetic background of degenerative disc diseases in the lumbar spine. Lumbar disc diseases (LDDs), such as lumbar disc degeneration and lumbar disc herniation, are the main cause of low back pain. There are a lot of studies that tried to identify the causes of LDDs. The causes have been categorized into environmental factors and genetic factors. Recent studies revealed that LDDs are mainly caused by genetic factors. Numerous studies have been carried out using the genetic approach for LDDs. The history of these studies is divided into three periods: (1) era of epidemiological research using familial background and twins, (2) era of genomic research using DNA polymorphisms to identify susceptible genes for LDDs, and (3) era of functional research to determine how the genes cause LDDs. This review article was undertaken to present the history of genetic approach to LDDs and to discuss the current issues and future perspectives.
- 著者
- Tomoichiro Asano Midori Fujishiro Akifumi Kushiyama Yusuke Nakatsu Masayasu Yoneda Hideaki Kamata Hideyuki Sakoda
- 出版者
- The Pharmaceutical Society of Japan
- 雑誌
- Biological and Pharmaceutical Bulletin (ISSN:09186158)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.9, pp.1610-1616, 2007-09-01 (Released:2007-09-01)
- 参考文献数
- 44
- 被引用文献数
- 29 56
Inositol phospholipids phosphorylated on D3-position of their inositol rings (3-phosphoinositides) are known to play important roles in various cellular events. Activation of PI (phosphatidylinositol) 3-kinase is essential for aspects of insulin-induced glucose metabolism, including translocation of GLUT4 to the cell surface and glycogen synthesis. The enzyme exists as a heterodimer containing a regulatory subunit and one of two widely-distributed isoforms of the p110 catalytic subunit: p110α or p110β. Activation of PI 3-kinase and its downstream AKT has been demonstrated to be essential for almost all of the insulin-induced glucose and lipid metabolism such as glucose uptake, glycogen synthesis, suppression of glucose output and triglyceride synthesis as well as insulin-induced mitogenesis. Accumulated PI(3,4,5)P3 activates several serine/threonine kinases containing a PH (pleckstrin homology) domain, including Akt, atypical PKCs, p70S6 kinase and GSK.In the obesity-induced insulin resistant condition, JNK and p70S6K are activated and phosphorylate IRS-proteins, which diminishes the insulin-induced tyrosine phosphorylation of IRS-proteins and thereby impairs the PI 3-kinase/AKT activations. Thus, the drugs which restore the impaired insulin-induced PI 3-kinase/AKT activation, for example, by suppressing JNK or p70S6K, PTEN or SHIP2, could be novel agents to treat diabetes mellitus.
- 著者
- 武藤 崇 前川 久男
- 出版者
- 一般社団法人 日本特殊教育学会
- 雑誌
- 特殊教育学研究 (ISSN:03873374)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.1, pp.91-96, 2000-06-30 (Released:2017-07-28)