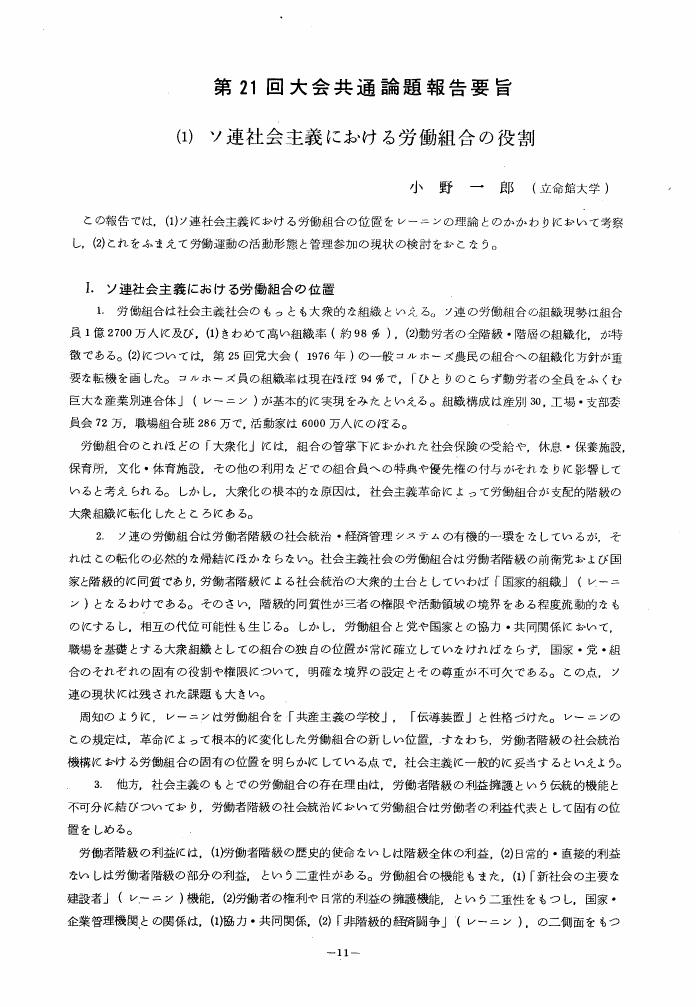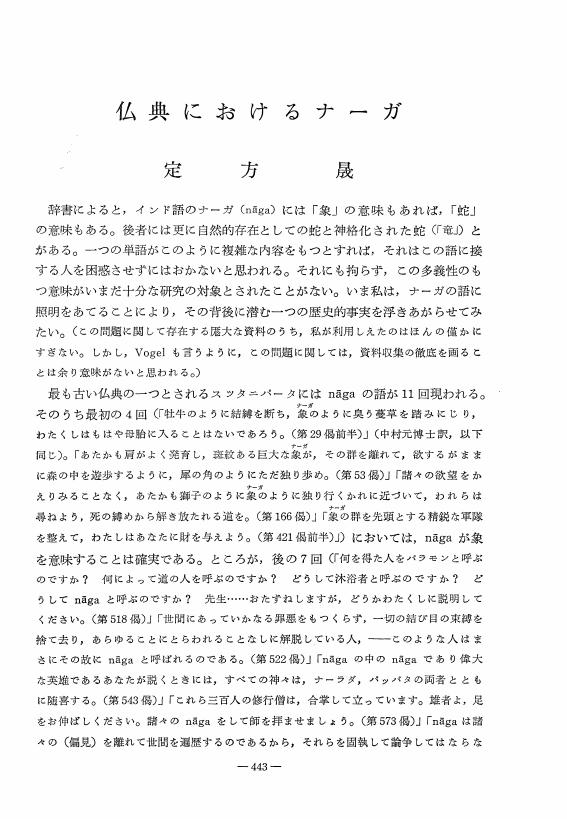- 著者
- 露木 恵美子
- 出版者
- 研究・イノベーション学会
- 雑誌
- 研究 技術 計画 (ISSN:09147020)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.1, pp.39-57, 2019-03-20 (Released:2020-06-30)
- 参考文献数
- 26
This paper attempts to construct a ba ("field") theory toward collective creativity. Ba is a foundation of knowledge creation. I define ba as "a time-space given meaning by humans' inter-subjective/inter-corporeal relationality." In order to create a ba model, I introduce concepts from Husserl's inter-subjectivity and Merleau-Ponty's inter-corporality in phenomenology as generative principles and use Bio holonics based on Nishida Kitaro's basho theory as a foundation. Furthermore, I introduce Yamaguchi's three layers model of phenomenology. The third layer in Yamaguchi's theory is highly related to the transcendental status of human's creativity. Through these theoretical background, I am able to highlight the characteristics of ba, their generative mechanisms, as well as their functioning and effectiveness in collective creativity.
2 0 0 0 OA 創造性の枠組み・測定手法に関するレビュー論文の紹介
- 著者
- 清水 大地
- 出版者
- 日本認知科学会
- 雑誌
- 認知科学 (ISSN:13417924)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.2, pp.283-290, 2019-06-01 (Released:2019-12-01)
- 被引用文献数
- 1
1950 年のAPA 会長就任講演において,知能に関する研究者であるGuilford は創造性研究の必要性に関する重要な指摘を行った.その指摘に伴い,数多くの創造性に関する研究がこれまで心理学や認知科学において蓄積されてきた.特に,近年は情報技術やAI の発展に伴い,ヒトの有する新奇なモノを生成するcreativity という概念に再び大きな着目が集まりつつある.例えば2018 年度には,アメリカのオレゴン州において第1 回のCreativity Conference が開催され,Csikszentmihalyi やSternberg といった名だたる研究者を含む数多くの研究者・実践者が集まり活発な議論が繰り広げられた.また2019 年度には,Cognitive Science Society のAnnual Conference(Cog Sci 2019) においてcreativity がテーマとして掲げられている. このような興味・関心の高まりと並行して,近年の創造性研究においては,対象とする創造性の定義や枠組みを見直そうとする機運が高まっている.紹介する各論文が主張する通り,creativity という曖昧で抽象的な存在を対象にした研究を行う際には,その対象をどのようなものと理解するのか,という定義や枠組みに関する問題が常に付随する.例えばRhodes (1961) による創造性を捉える観点を整理したFour P’s Approach (Person, Process,Product, Press) がその代表として挙げられるだろう.特にこれまでの心理学や認知科学では,主に個人の高次認知過程や特性に焦点を当てたアプローチが営まれてきた.一方近年では,Csikszentmihalyi (1991) のSystems model のように,創造性を個人・環境・社会との関係性の中から生じるものと捉えて検証する試みも徐々に営まれつつある.以上を踏まえ,本稿ではcreativity に関する定義・枠組み・測定手法に関する包括的な整理や問い直しを試みた論文を3 本紹介する. 以上の論文を参照することにより,暗黙的な背景設定の下で行われる傾向の強い創造性という概念を今一度考え直すことを本稿は目的とする.とはいえ定義・枠組みに関する一部の論文を取り上げたにとどまっており,あくまで最近の動向としてご確認いただければ幸いである.
2 0 0 0 OA 理容業における労働と技術 制度化の視点から
- 著者
- 藤﨑 朋子
- 出版者
- 日本労働社会学会
- 雑誌
- 労働社会学研究 (ISSN:13457357)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, pp.31-63, 2011 (Released:2022-04-15)
- 参考文献数
- 16
This paper aims to examine the process by which barbers' techniques and labour became institutionalised in the formative years of the barber industry in Japan.) Drawing on secondary sources and interviews with the staff of a vocational school, the paper focuses on the role of a textbook on haircutting theory, which was widely consumed among barbers and students at barber schools and that was responsible for the consolidation of what was then considered to be standard techniques. The training of barbers, which had hitherto been based on the apprentice system, was unified into school education system during the 1950s that called for a partial amendment of the Barber Law. Meanwhile, with a view to ensuring barbers' effciency in work and management, the Barbers Union brought the theory and techniqucs of haircutting into modules at barber schools. The findings demonstrate that, although the standardised techniques of haircutting promised barbers rational labour, their uniformity turned so obsolete in the wake of Japan's consumer society in the 1970s onwards that they have held little appeal to students in hairdressing. As a result, the standardisation of barbers' techniques and labour has given rise to conflict, which has eventually led to the decline in the number of barbers in favour of beauticians.
2 0 0 0 OA オバマ政権下における紛争介入政策の検証 ――介入と不介入の狭間で
- 著者
- 西住 祐亮
- 出版者
- 国際安全保障学会
- 雑誌
- 国際安全保障 (ISSN:13467573)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.1, pp.60-78, 2017-06-30 (Released:2022-04-01)
2 0 0 0 OA 紹介天体と軌道の力学
- 著者
- 長沢 工
- 出版者
- 日本測地学会
- 雑誌
- 測地学会誌 (ISSN:00380830)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.3, pp.189, 1998-09-25 (Released:2010-09-07)
2 0 0 0 OA 糊化過程における馬鈴薯澱粉粒の構造と力学的特性
- 著者
- 加藤 寿美子 松生 勝
- 出版者
- The Japan Society of Home Economics
- 雑誌
- 家政学雑誌 (ISSN:04499069)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.1, pp.3-12, 1983-01-20 (Released:2010-03-10)
- 参考文献数
- 17
馬鈴薯澱粉の糊化過程における構造と物性の変化について検討した.糊化のさいの澱粉濃度依存性については, 1~6%懸濁液では低濃度ほど最高粘度値は小で, 最高粘度到達温度は高く, 光散乱像, 偏光十字の消失は速やかであった.加熱過程における濃度別粘度特性と偏光顕微鏡ならびに光散乱像による粒子の崩壊挙動は矛盾しなかった.加熱が急速に進行する場合は, ミセルのランダムな配向やその崩壊は緩慢な加熱より遅れて生じた.単一馬鈴薯澱粉粒の光散乱 {象は粒子の形状や内部構造を反映し, 小角度側のローブは楕円体の長軸方向に垂直に伸び, さらに高角度側に高次の強度極大を示した.これは形成核を中心に発達した同心円状の層状組織の半径方向への周期性によるものと推定される.
2 0 0 0 OA 第21回大会共通論題報告要旨 (1)ソ連社会主義における労働組合の役割
- 著者
- 小野 一郎
- 出版者
- 比較経済体制学会
- 雑誌
- 社会主義経済学会会報 (ISSN:18839789)
- 巻号頁・発行日
- vol.1982, no.19, pp.11-13, 1982-03-01 (Released:2009-07-31)
2 0 0 0 OA 油圧ダンパを用いた鉄道車両用上下制振システムの開発
- 著者
- 菅原 能生
- 出版者
- 公益社団法人 計測自動制御学会
- 雑誌
- 計測と制御 (ISSN:04534662)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.9, pp.668-671, 2015-09-10 (Released:2015-09-25)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 1
- 著者
- 松永 武 ユーリ トカチェンコ
- 出版者
- 一般社団法人 日本原子力学会
- 雑誌
- 日本原子力学会誌ATOMOΣ (ISSN:18822606)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.10, pp.684-688, 2011 (Released:2019-09-06)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 1 1
福島原子力発電所の損壊により大気中に放出された放射性核種は,地表面の広域汚染をもたらしている。地表面土壌に沈着した放射性核種の一部は河川に移行する。河川での放射性核種の移行は長期的である一方,降雨時の短期変化も重要であり,さまざまな時間スケールを伴っている。また,放射性核種ごとの挙動の相違も大きい。本稿では,チェルノブイリ事故・大気圏内核実験影響の関連研究を参照し,河川における放射性核種の移行の特徴をまとめた。
2 0 0 0 OA 日本におけるラウンドアバウトの実測最大交通量と交通容量の分析
- 著者
- 神戸 信人 尾高 慎二 康 楠 中村 英樹 森田 綽之
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 土木学会論文集D3(土木計画学) (ISSN:21856540)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.5, pp.I_1017-I_1025, 2015 (Released:2015-12-21)
- 参考文献数
- 5
近年,我が国では,地域の自発的な取り組みによりラウンドアバウトの社会実験や導入事例が増え,平成25年6月には道路交通法の一部を改正する法律が成立し,ラウンドアバウトが環状交差点として法的に位置付けられた.一方,未だラウンドアバウトの導入事例が少ないため,ラウンドアバウトを導入する際に必要となる,自動車や横断歩行者・自転車の交通状況の実測値を踏まえた交通容量上の判断基準は明確になっていないのが現状である.本研究では,ラウンドアバウト運用のされている既存円形交差点やラウンドアバウト社会実験での観測データを用いて,実現交通量の特性を分析した上で,軽井沢町六本辻ラウンドアバウトで観測された交通容量に関する考察を行うとともに,提案されている横断歩行者等を考慮した流入部交通容量推定式との比較を行う.
- 著者
- Motoki Tanaka Katsuyuki Hamasaki Shigeki Dan
- 出版者
- Carcinological Society of Japan
- 雑誌
- Crustacean Research (ISSN:02873478)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, pp.69-78, 2023-09-01 (Released:2023-09-01)
- 参考文献数
- 24
- 被引用文献数
- 1
We conducted two laboratory experiments to evaluate the dietary effects of phytoplankton and zooplankton on the larval survival, duration and growth of the amphidromous atyid shrimp Atyopsis spinipes. In the first experiment, commercially preserved or cultured phytoplankton Tetraselmis sp. and cultured zooplankton rotifers were used to rear larvae. In the second experiment, cultured Tetraselmis and rotifers were used to feed larvae for 17 days after hatching, after which the effect of supplementing their diet with Artemia nauplii was tested. The effects of different culture vessel volumes (8 mL and 40 mL) on larval performance were also assessed. In the first experiment, larvae fed only with preserved Tetraselmis did not survive to the juvenile stage, whereas larvae fed with rotifers showed better survival and development. In the second experiment, most larvae receiving Artemia supplementation survived to the juvenile stage. Larvae cultured in larger containers (40 mL) had significantly higher survival rates than those cultured in smaller containers (8 mL). The present study demonstrates larval culture methodologies for A. spinipes that can promote the development of larvae into the juvenile stage with high survival rates.
- 著者
- タピア フリアン タピア・デ・アルバレス アスンタ 藤田 護
- 出版者
- アンデス・アマゾン学会
- 雑誌
- アンデス・アマゾン研究 (ISSN:24340634)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.19-51, 2023-12-20 (Released:2023-12-21)
- 参考文献数
- 14
本稿は、アイマラ語による口承の物語や歴史語りを原文対訳の形式で公開しつつ、それぞれの語りの特徴について考察を加えるという、藤田が展開してきた取り組みの一環を構成する。ここでとりあげるのは、弟フリアン・タピアと姉アスンタ・タピア・デ・アルバレスによって語られた、両姉弟の祖父がキリワヤ(ボリビアのラパス県ムリーリョ郡)のアシエンダ領主によって虐待されていたのに対し、祖母がラパスの街に住む自身の姉妹の結婚相手の軍人(大佐)を頼り、大佐からの働きかけでこの虐待を止めてもらうという、家族の中で伝承されてきたオーラルヒストリーである。冒頭Ⅰ章では、どのような協力関係の下でこの調査が行われたかについて述べる。Ⅱ章では、この語りのあらすじを示す。Ⅲ章では、この語りがアイマラの人々と支配階層のあいだのどのような社会関係を示しているか、姉と弟で語りの強調点がどのように異なっていて、またどの点は共通で踏まえられているか、そしてこの語りのアイマラ語の文体にどのような特徴が見られるかについて考察する。Ⅳ章では、アイマラ語の表記や、訳に用いるスペイン語のバリアント(アンデス・スペイン語)とその意義について述べた後で、原文対訳テクストを掲げる。Ⅴ章では、結論と今後の展望を述べる。
- 著者
- Yasuyuki Shiraishi Yuka Kurita Hiromasa Mori Kazuyuki Oishi Miyuki Matsukawa
- 出版者
- The Japanese Circulation Society
- 雑誌
- Circulation Journal (ISSN:13469843)
- 巻号頁・発行日
- pp.CJ-23-0440, (Released:2023-12-22)
- 参考文献数
- 28
Background: This retrospective observational study investigated the incidence of worsening renal function (WRF) in patients hospitalized for heart failure (HF) and treated with intravenous diuretics in Japan.Methods and Results: Associations between WRF at any point and HF treatments, and the effects of WRF on outcomes were evaluated (Diagnosis Procedure Combination database). Of 1,788 patients analyzed (mean [±SD] age 80.5±10.2 years; 54.4% male), 641 (35.9%) had WRF during a course of hospitalization for worsening HF: 208 (32.4%) presented with WRF before admission (BA-WRF; estimated glomerular filtration rate decreased by ≥25% from baseline at least once between 30 days prior to admission and admission); 44 (6.9%) had WRF that persisted before and after admission (P-WRF); and 389 (60.7%) had WRF develop after admission (AA-WRF). Delayed initial diuretic administration, higher maximum doses of intravenous diuretics during hospitalization, and diuretic readministration during hospitalization were associated with a significantly higher incidence of AA-WRF. Patients with WRF at any time point were at higher risk of death during hospitalization compared with patients without WRF, with adjusted hazard ratios of 3.56 (95% confidence interval [CI] 2.23–5.69) for BA-WRF, 3.23 (95% CI 2.21–4.71) for AA-WRF, and 13.16 (95% CI 8.19–21.15) for P-WRF (all P<0.0001).Conclusions: Forty percent of WRF occurred before admission for acute HF; there was no difference in mortality between patients with BA-WRF and AA-WRF.
2 0 0 0 OA 酒母 (1)
- 著者
- 黒須 猛行
- 出版者
- 公益財団法人 日本醸造協会
- 雑誌
- 日本醸造協会誌 (ISSN:09147314)
- 巻号頁・発行日
- vol.93, no.5, pp.334-343, 1998-05-15 (Released:2011-09-20)
- 参考文献数
- 2
優良酵母を安全かつ大量に培養する工程が, 酒母造りである。酒母にはいろいろな種類があるが, 重要ポイントは共通である。そこで, 今回は酒母の基本技術について, 著者に解説していただいた。
2 0 0 0 OA 一九三〇年代 母親の衛生実践の一局面 新中間層家庭における
- 著者
- 宝月 理恵
- 出版者
- 社会学研究会
- 雑誌
- ソシオロジ (ISSN:05841380)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.3, pp.125-141, 2007-02-28 (Released:2016-03-23)
- 参考文献数
- 27
2 0 0 0 OA 行為と責任の同時存在の原則
- 著者
- 石井 徹哉
- 出版者
- 日本刑法学会
- 雑誌
- 刑法雑誌 (ISSN:00220191)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.2, pp.242-256, 2006-01-30 (Released:2020-11-05)
2 0 0 0 OA リン酸エッチングが象牙質被着面に与える影響
- 著者
- 戸井田 哲也 中林 宣男
- 出版者
- 一般社団法人 日本歯科理工学会
- 雑誌
- 歯科材料・器械 (ISSN:02865858)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.3, pp.231-240, 1996-05-25 (Released:2018-04-06)
- 参考文献数
- 28
- 被引用文献数
- 4
酸による脱灰は象牙質コラーゲンを変性させる場合があり, この脱灰象牙質は乾燥により容易に収縮する. 収縮した脱灰象牙質のモノマー透過性は低いため, そこに樹脂含浸象牙質を生成させることは困難である. 研削面の一部をプロテクトバニッシュで保護した後に接着操作を行い, その接着縦断面を塩酸および次亜塩素酸ナトリウムに浸漬させてSEM観察することは, 樹脂含浸象牙質の生成のメカニズムを理解するのに有効な方法である. この観察法により, リン酸のエッチング時間を延長すると象牙質の脱灰はそれだけ深く進行し, 乾燥による脱灰象牙質の収縮の度合いも大きくなること, リン酸の脱灰力は解離したリン酸の濃度と量に関係することを明らかにすることができた.
2 0 0 0 OA 3.ワクチン
- 著者
- 加藤 達夫
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.91, no.10, pp.2841-2844, 2002-10-10 (Released:2008-06-12)
- 参考文献数
- 3
2 0 0 0 OA 仏典におけるナーガ
- 著者
- 定方 晟
- 出版者
- Japanese Association of Indian and Buddhist Studies
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.1, pp.443-437, 1971-12-31 (Released:2010-03-09)
2 0 0 0 OA 呼吸困難のコントロールがオピオイドのみでは難しくミダゾラムを併用した終末期がん患者の要因
- 著者
- 奥田 有香 栗山 俊之 月山 淑 松田 能宣 山口 崇 森 雅紀 下川 敏雄 川股 知之
- 出版者
- 日本緩和医療学会
- 雑誌
- Palliative Care Research (ISSN:18805302)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.4, pp.247-252, 2023 (Released:2023-11-24)
- 参考文献数
- 12
【目的】終末期がん患者の呼吸困難に対してオピオイドのみではコントロールが難しくミダゾラムの併用を必要とした要因を検討した.【方法】2019年4月から2021年7月に当院で呼吸困難緩和目的にオピオイド注射剤を導入したがん患者を抽出し,オピオイドのみ投与したオピオイド単独群,オピオイドにミダゾラムを併用したミダゾラム併用群に分類し後方視的に検討した.【結果】適格患者は107人で,オピオイド単独群85人(79.4%),ミダゾラム併用群22人(20.6%)であった.単変量解析では60歳未満(p=0.004)と男性(p=0.034),多変量解析では60歳未満(OR=5.34, 95%CI: 1.66–17.21; p=0.005)がミダゾラム併用と有意に関連していた.【結論】呼吸困難に対してオピオイドを使用したがん患者において60歳未満がミダゾラム併用に関連する因子であった.