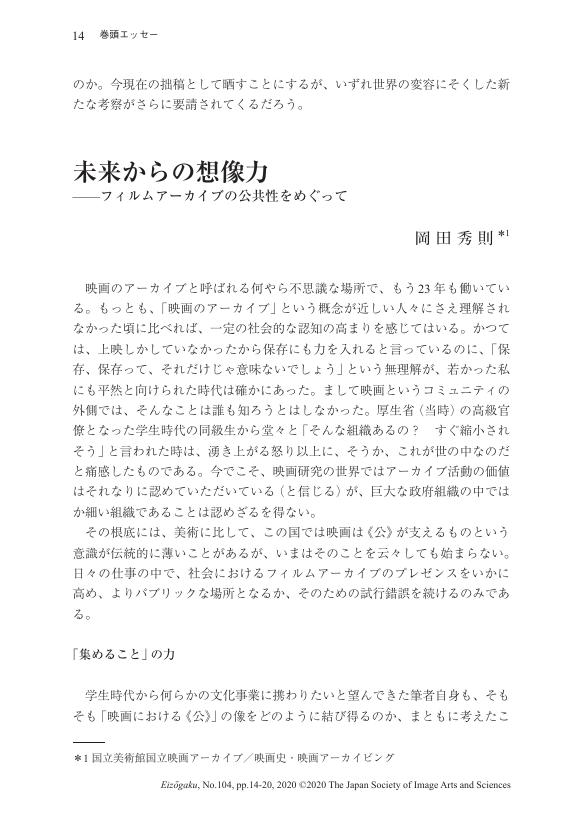2 0 0 0 OA 発熱植物ハスの体温調節機構に関する制御工学的解析
- 著者
- 広間 達夫 伊藤 菊一 原 道宏 鳥巣 諒
- 出版者
- 日本生物環境工学会
- 雑誌
- 植物環境工学 (ISSN:18802028)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.2, pp.52-58, 2011-06-01 (Released:2011-06-01)
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 1
発熱期のハスの体温調節機構を解析するために, ハスを鉢栽培し, 屋外で開花開始から種子結実終了までのハスの花托体温と気温の関係を調べる屋外実験を実施した. 同時に, 発熱期および無発熱期のハスを恒温槽に入れ槽内温度を階段関数的に変化させそのときの花托体温のステップ応答を測定する屋内実験を実施した. (i)これら屋外と屋内の2実験において, 周囲気温を入力, そのときの花托体温を出力とする入出力関係を伝達関数で表現した. (ii)他方, 屋外実験(太陽光による一種の周波数応答実験)の解析を行い, 自然環境下の発熱期のハスが気温の変動を組み込んで自己の花托体温を決定するというハスの体温調節モデルを導出した. (iii)最後に, iとiiの結果に制御理論を適用して, ハスの体温制御機構を総合的に検討した. 得られた主な結果は以下の通りである.(1)発熱期のハスは, ある種の体内温度計を内臓し, これと時々刻々変動する気温の影響の和を目標値とする, 可変目標値モデル提案した.(2)発熱の活性化の程度は活性化係数で表すことができ, 発熱はステージ2の場合が, 最も活性化係数が大きくて発熱活動が最も盛んであることを確認した.(3)ハスの花托体温と気温依存温度の差は発熱相当温度であり, 花托は発熱相当温度分の熱産生を行って体温を気温より高温に保っていると考えられる.(4)ハスの体温制御系は, 発熱期の花托体温をフィードバックし可変目標値との偏差を制御器に導くという制御機構で表すことができる.(5)気温からハス花托に至る伝達関数は一次遅れ系で, 発熱期の制御器は積分動作で表現することができる.
2 0 0 0 OA スポットウェルドボンド継手の疲労強度と疲労破壊機構に及ぼす鋼材強度レベルの影響
- 著者
- 藤井 朋之 東郷 敬一郎 山本 崇博 鈴木 幸則 島村 佳伸 尾嶋 良文
- 出版者
- 公益社団法人 日本材料学会
- 雑誌
- 材料 (ISSN:05145163)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.12, pp.770-777, 2013-12-15 (Released:2013-12-20)
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 4 5
In this paper, fatigue tests and finite element analysis are carried out on spot weld-bonded joints of mild steel (270MPa class) and ultra-high strength steel (980MPa class) in order to investigate influence of strength level of base steels on fatigue strength and fatigue fracture behavior of spot weld-bonded joints. From the fatigue tests and finite element analysis, the following results are obtained : (1) The fatigue strength of the spot weld-bonded specimen is higher than that of the spot welded specimen. (2) The fatigue limit of the spot weld-bonded specimens of the ultra-high strength steel is higher than that of the mild steel. (3) The interfacial debonding propagates from the adhesive edge to a nugget edge, and the fatigue crack initiates at the nugget edge in both steels. (4) The fatigue strength of spot weld-bonded specimens is improved because the stress concentration at the nugget edge is reduced by adhesive bonding during large part of fatigue life.
2 0 0 0 OA 複素剛性モデルを用いた免震構造物の地震時応答変位制御
- 著者
- 五十子 幸樹 井上 範夫
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会構造系論文集 (ISSN:13404202)
- 巻号頁・発行日
- vol.75, no.655, pp.1653-1660, 2010-09-30 (Released:2010-10-20)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 3 1
Study on frequency transfer characteristics of a displacement-dependent damper modeled by complex stiffness shows that it has advantage in reduction of base shear and maximum response acceleration of the superstructure of a base-isolated building compared with a conventional velocity-dependent damper such as an oil damper. To realize a displacement-dependent damper, a simple control rule to simulate the complex damping model for active or semi-active dampers is proposed.
2 0 0 0 OA 時代は前へ進んでいるのか? ―「おんな紋」から考える選択的夫婦別姓問題
- 著者
- 遠藤 薫
- 出版者
- 公益財団法人 日本学術協力財団
- 雑誌
- 学術の動向 (ISSN:13423363)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.12, pp.12_102-12_105, 2016-12-01 (Released:2017-04-07)
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 1 1
- 著者
- 近藤 克則 芦田 登代 平井 寛 三澤 仁平 鈴木 佳代
- 出版者
- 公益財団法人 医療科学研究所
- 雑誌
- 医療と社会 (ISSN:09169202)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.1, pp.19-30, 2012 (Released:2012-04-28)
- 参考文献数
- 28
- 被引用文献数
- 12 11
日本の高齢者における等価所得・教育年数と死亡,要介護認定,健康寿命の喪失(死亡または要介護認定)との関連を明らかにすることを目的とした。協力を得られた6自治体に居住する高齢者14,652人(平均年齢71.0歳)を4年(1,461日)間追跡し,要介護認定および死亡データを得た。Cox比例ハザードモデルを用い,死亡,要介護認定,健康寿命の喪失をエンドポイントに等価所得・教育年数(共に5区分)を同時投入して年齢調整済みハザード比(HR)を男女別に求めた。その結果,男性では,最高所得層に比べ最低所得層でHR1.55-1.75,最長教育年数に比べ最短教育年数層ではHR1.45-1.97の統計学的にも有意な健康格差を認めた。一方,女性では,所得で0.92-1.22,教育年数で1.00-1.35と有意な健康格差は認めなかった。等価所得と教育年数の2つの社会経済指標と用いた健康指標(死亡,要介護認定,健康寿命の喪失)とで,健康格差の大きさも関連の程度も異なっていた。日本の高齢男性には,統計学的に有意な健康格差を認めたが,女性では認めなかった。これは健康格差が(少)ない社会・集団がありうる可能性を示唆しており,所見の再現性の検証や健康格差のモニタリング,生成機序の解明などが望まれる。
2 0 0 0 OA 鳩の蛔虫Ascaridia Columbae (Gmelin, 1790)に就て
- 著者
- 杉本 正篤
- 出版者
- 公益社団法人 日本獣医学会
- 雑誌
- 中央獸醫會雑誌 (ISSN:18839096)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.4, pp.365-371, 1928-04-20 (Released:2008-10-24)
- 参考文献数
- 7
- 著者
- 田切 美智雄 堀江 憲路 足立 達朗
- 出版者
- 一般社団法人 日本地質学会
- 雑誌
- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)
- 巻号頁・発行日
- vol.122, no.6, pp.231-247, 2016-06-15 (Released:2016-08-01)
- 参考文献数
- 81
- 被引用文献数
- 2 6
日立変成地域のカンブリア系について,ジルコンU-Pb SHRIMP年代値を追加し,既報の年代値をまとめ,各地層を再定義し,地質図を改めた.層序については,早期から晩期のカンブリア系を日立火山深成複合岩体として一括し,その中に赤沢層,玉簾層,変成花崗岩類,変成ポーフィリィを含めた.玉簾層の一部を分離して滝沢層を新設した.西堂平層の堆積年代は白亜紀前期である.さらに,白亜紀後期に火成岩貫入と中圧型変成作用が起った.これは阿武隈帯の竹貫変成岩類の変成履歴とも共通し,東北日本列島でこのような急激なテクトニクスが起こった時期があったと推定した.古第三紀の中央構造線が日本列島全体を縦断していたと仮定して,日本海形成前における,カンブリア系を含む日立古生層と東北日本列島基盤の復元を試み,日立古生層や阿武隈帯は中国東北部の佳木斯・ハンカ地帯に近接することを示した.カンブリア系日立火山深成複合岩体は北中国地塊の東縁に帰属することを主張した.
2 0 0 0 OA 生体中の微量元素の役割
- 著者
- 山根 靖弘
- 出版者
- Japan Health Physics Society
- 雑誌
- 保健物理 (ISSN:03676110)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.3, pp.269-277, 1990 (Released:2010-02-25)
- 参考文献数
- 4
- 被引用文献数
- 1
- 著者
- 小松 龍世 杉山 佑
- 出版者
- 一般社団法人 日本航空宇宙学会
- 雑誌
- 日本航空宇宙学会誌 (ISSN:00214663)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.6, pp.212-215, 2021-06-05 (Released:2021-06-05)
- 参考文献数
- 1
- 著者
- 向井 伸哉
- 出版者
- 公益財団法人 史学会
- 雑誌
- 史学雑誌 (ISSN:00182478)
- 巻号頁・発行日
- vol.127, no.10, pp.1-30, 2018 (Released:2019-10-20)
本稿は、南仏ラングドック地方の中央に位置するベジエ市とその南九キロメートルに位置するヴァンドレス村を対象に、十四世紀後半の都市文書と村落文書を組み合わせ、都市=農村関係の政治的側面について解明を行う。 十四世紀後半、ベジエのエリート(都市自治体の役職経験者)は、①ベジエの国王役人、②一時的な司法的・行政的任務の遂行者、③国王税・地方税の徴税人、④ベジエのコンシュル(執政官=自治体代表)、⑤金貸し、村の所得税収・資産税収ならびに農作物の購入者、⑥個人的協力者・助言者、⑦自治体弁護士など、様々な資格・役割で村落共同体の前に現れる。 ①②の資格では村に対して司法・行政上の決定権を行使し、③⑤の資格では村に対して財政上の決定権や影響力を行使しつつ、金銭的援助や営利目的の投資を行い、④の資格ではヴァンドレスのコンシュルにある時は対等な関係で助力を与え、ある時は上位の立場からこれを指導し、⑥⑦の資格ではヴァンドレスのコンシュルに様々な助言・助力を与えた。職業の観点からすると、①②には大土地所有者と法曹、③⑤には実業家(商工業)が多く、⑦は法曹が占めている。 彼ら都市エリートは、ヴァンドレスのエリートに対して、経済的、学識的、政治的資本の所有という点で圧倒的優位に立っており、これらの資本を利用しながら、村を時に支配し、時に保護した。 十四世紀後半の過酷な戦争環境を生き延びる上で、たしかに村は外部からの軍事的保護を頼りにせず自衛機能を強化した。しかしながら、軍事以外の分野では卓越した経済的・学識的・政治的資本を有する都市エリートの保護を必要とした。領主制から王朝国家へと統治レジームが移行する一方で、戦争による治安悪化が常態化し外部権力からの軍事的保護が無効になった中世後期南フランスにおいて、村落の保護者の役割は、もはや領主ではなく、いまだ君主でもなく、他ならぬ地域首府の都市エリートによって担われたのだ。
2 0 0 0 OA 日本の少子化と女子労働 ―新家政学的接近の限界に関する考察―
- 著者
- 今井 博之
- 出版者
- 数理社会学会
- 雑誌
- 理論と方法 (ISSN:09131442)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.2, pp.199-210, 2001-10-31 (Released:2016-09-30)
- 参考文献数
- 16
合計特殊出生率が1.4をもしたまわっていることが表すように、近年の日本では少子化が深刻となっているが、その原因分析においては、女子労働に注目して出生力を出産・育児の機会費用と結びつける新家政学的接近が有力な位置を占めている。本稿は、その日本における有効性を検討することを目的としており、2つの観点のそれぞれから否定的な結論を導く。 第1に、バッツ=ウォード型モデルによる時系列分析を試みる。既存研究を概観して2つの式をとりあげ、いずれが表すモデルも1968-2000年の日本の合計特殊出生率に適合しないことを示す。 第2に、新家政学的接近が出生力と妻の労働力参加との負の関係を前提としていることに注目し、都道府県別データによるクロス・セクション分析を行う。出生力の指標としては1995年の「国勢調査」からえられる平均同居児数を用いる。既婚女子については有業の割合をとりあげて、さらに有業の既婚女子については正規雇用の割合をとりあげて分析を行い、出生力と妻の労働力参加との間にむしろ正の関係が観察されることを示す。
2 0 0 0 OA 日本におけるBig Fiveパーソナリティ特性とBMIの関連
- 著者
- 吉野 伸哉 小塩 真司
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 心理学研究 (ISSN:00215236)
- 巻号頁・発行日
- vol.91, no.4, pp.267-273, 2020 (Released:2020-10-25)
- 参考文献数
- 33
- 被引用文献数
- 2
The purpose of this study was to examine the associations between the Big Five personality traits and a person’s body mass index (BMI). We used three large datasets (survey 1, N = 3,063; survey 2, N = 4,242; survey 3, N = 17,471) including Japanese participants and examined the associations using correlation and multiple regression analyses. Consecutively, we conducted a meta-analysis including the results in the present study and a previous study. The results of these analyses show that Conscientiousness is consistently negatively associated with BMI. Extraversion is positively associated with BMI only for male participants. The pattern of relationships between the Big Five personality traits and BMI in Japan is similar to Western countries rather than to other East Asian countries. We discuss these associations in terms of eating habits and lifestyles.
2 0 0 0 OA 未来からの想像力——フィルムアーカイブの公共性をめぐって
- 著者
- 岡田 秀則
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.104, pp.14-20, 2020-07-25 (Released:2020-08-25)
2 0 0 0 OA 細胞内タンパク質のリサイクルとその生理的意義
- 著者
- 田中 啓二
- 出版者
- 公益社団法人 日本栄養・食糧学会
- 雑誌
- 日本栄養・食糧学会誌 (ISSN:02873516)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.4, pp.221-228, 2011 (Released:2011-10-18)
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 1
生体を構成する主要成分であり, 生命現象を支える機能素子であるタンパク質は, 細胞内で絶えずダイナミックに合成と分解を繰り返しており, ヒトでは, 毎日, 総タンパク質の約3%が数分から数カ月と千差万別の寿命をもってターンオーバー (新陳代謝) している。タンパク質分解は, 不良品分子の積極的な除去に関与しているほか, 良品分子であっても不要な (細胞活動に支障をきたす) 場合, あるいは必要とする栄養素 (アミノ酸やその分解による代謝エネルギー) の確保のために, 積極的に作動される。タンパク質分解研究は, 過去四半世紀の間に未曾有の発展を遂げてきたが, 現在なお拡大の一途を辿っており, 生命の謎を解くキープレイヤーとして現代生命科学の中枢の一翼を占めるに至っている。我々はタンパク質分解システムについて分子から個体レベルに至る包括的な研究を継続して進めてきた。その研究小史を振り返りながら, タンパク質分解 (リサイクルシステム) の重要性について概説したい。
- 著者
- Ryo SAITO James K CHAMBERS Takuya E. KISHIMOTO Kazuyuki UCHIDA
- 出版者
- JAPANESE SOCIETY OF VETERINARY SCIENCE
- 雑誌
- Journal of Veterinary Medical Science (ISSN:09167250)
- 巻号頁・発行日
- pp.21-0258, (Released:2021-06-23)
- 被引用文献数
- 14
Meningioma is the most common primary brain tumor in cats, although there are few reports about their pathological features. To investigate the histopathological subtypes and immunohistochemical features including expression of cytokeratin and cell adhesion molecules, 45 cases of feline meningioma were examined. The mean age was 12.5 years (range 6–21 years). No statistically significant sex predilection was observed. Regarding the anatomical location of meningioma, tumors mostly developed in the cerebrum, followed by spinal cord and cerebellum, and multiple meningioma was observed in one cat. Microscopically, linear or focal mineralization was observed in 40 cases and cholesterol cleft was observed in 14 cases. Based on histopathological subtypes, there were 15 fibrous, 22 transitional, 2 meningothelial, 5 atypical, and 1 anaplastic meningiomas. These subtypes are classified into grade 1 (39 cases), grade 2 (5 cases), and grade 3 (1 case). There was no significant difference in the Ki-67 index among histological subtypes or grades. Immunohistochemically, the tumor cells were positive for cytokeratin in 5 cases (12.8%), vimentin in 17 cases (43.6%), E-cadherin in 36 cases (92.3%), β-catenin in 21 cases (53.8%), and N-cadherin in 1 case (2.6%), demonstrating the utility of E-cadherin-immunohistochemistry for the diagnosis of feline meningiomas.
- 著者
- Mizuka Ohtaka Kaori Karasawa
- 出版者
- The Japanese Group Dynamics Association
- 雑誌
- 実験社会心理学研究 (ISSN:03877973)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.2, pp.111-115, 2019 (Released:2019-03-26)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 4
Although previous studies have verified that perspective-taking differs according to the individuals involved and their relationships, the balance between individual and relationship effects remains unclear. Thus, we examined perspective-taking in families based on the social relations model (Kenny, Kashy, & Cook, 2006). We conducted a triadic survey of 380 undergraduates and their fathers and mothers. We analyzed the triadic responses of the 166 families in which all three members completed the survey. It was found that perspective-taking in families is affected by the family itself, each actor, fathers as partners and all dyadic relationships. The relative contributions of individual effects and relationship effects differed between parent-child relationships and marital relationships. We discuss the implications of our findings for enhancing perspective-taking.
2 0 0 0 OA 立方骨サポートインソールが平地および片斜面における立位重心動揺に与える影響
- 著者
- 深木 良祐 髙田 雄一 奥村 宣久 松岡 審爾 内山 英一
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.40 Suppl. No.2 (第48回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.48102091, 2013 (Released:2013-06-20)
【はじめに,目的】 ヒトの立位バランス能力は生活を営む上で重要な能力の一つである.転倒の要因には筋力や協調性などの運動要因,深部覚や視覚・聴覚などの感覚要因,注意や意識や学習などの高次脳機能要因,床や照明や障害物などの外的環境要因があるが,立位バランスにはこれらが大きく影響していると考えられる.外的環境要因への介入に,インソール療法があげられるが,近年,立方骨サポート理論を基に作成されたBMZ社製インソール(以下BMZ)が注目されている.しかし,既存のインソールとBMZについて重心動揺を比較している研究はない.よって本研究の目的では,平地及び片斜面上でのインソールなし時,既存のインソール(インパクトトレーディング社製インソール 以下SUPER feet),BMZについて重心動揺を計測し,効果を明らかにすることとした.【方法】 対象者は足部形状に問題のない(以下通常足)学生20名(男性10名,女性10名),足部扁平足(以下扁平足)の学生20名(男性10名,女性10名)の計40名(身長164.4±8.2cm,体重56.8±7.9kg,靴のサイズ25.2±1.1cm)とし,扁平足の分類にはbony arch index(以下BAI)を用いた.計測には多目的重心動揺計測システムzebris(インターリハ株式会社製)を平地と右片斜面(15度の傾斜台)で計測した.紐なし運動靴でインソールなし,SUPER feet,BMZの総軌跡長と外周面積を計測し3条件で比較した.計測肢位は足間を10cm広げた立位とし,目線上に設置したマークを注視させた.計測は平地,片斜面の順とし,インソールの順はランダムとした.計測時間はそれぞれ30秒とし,条件変更の際1分間の休息を与えた.計測回数は各3回とし,平均値を解析に用いた.各条件での3回の測定値の平均を代表値とし,統計ソフトIBM SPSS statistics Version 19による,2要因に対応があり,1要因に対応のない3元配置分散分析を行い,各統計処理の有意水準は5%とした.【倫理的配慮,説明と同意】 全対象者に対して,事前に書面および口頭で本研究の方法と目的を説明し,研究協力の同意を得た上で実施した.【結果】 総軌跡長では,平地時,通常足でインソールなしは381.0±73.5mm,SUPER feetは365.8±76.2mm,BMZは369.1±73.5mmであり,扁平足でインソールなしは449.2±60.1mm,SUPER feetは412.2±57.9mm,BMZは417.6±73.5mmであった.片斜面時,通常足でインソールなしは1038.2±231.0mm,SUPER feetは1090.0±345.0mm,BMZは1001.4±240.3mmであり,扁平足でインソールなしは1150.9±308.4mm,SUPER feetは1168.5±434.1mm,BMZは1069.8±287.0mmであった.平地と片斜面で有意差が認められたが,インソールと足部環境の間に交互作用が発生した.平地では普通足,扁平足ともにインソールなしと比較し,SUPER feet,BMZ挿入後に有意に減少した(P<0.05).また,片斜面ではインソールなし,SUPER feetと比較し,BMZで有意に減少した(P<0.05).外周面積では,平地時,通常足でインソールなしは72.7±31.0mm²,SUPER feetは71.5±38.6mm²,BMZは82.4±51.1mm²であり,扁平足でインソールなしは103.3±56.5mm²,SUPER feetは91.1±40.0mm²,BMZは99.8±52.8mm²であった.片斜面時,通常足でインソールなしは108.6±70.4mm²,SUPER feetは118.6±109.1mm²,BMZは107.0±76.1mm²であり,扁平足でインソールなしは139.1±70.2mm²,SUPER feetは131.2±88.6mm²,BMZは133.0±71.5mm²であった.平地,片斜面ともにインソール挿入による有意差は認められなかった.【考察】 総軌跡長において,先行研究より内側縦アーチへの適度な圧が平地での重心動揺を小さくするという報告がある.内側縦アーチをサポートするSUPER feetではこれにより総軌跡長が有意に減少したと考える.しかしBMZは3つの足部アーチを1つの連動した足ドームとして捉え,これを支えている立方骨を支持する.よってSUPER feetの挿入による平地での重心動揺が安定した機序とは異なる影響である.片斜面ではインソールなし,SUPER feetと比較し,BMZで有意に減少した.SUPER feetでは片斜面に対して下方の足は足部回外がさらに増加するため,不安定になるのに対し、BMZではSUPER feetと比較し足部のアライメントをより中間位に保持できたものと考えられる.今後インソール挿入後のアライメントの変化についても検討する必要がある.【理学療法学研究としての意義】 本研究より,BMZには不整地における重心動揺距離のコントロールを容易にする効果が示唆された.
2 0 0 0 OA 情報分野の先端科学技術に対するリスク認知―知識要因に着目した検討―
- 著者
- 高木 彩 武田 美亜 小森 めぐみ 今野 将
- 出版者
- 一般社団法人 日本リスク学会
- 雑誌
- リスク学研究 (ISSN:24358428)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.4, pp.213-221, 2021-06-25 (Released:2021-06-23)
- 参考文献数
- 21
Emerging information technologies are rapidly growing and expected to change the social systems drastically. This study investigated the relationships between knowledge and risk perceptions regarding new technologies such as AI, machine learning, self-driving, and VR. We conducted an online survey and measured the risk perception and basic scientific knowledge and domain specific knowledge (subjective and objective knowledge regarding emerging information technologies). The results of hierarchical regression analyses showed that the interactive effect of subjective and objective domain specific knowledge was significant. Participants who rated higher in both of subjective and objective knowledge perceived lower risk than other participants. Basic scientific knowledge was correlated with objective knowledge but not significant predictor of risk perception. The explanatory power of the knowledge factors was lower than institutional trust.
2 0 0 0 OA 閉経期女性の骨代謝における食事と運動の役割
- 著者
- 石見 佳子
- 出版者
- 公益社団法人 日本ビタミン学会
- 雑誌
- ビタミン (ISSN:0006386X)
- 巻号頁・発行日
- vol.90, no.9, pp.415-425, 2016 (Released:2017-12-26)
2 0 0 0 OA 窃盗症の発症過程における認知と行動の変化
- 著者
- 浅見 祐香 野村 和孝 嶋田 洋徳 大石 裕代 大石 雅之
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 心理学研究 (ISSN:00215236)
- 巻号頁・発行日
- pp.92.19053, (Released:2021-03-31)
- 参考文献数
- 30
- 被引用文献数
- 2
The present study aimed to clarify the cognitive and behavioral features of the process from the onset of stealing to the development of kleptomania. We also analyzed the differences between kleptomania and shoplifting for personal gain. Semi-structured interviews were conducted with 25 participants (15 patients with kleptomania, 4 shoplifters, and 6 with other addictions). An analysis based on a modified grounded theory approach (M-GTA) revealed 24 concepts and 5 categories. We identified four stages of the process of kleptomania. The stages were “first theft,” “increasing frequency of stealing,” “pathological stealing” where the act of stealing was more beneficial than the stolen goods, followed by “automatic stealing” whenever they steal automatically in their favorite stores. We identified “breaking dependence on stealing” as the fifth category. In contrast, shoplifters for personal gain did not move into “pathological stealing.” Thus, it is assumed that the development of kleptomania involves a series of processes from starting to steal to addiction, then, it is assumed to enter a dependent stage from the stage of “pathological stealing.”