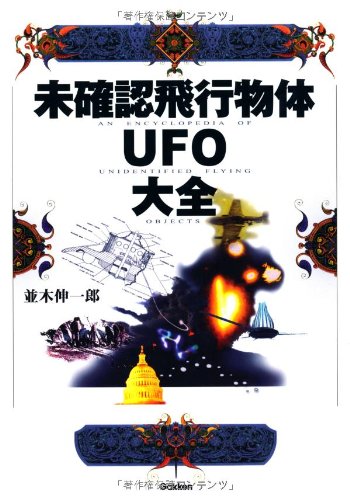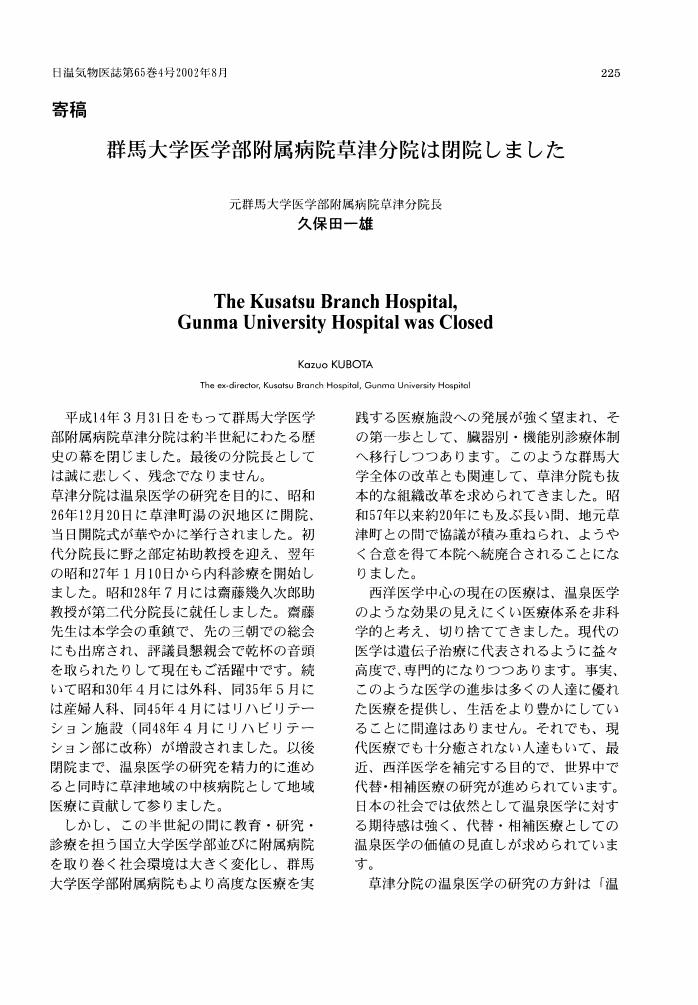4 0 0 0 OA 怒り刺激に対する血液循環応答と心拍変動解析
- 著者
- 山下 政司
- 出版者
- 公益社団法人 日本生体医工学会
- 雑誌
- 生体医工学 (ISSN:1347443X)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.6, pp.843-849, 2011-12-10 (Released:2012-04-10)
- 参考文献数
- 30
There is autonomic specificity in emotion. Objective evaluation for emotion using physiological parameters has some possibilities of applications to the creation of comfortable environment, emotional movies or advertisements, to the human interface of the machine that obeys emotions, and to an understanding of emotions of the patients who cannot speak. As anger correlates with the stress, the psychosomatic disease and coronary heart disease, an understanding of the physiological features is important in medicine. But, the responses of blood circulation and autonomic nerve activities in anger, which is often felt in daily life, are not clear. Therefore, the measurement of blood circulation in anger was introduced, and the autonomic nerve activities and the minimum value of the cross-correlation coefficients between RSA and the respiratory wave (ρmin), which could associate with the autonomic nerve activity, were evaluated. Further, the correlation of the physiological parameters with subjective evaluation was investigated. Anger increased SBP/DBP and maintained their levels for a while. These reasons were estimated by the analysis of Pulse Wave Amplitude to the effects of sympathetic α-adrenergic vasoconstriction of the arteriole and slow metabolism of noradrenaline and adrenaline which must be elicited by anger. Anger did not change HR, but increased double product and maintained its level for a while. On the other hand, the correlation of ρmin with subjective evaluation was obtained. Therefore, ρmin is an effective index to objective evaluation for anger strength.
- 著者
- 三宅 茂太 芦刈 圭一 加藤 真吾 高津 智弘 桑島 拓史 金子 裕明 永井 康貴 亘 育江 佐藤 高光 山岡 悠太郎 山本 哲哉 梁 明秀 前田 愼 中島 淳 日暮 琢磨
- 出版者
- 一般社団法人 日本消化器内視鏡学会
- 雑誌
- 日本消化器内視鏡学会雑誌 (ISSN:03871207)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.12, pp.2533-2543, 2022 (Released:2022-12-20)
- 参考文献数
- 27
【目的】消化管内視鏡検査(Gastrointestinal endoscopy:GIE)は,多くの疾患の早期発見および治療に有用であるが,GIEはコロナウイルス病2019(COVID-19)大流行期における高リスク処置と考えられている.本研究は,医療スタッフが曝露される唾液,胃液および腸液における重症急性呼吸器症候群コロナウイルス2(SARS-CoV-2)陽性割合を明らかにすることを目的とした.【方法】本研究は単一施設における横断研究であり,2020年6月1日から7月31日まで,横浜市立大学附属病院でGIEを受けた患者を対象とした.すべての研究参加者は3mlの唾液を提出した.上部GIEの場合,10mlの胃液を内視鏡を通して採取し,下部GIEの場合,10mlの腸液を内視鏡を介して採取した.主要評価項目は唾液,胃液および腸液中のSARS-CoV-2の陽性率とした.また,SARS-CoV-2の血清特異的抗体や患者の背景情報についても検討した.【結果】合計783検体(上部GIE:560および下部GIE:223)を分析した.唾液検体のPCRでは,全例が陰性であった.一方で,消化管液検体においては2.0%(16/783)がSARS-CoV-2陽性であった.PCR陽性症例とPCR陰性症例の間では,年齢,性別,内視鏡検査の目的,投薬,抗体検査陽性率に有意差は認めなかった.【結論】無症候性の患者において,唾液中に検出可能なウイルスを持たない患者であっても,消化管にSARS-CoV-2を有していた.内視鏡検査の医療スタッフは処置を行う際に感染に留意する必要がある.本研究はUMIN 000040587として登録されている.
4 0 0 0 OA 判例について
- 著者
- 金築 誠志
- 出版者
- 中央ロー・ジャーナル編集委員会
- 雑誌
- 中央ロー・ジャーナル (ISSN:13496239)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.4, pp.3-37, 2016-03-31
実定法上の判例の意義を念頭に置きながら、結論命題とともに一般的命題も主論となり得ることを明らかにしつつ、主論及び傍論の諸類型、決定方法等について論述する。
4 0 0 0 OA 銀行会社要録 : 附・役員録
4 0 0 0 OA 帝政ロシアにおけるノヴォロシア・ベッサラビアの成立 : 併合から総督府の設置まで
- 著者
- 志田 恭子
- 出版者
- 北海道大学スラブ研究センター
- 雑誌
- スラヴ研究 (ISSN:05626579)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, pp.245-268, 2002
4 0 0 0 未確認飛行物体UFO大全
- 著者
- 並木伸一郎著
- 出版者
- 学研マーケティング (発売)
- 巻号頁・発行日
- 2010
4 0 0 0 OA 日本産カキシメジ類の分類学的検討
4 0 0 0 OA 「起き上がるカブトムシ」の観察 環境-行為系の創発
- 著者
- 佐々木 正人
- 出版者
- 日本質的心理学会
- 雑誌
- 質的心理学研究 (ISSN:24357065)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.1, pp.46-62, 2011 (Released:2020-07-09)
床の上に仰向けに置いたカブトムシが,様々な物など,周囲の性質を使って起き上がる過程を観察した。床の溝,タオル,うちわ,鍋敷,チラシ,爪楊枝,リボン(細,太),ビニルヒモ,ティッシュ,T シャツ,シソの葉,メモ用紙,割り箸,フィルムの蓋を起き上がりに利用する虫の行為が記録された(図 1~17)。周囲の性質で起き上がりに利用されたのは,物の網目状の肌理,床とその上に置かれた物の縁・隙間,穴上の陥没,抱え込んで揺らすことのできる物,床とひも状,棒状,円形状の物がつくる隙間であった。これらの観察をまとめるとカブトムシの起き上がりが,1)「地面-単一の脚」(図 18a),2)「変形する物-複数の脚・湾曲した背-地面」(図18b),3)「固い物-複数の脚・湾曲した背-地面」(図 18c)の 3 種の環境-行為系の創発として記述できることが明らかになった。
4 0 0 0 OA 国生み神話の敗戦 ─「国学的なるもの」の表象をめぐって(その一)
- 著者
- 田中 康二
- 出版者
- 皇學館大学
- 雑誌
- 皇學館大学紀要 = Bulletin of Kogakkan University (ISSN:18836984)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.1, pp.1-57, 2023-03-15
- 著者
- 高橋 香苗
- 出版者
- 国際ジェンダー学会
- 雑誌
- 国際ジェンダー学会誌 (ISSN:13487337)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, pp.112-131, 2021 (Released:2022-12-25)
- 参考文献数
- 40
日本社会における母親像は多様化しつつある。その一方でギャル系のファッションを好む母親,いわゆるギャルママをとりまく現状からは,多様化といってもその許容される範囲には,いまだ限界があるのではないかということが示唆される。母親の役割葛藤に関する研究では,母親としての自己と個としての自己の双方の充実が母親にとって重要であることが指摘され,その不均衡さの問題は母親自身の就業や学歴との関連,あるいは異文化という視点から論じられてきた。しかし,外見のイメージにおける母親らしさと自分らしさを母親たちがいかに両立しているのか,という視点にたった議論は展開されていないという課題があった。こうした課題をふまえ,本研究はファッションにおいても特徴をもつギャルママを対象としたインタビュー・データを分析した。その結果,外見の上では母親らしさではなく自分の好きな格好をする一方で子育ての実務的な面では母親らしいことをとにかく頑張るというギャルママの行動は,外見と役割とを切り離して個としての自己と母親としての自己を両立させる一つの実践であるということが明らかになった。こうしたギャルママの論理は,一見すると新しい母親像の提示であるが,一方で当事者たちは自己犠牲の母親という規範性に疑問を抱いているわけではなく,むしろそれらを参照していることから,そこには保守的な自己犠牲の母親像を強化する働きがあることが見出された。
- 著者
- 宍戸 邦章
- 出版者
- 大阪商業大学商経学会
- 雑誌
- 大阪商業大学論集 = THE REVIEW OF OSAKA UNIVERSITY OF COMMERCE (ISSN:02870959)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.1, pp.437-449, 2019-05-30
4 0 0 0 OA フランス知識人が見た日本の大陸・植民地政策(六) ―ヴィシー政権の政治家と仏印進駐―
- 著者
- モロジャコフ ワシ―リー
- 出版者
- 拓殖大学国際日本文化研究所
- 雑誌
- 拓殖大学国際日本文化研究 = Journal of the Research Institute for Global Japanese Studies (ISSN:24336904)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.37-59, 2023-03-25
本稿の目的は、一九四〇年の日本の仏印(インドシナ)進駐政策に対するヴィシー政権(フランス)の主役たちの意見と立場、その相互関係と決定の過程を解明することにある。本稿では、「政治」よりも、むしろ「政治家」にフォーカスした。そして、本稿では主な資料として、外交文書や新聞・雑誌の記事よりも、むしろ政治家たち― フランス国主席兼首相アンリ・フィリップ・ペタン元帥(Henri-Philippe Pétain; 一八五六~一九五一年)、外務大臣ポール・ボドゥアン(Paul Baudouin; 一八九四~一九六四年)、植民地大臣であったアルベール・リヴィエール(Albert Rivière; 一八九一~一九五三年)、アンリ・レムリ(Henry Lémery; 一八七四~一九七二年)とシャルル・プラトン海軍小将(Charles Platon;一八八六~一九四四年)の三人、国防大臣マキシム・ウェイガン陸軍上級大将(Maxime Weygand; 一八六七~一九六五年)、極東艦隊指揮官のちインドシナ総督ジャン・ドクー海軍中将(Jean Decoux; 一八八四~一九六三年)―のステートメント、ノート、日記、回想録を採用した。彼らはそれぞれ一流の知識人として、自身の専門的、総合的知識と分析能力に基づいて事情を把握、分析して、様々な方針を提案し、決定した。
4 0 0 0 OA 平成と令和の大礼を振り返る
- 著者
- 所 功 楠本 祐一 久禮 旦雄
- 出版者
- 京都産業大学日本文化研究所
- 雑誌
- 京都産業大学日本文化研究所紀要 = THE BULLETIN OF THE INSTITUTE OF JAPANESE CULTURE KYOTO SANGYO UNIVERSITY (ISSN:13417207)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, pp.85-111, 2023-03-31
4 0 0 0 OA 群馬大学医学部附属病院草津分院は閉院しました
- 著者
- 久保田 一雄
- 出版者
- 一般社団法人 日本温泉気候物理医学会
- 雑誌
- 日本温泉気候物理医学会雑誌 (ISSN:00290343)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.4, pp.225-227, 2002 (Released:2010-04-30)
- 参考文献数
- 11
4 0 0 0 OA 『歎異抄』を浄土信仰の流れに位置づける ―蓮如本錯簡説を踏まえた読み直し―
- 著者
- 吉村 均
- 出版者
- 明治学院大学教養教育センター
- 雑誌
- 明治学院大学教養教育センター紀要 : カルチュール = The MGU journal of liberal arts studies : Karuchuru (ISSN:18818099)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, pp.9-24, 2023-03-25
【査読論文/Refereed Articles】
4 0 0 0 OA 統計にみる明治・大正・昭和初期における全国の娼妓数
- 著者
- 今村 洋一
- 出版者
- 椙山女学園大学文化情報学部
- 雑誌
- 椙山女学園大学文化情報学部紀要 = Journal of the School of Culture-Information studies (ISSN:24365416)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, pp.35-47, 2023-03-31
4 0 0 0 OA 戦間期の企業内クラブの活動 千代田生命体育会山岳部を事例に
- 著者
- 阪東 峻一
- 出版者
- 学校法人 関東学園大学
- 雑誌
- 関東学園大学経済学紀要 (ISSN:21878498)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, pp.43, 2023 (Released:2023-03-31)
- 参考文献数
- 35
It is widely known that during the interwar period in Japan, consumption society was formed, and travel and hiking became popular for leisure. This paper focuses on the activities of intra-company clubs in Tokyo to clarify the actual activities and their motivations to reveal the consumption society in the interwar period. An analysis of the 1930s activity records of Chiyoda life insurance company athletic association’s mountain club, reveals that the club members paid their own expenses for their activities. This included day trips and overnight trips on weekends, and extended expeditions during summer and new year holidays. Most of the activities were similar to hiking, with most of the members climbing medium to low mountains in the suburbs Tokyo. Most of the club members were men, but some women also participated. The means of transportation was public transportation such as trains and buses. Railroad lines that opened during the interwar period often passed through mountainous areas and made hikers easily accessible to the mountains. Furthermore, the motivation for the activities showed that the club members liked to participate on their own and enjoyed hiking in their leisure time. Travel and hiking, which were popular in the interwar period, were actively practiced as leisure activities of the new middle class of office workers, which this paper founds to be the bearers of a consumption society.
4 0 0 0 OA 青年犯罪者の共感性の特性
- 著者
- 河野 荘子 岡本 英生 近藤 淳哉
- 出版者
- 日本青年心理学会
- 雑誌
- 青年心理学研究 (ISSN:09153349)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.1, pp.1-11, 2013-08-30 (Released:2017-05-22)
- 被引用文献数
- 4
本研究は,共感性を多次元的なものと定義し,犯罪者と一般青年との比較を通して,犯罪者の共感性の特徴について明らかにしようとするものである。その結果,犯罪者は,他者の不運な感情体験や苦しみに対して同情的で,何らかの配慮をすることに方向づけられやすい一方で,他者の立場にたって物事をとらえる視点が十分に高くない「アンバランスな共感性」を持つことが示された。また,この状態では,他者の苦しみによって,自分の苦しみが増大することを抑制する自己防御システムが働きにくくなることが推測された。