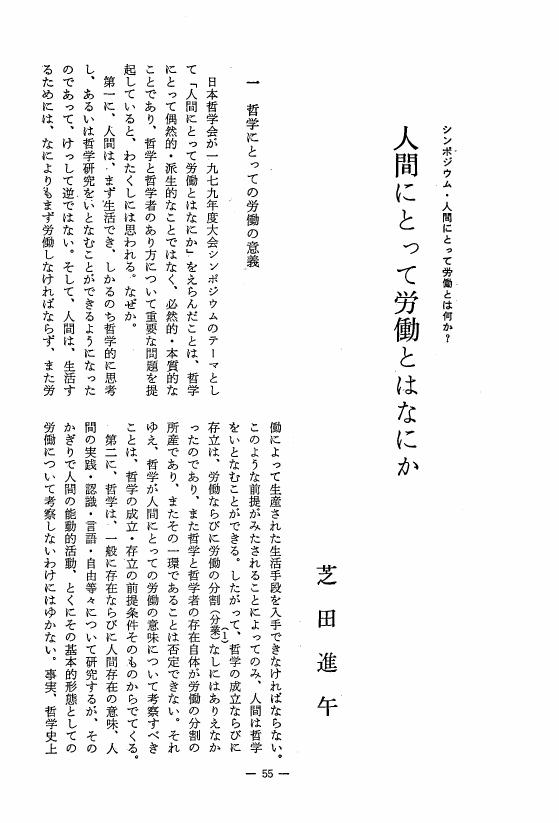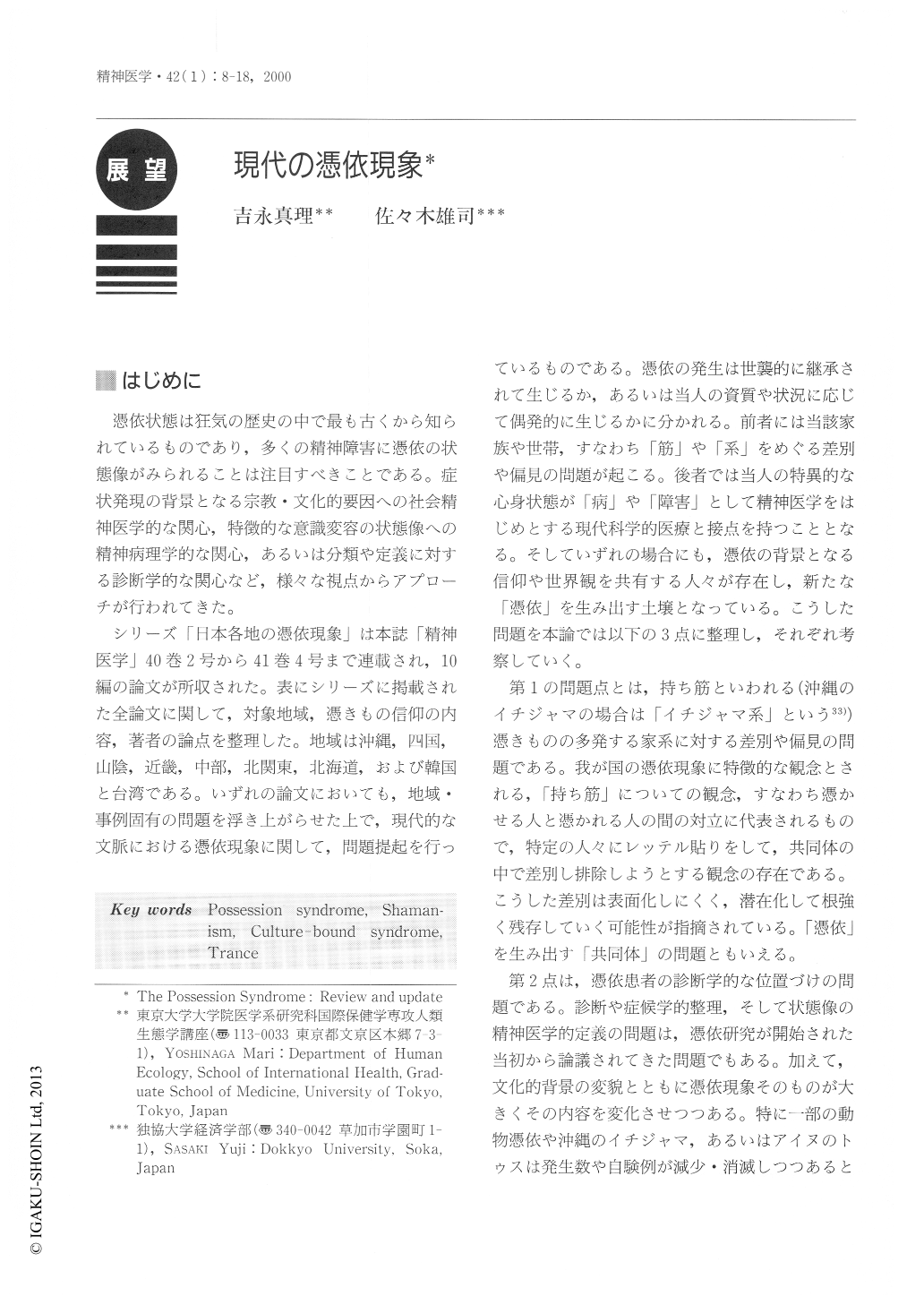4 0 0 0 OA Janthinobacterium lividumが原因と推定された紫変色うどん
- 著者
- 成松 浩志 岡本 英子 若松 正人 加藤 聖紀 緒方 喜久代
- 出版者
- 日本食品微生物学会
- 雑誌
- 日本食品微生物学会雑誌 (ISSN:13408267)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.4, pp.209-211, 2014-12-31 (Released:2015-01-27)
- 参考文献数
- 1
4 0 0 0 OA 幌満かんらん岩体起源のコランダムを含むガブロの発見
- 著者
- 森下 知晃 小寺 忠広
- 出版者
- 一般社団法人 日本鉱物科学会
- 雑誌
- 岩鉱 (ISSN:09149783)
- 巻号頁・発行日
- vol.93, no.2, pp.52-63, 1998 (Released:2006-08-30)
- 参考文献数
- 38
- 被引用文献数
- 9 12
北海道様似郡様似町を流れるポンサヌーシベツ川よりコランダムの巨晶を含むガブロの転石を発見した。このガブロの供給源はガブロの鉱物組み合わせ,組織,化学組成の特徴から幌満かんらん岩体に産するGBIIガブロ(塩谷・新井田,1997)であると推定される。コランダムと他の鉱物との組織的な関係はコランダムがガブロ(=GBII)の最も新しい変成条件下では不安定であったことを示す。コランダムの分解反応はガブロ(=GBII)が温度上昇か圧力減少(もしくは両方)を受けたことを示唆する。コランダムの形成は分解反応の逆の条件(温度下降か圧力上昇)やざくろ石パイロキシナイトと共存するような比較的高圧条件が考えられる。後者の条件からはガブロ(=GBII)が高圧変成作用を受け,その後にマントルダイアピルの一部としてかんらん岩体とともに上昇してきた可能性が示唆される。
4 0 0 0 OA 中世竹取説話分類の再検討(一) : 卵生篇
- 著者
- 飯田 さやか
- 雑誌
- 大妻国文 (ISSN:02870819)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, pp.61-80, 2022-03-16
4 0 0 0 OA 半側空間無視における時計描画の数字の配置について
- 著者
- 宮崎 泰広 種村 純
- 出版者
- 一般社団法人 日本高次脳機能障害学会
- 雑誌
- 高次脳機能研究 (旧 失語症研究) (ISSN:13484818)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.1, pp.20-29, 2016-03-31 (Released:2017-04-03)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 1
半側空間無視における時計描画の数字の配置に関与する要因を検討した。対象は脳血管障害により半側空間無視を呈し, かつ時計描画において数字を不適切に配置した 32 名とした。数字の配置に関する分析として, 時計の左右側における数字の分布率を示す Transposition index (TI) を用いた。分析項目は, (1) TI と損傷部位の関係, (2) TI と線分抹消課題のLaterality index (LI) の関係, (3) 反時計回りに数字を記入した際の反応, (4) 単一の数字を記入した際の反応の 4 つとした。結果は数字の配置の偏りが症例により異なりTI は広範に分布した。さらに時計の外円内の右側のみに数字を配置した症例は, 6 までと 6 以上の数字を書く 2 群が確認された。前者は頭頂葉に限局した損傷例で, 後者は前頭葉や頭頂葉を含む広範な脳損傷例であった。また TI と LI は関連を認めなかった。反時計回りや単一の数字を記入する場合では数字の配置に偏りを認めない症例が確認された。以上より, 半側空間無視における時計描画の数字の配置の誤りは, 半側空間無視に合併するその他の障害の影響を受けることを示唆した。
4 0 0 0 OA Gitとブロックチェーンを用いる文書管理方法の考察に基づく提案
- 著者
- 池田 大地 森田 光
- 出版者
- 情報ネットワーク法学会
- 雑誌
- 情報ネットワーク・ローレビュー (ISSN:24350303)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, pp.62-75, 2018-11-29 (Released:2020-01-16)
- 参考文献数
- 8
日本の森友学園問題をはじめとして、公的機関による決定事項に対する疑惑に注目が集まっている。関係者が、事実を隠蔽したり、他者の認識をミスリードするために改ざんをするようでは、根本解決に向けての議論ができないばかりか、社会の浄化作用を機能不全に陥らせることが懸念される。これに対して、著者らは、不正や疑惑が出れば、その事実を解明するため、過去の事実に遡るための手段が重要であるとの立場から研究してきた。遡って事実の解明ができるならば、不正抑止にもなり得るからだ。本稿では、事実の定義、文書管理機能、改ざん防止機能の三点から考察し検討を加えた。特に、第一項の「事実の定義」は核心部分であり、簡便に事実から情報の形に生成し、事実に関係付けられる情報同士を相互参照することで、疑惑や不正の因果関係を検証することができるようにするものである。第二項は定義された事実を情報として保存する文書管理機能のことを示す。特に、文書保存ができれば十分な機能であるが、象徴的な意味でGitという名称を用い、Gitのトランスペアレント(透明)で文書の加筆訂正などの更新や削除などバージョン毎の相互参照性可能なモデルの機能のことを意味する。また、第三項は改ざん防止機能であり、情報セキュリティを守ると根幹部分を示す。ここでは、他にも類似するモデルは多く存在するけれど、いろいろな実装が進んでいるためブロックチェーンの実装を使う場合を想定して議論する。文書改ざん防止機能を果たすものには、他にもブロックチェーンの源流のマークルツリー[7]などモデルが多く存在する。以上の三機能から文書管理の仕組みを構築できる。
4 0 0 0 OA 人間にとって労働とはなにか
- 著者
- 芝田 進午
- 出版者
- 日本哲学会
- 雑誌
- 哲学 (ISSN:03873358)
- 巻号頁・発行日
- vol.1979, no.29, pp.55-64, 1979-05-01 (Released:2009-07-23)
4 0 0 0 OA 同性愛映画としての『ショーシャンクの空に』
- 著者
- 國友 万裕
- 出版者
- 映画英語教育学会
- 雑誌
- 映画英語教育研究 : 紀要 (ISSN:13429914)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, pp.137, 2015 (Released:2020-03-25)
Gay characters in films are more and more prominent these days. The biases against gay people are gradually decreasing. So it is time to think about films from homosexual points of view. It has been said that American films are potentially homosexual, although they hide their homosexuality under the veils of heterosexism. As closeted homosexuality is an essential part of most American films, the one way to see American films is to assume man-to-man relationship to be a kind of homosexuality. The Shawshank Redemption can easily be said to be a beautiful love story between the two male prisoners Andy and Red. The Shawshank Redemption is, like other prison films, filled with homosexual connotations such as sexual violence and male rape. Under the harsh circumstances the two male prisoners create a loving relationship. But their skin colors and their social classes are so different that we tend to overlook their homoerotic desire. In this thesis, their homosexuality would be examined.
4 0 0 0 OA わが国ホテル業における事業者間の協働と会計情報の共有のあり方
- 著者
- 木伏 源太
- 巻号頁・発行日
- pp.1-149, 2023-03
4 0 0 0 OA 日本の大衆メディアにおける日系人の表象
- 著者
- 佃 陽 子
- 出版者
- 成城大学法学会
- 雑誌
- 成城法学.教養論集 (ISSN:03898075)
- 巻号頁・発行日
- no.27, pp.69-85, 2018-03
4 0 0 0 現代の憑依現象
- 著者
- 吉永 真理 佐々木 雄司
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- 精神医学 (ISSN:04881281)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.1, pp.8-18, 2000-01-15
はじめに 憑依状態は狂気の歴史の中で最も古くから知られているものであり,多くの精神障害に憑依の状態像がみられることは注目すべきことである。症状発現の背景となる宗教・文化的要因への社会精神医学的な関心,特徴的な意識変容の状態像への精神病理学的な関心,あるいは分類や定義に対する診断学的な関心など,様々な視点からアプローチが行われてきた。 シリーズ「日本各地の憑依現象」は本誌「精神医学」40巻2号から41巻4号まで連載され,10編の論文が所収された。表にシリーズに掲載された全論文に関して,対象地域,憑きもの信仰の内容,著者の論点を整理した。地域は沖縄,四国,山陰,近畿,中部,北関東,北海道,および韓国と台湾である。いずれの論文においても,地域・事例固有の問題を浮き上がらせた上で,現代的な文脈における憑依現象に関して,問題提起を行っているものである。憑依の発生は世襲的に継承されて生じるか,あるいは当人の資質や状況に応じて偶発的に生じるかに分かれる。前者には当該家族や世帯,すなわち「筋」や「系」をめぐる差別や偏見の問題が起こる。後者では当人の特異的な心身状態が「病」や「障害」として精神医学をはじめとする現代科学的医療と接点を持つこととなる。そしていずれの場合にも,憑依の背景となる信仰や世界観を共有する人々が存在し,新たな「憑依」を生み出す土壌となっている。こうした問題を本論では以下の3点に整理し,それぞれ考察していく。
4 0 0 0 OA 対話中における聞き手の頭部運動と相槌の相乗機能の解析
- 著者
- 飯塚 海斗 大塚 和弘
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会論文誌 (ISSN:13460714)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.3, pp.J-M91_1-17, 2023-05-01 (Released:2023-05-01)
- 参考文献数
- 37
A novel machine learning framework is proposed to automatically recognize the synergetic functions of the Aizuchi and the head movements of listeners in conversations. The listeners’ head movements, such as nodding, and Aizuchi, i.e., listeners’ short back-channel utterances, play a variety of functions, such as expressing the sign of listening, agreement, and emotions. This paper presents a functional Aizuchi corpus and analyzes it with the functional head-movement corpus that the authors have previously created. The analysis reveals the synergetic relationship between Aizuchi and head movements including reinforcement, multiplexing, and complementary. Then, this paper defines a functional category system called synergetic functions, which classifies reinforcement and multiplexing as product functions and complementary as sum functions. Next, several models using convolutional neural networks (CNNs) are designed to recognize such synergetic functions from the time series of the prosodic features and the head pose of the listeners. More specifically, we compare some different architectures, which employ early/late feature fusions and single/two-stage decision-making. The experimental results shows the proposed models achieved the maximum F1-score of 0.71 for the product function of Aizuchi’s continuer and head movement back-channel and that of 0.88 for a sum function called back-channel acknowledgment that was complementarily expressed by head movements and Aizuchi. These results confirms the potential of the proposed framework.
- 著者
- Kimio INOUE Toshio MORI Takahisa MIZUYAMA
- 出版者
- Japan Society of Erosion Control Engineering
- 雑誌
- International Journal of Erosion Control Engineering (ISSN:18826547)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.2, pp.134-143, 2012 (Released:2012-12-27)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 2 3
Large landslides or debris flows caused by heavy rainfall or earthquakes often block rivers in mountainous areas and form landslide dams. The area upstream of the landslide dam is submerged under water and the downstream area is flooded when the landslide dam breaks. In recorded history, as many as 22 landslide dams have formed upstream of the Shinano River and the Hime River, in the northern part of Nagano Prefecture in central Japan, and all except three have subsequently broken. This abundance of landslide dams is probably caused by the geotectonic background of this area, which is located at the western end of the “Fossa Magna” major tectonic line. In this study, we examined three large historical landslide dams and outburst disasters in the north Fossa Magna area.
4 0 0 0 OA 高層居住に対する批判の論拠 : 高層・超高層集合住宅の住環境デザイン設計指針
- 著者
- 大森 峰輝
- 出版者
- 一般社団法人 日本デザイン学会
- 雑誌
- デザイン学研究 (ISSN:09108173)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.4, pp.73-80, 2001-11-30 (Released:2017-07-19)
- 参考文献数
- 28
高層居住は我々にとって好ましくないことであるというような指摘や報告がされる場合がある。本稿では、これらに係る著述の論拠を探り、高層・超高層集合住宅の住環境デザインに際しての設計指針について検討した。その結果は、以下のようにまとめられる。1)高層居住に対する批判の論点は、生理・心理的影響、外出や子供の遊びなどの行動制約と拘束の問題、日常生活の安全性の問題の3つに分類できる。2)生理・心理的な影響、行動制約や拘束を回避するには、遊び場やコミュニティ・スペースを分散配置する等の対策を検討すべきである。3)犯罪や事故の原因が、必ずしも高層であることによるものだとは言えない。しかし、居住者の自治意識・連帯感を高める上で、住戸タイプ(間取り)の複合等の対策により居住者の年齢・家族構成等について配慮すべきである。
4 0 0 0 OA 前照灯の点灯が燃費に与える影響 -日本の使用実態を考慮した燃費影響の試算-
- 著者
- 志村 渉 鈴木 央一
- 出版者
- 公益社団法人 自動車技術会
- 雑誌
- 自動車技術会論文集 (ISSN:02878321)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.2, pp.505-510, 2021 (Released:2021-03-11)
- 参考文献数
- 6
欧米では、高効率な前照灯やオルタネータ等、オフサイクルにおいて燃費向上が見込める技術を積極的に評価しており、日本でも評価制度の導入が検討されている。本稿では、モード走行時に前照灯を点灯した際の燃費影響を評価するとともに、日本市場における前照灯の使用頻度を推定することにより、実燃費への影響を試算した。
- 著者
- 百々 幸雄 川久保 善智 澤田 純明 石田 肇
- 出版者
- 一般社団法人 日本人類学会
- 雑誌
- Anthropological Science (Japanese Series) (ISSN:13443992)
- 巻号頁・発行日
- vol.120, no.1, pp.1-13, 2012 (Released:2012-08-22)
- 参考文献数
- 67
- 被引用文献数
- 5 3
北海道アイヌの成立には,オホーツク人の遺伝的影響がかなり強く及んでいたという近年の研究成果に鑑みて,視野の中心を北海道に据えて,東アジアと北東アジアにおける北海道アイヌの人類学的位置を,頭蓋の形態小変異を指標にして,概観してみた。使用した形態小変異は観察者間誤差の少ない9項目で,日本列島の10集団とサハリンおよび大陸北東アジアの3集団を対象に分析を行った。集団間の親疎関係の推定にはスミスの距離(MMD)を用い,棒グラフとMMDマトリックスの主座標分析で集団間の相互関係を図示した。オホーツク人は北海道アイヌとサハリン・アムール・バイカルといった北東アジア集団のほぼ中間に位置したが,北海道アイヌとの形態距離はかなり近く,北海道や本州の縄文人と同程度であった。これに対して,大陸東アジアにその原郷が求められる弥生系集団は,北海道アイヌから遠く離れていた。9項目による分析結果が妥当なものであったかどうかを検証し,さらに,北海道の続縄文人の形態学的な位置づけを明らかにするために,著者のひとりが独自にデータを収集した12集団についても,20項目の形態小変異を用いて,同様の分析を行った。9項目による分析結果と20項目による分析結果はほとんど同じで,北海道アイヌの母体になった集団は,やはり従来の指摘どおり,北海道や本州の縄文人と北海道の続縄文人であると考えられたが,北海道アイヌの成立には,オホーツク人の遺伝的影響をも考慮しなければならないと思われる。
4 0 0 0 OA オホーツク海における海氷の減少イベントに対応する大気循環
- 著者
- 釜江 陽一 植田 宏昭 井上 知栄 三寺 史夫
- 出版者
- Meteorological Society of Japan
- 雑誌
- 気象集誌. 第2輯 (ISSN:00261165)
- 巻号頁・発行日
- vol.101, no.2, pp.125-137, 2023 (Released:2023-03-07)
- 参考文献数
- 31
- 被引用文献数
- 1
冬季オホーツク海における海氷分布は、極東域および北太平洋域の大気と強く相互作用する。先行研究は、オホーツク海海氷面積の年々変動は広域の大気循環と対応することを指摘している。一方で、オホーツク海における海氷面積の数日から1週間程度の時間スケールでの急激な変動に対応する大気現象については明らかにされていない。本研究では、日ごとの高解像度海洋再解析データを用いることで、オホーツク海海氷密接度の急激な減少イベントをもたらす大気循環について調査した。1993年から2019年にかけて、海氷急減イベントを合計21事例抽出した。急減イベントに共通した大気循環の特徴として、オホーツク海南部における発達した温帯低気圧とベーリング海北部における高気圧偏差、およびその間の強い地表の南東風が確認された。海氷の季節的な張り出しを左右する気候学的な西風とは逆向きである強い南東風は、オホーツク海海氷密接度の急減をもたらす。オホーツク海北部と中部で起こる海氷の急減は、海氷の移流と東風に伴う海氷融解によって起こる。東へと移動する温帯低気圧は、海氷密接度の急減と北太平洋北部の海面気圧の低下をもたらし、結果としてオホーツク海海氷密接度の変動とアリューシャン低気圧の強度の変動の間には時間差が存在する。
4 0 0 0 OA 縄文時代の若干の宗教的観念について
- 著者
- ネリー ナウマン
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 民族學研究 (ISSN:24240508)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.4, pp.277-297, 1975-03-31 (Released:2018-03-27)
Though mostly spoken of only in generalizations, it is commonly accepted that Jomon clay figurines bear some religious significance. By elucidating the hidden meaning of these figurines we should, therefore, be able to gain insight into the religious thoughts of Jomon people. This study is a first attempt in this direction. Because only a detailed interpretation can serve this purpose, a very small number of figurines coming from a locally and temporally limited area are taken into consideration, namely figurines of the Katsusaka type of pottery (in a broad sense) of the Middle Jomon period. Some features of these figurines are also present in the pottery of the neolithic Yang-shao culture of China as well as in the pottery of precolumbian America. The face of the "weeping deity" is even present in one of the oldest ceramic cultures of Mesopotamia. This "weeping deity" is sometimes connected with the serpent, as is the case with a small figurine from Tonai (Nagano). There is evidence that the iconographic unity presented by these figurines - consisting in an uplifted, dishlike, sunken face, nose and connected eyebrows slightly raised and strokes leading down from the eyes, while a serpent may be coiled up on the head - represents a moon deity.
- 著者
- 北條 勝貴
- 出版者
- 国立歴史民俗博物館
- 雑誌
- 国立歴史民俗博物館研究報告 = Bulletin of the National Museum of Japanese History (ISSN:02867400)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, pp.41-80, 1997-03-28
古代最大の規模を有する氏族の1つである秦氏については,現在,各集団における在地的特徴・個別的性格の解明が要請されている。そのための方法として,氏族の有する歴史性――文化全般の蓄積が顕著に反映される,種々の氏神に対する信仰形態の検討が重要視される。山背国葛野郡を本拠とする秦氏の集団は,古来同氏族の族長的地位を保持してきた。その勢力範囲には幾つかの神社が存在するが,中でも松尾大社は隣接する愛宕郡の賀茂社に並ぶ巨大勢力を築いており,その創祀や信仰の展開には注意を要する。同社の祭神には2柱あり,大山咋神と市杵嶋姫命という男女の神とされている。前者は秦氏渡来以前より同地に奉祀されていた農業神らしいが,後者は筑前国宗像郡に鎮座する胸肩君の氏神――宗像三女神の1神で,元来沖ノ島にあって渡来人や海人集団から特別な崇拝を受けた海洋神であった。松尾大社の周辺に立地する葛野坐月読神社や木嶋坐天照御魂神社も,それぞれ玄界灘に由来し,海人系の壱岐氏・対馬氏によって奉祀されていた神格である。その分祀は,渡来人や海人集団の移動に伴うものと考えざるをえない。海岸部から内陸部へ,北九州地域から畿内諸国への海人集団の東遷は,考古学的にもある程度立証されている。それは彼らの主体的行動に基づく場合もあるが,多く5世紀後半以降は,半島との交通権・制海権を掌握・独占しようとするヤマト王権によって促進された。半島よりの秦氏の渡来も,そのような社会状況を背景に移動と停留を繰り返しつつ,海人集団との繋がりを持って行われたものと推測される。松尾大社に鎮座する市杵嶋姫命も,胸肩氏と血縁的・文化的に接触した秦氏の1集団により,玄界灘より分祀されてきたものと想定される。元来松尾山には大山咋神と一対の普遍的女性神(神霊の依代たるタマヨリヒメ)が祀られており,市杵嶋姫命はその神格に重複し限定を加える形で鎮座したものであろう。