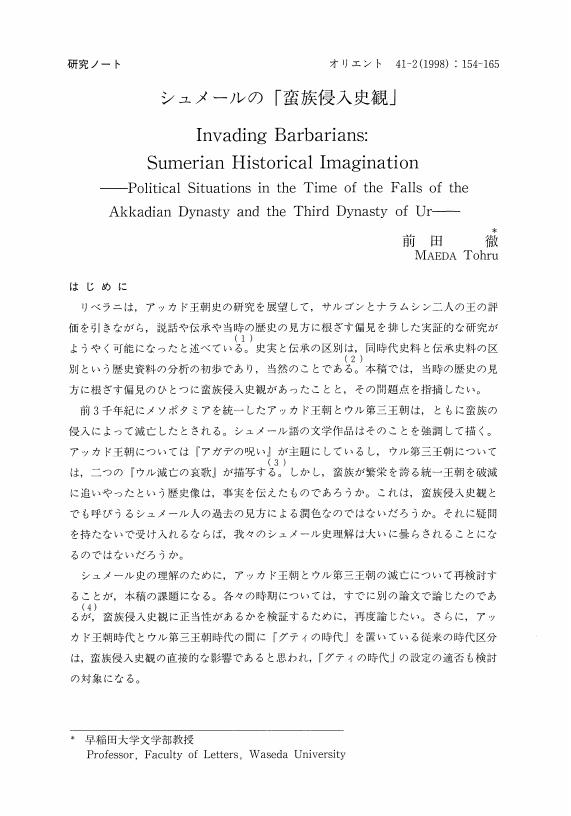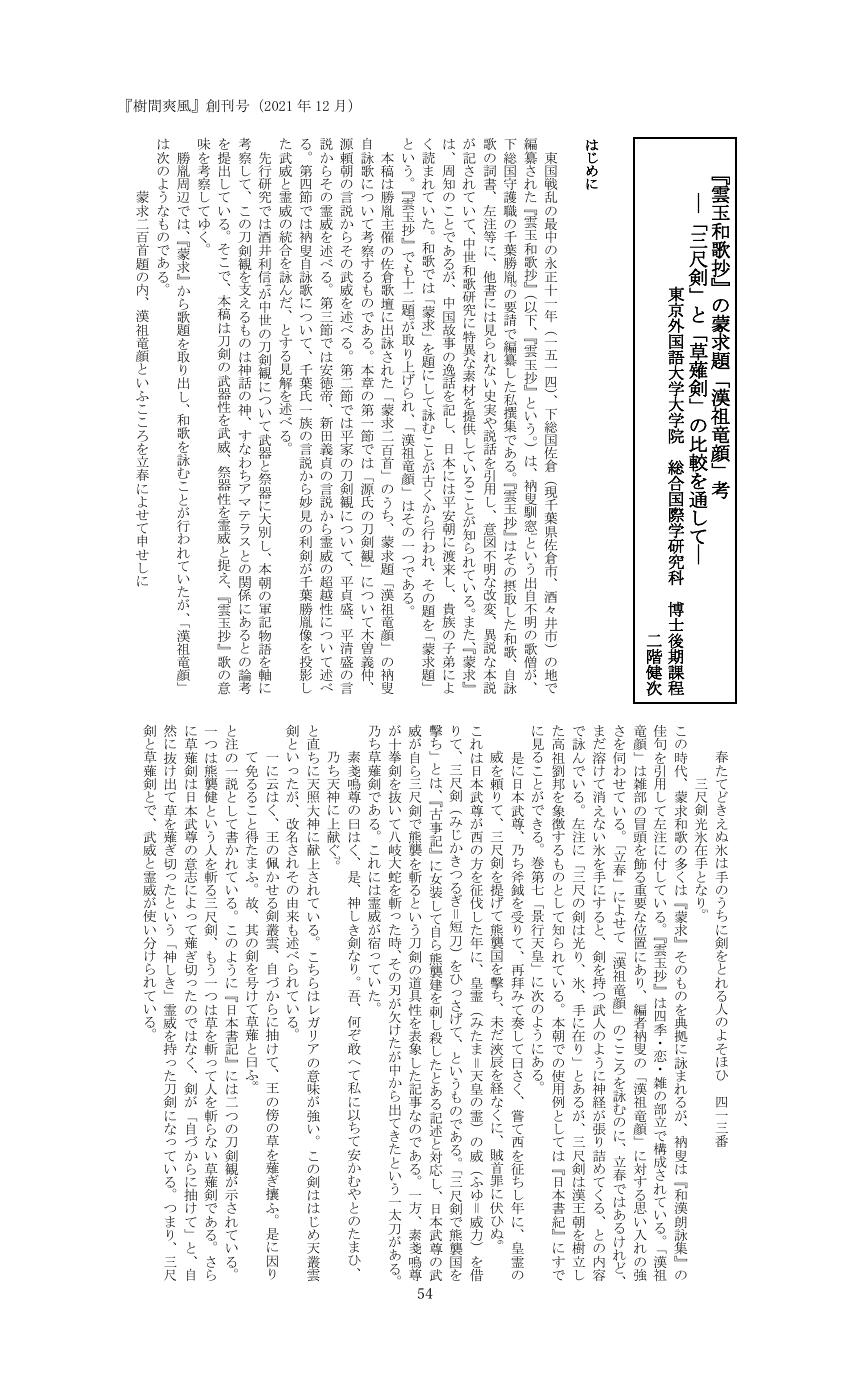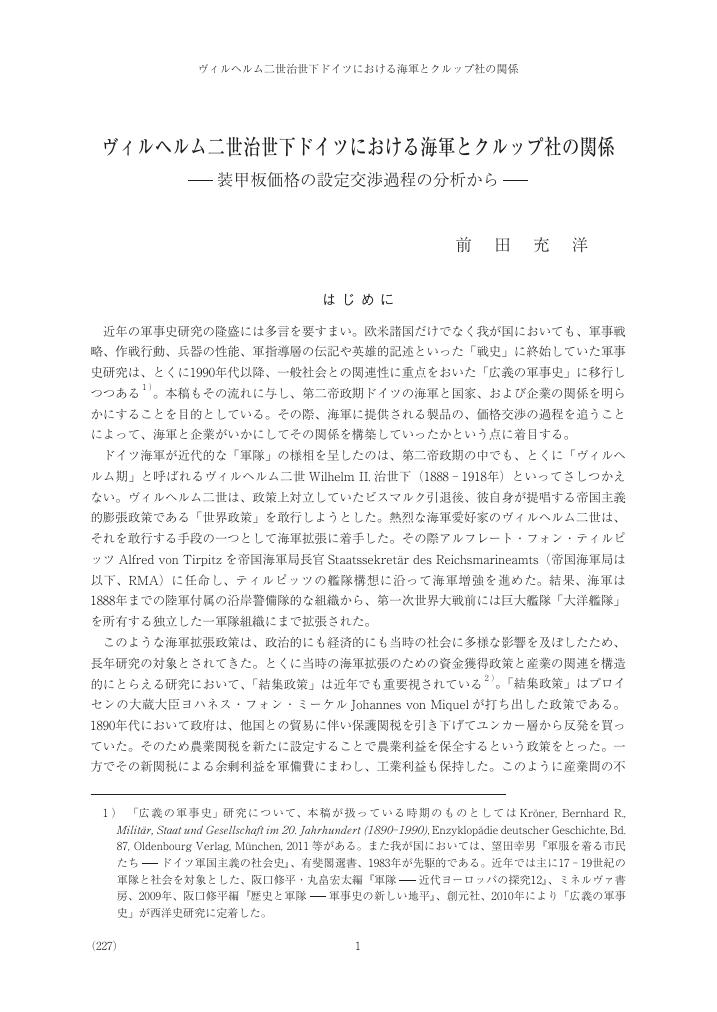4 0 0 0 OA 涅槃会の供え菓子 佐渡のやせごま
- 著者
- 小林 瑠美子 小谷 スミ子
- 出版者
- 日本調理科学会
- 雑誌
- 日本調理科学会大会研究発表要旨集 平成17年度日本調理科学会大会
- 巻号頁・発行日
- pp.171, 2005 (Released:2005-09-13)
【目的】旧暦の2月15日、涅槃会(お釈迦様が亡くなった日)に、佐渡地方では「やせごま(やせうま、しんこだんご)」を供えお参りする。これは団子の一種で、直径5cm、長さ15cm位の円筒形をしていて、輪切りにすると金太郎あめのように同じ模様がでる。本研究ではやせごまが作られるようになった由来、風土との関係を調べると同時に、佐渡以外の地域に見られる類似した伝統食を調べることを目的とした。【方法】佐渡在住者10名を対象に2004年11月_から_12月に聞き取り調査を行った。文献調査は、日本の食生活全集および各種資料を用いた。【結果】1.聞き取り調査の結果、「やせごま」は国仲平野の新穂(にいぼ)、畑野地区を中心に、両津、金井、佐和田地区で作られていた。羽茂(はもち)地区では「くじらもち」の名で作られており下北半島で端午の節句に作られる「べこもち(くじらもち)」との関連が伺えた。小木地区では法事にも作られていた。相川地区では寺で作るが家庭で作る習慣はなく、真野、赤泊地区ではあまり作られていなかった。2.涅槃会の供え菓子は主に北陸地方に見られた。3.長野県全般で作られている「やしょうま」、長野県に隣接する新潟県津南町の「やしょうま(みみだんご)」と岐阜県恵那市の「花くさもち」、長野から離れた福井県遠敷郡の「花くず」は「やせごま」に似た作り方であった。4.北陸地域では「涅槃会のだんごまき」をする風習が残っており、新潟県中越では「だんごまきの涅槃だんご」、富山県氷見市や魚津市では「お釈迦のだんご」、福井県では「ねはんだんご」と呼ばれる赤、白、緑、黄に彩られた大小さまざまな団子がお寺でまかれていた。能登半島の寺では「犬の子(いんのこ)」と呼ばれる団子をまく風習が残っていた。
4 0 0 0 OA 餅菓子文化の伝承 : 北海道における『べこもち』の歴史と地域性
- 著者
- 荒井 三津子 杉村 留美子 片村 早花 佐藤 理紗子 太田垣 恵 鈴木 恵 Mitsuko Arai Rumiko Sugimura Sayaka Katamura Risako Sato Megumi Otagaki Megumi Suzuki 北海道文教大学人間科学部健康栄養学科 北海道文教大学人間科学部健康栄養学科 北海道文教大学人間科学部健康栄養学科 北海道文教大学人間科学部健康栄養学科 北海道文教大学人間科学部健康栄養学科 北海道文教大学人間科学部健康栄養学科
- 雑誌
- 北海道文教大学研究紀要 = Bulletin of Hokkaido Bunkyo University
- 巻号頁・発行日
- no.36, pp.45-54, 2012-03-15
青森県のごく一部の地域と北海道でのみ作られるべこもちは、同じ材料と形でも地域によって名称が異なったり、型で抜くものや手で成形するもの、立体造形的に花などを作るもの、黒砂糖色の一色、黒白の二色、多色づかいのものなど、実に多様である。そのルーツも、北前船ルートと津軽海峡ルートが主に考えられる。べこもちの地理的な分布と、ルーツを探り、北海道の開拓の歴史と食文化を考察する。
4 0 0 0 OA 体幹研究と理学療法
- 著者
- 大沼 俊博 渡邊 裕文 藤本 将志 赤松 圭介 谷埜 予士次 鈴木 俊明
- 出版者
- 関西理学療法学会
- 雑誌
- 関西理学療法 (ISSN:13469606)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, pp.11-22, 2013 (Released:2013-12-28)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 13
In a clinical setup, difficulty in maintaining posture and controlling movements while bending, lateral bending, or performing rotation of the thoracic and lumbar region due to reduced activities of the abdominal oblique, multifidus, longissimus, and iliocostalis muscles, when in the seated and standing positions, and during walking, is often encountered. We trained patients with postural and control difficulties to shift their body weight laterally from one limb to the other while standing to increase the activities of the trunk muscles and improve the seated, standing, and gait postures. The activities of the trunk muscles, that serve as clinical indicators, were evaluated using electromyography and measurement of tissue stiffness. In the present study, we present the results of our research on the activities of the trunk muscles in the sitting and standing positions, and during sustained lateral shifting of body weight from one limb to the other while standing, and discuss their clinical implications.
4 0 0 0 OA 研究者にとっての「社会実装」
- 著者
- 木俵 豊
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 情報・システムソサイエティ誌 (ISSN:21899797)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.4, pp.14-15, 2021-02-01 (Released:2021-02-01)
4 0 0 0 OA 下北半島北東部に分布するヒバ埋没林の成因に関わる人為的影響
- 著者
- 岡本 透 大丸 裕武 池田 重人 吉永 秀一郎
- 出版者
- 日本第四紀学会
- 雑誌
- 第四紀研究 (ISSN:04182642)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.3, pp.215-226, 2000-06-01 (Released:2009-08-21)
- 参考文献数
- 30
- 被引用文献数
- 6 9
下北半島北東部の太平洋岸には,砂丘砂や泥土に覆われたヒバの埋没林が各所に認められる.この埋没林の形成期は,約2,600~2,000年前,約1,000~850年前,約500年前,および現代である.調査地域に分布する砂丘砂中に認められる埋没腐植層の年代は,14C年代値と白頭山苫小牧火山灰の年代から,約5,300年前,約2,700年前,約1,000~900年前,約600~500年前,そして約200年前に区分された.埋没腐植層の年代により,調査地域に分布する砂丘の形成期は,約5,000年前以降,約2,500年前以降,約1,000年前以降,約600年前以降,約100年前以降と推定された.約2,500年前以降は,砂丘の形成期の年代とヒバ埋没林の形成期の年代とがほぼ一致するため,ヒバ埋没林の形成には砂丘砂の移動が大きく関与している.約2,600~2,000年前のヒバ埋没林は,その年代と分布から,約3,000~2,000年前の小海退にともなう砂丘砂の移動によって形成された.約1,000年前以降に形成された砂丘については,人為的影響によって形成された可能性がある.一方,調査地域周辺には,約700~500年前の製鉄遺跡が数多く分布し,江戸時代後期にも南部藩などによって製鉄が試みられている.砂鉄採取のための砂丘の掘り崩しや,製鉄用の木炭を得るための沿岸部における森林伐採といった人為的影響によって,約600年前以降と約100年前以降に砂丘砂の移動があった.それにともなって,約500年前,現代の年代を示すヒバ埋没林が形成された.
4 0 0 0 OA 『図書館戦争』における非暴力的戦いについての考察 (志保田務教授退任記念号)
- 著者
- 藤間 真 Makoto TOHMA
- 雑誌
- 桃山学院大学環太平洋圏経営研究 = St. Andrew's University Pan-Pacific Business Review (ISSN:13455214)
- 巻号頁・発行日
- no.9, pp.213-229, 2008-03-25
4 0 0 0 OA シュメールの「蛮族侵入史観」
- 著者
- 前田 徹
- 出版者
- 一般社団法人 日本オリエント学会
- 雑誌
- オリエント (ISSN:00305219)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.2, pp.154-165, 1998 (Released:2010-03-12)
4 0 0 0 OA 『雲玉和歌抄』の蒙求題「漢祖竜顔」考 「三尺剣」と「草薙剣」の比較を通して
- 著者
- 二階 健次
- 出版者
- 和漢韻文研究会
- 雑誌
- 樹間爽風 (ISSN:24367494)
- 巻号頁・発行日
- vol.2021, no.1, pp.54-62, 2021 (Released:2023-04-28)
- 著者
- 伊藤 隼 佐藤 真 山崎 裕治
- 出版者
- 日本哺乳類学会
- 雑誌
- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.2, pp.247-255, 2022 (Released:2022-08-10)
- 参考文献数
- 33
The racoon (Procyon lotor) is an invasive alien species with an expanding distribution throughout Japan. Given that racoons have a negative impact on ecosystems and agricultural crops, management and control of their population is required. In Toyama Prefecture, where the distribution has not been clearly defined, we investigated the current distribution based on claw marks of the racoon and camera traps. We found claw marks of them at 94 (48.7%) of 193 survey sites in the lowlands of Toyama Prefecture. The 94 sites were located in the eastern and western areas of the prefecture. We also recorded one incidence using a camera trap survey, suggesting a low population density of racoon in Toyama Prefecture. Our results showed that within different areas of Toyama Prefecture, the population density of racoons varied. Thus, it is necessary to devise management strategies that are specific to each area.
- 著者
- 海野 敦史
- 出版者
- 公益財団法人 情報通信学会
- 雑誌
- 情報通信学会誌 (ISSN:02894513)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.3, pp.1-12, 2016 (Released:2017-02-06)
米国の法執行機関による IMSI キャッチャーを通じた情報収集について、それが令状手続によらずに行われる場合に、米国憲法修正 4 条にいう「不合理な捜索」に該当する可能性が議論の焦点となっている。これは、①公権力が個々の通信に関する情報を直接かつ一方的に収集する、②対象となった携帯電話端末の占有者において当該収集の事実を知ること及びそれを回避することが物理的に困難である、③収集・分析対象の情報の中には端末の所在地のように利用者のプライバシーに関する利益に深く関わると認められるものが含まれ得る、などの点にかんがみ、物理的な不法侵入の不存在や誰もが容易にアクセス可能な公共の空間における電波の受信という手法等にかかわらず、「プライバシーの合理的な期待」の保護と解されている同条の趣旨に基づき、令状主義の原則の要請に服すると考えられる。このとき、米国法上、通信傍受や通話番号等記録装置の設置・使用のあり方に関する電子通信プライバシー法の規律と同様に、かかる要請を具体化する新たな立法措置が求められる中で、通信傍受でも通話番号等記録装置の設置・使用でもない固有の特質を有する新種の「捜索」として位置づけられ得る。このことは、我が国において、今後 IMSI キャッチャーが普及するか否かを問わず、技術革新に対応した新種の捜査について、その実施が各人のプライバシーの権利等の基本権又は基本権に関する法益に対する本質的な制約となり得る限り、強制処分としての立法上の位置づけの再整理が必要となるという示唆を与える。
4 0 0 0 OA 豆腐のゲル強度に及ぼす塩類の影響
- 著者
- 眞壁 優美
- 出版者
- 日本海水学会
- 雑誌
- 日本海水学会誌 (ISSN:03694550)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.4, pp.302-305, 2006 (Released:2013-02-19)
- 参考文献数
- 8
塩類濃度およびその組成を変化させたときの食感に及ぼす影響について検討するため, 大豆加工製品である豆腐を対象として, 豆腐ゲルのゲル強度を測定し検討を行った, マグネシウムイオンやカルシウムイオンのように2価陽イオンを持つ塩のゲル強度への効果は大きかった. 1価の陽イオンを持つ塩と2価の陽イオンを持つ塩では, 2価の陽イオンを持つ塩の方がゲル強度に対する効果は大きかった. 塩化マグネシウムと塩化カルシウムでは, 0.05mol/L以上の高濃度領域においてゲル強度に対する効果が異なり, 塩化マグネシウムにおいてゲル強度が減少した. また, 塩化マグネシウム塩化ナトリウム混合溶液を用いた場合においては, 塩化ナトリウムはゲル強度に対して大きな影響はないが, 保水力に関与することが示唆された.
- 著者
- 黒木 学
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能 (ISSN:21882266)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.3, pp.328-335, 2007-05-01 (Released:2020-09-29)
4 0 0 0 IR 中国文明における帝と天の観念の展開 -その思想史的考察-
- 著者
- 吉永 慎二郎 YOSHINAGA Shinjiro
- 出版者
- 秋田中国学会
- 雑誌
- 秋田中国学会50周年記念論集
- 巻号頁・発行日
- pp.97-117, 2005-01-01
4 0 0 0 OA 大会情処ツアー体験記 AI編 -目の前にキーワードが飛んでくる感覚-
- 著者
- 高橋 正人
- 出版者
- The Japanese Society of Physical Fitness and Sports Medicine
- 雑誌
- 体力科学 (ISSN:0039906X)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.1, pp.237-243, 1996-02-01 (Released:2010-09-30)
- 参考文献数
- 23
- 被引用文献数
- 1 1
Unfortunately, anabolic androgenic steroid (AAS) abuse is prevalent in Japan. Most steroid abusers are amateur bodybuilders, powerlifters, wrestlers, and “fitness enthusiasists.” The case presented is of a young amateur bodybuilder, who suffered gynecomastia, whose only significant risk factor was his nonmedical use of an AAS.A 27-yr-old male was admitted to our hospital in December 1992 with gynecomastia. He reported starting to use an AAS, oxymetolone (Anadrol®) 30 mg daily, at the age of 23 yrs in 1987. He had developed bilateral painful gynecomastia, impotence and decreased sex drive within 3 months of starting AAS use. He stopped using it, and was admitted to another clinic in 1991. He took testosterone propionate (Testinon®) 25 mg weekly, but, as he was anxious about the long-term use or this medication, he was adimitted to our clinic.On physical examination his gynecomastia had diminished slightly, but he still had breast tenderness. All his laboratory examination results were almost within the normal ranges. Neverthless his serum free testosterone level was slightly low, so he took tamoxifen (Nolvadex®) and Chinese medicines. Consequently, his gynecomastia improved after treatment, for 5 months.Gynecomastia develops when an AAS is converted to estrogen. In conclusion, tamoxifen administration may be useful to reverse gynecomastia caused by AAS doping in sportsmen.
4 0 0 0 OA 19世紀パリの水まわり事情と衛生(続・完)
- 著者
- 大森 弘喜
- 出版者
- 成城大学
- 雑誌
- 成城大學經濟研究 = Seijo University economic papers (ISSN:03874753)
- 巻号頁・発行日
- no.197, pp.1-68, 2012-07
4 0 0 0 OA ヨーロッパ市民権制定と「ヨーロッパ人」アイデンティティーの形成
- 著者
- 鈴木 規子
- 出版者
- 日本EU学会
- 雑誌
- 日本EU学会年報 (ISSN:18843123)
- 巻号頁・発行日
- vol.2003, no.23, pp.212-230,307, 2003-09-30 (Released:2010-05-21)
In 1992, the Treaty of Maastricht institutionalised the rights of European Union citizens to vote in local elections in their country of residence. This paper describes the main characteristics of the concept of EU citizenship and analyses the way in which national and/or European identities affected the voting behaviour of non-French residents during the French local elections in March 2001.The introduction of these limited political rights within the EU established the notion of “multiple citizenship”, combining both the traditional idea of citizenship of a nation-state, and that of the new wider citizenship based on a multi-national agreement.The author takes the case of the March 2001 local elections, when some reluctance to extend voting rights to include all EU citizens residing in France became apparent amongst the French public, and political parties adopted different attitudes to the issue, in some cases even questioning the basic principle of giving foreigners the right to vote. The newly acquired rights of EU citizens were seen to have created unequal political status in the absence of similar rights for long-term residents in France from non-EU countries.It is important to note that majority of EU citizens in France who have obtained voting rights are from South European countries such as Portugal, Italy and Spain. This fact has drawn the attention of many political parties which had in fact encouraged those with South European nationalities, particularly Portuguese, to stand for the local election of March 2001. The paper argues that some political parties expected these candidates with South European nationalities to attract a large number of potential voters among EU citizens from South European countries.Another aspect covered by the paper concerns the various levels of identity—local, national and regional—reflected in the exercise of voting rights of EU expatriates, within a political system which recognizes the diversity of cultural origins of its electorate.Finally, the author suggests possible future means of achieving European integration and describes several incidents which illustrate the impact of the participation of non-French EU citizens in local elections.
4 0 0 0 OA 種々の界面活性剤のカビの生育に与える影響
- 著者
- 濱田 信夫 中村 正樹
- 出版者
- Osaka Urban Living and Health Association
- 雑誌
- 生活衛生 (ISSN:05824176)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.6, pp.365-371, 2005 (Released:2005-12-07)
- 参考文献数
- 5
- 被引用文献数
- 1
Three kinds of fungi were cultured on various media (including different 30 surfactants, anionic, nonionic, amphoteric, and cationic surfactants) and a comparison of their growth was made. The growth of all three fungi was inhibited by anionic, amphoteric, and cationic surfactants. In particular, no colonies of these fungi were found on 0.25% of these surfactants and only small colonies were found on 0.05%. On the other hand, although two fatty acid-amide type nonionic surfactants inhibited the growth of the three fungi, no inhibition on the their growth was found on media including other nonionics. For example, fatty-acid ester type nonionics promoted the growth of all three fungi. In particular, Scolecobasidium constrictum, a dominant fungus in washing machines, grew well on media including polyoxyethylene-alkylether nonionic surfactants, in contrast with Cladosporium cladosporioides, a common fungus in indoor environments. Fatty-acid amide type surfactants were noticed for their potential to be exploited in detergent for fungus-free washing machines.
- 著者
- 中垣 浩平 尾野藤 直樹
- 出版者
- 一般社団法人 日本体育学会
- 雑誌
- 体育学研究 (ISSN:04846710)
- 巻号頁・発行日
- pp.13034, (Released:2014-01-23)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 1
The purpose of this study was to evaluate the utility of simplified quantification of training in for a Japanese national canoe sprint team using the modified session rating of perceived exertion method. We recorded the team's training using a method that integrates the original weighting factor (WF) and the duration (time) of the training session. Training load was quantified as the product of WF and time. Training monotony was calculated by as the mean daily load divided to the standard deviation of load. Training strain was calculated by multiplying the weekly training load by training monotony. A fitness-fatigue model was applied to the relationships between training load and performance. The model-predicted performance using the training load was significantly correlated with actual paddling performance. The training load and strain were significantly correlated with resting heart rate in the early morning. These results suggest that simplified quantification of training can be used to prescribe training for the improvement of performance and the prevention of overtraining syndrome.
- 著者
- 前田 充洋
- 出版者
- 日本西洋史学会
- 雑誌
- 西洋史学 (ISSN:03869253)
- 巻号頁・発行日
- vol.248, pp.1, 2012 (Released:2022-04-27)