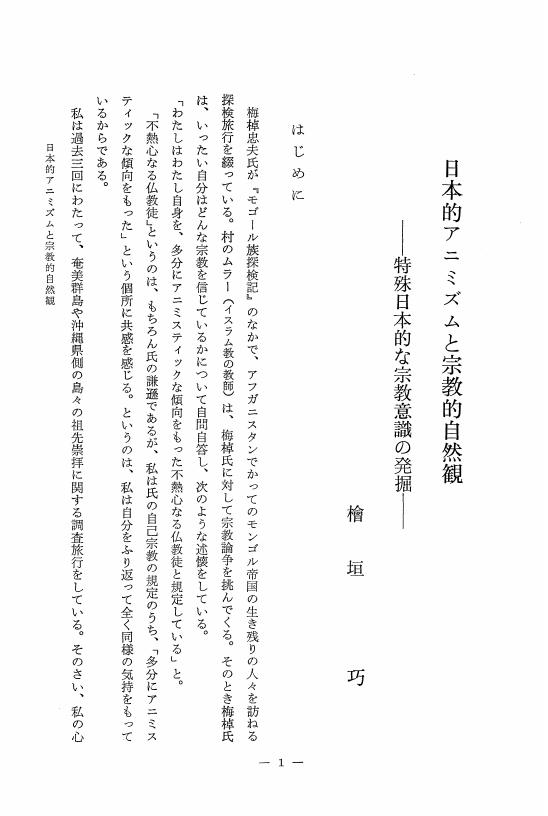4 0 0 0 OA 日本的アニミズムと宗教的自然観 特殊日本的な宗教意識の発掘
- 著者
- 檜垣 巧
- 出版者
- 密教研究会
- 雑誌
- 密教文化 (ISSN:02869837)
- 巻号頁・発行日
- vol.1989, no.165, pp.1-31, 1989-03-10 (Released:2010-03-12)
- 参考文献数
- 13
4 0 0 0 OA 「地域ブランド調査」における地域の魅力度の構成要素
- 著者
- 田中 耕市
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- E-journal GEO (ISSN:18808107)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.1, pp.30-39, 2017 (Released:2017-06-09)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 1
本稿は,2015年に実施された「地域ブランド調査」を利用して,1,000市区町村を対象とした主観的評価に基づく地域の魅力度の構成要素とそのウェイトを明らかにした.はじめに,地域の魅力度に関わると考えられる同調査の75項目から,主成分分析によって13の主成分を導出した.次に,それらの13主成分を説明変数,市区町村の魅力度を被説明変数とする重回帰分析を行った結果,魅力度は11の構成要素から成り立っていた.それらのうち,魅力度におけるウェイトが最も高かったのは観光・レジャーであり,農林水産・食品,生活・買い物の利便性,歴史がそれに続くことが明らかになった.本稿で解明した地域の魅力度の構成要素とそのウェイトをもとに,客観的な地域の魅力度を評価することが可能となる.
4 0 0 0 OA 立位で排尿可能な女性用便器の開発
- 著者
- 高橋 信子 山崎 信寿
- 出版者
- 日本看護技術学会
- 雑誌
- 日本看護技術学会誌 (ISSN:13495429)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.1, pp.50-57, 2005-04-30 (Released:2016-10-25)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 1
立ち座り動作の困難な女性が, 安楽に立位で排尿できるようにするための女性用便器を開発した. 便器の寸法やデザインは, 身体関節に何らかの苦痛が生じている女性被験者 (20~76歳) 10名の立位排尿実験から外形中央幅22cm, 高さ30cmのピーナツ殻形状とした. 膝関節や股関節に障害のある女性10名について試作便器の検証を行った結果, 一般的な立位姿勢であれば, 下肢および衣服を汚すことや尿が便器の外に飛散することなく, 安楽に排尿できることが確認できた.
- 著者
- 山下 玲 姜 泰安 松岡 宏高
- 出版者
- 東洋大学ライフデザイン学部
- 雑誌
- ライフデザイン学研究 = Journal of Human Life Design (ISSN:18810276)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, pp.89-100, 2019-03
4 0 0 0 OA ソーシャル・サポート,ケア,社会関係資本
- 著者
- 稲葉 昭英
- 出版者
- 福祉社会学会
- 雑誌
- 福祉社会学研究 (ISSN:13493337)
- 巻号頁・発行日
- vol.2007, no.4, pp.61-76, 2007-06-23 (Released:2012-09-24)
- 参考文献数
- 24
ソーシャル・サポート研究の概要を紹介しつつ,その理論的な再構成を行い,社会関係資本研究にむけて提言を行うことが本稿の目的である. ソーシャル・サポートは有害なライフイベントが個人に及ぼす影響を緩衝する対入関係的要因として概念化され,経験的研究の中でそれが探索された.サポートと関連を有するニーズには受け手の想定するニーズ,送り手の想定する「受け手の」ニーズ,「受け手の福祉に貢献する」ニーズの3者が存在し,それぞれの重なりの中に従来のサポート研究を位置づけることができる.こうしたソーシャル・サポート研究は,事実上ケアの経験的研究といいうる側面を持つ.また,サポート研究において大きな効果が検証されてきた「サポートの利用可能性」は,ケアによるニーズの充足可能性と考えることが可能であり,ケアによるケイパビリティの重要性を示したものと整理することができる.ソーシャル・サポート研究は,健康やメンタルヘルスに関連した分野での対人関係資源の研究であったため,他の分野への広がりは大きくなかったが,中範囲レベルでの研究の蓄積が進んだ.分析単位を個人におく社会関係資本の概念は,ソーシャル・サポートとの接点を大きく持つ.社会関係資本研究は,分析単位を集合体レベルに置くことで様々な可能性をもちうると思われるが,マクロな事象間の関連を説明する理論として分析単位を個人に置くモデルを用いることが有効であると思われる.
- 著者
- Naohiko OHKOUCHI
- 出版者
- The Japan Academy
- 雑誌
- Proceedings of the Japan Academy, Series B (ISSN:03862208)
- 巻号頁・発行日
- vol.99, no.5, pp.131-154, 2023-05-11 (Released:2023-05-11)
- 参考文献数
- 168
- 被引用文献数
- 6
Food web research is rapidly expanding through study of natural fractional abundance of 15N in individual amino acids. This paper overviews the principles of this isotope approach, and from my perspective, reanalyzes applications, and further extends the discussion. It applies kinetic isotope effects that enriches 15N in certain amino acids associated with the metabolic processes, which was clearly demonstrated by observations of both natural ecosystem and laboratory experiments. In trophic processes ‘trophic amino acids’ such as glutamic acid that significantly enrich 15N, whereas ‘source amino acids’ such as phenylalanine and methionine show little 15N enrichment. Through various applications conducted over the years, the principles of the method have shown to operate well and disentangle complex food webs and relevant problems. Applications include food chain length estimate, nitrogen resource assessment, tracking fish migration, and reconstruction of paleodiet. With this approach, considerations of a wide range of classical issues have been reinvigorated, while in the same time, new challenging frontiers are emerging.
- 著者
- 黒田 勇
- 出版者
- 関西大学社会学部
- 雑誌
- 関西大学社会学部紀要 (ISSN:02876817)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.2, pp.141-163, 2020-03-31
This research note aims to reveal the history of the sports events operated by two newspaper companies, The Osaka Asahi and The Osaka Mainichi, in the early 20th century. It focuses on Minato Ward of Osaka City where several sport-events were held, the 6th Far Eastern Championship Games in1923, for example, and "Ichioka Paradise" was built in 1925, which consisted of several amusement facilities and the Japan's first artificial skating link.
- 著者
- 飯村 諭吉
- 出版者
- 日本音楽表現学会
- 雑誌
- 音楽表現学 (ISSN:13489038)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, pp.1-12, 2021-11-30 (Released:2022-11-30)
- 参考文献数
- 41
本稿の目的は、昭和初期におけるヨハネス・ブラームスの交響曲の紹介方法について、新交響楽団の機関紙における曲目解説に着目して明らかにすることである。ここでは、新交響楽団の機関紙『曲目と解説』、『フィルハーモニー・パンフレット』、『音楽雑誌フィルハーモニー』、『日本交響楽団誌』を主史料として使用した。これらの調査から、ブラームスの交響曲の曲目解説は、牛山充、堀内敬三、服部龍太郎、門馬直衛、属啓成らの音楽評論家が執筆を担当していることが確認された。また、《交響曲第2 番》から《交響曲第4 番》までの曲目解説においては、それぞれの主題に対応する管弦楽器の旋律的な動きとそれを担当する伴奏楽器の特徴的な動きが紹介されていた。新交響楽団の機関紙における曲目解説は、定期公演の聴衆に各楽章の演奏順序を提示するだけではなく、楽曲分析に基づく管弦楽の演奏上の基礎的な知識を提供していることが注目される。
- 著者
- 船橋 亜希
- 出版者
- 日本パーソナリティ心理学会
- 雑誌
- 日本パーソナリティ心理学会発表論文集 20 (ISSN:24332992)
- 巻号頁・発行日
- pp.138, 2011-09-02 (Released:2017-09-01)
- 著者
- 田中 幸平 高村 優作 大松 聡子 藤井 慎太郎 生野 公貴 万治 淳史 阿部 浩明 森岡 周 河島 則天
- 出版者
- 日本理学療法士協会(現 一般社団法人日本理学療法学会連合)
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.44 Suppl. No.2 (第52回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.1130, 2017 (Released:2017-04-24)
【はじめに,目的】半側空間無視(USN:Unilateral Spacing Neglect)は,右半球損傷後に後発する高次脳機能障害の一つであり,病巣半球と反対側の刺激に対して,反応/回答したり,その方向に注意を向けることに停滞が生じる病態である。高村らは最近,半側空間無視症状の回復過程において,病識の向上に伴う左空間への意図的な視線偏向が生じること,その行動的特徴は前頭機能の過剰動員によって裏付けられることを明らかにしている。本研究では,こうした半側空間無視症例の選択注視特性について,無視症状のない右半球損傷群,さらに脳損傷のない健常群との比較を行い,高次脳機能障害の評価を行う際の参照値を得ることを目的とした。【方法】脳損傷のない健常群(53名,55.5±19.3歳)と右半球損傷患者(40名,発症後69.0±133.4日)を対象とした。右半球損傷患者は,BIT行動性無視検査の得点とCatharine bergego scaleの客観得点と主観得点の差を基に,BITがカットオフ値以下をUSN++群(n=16,70.4±19.0歳),BITが131点以上だが日常生活上で無視症状を認めるもしくはCBSの差が1点以上であるUSN+群(n=12,62.7±11.2歳)と無視症状を認めないRight Hemisphere Disease:RHD群(n=12,64.9±6.7歳)に分類した。対象者は視線計測装置内蔵のPCモニタ(Tobii TX60)の前に座位姿勢を取り,モニター上に水平方向に配置された5つの正円オブジェクトを視線(眼球運動)で追跡・注視する選択反応課題を実施した。注視対象はオブジェクトの色彩変化(黒から赤)を点滅で呈示し,呈示前500ms前にビープ音を鳴らすことで注意レベルの安定化を図った。注視対象の呈示時間は2000msとし,呈示後1500msの安静状態とビープ音後500msを設けた。左右方向への視線推移データから各群におけるビープ音~注視対象呈示前500ms間の視線配分(視線偏向)を算出した。視線配分の算出値は水平面上0~1で表し,PCディスプレイ上の最も左を0とした。【結果】健常群の視線配分はほぼ中心にあり,加齢的影響はみられなかった(r=-0.191)。USN++群では全体的に視線が右偏向を呈していたが,中には左偏向を示す症例が散見された。USN+群ではUSN++群よりも右偏向の程度が減少し,高村の報告と同様に,左偏向を示すものが散見された。RHD群は明らかな左右の視線偏向を認めず,健常群と同様の視線配分になっていた。【結論】半側空間無視症例の中には,課題実施時に明らかな右視線偏向を示す症例と,反対に左視線偏向を示す症例が存在した。無視空間である左空間に視線偏向を示す症例は,高村らの先行研究と同様に空間無視に対する選択的注意(代償)を向けていることを示していると考えられる。また,健常群の結果から視線配分には加齢的影響はなく,RHD群も同様の傾向を示していることから,健常群の結果を参考値とし右半球損傷患者の空間無視に対する介入を進めていくことが可能と考えられる。
4 0 0 0 OA 神経科学の観点から —感情と行動、脳、遺伝子の連関について—
- 著者
- 野村 理朗
- 出版者
- 日本感情心理学会
- 雑誌
- 感情心理学研究 (ISSN:18828817)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.2, pp.143-155, 2008 (Released:2008-12-17)
- 参考文献数
- 30
- 被引用文献数
- 2 2
Recent developments in brain functional neuroimaging studies have established important physiological links between environmental stimuli and robust differences in emotional processing within distinct brain regions and circuits that have been linked to the manifestation of various conditions. Such techniques might enable us to evaluate information processing at the brain level in individuals by exploring the impact of genetic variation and provide an approach to perform functional genomic studies. Here, I propose that psychological and brain function imaging studies with concurrent biochemical and pharmacological measurement, in particular those investigating the effect of gene polymorphisms, appear to be quite useful in clarifying the relationships between emotion, brain and gene functions.
4 0 0 0 OA スイスの「経済に関する国の供給政策」と農政改革 : 備蓄政策を中心として
- 著者
- 樋口修
- 出版者
- 国立国会図書館
- 雑誌
- レファレンス (ISSN:1349208X)
- 巻号頁・発行日
- no.685, 2008-02
- 著者
- 長谷部 史彦
- 出版者
- Keio University Faculty of Letters, Department of Asian History
- 雑誌
- Al-Madaniyya (ISSN:24360678)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.27-68, 2023 (Released:2023-05-07)
In this paper, we attempt to unveil the personality of Ibn al-‘Ajamī, the hitherto unexplored author of Mabāhij al-ikhwān wa manāhij al-khillān fī ḥawādith al-duhūr wa al-azmān and its sequel called Ta’rīkh āl ‘Uthmān. The paper first reviews the descriptions in these historical writings, of which only two manuscripts are known at this point and examines their characteristics and importance as the chronicles of Ottoman Cairo. Focusing on three points: Ibn al-ʻAjamī’s family relations, Būlāq as his place of residence and work, and he as a weigher, we seek to reveal the reality of this little-known “laboring citizen historian” who was in the economic middle strata and made his living from steady work supporting the market economy of Cairo, the largest Arab trading city in the early modern era.
4 0 0 0 OA 痒みの病理と心理学
- 著者
- 羽白 誠
- 出版者
- 一般社団法人 国立医療学会
- 雑誌
- 医療 (ISSN:00211699)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.9, pp.538-542, 2004-09-20 (Released:2011-10-07)
- 参考文献数
- 11
痒みの伝導路は痛みとほぼ同じであるが, その神経は異なることがわかってきた. 痒みは末梢で炎症などで生じる起痒物質により修飾され, 中枢神経でオピオイドなどにより修飾を受けて, 大脳で認知される. 痒みにつきものの掻破は, 行動そのものの中枢は遠位延髄であり, 痒みの求心神経とは脊髄レベルの反射を形成せず, 大脳皮質からの信号によって起こると考えられている. また痛みは痒みを抑制しており, 両者は連携をとっている. 大脳での痒みの認知は精神状態によって, あるいは周囲の環境によって変化することがあると報告されている. 痒みのコントロールには起痒物質の拮抗薬を用いるのが一般的であるが, 抗不安薬や抗精神病薬, オピオイド拮抗薬なども用いることができる. しかし掻破を特異的に抑制する薬剤はいまのところなく, 皮膚科医にはなじみがうすいが行動療法が主体となっている.
4 0 0 0 OA アメリカ企業における業績評価制度の変革運動(ノーレイティング)とその背景
- 著者
- 鈴木 良始 Yoshiji Suzuki
- 出版者
- 同志社大学商学会
- 雑誌
- 同志社商学 = Doshisha Shogaku (The Doshisha Business Review) (ISSN:03872858)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.3, pp.325-342, 2017-11-30
研究(Article)
4 0 0 0 OA その他の酒類の成分 (ジン・ウオッカ)
- 著者
- 西村 驥一
- 出版者
- 公益財団法人 日本醸造協会
- 雑誌
- 日本釀造協會雜誌 (ISSN:0369416X)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.2, pp.106-112, 1978-02-15 (Released:2011-11-29)
- 参考文献数
- 52
4 0 0 0 OA メモリーノートの活用の成否に関わる要因 ─回復期病棟における検討─
- 著者
- 大石 斐子 齋藤 玲子 小田柿 誠二 補永 薫 立石 雅子
- 出版者
- 認知リハビリテーション研究会
- 雑誌
- 認知リハビリテーション (ISSN:24364223)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.1, pp.29-37, 2013 (Released:2022-05-26)
- 参考文献数
- 18
回復期リハビリテーション病棟にてメモリーノート訓練を実施し,活用の成否に関わる要因について神経心理学的検査と独自に作成したメモリーノートの使用に関する評価を用いて検討した。訓練は,ノートの使用方法を学習する机上訓練と,病棟生活における活用を促す実用訓練を行った。メモリーノートを習得し,スケジュール管理を自発的に行えるようになった自立群(9名)と,訓練終了時に援助が必要であった非自立群(10名)を比較すると,知的機能,「情動」,「受容性」は両群ともに導入時より良好であった。記憶障害を含む高次脳機能障害は,自立群が非自立群よりも軽度である傾向にあった。また,自立群のほうが非自立群よりも,記憶障害に対する「モニタリング能力」とメモリーノート使用の「動機づけ」が高かった。これらの条件が備わっている症例には,回復期リハビリにおいても代償手段の訓練を実施することの有効性があると考えられた。
4 0 0 0 OA 自発休眠期の気温を考慮したソメイヨシノの開花日の簡便な推定法
- 著者
- 青野 靖之 村上 なつき
- 出版者
- The Society of Agricultural Meteorology of Japan
- 雑誌
- 生物と気象 (ISSN:13465368)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, pp.25-33, 2017 (Released:2017-04-10)
- 参考文献数
- 32
- 被引用文献数
- 6 8
We constructed a simplified method to estimate first flowering dates of cherry tree (Prunus×yedoensis), considering temperature conditions in endodormancy process. We adopted the DTS method, which is an accumulation model of forcing effect of temperatures during developing process, as an estimation model of cherry blossom phenology in this study. In our previous studies, DTS method with fixed (pre-determined) starting dates for each site showed high accuracies for cold regions, whereas low accuracies for warm regions. Such accuracy drop was attributed to the volatility in endodormancy completion in warmer region of Japan, affected by inter-annual variation in chilling temperature during winter season. In order to reduce such error, it had been necessary to calculate chilling hours from hourly temperature data and evaluate the progress in endodormancy releasing process, with complicated conventional procedures. In our new model, an annual discrepancy in starting date of forcing effect from the pre-determined dates, calculated from a simplified procedure in our previous model, were calculated as the product of the correction coefficient, Ci, for each year and a winter temperature normal value above a threshold of chilling effect for endodormancy release, (TDJ-1.5), for each site. Annual correlation coefficient Ci was calculated from averaged winter temperatures at 7 secular observatories in warm region in Japan. Estimated first flowering dates with and without correction of starting dates were compared each other. The estimations by new method kept under about 3.2 days of RMSE. The introduction of new method also reduced RMSE within 3 days into approximately half of stations, applied to verification of new method with relatively long (50-year) period.
4 0 0 0 OA 匿名表現の自由の保障の程度 米国法上の議論を手がかりとして
- 著者
- 海野 敦史
- 出版者
- 公益財団法人 情報通信学会
- 雑誌
- 情報通信学会誌 (ISSN:02894513)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.1, pp.1-12, 2019 (Released:2019-07-22)
匿名表現の自由が憲法上保障される程度に関し、米国法上の議論を参照しつつ考察すると、以下の帰結が導かれる。すなわち、①匿名性は個人の尊厳の確保に資する役割を果たすうえに、それが表現物と結びつくことにより固有の価値を有することを踏まえ、匿名表現の自由は憲法21条1項に基づき保障される、②他人の基本権に関する法益を著しく害する表現については、公共の福祉に基づき制約され、当該他人との関係において表現者を特定する必要性が生じ得る限りにおいて、その匿名性についても制約される、③公共的事項に関する表現のうち、その表現者の身元の把握が民主政の意思決定過程における各種の判断に際して必要となると認められる場合における匿名表現の自由については、国民の「知る権利」と緊張関係に立つ結果、憲法上一定の範囲で制約され得る、④前記③以外の表現に関する匿名表現の自由は、前記②の場合を除き、憲法上手厚く保障される、⑤匿名性は、非表現の行為との関係においても憲法上一定の保護を受ける、と考えられる。
4 0 0 0 OA 慢性的なストレス負荷による新たなミクログリア作動原理の解明
慢性疲労症候群(CFS)や線維筋痛症(FM)などのモデル動物を用いて、病的疼痛の分子メカニズム、特にミクログリアの関与を明らかにすることをめざした。これらの慢性ストレスモデルでは末梢組織の明らかな炎症や損傷は見られないが、中枢の脊髄後角においてミクログリアの増殖と活性化が認められた。CFSモデルにおいてミクログリアの活性化を抑制すると病的な疼痛は抑制された。脊髄後角のミクログリア活性化の領域は固有感覚の入力部位に一致していること、抗重力筋や脊髄神経節の検索から、固有感覚の慢性的な過剰刺激がこれらの疾患の引金になっている可能性が示唆された。